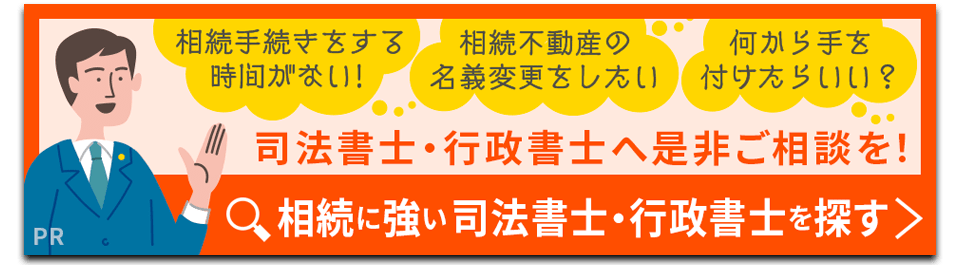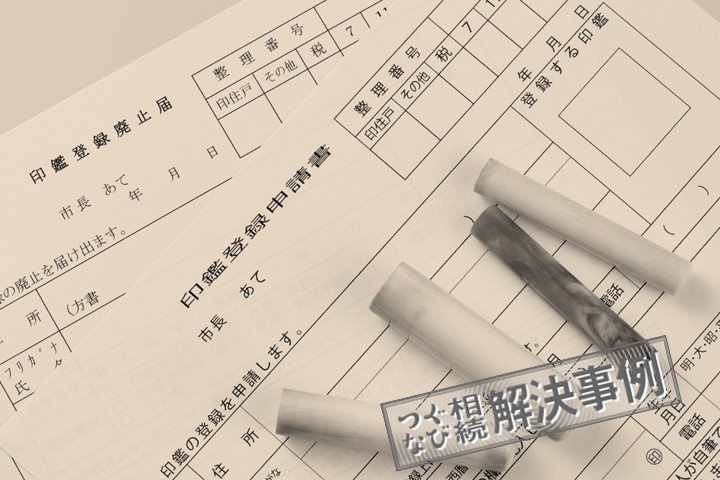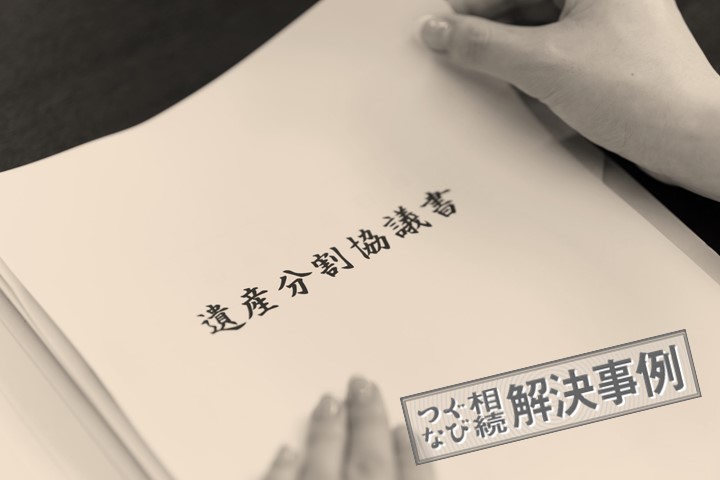遺族の生活を支える「遺族年金」。ここでは受給資格や手続き期限、具体的な手続きのステップを解説します。
必要書類が多く、手続きが煩雑で、さらには受給まで約110日もかかるといわれているため、早めの手続きがおすすめです。
また、行政書士や社会保険労務士といった専門家に依頼するのも一つの手で、その際に必要な書類も合わせて解説します。
目次
1. 遺族年金は2種類

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の加入者、またはその加入者だった方が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
亡くなった方の年金の納付状況などにより、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が支給されます。
「遺族基礎年金」は、一定の条件を満たしている国民年金の加入者、または加入者であった方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた子(18歳に到達した年度の末日までの子。
障害のある子は20歳未満)のいる配偶者またはその子に対して支給されます。
「遺族厚生年金」は、一定の条件を満たしている厚生年金保険の加入者、または加入者であった方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。
このように「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」は、亡くなった方が加入していた年金の種類により、受給要件や受給期間、年金額が異なる制度になっています。
1-1 遺族年金の手続きの前にすること
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、年金を受け取る権利がなくなるため、年金の受給停止の手続きが必要になります。
その際に、受け取ることができた年金のうちまだ受け取っていない年金があった場合については、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができますので、年金の受給停止の手続きと合わせて未支給年金の請求手続きも行います。
手続きは、お近くの年金事務所または「街角の年金相談センター」で行うことができます。
それぞれの手続きには必要な添付書類がありますので、詳しくは「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」またはお近くの年金事務所に問い合わせを行ってください。
【関連記事】遺族年金の仕組みや種類についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族共済年金と遺族厚生年金の違いは?共済年金の金額の目安もご紹介!
2. 遺族基礎年金の手続き

遺族基礎年金の請求手続きの流れは以下のようになります。
- 市(区)役所または町村役場に死亡届を提出します。
- 亡くなった方が年金受給者だった場合は、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出します。
- 「年金請求書」ならびに下記に記載した必要書類を市(区)役所または町村役場に提出します。
- 「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構から届きます。
- 年金証書が届いてから約1~2カ月後に年金の振込みが始まります。
2-1 必要な書類とは
遺族基礎年金を請求する場合に必要な書類は以下になります。
必要書類は、請求者や亡くなられた方との関係によって異なってきますので、事前に電話などで確認するようにしましょう。
- 年金請求書(様式第108号):
手続きに必要な請求書は、住所地の市(区)役所または町村役場、お近くの年金事務所または「街角の年金相談センター」にあります。
日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。 - 必ず必要になる書類
・年金手帳
・戸籍謄本(受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの)
・世帯全員の住民票の写し[※]
・死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)[※]
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書または非課税証明書、源泉徴収票など)[※]
・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高等学校在学中は在学証明書または学生証など)[※]
・市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・請求者の本人名義の受取先金融機関の通帳等
・印鑑
※年金請求書へのマイナンバー記入により省略可能
- 死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
・第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書(所定の様式あり)
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書(すでに損害賠償金が決定済みの場合)
- 状況によって必要な書類
・年金証書
・合算対象期間(国民年金に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったりしたことなどにより、年金額には反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間のことをいいます)が確認できる書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者か組合員または被保険者であったことを証明するための書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証明するための書類の写し
・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等を受けることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証明するための書類の写し
・その他、海外在住の期間等があったときは、そのことを証明するための書類
以上、参照先:日本年金機構 遺族年金に関する届出・手続き>遺族基礎年金を受けられるとき
2-2 提出先
遺族基礎年金の請求書の提出先は、原則として受け取る人がお住まいの住所地の市(区)役所または町村役場の窓口になります。
ただし、死亡日が国民年金第3号の被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または「街角の年金相談センター」で行ってください。
3. 遺族厚生年金の手続き

遺族厚生年金の請求手続きの流れは以下のようになります。
- 市(区)役所または町村役場に死亡届を提出します。
- 亡くなった方が厚生年金保険の加入者だった場合、会社等から「資格喪失届」を提出してもらいます。
亡くなった方が年金受給者だった場合、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出します。 - 「年金請求書」ならびに下記に記載した必要書類を、年金事務所、「街角の年金相談センター」等に提出します。
- 「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構から届きます。
- 年金証書が届いてから約1~2カ月後に年金の振込みが始まります。
3-1 必要な書類
遺族厚生年金を請求する場合に必要となる書類は以下になります。
必要書類は、請求者や亡くなられた方との関係によって異なってきますので、事前に電話などで確認するようにしましょう。
- 年金請求書(様式第105号):
手続きに必要な請求書は、住所地の市(区)役所または町村役場、お近くの年金事務所または「街角の年金相談センター」にあります。日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。 - 必ず必要になる書類
・年金手帳
・戸籍謄本(受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの)
・世帯全員の住民票の写し[※]
・死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)[※]
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書または非課税証明書、源泉徴収票など)[※]
・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高等学校在学中は在学証明書または学生証など)[※]
・市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・請求者の本人名義の受取先金融機関の通帳等
・印鑑
※年金請求書へのマイナンバー記入により省略可能
- 死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
・第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書(所定の様式あり)
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書(すでに損害賠償金が決定済みの場合)
- 状況によって必要な書類
・年金証書
・合算対象期間(国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったりしたことなどにより、年金額には反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間のことをいいます)が確認できる書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者か組合員または被保険者であったことを証明するための書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証明するための書類の写し
・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等を受けることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証明するための書類の写し
・その他、海外在住の期間等があったときは、そのことを証明するための書類
以上、参照先:日本年金機構 遺族年金に関する届出・手続き>遺族厚生年金を受けられるとき
3-2 提出先
遺族厚生年金の請求書の提出先は、お近くの年金事務所または「街角の年金相談センター」になります。
4. 遺族年金の手続き期限は?

亡くなった方が受給していた年金の、受給停止手続きの期限については、国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金保険の場合は死亡日から10日以内になります。
その他に、前述の未支給年金の請求手続きは特に期限はありませんが、上記の年金の受給停止手続きと同時に手続きができますので、一度に行うと良いでしょう。
次に、遺族年金の請求に関する手続き期限についてですが、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、支給事由が発生した日(通常は死亡日)の翌日から5年です。
5年を経過すると時効により受給権が消滅することがあります。
5. 手続きにかかる時間はどのくらい?
それでは、遺族年金の請求手続きを行ってから年金が決定されて受給できるまでには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。
年金請求の手続きを行うと、約60日後に日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が届き、その書類が到着して1~2カ月後から遺族年金を受け取ることができるようになります(その1~2か月の間に「年金振込通知書」「年金支払通知書」が届きます)。
実際に遺族年金が受給できるまでは約110日かかると言われており、請求手続き時に書類不備などがあるとさらに時間がかかる場合もありますので、注意が必要です。
6. 遺族年金の手続きは代理人でもできる

遺族年金の手続きは、やるべきことが多く、必要な書類の種類や入手方法、記入方法などわからないことがたくさんあります。
また、必要な書類を入手するためには、平日に年金事務所や市区町村の役所・役場に出向く必要があり、時間的に難しいという場合もあります。
どうしても自分ではできそうもないという方は、遺族年金の手続きを代理人、例えば行政書士、社会保険労務士といった専門家に依頼して代行してもらうこともできます。
代理人に手続きを委任する場合には、代理人は以下のものを準備しなければなりません。
なお、行政書士や社会保険労務士に遺族年金手続きを依頼した場合の費用感は2万円~5万円と見ておきましょう。(ただし、費用は申請の難易度ならびに依頼する行政書士や社会保険労務士により変わりますので、必ず事前に見積りを取って確認した後に依頼してください)
- 請求者本人の委任状(請求者本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証+年金手帳など)
- 請求者本人の印鑑
- 委任者の基礎年金番号やマイナンバー、委任者の本人確認書類の写しなど
委任状は、日本年金機構のホームページからダウンロードして使用してもかまいませんし、次の項目を記載した任意の様式でも問題ありません。
- 委任年月日(委任状を記入した年月日)
- 代理人の氏名
- 代理人の住所
- 代理人の電話番号
- 請求者本人との関係
- 請求者本人の基礎年金番号
- 請求者本人の署名・押印
- 請求者本人の生年月日
- 請求者本人の性別
- 請求者本人の住所
- 請求者本人の電話番号
- 委任する内容(年金の見込額について、年金の請求について、各種再交付手続きについてなど)
- 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付または請求者本人に郵送)
複雑な手続きも行政書士や社会保険労務士のような専門家に依頼することでスムーズに進められます。
手続きを行う際の選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
つぐなびでは、相続手続きほか相続税の申告や相続トラブルなど、相続に関するあなたのお悩みを相談しやすい事務所を厳選して掲載しています。
【関連記事】遺族年金の条件や受給資格についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族年金の条件・受給資格とは|【もらえない時の救済措置!】も解説
【関連記事】妻が遺族年金をいくら受けとれるのかについてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族年金を妻はいくらもらえる?|【年間170万円以上】の場合も!
【関連記事】遺族年金と自分の年金についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?|【遺族厚生年金と国民年金】
執筆者プロフィール

山本 務
特定社会保険労務士。理系大学卒業後、プログラマー・SEを経て上場企業人事部で人事労務管理業務を約10年経験し、2016年に独立。独立後も2020年3月まで労働局の総合労働相談員として200件以上のあっせん事案に関与。労働相談は労働局の電話相談も含めて1,000件以上の対応実績あり。これまでの知識と経験を活かし、各種サイトでの人事労務関係に関する記事の執筆や監修も積極的に行っている。
オフィシャルサイト: やまもと社会保険労務士事務所
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるようにご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。