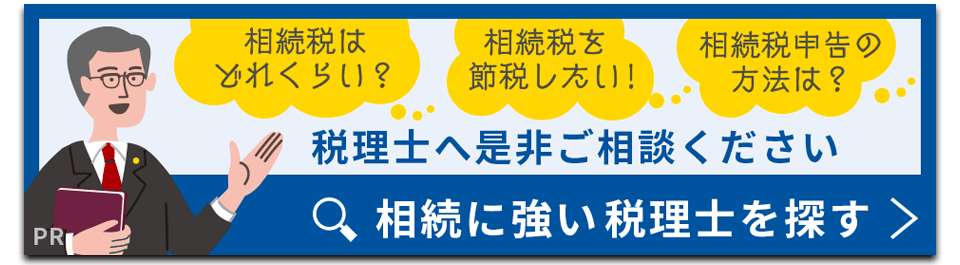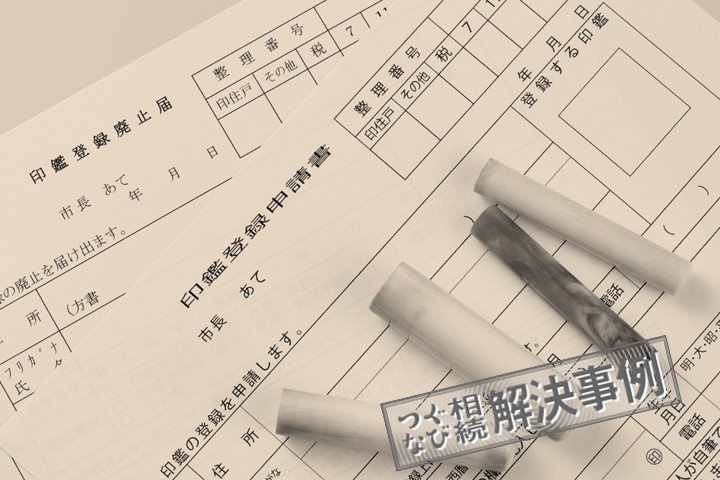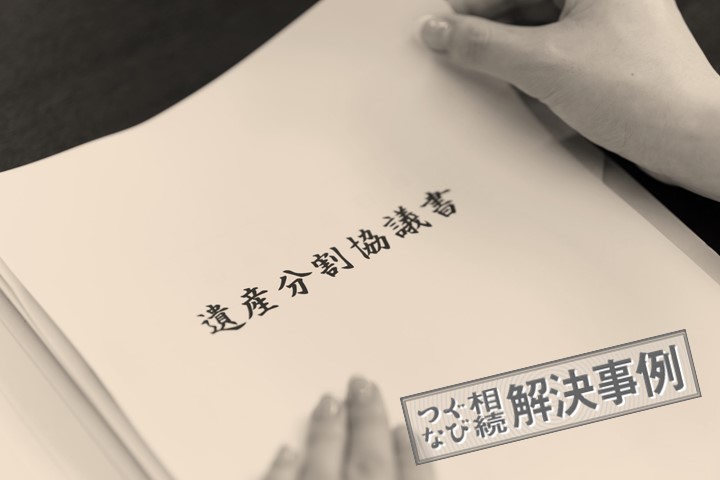亡くなった方の財産を相続する際には、基本的に相続税を支払わなければなりません。
しかし、相続税を支払わなくても良いのか確認したい方や、どの程度の相続税を支払うのか気になる方もいるでしょう。
そこで、相続税はいくらまで無税になるか、無税かどうか判断する方法や、算出方法などを紹介します。
相続税を支払わなければならないのかどうか、確認してみましょう。
目次
1. 相続税はいくらまで無税?
相続税は、財産を相続した際に必ず支払わなければならないというイメージを持つ方も多いです。
しかし、なかには財産を相続した後も税金を支払う必要がないこともあります。
相続税が無税になるケースはいくつかあるため、それぞれ金額や要件をチェックしておきましょう。
1-1 基礎控除を使えば3,600万円までは税金がかからない
基礎控除を使うと、3,600万円まで相続税を支払う必要もなく、相続税の申告も不要です。
しかし、借入金や未払金などの負債があり、限定承認や相続放棄をする際には相続税が発生したことを知ってから3か月以内に申告しなければなりません。
必要な書類を準備して、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所へ申請しましょう。
1-2 特例や控除を使うと基礎控除以上でも非課税になるケースもある
それぞれの相続人の相続税額を算出し、控除を利用すれば非課税になることがあります。主な控除や特例としては以下が挙げられます。
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 暦年課税および相続時精算課税の贈与税額控除
- 小規模宅地等の特例
控除や特例を使って非課税になった場合、相続税自体はあるため、対象の控除や特例は相続税申告時に申告する必要があります。
2. 相続税が無税か計算するための「基礎控除」とは?
法定相続人が1人だった場合基礎控除額は3,600万円であり、以降1人追加されるごとに600万円ずつ足していきます。
つまり、財産が3,600万以下の場合は無税です。
3,600万円以上だったとしても、法定相続人が2名以上であり財産の総額が基礎控除以下の場合は相続税を支払う必要がありません。
2-1 基礎控除の計算方法
基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で計算できます。
基礎控除を計算する際に、法定相続人が何人なのか分からないという方もいるでしょう。
法定相続人は法律で財産を相続する権利がある人であり、遺言書がなければ法定相続人が相続する仕組みです。
法定相続には要件が定められているため、あらかじめ法定相続人の数え方についても理解しておきましょう。
2-2 法定相続人のカウント方法
相続順位が高い人が、法定相続人としてカウントされます。
例えば、子供がいる場合は子供と配偶者が、子供がいない場合には配偶者が、配偶者がいない場合は父母・祖父母
あるいは兄弟姉妹が法定相続人です。
配偶者は被相続人との関係が非常に深く、ほかの法定相続人と比較して特別だと言えるでしょう。
また、法定相続人の順位は以下の通り決められています。
|
順位 |
法定相続人(代襲相続人) |
|
第1順位 |
子(孫) |
|
第2順位 |
父母(祖父母) |
|
第3順位 |
兄弟・姉妹(甥・姪) |
法定相続人が死亡している場合は世代を問わず相続する権利があり、代襲相続と呼ばれています。
基礎控除を算出する時には、代襲相続人を法定相続人に含める必要があります。
2-3 相続税はいくらまで無税になるか確認できる早見表
相続税が無税になるパターンを、配偶者の有無で見てみましょう。
【配偶者がいる場合】
| 配偶者+子 | 配偶者が2分の1、子の人数で分ける |
| 配偶者+父母 | 配偶者が3分の2、3分の1を父母で分ける |
| 配偶者+兄弟・姉妹 | 配偶者が4分の3、4分の1を兄弟・姉妹の人数で分ける |
| 配偶者のみ | 全額相続 |
【配偶者がいない場合】
配偶者がいない場合は、子供だけ、父母だけ、兄弟・姉妹だけで、それぞれ全額を人数分で分けます。
法定相続人が、法定相続分通りに相続できないケースもあります。
遺言書で指定がないと、相続の取り分は財産分割協議を行い、法定相続人の間で決めて分割することが多いです。
しかし、法定相続分は相続税を算出するときにも使うため、どのようなものなのか確認しておきましょう。
法定相続人が相続を放棄したり、養子がいたりする場合もあります。
法定相続分の確認方法は以下の通りです。
| 養子がいるパターン | 養子も法定相続人になりますが、人数が限られています。実の子供が居る場合は1人まで、実の子供が居ない場合は2人までです。 |
| 相続放棄されたパターン | 相続放棄をした法定相続人は、当然相続はできません。しかし、基礎控除の計算をする際には、相続放棄をした相続人も法定相続人として計算します。 |
| 内縁の相手がいるパターン | 法律上の婚姻関係がないと法定相続人にはなれないため、基礎控除を算出する際も法定相続人としてカウントしません。 |
3. 相続税の計算時に非課税となるもの
相続税を計算する際に、どのようなものなら非課税になるのか、確認しておかなければなりません。
非課税だと勘違いをして計算すると問題に発展するため、非課税となるものについて正しい知識を身に付けておきましょう。
非課税になる主な項目、物品を4つに分けて紹介します。
3-1 葬式費用
葬式費用とは、通夜や告別式で葬儀社に支払った金額、通夜や告別式での飲食にかかった金額、葬儀を手伝ってくれた知人や友人への心付けなどです。
心付けでも、渡したことを証明できれば葬儀費用として非課税になるため、渡した相手や渡した日を記録しておきましょう。
また、お寺や神社、教会へのお布施や読経料、埋葬や火葬・納骨の費用、通夜や告別式で参列者へ渡す御礼費用なども挙げられます。
お布施や読経料は渡した日と渡した相手を記録しておくことが大切です。なお、事件や事故などの場合、遺体の捜索や遺骨の運搬などの費用も非課税です。
3-2 仏壇や仏具などの祭祀財産
仏具や仏壇でも、故人が生きている時に購入して残したものは相続税が非課税ですが、亡くなってから財産を使って仏壇や仏具を買った場合は相続税を支払わなければなりません。
つまり、現金を残す方法と比較して、仏壇や仏具といった非課税の財産にすることによって相続税を軽減でき、相続税対策になるでしょう。
3-3 債務
財産から差し引ける債務とは、相続人が亡くなった時に確実なもののみです。入院費の未払分や、被相続人に課せられた税金も債務です。
なお、公租公課は被相続人が亡くなった際に納税義務が確定しているもの、準確定申告で納めた所得税額は差し引くことが可能です。
しかし、相続人が納付したものや徴収された加算税や延滞税は財産から差し引きません。
3-4 寄付金
相続税の申告期限内に相続した財産を、公共団体や国、公益法人に寄付すると、寄付した分の相続税が非課税になります。
なお、申告期限は故人が亡くなったのを知った日の翌日から起算して、10か月以内です。
4. 相続税が無税になる可能性もある控除や特例
控除や特例を活用すると、相続税が無税になることがあります。
しかし、それぞれ要件や割合が決められているため、正しい方法で計算しなければなりません。
そこで、主な控除や特例、要件を紹介します。
4-1 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が財産を相続する際、配偶者が受け取った財産のうち法定相続部、もしくは1億6,000万円どちらか高いほうの金額までが控除されます。
例えば、相続したのが1億6,000万円以下の場合、相続割合を問わず配偶者は相続税を支払う必要がありません。
しかし、以下の要件を満たす必要があります。
- 税務署へ相続税申告書を出している
- 財産分割協議が終わっている
- 法律上の配偶者である
法律上の配偶者の必要があるため、事実婚は認められません。
また、財産分割協議が終わっていなくても申告期限後3年以内の分割見込書を出すと条件を満たせます。
4-2 小規模宅地等の特例
事業者住宅を相続した際に使える特例であり、土地の評価額を最大で80%削減することが可能です。
限度面積や適用条件減税割合は、以下のように決められています。
特定居住用宅地:限度面積330平方メートル、減額率80%
特定事業用宅地:限度面積400平方メートル、減額率80%
貸付事業用宅地:限度面積200平方メートル、減額率50%
相続することが多い自宅の条件は、配偶者が相続した場合は条件がなく、同居している親族が相続する際には相続税の申告期限内に居住継続宅地所有をしなければなりません。
別居する親族が相続する際には、相続税の期限内に宅地所有が必要であり、持ち家に居住していないことが条件です。
4-3 未成年者控除
未成年者は働いていないことが多く、所得も無いことが前提です。そのため、未成年者が財産を相続した際には、相続税の一部が免除される制度があります。
財産を相続した未成年者が20歳になるまで、1年ごとに10万円控除されることが特徴です。
20歳以上の方と同様に相続税を算出し、相続税額から未成年者控除額を差し引いて計算します。
なお、相続した財産の額から未成年者控除額を差し引くわけではないため注意しましょう。
4-4 障害者控除
障害者控除は、障害を持っている法定相続人が財産を相続した際に、法定相続人が納税すべき金額から一部を控除する特例です。
障害者控除の金額は、一般障害者と特別障害者で以下のように定められています。
一般障害者:満85歳までの1年につき10万円
特別障害者:満85際までの1年につき20万円
金額は相続人の年齢や、障害の度合いで異なることが特徴です。
4-5 相次相続控除(二次相続)
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)は、10年以内に何度も相続をした際、一次相続で納税した税金の一部を、二次相続の相続税から控除できるものです。
相次相続控除の控除額は、第一次相続で支払う相続税額のなかで経過年数×10%の割合で減額されます。
例えば、第二次相続の被相続人が第一次相続の際に100万円を納税した直後に他界した場合、経過年数の減額はなく、100万円が第二相続で控除されるのです。
なお、要件としては相続人であること、相続発生前の10年以内の相続で被相続人が財産を相続したこと、前回の相続で被相続人に税金が課せられていることの3つが挙げられます。
今回の相続の被相続人の相続人でなければいけないため、遺言書で財産を受け取った方や、相続放棄をした方は対象外です。
さらに、前回の相続で被相続人に相続税が課せられている必要があります。例えば、軽減措置で相続税を納税していないと、対象外になります。
4-6 贈与税額控除
相続もしくは遺贈で財産を受け取った方が、被相続人から開始される前の3年以内に暦年贈与を受けた際には、贈与で受け取った財産の金額を相続税の課税価格に足して算出します。
贈与の際に贈与税を支払っていると、贈与税と相続税が二重課税されてしまいます。
そのため、贈与の際に支払った贈与税は、相続税額から控除されるのです。
贈与税は1月1日~12月31日までの贈与に課税されるものですが、相続税の課税価格に足す贈与は、相続開始前3年以内の応当日です。
また、贈与税額控除は、以下の計算式の合計で算出できます。
①相続開始の前年分の贈与税額控除
該当年の暦年課税の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/該当年分の贈与税の課税価額合計
②相続開始の前々年分の贈与税額控除
該当年の暦年課税の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/該当年分の贈与税の課税価額合計
③相続開始の前々々年分の贈与税額控除
該当年の暦年課税の贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額/該当年分の贈与税の課税価額合計
相続税額と比較して贈与税額が大きいケースがありますが、贈与税額が大きい場合は相続税納付額はゼロ円であり、過去の贈与税額部分は返還されません。
4-7 みなし相続財産の非課税枠
相続した財産のほかに、相続人が亡くなった時に受け取る、みなし相続財産と呼ばれるものがあります。
みなし相続財産とは、死亡退職金や生命保険金などです。死亡退職金、生命保険金いずれも、非課税枠の計算は500万円×法定相続人の数です。
さらに、退職金と生命保険金が両方支払われた際は、それぞれの非課税枠を算出して課税価格を計算します。
4-8 その他の控除や納税が猶予されるもの
そのほかの控除や特例として、外国税額控除、特定計画山林の納税猶予、家なき子の特例などが挙げられます。
外国税額控除は、被相続人の財産の一部が、相続税制度がある外国にあるケースで、外国と日本とで相続税が二重払いになることを防ぐためのものです。
外国で相続税を納めている方は、日本で相続税を納める際に、外国にある財産の割合を控除できます。
なお、外国税額控除額は、以下のいずれか低いほうの金額です。
外国で納めた相続税の金額
日本の相続税額の相続財産の合計に対して海外にある財産の割合を掛けたもの
また、特定計画山林については、納税が猶予されます。
農地を相続した場合は、一定の条件を満たすことで相続税の納税を猶予されることがあります。
また、場合によっては相続税が非課税になるケースもあるのです。ほかにも、特定計画山林の特例があり、一定の条件を満たせば納税が猶予されます。
どのような控除でも、申告をしなければ適用されないため注意しましょう。
さらに、家なき子の特例は、小規模宅地等の特例で、同居していなかった場合で住宅を所有していない相続人が相続する際には、小規模宅地等の特例と同じ内容の特例を受けられます。
しかし、家なき子の特例を悪用する事件が多発しました。そのため、税制が改正され、以下のどれかに該当する場合は特例が適用されなくなりました。
- 相続開始前に1回でも持ち家があった
- 相続開始前の3年以内に、自分の三親等以内の親族や同族会社が保有する建物に住んでいた
5. 相続税が無税かどうか把握するための計算方法
税金について詳しく知らない方でも、相続税が無税かどうかを確認するための計算をすることは可能です。
相続する可能性がある場合には、以下のステップで相続税を計算しましょう。
税金について詳しく知らない方でも、相続税が無税かどうかを確認するための計算をすることは可能です。
相続する可能性がある場合には、以下のステップで相続税を計算しましょう。
5-1 STEP1.課税される遺産の総額を計算する
相続税を納税しなければならない場合は、相続税の総額を算出しましょう。
財産総額を法定相続人で按分して、税率を掛けて控除を差し引いて相続税額を計算します。
次に、相続税額を合計して相続税の総額を算出しましょう。
貯金はもちろん、債務も相続の対象です。
全ての財産の総額を計算することから始めましょう。
5-2 STEP2.債務や葬式費用などを遺産総額から引き、課税遺産総額を計算する
相続税を算出する際には、葬式費用や債務、相続開始前の3年以内に収めている贈与税は差し引きます。
また、差し引きされる財産の具体例は以下の通りです。
債務:借入金、未払金、連帯保証債務
葬式費用:通夜や告別式の費用、遺骨や遺体の移動費用、お布施で渡した費用
支払った税金:3年以内の贈与財産の贈与で納税した贈与税、相続時精算課税制度適用時に納税した贈与税
5-3 STEP3.基礎控除額を差し引く
法定相続人の数と財産の総額を確認したら、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の計算式で基礎控除を算出します。
例えば、子供が3人と配偶者で法定相続人が4人だったケースでは、3,000万円+2,400万円で5,400万円が基礎控除額です。
法定相続人が多いと、基礎控除額も大きくなります。
法定相続人の金額ごとの控除と税率は、以下のように決められています。
|
法定相続分ごとの取得金額 |
控除額 |
税率 |
|
1,000万円以下 |
‐ |
10% |
|
3,000万円以下 |
50万円 |
15% |
|
5,000万円以下 |
200万円 |
20% |
|
1億円以下 |
700万円 |
30% |
|
2億円以下 |
1,700万円 |
40% |
|
3億円以下 |
2,700万円 |
45% |
|
6億円以下 |
4,200万円 |
50% |
5-4 STEP4.相続人ごとに相続できる遺産総額を計算する
相続税を納税しなければならない場合は、相続税の総額を算出しましょう。
財産総額を法定相続人で按分して、税率を掛けて控除を差し引いて相続税額を計算します。
次に、相続税額を合計して相続税の総額を算出しましょう。
法定相続人の金額ごとの控除と税率は、以下のように決められています。
5-5 STEP5.特例や控除などを差し引き、最終的な納税額を計算する
財産の総額から、特例や控除などの金額を差し引きます。
合計がプラスであれば相続税は課税されますが、マイナスの場合は相続税は無税です。
6. 相続税が無税の場合でも申告が必要なケースもあるので要注意!
相続税が無税なら、申告自体不要だと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、無税でも申告しなければならないことがあります。そこで、申告が必要な主なケースを確認しておきましょう。
6-1 課税財産が基礎控除以下の場合は申告不要
相続税がゼロ円の場合は、税務署に申告をしなくてもよいケースがあります。
申告が不要なケースは、財産総額が相続税の基礎控除額以下だった場合です。
相続税は財産のなかで基礎控除額を超えた場合に課税されます。
配偶者の特例や小規模宅地の特例などを受ける前に、財産の総額が基礎控除以下だった場合申告は不要です。
しかし、株式や不動産を加算し、財産の総額を正しく把握している必要があるため注意しましょう。
6-2 特例や控除を利用して無税になった場合は申告が必要
基礎控除額以上の財産がある場合は、基礎控除額を超えた部分に相続税がかかるため申告や納税をしなければなりません。
特例を使って相続税がゼロ円だった場合は、相続税の申告だけ行います。
特例は相続税評価額を下げられるほか、基礎控除以下であった場合にゼロ円申告をしなければならないものや、相続税の課税対象財産が0だった場合に申告が必要なものがあります。
特例は要件が定められているため、財産を誰が相続するのか、どのように相続したのかなど、要件を満たせるかどうか確認する必要があります。
7. 相続税をできるだけ無税に近づけるためには節税対策が効果的
相続税を無税に近づけるための節税対策として定番なのは、生前贈与です。
生前贈与のなかでも、1年間で110万円の財産をゼロ円で子供や孫に移す暦年贈与が挙げられます。
1月1日から12月31日の暦年ごとに、贈与した財産の合計額に応じて増税を支払う方法で、1年間で110万円以内で寄贈する棟の契約書を作る必要があります。
贈与税は1年間で110万円の基礎控除があるため、110万円以内で寄贈をすれば課税されないのです。
贈与税の非課税枠を使うことで、ゼロ円で財産を移すことが可能です。
現金を贈与する方法が最も簡単で、財産に要件もありません。
ほかにも節税対策の種類はいくつかありますが、いずれも早めに行うことが重要です。
なお、相続税の節税対策を行っても、贈与が不公平で親族間で争いに発展するケースは少なくありません。
節税対策をする際にはトラブルにならないよう、検討する必要があります。
相続のトラブルは誰にでも起こるものであり、「自分の親族は大丈夫だ」と考えず、しっかり検討・準備をしましょう。
8. 相続税が無税か、申告が必要か、気になる場合は税理士に相談
相続した財産の合計が基礎控除額以下の場合、相続税が無税です。
さらに、基礎控除額以上だった場合でも特例や控除を使えば相続税を支払わなくて良いケースがあります。
相続税がどのくらいなのか確認したい場合には、紹介した計算方法を使って相続税をチェックするのがおすすめです。
しかし、相続税の控除や特例は適用条件が決められており、正しく判断するのは非常に難しいと言えます。
申告期限が決められているため、仕事や家事をこなしながら手続きを行うのは負担が大きいものです。
相続税については税理士に相談しましょう。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。