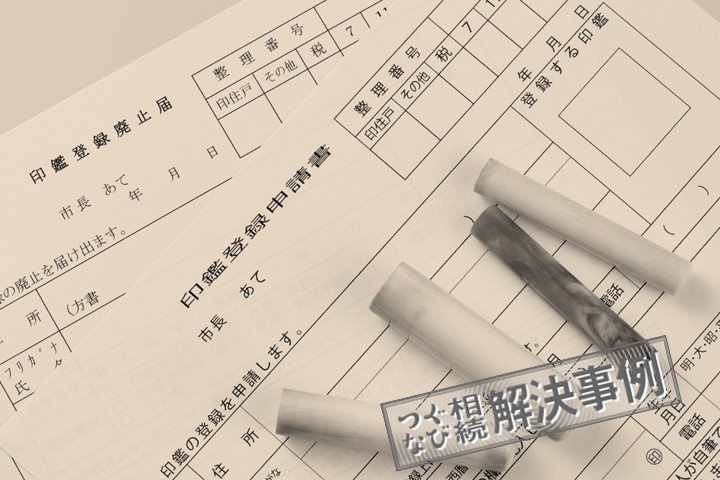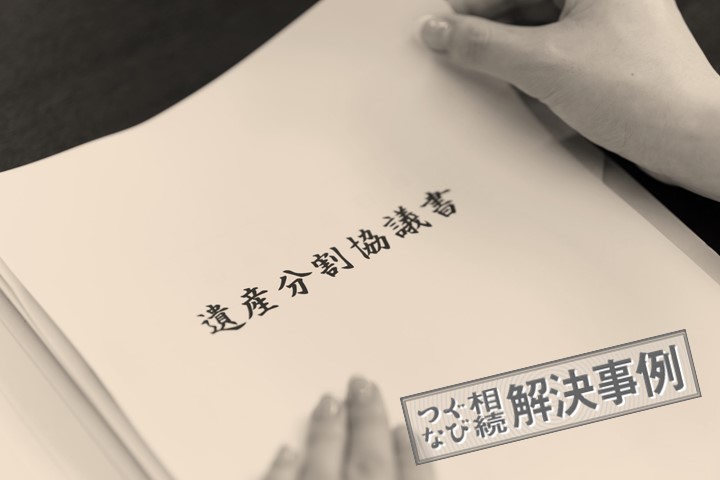相続税の抜け道、節税方法を紹介します。誰もが知る基本的なものからテクニカルなものまで幅広く扱いますので、相続税の抜け道を探している人はぜひ参考にしてみてください。
相続税にはたくさんの控除や特例が用意されています。すべてを完璧に理解するのは難しいですが、どんな減税方法が存在するのかをあらかじめ知っておくだけでも役に立つはずです。
目次
1. 相続税の抜け道?相続税対策・節税について知っておきたい7つのこと
相続税に抜け道があるとしたら、それは早めに動くことです。
生前贈与、生命保険の非課税枠の利用、アパートの建築、タワーマンションの購入、お墓の購入にいたるまで、相続税が節税できる方法はたくさんあります。
ですがそのほとんどは生前にできるものばかりです。死んでしまってからできる節税対策は数が限られます。
前もって計画的に進めておくことで将来の相続税をぐっと減らすことができますし、うまくいけば相続税の申告そのものを不要にできます。
純粋な意味での抜け道はありませんが、準備さえ怠らなければ大きなコストカットを期待できるのが相続税です。
1-1 生前贈与を活用する
生前贈与は相続開始後を意識した節税テクとして活用されています。
子供がまだ若かったり、孫がいる親は教育資金贈与、住宅取得等資金贈与、結婚・子育て資金贈与は非課税枠も大きいので、この3つの特例はぜひ押さえておきたいところです。
年間110万円以下なら贈与税がかからない
生前贈与すると受贈者に贈与税が課税されますが、毎年1月1日から12月31日までを課税年度とし、受贈者ごとに110万円の基礎控除があります(=暦年贈与)。
例えば、子夫婦と孫の3人にそれぞれ110万円ずつ贈与することで、年間330万円、10年間継続すると3300万円分の相続財産を無税で減らせます。
死亡前3年位内の贈与に対しては相続税が課税される
暦年贈与で相続財産を減らすテクニックは、死亡前3年分に限り効果がありません。上記期間に贈与した分は相続税の課税対象になるのです。
暦年贈与の基礎控除の範囲内で相続人に財産を移転させようとする場合、目標を達成できるよう、被相続人がなるべく若いうちに着手する必要があります。
税金なしで贈与できるもの
暦年贈与による贈与財産の価額が年間110万円を超えていても、教育・住宅・結婚・子育ての各用途なら、制度によりまとまった額の非課税枠が適用されます。
適用対象となるのは、親から子あるいは孫のように、直系尊属から直系卑属に贈与がされた場合に限ります。
上記の制度は暦年贈与と併用できます。例えば「直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の場合、非課税枠1千万円※と基礎控除の合計額である1,110万円までなら、まとまった額を贈与しても課税額ゼロとなります。
※令和5年12月31日までに資金を贈与し、受贈者が性能の高い住宅を取得した場合
1-2 生命保険を活用する
生命保険の加入は現金相続の際の節税策であり、納税資金対策にもなります。
掛金支払いと保険金に対する非課税枠の相乗効果により、最低でも預貯金のうち500万円までは課税額ゼロで所有を移せるのです。
特におすすめできるのは、会社経営者や地主家系等、換金性の低い(もしくは換金出来ない)財産に資産比率が偏っている人です。
生命保険の非課税枠
生命保険にはひとりあたり500万円の非課税枠が適用されます。法定相続人が配偶者と子の計2名であれば、保険金請求時に500万円×2人=1千万円まで非課税となります。
注意したいのは、契約者と被保険者が同一人物でないと非課税の枠は使えない点です。
例えば、夫婦それぞれ被保険者となり、夫が2人分の掛金を支払う(=夫が契約者)場合を考えてみましょう。夫の死亡時には相続税の非課税枠の適用があるものの、妻の死亡時にはありません。
受取人が夫なら所得税、受取人が子であれば贈与税……とのように、保険金に対する課税の種類自体が変わってしまうためです。
子供や孫に生命保険をかける
解約返戻金の変動を使った相続税対策もあります。解約返戻金とは、積立式の生命保険を途中で解約した場合に戻ってくるお金であり、その権利は契約者自身に帰属すると考えられます。
つまり、自分が掛金を支払っている保険の「契約者の地位」を子供や孫に引き継ぐことで、解約返戻金=元々は相続財産である現金を譲り渡せるのです。
1-3 不動産を活用する
不動産を利用した節税対策があります。タワーマンションの最上階を買うと節税になる、土地にアパートを建てると節税になる、そういった話はよく耳にします。
現金のまま保有するのは相続税対策の点からは得策とはいえません。現金を不動産の形に変えることで相続税をカットできるケースはたくさんあります。
しかし不動産を活用した節税対策にはテクニカルな要素を含むものが多いのが難点です。望ましい結果を得るには専門的な知識や綿密なシュミレーションが求められます。
相続税対策を目的として不動産の活用を視野に入れる姿勢は大切です。しかし良い形で実現させるには税理士など専門家のアドバイスが欠かせません。
不動産投資をする・タワーマンションを購入する
不動産投資は節税効果があると言われます。三大都市圏等にある好条件の物件を購入すれば、取引価格にあたる「時価」が跳ね上がる一方で、課税計算の元になる「相続税評価額」は低いままです。
つまり、僅少の納税資金で高額な財産を受け継げることになります。節税策として人気のタワーマンションは、平成29年の税制改革により、低層階ほど固定資産税が安くなる調整が入り、ますます所有しやすくなりました。
ただ、取引価格と相続税評価額の乖離を利用した節税策は、国税庁が動向を掴み問題視しているところです。
相続開始後に「相続税評価額ではなく時価から課税額を計算する」等と否認されてしまうと、元も子もありません。今後の税制改正や国税不服審査の判例には要注目です。
更地に賃貸アパートやマンションを建築・経営する
更地に賃貸アパートやマンションを建築すると、土地と建物を含めた不動産全体の相続税評価額が下がります。建物に他人が住むとそのぶん所有者が利用できなくなるからです。
具体的な節税額は該当する土地の借地権割合やアパートの満室率によって変わりますが、目安として15%から20%程度の土地の評価減が期待できます。
条件を満たせば小規模宅地等の特例(貸付用事業用宅地)も重ねて適用されますので、さらなる相続税の減額が見込めます。
更地にアパートやマンションを建て他人に貸し出すことは、相続税評価額を半分近くまで下げられる可能性を秘めているのです。
ただ、支出オーバーや入居率低下によって賃貸経営がうまくいかなければ、節税どころか大赤字を出しかねません。そのあたりは慎重になる必要があります。
1-4 お墓や仏壇など非課税財産の生前購入する
お墓や仏壇は「祭祀財産」にあたり、相続開始時は非課税財産として扱われます。ものによっては購入に数百万単位のお金がかかり、そのぶんは節税効果が期待できるのです。
ただし、生前の購入分しか非課税と見なされない点の他、祭祀承継者(=お墓等を受け継いで法事・祭事を続ける人)を巡って相続トラブルとなる可能性がある点には注意しましょう。
1-5 養子縁組をして法定相続人を増やす
相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠では、法定相続人の数に応じて非課税額が増えます。法定相続人には養子も含まれており、子供の配偶者や孫等と養子縁組しておけば、相続税の基礎控除なら+600万円の加算を利用出来るのです。
注意したいのは、過度な税対策を防ぐ観点で、養子の数には税法上の制限がある点です。戸籍法上の手続きで2人・3人……と次々に養子縁組を進めても、実子がいれば1人、実子がいない場合は2人までしか相続税の計算には含められません。
1-6 寄付を行う
公益法人等の指定の団体に遺産を寄付した場合、その価額について相続税の全額控除が受けられます(寄附金控除)。
子供がいなかったり、維持費が嵩む遊休不動産が合ったりするようなケースでは、教育・学術・福祉等の分野で有効活用できる団体に課税額ゼロで移転できるのです。
ただし「相続人名義で学校法人を立ち上げさせる」等、明らかに税対策と思われる場合は適用できません。
加えて注意したいのは、たとえ善意であっても、生前の調整がないと寄付を受け入れる団体にとって迷惑になる可能性がある点です。
1-7 相続税の控除や特例についての理解をする
相続税の減税につながる控除の仕組みや特例がたくさんあります。
基礎控除は相続税の申告が必要になるかならないかの基準になりますので、なんとしても理解しておきたいところです。そのうえで余裕があれば各種控除や特例の知識を深めましょう。
小規模宅地等の特例に代表されるよう、相続税の控除や特例には要件が細かく専門家でないと判断が難しいものが含まれます。完璧に理解する必要はありません。
ですが全く知らないのも問題です。控除や特例が使えるにもかかわらず放置すると無駄な税金を支払うハメになってしまいます。これは使えそうだと思った控除や特例があれば、積極的に税理士に相談しましょう。
2. 相続税の正式な抜け道として知っておきたい相続税の7つの控除
相続税における控除といえば基礎控除、配偶者控除あたりが有名ですが、控除の種類はほかにもあります。相次相続控除や外国税額控除など知らない人も多いのではないでしょうか。
ここでは相続税の抜け道につながる7つの控除を紹介します。控除の計算には複雑なものも含まれますので、気になる控除や詳しく知りたい控除があれば税理士に相談するなどして確認しましょう。
2-1 基礎控除
無条件に相続財産から控除されるのが基礎控除です。基礎控除をしてもなお相続財産がマイナスであれば相続税の申告は基本的に不要ですが、プラスであれば相続税の申告が必要になってきます。
基礎控除の計算は相続税の申告対象になるかならないかの決め手になりますので、相続税を考える際には最低限マスターしておきたい知識です。
相続税の基礎控除額は「3,000万+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続人が二人なら4,200万円が基礎控除額です。相続した財産が4,200万円より多いか少ないかで申告の要否が変わります。
法定相続人の数が多いほど控除を受けられる仕組みなので、節税のために養子縁組をして法定相続人を増やすなどの方法も考えられます。
2-2 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者が財産を相続すると課税価格の1億6,000円まで無税の扱いを受けます。
さらに1億6,000万円を超える場合であっても、法定相続分が1億6,000万円以上なら、さらに法定相続分の額まで非課税枠が広がります。(子供がいる場合の)配偶者の法定相続分は2分の1なので、相続財産の総額が4億円なら2億円まで無税になります。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)が認められている背景には配偶者の生活保障の必要性や、残されたもう一方の親が死亡したとき、いわゆる二次相続の際にどのみち課税されるからという理由があります。
基礎控除と異なり配偶者控除は申告してはじめて認められるので注意が必要です。
2-3 未成年者控除
財産を相続したのが未成年者であれば税金控除の対象です。未成年が相続開始から20歳に達するまでの年数によって控除額が決まります。
控除額は1年につき10万円で、未成年者が12歳なら成人するまで8年ありますので、80万円(10万円×8年)が相続税額から引かれます。
未成年者控除の特徴は控除額のくりこしが認められる点です。未成年者の納税額が80万円を超える場合は納税額が0円になるのはもちろん、控除し切れなかったぶんは扶養義務者の相続税額から控除できます。
2-4 障害者控除
未成年者控除と似たものとして障害者控除があります。財産を相続したのが障害者であれば、相続開始から85歳になるまでの年数によって控除額が決まります。
控除額は1年につき10万円が原則ですが、身体障害者手帳1級~2級や重度の知的障がい者、その他にいつも病床にいて複雑な介護を要する人等は、特別障害者として1年あたりの控除額が20万円に増額されます。
未成年者控除と同じく控除額のくりこしが認められますので、控除し切れなかったぶんは扶養義務者の相続税額から控除できます。
2-5 贈与税額控除
贈与税の二重払いを防ぐために贈与税が控除される場合があります。いわゆる贈与税額控除です。贈与税額控除が適用される場面は、暦年贈与と相続税精算課税が適用されるケースです。
暦年贈与を使うと1年あたり110万円までの贈与税が非課税になりますが、死亡から3年以内の贈与についてはさかのぼって課税対象になりますので、3年間ぶんの贈与税がまるまる課税されてしまいます。
しかしその3年の間に、(非課税枠でおさまらない)110万を超える贈与がされた場合、既にいくらかの贈与税が支払われているはずです。
贈与税額控除はこのように贈与税の二重払いが起こる場面で適用されます。相続税精算課税でも類似の問題が生じますので、その際は同じく贈与税額控除が適用されます。
2-6 相次相続控除
相次相続控除は10年の間に相続が連続した場合に適用される税額控除です。
相続税は納める金額が高額になりがちなのでお金の準備が大変です。にもかかわらず短期間のうちに相続が発生してしまうと納税者にとっては酷な結果を招きます。
両親の一方が亡くなった場合の相続(一次相続)は、配偶者控除や小規模宅地等の特例など大胆な相続税評価額の控除が使えます。
しかし、残された一方も死亡した際の相続(二次相続)では、これといった特例が使えないケースが多く、相続人の納税負担が大きくなりがちです。
短期間のうちに両親が相次いで死亡した場合、納税者の負担が甚大になることが予想されますので、相次相続控除という形で特別の控除を認めバランスをとっているのです。
2-7 外国税額控除
外国税額控除は二重課税の問題を解消するために認められた制度です。海外にある財産を相続した場合は、日本での課税と日本以外の国での課税の、二つの課税が問題になります。
日本以外の国で課税されたあげく、さらに日本でも課税が重なると税金の二重払いになってしまいます。納税者にとってあまりにも酷な結果になりますので、二重課税が生じないよう調整するのが外国税額控除です。
3. 相続税の支払いを逃れる方法はあるの?
相続税は税務署が特に力を入れている税金の一つです。
特例や控除など適法な節税方法を除けば、相続税の支払いを免れる方法はないと諦めたほうが良いです。相続税の支払対象になる遺産を相続したにもかかわらず無申告をつらぬけば、いずれ税務調査が入ります。
国税庁や税務署はKSK(国税総合管理)と呼ばれる巨大なデータベースを用いて納税者の情報を一元管理しています。
銀行や市役所、生命保険会社らと連携をとり、まとまった現金の移動や保険金の入金、不動産名義の取得など、財産の動きはあらかた税務署が把握しています。
適切な申告がされず無申告や申告漏れがあると、本税に加えて延滞税や加算税も支払うハメになります。相続税の支払い逃れはできないと覚悟して、適切な節税対策、納税申告を目指しましょう。
4. 死後に相続税を節税する3つの方法
相続税対策には生前を前提とするものが多く、死後にあっては打てる手が限られます。しかし相続開始後でもまったく手がないわけではありません。
むしろ死後にやるべき対策をやらなかったがために、無駄な相続税を支払うケースもあります。
また相続税の申告には10か月の法定期限がありますので、対策を打つとしても急ぐ必要があります。相続直後は精神的にも余裕がないのが普通なので、そういった意味でも死後の対策については税理士に相談することをおすすめします。
4-1 葬儀費用として使う
葬儀費用は被相続人名義の残債と合わせて「債務控除」の対象になります。被相続人の社会的地位等を考慮して適当な金額であれば、領収書等を残しつつ規模の大きいお葬式を開くことで、いくらか相続税を安く抑えられます。
4-2 土地の評価額が下がるように分筆する
相続税評価額の低下を狙ってあえて土地の評価額を下げると節税につながります。
土地には路線価と言われる相続税評価の基準になる価格が設定されているところ、例えば土地によっては路線価が二つ存在する場合があります。
二つあるときは高い路線価で計算するのがルールである一方、高い路線価で計算されてしまう結果、土地の評価額が高くなってしまいます。
ルールである以上仕方のない結論とも言えますが、そこをあえて土地を二つに分ける、つまり分筆することで土地の一部を低い路線価で計算することが可能になります。結果として土地の評価額が下がり相続税も安くなるのです。
4-3 税理士に相談をする
相続税対策の基本は生前に手を打つのが基本ですが、死後であっても税理士が思ってもみなかった方法を提案してくれる場合があります。例えば土地の評価です。
土地は路線価で評価するのが基本ですが、不整形地など土地の利便性の悪さを証明することで相続税評価額が下がる余地がでてきます。
不整形地の証明には説得力のある図面の作成や申告書の作成が前提になりますので、税理士の力が必要不可欠です。
不整形地のような話は一例にすぎず、税理士が申告書の作成にかかわることで節税につながるケースはたくさんあります。積極的に税理士に相談してみましょう。
5. 相続税の節税や、合法的な抜け道を知りたい場合は税理士に相談
王道からテクニカルなものまで、相続税対策は幅広く存在します。相続税対策はやったほうがいいのは間違いないです。
しかし節税には細かい要件だったり、死後税務署に否認され使えなくなってしまうリスクを抱える方法も含まれます。
特に不動産を使った節税対策は、近年の三大都市圏の価格高騰や賃貸経営ブームに踊らされず、慎重に見極める必要があります。
また節税を重視しすぎて遺留分への配慮等が漏れ、相続時の取り分が不公平となってしまうのも本末転倒です。
相続トラブルが起きると、遺産分割調停や審判・家事訴訟のため相続財産の帰属が長期間あいまいになり、その間の維持がおろそかになる可能性があります。
特に土地建物は、ちょっとしたメンテナンス不良が大幅な価値下落あるいは赤字に繋がる恐れがあるため、注意しなくてはなりません。
税務署に否認されない安全な節税テクニックは、各種制度の特徴とメリット・デメリットを理解している税理士に相談するのが安全です。
6. まとめ
今回は相続税の節税につながる方法をいくつか紹介しました。暦年贈与やマンション建築などよく聞くものもあれば、養子縁組や土地の分筆などテクニカルに感じたものもあったのではないでしょうか。
- 相続税対策は生前が基本
- 控除や特例を知らないと損をする
- 死後でも税理士を頼ると思わぬ節税方法を案内されることがある
相続税は莫大な納税額に及ぶ可能性があるため、抜け道を探したくなる気持ちもわかります。しかし中にはリスクを含むものが含まれています。
あまたある控除や特例の存在を知るのはもちろん有効ですが、本当にその方法が期待する結果を生むかどうかについては、今一度、税理士に相談してみるのがいいでしょう。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。