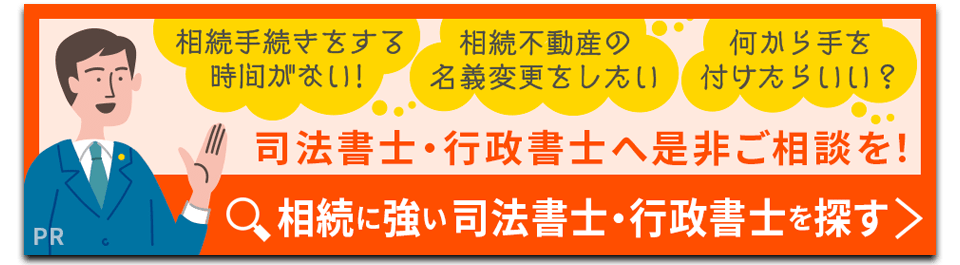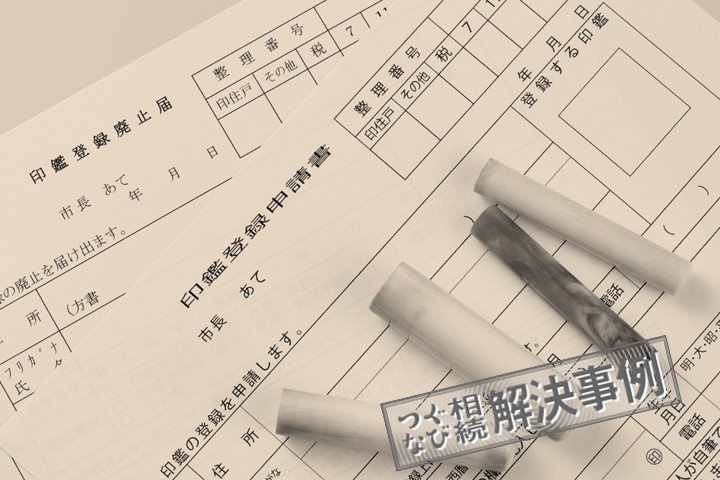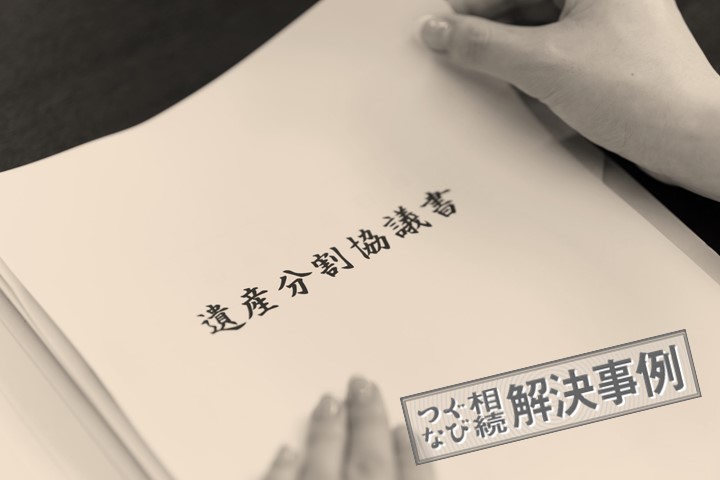将来について考えた時、家族に不幸があった場合に知っておくべき知識はいくつもあります。
その1つが「遺族年金」です。
遺族年金を受け取るためには、様々な要件があります。
今回の記事では、いくつかある遺族年金の中の「遺族厚生年金」について詳しく解説していきます。
受給するための条件や対象者、手続きについて知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 遺族年金とは?
遺族年金とは、公的年金の被保険者に該当する方が死亡した場合に家族が受け取れる年金です。
いくつか種類がありそれぞれで特徴が異なるため、以下の項目で詳しく解説していきます。
1-1 被保険者の死後、遺族に給付される公的年金
遺族年金を受け取れる家族は、死亡した被保険者の収入で生計を立てていた配偶者や子どもなどが該当します。
被保険者の家族構成や職業によって受け取る年金の種類も変わってきます。
また、配偶者が受け取る場合には、似た条件であっても妻と夫ではもらえる金額なども違います。
1-2 遺族年金の種類
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
これは死亡した被保険者の家族構成や職業によってもらえる種類が変わります。
2つの種類のどちらか、もしくは両方受けられる場合もあります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡した人が国民年金の被保険者だった場合に受け取ることができます。
死亡した方が第1号被保険者か第2号被保険者に該当していることが条件です。
遺族基礎年金を受け取れる方は、死亡した方の収入で生計を立てていた「子どもがいる配偶者」もしくは「子ども(対象者となる親がいない場合)」が対象となります。
条件となる「子ども」とは、18歳になる年度の3月31日までの間にある子ども、被保険者が死亡した時に胎児であった子ども、20歳未満で1~2級の障害を持っている子どもが該当します。
受け取れる条件は、以下の通りです。
・死亡した被保険者が国民年金に加入していた
・死亡した被保険者が老齢基礎年金を受給していた
・被保険者の60~65歳の人で日本に住んでいる
・老齢基礎年金の受給資格期間である
・死亡した方が生前保険料を納めていた
遺族基礎年金を受け取れるのは、配偶者または子どものみです。
配偶者が死亡、再婚、直系血族または直系姻族以外の者の養子になった場合と、子どもが死亡、婚姻、離縁によって被保険者だった者の子でなくなった、直系親族以外の者の養子になった、18歳になった年度の3月31日が終了した、1~2級の障害に該当するが20歳になった場合は受け取ることができません。
受け取れる金額は、本体となる老齢基礎年金と同額の部分、加算部分と言われる子どもを扶養するための部分で構成されています。
【関連記事】遺族年金についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族基礎年金ガイド|遺族基礎年金とは?条件・手続き・注意点を簡単解説
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、死亡した人が厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に該当していた場合に遺族が受け取れる年金です。
ここからは、今回の記事のメインとなる「遺族厚生年金」について詳しく解説していきます。
【関連記事】遺族年金についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?|【遺族厚生年金と国民年金】
2. 遺族厚生年金の受給条件や対象者
遺族厚生年金の特徴としては、上記で説明した遺族基礎年金よりも受給資格が広範囲になります。
受給条件や対象者については以下の通りです。
2-1 受給条件
遺族厚生年金を受け取るためには、死亡した人が納めていたということが条件となります。
死亡日の前日において保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上であるということが必要です。
特例として、2026年3月31日までであれば死亡した日の前々月までの1年間に滞納していなければ受け取ることが可能です。
2-2 対象者
受け取れる人には優先順位が決まっていて、以下の通りとなっています。
対象となるのは「被保険者に生計維持を維持されていた」という点を前提とします。
1位は「妻」で、配偶者は妻が年齢不問、夫の場合は55歳以上という年齢制限が決まっています。
2位の子どもは18歳を迎える年度の3月31日までにある方、もしくは20歳未満で1~2級の障害を持っている方となります。
3位は「父母」で55歳以上、4位は「夫」、5は「祖父母」で55歳以上と決まっています。
夫が死亡した時に55歳以上であれば受け取ることができますが、実際に受け取れるのは60歳以降となっています。
「生計を維持されていた」とはどういう状態を指す?
この状態は、死亡した人と受け取る人が「同居 (他にも別居しているが仕送りや健康保険の扶養親族であるなど)」ということ、「前年度の収入が850万円未満(所得は655万5,000円未満)である」ということを満たしている必要があります。
これらの内容から判断されるので、条件を満たしていなければ受け取れる資格がない可能性もあると言えます。
配偶者
配偶者でも、妻と夫では年齢制限が変わってきます。
妻は年齢不問で受け取ることが可能です。
しかし、夫が死亡した時に30歳未満かつ、子どもがいない妻の場合は5年間が給付期間となります。
夫については妻が死亡した時に55歳未満である場合は受け取ることができません。
夫が受け取れるのは、妻が死亡した時に55歳以上であるということ、遺族基礎年金を受け取れる場合のみとなっています。
条件を満たしていなければ夫は遺族厚生年金を受け取ることができず、下位の人が受け取れるようになります。
また、夫は妻が死亡した時に55歳以上であってもすぐに受給できるという訳ではありません。
原則として、60歳になるまで支給停止状態となり60歳を超えなければ受け取ることはできないのです。
例外的には妻が死亡した時に55歳以上の夫が遺族基礎年金を受け取れる場合は60歳になるまでの支給停止はありません。
子どもがいる配偶者と子どもは遺族基礎年金も一緒に受けることが可能です。
子・孫
18歳の年度末を迎えていない子ども(孫)や20歳未満で1~2級の障害を持っている子ども(孫)が対象となります。
子どもは配偶者に次いで優先順位が2位ですので、配偶者が受け取る場合には子どもは受け取ることはできません。
孫の優先順位は第3位となるので、死亡した人の父母が生きている場合は受け取ることができない場合が多いと言えます。
55歳以上の父母・祖父母
遺族基礎年金とは違って、父母や祖父母も受け取れる対象に入っています。
父母が第4位、祖父母は第6位で、厚生年金被保険者が亡くなった時に55歳以上であるという点は満たしている場合が多いはずですので、上位に該当する人がいなければ受け取れる可能性も高いです。
被保険者が死亡した時に上記の人が55歳以上60歳未満である場合、支給開始は60歳となります。
2-3 受給できる期間
死亡した被保険者に条件を満たす配偶者や子どもがいる場合は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ることができ、うち遺族基礎年金は1番下の子どもが18歳を迎える年度の3月31日になるまでは支給されます。
1~2級の障害を持っている子どもをもつ場合は20歳になるまでの期間です。
これらの期間を過ぎると、そこから遺族厚生年金のみの支給となりますが受け取る人が妻の場合は65歳になるまでの期間は中高齢寡婦加算を受け取ることができます。
妻が65歳を迎えると、自身の老齢基礎年金を受けることになるので中高齢寡婦加算がなくなります。
2-4 受給金額の算出方法
遺族厚生年金で受け取れる金額を算出するには、厚生年金に加入している期間の個人の収入額を確認しなければいけません。
算出する際は、平成15年3月までの被保険者期間の月数とその間の標準報酬月額の平均、平成15年4月から死亡するまでの被保険者期間の月の数または、その期間の標準報酬月額の平均を使います。
詳しい計算方法については以下の通りです。
・報酬比例部分の年金額
平均標準報酬月額×1000分の7.125×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×1000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数×4分の3
・報酬比例部分の年金額
平均標準報酬月額×1000分の7.5×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×1000分の5.769×平成15年4月以後の被保険者期間の月数×1.000×4分の3
誕生日が昭和13年4月2日以降の方は「0.998」になります。
3. 遺族厚生年金を受給するための手続き
遺族厚生年金を受け取るためにはどのような流れで手続きを進めていけば良いのでしょうか?
続いて遺族厚生年金を受給するための手続きを解説していきます。
3-1 手続きの流れ
まず、最初に市町村役場に死亡届を出します。次に、死亡した人が現役の加入者だった場合、会社などを通じて「資格喪失届」を出します。
死亡した人が年金を受給していた場合は、年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を出します。
最後に、必要書類を揃えて年金事務所か年金相談センターに提出してください。
3-2 必要な書類
必要書類は以下の通りです。
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の年金手帳
・死亡者の住民票の除票
・子どもの収入が確認できる書類
・請求者の収入が確認できる書類
・死亡者の死亡診断書(死体検案書)のコピーもしくは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(請求者本人名義)
・印鑑
4. 遺族厚生年金を受け取ったら確定申告は必要?
遺族厚生年金については、非課税となるので確定申告をする必要はありません。
一時所得に該当するように見えますが、遺族年金を受け取る権利は固有の権利なので、厚生年金保険法41条2項では「老齢厚生年金以外の厚生年金について所得税・住民税ともに非課税である」と決まっています。
5. まとめ
今回は、遺族年金の種類や遺族厚生年金の受給資格や対象者などについて説明しました。
遺族厚生年金は、他の遺族年金と合わせても受給できる金額が高いものです。
そのため、誰が受け取ることになるのか、どうやって受け取れるのかを改めて確認しておくようにしましょう。
この記事の監修者
 工藤 崇(くどう たかし)
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。