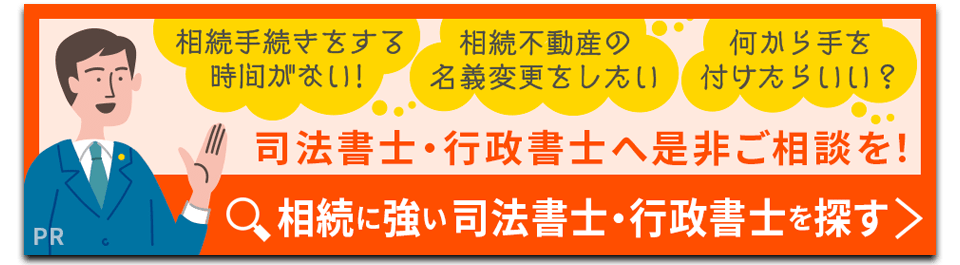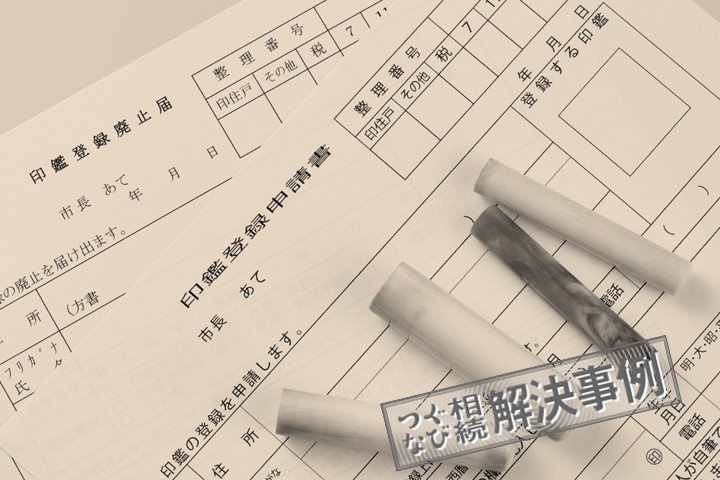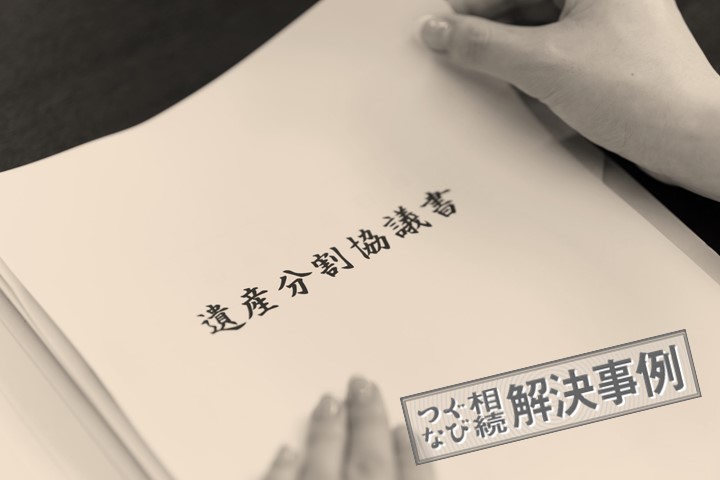寡婦年金とは、国民年金第1号被保険者の給付制度で、第1号被保険者として保険料納付・保険料免除された期間が合計10年以上ある夫の死亡時、その夫に生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚含む)が10年以上あった妻に支給される年金です。
この記事ではそんな寡婦のための年金制度「寡婦年金」について解説します。
申請をしないと受給できない年金のため、「該当するかもしれない」という場合は受給条件や手続き方法をしっかり確認しましょう。
1. 寡婦年金とはなにか

寡婦年金の「寡婦」とは、夫と死別した後も再婚していない女性(未亡人)のことをいいます。
寡婦年金とは、国民年金第1号被保険者独自の給付制度で、第1号被保険者として保険料を納付した期間と保険料を免除された期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していた妻に対して、夫の代わりに支給される年金です。
支給期間は60歳から65歳になるまでです。ただし、平成29年7月31日以前に亡くなった場合は納付と免除期間あわせて25年以上となります。
寡婦年金は受給できる期間が設けられている有期年金で、妻が自身の年金を受け取れるようになるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。
2. 寡婦年金の受給条件
ここでは、寡婦年金を受給できるのが誰なのか、また、受給するためにはどのような条件が必要かを見ていくことにします。
2-1 受給できるのは妻のみ
寡婦年金は、国民年金に加入していた夫と生計を同じくしていた妻だけが受けることができます。
ですから、妻が先に死亡したとしても残された夫には寡婦年金は支給されません。夫には寡婦年金にあたる給付制度がないため、男女で差が見られる年金制度であると言えます。
2-2 国民年金保険料納付期間が10年以上である
夫が国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を10年以上納付している必要があります。
寡婦年金は、亡くなった夫が第1号被保険者として支払った国民年金保険料の掛け捨てを防止することが目的のため、保険料納付要件の10年には、厚生年金保険の加入期間を算入することはできないことに注意してください。
2-3 婚姻期間が10年以上である
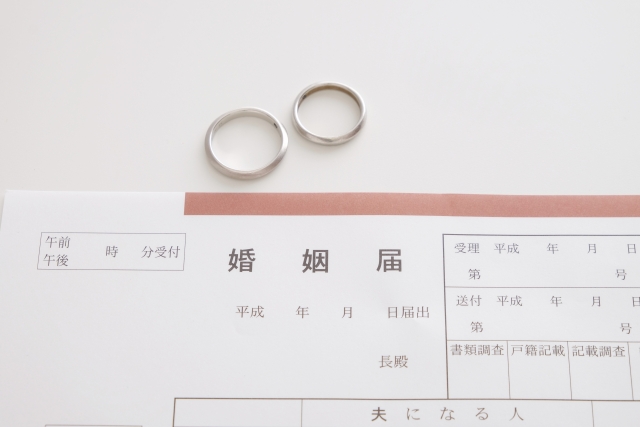
夫が亡くなったときに、妻がその夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、65歳未満であることも条件になります。婚姻していない場合でも、事実婚であることが認められれば寡婦年金を受けることが可能です。
2-4 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがない
寡婦年金を受けるためには、亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないことも条件になります。
2-5 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと
原則として、老齢基礎年金は65歳から受けられる給付制度になっています。しかし、この老齢基礎年金は希望すれば60歳から受け取ることが可能になっており、これを「繰り上げ支給の老齢基礎年金」といいます。
寡婦年金は老齢基礎年金との併給ができないため、老齢基礎年金を60歳からの繰り上げ支給にしている場合は受け取ることができません。
夫が亡くなった時点で、ご自身の年齢や繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているかどうかが寡婦年金を受けられるかどうかの条件にもなりますので注意してください。
2-6 5年以内に請求すること
寡婦年金を受けるためには、妻は夫が亡くなった後、5年以内に請求する必要があります。
3. 寡婦年金がもらえないケース

逆に、寡婦年金を受給することができない場合にはどのような状況があるのかについて確認してみましょう。
3-1 死亡一時金を選択したとき
夫が亡くなったときに、妻が寡婦年金と死亡一時金のどちらも受け取る権利が発生した場合には、寡婦年金か死亡一時金のどちらか一方を受給することができます。
しかし、その際に死亡一時金を選択したときには寡婦年金は受給できなくなります。
3-2 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給しているとき
また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は寡婦年金を受給することはできません。寡婦年金は遺族基礎年金と同時に受給することはできないのです。
3-3 受給権が消滅したときや支給停止になったとき
上記とは異なり、すでに寡婦年金を受給している際に、ある条件に該当したことにより受給権が消滅(失権)したり支給停止になったりする場合があります。
- 受給権が消滅(失権)する場合: 寡婦年金の受給権は、亡くなった夫の妻が次のいずれかに該当したときに消滅します。
- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 再婚したとき(事実婚を含みます)
- 直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
- 支給停止になる場合: 寡婦年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
4. 寡婦年金の額

寡婦年金は、夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者を含む)に基づき、夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3の金額(付加年金部分は除きます)を受給することができます。
ただし、老齢基礎年金額は夫の第1号被保険者であった期間だけで計算されます。
例えば、老齢基礎年金額が780,000円だった場合、寡婦年金の金額は780,000円の4分の3の585,000円になります。
4-1 請求の期限と受給できる期間
寡婦年金は、請求者が請求手続きを行わないと受給できません。ここでは、寡婦年金を請求できる期限と受給できる期間について見ていきましょう。
4-2 請求期限はある?
寡婦年金を受ける権利は、夫が亡くなった日の翌日から(権利が発生してから)5年を経過すると時効によって消滅します。寡婦年金を受給する場合には、請求手続きを忘れずに行うよう注意しましょう。
4-3 受給期間
夫の死亡日(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日)の翌月から65歳になるまで、もしくは死亡、婚姻するまでの間、支給されます。
5. 他の年金と同時に受給できるのか
ここまで述べてきた条件を満たすことで寡婦年金を受給できます。では、寡婦年金と他の年金を同時に受け取ることはできるのでしょうか。
5-1 遺族基礎年金
寡婦年金と遺族基礎年金については、両方の受給要件に該当していたとしても両方の年金を同時に受けることはできません。
ただし、支給時期が重複しない場合に限りそれぞれを受け取ることはでき、支給時期が重複する期間は、いずれか一方の年金を選択することとなります。
例えば、夫が死亡して遺族基礎年金を受給していた妻が、息子が18歳に達したことにより59歳の時に遺族基礎年金を受給できなくなったとします。
このケースでは、再婚せずに寡婦年金を受給できる条件を満たしていれば、60歳になってから5年間、寡婦年金を受けることができます。
つまり、”同時”に受給するのでなければ、寡婦年金と遺族基礎年金はその両方を受け取ることができるのです。
受給できる金額については、通常、寡婦年金よりも遺族基礎年金の方が受給できる金額が大きいはずですので、どちらも受給することができる場合には、必ずしも寡婦年金を選択する必要はなく、受けられる金額をしっかり比較してください。
5-2 死亡一時金
遺族基礎年金と異なり、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受給することができません。
ですので、寡婦年金と死亡一時金のどちらも受け取ることができる権利を持っている方は、より受給できる額の多い方を選択するとよいでしょう。
なお、死亡一時金の額は保険料を納めた月数に応じて変わってきますが、120,000円~320,000円です。
夫に先立たれた妻が寡婦年金を受給できる期間は、60歳から65歳までの5年間です。
もしも、妻が60歳になる前に夫が死亡し寡婦年金を受給するまで長い期間があるという場合には、60歳まで待って寡婦年金を受給するのではなく、死亡一時金を受け取るということも選択肢の一つとして考えることができます。
5-3 寡婦年金と死亡一時金どちらを選べばいい?
死亡一時金の場合、受給できるのは最大で32万円。
一方、寡婦年金の場合は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金のうちの4分の3ですから、結果的に受給できる額が多いのは寡婦年金であると思われますので、受給額の多い方を選ぶとしたら寡婦年金を選ぶことになります。
しかし、妻が、本来は65歳になってから受け取ることのできる老齢基礎年金を65歳になる前に繰り上げ受給していた場合に注意です。
老齢基礎年金と寡婦年金を同時に受給することができないため、この妻は65歳になっても寡婦年金を受け取ることができません。そのような場合には、死亡一時金を受け取るようにしましょう。
6. 寡婦年金を請求するには

ここでは、寡婦年金の請求手続きを行うために必要な書類と書類の提出先について見ていきます。
6-1 請求に必要な書類
寡婦年金の請求には、所定の請求書のほか、下記のような書類の準備が必要です。
①年金請求書(国民年金寡婦年金)
年金請求書の様式や記入例は、市区町村役場、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口などで入手することができます。
②必ず必要になる書類
- 亡くなった方の年金手帳
- 請求者の戸籍謄本など、死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日が確認できる書類
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 請求者名義の受取先金融機関の通帳やキャッシュカード
- 年金証書
- 印鑑(認印も可)
③死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故の内容がわかる新聞の写しなど)
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損害賠償金の算定書(すでに決定済みの場合には示談書等の受領額がわかるもの)
- 損害保険会社等への照会にかかる「同意書」(所定の様式があるので年金事務所に問い合わせること)
7. 提出先
書類の提出先は、住所地の市区町村役場の窓口になります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きを行うことが可能です。
8. まとめ
寡婦年金の手続き方法や基本的な仕組みについて解説してきました。申請しないと受給できない年金で、かつ申請の期限もあるため、該当する場合は必ず申請するようにしましょう。
【関連記事】遺族厚生年金についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族厚生年金ガイド|遺族厚生年金とは?条件・対象者・手続きを簡単解解説
【関連記事】遺族基礎年金についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:遺族基礎年金ガイド|遺族基礎年金とは?条件・手続き・注意点を簡単解説

山本 務
特定社会保険労務士。理系大学卒業後、プログラマー・SEを経て上場企業人事部で人事労務管理業務を約10年経験し、2016年に独立。独立後も2020年3月まで労働局の総合労働相談員として200件以上のあっせん事案に関与。労働相談は労働局の電話相談も含めて1,000件以上の対応実績あり。これまでの知識と経験を活かし、各種サイトでの人事労務関係に関する記事の執筆や監修も積極的に行っている。
オフィシャルサイト: やまもと社会保険労務士事務所
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるようにご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。