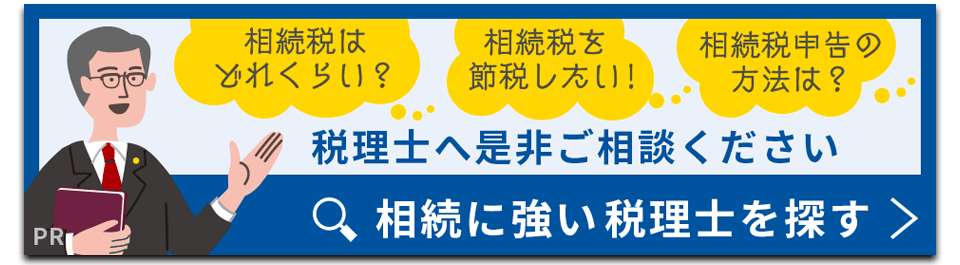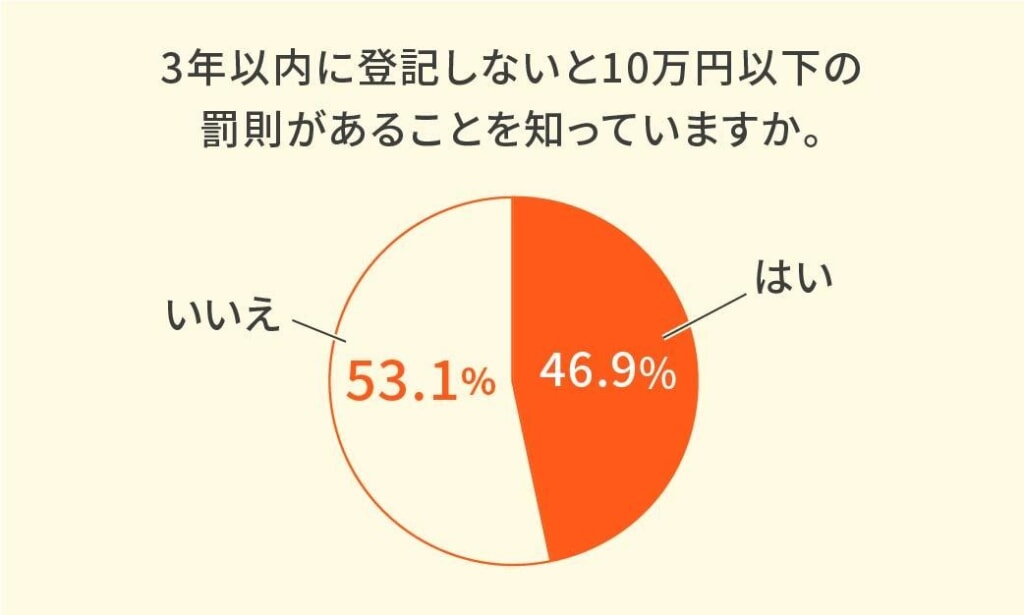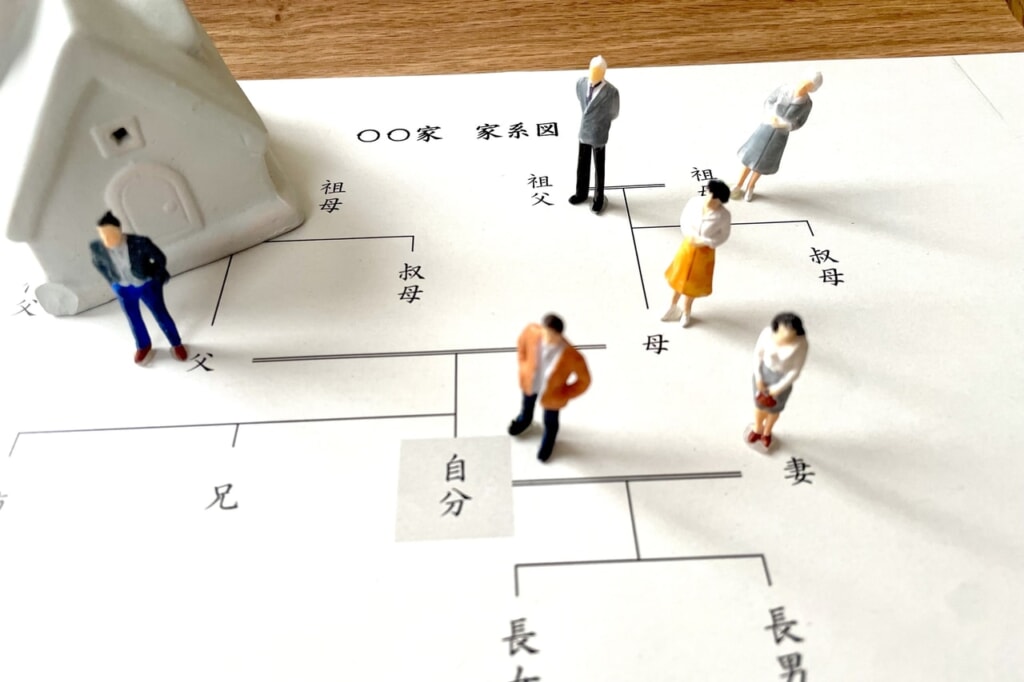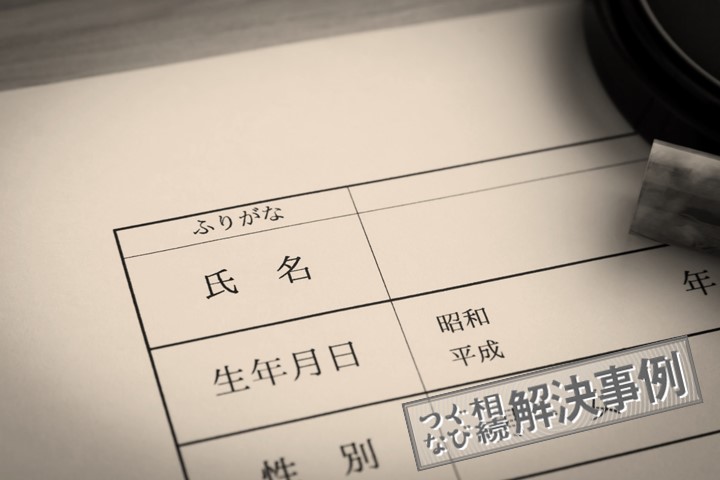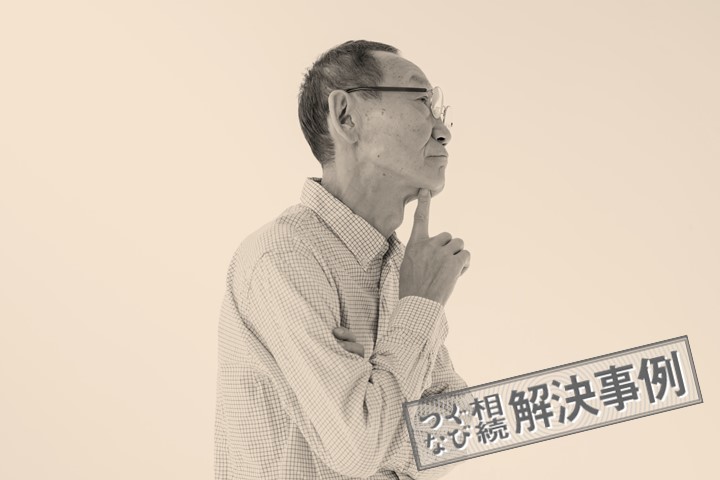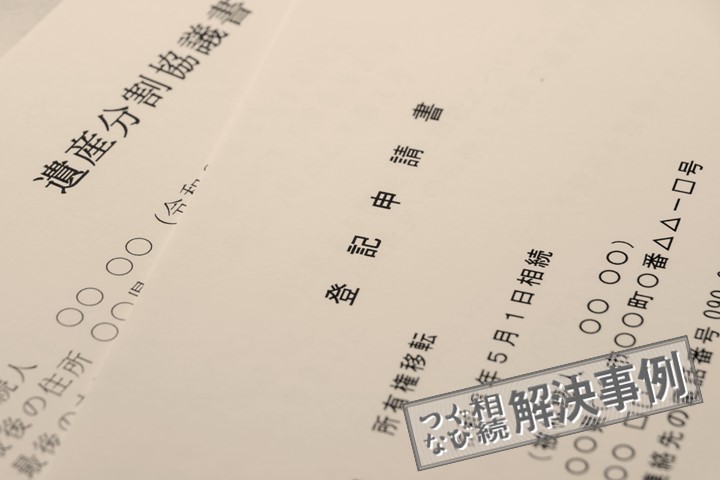土地の相続税評価額は、路線価または固定資産税評価額を用いて計算します。
土地の相続税を正しく計算するには、路線価・固定資産税評価額の概要や、それらを用いた相続税評価額の計算方法を理解しなければなりません。
今回は、土地の相続税評価額の計算方法を詳しく解説します。
目次
1. 土地の相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税を計算するときに基準となる価格のことをいいます。
相続する財産には、現金や預貯金など金額がはっきりわかるものと、そうではないものとがあります。
金額がはっきりしない財産については、価値を調べて値付けをしなければ相続税の計算ができません。
土地や建物などの不動産は、こうした価値評価が必要となる財産の代表例です。
土地の相続税評価額は、「路線価方式」または「倍率方式」によって計算されます。
路線価方式は、市街地を中心に、路線価が設定されている土地で用いられる相続税評価額の計算方法です。
一方、路線価がない土地では、固定資産税評価額を基準とする倍率方式が用いられます。
参考:財産評価|国税庁
2. 土地の評価で知っておきたい「路線価」と「固定資産税評価額」
土地の相続税評価額は、路線価方式の場合は「路線価」、倍率方式の場合は「固定資産税評価額」を用いて計算されます。
したがって、土地の相続税評価額を計算する際には、「路線価」「固定資産税評価額」について正しく理解しておくことが大切です。
2-1 路線価
路線価とは、その道路に面している土地1平方メートルあたりの価格のことで、国税庁が定めています。
原則として、路線価に土地面積を掛けたものが相続税評価額となります。
公示価格や実際の土地取引価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などを参考にして毎年1月1日時点での路線価が決められ、7月1日に発表されます。
基本的には年1回の発表ですが、災害などの事由により調整が行われることもあります。
なお、路線価は公示価格の約8割を目安に設定されています。
1年間の価値変動によって納税額に不平等が生じないようにするためです。
路線価については、こちらの記事も参考にしてみてください。
相続税路線価の調べ方についてはこちらをご覧ください
>相続税路線価の調べ方を解説!|路線価による土地の評価額の計算方法
2-2 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、土地や建物など固定資産の価値を表すものです。
地方税のため、市区町村が「固定資産評価基準」に基づいて評価額を決定し、それをもとに算出した納税額を不動産の所有者に通知します。
市街化区域内にある土地については都市計画税もあわせて徴収されます。
ちなみに固定資産税の税額は、原則として固定資産税評価額の1.4%です。
土地の場合、公示価格の約7割が固定資産税評価額の目安といわれています。
相続税評価額を算出する際、路線価がない宅地については「倍率方式」が用いられますが、その基準となるのが固定資産税評価額です。
2-3 路線価と固定資産税評価額の調べ方
路線価図はインターネット上に公開されているため、誰でも自由に確認できます。
以下のサイトを利用して調べてみてください。
・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表|国税庁
・全国地価マップ|一般財団法人 資産評価システム研究センター
固定資産税評価額は、以下のいずれかで確認します。
・固定資産税課税明細書
・固定資産税評価証明書または固定資産課税台帳
「固定資産税課税明細書」は、毎年、不動産の所有者に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されています。
なお、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税されるため、年の途中で取得した場合は課税証明書が郵送されません。
売買契約締結時に固定資産税の日割り清算を行うと同時に、売主から課税明細書を受け取るのが一般的です。
紛失などで手元にない場合は、所在地の市役所などで「固定資産税評価証明書」と取得するか、「固定資産課税台帳」を閲覧することで確認できます。
ただし、誰でも気軽にというわけにはいきません。
原則として、取得・閲覧は納税者(不動産所有者)本人に限られています。また、利用時には運転免許証などの身分証明書の提示が求められます。
第三者の取得・閲覧には納税者本人の委任状が必要です。
固定資産税は誰が支払うのかについてはこちらをご覧ください。
3. 土地の評価方法①路線価方式
路線価を基準にして相続税評価額を算出する方法を、路線価方式といいます。
路線価は「路線価図」に記載されています。まずは路線価図の見方を解説しましょう。

出典:「路線価図・評価倍率表(国税庁)」
道路上に「1,480C」「2,110C」などと記載されているのがお分かりでしょうか。
数字の部分が路線価で、千円単位で表示されています。
つまり、数字に1,000円を掛けたものが、その道路に面する土地1平方メートルあたりの路線価ということです。
さらに、1平方メートルあたりの路線価に地積を掛けたものが、その宅地の相続税評価額となります。
たとえば、「1,480C」と記載された道路に面した70平方メートルの宅地があるとしましょう。
この場合、次のようにして相続税評価額を算出します。
路線価:1,480 × 1,000 = 148万円
相続税評価額:148万円 × 70平方メートル = 1億360万円
借地の場合は、上記で算出した相続税評価額に借地権割合を乗じることで、借地権の相続税評価額が計算できます。
末尾のアルファベットは借地権割合です。借地権割合は90~30%まで7段階に分けられ、A~Gのアルファベットで表現されています。
上記の宅地が借地の場合、借地権の相続税評価額は次のように変わります。(C=70%)
相続税評価額:148万円 × 70平方メートル × 0.7 = 7,252万円
このように、路線価方式での相続税評価額の計算方法はとてもシンプルです。
ただし、これは長辺と短編のバランスが良く、使い勝手に問題がない土地を想定した概算でしかありません。
同じ面積の土地でも形状や接道状況などはさまざまです。
そこで、実際には次のように「補正率」を乗じて評価額を算出します。
・相続税評価額 = 路線価 × 補正率 × 地積
なお、補正率については記事の後半で改めて解説します。
4. 土地の評価方法②倍率方式
倍率方式は、路線価がない宅地の評価に利用されます。
倍率方式では、固定資産税評価額に地域ごとに定められた「評価倍率」を掛けて相続税評価額を求めます。
評価倍率は前掲の「路線価図・評価倍率表(国税庁)」で確認できます。(トップページ → 都道府県を選択 → 評価倍率表)
評価倍率表を開くと、宅地の欄に「路線」と書かれている地域と、「1.1」「1.2」などの数値がかかれている地域があることがわかります。この数値が評価倍率です。
倍率方式で相続税評価額を求めるには、次のように計算します。
・相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率
たとえば、固定資産税評価額1,000万円・評価倍率1.1の場合、その宅地の相続税評価額は1,100万円ということになります。
相続税評価額:1,000万円 × 1.1 = 1,000万円
なお、借地の場合は路線価方式と同じように、借地権割合を乗じることで、借地権の相続税評価額が計算できます。
上記の宅地が借地(借地権割合40%)だとしたら、借地権の相続税評価額は以下のようになります。
借地権割合も評価倍率表に記載されているので確認してください。
相続税評価額:1,000万円 × 0.4 × 1.1 = 440万円
5. 土地の状況によって補正しなければいけない
路線価方式で相続税評価額を計算する際、土地の形や状態によっては評価額の補正が必要になります。
補正によって評価額が少なくなれば相続税の負担軽減につながるので、内容を把握しておきましょう。
適用される補正率にはいくつかの種類がありますが、今回は次の5つについて解説します。
・奥行価格補正
・不整形地補正
・間口狭小補正
・奥行長大補正
・規模格差補正
それぞれの補正率は国税庁のWebサイトで確認できます。
「土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31年1月分以降用)」を参考にしてください。
5-1 奥行価格補正
一般的な土地に比べ、土地の奥行きが長すぎたり短すぎたりする場合、「使いにくい」土地である可能性が高いため、価格補正を行います。
この場合の相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。
・相続税評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 地積
奥行価格補正率は、その土地が所在する地区区分と奥行距離によって定められています。
普通住宅地区の場合、奥行10メートル以上24メートル未満は標準です。
それ以外の場合には、距離に応じた1.00未満の補正率が適用されます。
5-2 不整形地補正
不整形地とは、宅地として利用しづらい台形や三角形などの土地のことです。
なお、正方形や長方形の土地でも、道路に対して土地が斜めに接している場合などには不整形地補正が行われます。
不整形地補正率を計算するには、まず「地区区分」と「地積区分」を調べる必要があります。
地積区分は、国税庁の調整率表「④不整形地補正率を算定する際の地積区分表」に、土地の地区区分と地積を当てはめれば分かります。
地区区分と地積区分がわかったら、次に「かげ地割合」を求めます。
かげ地割合とは、その土地を整形地(正方形や長方形)で囲ったと想定してそこからはみ出る部分の割合のことです。
・かげ地割合 = 想定整形地の地積 - 不整形地の地積 ÷ 想定整形地の割合
地区区分・地積区分・かげ地割合がそろったところで、同じく調整率表の「⑤不整形地補正率表」で補正率を確認します。
不整形地にはさまざまなパターンがあるため、計算方法については省略しますが、地区区分・地積区分・かげ地割合を用いた計算の考え方はぜひ覚えておいてください。
5-3 間口狭小補正
間口狭小補正は、接道部の間口が狭くて道路への出入りが不便とされる土地に適用されます。計算式は以下のとおりです。
・相続税評価額 = 路線価 × 間口狭小補正率 × 地積
間口狭小補正率は、地区区分と間口距離によって異なります。
普通住宅地区の場合、間口8メートル未満について次のように補正率が定められています。
4メートル未満:0.90
4メートル以上6メートル未満:0.94
6メートル以上8メートル未満:0.97
5-4 奥行長大補正
奥行長大補正は、間口に対して奥行が長い土地に適用される補正です。
具体的には、「奥行距離 ÷ 間口距離」が2以上の土地に適用されます。計算式は以下のとおりです。
・相続税評価額 = 路線価 × 奥行長大補正率 × 地積
奥行長大補正率は、奥行距離を間口距離で割った値によって異なります。
地区区分によっても異なるので、調整率表「⑦奥行長大補正率表」で確認してください。
5-5 規模格差補正
三大都市圏では500平方メートル以上、その他のエリアでは1,000平方メートル以上の宅地に適用されるのが、規模格差補正です。
規模格差補正率の求め方と相続税評価額の計算式は、それぞれ以下のようになります。
・規模格差補正率 = (地積 × 記号B + 記号C)÷ 地積 × 0.8
・相続税評価額 = 路線価 × 規模格差補正率 × 地積
記号B・記号Cは、調整率表「⑧規模格差補正率を算定する際の表」に記載されている数値です。
たとえば、三大都市圏に所在する宅地500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合、記号Bは0.95、記号Cは25になります。
路線価100千円、地積500平方メートルで試算してみましょう。
規模格差補正率:(500平方メートル × 0.95 + 25)÷ 500平方メートル × 0.8 = 0.8
相続税評価額:100千円 × 0.8 × 500平方メートル = 4,000万円
規模格差補正により、補正前(5,000万円)に比べ、相続税評価額が80%に減額されたことがわかります。
路線価の見方と計算方法についてはこちらをご覧ください。
6. 評価額が下がる場合の土地の利用状況
各種補正のほか、土地の利用状況によっても相続税評価額が下がる可能性があります。
相続税評価額が下がるのは、主に土地を第三者に貸し出している場合です。
6-1 賃貸マンションや賃貸アパート
賃貸マンションや賃貸アパートを相続した場合、その土地(貸家建付地)の相続税評価額は自分で土地を使用するのと比べて、2~3割ほど下がります。
アパートやマンションの入居者は借地借家法で保護されているため、正当な事由なく退去を迫ることはできません。
所有地でありながら自由に利用できないため、土地の相続税評価額の減額が認められています。
6-2 借地
借地の場合、路線価図に記載の借地権割合に応じて評価額が下がります。
たとえば、「100D」と書かれた道路に面した土地なら、路線価は100千円、借地権割合は60%です。
地積100平方メートルとして、相続税評価額がどのくらい違うのか見てみましょう。
・通常:100千円 × 100平方メートル = 1,000万円
・借地(いわゆる「底地権」):100千円 × 100平方メートル × (1-0.6) = 400万円
上記は普通借地権の例です。定期借地権や権利金の有無など、借地権の評価は状況によって異なることに注意してください。
6-3 私道
私道の相続税評価額は、その土地の本来の相続税評価額の30%相当額です。
ただし、通り抜けなど不特定多数の人が利用する私道については、評価しないものとされています。
参考:No.4622 私道の評価|国税庁
7. 土地の相続税を計算するには専門家に依頼するのがおすすめ
相続税の計算において、土地は特に複雑で難しいものといわれています。
高額なだけに納税額にも大きく影響するため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
相談先選びには「つぐなび」がきっと役立ちます。
つぐなびとは、主に相続に強い税理士・弁護士・司法書士を検索できるサービスです。
都道府県別・相談内容別に検索できるため、お悩みに合った専門家をスムーズに見つけることができます。
実績や料金、お客様の評判なども確認できて安心です。
この記事の監修者:阿部 由羅
 ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。
ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。