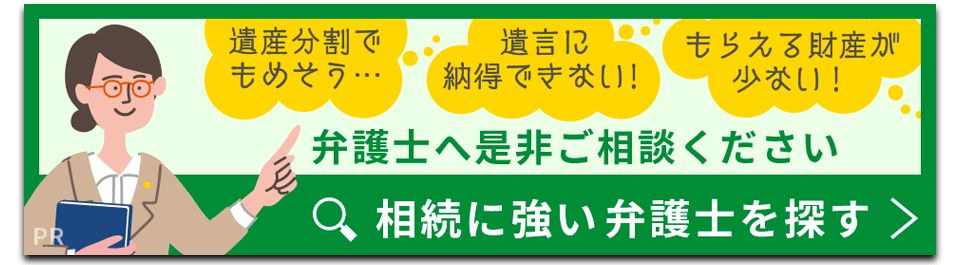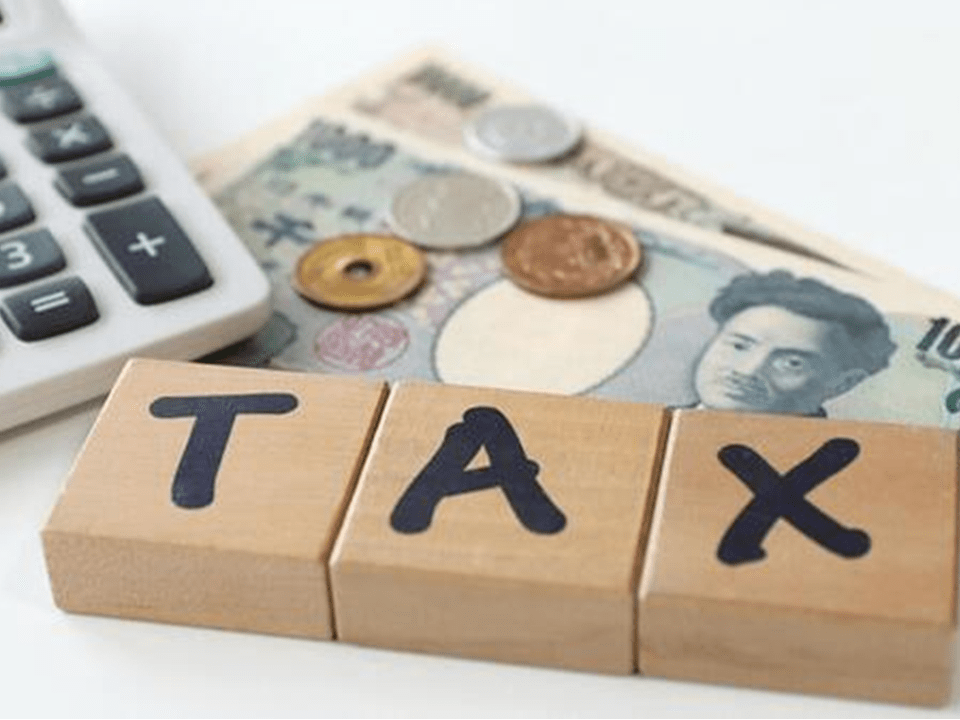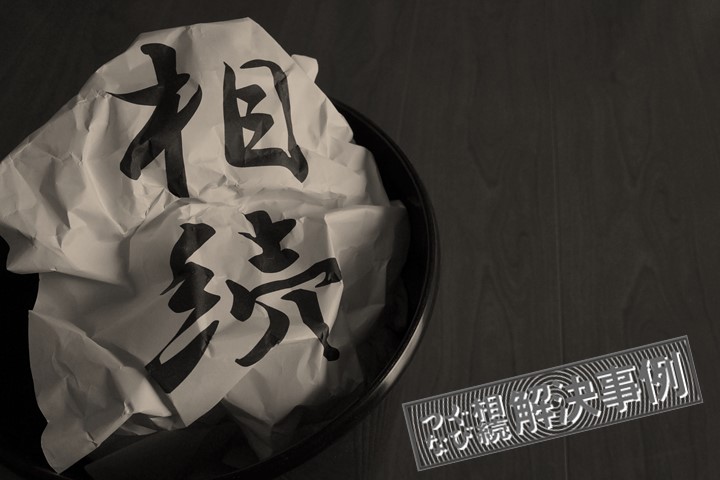遺留分放棄、という言葉をご存じでしょうか。相続放棄と混同されがちですが、全く異なります。
遺留分放棄とは、遺留分の権利を持つ人が、相続開始後に遺留分に関する権利を行使しないことを言います。被相続人が生前の場合に遺留分の権利者が遺留分放棄するためには家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
ここでは、遺留分放棄の基本的な考え方に加え、被相続人・相続人から見たメリットを解説します。
目次
遺留分放棄とはなにか
遺留分放棄とは、遺留分侵害額請求をすることのできる遺留分権利者が、相続開始後に遺留分に関する権利を行使しないこととするものです。
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合をいいます。
遺留分は遺言に優先するため、仮に遺言の中で「相続財産をすべて長男に相続する」旨の記載があったとしても、遺留分権利者であれば民法で遺留分として認められた割合に相当する金銭の支払いを、遺言によって財産を取得するとされた者に対して請求することができます。
遺留分権利者が遺留分に相当する金銭の支払いを請求することを、「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分侵害額請求というのは、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていたものです。
従来の遺留分減殺請求は、行使されると遺留分権利者は遺産そのものの共有持分を取得できる効果がありました。
しかし、共有状態となると相続争いが長引きやすいことに加え、遺留分権利者もまた金銭的な補償があれば足りることも多いのが実情でした。
そこで、2019年7月1日に施行された改正民法において遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に改められ、遺留分に相当する金銭を請求する権利に変わりました。
もっとも、遺留分侵害額請求が相続人の一部によって行われた場合、遺言によって遺産の全部を相続することとなった相続人は遺留分に相当する金銭を支払う余力がなく、結果的に遺産として取得した不動産や貴金属、株式などを売却せざるを得ないことがあります。
特に、被相続人が会社経営をしていて会社の株式の全部を後継者一人に引き継ぎたいというケースでは、他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されると事業承継に悪影響が出る可能性があります。
このような事情がある場合には、遺言を残すだけでは確実ではないため、遺言と合わせて遺留分の放棄を行う必要があります。
遺留分放棄と相続放棄の違い
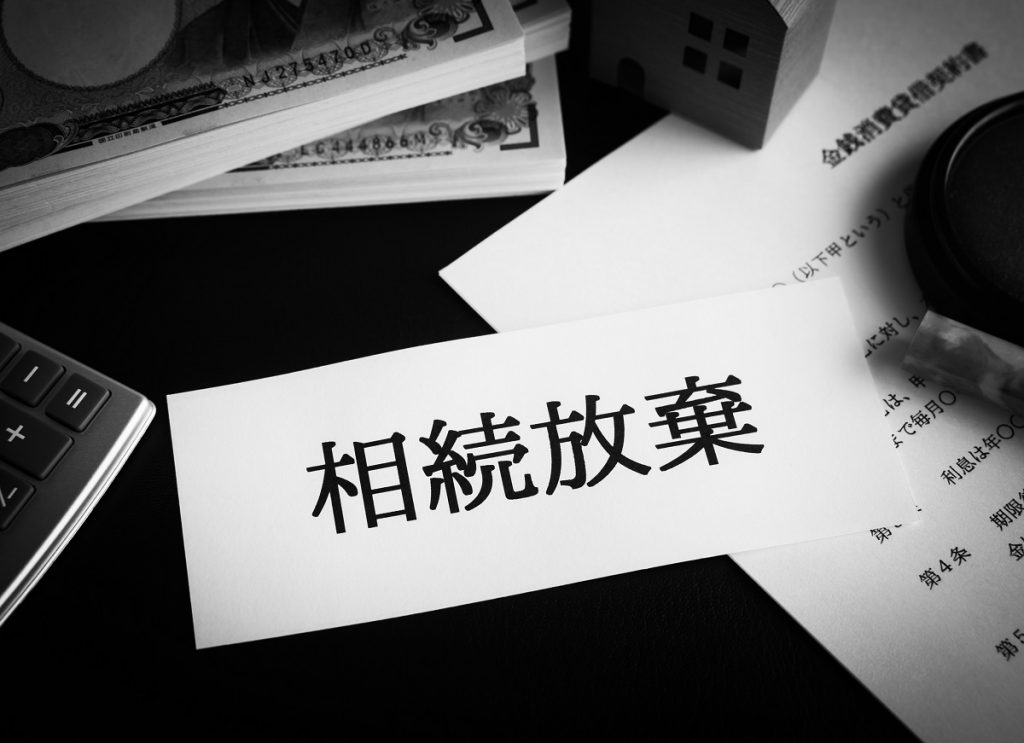
遺留分放棄とよく混同される制度として、相続放棄があります。相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続財産について相続する権利を放棄することをいいます。
相続放棄と遺留分放棄の違いは、次のような点にあります。
- 放棄する対象の違い: 相続放棄は相続人としての一切の地位を失いますが、遺留分放棄は相続人としての地位は残ります。
- したがって、相続放棄をした相続人は被相続人の負債も含めて引き継がないことになりますが、遺留分放棄の対象は遺留分のみであるため被相続人の他の財産や負債は引き継ぐことがあります。
- 行使できる時期の違い: 相続放棄は相続開始後にしかできませんが、遺留分放棄は被相続人の生前から可能です。
なお、相続放棄は家庭裁判所に対する申述が必要です。
これに対し、遺留分放棄は、被相続人の生前に行う場合には家庭裁判所から許可を受ける必要があるものの、相続開始後に遺留分放棄をする場合には家庭裁判所への申述は不要であり、他の相続人に対して意思表示をすれば効力が発生します。
遺留分放棄をするメリットはなにか

遺留分放棄をすることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、相続人、被相続人、遺贈や贈与を受けた人など立場ごとに遺留分放棄のメリットを説明します。
相続人にとってのメリットとは
遺留分を放棄する相続人にとってのメリットとしては、相続トラブルに巻き込まれにくいということが挙げられます。
遺留分に関する権利を持っていると、遺言の内容によっては遺留分侵害額請求をすべきか悩むことになります。
また、仮に遺留分侵害額請求権を行使したら今度は、相続争いがなかなか解決せず負担感を長年引きずることになるかもしれません。
そのような相続争いの当事者になるくらいなら、あらかじめ遺留分に関する権利を行使しないこととしておいた方が気は楽ということがあります。
また、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合には、被相続人から遺留分を放棄する人へ代償の支払いがなされることがよくあります。
何ら代償支払いなしに遺留分放棄をしようとしても、裁判所は遺留分権利者の自由意志に基づくものではないとして放棄を許可しないことがあるためです。
このため、代償の支払いを受けられる場合には、遺留分放棄をすることで、本来は遺留分侵害額請求をしてはじめて受け取れる遺留分に相当する分を先払いしてもらえるメリットがあります。
被相続人にとってのメリットとは
遺留分放棄のメリットを一番享受できるのは、やはり被相続人です。
被相続人としては、遺留分を放棄してもらうことによって自分の意思に沿った遺言どおりの相続を確実に実現することができます。特に、会社経営をしている人にとって、遺留分放棄は不可欠です。
また、遺留分侵害額請求がされると、そこから泥沼の相続争いに発展することが珍しくありません。遺留分があることによってかえって親族間に禍根を残すことにもなりかねず、被相続人としては気がかりです。
遺留分が放棄されていれば、自分の死後に相続争いが発生するリスクをある程度は抑えることができます。
もっとも、被相続人が遺留分権利者に遺留分の放棄をしてほしいという場合には、その必要性を十分に説明し、代償を支払うなど、遺留分権利者から納得が得られるような形で手続をすすめることが重要です。
遺贈・贈与を受けた人にもメリットがある
遺言によって財産を取得させることを遺贈といいます。
遺贈や生前贈与を受けた人は、相続開始後に遺留分侵害額請求を受けることになれば、遺留分に相当する金銭を相手に支払う義務を負います。
しかし、相続した財産が現金や預貯金でなく、非公開株式や不動産である場合には、遺産自体を簡単に金銭に換えられません。
このため、遺贈や生前贈与を受けた人に手元資金がない場合には、遺留分権利者へ支払い義務を果たすことができないという問題があります。
せっかく、遺言により遺贈を受けたり生前贈与を受けたりしても、大きな負担を負うことになっては本末転倒です。
被相続人の生前に遺留分が放棄されていれば、遺贈や生前贈与を受けた人は遺留分侵害額請求をされるおそれがないため、安心して相続や生前贈与を受けることができます。
生前に遺留分放棄をするには

生前に遺留分放棄をする場合の具体的な手続について、以下説明します。
遺留分放棄の手続きの流れ
遺留分権利者が遺留分を被相続人の生前に放棄する場合、家庭裁判所に対して申立てを行い、許可を得る必要があります。
なぜ、家庭裁判所からの許可を得る必要があるのかというと、生前に行われる遺留分放棄は被相続人の強い意思によって半ば強制的に行われる可能性があるためです。
このため、遺留分放棄が遺留分権利者の真意によるものであるのかを、家庭裁判所が判断する仕組みとなっています。
したがって、例えば、遺言者が遺留分権利者となる者に対して「遺留分を放棄する」といった書面を書かせたとしても遺留分放棄の法的な効力はありません。
家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てをして受理されると、その後家庭裁判所において審問が行われます。
審問は、裁判所における面談であり、申立人は家族関係や相続財産の状況や、遺留分放棄の申立てに至った事情などについて口頭で説明します。
その後、審問の内容等に基づいて裁判所が審議を行い、最終的に遺留分の放棄を許可すべきか否かの結論が申立人に通知されます。
申立人と申立先
遺留分放棄の申立人となるのは、遺留分を有する相続人(遺留分権利者)です。遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(両親や祖父母など)です。被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分が認められていません。
したがって、被相続人の兄弟姉妹は申立人とはなりません。
申立先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄の家庭裁判所は、裁判所の公式サイトで調べることができます。
必要書類と費用
遺留分放棄の申立てに必要な書類は、以下の通りです。
- 申立書
- 申立添付書類(被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本)
このほか、家庭裁判所の審理経過に応じて、別の書類の提出が求められる可能性もあります。申立書は、裁判所の公式サイトにひな型や記載例が掲載されています。
申立書には、「申立ての理由」として遺留分放棄をすることになった経緯などを記載する必要があります。
特に、被相続人から遺留分放棄に対する代償を得ているといった事情は重要なので、このような事実があれば記載しておくとよいでしょう。
このほか、申立書には「財産目録」として、相続財産となるものの概要も記載する必要があります。
気を付けたいポイント
遺留分放棄の許可を得られた場合には、裁判所に申請することで遺留分放棄を証明する書面をもらうことができます。
この証明書は必ず発行を申請し、相続人の間で共有しておく必要があります。
遺留分放棄が許可されたかは申立てをした本人にしか知らされないので、遺留分を放棄した人が無用のトラブルに巻き込まれないためにも、関係者には遺留分放棄をした旨を伝えておく必要があるのです。
相続開始後に遺留分放棄をするには

相続開始後に遺留分を放棄する場合には、生前に放棄する場合とは異なり家庭裁判所への申し立ては不要であり、そのほかにも特別な方式は決められていません。
したがって、相続開始後の遺留分放棄を明確にしたい場合には、遺留分権利者から他の相続人に対して遺留分を放棄する旨の内容証明郵便を送る、他の相続人との間で遺留分を放棄する内容の合意書を作成、といった方法で足ります。
そもそも、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年行使しなければ時効により消滅します(民法1048条)。
このため、遺留分権利者が遺留分に関する権利を行使するつもりがない場合には、特に意思表示をせずに1年が経過することで、遺留分が放棄されたのと同じ状況になることも多いのです。
遺留分放棄に関する裁判所の基準とは
生前の遺留分放棄は、裁判所が許可するか否かを判断します。
したがって、すべての遺留分放棄の申し立てについて許可が出るわけではありません。統計上、遺留分放棄の許可が出るのは申立ての9割程度です。
そこで、裁判所がどのような基準で遺留分放棄の可否を判断しているのかを説明します。
自由意思に基づいていること
一番重要な観点は、遺留分権利者の自由意志による放棄であることです。
遺留分放棄が被相続人の強制によって行われることがあれば、相続人の最低限の生活を保障する遺留分制度の意味がなくなってしまいます。遺留分権利者の自由意志に基づいているかは、主に次に説明する2つの点によって判断されています。
理由が合理的であること
第一に、遺留分権利者が遺留分放棄に至った理由が合理的なものであることです。例えば、被相続人から十分な生活の援助を受けてきたことや、会社の後継者に相続させる必要があることなどです。
代償が支払われていること
相続財産の規模が大きい場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで遺留分権利者が受けられるはずの経済的利益は相当額にのぼります。
これを敢えて放棄する以上、それに見合う代償が被相続人から支払われていないとバランスを欠きます。何ら代償なしに遺留分放棄を求めているとすれば、被相続人によって強制されている可能性もあるわけです。
このため、遺留分放棄の代償が支払われているかどうかは、遺留分権利者の自由意志による遺留分放棄であるかを確認する上で重要なポイントとなります。
事業を継承する場合は遺留分の除外合意と固定合意がある
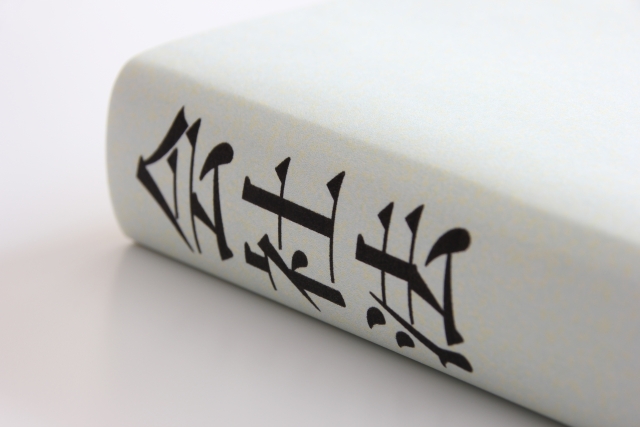
会社経営者が事業承継のために、遺留分権利者による遺留分侵害額請求を回避したいという場合には、除外合意と固定合意と呼ばれる手法もあります。
除外合意とは、被相続人の生前に相続人となる予定の者が全員で、株式について遺留分侵害額請求権を行使しないと合意しておくものです。
これにより、会社の後継者に対して承継した株式については遺留分侵害額請求の対象から除外することができます。
固定合意とは、万が一、遺留分侵害額請求権を行使された場合に会社の株式を承継する者の支払いの負担を低減する手法です。
具体的には、被相続人が会社の後継者に会社の株式を承継した場合に、遺留分侵害額の算定基礎となる株式評価額を固定しておく合意をいいます。
固定合意があれば、相続開始時点で株式の価値が上昇していたとしても、遺留分侵害額の金額は固定されるため、会社の後継者の負担が過大にならないように調整することができます。
もし遺留分放棄を撤回したくなったら
遺留分権利者が遺留分の放棄をすると、その後の撤回は困難です。
このため、被相続人の求めに応じて安易に遺留分の放棄に応じてしまい後から後悔することのないように、遺留分の放棄をする場合には慎重に検討する必要があります。
もっとも、遺留分放棄の許可の前提となった事実関係に変化が生じたような場合には、合理的な理由があるとして遺留分放棄の撤回が認められる可能性があります。
一度許可を受けた遺留分放棄を撤回・取り消ししたい場合には、家庭裁判所に対して取り消しを申し立てる必要があります。
ただし、遺留分放棄の撤回は例外的な取り扱いであるため、どうしても遺留分の放棄を撤回したいという場合には、弁護士などに相談して対応するとよいでしょう。

弁護士 松浦 絢子
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、男女問題など幅広い相談に対応している。