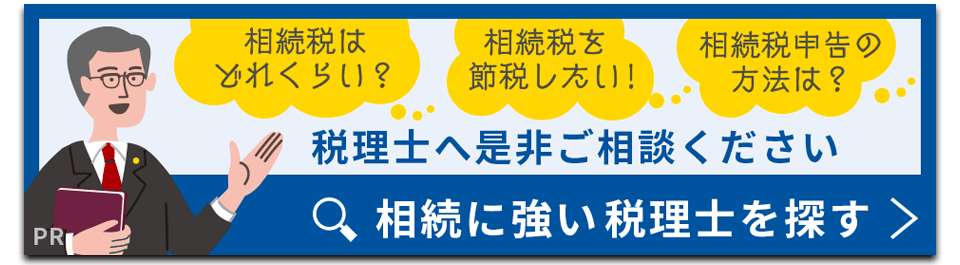相続税がゼロだった場合、申告の必要はないと考える方も多いでしょう。
しかし、特例・控除の適用のため申告書提出が必要になる場合があり、自己判断で申告しないと、取得財産に対する一定の課税と加算税を負担する羽目になる可能性があります。
税務について正確に判断できるよう、相続税がゼロになる仕組みを改めて整理し、納付すべき税がなくても申告しなければならないケースを紹介します。
目次
1. 相続税がゼロでも申告が必要な5つのケース
相続税が全くかからないとしても、計算結果がゼロになる理由により、申告書を提出しなければなりません。
当てはまるのは、以降で紹介する5つのケースです。
1-1 配偶者の税額の軽減をして相続税がゼロになる場合
配偶者の税額軽減とは、配偶者の課税価格が1億6,000万円もしくは法定相続分相当額のいずれか多いほうを上限として、配偶者に相続税がかからなくなる制度です。
本制度によって夫または妻の取得分は課税額ゼロになりますが、その代わり、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
ここで、両親と子の3人家族を想定してみましょう。
夫が死亡し、持ち家と預貯金で計4,000万分の遺産(債務等の控除後)を配偶者が全額取得したとします。
最終的には税額軽減によって課税額はゼロになりますが、軽減がなかった場合、基礎控除額を超える部分である400万円について各人の納付すべき額を計算しなければなりません。
軽減を含めた申告税額を書面に記載して提出しないと、無申告と判断されてしまいます。
1-2 小規模宅地等の特例を適用して相続税がゼロになる場合
小規模宅地等の特例とは、居住や事業の用に供している宅地等につき、課税評価額を下げる制度です。
本特例を適用する場合も、相続税がゼロになるか否かに関わらず、計算書を添付した申告書を提出しなければなりません。
【関連記事】小規模宅地の特例についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:小規模宅地の特例とは?相続税が減額される要件や必要書類を解説
1-3 農地の納税猶予の特例で納付すべき額がゼロになる場合
相続した農地には、営農継続等の一定の条件を満たすことにより、納税猶予および免除とする特例があります。
本特例を適用する場合も、土地や農業相続人の情報を書類にまとめ、相続税申告する必要があります。
また、納税猶予中の農地を相続する場合も、申告等の所定の手続きが必要です。
1-4 特定計画山林の特例で納付すべき額がゼロになる場合
特定計画山林の特例とは、特定計画特定森林経営計画が予定されるエリアの山林を相続した際に、一定の条件を満たせば相続税の納税が猶予されるものです。
本特例は、期限内に相続税申告した場合しか適用できません。
また、認定書の写し・対象の土地以外の財産の取得状況等につき、申告書に沿える等して届け出なければなりません。
1-5 寄附した場合の特例で課税額がゼロになる場合
特定の公益法人、例えば児童福祉施設等に遺産を寄附すれば、寄付した分には相続税の課税がありません。
ただし、寄附の状況や計算書を提出すること、つまり申告書の提出が適用条件です。
2. 相続財産が基礎控除額以下で相続税がゼロになる場合は申告は不要
相続税がゼロになるケースで「申告不要」と言い切れるのは、相続財産が基礎控除額を超えていない場合です。
基礎控除額の計算結果を整理すると共に、他にもある申告が適用条件でない制度(未成年者や障害者にかかる控除)を紹介します。
2-1 基礎控除額の計算方法
基礎控除の計算基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人で計算します。
基礎控除の計算例を見てみましょう。
【関連記事】相続税の基礎控除についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の基礎控除はどのくらい?その求め方を徹底解説
【事例】
- 法定相続人:妻・子2人
- 遺産総額:4,000万円
- 葬式費用:500万円
- 負債(借金等):0円
- 他の贈与財産等:0円
STEP① 遺産総額から負債や葬式費用を差し引きます。
例では相続時精算課税にかかる贈与分がなく、遺産総額に加算されません。
また、負債もないので、葬式費用のみ差し引きます。
遺産総額4,000万円-葬式費用500万円=3,500万円
【関連記事】非課税となる相続財産についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税が非課税になるのはどんな時?適用になる財産について解説
STEP② 相続開始前の3年以内の贈与財産がないため、算出した3,500万円から基礎控除額を差し引きます。
3,500万円-(3,000万円+600万円×3人)=-1300万円
STEP③ 基礎控除額は4,800万円で、算出した3,500万円を上回ります。
つまり、相続税はゼロ円であり申告の必要はありません。
2-2 法定相続人の数え方
法定相続人は、配偶者+相続順位が最も高い血族で構成されます。血族相続人の順位は以下の通りです。
- 必ず相続人になる:配偶者
- 第1順位:被相続人の子ども・孫などの代襲相続人
- 第2順位:両親・祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹、甥や姪など代襲相続人
配偶者は必ず相続人になりますが、子供や孫がいない場合には第2、第3の順番で遺産を分割しなければなりません。
また、第1順位が子供1人であり、配偶者が亡くなっている場合には、子供1人が遺産を相続します。
【関連記事】法定相続人の人数の確定についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の控除額は?基礎控除の改正や相続税の計算方法を解説!
【関連記事】兄弟間の相続についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:【兄弟間の相続】相続税はいくら?基礎控除の計算方法や、3つの注意点を解説
2-3 申告が不要の控除
相続税の基礎控除の他に申告不要で適用できる控除としては、基礎控除、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除、相続時精算課税制度が挙げられます。
うち相次相続控除は、被相続人につき過去10年以内に相続税が課税されていた場合に、納税額の一定額を相続税から差し引くことが可能な制度です。
前回の相続と二次相続の期間が短いと、控除額が大きくなります。
生前贈与にかかる相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税を納付しなくても良い制度です。
贈与者が死亡すると贈与分と相続財産の価額の合算して申告するのが原則ですが、その結果が基礎控除額以内であれば、申告する必要はありません。
3. 相続税の申告が必要かどうかは国税庁のサイトから判定できる
相続税の手続きをしなければならないかどうかは。
国税庁のホームページから確認することが可能です。
相続する財産の金額や法定相続人の数を入力すると結果が表示されるシステムであり、相続税の申告要否検討表はプリントできます。
4. 本当に相続税がゼロ?申告前に確認しておきたいチェックポイント
相続税がゼロ円かどうか、十分に確認しなければ申告ミスでトラブルが起こることがあります。
申告ミスがないよう、申告前に確認しておくべき2つのポイントを紹介します。
4-1 財産はすべて明らかにしているか、みなし財産やタンス預金も含めているか
相続税申告すべき財産にはは、自宅等で保管する現金(いわゆるタンス預金)も含まれます。
また、法律上は相続財産には当てはまらない死亡保険金・各種定期金給付契約(年金等)も、みなし相続財産として判断されます。
家族が亡くなった際に遺品を徹底的に調査し、契約書類や現金の保管状況を調べ、申告すべき総額をチェックしなければなりません。
【関連記事】みなし相続財産についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:みなし相続財産とは?みなし相続財産の遺産分割もわかりやすく解説
4-2 被相続人から生前贈与がされていなかったか
生前贈与した人が死亡した場合、死亡時からさかのぼり3年以内の贈与は相続税の課税対象になります。
例えば、親が20年間に渡って50万円ずつ子供に生前贈与をしていたのであれば、最後の3年分の金額、50万円×3年=150万円が相続財産として判断されます。
なお、相続時精算課税を適用した贈与については、期間の制限なくその全てが相続税申告を要します。
相続税の財産が基礎控除内でも、3年間の生前贈与を合わせると基礎控除の範囲を超える場合があるため必ず確認しましょう。
【関連記事】相続税精算課税制度についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続時精算課税制度のメリット・注意点を解説|相続時精算課税の節税を!
4-3 相続税がゼロでも申告する場合は申告期限までに行う必要あり
相続税がゼロ円でも、申告が必要な場合は期限内に手続きをしなければなりません。
しかし、やむを得ない事情で期限内に申告できないこともあるでしょう。
そこで、申告期限を過ぎて手続きできるのか、申告しなかった場合はどのような問題が起こるのかを紹介します。
4-4 申告期限を過ぎたら特例や控除が受けられなくなる
税金が高いことを理由に財産を手放さなくても良いよう、相続には特例が設けられています。
節税効果が期待できるのは控除・特例ですが、申告期限を過ぎると適用されません。
期限後申告で適用できなくなるものとして、配偶者控除や小規模宅地等の特例があります。
控除や特例を利用することで相続税を抑えられることが可能であるため、申告期限までに手続きを行いましょう。
【関連記事】相続税の申告期限についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の申告期限はいつ?申告期限が過ぎた場合のペナルティや時効も合わせて解説
4-5 無申告者にはペナルティが発生する
申告をしなかった場合は、延滞税といったペナルティが発生します。
延滞税は期限から2ヶ月以内は年率7.3%(延滞税特例基準割合+1%と比べて低い方)となり、日割り計算で滞納期間に応じて増加します。
延滞税の税率は、本来の納付期限から2ヶ月以上が経った場合、以降年率14.6%(延滞税特例基準割合+7.3%と比べて低い方)と上昇します。
金額として大きいのは、無申告加算税(課税額の最大20%)です。
申告の必要性に気付いていながら遺産を隠そうとした悪質な例では、相続税額に対し最大40%を加算した重加算税を支払う必要があります。
4-6 遺産分割が間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する
財産の価値を判断しにくい場合には、評価額を決めるまでに時間がかかるため、遺産分割が申告期限に間に合わないこともあります。
また、場合によっては遺産分割の話し合いがまとまらないこともあります。
しかし、未分割の場合は特例や控除を受けられないことがあります。
その場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しましょう。
期限が過ぎた後3年以内に分割し申告すれば、特例や控除を受けることが可能です。
5. 相続税がゼロでも一度は税理士に相談を
相続税は、ゼロ円でも申告が必要なケースと申告が不要なケースがあります。
また、計算方法も簡単とはいえず、ミスをする可能性もあるでしょう。
相続税の計算や手続きは普段意識することがないため、個人で申告するのは不安だという方も多いです。
手続きに必要な書類の準備もしなければならず、個人で行うと手間取ってしまい期限に間に合わない可能性があるため注意しなければなりません。
相続税の計算や申告に不安がある場合には、ミスなく手続きを行うためにも、税理士に相談しましょう。
 遠藤 秋乃(えんどう あきの)
遠藤 秋乃(えんどう あきの)大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。