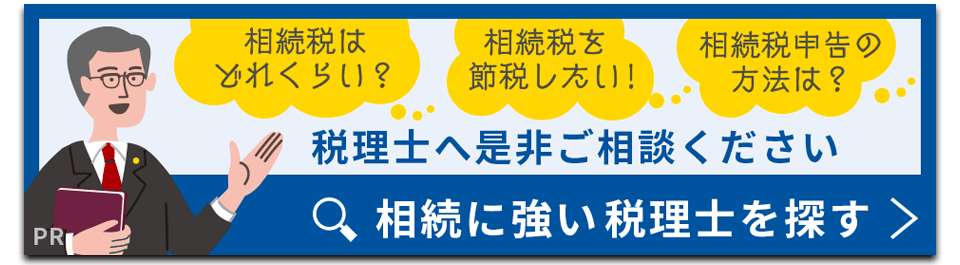「課税遺産総額が基礎控除額以下」ならば相続税申告書の提出は必要ありません。
基礎控除額は法定相続人の人数を理由として変化しますが、「総額が3,600万円以下ならば相続税申告は必要ない」と思い描くと理解しやすいでしょう。
総額が基礎控除額を超過する場合でも、適用できる控除を利用することによって、相続税額がまったく無くなり申告が必要でなくなる人がいます。
それとは逆に、相続税額がまったく無くなる場合であっても、相続税申告が必要不可欠となることもあるので注意が必要です。
実際には申告が必要である場合でも思い違いをしてしまうと、加算税や延滞税といったペナルティを課されたり、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿で確かめて、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続が入ったりする見通しが高くなってしまいます。
目次
1. 相続税が基礎控除未満で申告税がかからない場合は申告不要
相続人同士が友好的な関係であるため、遺産の分与でトラブルに発展することが想定できないとしても、相続税がどれほど課されるかといった心配事が心に残って安心しきれない人も多いはずです。
申告しなかったり、計算した納税額が正しいものでなかったりすると、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税といった、ある意味制裁措置としての税金が課されることが見込まれます。
しかしながら、相続した資産へたちどころに税金が課せられるというわけではなく、相続税には「基礎控除」と呼ばれる法制があります。
被相続人が所蔵していた遺産があった際、一定の金額以下であれば相続税は課されずに申告する必要もなくなるといった措置です。
最初に遺産をきちんと調べて、プラスの資産から基礎控除・被相続人の負債を差し引いてみることから始めてみましょう。
1-1 基礎控除額の計算方法
相続税における基礎控除額は「3,000万円+600万円✕法定相続人の人数」で算出した金額となります。
法定相続人が多人数もいることによって、基礎控除額が増大するために相続人にとっては、よい結果が期待できることになります。
なお法定相続人とは、配偶者と血族を指していますが、血族であるならば誰も彼も事実上の相続人となれるわけではありません。
血族には次にリストされた優先順位があります。
- 常に相続人:配偶者
- 第1順位:被相続人の子・その代襲相続人(孫等)
- 第2順位:直系尊属(両親・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹・その代襲相続人(甥・姪)
配偶者は必ず相続人となれますが、子や代襲相続人が存在しなければ、第2順位もしくは第3順位の方々へと遺産を分割する必要があります。
また、第1順位が子1人で配偶者も既に亡くなっている場合は、子1人だけが被相続人の遺産を継承することになります。
1-2 二次相続の場合は基礎控除額が少なくなる
二次相続の場合だけ利用できる「相次相続控除」と呼ばれる措置が存在します。控除を受けられる人は、次にリストされた全ての条件に合致した場合に限定されています。
- 相続人であること
- 二次相続の開始前10年以内に一次相続により資産を私有財産化したこと
- 一次相続の時に相続税が課されたこと
相次相続控除の計算は入り組んでいて簡単に理解できませんが、理解できるように説明を加える「二次相続における被相続人が一次相続で納めた相続税額」のうち、「経過年数1年につき10%」の税額に相当します。
要するに一次相続と二次相続との間隔が近くなるほど、相次相続控除が増加するいうことです。また一次相続と二次相続との間隔が10年を超過した場合には適用されません。
2. 平成27年の税制改正で相続税の基礎控除額の引き下げ!改正前の金額で計算しないよう注意
相続税の基礎控除額は、相続税申告の判断を下すにおいて重要視されるべき要素です。
平成27年1月1日以降は法改正されたことによって、相続税の申告に直接関係する人が大幅に増加しているため、これから先に親の資産を相続することが否定できない場合は、無関係なことではありませんのでしっかりと考えてみてください。
平成25年度税制改正を受けて、平成27年1月1日以降に生じる相続における基礎控除額の計算式は、3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)となっています。
なお、平成25年度税制改正前における基礎控除額の計算式は、5,000万円+(1,000万円✕法定相続人の数)でした。
このようなわけで税制改正前後を比較してみると、基礎控除額が多分に縮小されたことがが見て取れます。このように引き下げられたことによって、相続税を申告・納税する必要性を有する蓋然性が上昇しています。
実際に財務省の統計によれば、死亡者数に占める相続税の課税件数の割合が近年において次のように推移しており、税制改正によって課税される割合がおおよそ二倍に増加していることがわかります。
|
相続税の課税状況の推移 |
|
|
平成25年 |
4.3% |
|
平成26年 |
4.4% |
|
平成27年 |
8.0% |
|
平成28年 |
8.1% |
|
平成29年 |
8.3% |
このように基礎控除額の規則は複雑ですが、まずは「3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)」という計算式を習得して、「基礎控除額を超過すると相続税の申告が必要となる」ということだけでも把握しておくことが必要です。
3. 遺産総額が基礎控除未満か、相続税の支払いが必要か計算する方法
相続税を申告することになった場合や生前に相続税対策を考えたい場合は、事前に税額がいくらになるかがわかれば安心です。
しかしながら相続税の税額計算は、所有権を得た遺産の額に税率をかけて気軽に導き出せるものではありません。数多くの手順どおりに進めなければならないほか、不動産の価格は自ら価値判断しなければなりません。
あらゆる課税対象となる相続財産と評価額を算定できれば、負担しなければならない相続税の算出まであともう少しです。下記のとおり幾つかのプロセスを経ることが必要なため、こころもち理解が難しくなります。
|
事例 |
|
|
プラスの資産 |
9,000万円 |
|
マイナスの資産 |
3,000万円 |
|
みなし財産 |
2,000万円 |
|
3年以内贈与財産 |
0万円 |
|
相続時精算課税制度 |
0万円 |
|
法定相続人 |
3人(配偶者・子1・子2) |
STEP① 遺産総額を算出する
元からある相続財産におけるプラスの資産から、葬儀費用や債務といったマイナスの資産を控除して、みなし相続財産や贈与財産(相続開始前3年以内)を加算した遺産総額の計算方法は、遺産総額=プラスの資産+みなし相続財産+3年以内贈与財産+相続時精算課税制度対象財産-マイナス資産となります。
事例を計算式に適用すると遺産総額は、8,000万円=9,000万円+2,000万円+0万円+0円-3,000万円となります。
課税価格の合計額が割り出せると、続いて事実上の課税遺産総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を控除して算出します。
基礎控除額は、3,000万円+600万円✕法定相続人の数です。基礎控除額を控除した価額がゼロかマイナスとなった場合、相続税は課税されずに申告する必要もなくなります。
|
相続人の数と相続税の基礎控除額 |
||||||
|
相続人の数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
… |
|
基礎控除額 |
3,600万円 |
4,200万円 |
4,800万円 |
5,400万円 |
6,000万円 |
… |
STEP② 法定相続人の人数を決定し、基礎控除額を計算する
基礎控除額の算出方法は、基礎控除=3000万円+(600万円✕法定相続人の数)となります。事例における基礎控除額は法定相続人数が3人となるため、4,800万円=3,000万円+(600万円✕3人)です。
STEP③ 遺産総額から基礎控除額を引く
遺産総額から基礎控除額が控除された「課税遺産総額」の計算式は、遺産総額-相続税の基礎控除=課税遺産総額となります。
先ほど算出した遺産総額8,000万円から、基礎控除額4,800万円を控除した3,200万円が課税遺産総額です。
ついでながら相続税の基礎控除以下であった場合(遺産総額<相続税の基礎控除額)、相続税はまったく無いことになります。
STEP④ 基礎控除額未満の場合申告不要、超える場合は以下の計算をする
相続税の総額を算出するために税率を掛け算していきます。
ただし、相続税の算出は素直に課税遺産総額に税率を掛け算すればよいのではなく、ひとまず課税遺産総額に各相続人が法定相続分で相続した際の取得金額を算出して、めいめいの法定相続分に応じた取得金額に相続税率を掛け算して算出された税額を足し算することで総額が算出されます。
今回の法定相続分は、法定相続人が配偶者と子2人となるため、配偶者が2分の1、子が4分の1となります。まず課税総額に法定相続分を掛け算してみましょう。
- 配偶者:3,200万円✕1/2=1,600万円
- 子1:3,200万円✕1/4=800万円
- 子2:3,200万円✕1/4=800万円
これでそれぞれの取得金額が算出されました。
次に、各取得金額に税率を掛け算していきます。税率は下記の「相続税の速算表」を参考にしてください。
|
相続税の速算表 |
||
|
相続税の課税標準 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
― |
|
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
それぞれの取得金額に税率を掛け算した計算式は以下のとおりとなります。
- 配偶者:1,600万円✕15%-50万円=190万円
- 子1:800万円✕10%-0円=80万円
- 子2:800万円✕10%-0円=80万円
これらを全て加算した額が相続税の総額となるため、190万円+80万円+80万円=350万円となります。
STEP⑤ 相続人ごとの総額を算出する
相続税の総額に対して、相続人それぞれの取得割合を掛け算することで、より良識的な相続税負担にしていきます。
さらに税額控除があった場合は控除することによって、最終的な納付額が算出されます。
実際に課税される課税遺産総額が算出できれば、相続人全員で納める相続税の総額を計算します。
この場合、事実上遺産をいかなる方法で分与したかに関係なく、民法で規定された法定相続分の割合を用いて課税遺産総額を分配することによって、相続人それぞれの暫定的な税額を算出した合計が、相続人全員で納める相続税の総額となります。
相続人の構成によって法定相続分は次の通りとなります。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
- 配偶者と両親:配偶者2/3、両親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続人それぞれに対する暫定的な税額は、速算表を利用して算出します。
相続税の税率は緩やかに設定されている超過累進税率によって、遺産のうち一定額を超過する部分にはより一層高い税率が課される仕組みとなっています。
|
相続税の速算表 |
||
|
相続税額=(法定相続分で分配した相続人ごとの課税遺産総額✕税率)-控除額 |
||
|
法定相続分で分配した課税遺産総額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
― |
|
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
相続人全員で納めなければならない相続税の総額を認識することによって、事実上遺産を分与した割合に比例して相続人それぞれに振り分けます。
相続人それぞれの税額は、現在の状態になるまでにおけるそれぞれ別の過程に応じた加算や控除がされることになります。
配偶者と1親等の血族以外の相続人に対する税額は2割加算され、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除を適用して相続人それぞれの納付税額が決定されるのです。
配偶者の税額軽減とは、相続した遺産のうち1億6,000万円あるいは法定相続分以下の部分までは相続税が課されないという特例です。
たいていの場合において、配偶者は相続税の納税が免除されていますが、申告書は提出する必要があります。
STEP⑥ 控除される金額を算出し、相続税額を決定する
STEP5.で計算した相続人それぞれの相続税額から税額控除を控除していきます。
税額控除には配偶者控除をはじめとして、障碍者控除・未成年者控除・相次相続控除・贈与税額控除などがあります。
今回は配偶者控除が適用されますので、配偶者の納税額はゼロとなります。
よって、今回の事例における相続税の納付額は下記の通りです。
- 配偶者:0円
- 子ども1: 87.5万円
- 子ども2: 87.5万円
4. 相続税の申告が必要かは国税庁のサイトからも判定できる
相続により私有財産化した資産の評価がまだ済んでない場合、あるいは評価方法について調べたい場合は、相続税に関係する情報を整理してひとつにまとめられた、国税庁HP「相続税・贈与税特集」の「タックスアンサー(財産の評価)」を閲覧してください。
さらに、国税庁HPである「相続税の申告要否判定コーナー」においては、相続財産を入力することによって、相続税の申告が必要か否かについて、大まかな見解をしめすものです。
相続税の申告書を作成するものではないため意に留めてください。税務署から相続についての質疑のため連絡が届いた方が、税務署への回答を作成する際にも利用できます。
5. 本当に相続税が基礎控除未満になる?申告前に確認しておきたいチェックポイント
基礎控除より遺産総額が少ないから申告する必要がないと思っていたとしても、実は相続財産の算出が不完全で間違っていたといった誤謬があると、税務署に過失を具体的に取り上げて指し示されて、もう一度申告することになったり、加えて延滞税や加算税といった本来必要とされている税額を超えて納める必要が生じることとなってしまいます。
5-1 みなし財産やタンス預金などの財産もすべて明らかにしているか
特別気に掛けることが必要であることは、相続財産を見落とすことなくすべて調べ上げることです。特に思いが及ばない点は以下の通りとなります。
- タンス預金やへそくりといった現金
- 名義預金:被相続人が配偶者・子・孫の名義で開設した口座
- 名義が異なっていても、被相続人が通帳や印鑑を手中に収めていたり、名義人自身の都合でお金を出し入れできなければ、実質的に被相続人の資産であるとみなされます。
- 美術品、骨董品、宝石など
- みなし財産:生命保険金や死亡退職金
- 人に貸していて未返済のお金や商売の売り掛け金=債権
- 貸付金は債権として相続財産とみなされます。
- 自宅とは別に所有している山林などの土地
家族に心当たりがないもしくは気づいていない資産であっても、税務署は金融機関や登記情報を容赦せずに情報収集して明らかにします。
追徴課税されることがないようによく調べておくことが大切です。
5-2 被相続人から生前贈与がされていなかったか
生前贈与については、財産を贈与した人が亡くなると、その死亡時からさかのぼって3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となる、と税法に定められています。
仮に現在遺っている資産が相続税の基礎控除内であったとしても、3年分の生前贈与を加算すると基礎控除を超過してしまうことがないように着実に調べるようにしてください。
6. 基礎控除額以上で相続税がかからない場合でも、申告が必要なケースがあるので注意
相続税を算出するうえで、多岐にわたって控除できるものの存在を把握していないと、必要以上の相続税を納めることになってしまいます。
逆に、多岐にわたって控除できるものの存在を把握しておくことで大きく節税できます。
相続人全員が利用できる基礎控除、また相続人ごとに利用できる要件が異なる税額控除など、相続税を計算上減らせる控除について具体的に解説していきます。
相続人が過去3年以内に贈与税を納めていた・相続人に被相続人の配偶者や未成年者や障害者がいる・過去10年以内に被相続人が相続税を納めていた・外国で相続税に相当する税金を納める必要がある場合が税額控除に該当します。
6-1 自宅へ同居していた場合の控除や農業の特例を使う場合は申告が必要
申告が必要な特例・控除
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者控除
申告が不要な特例・控除
- 生命保険や死亡退職金の非課税枠
- 未成年者の税額控除
- 障害者の税額控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
6-2 申告漏れは追徴課税のペナルティーがあるので注意
相続税の納税を逃れる行為に対するペナルティーである追徴課税について解説していきます。
- 延滞税 納付期限までに相続税を納付しなかった際に生じるペナルティです。実際に納める税金は、不足していた相続税と追徴課税に延滞税を合算した金額となり、決められた期限よりあとになってしまった納付時期によって割合も変化します。
- 期限の翌日~2ヶ月:年7.3%もしくは前年の11月30日の公定歩合+4%の低い方
- 期限から2ヵ月超:年14.6%
- 過少申告課税 相続税の申告書に金額が不足して記載されていた際に生じるペナルティです。誤りを取り違えていることに気が付いた時点において、早急に修正申告することによって回避できることがあります。過少申告課税の金額は改めて納めることとなった税金の10%となり、改めて納める金額がそもそも納めていた相続税から50万円を超過した場合は、超過した金額に対しての15%が過少申告課税となるのです
- 追加課税額50万円まで:10%
- 追加課税額50万円超:15%
- 無申告加算税 適切な理由も無しの状態で、申告期限までに申告しなかった際に課せられる税金です。これについても実際の状況によって課税額が変動します。
- 自主的な期限後の申告:5%
- 税務調査による期限後の申告
- 納税額50万円まで:15%
- 納税額50万円超:20%
- 重加算税 相続税の対象となる資産を隠す目的を持ってわざと隠していたり、実際の事柄を別のものであるように見せかけるといった行動や振る舞いのたちが悪かった場合、重加算税といった非常に高く課税額のペナルティーが課せられます。
- 申告書が提出されていた場合:35%
- 申告書が提出されていなかった場合:40%
7. 相続税の計算や、課税遺産総額が基礎控除未満か心配な場合は税理士に相談
相続財産のすべてに相続税がかかるわけではなく、税金が課されない範囲の基礎控除額があるため、相続財産が基礎控除額より低くなることによって、相続税の申告ならびに納税は不要となります。
専門的な知識を要する不動産といったの資産の評価は自身で判断することは難しいため、相続財産が「基礎控除額以上」となることが見込まれる場合には、税理士などの専門家へ早い段階で良い案があれば教えてほしいと相談することをおすすめします。
相続税の申告期限は10ヶ月以内という制約があるため、期限を超過してしまうと実際のところ適用できた特例を利用できなくなる場合があります。
特例が利用できないことで相続税の負担増加、もしくは申告期限を超過したことによる追加のペナルティー税で損することがないように、早い段階から行おうとする対応を心掛けていくことが大切です。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。