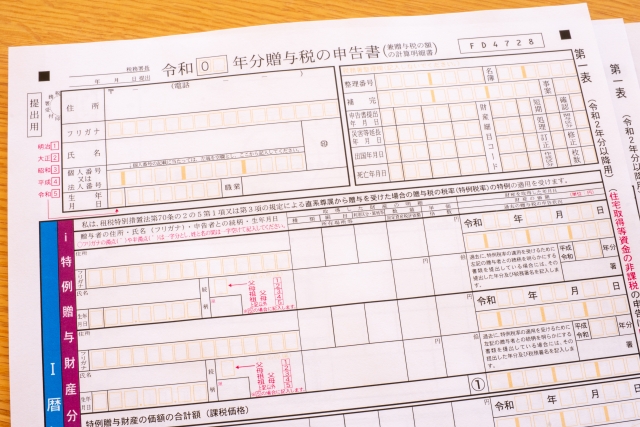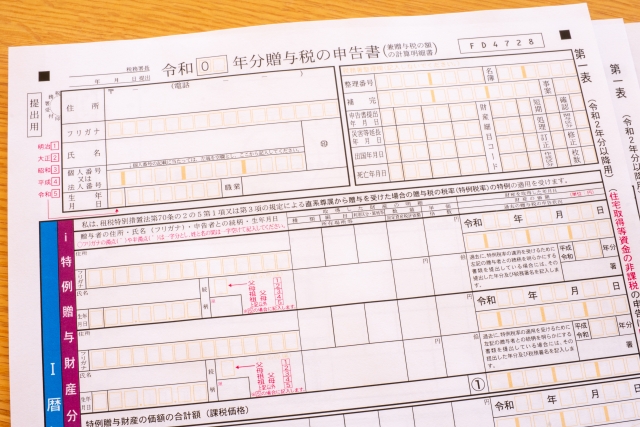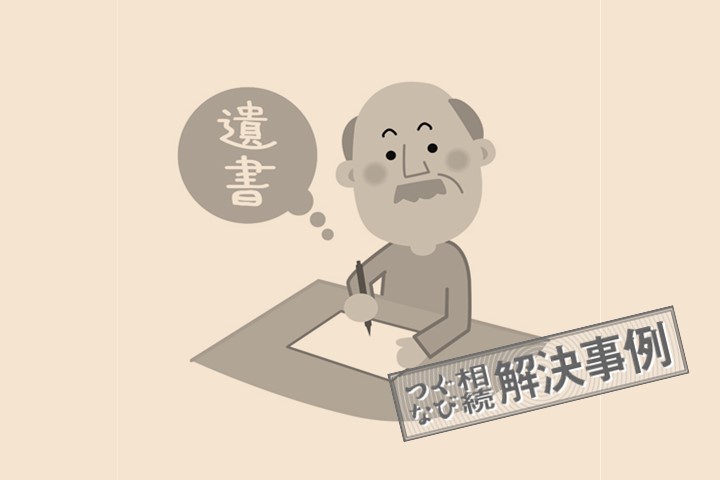遺言というと、そこに書かれているものは「絶対」という風に考える人もいるかもしれませんが、実はそうとも限りません。
もし、相続人の「遺留分」を無視したような内容であれば、その相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。ここでは、遺言と遺留分の関係について弁護士が解説します。
目次
遺言があった場合、遺留分はどうなる?
前述の通り、遺言があった場合に、遺言の内容が相続人に認められた「遺留分」を侵害するものであれば、遺留分侵害額請求をすることができます。
ここからは、遺留分や遺留分侵害額請求について詳しく説明します。
遺留分とはなにか
遺留分とは、特定の相続人が、相続において最低限取得することが認められた遺産の一定割合のことをいいます。
したがって、遺言によって一切相続を受けられないこととされていても、遺留分に関する民法の要件を満たす場合には、遺産の一部を受け取れることがあります。
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とはなにか
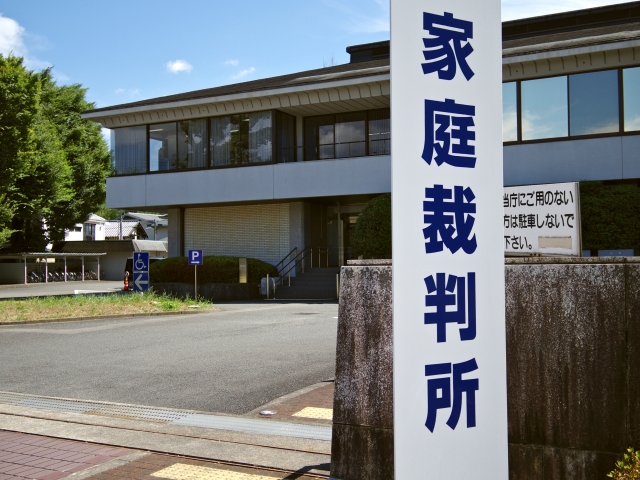
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されている相続人が遺留分を侵害している者に対して侵害された額を請求することをいいます。従前、相続人が自己の遺留分に関する権利を主張することを「遺留分減殺請求」と呼んでいました。
しかし、2019年7月1日に施行された改正民法において、従来の遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」に変更されています。
この改正に伴い、従来の遺留分減殺請求とは法的な効力も変わっていますので注意が必要です。特に大きな変更点は、遺留分侵害額請求が、金銭の支払いを求める権利に変更された点です。
従前は、例えば、不動産が遺産の場合に遺留分減殺請求がされると権利者は不動産の共有持分を取得する効果がありました。
しかし、共有状態となるとその後の遺産の処分に差し支えが生じることが多いほか、遺留分権利者としても金銭補償が受けられればよいと考える方が多いという事情がありました。
このため、民法改正後の遺留分侵害額請求では、遺産そのものではなく遺留分に相当する金銭の支払いにより解決するよう変更されたのです。
遺留分侵害額請求は、相手方に対する一方的意思表示によって効力を生じます。
ただし、家庭裁判所に遺留分に関する調停を申し立てただけでは足りず、内容証明郵便等によって相手方に意思表示をする必要があります。
遺留分を侵害する遺言があった場合
遺言の内容が「相続財産のすべてを長女Aに相続させる」といったものであった場合、他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。
このように、遺言が遺留分を侵害するものである場合に遺留分侵害額請求権を行使すれば、遺言の内容に優先して遺留分の侵害に相当する分の支払いを受けることができます。
もっとも、遺留分を侵害する遺言であったとしても、遺言自体は無効にはなりません。遺留分侵害額請求権は必ず行使されるとは限りませんので、行使されない場合には遺言の内容にしたがった相続が行われることになります。
また、遺留分侵害額請求権が行使された場合でも、権利者に侵害額に相当する金銭を支払えば、あとは遺言の内容どおりに遺産が承継されることになります。
遺留分権利者とその割合
次に、遺留分を受け取る権利のある人と、その遺留分の割合について説明します。
遺留分権利者
遺留分侵害額請求をすることのできる権利者は、法定相続人の一部です。具体的には、以下の通りです。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子及びその代襲相続人(子が死亡した場合等における孫など)
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
法定相続人であるにもかかわらず、遺留分侵害額請求をすることができないのは兄弟姉妹及びその代襲相続人です。
なお、代襲相続人とは、相続人となるべき者が死亡や欠格・廃除の制度によって相続権を有しない場合に代わりに相続する者をいい、相続人となるべきだった者の子や孫が代襲相続人にあたります。
遺留分割合
遺留分侵害額請求ができる遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。具体的には以下の通りです。
- 直系尊属(被相続人の親や祖父母など)が相続人となる場合、遺留分割合は法定相続分の3分の1
- 相続人が直系尊属以外の場合、遺留分割合は法定相続分の2分の1例えば、相続人が配偶者と子ども1人という場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。そして、配偶者と子どもは直系尊属にはあたりません。したがって、配偶者と子どもの遺留分はそれぞれ4分の1(2分の1 × 2分の1)となります。
遺言書の作成と効力
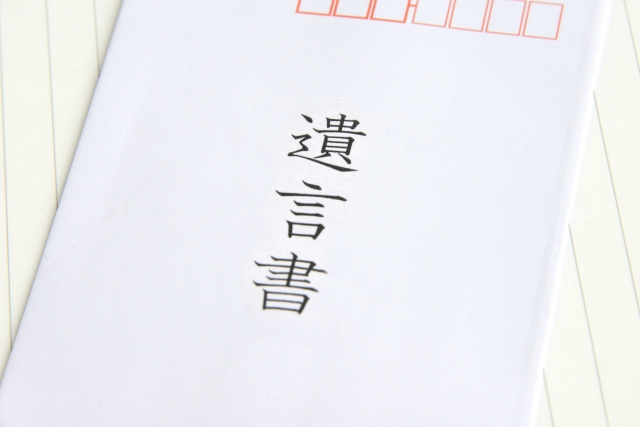
遺言書がない場合には、民法上定められた法定相続分に基づき相続が行われます。被相続人が法定相続分と異なる相続を希望する場合には、生前に遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書に従った相続を確実に行うためには、まず遺言書が民法の定める厳格な要件を満たしている必要があります。
そこで、以下では、遺言に関する民法上の基礎知識について説明します。
遺言書の種類
民法上の遺言の方式は、緊急時における方式(危急時遺言)と通常時における方式の2つに大きく分けられます。
危急時遺言とは、突然の事故などで死の間際に残す遺言であり、ほとんど利用されていません。被相続人の生前対策としての遺言は基本的に通常時における方式です。
通常時における遺言の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が民法上定められています。
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者本人が手書き(自筆)で遺言の全文、遺言者の氏名、遺言作成の日付を書いた上で押印するものをいいます。
次に説明する公正証書遺言ほど手続きに手間がかからないことから、比較的よく利用されている方式といえます。自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多いため、紛失や改ざんのおそれがあります。
また、専門家の助言を受けずに自分一人で作成することができるため、民法の定める要件を満たしていないことが相続開始後に明らかとなり、相続争いの種になることがあります。
- 公正証書遺言
遺言の内容通りの相続を確実に実現したい場合には、公正証書遺言を選択することがおすすめです。公正証書遺言は、全国にある公証役場において公証人が立ち会って作成します。
したがって、遺言が民法上の要件を満たしておらず無効になるといった事態を避けることができます。また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、紛失したり改ざんされたりするリスクがありません。
しかし、公証人は遺言の形式が適法であるかを確認するだけですので、相続財産の分け方など個別の相談に乗ってくれるわけではありません。
このため、遺言の内容に関してアドバイスをもらいたい場合には、弁護士など相続に強い士業に相談する必要があります。
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じ様に公証役場で作成する遺言です。ただし、公正証書遺言と異なり、遺言の内容は立ち会った公証人や証人、相続人に対して開示されません。
このため、相続開始まで内容を秘密にしておきたい場合に秘密証書遺言が選択されます。ただし、遺言の内容を誰も確認しないため、相続開始後に遺言の適法性をめぐって争いになるリスクはあります。
このせいもあって、秘密証書遺言はあまり利用されていません。
遺言書の効力
遺言書は、遺言者が死亡して相続が開始した時点で効力が生じます。遺言書に記載することで法的な効力が発生する内容には様々なものがありますが、以下の事項が代表的です。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 相続人の廃除
- 子どもの認知
また、遺言書は一度作成した後でも、遺言者の意思によっていつでも撤回することができます。
ただし、遺言の撤回は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれかの方式によって行う必要があります。このほか、遺言の撤回を明示していなくても、撤回とみなされることがあります。
例えば、遺言者が作成した遺言と矛盾する別の遺言を後から作成した場合、後から作成した遺言が優先され、前に作成した遺言は撤回されたものとみなされます。
遺言書を勝手に開封してはいけない

遺言の3方式のうち自筆証書遺言は、遺言者の自宅などで保管されていることがあります。
このため、遺言者の死亡後に遺品の整理をしている中で親族が偶然、遺言書の存在に気がつくことがあります。
このような場合、遺言書を勝手に開封することは厳禁です。遺言書の保管者又は発見者は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続を経る必要があるためです。
故意に遺言を開封した場合には過料が課せられることもあります。とはいえ、遺言書を発見した人が開封してしまっても、遺言自体が無効になるわけではありません。
したがって、開封後であっても家庭裁判所の検認手続は受ける必要がありますし、開封した相続人が相続権を失うこともありません。
ただし、発見した遺言書の内容が自分に不利だったからといって、遺言書を隠したり捨ててしまったりすると、相続権を失うことがあるため注意が必要です。
遺言で遺留分を調整するには
遺留分に関する権利を相続人に行使させないようにする一番確実な方法は、相続開始前に遺留分権利者に遺留分を放棄させることです。ただし、遺留分の放棄は、家庭裁判所への申し立てが必要です。
裁判所は、遺留分の放棄が権利者の自由な意思であることや、遺留分放棄の代償を支払ったことなどを確認します。
したがって、遺言者が遺留分権利者の意思に反して遺留分を放棄させることはできません。
これに対し、遺留分の放棄までは求めないけれども遺留分に関係なく特定の相続人に財産を相続させたいというケースでは、以下の2つの方法によって遺留分の調整を行うことが多いといえます。
遺言に付言事項を加える
遺言の付言事項というのは、遺言の法的な効力とは関わりのない遺言者から相続人へのメッセージを指します。
特定の相続人にすべての財産を相続させたいなど、遺留分を侵害する内容の相続を実現したい場合には、付言事項として遺留分侵害額請求をしないで欲しい旨を記載しておくことがあります。
付言事項はあくまでも法的効力のないメッセージに過ぎませんので、相続人がこれと異なる行動をすることを制限できるわけではありません。
しかし、付言事項にメッセージを残すことによって、相続人が故人の遺志を汲んでくれる可能性があります。
遺留分請求された場合の対象財産を指定しておく
遺言により遺産を受け取る相続人を受遺者と呼びます。受遺者が複数いる場合には、原則として受遺者が遺言により受け取る財産の価額の割合に応じて遺留分侵害額を支払うことになります(民法1047条1項2号)。
もっとも、遺言によりこの民法の規定と異なる内容を定めることも可能と解釈されています。
このため、遺留分対策として、遺言において遺留分侵害額請求の対象とすべき財産をあらかじめ指定しておくことがあります。
まとめ
遺言と遺留分の関係性について理解できましたか。遺言で特定の人物に全ての財産を相続させるよう指定することもできますが、遺留分侵害額請求をされるなど相続トラブルに発展する可能性もあります。
そういった内容の遺言を希望する際には、作成時に遺留分侵害額請求されることを見越して、対象とすべき財産を指定するなどの工夫が必要となります。
遺言は、ただ思いのままに書けばよいという者ではなく、専門的な知識も必要です。弁護士をはじめとした相続に強い士業に相談することをおすすめします。

弁護士 松浦 絢子
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、男女問題など幅広い相談に対応している。