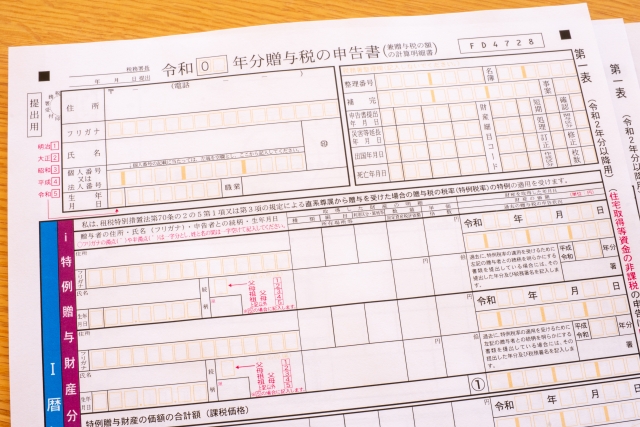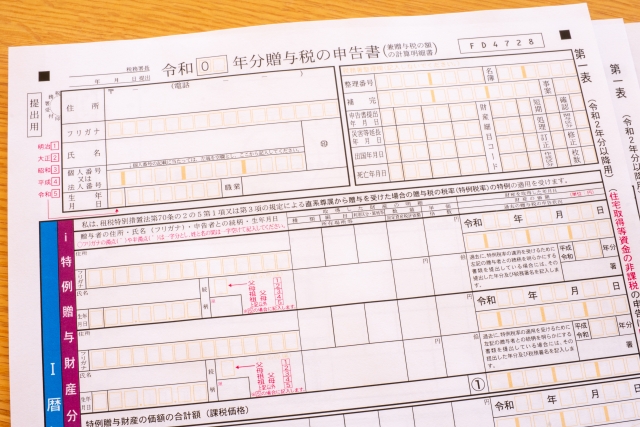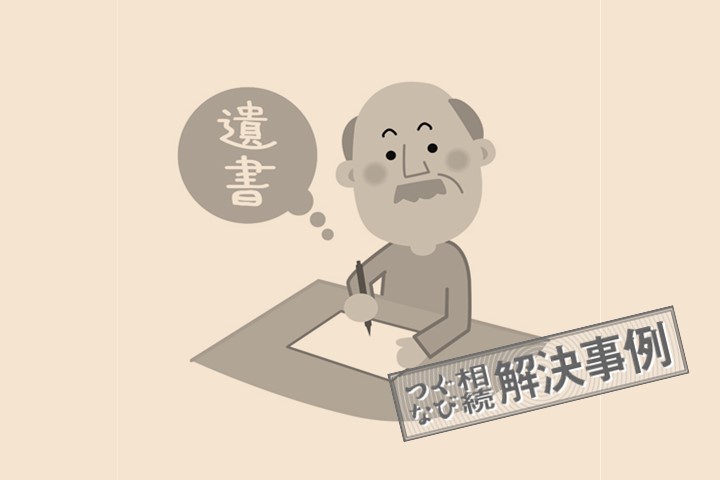特別受益とは、被相続人から相続人が遺贈を受ける、もしくは被相続人から生前贈与を受けるなどして特別な利益を得たことを意味します。
ここでは、特別受益に関する基本的な解説に加え、関連する法改正を詳解。計算方法や寄与分との関係にも触れます。
目次
1. 特別受益とは

「特別受益」とは、相続人が被相続人から遺贈を受け、または被相続人の生前に贈与を受けるなど、被相続人から特別な利益を得たことをいいます。
共同相続人のうちの一人が、被相続人から遺贈を受け、または被相続人から贈与を受けているにも関わらず、他の相続人と同様の相続分を取得してしまうと、不公平な相続手続きとなってしまいます。
そこで、相続人が被相続人から遺贈を受け、または生前に贈与を受けている場合には、それを特別受益と考え、この特別受益を「相続分の前渡し」とみなして取得すべき相続分を計算することになります。
簡単に言うと、特別受益の分だけ相続分を減らす、という計算方法になります。
特別受益としてみなされるのは、「遺贈」または「婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与」を受けた場合とされております。
では、具体的にはどのようなものが特別受益に該当するのか、以下、ご紹介します。
1-1 遺贈
遺言書を作成する者はその遺言により、自己の相続発生時に、特定の者に対して財産を譲る旨を定めることができます。
これを「遺贈」といいます。
遺贈は、相続人以外の第三者のみならず、相続人に対しても行うことができます。被相続人から相続人に対してなされた遺贈は、そのすべてについて特別受益に該当します。
なお、遺言書に「相続させる」と記載されたものでも、実質的に遺贈であると解される場合には、特別受益に該当します。
1-2 婚姻のための贈与

「婚姻のための贈与」とは、持参金や支度金、結婚生活のための家具購入費用などが特別受益の対象となり得ます。
しかし、通常の範囲での結納金や結婚式の費用などは特別受益に該当しないと考えられることが多いようです。結納金や挙式費用は親が用意して負担するもの、との考えが以前は一般的であったからです。
ただし、社会情勢の変化により、結納金や挙式費用は当事者が負担すべきものとの考え方が一般的になれば、これらも特別受益に該当する可能性があります。
また、被相続人から一部の相続人だけが結婚費用の支払いを負担してもらっていて、他の相続人は自ら支払っている、といった不公平が生じている場合には、特別受益に該当する可能性が高いかもしれません。
1-3 養子縁組のための贈与
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがありますが、特別養子縁組の場合は、養子は養親の相続に関してのみ相続人となります。
これに対して普通養子縁組の場合には、養子は実親と養親、両方の相続人となります。
例えば普通養子縁組において、縁組をする際に実親が子に持参金を贈与した場合には、実親の相続時において、その持参金が特別受益に該当することになります。
1-4 生計の資本としての贈与
「生計の資本としての贈与」とは、住宅購入のための資金や宅地の贈与、事業を始めるに際しての開業資金や独立資金の贈与、田や畑などの農地の贈与などが該当します。
これらの贈与を被相続人から受けていた場合、特別受益の対象となり得ます。
1-5 不公平な生命保険金
受取人が相続人中の一人に指定されている生命保険金請求権は、原則として「特別受益」には該当しません。当該生命保険金請求権は、受取人固有の財産であり相続財産には含まれないからです。
ただし、その生命保険金請求権により高額な保険金を受け取るなど、相続人間の不公平が著しくなる場合には、例外的に「特別受益」となることもあります。
被相続人が相続人中の一人を受取人に指定したことがその者への生活保障の意図であったか否か、その他、受取人の生活状況、保険金の額やその額が相続財産に占める割合などを勘案し、「特別受益」に該当するか否かを総合的に判断することになります。
1-6 学費
普通教育以上の高等教育費用、留学費用などは「特別受益」に該当する可能性があります。
ただし、被相続人の資産、生活レベルや社会的地位などに照らして扶養義務の範囲とみなされるものであれば、「特別受益」には該当しません。
しかしその場合でも、兄弟姉妹間での不公平が生じるときには、「特別受益」に該当する可能性が出てきます。
1-7 土地・建物の無償使用

被相続人の土地や建物を無償で使用させてもらっていた場合、原則としては「特別受益」に該当しないと考えられますが、他の相続人との間で不公平が生じるとみなされる事情があるときは、「特別受益」に該当することもあり得ます。
1-8 生活費の援助
被相続人から生活費の援助を受けていた場合、それが扶養義務の範囲であれば「特別受益」には該当しません。
しかし、扶養義務の範囲を越えた援助とみなされるような場合には、「特別受益」に該当し得ます。
特別受益の計算方法
特別受益が発生する場合には、相続分の計算方法が通常のやり方とは異なってきます。具体的には、次のような計算方法により各相続人の相続分を算出することになります。
- 特別受益を受けた相続人の相続分
(相続開始時の相続財産の価額 + 特別受益額)× 法定相続分 - 特別受益額 = 相続分
- 特別受益を受けていない相続人の相続分
(相続開始時の相続財産の価額 + 特別受益額)× 法定相続分 = 相続分
なお、「特別受益額」は、相続開始時の価額で算出されることになります。
1-9 特別受益の計算例
特別受益の計算例を、具体的な事例に基づき、いくつかあげてみたいと思います。
計算例①:法定相続分の範囲内で特別受益が発生した場合
相続財産が5000万円で、相続人は子Aと子Bの2名で、Aが1000万円の特別受益を受けた場合。
〈特別受益を受けたAの相続分〉
(5000万円+1000万円)× 1/2 - 1000万円 = 2000万円
〈特別受益を受けていないBの相続分〉
(5000万円+1000万円)× 1/2 = 3000万円
計算例②:法定相続分を越える特別受益が発生した場合
相続財産が5000万円で、相続人は子Aと子Bの2名で、Aが6000万円の特別受益を受けた場合。
〈特別受益を受けたAの相続分〉
(5000万円+6000万円)× 1/2 - 6000万円 = -500万円 →0円
〈特別受益を受けていないBの相続分〉
(5000万円+6000万円)× 1/2 = 5500万円 →5000万円
法定相続分を越える特別受益を受けた場合であっても、特別受益を受けた相続人は、その超過部分を返す必要はありません。
上記の計算例によれば、Aは-500万円になりますが、これを相続財産中に返金する必要はありません。
この場合、特別受益を受けた相続人の相続分はゼロとなり、他の相続人は現にある相続財産5000万円を相続することになります。
計算例③:法定相続分を越える特別受益が発生し、特別受益者以外の相続人が複数いる場合
相続財産が5000万円で、相続人が妻Aと子Bと子Cの3名で、子Bが3000万円の特別受益を受けた場合。
〈特別受益を受けた子Bの相続分〉
(5000万円+3000万円)× 1/4 - 3000万円 =-1000万円 →0
〈特別受益を受けていない妻Aの相続分〉
(5000万円+3000万円)× 1/2 = 4000万円 →※1
〈特別受益を受けていない子Cの相続分〉
(5000万円+3000万円)× 1/4 = 2000万円 →※2
※1: 5000万円 × 4000万/6000万 = 33,333,333円
※2: 5000万円 × 2000万/6000万 = 16,666,666円
法定相続分を越える特別受益を受けた場合であっても、特別受益を受けた相続人(特別受益者)は、その超過部分を返す必要がないのは前述の通りです。
よって、特別受益者Bの相続分はゼロになります。
では、特別受益を受けていない妻Aと子Cの相続分はどうなるのでしょうか?
上記の計算では、Aは4000万円、Cは2000万円取得できる計算ですが、相続財産は5000万円しかありません。
不足する1000万円につきどのように考えるべきかという問題です。これについては3通りの計算方法があるとされます。
- (ア) 相続開始時の相続財産について、超過特別受益者(B)を除いた他の共同相続人の具体的相続分の比率に応じ、各自の相続分を算定する方法(:相続財産×各相続人の具体的相続分比率)
- (イ)超過特別受益額(-1000万円)を、超過特別受益者(B)を除いた他の共同相続人の法定相続分に応じて負担する方法
- (ウ)配偶者別格の原則により、配偶者を除いた他の共同相続人で、(ア)または(イ)により計算する方法
実務では、共同相続人の公平性を考慮し、(ア)の方法を用いることが多いようです。よって、上記の「※1」と「※2」を(ア)の方法で算出してみます。
よって、(ア)の計算方法によれば、相続財産5000万円に対し、妻Aは33,333,333円、特別受益者である子Bは0円、子Cは16,666,666円の相続分となります。
2. 特別受益は相続税の対象ではない

特別受益は相続税の対象とはなりません。そのため、相続税を計算する場合に特別受益を考慮する必要はありません。しかし、注意が必要なのは「生前贈与加算」です。
生前贈与加算とは、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた相続人は、相続税の申告時、相続税課税価格に贈与額を加算しなければならないという制度です。
亡くなる直前に相続財産を減らすため贈与をしたとしても、結局、その贈与分は相続財産に加算され相続税の計算をしなければならないというものです。
なお、贈与する際に贈与税を支払っている場合は、支払った贈与税額を相続税から差し引くことになります。
これら税務に関しての詳細は税理士にご確認下さい。
3. 特別受益を考慮して相続分を計算しないケースもある
相続人が特別受益を受けていたとしても、特別受益を考慮せずに相続分を算出するケースがいくつかあります。以下に説明します。
3-1 相続人が一人のみ
被相続人に法定相続人が一人しかいない場合には、特別受益を考慮する必要はありません。特別受益の制度は、他の相続人との間の不公平を是正するためのものであり、他に相続人がいない以上は、不公平は生じないからです。
相続人が一人だけの場合には、特別受益を考慮する必要は一切ありません。
3-2 受益者が相続放棄
特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合は、特別受益を考慮することなく相続分の計算をすることになります。
相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったものとみなされることになるため、特別受益を考慮して相続分を計算する必要はなくなります。
相続放棄をした相続人を除き、他の相続人が通常の算定方法で相続分を計算することになります。
3-3 相続財産がマイナス
被相続人が多大な債務を抱えていたような場合には、相続財産がマイナスになることがあります。相続財産とは、預貯金や不動産といったプラスの財産のみならず、借金などのマイナス財産も含まれます。
相続人が被相続人の財産を相続により承継した場合には、その借金等を弁済しなければなりません。相続財産が借金等のマイナスの財産しか残っていない場合には、特別受益を考慮して相続分を計算する必要はありません。
この場合には、相続人は法定相続分に応じて、債務を承継することになります。
もっとも、通常であればこのような場合には、家庭裁判所における相続放棄の手続を考えるべきかもしれません。
3-4 遺言書に「考慮しない」と意思表示がある
被相続人が特別受益を考慮しないよう求めている場合には、特別受益を考慮せずに相続分を計算することになります。被相続人が「特別受益を考慮しないように求めること」を「特別受益者に対する持ち戻し免除」といいます。
例えば、被相続人が遺言書で「特別受益者の持ち戻しを免除する」といった記載をしている場合には、特別受益を考慮せずに相続分を計算することになります。
その他、被相続人による贈与や遺贈が、特定の相続人に対し相続分の他に特に利益を与える趣旨であることが分かる場合にも、「黙示による持ち戻し免除の意思表示」が認められるとされています。
例えば、重度の病症により独立した生計を営むことが困難な子に対し、被相続人が生前に住居用の宅地を贈与していたというケースで「黙示の持ち戻し免除の意思表示」が認定された事例があります。
このような場合も、特別受益を考慮せずに相続分を計算することになります。
3-5 他の相続人が主張・請求しない
特別受益を受けた相続人がいる場合であっても、他の相続人が、特別受益があることを主張しない場合や、特別受益を考慮して相続分を計算するよう請求しない場合には、特別受益を考慮せずに相続分を計算することができます。
特別受益の制度は、他の相続人との間の不公平を是正するためのものであるため、他の相続人が不公平であることを主張しない以上、考慮する必要がないからです。
なお、遺贈の場合は遺言書があるため他の相続人はそれが特別受益であることを立証しやすいといえますが、贈与の場合には立証しにくいケースもあります。
相続人中の一部が特別受益を受けていると思われたとしても、それを立証できるかどうか難しいケースも多々あるのです。
そのような場合においては、弁護士等の専門士業に相談することをお勧めいたします。
4. 特別受益に時効はない

特別受益には時効はありません。よって、被相続人が亡くなる10年前に行われた贈与であっても、特別受益となる可能性はあります。
なお、2019年7月1日に施行された改正民法により、相続人に対する贈与は、原則として被相続人の死亡前10年以内になされたものに限り特別受益に該当することとされました。
この改正民法については後で詳述致しますが、2019年7月1日よりも前に発生した相続に関しては改正法の適用がないため、被相続人が亡くなる10年以上前に行われた贈与であっても、特別受益となる可能性があります。
つまり、改正法適用前の相続に関しては、例えば被相続人の死亡より30年前になされた贈与であっても、特別受益となる可能性があるということです。
5. 特別受益と持戻しの免除について
特別受益の持ち戻し免除については、「特別受益を考慮せずに相続分を算出するケース」においても説明しましたが、ここでもう少し詳しくご説明します。
被相続人が「特別受益を考慮しないように求めること」を「特別受益の持ち戻し免除」といいますが、持ち戻し免除の対象となるのは、法定相続人です。
その相続において相続権を有する相続人のみが持ち戻し免除の対象者となるのであり、相続人となる可能性がある者であっても、先順位の法定相続人が存在する場合には、その者は相続人とならないため、持ち戻しの有無は問題とならず持ち戻し免除の対象と考える必要はありません。
被相続人による持ち戻し免除は、必ずしも遺言書により行わなければならないわけではありません。
しかし、特別受益の持ち戻し免除の有無は、相続人の相続分に大きな影響を与えることになるものです。被相続人による意思表示が不明確であると、相続人間の争いを生じかねません。
特別受益の持ち戻し免除の意思がある場合には、遺言書において、「特別受益の持ち戻しを免除する」といった記載を明確に表記しておいた方がよいでしょう。
なお、被相続人による持ち戻し免除の意思表示があると、他の相続人は特別受益を受けた相続人に対し、「特別受益分だけ相続分を減らすべきだ」といった主張はできなくなります。
しかし、この場合でも、特別受益が他の相続人の「遺留分」を侵害しているような場合には、その遺留分の侵害を回復するよう請求することが可能です。
遺留分とは一定の相続人に認められる最低限度の遺産取得分のことですが、詳細は弁護士、司法書士等の専門士業に確認しましょう。
6. 特別受益に関する法改正

2019年7月1日施行の民法改正により、遺留分算定時の特別受益に該当する贈与の範囲が変更されました。従前は、被相続人が亡くなる何十年前の贈与であっても、期間の制限なく特別受益となる可能性がありました。
しかし、民法改正により、原則として被相続人が亡くなる前「10年以内」の贈与に限り、特別受益に該当し得るものとなりました。
ただし、贈与の当事者である被相続人と相続人とが、遺留分を有する他の相続人に損害を加えることを知りながら贈与した場合には、10年前の日よりも前になされた贈与についても、特別受益に該当し得ることとされております。
なお、改正民法が施行される2019年7月1日よりも前に開始された相続に関しては、改正民法の適用はありません。
2019年6月30日以前に発生した相続については、被相続人が亡くなる何十年前の贈与であっても、特別受益となる可能性があります。
6-1 持戻し期間が10年へ改正
「特別受益の持ち戻し」とは、特別受益に該当する遺贈または贈与の価額を相続財産価格に組み入れたうえで、特別受益者の取得分を清算し、各相続人の相続分を計算することをいいます。
前述の通り、2019年7月1日施行の民法改正により、贈与に関しては原則として被相続人が亡くなる前「10年以内」の贈与に限り、特別受益に該当し得るものとなりました。
よって、特別受益とみなされる贈与の持ち戻しも、原則として被相続人が亡くなる前「10年以内」の贈与に関してのみ、持ち戻しの対象となり得ることとなります。
ただし、贈与の当事者である被相続人と相続人とが、遺留分を有する他の相続人に損害を加えることを知りながら贈与した場合には、10年前の日よりも前になされた贈与も持ち戻しの対象となります。
6-2 配偶者への持戻し免除の改正

配偶者が被相続人と共に生活していた自宅について、配偶者が被相続人からその贈与を受けた場合、当該贈与が特別受益に該当すると認定されることがありました。
通常、夫婦の一方が死亡した場合、他方配偶者はそれまで居住してきた自宅に住み続けたいと考えるのが一般的だと思われます。
ところが、その希望に基づき配偶者が自宅を取得することが特別受益に該当してしまうのであれば、配偶者は自宅以外の預貯金等の相続財産について、取得分が減少してしまうことになります。
そうなれば、配偶者の生活が脅かされることになりかねません。
そのため、このような事象を回避し、残された配偶者を保護するための施策が必要、といわれてきました。
そこで、2019年7月1日施行の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対して居住用の不動産を遺贈または贈与したときは、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりました。
つまり、結婚20年以上の夫婦間による自宅の遺贈または贈与については、原則として特別受益に該当しない、ということになったのです。
被相続人が遺言書において、配偶者への自宅の遺贈または贈与について持ち戻しを免除する、という記載をしてなくとも、原則として特別受益には該当しないことになります。
ただし、婚姻期間が20年に満たない夫婦の場合には、この規定の適用はありません。
婚姻期間が20年に満たない場合に、配偶者に対して自宅の土地、建物を遺贈または贈与する場合、その遺贈や贈与を特別受益に該当させたくないと考えるときには、「特別受益の持ち戻しを免除する」といった記載を遺言書等で明確に表記しておく必要があります。
7. 特別受益と寄与分の関係

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に関して特別の寄与をした者がいるときは、その者の功績を認めて相続における取得分を増やすという制度です。
特別の寄与をした者とは例えば、被相続人の事業を手伝って財産の増加に尽くした者や、被相続人の看護や介助を行い被相続人の財産が消費されることを防いだ者などを言います。
被相続人の相続財産を維持増加させた相続人と、そうではない相続人との間の公平を図るため、被相続人の財産に特別の寄与をした相続人を保護するための制度といえます。
寄与分が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 被相続人の法定相続人であること。
- 「特別」の寄与をしていること。
- 被相続人の財産の「維持」または「増加」をしていること。
各要件に関して、以下簡単にご説明します。
7-1 被相続人の法定相続人であること
寄与分は法定相続人にしか認められません。たとえ被相続人の財産に寄与していても、相続人以外の者には、寄与分は認められません。
なお、相続人以外の親族に関しては、後述する「特別寄与料の請求」が認められる場合があります。
7-2 「特別」の寄与をしていること
寄与分が認められるには、その寄与が「特別」なものでなければなりません。夫婦や親子の扶養義務の範囲内の行為とみなされるものは、特別の寄与とは認められず、寄与分は発生しないと考えられます。
また、全ての相続人が同等の寄与をしていれば、特別の寄与は生じないことになります。
7-3 被相続人の財産の「維持」または「増加」をしていること
特別な寄与をしていたとしても、結果的に被相続人の財産の維持や増加がなされていなければ、寄与分は認められません。ただし、その維持や増加は現存しなくても良いとされています。
一時的にでも被相続人の財産が維持・増加されていれば、寄与分が認められる可能性があります。
以上の通り、寄与分とは、特別な寄与により相続財産を維持・増加させた相続人を対象として、他の相続人との公平を図る制度です。
つまり、寄与分は相続分を算定する際に具体的な取得分を修正するためのものですが、これは特別受益の裏返しの制度ともいえます。
特別受益は特別受益者がすでに得ている受益分を相続財産に含めて計算するものですが、寄与分は逆に、寄与者が得るべき寄与分を相続財産から除外して各相続人の相続分を計算することになります。
7-4 特別受益者と寄与者が同一人物の場合
特別受益者と寄与者が同一の相続人である場合においては、その者の取得分につき特別受益の価額をマイナスし、寄与分の価額をプラスすることになります。
この「特別受益額のマイナス」と「寄与分額のプラス」について、行う順序により二種類の方法があります。
①最初に「特別受益額のマイナス」を行い次に「寄与分額のプラス」を行う方法と、②「寄与分額のプラス」を行い次に「特別受益額のマイナス」を行う方法です。
①と②とでは、特別受益者が相続分を越える特別受益を受けていた場合(これを「超過特別受益」といいます)に違いが出てきます。
結論から申し上げますと、実務では①最初に「特別受益額のマイナス」を行い、次に「寄与分額のプラス」を行う方法を採用します。
以下、具体例を挙げて計算の方法、及び①と②の違いを説明します。
- 例)相続財産が5000万円で、相続人は子Aと子Bの2名で、Aが4000万円の特別受益を受けており、2000万円の寄与分がある場合
《①最初に「特別受益額のマイナス」を行い次に「寄与分額のプラス」を行う方法》
〈特別受益及び寄与分があるAの相続分〉
(5000万円+4000万円-2000万円)× 1/2 - 4000万円 + 2000万 = ※
〈特別受益も寄与分もないBの相続分〉
(5000万円+4000万円-2000万円)× 1/2 = ※
しかし、前述した通り、法定相続分を越える特別受益を受けた場合であっても、特別受益を受けた相続人はその超過部分を返す必要がありません。
この場合、特別受益を受けた相続人の相続分はゼロになるため、-500万円ではなく0円になります。
そして、これに寄与分額である2000万円をプラスするため、Aの相続分は2000万円となります。
特別受益と寄与分がないBは、Aが取得する相続分を除いた、実際に残存する相続財産を取得することになるため、その取得額は3000万円になります。
〈特別受益及び寄与分があるAの相続分〉
(5000万円+4000万円-2000万円)× 1/2 - 4000万円 = -500万円 → 0円 + 2000万円 = 2000万円
〈特別受益も寄与分もないBの相続分〉
(5000万円+4000万円-2000万円)× 1/2 =3500万円 → 3000万円
ちなみに、②の方法で計算すると、次のようになります。
《②最初に「寄与分額のプラス」を行い次に「特別受益額のマイナス」を行う方法》
〈寄与分及び特別受益があるAの相続分〉
(5000万円-2000万円+4000万円)× 1/2 + 2000万 - 4000万円 = 1500万円
〈寄与分も特別受益もないBの相続分〉
(5000万円-2000万円+4000万円)× 1/2 = 1500万円
この②の計算によると、Aの超過特別受益がゼロにならないため、①と算出される相続分に違いが出てきます。
実務では前述の「①最初に「特別受益額のマイナス」を行い次に「寄与分額のプラス」を行う方法」が採用されると考えられておりますので、その点ご注意ください。
8. 特別寄与料の請求

2019年7月1日施行の民法改正により、相続人以外の親族の中に、被相続人の財産の維持、増加に寄与した者がいる場合、特別寄与料の請求が認められることになりました。
この特別寄与料の請求は、前述の寄与分とは異なるものです。寄与分は相続人にのみ認められる制度ですが、この特別寄与料の請求は相続人以外の親族にも認められる制度です。
相続人でない親族が、被相続人の財産の維持、増加に寄与している場合、その者に一定の権利を与えるという制度です。
特別寄与料の請求が認められるための要件は、次の通りです。
- 相続人以外の、被相続人の親族(六親等内の血族、三親等内の姻族)であること
- 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと
- 被相続人の財産の維持または増加に寄与したこと
以下、それぞれの要件を説明します。
8-1 相続人以外の、被相続人の親族であること
特別寄与料の請求が認められるのは、被相続人の「親族」に限られます。被相続人の財産の維持・増加に寄与していても、六親等内の血族または三親等内の姻族以外の者には、特別寄与料の請求は認められません。
8-2 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと
特別寄与料の請求が認められるためには、その親族が「無償」で被相続人の療養看護やその他の労務を提供していたことが必要です。労務を提供するにつき対価を得ていた場合には、特別寄与料の請求は認められません。
また、「労務の提供」が要件であるため、被相続人のために財産を給付したとしても、特別寄与料の請求は認められません。
例えば、被相続人のために療養看護を行った親族には特別寄与料の請求が認められますが、療養看護費用を支出した親族には、特別寄与料の請求は認められない、ということになります。
8-3 被相続人の財産の維持または増加に寄与したこと
親族が被相続人のために無償で療養看護、その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産が維持、増加している必要があります。
例えば、親族が療養看護を行ったことでヘルパーなどへの介護費用の支払いが減少していれば、被相続人の財産の維持に寄与したといえるでしょう。
上記①から③の要件を満たした場合、その親族は相続人に対して、特別寄与料の請求ができます。ただし、特別寄与料の請求は金銭請求に限られます。不動産等の持分を分けるように請求することはできません。
また、特別寄与料の請求権があったとしても、遺産分割協議に参加することはできません。
なお、特別寄与料の請求をめぐって相続人との間で争いになった場合には、特別寄与料の請求権を有する親族は、家庭裁判所に対して処分を求めることができます。
詳細は弁護士や司法書士にご相談下さい。
9. 寄与分は遺言で決めることができる?

寄与分を遺言書で定めることはできません。遺言書で定めることができる内容は民法で規定されていますが、遺言書で寄与分を定めることができるとする規定は、民法には存在しないのです。
しかし、寄与分を認定する際に遺言書の内容が判断材料の一つとなる可能性はあります。
そこで遺言書に、寄与分を与えるべき具体的事情や、それに基づく寄与分の割合を詳細に記載しておくと、寄与分の認定に影響を与える可能性があります。
もっとも、遺言書には遺贈することや、遺産分割の方法を記載することができますので、寄与分を考慮した遺贈などを記載してもよいでしょう。ただし、遺贈に対しては他の相続人による遺留分侵害額請求が認められてしまいます。
ところが、寄与分に対しては遺留分侵害額請求が認められない、という利点があります。
そこで、遺言書に寄与分を考慮した遺贈や分割方法を記載したうえで、その遺贈や分割方法が寄与分を考慮したものであること、及び寄与分を与えるべき必要性と具体的事情を詳細に記載しておくという方法も考えられます。
必ずとはいえませんが、寄与分が認定される可能性が高くなると思われます。
そのうえで遺言書に、相続人同士で争いを起こして欲しくない旨、遺言書に従って欲しいとの希望等を記載し、遺言者の意思を汲み取って欲しいことを表現してみてはいかがでしょうか。
 山下晋広
山下晋広司法書士。2000年、司法書士試験合格。2004年、司法書士事務所を開業。所属する東京司法書士会では、調停センター運営委員、広報委員を担当。大学では文学部にて東洋哲学を学び、博物館学芸員を志しつつも、諸事情にて転身。現在、司法書士として研鑽を積む。主な業務は相続手続・不動産登記手続・企業法務・成年後見業務。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。