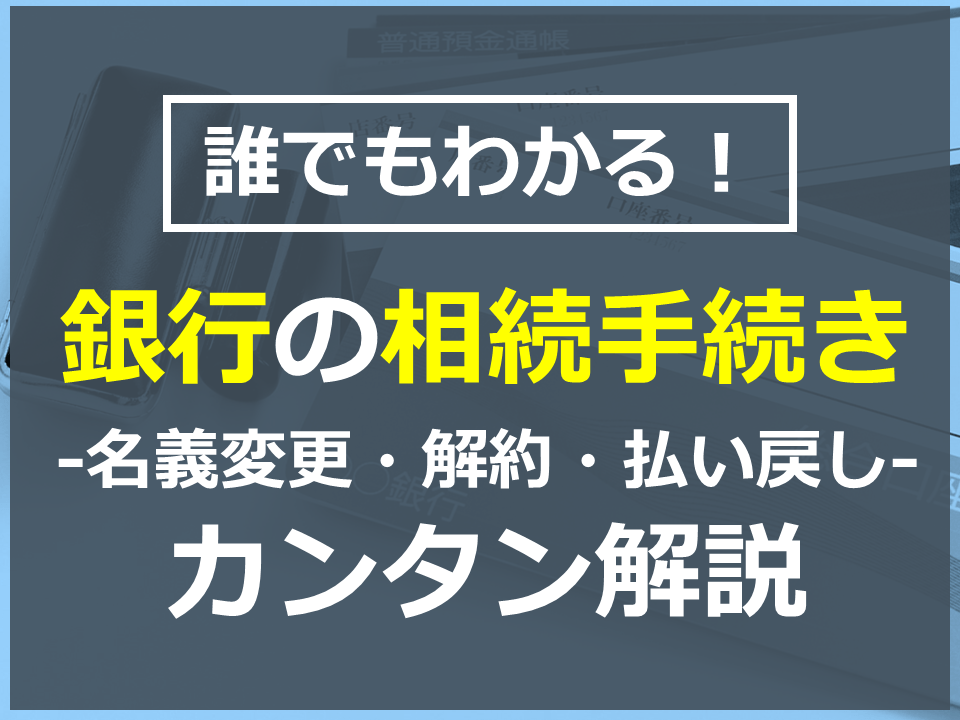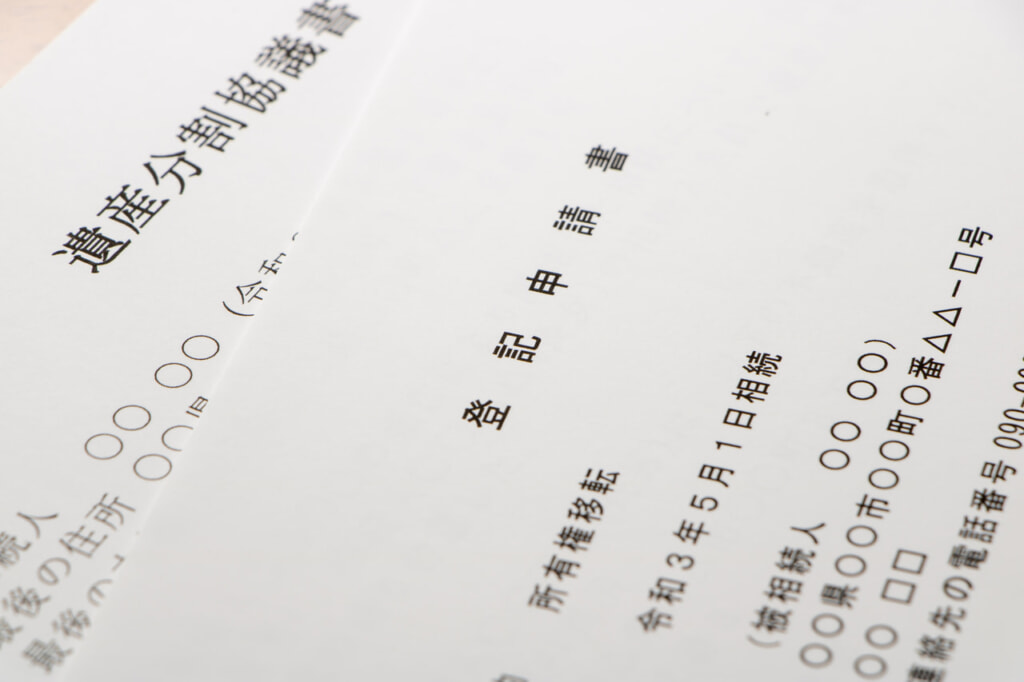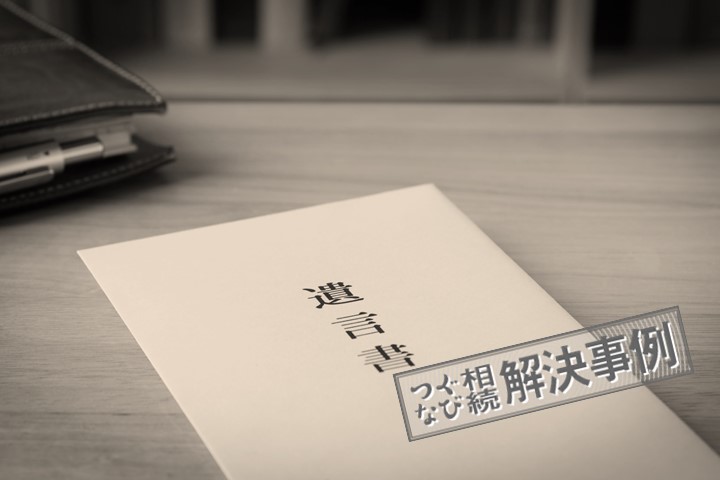世の中には、様々な電子マネーの種類があります。
用途別に使い分けている人もいて、キャッシュレス決済が浸透してきた現代では、何かしらの電子マネーを使用している人が多いです。
金額を入金して使うタイプの電子マネーを亡くなった人の持ち物から見つけた場合、電子マネーは相続の対象になるのか、また残高を引き継ぐことはできるのでしょうか?
ここでは、電子マネーを相続できるのか、手続きの方法などと合わせて解説していきます。
目次
1. 電子マネーとは?
電子マネーとは、電子データで行う決済サービスの1つです。
デジタル化した現金を通信して支払いを完結する方法となります。
クレジットカードと同じものだと間違われる場合もありますが、クレジットカードは一度クレジット会社が金額を立て替えて支払い、その後まとめて請求する方法です。
使い過ぎないようにしたいと考える人や、現金払いと同じ感覚で使いたいなら、電子マネーの方がクレジットカードよりもハードルが低くて取り入れやすくなります。
このような特徴がある電子マネーはいくつもの種類がありますが、主に4つに分類できます。
・交通系
主に電車やバスなどで使用できる電子マネーです。
Suica、PASMO、はやかけんなど地域性のある名前も多いです。
電車やバスに乗る際にきっぷを買う必要がないだけでなく、駅のコンビニや自動販売機などでも使用できます。
・流通系
コンビニやスーパーでも利用できる電子マネーです。
nanacoやWAONなどが該当し、コンビニやスーパーの買い物で使用できます。
キャッシュレスの買い物が可能なだけでなく、独自のポイント制度もあります。
・クレジットカード系
クレジットカード系は、クレジットカードと連動しているもので入金する手間がなく、後日クレジットカード会社からまとめて請求される電子マネーです。
QUICPay、iDなどが該当します。
・QRコード決済系
QRコード決済系は、スマートフォンを通じた電子マネーです。
入金して使用するものもあれば、クレジットカードとの連携や携帯電話の利用料金との合算、ポイントを利用料金に加算できるなど利用者側の自由度が高いのもポイントです。
PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、d払いなどがあります。
1-1 ポストペイ(後払い)型
さらに電子マネーの支払い方法にも3つのパターンがあります。
ポストペイ(後払い)型は、登録時にクレジットカード情報の入力が必要で、電子マネーの利用額とクレジットカードの利用額を合算して引き落とします。
事前に入金するタイプではないので、残高が不足して使用できないという心配もありません。
その代わり、クレジットカードの請求と合算されてくるので使いすぎないような注意が求められます。
1-2 プリペイド(前払い)型
電子マネーの主流の支払い方法がプリペイド(前払い)型です。
自分自身で使う分だけ電子マネーに入金するタイプで、残高分のみが使用できます。
入金した分しか使えないので、使い過ぎてしまう心配もありません。
クレジットカードとの連携がないので、誰もが気軽に持ちやすい電子マネーとなります。
先払い型なら現金払いと同じような感覚であり、後払い型やクレジットカードのような事前審査も不要です。
1-3 デビット(即時払い)型
デビット(即時払い)型は、電子マネーを使用したのと同時に銀行口座から支払い金額が引き落とされるものです。
口座に残っている金額が使用できる金額になるので、残高不足になってしまうと決済もできません。
2. 電子マネーは、チャージされた残高があれば相続できる
同じ電子マネーに分類されていても、電子マネーの種類や支払い方法に違いがあることが分かりました。
もし家族が電子マネーを使用していて、その後亡くなった場合は家族が電子マネーを相続することはできるのでしょうか?
ここでポイントになるのが、電子マネーの支払い方法です。
ポストペイ(後払い)型、デビット(即時払い)型は支払いをして初めて決済される仕組みなので相続の対象にはなりません。
一方のプリペイド(前払い)型の電子マネーであれば、事前にチャージされた残高が残っている場合のみ相続の対象になります。
各社の規約によって変わる部分があるかもしれませんが、基本的には相続の対象になるということです。
電子マネーは現金を電子化したものであり、取扱方法も現金と同じです。
各会社の規約によって現金に出来ない場合もありますが、時間のロスやポイント還元なども可能なので確認すると良いでしょう。
3. 相続の手続き方法について
電子マネーは、日本銀行のホームページでも電子的なやりとりを通じた決済方法としています。
クレジットカードとは別のものと認識されているため、相続に関しても手続きが必要です。
しかし、電子マネーの中には一部認められていないものがあります。
相続可能な電子マネーかどうか事前に確認しておきましょう。
3-1 相続の対象か問い合わせる
まず、電子マネーそのものが相続の対象になっているかどうかを確認します。
基本的には、相続を始める時点で残高があるかどうかが判断の基準です。
また各社の規約によっても変わってきますが、多くの所で相続人によって承継可能もしくはチャージ分は家族の使用を黙認しています。
実際にSuicaでは、相続人によっての承継が認められていて、死亡した会員の払いもどし手続きの方法がホームページに記載されています。
この方法で手続きを済ませると払い戻しが可能です。
楽天Edyでは、残高を必ず使用してからの破棄を求めています。
流通系のnanacoは、契約者が亡くなった後はチャージ残高が無くなり、利用もできないと明記してあります。
このように、同じ電子マネーでも各社によって対応が変わってくるため、利用方法や規約の確認、また問い合わせるなどの方法を取るようにしましょう。
電子マネーは入金額が比較的少額であり、相続可能かなどの手続きや書類での変更が面倒に感じるかもしれません。
しかし、電子マネーに紐づいているクレジットカードなどがある場合は、本人が亡くなった後に使用すると不正利用とされてしまいます。
金額に関わらず、電子マネーは相続の対象であると認識して問い合わせる必要があります。
3-2 遺産分割協議書などを作成する
電子マネーに関しての問い合わせが済んだら、遺産分割協議書などの作成を行います。
遺産分割協議書は、相続できるものに関して預貯金などと同じように誰が相続するのかという遺産分割協議を行った後、結果をまとめたものになります。
遺産分割協議書は、銀行などで預金の相続手続きや不動産の相続登記、相続税の申告時などに提出を求められる場合がある書類です。
相続人同士の間に起こりうるトラブルも防げるので、遺産分割協議書などの作成は必要となります。
3-3 払い戻しなどの手続きを行う
相続する電子マネーがあり、さらに遺産分割協議書などを作成したら、各社に連絡して払い戻しの手続きを開始します。
もし、遺言書などがない場合は遺産分割協議書の他に以下の書類が必要です。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続する人の住民票
・相続する人の本人確認書類
・被相続人の出生まで確認できる連続した戸籍や除籍、原戸籍謄本
・被相続人が最後に住んでいた住所が分かる住民票の除票や戸籍の附票
これらの書類によって、電子マネーなどの財産を含めた相続を相続人全員が納得していると証明できます。
しかし、全ての電子マネーにおいてこれらの書類を用意するとは限りません。
例としてモバイルSuicaでみてみると、会員の死亡が証明できる公的機関が発行した書類や返金を受ける人の確認書類を必要としています。
そのため、銀行などの比べると比較的簡単な書類の提出や手続きで終わる可能性が高いです。
4. PayPayの規約変更に注目!
電子マネーが普及している反面、相続に関して各社の対応は分かれてしまうことが分かります。
少し前まではQRコード決済サービスのPayPayも、利用者が亡くなった場合はその時点で残高が無くなると規約に記載されていました。
その後、上限金額を500万円から100万円に変更しましたが、もしかしたら500万円近い資産を相続できなかった人もいたかもしれません。
このような状況を踏まえたのか、現在のPayPayでは利用規約の改定が行われ、PayPayマネーやマネーライトの相続や承継が認められるように変更されました。
これにより、PayPay利用者がアカウントに残高を残した状態でも相続人の手続きによって払い戻しができるようになったのです。
PayPayのようなオンラインサービスでは、事前に相続人などが資産の残高確認など状況を把握するのが困難です。
特にスマートフォンにセキュリティ対策としてロックをかけていた場合、家族であっても解除できない可能性が高いでしょう。
このような場合、契約者以外がログインしてしまうと不正アクセス禁止法に触れる可能性がありますが、相続人が亡くなった人のサービスにログインしたり、PayPayの残高を受け取ったりしても相続財産となるので法律的な問題にはなりません。
PayPayでは規約改定が行われてから、身元の確認ができた遺族を対象に払い戻しに応じるようになりました。
亡くなった人のPayPay残高の払い戻しは、以下の書類が必要です。
・死亡が確認できる書類(除籍謄本や戸籍謄本)
・請求者が登録者の相続人だと分かる戸籍謄本一式
・法定相続情報一覧図(法務局が発行した認証紋付きの書類の原本)
・登録者の携帯契約書もしくは請求書(亡くなった人の名前と番号が記載されている書類のみ有効)
・問い合わせ者の本人確認書類
これらの書類をPayPayカスタマーサポートに送付すると手続きが行われます。
手続き方法の不明点は、事前に問い合わせすると安心です。
5. まとめ
電子マネーには様々な種類があり、支払い方法も分かれています。
そのため、電子マネーの支払い方法にとって相続可能な資産かどうかも変わってくるでしょう。
直接的な現金のやりとりはないものの、決済方法としては確立しているため、きちんとした資産として認められています。
資産である以上、相続の対象になるので正しい方法で手続きを済ませることが大切です。
電子マネーの残高が資産になるかどうかは、各社によって変わります。
亡くなった時点で残高が残らないものもあれば、請求できるものもあるので事前に問い合わせておくと安心です。
死亡後の名義変更・解約手続きの関連記事
この記事の監修者
 工藤 崇(くどう たかし)
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。