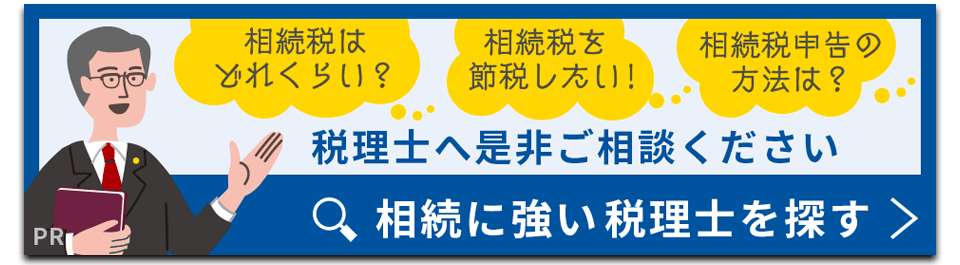相続税の申告時に、被相続人の預金から引き出した現金を申告すべきか悩む方も多いです。相続税の申告時には、現金も申告が必要なのでしょうか。
そこで今回は、相続税の申告時には、現金も申告が必要か、現金を申告しなかった場合はペナルティーがある のかについて解説します。
目次
1. 相続税の申告時には、現金も申告が必要?
相続開始直前に引き出した現金で相続開始時点で手許に残っていた現金は相続税申告書に計上する必要があります。
税務署は相続税申告後に被相続人の預貯金の過去の移動履歴を5年分は調べますから、相続が発生する前に引き出された現金の行方を厳しくチェックするからです。
1-1 相続税に含まれる「手許現金」とは
手許現金(手元現金)とは、相続開始時点で預金口座等に入っていない手持ちの現金のことを指しています。
具体的には、タンス預金、金庫の中の現金、貸金庫の中の現金、財布の中の現金、亡くなる直前に引出した現金などが該当します。
1-2 相続開始時に引き出した現金もタンス預金も申告が必要
タンス預金はもちろん相続税の申告が必要です。
まれに預金の残高証明書に記載されていなければ相続税はかからないと勝手に判断して、亡くなる直前に多額の現金を引き出す人も見受けられますが、手許現金として相続税の対象になりますので、これも含めて相続税の申告をしなければなりません。
【関連記事】タンス預金と税務調査ついてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の税務調査とは?調査内容や対象者をわかりやすく解説
>コラム:タンス預金は税務調査でバレる?調査に入られやすいケースやリスクを解説
>コラム:相続税の税務調査とは?その時期についても詳しく解説
2. 相続税の申告時の現金の計算方法
相続税の申告時の現金の計算方法はどのようにすればよいのでしょうか。
ここでは、葬儀費用として現金を使った場合と、相続開始前に引き出した現金を生活費で使っていた場合について解説します。
2-1 葬儀費用として現金を使った場合
葬儀費用として引き出した現金は、当然のことながら葬儀のために使います。そのため、相続の発生した瞬間においては現金で残っていたことになります。
相続税の計算上は、たとえば預金800万円、手許現金200万円の合計1,000万円の財産を計上したうえで、葬儀にかかった200万円の費用をマイナスとして、相続財産1,000万円から控除します。
この事例において相続税の対象となるのは、600万円+200万円-200万円=800万円になります。
また仮に相続開始の直前に現金を引き出していなかったのであれば、預金残高は1,000万円であり、1,000万円の預金と葬儀費用200万円を申告すれば相続税の課税対象は800万円となることから、やはり相続開始直前に引き出した葬儀費用を申告しなければ整合性がとれなくなってしまいます。
この点について税務調査に遭遇した場合には、調査官は徹底的に追及します。
相続開始の直前に行われた現金引き出しの経緯、被相続人の相続開始の直前の状態、意識はいつまであったのか、預金通帳やカードの管理は誰に任せていたのかなど根掘り葉掘り質問攻めをしてきます。
実際には相続税の計算から引くことができるからという理由で手許現金を計上しないまま申告してしまうと、調査官にとって格好の追徴課税ポイントになっているのです。
相続開始の直前に引き出した現金の使途については税理士に相談しましょう。
2-2 相続開始前に引き出した現金を生活費で使っていた場合
相続開始前に引き出した現金を生活費等で使った金額については、手許現金の金額からマイナスすることができます。
たとえば、乙さんが相続開始前にATMで200万円の現金を引出し、実際に父に相続が発生する前に、生活費等に80万円を使っていたとします。
この場合、相続が発生した時点における現金は、200万円から80万円を引いた120万円ということになります。
この金額を手許現金として申告すれば全く問題ありません。この場合、生活費等で使った領収書などの証拠はなくても問題ありません(生活費の領収書を全て残している人などおりませんので)。
ただし、葬儀費用との整合性について税務署から追及されることがあるので注意しましょう。
例えば、相続開始直前に200万円引出して、相続が発生する前に生活費で全て使い切っていたと調査官に主張したとします。
そうすると、調査官は次のように質問してきます。
「それでは葬儀費用は誰がどのように支払ったのか詳細に教えていただけますか?」
「相続開始前の引出し現金は使い切っていたのであれば、相続人の誰かが自分の預金からお金を引出して葬儀屋に支払ったことになりますよね?その出金の履歴を確認させてください」
この質問に対して、「私は昔からタンスに現金をしまっているんです。そこから払いました」などと答えると、「タンス預金があるんですね?そのタンス、今すぐ確認させてください」と事態はさらに悪化します。
このような事態を避けるためにも、領収書の提出が求められないからといって嘘はつかないのが賢明です。
3. 相続税の申告時に現金を申告しないとバレる?バレない?
相続税の申告時に現金を申告しないと、税務署にバレてしまうのでしょうか。実は税務署は現金の流れを細かくチェックできるためバレる可能性が高いです。
ここでは、相続税の申告時に現金を申告しないとバレる理由を解説します。
3-1 税務署は過去10年分の預貯金の履歴を確認している
税務署は、個人収入や資産の動きを「国税総合管理(KSK)システム」で把握しています。
このシステムから税務署は「個人がどれだけ収入を得て資産を保有し税を納めているのか」について過去10年分の預貯金の履歴を照会することができます。
そのため生前の収入が多いのにもかかわらず相続税額が少ない場合、「資産をどこかに隠している可能性がある」と疑われてしまうことになるのです。
3-2 被相続人の財産を把握しているため、手渡しで貰っていた金額やタンス預金も推定できる
税務署は預貯金の照会によって、手渡しで貰っていた金額やタンス預金についても容易に推定することができるのです。
ちなみに相続が開始して5か月が過ぎたあたりに、税務署から「相続税申告についてのご案内」という書類が届くことがあります。
これが怖いのはKSKシステムによる「相続の発生しそうな家庭」という選定を経ていることです。これが届くと税務署からマークされているというメッセージであると認識すべきです。
税務署の影におびえながら脱税行為をするよりも、合法的な相続税対策をするほうが金額的にも精神的にもよいでしょう。
タンス預金で相続税を脱税しようとしても、金額はせいぜい数百・数千万円です。
一方小さい孫が何人かいれば、教育資金の一部贈与(1500万円×孫の数)の制度を利用するだけでタンス預金脱税を遥かに凌ぐ節税効果を上げることができます。
これ以外にも、保険料の支払いが一括である生命保険(一時払い終身保険)に加入すれば「500万円×相続人数」という制度を利用することもできます。
タンス預金脱税課税はリスクが大きい割には減らせる税額は小さいのです。税務署にバレる・バレないにかかわらず、タンス預金脱税を選択すべきではありません。
3-3 現金であっても高確率でバレるため、相続税対策で現金を隠すのは得策ではない
このように現金であってもバレる可能性・確率が高く、その後税務調査が入りタンス預金などの存在が発覚すると、申告しなかった相続財産の分の税金を支払わなければなりません。
追徴課税は、通常の相続税率よりも高く設定されているために、相続税対策と称して現金を隠すのは決して得策ではなく、正直に申告したほうが無駄な税金を支払わずにすみます。
【関連記事】相続税の税務調査についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の税務調査とは?調査内容や対象者をわかりやすく解説
>コラム:相続税の税務調査とは?相続税の税務調査や時期を詳しく解説
>コラム:相続税を申告しないと【税務調査が来やすい?】無申告時の罰則も解説
4. 相続税の申告時に現金を申告しなかった場合はペナルティーがある
相続税の申告時に、現金を申告しなかった場合はペナルティーが課せられるので必ず申告するようにしましょう。
ここでは、申告漏れが疑われる際の税務調査と、修正申告について解説します。
4-1 申告漏れが疑われる場合は税務調査となる
タンス預金など現金を申告せず申告漏れの疑義がある場合には税務調査が入ることになります。
税務調査では、預貯金のため通帳なども調べられます。この際、被相続人の通帳だけでなく、相続人の通帳も含め、過去10年間遡って調べられます。
高額な出金額があれば、引き出したお金をタンス預金として隠している可能性が高いといえますが、その目安とされているのが100万円以上の出金額がある場合です。
引き出したお金の使い道をしっかりと説明することができれば問題ありませんが、きちんと説明できず疑いをかけられると、税務署が実地調査を行うことになります。
税務署では全国の国税局と税務署をネットワークで結ぶ「国税総合管理(KSK)システム」によって申告・納税の実積などの情報を一元的に管理するシステムを2000年から運用しています。
日本全国すべての納税者の申告書がこのシステムで把握され、加えて資産の購入・売却履歴などの個人情報も蓄積されています。税務署はこれらの情報を駆使して税務調査の対象を選定しているのです。
KSKシステムに加えて税務署では対象者を選定した上でさまざまな税務調査を行い、タンス預金などの申告漏れしている財産を調査していきます。
相続税の税務調査には強制調査と任意調査がありますが、一般的な税務調査では「任意調査」が行われます。
任意調査とは納税者の同意を得て行われる調査で、基本的に税務調査前には事前通知があります。
任意といえども納税者には受忍義務があり、調査を拒否すれば罰測が適用されます。任意調査には段階として準備調査と実地調査がありますが、納税者に直接かかわってくるのは実地調査です。
実地調査においては、相続人への聴き取りをはじめ、相続人や被相続人の通帳や印鑑の確認、家具の中などを調査されます。
また「反面調査」が行われ、取引銀行や証券会社、生命保険会社、関係金融機関への確認作業などの情報を聴き出すこともあります。
4-2 税務調査となった場合は修正申告や追徴課税の対象となる可能性が高い
相続財産となるべき現金の存在について、相続税の申告時に気付かず後から発覚した場合には、気付いた時点でただちに税務署に対して修正申告をする必要があります。
現金であれば多少申告漏れがあったとしても税務署には気付かれないと思うかもしれませんが、税務署は現金の申告漏れが多発しているため、税務調査では厳格に確認されます。
このため、税務署に見つからずにやり過ごすことはできないと考えておいた方がよいのです。
自発的に修正申告をせず、税務調査があって初めて修正申告を行うような場合、延滞税や過少申告加算税のほか、意図的な財産隠しと認められた場合には重加算税も課されるなど、納税額が多額になります。
したがって、相続税の申告後にタンス預金などを見つけた場合にはそのままにせず、すぐに税務署に対して修正申告をする必要があるのです。
【関連記事】相続の追徴課税についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:相続税の追徴課税とは?内容や計算方法、時効の時期まで解説!
ちなみに亡くなった人のタンス預金を見つけた場合に、他の相続人に隠して独占してしまおうという思いが頭をよぎるかもしれません。
しかし、これも後で発覚したときに他の相続人との関係で横領という犯罪に問われる可能性があるため、決してすべきではありません。
そもそも、相続後に税務調査が入った場合には、前に説明したようにタンス預金の存在は高い確率でバレてしまいます。
このとき、同時に相続人にも現金が隠されていたことが判明してしまいますので、他の相続人にばれないように独占するということは難しいのです。
4-3 相続税の申告後に現金に気付いたら自主的に修正申告を行うのがおすすめ
相続税の申告をした後に現金の申告漏れがあることに気づいた場合に、税務調査が入る前に自発的に申告をすれば加算税が免除されますので、先手を打って自主的に修正申告をすることをおすすめします。
相続税における手許現金について二つの重要なポイントがあります。
一つ目は、引き出したお金の残金は「手元現金」として忘れずに申告すること。
二つ目は、支払いの記録をきちんと残しておくということです。
支払いの記録をきちんと残しておくのは何も税務署のためだけではなく、他の相続人にキチンと説明できるようにしておかなければならないからです。
相続トラブルを回避するためにも、被相続人のお金の管理を行っている場合は、堂々と説明できるような証拠(領収証など)を残しておきましょう。
5. 相続税の申告時に現金の計算に悩んだら税理士に相談
相続税の申告時に現金の計算に悩んだら税理士に相談しましょう。現金を加えて正しく計算したら実は基礎控除額を超えていた、ということもあります。
この状況を税務署から指摘されたら、相続税に加え、無申告加算税や延滞税を納めることになるのです。
すべての財産を洗い出して申告の要不要を判定するのは、非常に大変です。そして、相続税の申告は相続開始を知った日以後10か月以内と決まっています。
預金を含む相続財産の申告・納税作業は、一般の人に荷が重すぎるかもしれません。預金の扱いに悩んだり、その計算の仕方、申告の要不要の判定などに悩んだり困ったりしたら、ぜひ相続税に強い税理士に相談しましょう。