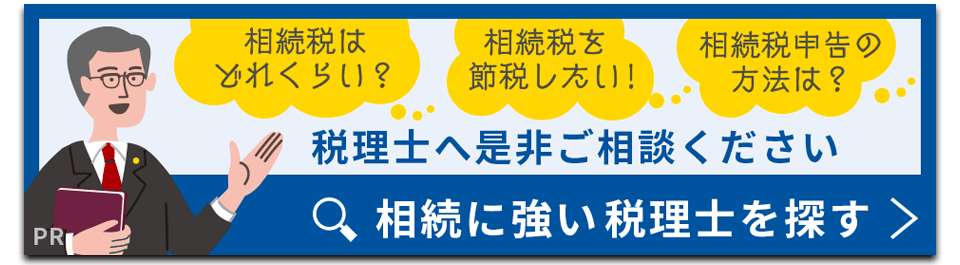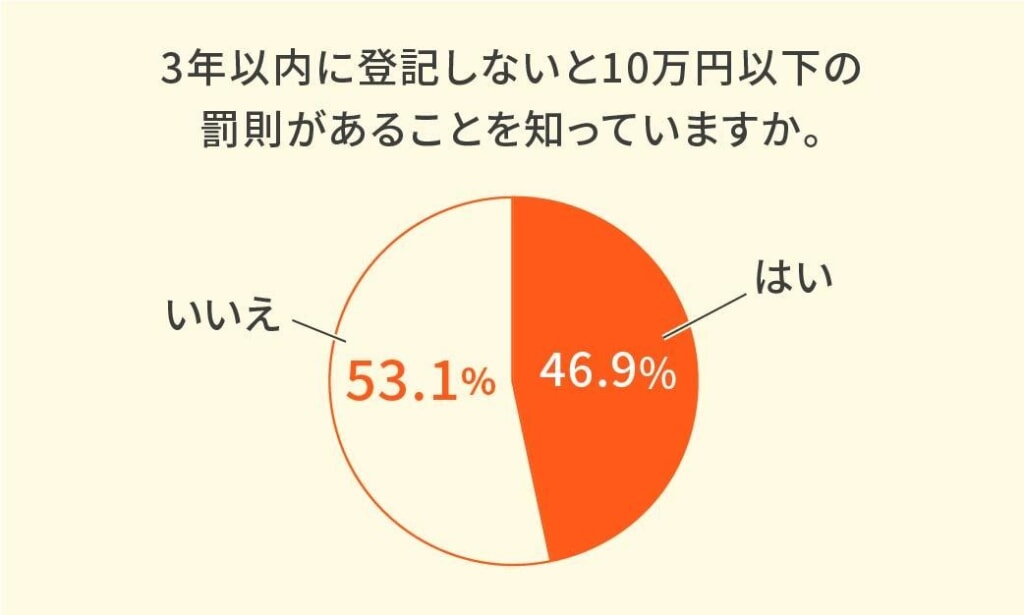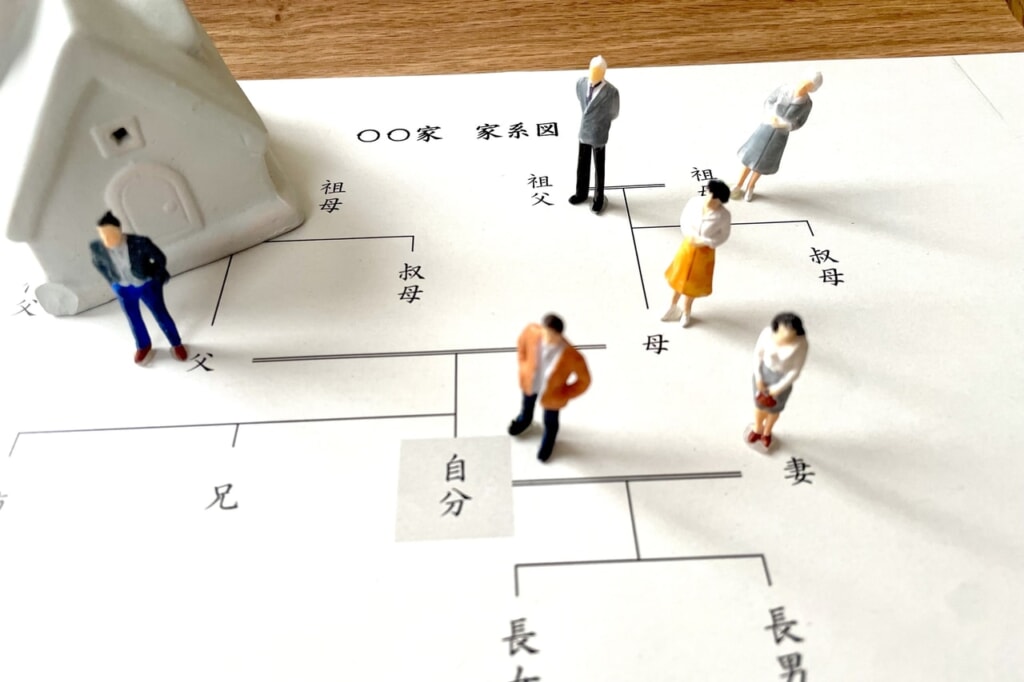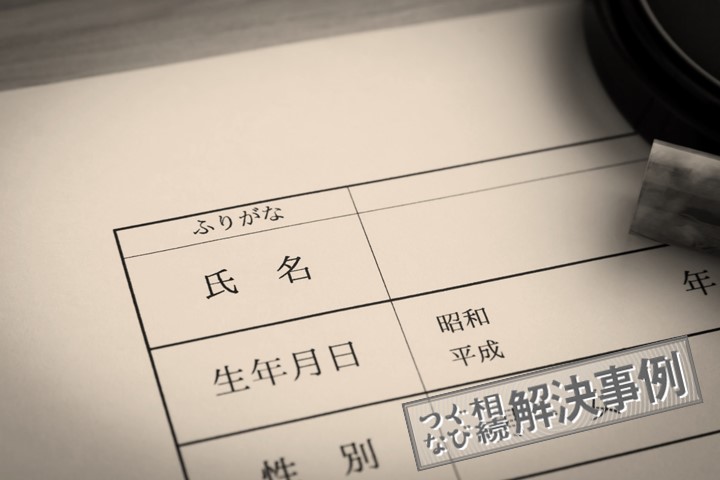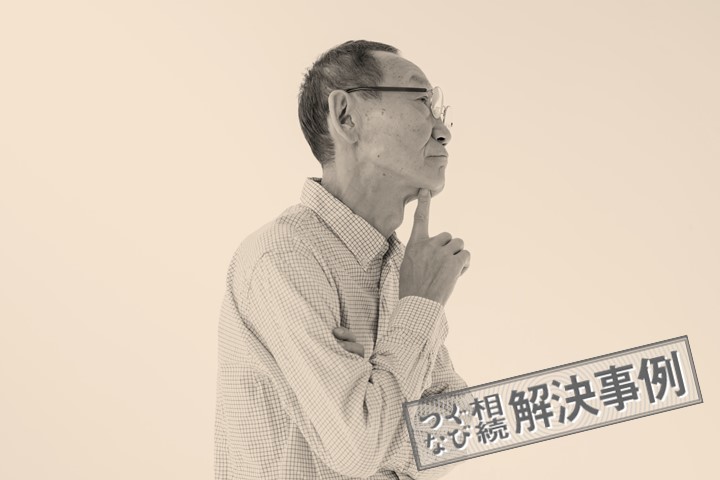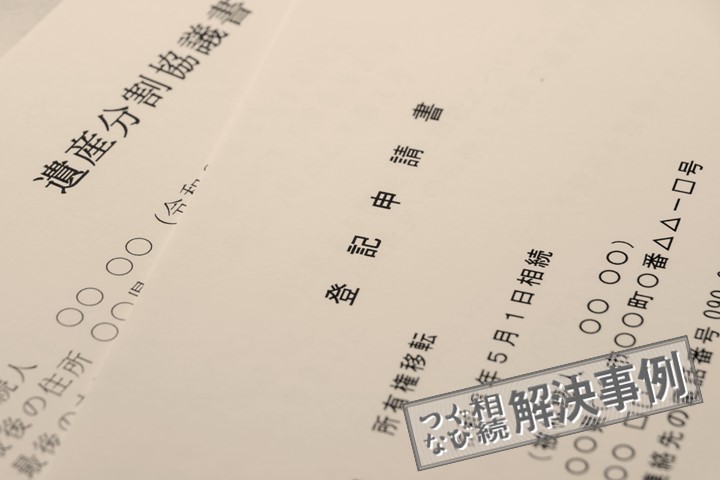土地の相続税評価額は、路線価もしくは固定資産税評価額を基に計算します。
固定資産税通知書さえあればおよその評価額を知ることができます。
基本的な評価額の計算方法をマスターしたうえで、相続税評価額のマイナスにつながる土地の特徴や制度も知っておけば節税への第一歩になります。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
「相続税評価額」とは?時価になるって本当?
相続税評価額は相続税を割り出す際に基準となる価格です。
相続税評価額が高く評価されるほど支払う相続税が増えますので、私たちとしてはなるべく低く評価されてほしいところです。
相続税法によると相続税評価額は「時価」によるとされています。
時価と聞くと、不動産を売買する際の査定価格を思い浮かべますが、相続税評価額とは違います。
世間一般の時価とはまた異なる、相続税を算出するために用いる独自の価額と考えるほうがわかりやすいです。
相続税評価額は相続税を計算するために使う独自の概念であり、世間一般でイメージされる時価とは別物だととらえましょう。
土地の相続税評価額の計算方法
土地の正確な相続税評価額は予想は、土地の形や周辺環境により異なるため、税理士でないと難しいのが正直なところです。
自分で相続税評価額を計算する時のポイントは、計算の際、路線価方式と倍率方式のいずれかの方法を用いる点です。
▼分かりやすい相続税評価額の計算方法(土地の場合)
路線価方式の計算式……路線価×土地の面積(㎡)
倍率方式の計算式……固定資産税評価額×評価倍率
路線価方式
路線価方式と倍率方式の2つの計算方式がありますが、路線価方式で計算するのが原則です。
路線価方式は路線価に土地面積を乗じて算出します。
路線価は国税庁のHPで調べることができます。ご自身の土地の路線価を調べてみましょう。
例えば170Dと記載されていたら、170円に千円を掛けたもの、つまり17万円が路線価です(アルファベットは借地権割合を示しますが後で解説します)。
路線価格がわかったら、あとは路線価に土地の面積を乗じるだけです。
土地の面積は固定資産税の納付書に記載されています。現況地籍が100㎡なら、17万円(路線価)に100を乗じた1,700万円が概算の相続税評価額です。
倍率方式
路線価方式での計算が原則ですが、路線価が記載されておらず、市区町村別の「評価倍率表」に別途記載のある住所もあります。
その場合は倍率方式で計算しますが、こちらは計算が簡単です。
固定資産税通知書記載の固定資産税評価額に倍率を乗じるだけです。
倍率は路線価と同じく国税庁のHPで確認できます。
固定資産税評価額が1,000万円で評価倍率が1.1であれば、1,000万円×倍率1.1=1,100万円が概算の相続税評価額です。
倍率方式が採用される、市街地から離れた郊外では路線価が記載されてない場合が多いです。
その際は路線価方式ではなく倍率方式で計算しましょう。
借地権の場合
路線価方式あるいは倍率方式を用いた評価額は、所有権を相続した時の「自用地」の価格です。
相続したのが土地の権利が「借地権」となっている場合は、以下の計算を追加で行うことで評価が下がります。
自用地の評価額 × 借地権割合
借地権割合は住所によって異なり、30%~90%の範囲で定められます。
路線価図を見ると、採用する借地権割合はアルファベットで表記されているのが一般的です。
相続税路線価と固定資産税路線価は異なる
相続税路線価と固定資産税路線価は異なり、また売買価格とも別物として扱われます。
違いは簡単で、相続税路線価(評価倍率)は相続税、固定資産税路線価は固定資産税の算出を目的とします。
税金計算を目的として使われる独自の価額基準である点は共通しますが、対象となる税金の種類が違います。
評価額の目安は、一般的な市場価格を100%とすると、相続税路線価はその80%、固定資産税路線価は70%です。
注意したいのは相続税路線価も固定資産税路線価も一般的な土地の取引価格よりも低く見積もられる点です。
土地の相続税評価額が800万円だとしても、実際に売りに出した時の価格はそれよりも高額になるのが通常です。
土地に家・家屋などの建物がある場合は?利用状況別の相続税評価額
更地ではなく土地にある場合、利用状況により相続税評価額の考え方は変わります。
自己が使用する家屋であれば固定資産税評価額をそのまま相続税評価額と考えますが、賃貸経営で他人に住ませている場合は、一定の方法で評価を下げるような計算をします。
家屋の場合
土地の上に立つのが家屋の場合は「固定資産税評価額×1.0」で計算します。
ごく簡単には、市区町村の課税台帳及び送付される納税通知書に掲載の評価額を、そのまま相続税評価額と捉えます。
貸宅地の場合
借地権等が上に存する宅地は、税法上「貸宅地」となります。
簡単に言えば、家を建てるための土地につき、地主として賃貸借契約を結び他人の家が建っている(もしくは今後建つ)状態で相続したケースです。
貸宅地の評価方法は以下の通りです。
自用地の評価額 ×(1-借地権割合)
自用地の評価額が1,000万円で借地権割合が60%の場合、400万円が相続税評価額になります。
貸家建付地の場合
相続した土地の上にアパートを建てて大家になっている場合、土地の扱いは税法上「貸家建付地」となります。
貸宅地と同じく所有者が自ら使用することはないものの、土地・建物共に被相続人に所有権が属する点で異なります。
貸家建付地の評価では、空室率とも言い換えられる「賃貸割合」を考慮します。
貸家建付地の賃貸割合=被相続人の死亡時に賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計
上記の方法で賃貸割合が計算できたら、下記の式を使って貸家建付地の評価額を算出できます。
自用地の評価額 ×(1-借地権割合×30%×賃貸割合)
マンションが建築されている場合
マンションが建築されている土地の相続税評価額は貸家建付地と同じです。
すなわち、被相続人が亡くなった日の賃貸割合を考慮し、以下の式を用いて評価できます。
自用地評の価額 ×(1-借地権割合×30%×賃貸割合)
遊休地がある場合は、生前に賃貸アパートやマンションを建設して貸家建付地とすることで、土地の相続税評価額が下がります。
駐車場にしている場合
駐車場を運営しているのが土地の所有者自身か否かで結論は変わります。
土地所有者が自ら土地を駐車場として利用している場合、自用地として路線価方式または倍率方式で算出した相続税評価額を用います。
コインパーキング経営や、アパート等に併設される入居者専用の駐車場は、貸宅地と同じ計算式で評価できます。
私道にしている場合
相続した宅地等につき私道に該当する部分は、道路でない場合の30%相当額で評価します。
近隣住民のための専用道路ではなく、不特定多数の人間が行き来しているケースでは、公共の用に供するものとして評価額はゼロになります。
小規模宅地等の特例が適用できる場合
相続した土地に小規模宅地等の特例を適用できる場合、自用地なら80%、貸宅地や貸家建付地なら50%の評価減があります。
上記特例を適用できるのは、配偶者・その他同居家族・別居中の持ち家のない家族が相続して住み続ける場合や、賃貸事業を継いで営業を続ける場合に限られます。
生前対策や相続直後では、適用可否をきちんと確かめておきましょう。
相続税で土地の相続税評価額が減る場合
算出した土地の評価額は、形状や周辺環境により補正がかかります。
利用価値の低い土地は、状況を考慮し一定の方法で下方修正されるのです。
不整形地の評価
不整形地とは、方形ではないいびつな形の土地を差します。
典型的なのは、隣接する二面が接道しつつも角が切られたような土地(角地/隅切り地とも)や、三角地、袋地(旗竿地)です。
こうした土地は、採光性や建築設計、道路の出入りの難しさ等から、一般に周辺の土地と比べて利用価値が低いとされます。
相続した土地が不整形地である場合の評価額は、所在する地区と形状の歪さに応じた「不整形地補正率」を用い、最も補正が強い場合で整形地価格の70%となります。
間口が狭い宅地・奥行が長大な宅地の評価
縦横比のバランスが悪い土地は、間口狭小補正率もしくは奥行長大補正率によって評価が下がります。
補正が認められるのは、間口距離8m未満、あるいは奥行距離が間口距離の3倍以上ある場合です(いずれも普通住宅地区の場合)。
土地の相続税評価額の計算や節税方法は税理士に相談
価値の高さゆえ不動産の相続税評価額は相続税の申告に大きな影響をおよぼします。
路線価と土地の面積がわかれば一般の人でもおよその評価額は検討がつきますので、一度ご自身で調べてみると良いでしょう。
そのうえでご自身の土地に相続税評価額を下げられる要素がないか考えてみましょう。
相続財産の減額は税務署が積極的に案内してくれるわけではなくこちらから申告しなければいけません。
土地がからむ相続税評価はうまく申告すると節税につながるポイントも多いです。
反面、複雑な計算が求められることもあり、申告書には図面の作成が必要になる場面もあります。
節税のために相続税評価額をできる限り下げたいと希望する方は税理士への相談ををおすすめします。
まとめ
土地の相続税評価額の算定には、
- 小規模宅地等の特例
- 私道扱いによる相続税評価額の減額
- 不整形地による相続税評価額の減額
など節税方法につながる要素がたくさんあります。
土地の相続税評価を効率よく下げることができれば相続税の申告自体が不要になるケースもでてきます。
土地を相続する際の節税につながるポイントを税理士は熟知していますので、気になる方は相談してみると良いでしょう。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。