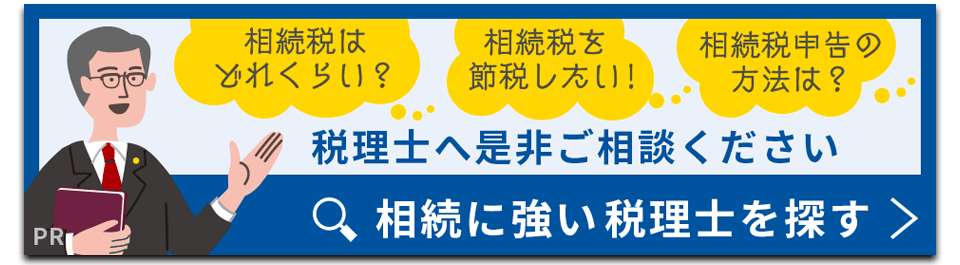相続税とは、亡くなった家族の財産を承継した相続人・受遺者に課される税金です。相続財産の総額や相続人の数などによって、相続税額は変化します。
相続税申告には期限が設定されているため、計画的に申告の準備をすることが大切です。相続税の課税対象財産や計算方法、さらに生前贈与を活用した相続税対策など、相続税の基本について解説します。
目次
1. 相続税とは
相続とは、亡くなった家族の財産を、遺言や遺産分割などによって承継することを意味します。相続との関係では、故人を「被相続人」、財産を承継する人を「相続人」(遺言により財産を贈与された場合には「受遺者」)といいます。被相続人が亡くなった時点で、日本国内に住所がある相続人は相続した全財産に、海外に居住していて日本国内に住所がない相続人は、相続した財産のうち、日本国内に存在するものだけに相続税が課されます。
相続税において適用されている超過累進税率によると、相続財産の金額が増えれば増えるほど税率が高くなります。以下の速算表を用いると、超過累進税率に従って相続税を簡単に計算できます。
| 【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 | ||
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁の相続税の速算表をもとに作成
2. 相続税の税額計算の仕組み
相続税の計算をする流れは以下の通りです。
①課税遺産総額の計算をする
課税遺産総額=課税対象財産の合計額-基礎控除額
相続税の課税対象としては、主に以下の財産が挙げられます。
・被相続人が死亡時に所有していた財産
・被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産
・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
・生命保険金
・被相続人の死亡によって支給される退職手当金
など
ただし、以下の財産は相続税が非課税とされています。
・墓地・墓石、仏壇などの祭祀財産
・生命保険金のうち「500万円×法定相続人」までの部分
・退職手当金のうち「500万円×法定相続人」までの部分
など
なお、被相続人の債務や葬儀費用は、課税対象財産から控除します。
上記に従って積算した課税対象財産の合計額から、相続税の基礎控除額を差し引きます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
(例)法定相続人が3人の場合:基礎控除額=4,800万円
基礎控除額を差し引いた結果、課税遺産総額が0円以下となる場合には、相続税が課税されませんので、原則として相続税申告は不要です。
②相続税の総額を計算する
課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分に応じて取得したとみなして速算表を適用し、各法定相続人の相続税額を計算します。その合計額が、相続税の総額です。
(例)課税遺産総額が5,000万円、法定相続人は配偶者と子2人の場合の相続税額
配偶者:2,500万円×15%-50万円=325万円
子1:1,250万円×15%-50万円=137.5万円
子2:1,250万円×15%-50万円=137.5万円
→合計600万円
③各相続人・受遺者の相続税額を計算する
各相続人・受遺者の相続税額=相続税の総額×実際に承継した課税対象財産の額÷課税対象財産の総額-各種控除額
相続税の総額を、実際の相続割合に応じて、各相続人・受遺者に割り当てます。
(例)相続税の総額が600万円で、実際には課税対象財産を配偶者と子2人が3等分して相続した場合
→配偶者・子2人の相続税額は、それぞれ200万円ずつ
なお、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人が遺産等を取得した場合、その人が負担する相続税額は2割加算されます。
その後、以下に挙げるような各種控除を適用して、最終的な各人の相続税額が決まります。
・配偶者控除
・未成年者控除
・障害者控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
など
3. 相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除について、もう少し詳しく掘り下げておきましょう。
相続税の基礎控除は、相続税の課税や相続税申告の要否を左右するボーダーラインです。課税遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税は課税されず、相続税申告も原則として不要となります。
平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除額が5,000万円から3,000万円に引き下げられ、より多くの方が相続税の課税・相続税申告の対象になりました。
そのため、早い段階で遺産等の調査を行い、相続税が課されるのかどうか確かめておくことを推奨します。
3-1 基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。
- 相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
法定相続人とは民法で規定されている相続人のことです。
例えば、法定相続人が3人であった場合、3,000万円+(600万円×3人)で相続税の基礎控除額は4,800万円となります。この場合、課税遺産総額が4,800万円以下であるなら、相続税は発生しません。
課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超過している場合、超過した価額に対して相続税が課されます。
例えば、相続税の基礎控除額が4,800万円で遺産の合計額が1億円であった場合、超過額の=5,200万円に対して相続税が課されることになるのです。
なお、法定相続人が相続放棄をした場合でも、相続税の基礎控除額の計算上は、相続放棄をした人も法定相続人の人数にカウントします。
例えば、3人の法定相続人のうち1人が相続放棄をしたとしても相続税の基礎控除額の計算上は、法定相続人は3人です。したがって、相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
また養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までカウントされます。
例えば、実子1人と養子2人の計3人が法定相続人の場合、相続税の基礎控除の計算上、養子は1人までしか法定相続人の数にカウントできません。したがって、法定相続人の数は2人となるため、相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円となります。
法定相続人とは
法定相続人とは、配偶者と血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹のうち、相続順位が最上位の者)を意味します。法定相続人には、遺産分割協議に参加する権利があります。
実際の相続割合は、遺言や遺産分割協議によって自由に決められますが、相続税の総額を計算するに当たっては、実際の相続割合にかかわらず、法定相続分(民法で定められた法定相続人の相続割合)が用いられます。
血族相続人の相続順位
血族相続人に関しては、民法で以下のとおり相続順位が決められています。
| 第1順位 | 子 |
| 第2順位 | 直系尊属(親など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
例えば子がいる場合は、直系尊属・兄弟姉妹は法定相続人となりません。
子がいなくても、直系尊属がいる場合には、兄弟姉妹は法定相続人となりません。
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、子も直系尊属もいない場合のみです。
なお、被相続人が死亡した時点で、法定相続人である子または兄弟姉妹が、死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、代襲相続によってさらにその子が法定相続人となります。
(例)
・被相続人の死亡時点で、すでに被相続人の子が死亡
→被相続人の孫が代襲相続により法定相続人となる
・被相続人の死亡時点で、すでに被相続人の兄弟姉妹が死亡(子はなし・直系尊属はすでに死亡)
→被相続人の甥・姪が代襲相続により法定相続人となる
4. 相続税額が0円でも相続税の申告が必要な場合がある
相続税額が0円となる場合でも、例外的に相続税申告が必要となる場合があります。
相続税0円でも相続税申告が必要となる例としては、以下の場合が挙げられます。
・小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
・配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
・相続時精算課税制度の適用を受けている場合
4-1 小規模宅地等の特例を適用する
小規模宅地等の特例を利用すると、相続によって承継した自宅用・事業用の宅地等につき、課税価額が50%または80%減額されます。
例えば、故人が居住するために利用していた土地を、同居していた親族が相続してそのまま住み続けるのであれば、小規模宅地等の特例を適用できます。
4-2 配偶者の税額軽減を適用する
被相続人と死別した配偶者の生活を保障するため、配偶者が承継した課税対象財産の総額が、次に挙げる金額のうち大きな金額を超えない場合には相続税が課されないことになっています。
なお金額を超過した場合であっても、超過した分にのみ相続税が課されます。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分
4-3 相続時精算課税制度を利用する
60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子供・孫に贈与する際に相続時精算課税制度を利用できます。この制度を利用することによって、総額2,500万円までの生前贈与につき、贈与税が課税されなくなります。
ただし、相続発生時に相続税が課されることになるため、節税効果が得られるとは限らない点に注意が必要です。
5. 相続税のシミュレーションをするには?
「相続税がいくらかかるのか自分で計算したい」と思っても、これまで解説したとおり、相続税の計算方法は複雑です。そのため、計算方法を完全に理解するのは、多くの方にとってなかなか難しいかもしれません。
相続税のシミュレーションを行う方法としては、簡易的には銀行・証券会社・税理士事務所などが提供している相続税計算シミュレーションツールの利用が考えられます。
ただし、具体的な状況に即した細かいシミュレーションを行いたい場合は、税理士に相談するのがよいでしょう。
6. 相続税の申告と納付期限
相続税は申告書と添付資料を税務署に提出してから納めることになります。
なお、遺産分割の協議が終了していない場合であったとしても、10ヵ月以内に相続税を納められなければ延滞税が発生してしまいます。
それゆえに遺産をどのように分けるかが決定していない場合であっても、暫定的に法定相続分に従った相続がなされたものと仮定して、法定相続人が相続税の申告と納税を行う必要があります。
そして、遺産をどのように分けるかが決定した後に相続税の金額を訂正することによって、不足していた際は追加で納税して、払い過ぎていた際は還付を受けます。
7. 生前贈与をしておいたほうが良いのか
生前贈与とは、生前に他人に対して(無償で)財産を贈与することを意味し、相続税を節税する目的として実施されることもあります。
年間に贈与を受ける額が110万円以下であった場合は贈与税が課されないことを利用して、毎年110万円以下(またはそれを少し超える金額)を贈与することで、無税または軽い贈与税負担のみで相続税の課税対象財産を減らせます。
8. 生前贈与をする際の注意点
1年間における贈与額が110万円以下であった場合は贈与税が課されませんが、毎年同一の金額で贈与を続けてしまうと定期贈与とみなされてしまい、贈与税が課されてしまうことがあります。
定期贈与とは、あらかじめ合意したルールに従って定期的に行われる贈与です。
毎年の贈与が全体として定期贈与とみなされた場合、両者の間で定期贈与の合意があった年に「定期金に関する権利」が贈与されたとして、一括して贈与税が課されます。
また、被相続人が死亡する前の3年以内に行われた生前贈与については、相続税の課税対象に含まれる点に注意が必要です(生前贈与加算)。
なお、生前贈与加算の対象財産について、すでに贈与税を納付している場合には、相続税額から控除できることを覚えておきましょう。
9. ペナルティを受けないためにも、迅速・正確に相続税を計算しよう
相続税を申告する期限と納付する期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
10か月というと長く感じられますが、遺産の整理や分割について話し合ったりしていると、あれよあれよと時間が過ぎ去ってしまいます。
相続税申告と納付の期限を厳守しなければ、延滞税等のペナルティを受けてしまうので、早い段階からの対応が必要です。
相続税申告や税額計算の方法がわからない場合や、期限が迫っていて対応が難しい場合には、税理士に助力を求めることを推奨します。
相続税に精通している税理士であれば、速やかに手続きを進めてくれますし、納税資金を準備するための方法等も提案してくれます。
生前の相続税対策についても、税理士に相談すれば有意義なアドバイスを得られるでしょう。
この記事の監修者:阿部 由羅

ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。