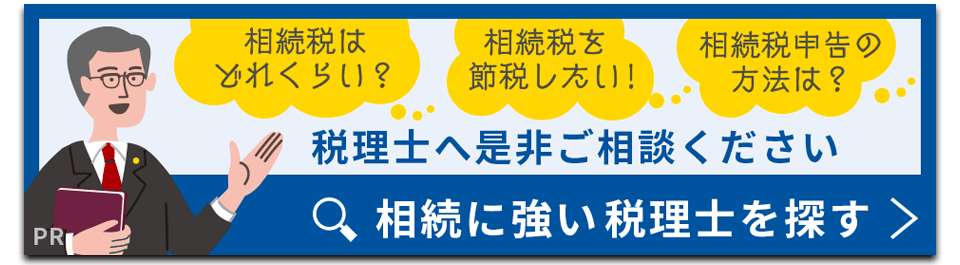相続税には「2割加算」という制度があるのをご存知でしょうか。誰が相続をするかによって、相続税の負担が異なる場合があるのです。
本来の相続税額が100万円のところを、120万円も納めなければならないと考えると、マイナスのイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、「2割加算」の制度は、うまく使えば節税対策として活用できるケースもあります。
今回は、2割加算の計算方法とは?対象者、相続放棄した場合や節税対策について、詳しく解説します。
目次
相続税の2割加算とは?
相続税の2割加算とは、相続財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の配偶者や1親等の血族以外の場合、本来の相続税額を2割上乗せした額の相続税を支払わなければならないという制度です。
「血族」とは、血のつながりのある親族のことを指し、「1親等の血族」は、被相続人からみた親や子(養親や養子を含む)のことを指します。
相続税法では、被相続人の配偶者や1親等の親族に当たらない者、すなわち、故人からみて血縁関係が遠い人が遺産を相続したような場合には相続税が加算されるという仕組みを設けているのです。
例えば、兄弟姉妹は2親等の血族であり「1親等の血族」以外の者にあたるので、税法上2割加算の対象になります。
相続税が2割加算される理由
相続税が2割加算される理由としてまず挙げられるのが、相続税の負担を公平にするためです。
例えば、孫(2親等)が相続する場合、本来であれば、①被相続人から子へ相続、②子から孫へ相続という順序となり、相続税が2回かかります。
しかし、子を飛ばして孫が直接遺産をもらえば相続税の課税が1回に減るため、その分負担を免れていることになります。
そこで、世間一般の相続と、税負担の点で公平になるよう調整する必要があるのです。
また、別の理由として、被相続人と関係が遠い者の相続は偶然性が高く「棚ぼた」的である点も考慮されています。
つまり、相続には遺された家族の生活を保障する役割もあるところ、もともと生活の元手となることが予想されていないような関係が遠い者への相続にはこの役割が当てはまりません。
その点で、本来相続すべき配偶者や子供への相続とは差がつけられるべきと考えられているのです。
相続税の2割加算の対象となる相続人
2割加算の対象者は、「配偶者・一親等の血族・代襲相続人となった孫以外の者」です。対象者/非対象者ともに、具体例を挙げてみましょう。
2割加算の対象者
- 祖父母(2親等)
- 兄弟姉妹及び代襲相続人(2親等)
- 孫(2親等)※代襲相続人を除く・孫養子
- 甥、姪
- 血の繋がりのない人(内縁関係にあった人など)
孫養子は、養子は民法上は、「実子」として扱われるため原則として2割加算の非対称者ですが、孫を養子にする場合には例外的に2割加算の対象となります。
これは、不当な課税回避の目的で孫を養子にする行為を防ぐためです。
2割加算の非対象者
- 配偶者
- 1親等の血族(父母・子)※養子も含む
- 子の代襲相続人
- 養子縁組をした者(孫養子は除く)
被相続人の子が既に死亡しており、代わって孫が代襲相続する場合には、その孫は2割加算の対象とはなりません。
この場合の孫はあくまで被相続人の子に代わって相続する立場にあり、1親等の血族として扱われるためです。
孫養子ではなく、婿養子や連れ子養子(再婚相手の子を養子にする)の場合には、民法上「実子」として扱われるため「1親等血族」にあたり、2割加算の対象から外れます。
相続税の2割加算の計算式・計算方法
「相続税額の2割加算」で負担増となる金額は、簡単に言ってしまえば、通常の相続税に20%を乗じた金額ですので、計算自体はそれほど難しくありません。
2割加算の計算式
2割加算が行われる場合の加算金額の計算式は「加算金額=税額控除前の相続税額×0.2」です。具体的な計算方法を、次の項目で見ていきましょう。
2割加算の計算方法例
次の事例をもとに、2割加算後の相続税額を実際に計算します。
- 被相続人Aの遺産総額:5億円
- 法定相続人:妻B、Aの兄C・姉D
- 相続分:妻3億円、兄と姉1億円ずつ
(1) まず、遺産総額から基礎控除額を除いて、課税遺産総額を算出します。
①基礎控除額の算式は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。
今回の事例では、3000万円+600万円×3人=4800万円となります。
②遺産総額から上記基礎控除額を引いた額が課税遺産総額となります。
今回の事例では、5億円 - 4,800万円 = 4億5,200万円が、課税遺産総額です。
(2)つぎに、上記金額を法定相続分に応じて分配し、各人の遺産の額を算出します。
民法上、配偶者と兄弟姉妹が相続した場合の法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(今回は2人いるため1/8ずつ)となるので、それぞれの遺産の額は以下のようになります。
- 妻B:4億5,200万円 × 3/4 = 3億3,900万円
- 兄C:4億5,200万円 × 1/4 × 1/2 = 5,650万円
- 姉D:4億5,200万円 × 1/4 × 1/2 = 5,650万円
(3)そして、相続税法所定の税率に従い、各人の法定相続分に応じた相続税額を算出します。
- 妻B:3億3,900万円 ×税率50% -控除額 4,200万円 = 1億2,750万円
- 兄C:5,650万円 ×税率 30% -控除額 700万円 = 995万円
- 姉D:5,650万円 ×税率30% -控除額700万円 = 995万円
(4)上記金額を足し合わせた金額が全体の相続税額となるので、これを各人の相続分に応じて分配します。
例えば、相続分が妻3億円、兄と姉1億円ずつとされていたときは以下のようになります。
- 1億2,750万円+995万円+995万円=1億4,740万円
- 妻B:1億4,740万円×3億円/5億円=8,844万円
- 兄C:1億4,740万円×1億円/5億円=2,948万円
- 姉D:1億4,740万円×1億円/5億円=2,948万円
(5)最後に、2割加算の対象となる兄と姉の加算税額を算出します。
- 兄C:2948万円×20%=589万6千円
- 姉D:2948万円×20%=589万6千円
このケースでは、加算対象となる兄Cと姉Dは、600万円近く税額が加算されることが分かります。
相続税の申告時に2割加算せず申告した場合、ペナルティが発生する
税法上、相続税の申告期限は相続開始(被相続人の死亡時)から10か月以内とされています。
この期限内に2割加算をしない状態で申告した場合には税務調査が入り、たとえ故意がなくても追徴課税が発生します。
また、申告漏れのペナルティとして、延滞税や加算税が課せられます。この金額は決して少なくなく、税金面で大きな損をすることになります。
計算自体は複雑ではないとはいえ、対象者を見落としたり、前提となる控除額を間違えてしまうことも考えられます。
専門家に任せるのが安心ですが、万が一税の申告漏れに気づいた際は、税務調査前に修正申告書を提出しましょう。
相続放棄した場合2割加算はどうなる?
借金やマイナスの遺産が多いなど、状況によっては相続放棄することもあります。その際に2割加算はどうなるのでしょうか?
ここでは、相続放棄した場合の2割加算について詳しく解説していきます。
1親等の血族が相続放棄した場合は2割加算されない
2割加算はあくまで税法上の制度なので、民法上の相続人としての地位を失っても影響がありません。
もともと2割加算の対象外である1親等の血族が相続放棄をした場合、民法上は相続人の地位を失いますが、1親等の血族であるという事実は変わらない以上、2割加算の対象外のままです。
代襲相続をした人が相続放棄した場合は2割加算される
ただし、代襲相続人である孫が相続放棄をした場合、2割加算の対象となります。
被相続人の子が既に死亡している場合、その子に子ども(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生します。
つまり、被相続人の孫が、被相続人の子に代わって相続人となります。
このとき、孫は子に代わって第一順位の相続人になりますが、孫が相続放棄したとしても一親等の血族ではない点は変わらないため、2割加算が適用されます。
相続放棄をしてもみなし財産がある場合は要注意
みなし相続財産とは、遺産分割対象となる民法上の相続財産ではないが、税法の計算上相続財産とみなされ相続税が発生する財産のことです。生命保険金や死亡退職金などがこれにあたります。
通常、相続放棄をすれば相続財産を受け取る地位を失いますが、みなし相続財産は本来の相続財産ではないため、民法上の相続放棄の影響を受けません。
したがって、たとえ相続放棄をしたとしても、みなし財産を受け取った者は、2割加算の対象外の者(配偶者や子)であれば相続税をそのまま納付し、2割加算の対象者(兄弟姉妹など)であれば加算後の相続税を納めなければなりません。
相続税の節税対策をする場合は、2割加算も計算する必要がある
相続税をなるべく抑えたいと、節税対策する場合もあるでしょう。
その際に2割加算についても考慮しながら計算することが重要です。節税対策の際の2割加算の注意点は以下のようになります。
生前贈与なら2割加算とはならない
被相続人の生前贈与に2割加算の適用はありません。
被相続人が亡くなる前に、2割加算対象である孫や兄弟姉妹に財産を贈与していたとしても、通常の贈与税がかかるのみで相続税は問題となりません。
もっとも、贈与税は相続税より税率が高くなる点には注意が必要です。
二次相続を検討すると、2割加算を入れても節税になる場合もある
2割加算税を負担してでも、2割加算対象者へ直接相続させることが、全体としてみて節税になる場合があります。すなわち、通常、孫へ財産を引き継がせるには
①被相続人から子への一次相続
②子から孫への2次相続
と2回の相続が必要で、相続税も2回分かかります。
そこで遺贈を利用し孫へ相続をさせることで、1回分の相続税で財産を引き継がせて節税するという方法があるのです。
単純な事例で考えてみましょう。
相続財産が3億円で、子1人、孫一人のとき、通常の相続では、
①子の相続時に9180万円
②孫の相続時に5049万円
合わせて1億4229万円の相続税がかかります。
一方、孫へ直接相続する場合は、2割加算を適用しても相続税額は1億1016万円にとどまります。
単純な事例にはなりますが、上記の例では1次相続の際に孫へ直接相続させたほうが、3413万円もの節税になります。
相続税の2割加算について詳しく知りたい場合は税理士に相談
今回は、相続税の2割加算の対象者や計算方法、相続放棄した場合や節税対策について説明しました。2割加算の算式自体はあまり複雑なものではありません。
しかし、対象者や税率の計算のルールには細かい部分もあるため、故人の葬儀や遺産分割などの慌ただしさのなかでは、うっかり申告漏れをしてしまうおそれがあります。
もし手続きに間違いがあり、延滞税などのペナルティが課されてしまうと、相続人ご自身が思わぬ出費を負担することになってしまいます。
相続税の2割加算について詳しく知りたい場合は、専門家である税理士に相談すると安心です。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
 この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように
ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。