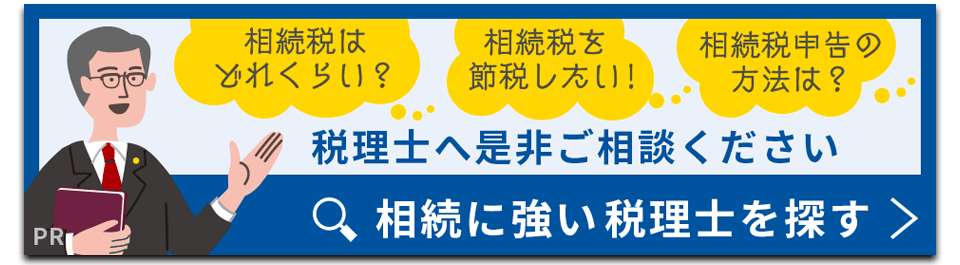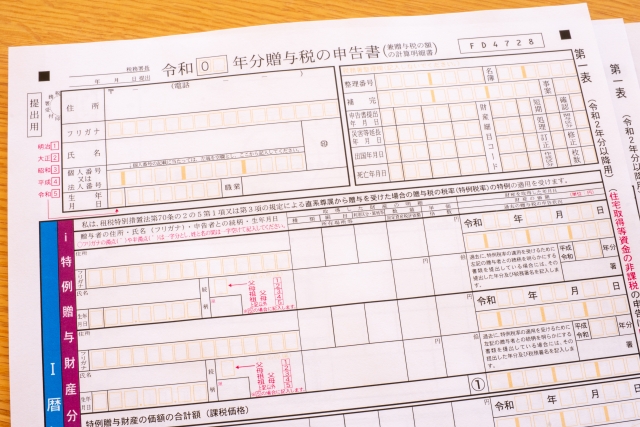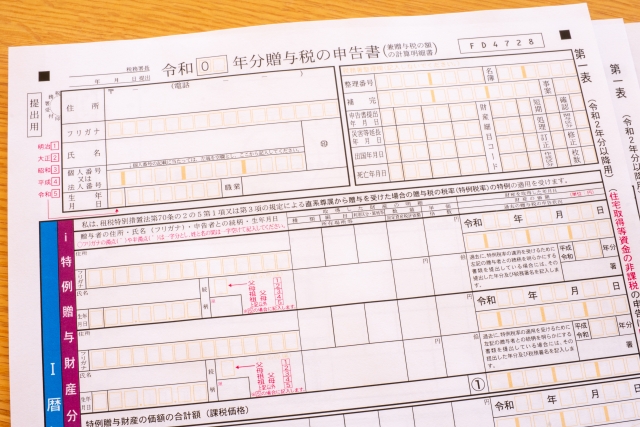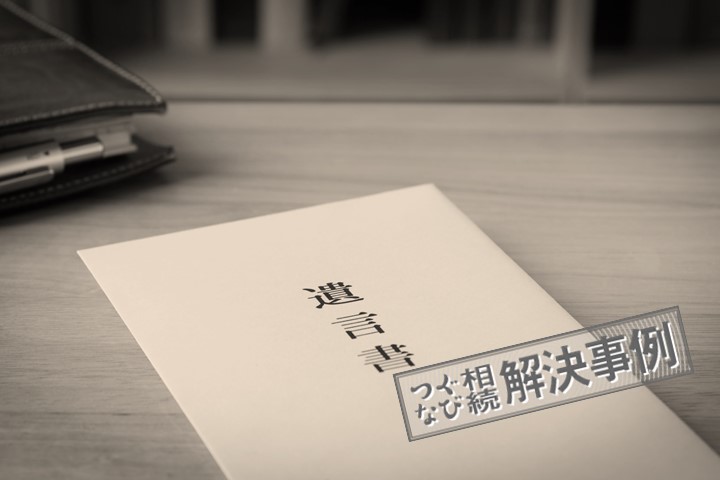親子間であっても金銭をもらっていたのであれば贈与税が原則かかってきます。
しかし、贈与税には時効がある為、中には「家族のやりとりなので、納税しなくてもバレないのでは? 」と考える人もいるかもしれません。
ここでは、贈与税の時効と、その時効がほぼ成立しない理由について解説します。
目次
贈与税の時効(納付期限)はいつ?

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
1人の人がその年の1月1日から12月31日までの間にもらった財産の価額の合計額が110万円を超える場合には、そのもらった年の翌年の2月1日から3月15日までの間にそのもらった人の住所地を所轄する税務署に贈与税の申告書を提出し、その申告した税額を納付する必要があります。
なお、1年間にもらった財産の価額の合計額が110万円以下である場合には贈与税は発生せず、申告する必要もありません。この110万円のことを基礎控除額といいます。
納付が遅れると追徴課税も
110万円を超える財産をもらったにもかかわらず贈与税の申告・納付をしなかった場合、又は実際の贈与よりも少ない金額で申告・納付をした場合でそれが後に税務署にわかってしまったときは、ペナルティーが課されます。
正しく期限までに申告・納付をした人が損することがあってはならないからです。
具体的には、申告しなかった場合に課される無申告加算税、申告書は提出したが、申告した税額が過小であった場合に課される過少申告加算税です。
さらに、こうして追徴課税されるということは本来の納税期限である3月15日を過ぎて、不足の税金を支払うことになりますから、その遅れた期間の利息に相当する延滞税もあわせて納付する必要があります。
贈与税にも時効がある

贈与税にも時効はあります。
贈与税の時効は原則6年とされていますが、悪質な場合、つまり意図的に贈与税を過小に申告したり、意図的に申告そのものを申告しなかりし場合などは7年となります。
時効までの起算日は?
では6年や7年といった時効の年数はいつからカウントするのでしょうか。
贈与税の時効は贈与税の申告期限を起算日としてカウントしていきます。
例えば、令和2年中にもらった財産が110万円を超えた場合には、令和3年の3月15日までに贈与税の申告・納付を終える必要があります。
よってそこから6年間又は7年間のうちに贈与が発覚しなければ贈与税の時効が成立します。贈与を受けた日が起算日ではないというのが注意点でしょうか。
時効が成立すると税金を払わなくてよい?
法律的には、贈与税の申告期限から6年、または7年が経過した後に税務署から贈与税の申告・納付がないことを指摘されたとしても、贈与税の時効によって贈与税の納税の必要はないということになります。
また、税務署といえど、贈与の事実をタイムリーに把握することは困難であり、贈与税単独での税務調査というのは実はほとんど行なわれません。
したがって、申告しなくてもばれないのでは?
あるいは、6年間や7年間ほどであれば隠し通して時効で逃げ切れるのでは?? と思いがちですが、いくつかの理由によって贈与税の時効が成立することは少ないといえます。
贈与税の時効が成立しにくい理由
なぜ贈与税の時効が成立しにくいのでしょうか。
そのためにはまず「贈与」についてのみなさんの理解を今一度整理しておく必要があります。
贈与とは財産をあげる人の「あげる」という意思さえあれば贈与になると考える人が多いのではないでしょうか。
実はこれが大きな間違いで、もらう人の「もらいます」という意思もなければ贈与にはなりません。
贈与とはあげる人ともらう人との契約行為であり、それぞれの意思がそろって初めて贈与が成立します。
ここが、贈与税の時効が成立しない一番のポイントです。
贈与したつもりでも「あげる」側の一方的な意思だけでは贈与そのものが成立していないのですから時効を主張したところで受け入れてもらえません。
気を付けたい名義預金と貸付金

では贈与税の時効が争われる場面とはどのような場合でしょうか。
実は贈与税の税務調査というのはほとんどなく、相続税の税務調査の場面で争われるケースがほとんどです。
例えば、亡くなった父が生前に子の預金口座に1000万円を移していたとしましょう。
しかし子はそのことを知らされておらず、その預金口座も父が管理していました。
無駄遣いしないようにという親心からでしょうか、こういうケースはとても多く見受けます。
贈与税の申告をせぬままその後、父が亡くなりました。
父の相続税の申告ではこの1000万円は預金残高からは無くなっているため、相続財産に計上していません。
後の相続税務調査で調査官から相続財産の計上漏れを指摘されましたが、この預金は過去に子へ贈与しており、贈与税の申告はしていなかったがすでに時効であると、相続人は主張をしました。
ではこの場合、預金を移して6年や7年が経過していれば、過去の贈与税については時効が成立するのでしょうか。
残念ながら贈与の時効は認められないでしょう。
先に述べたように、贈与とは「あげます」と「もらいます」の双方の意思が一致して初めて成立する契約です。
いくら父の「あげます」という意思があっても、子の「もらいます」の意思がなければ贈与そのものが成立していません。
たとえ時効の期間が過ぎていたとしても、贈与そのものが成立していないため、贈与税はかからなくとも、この1000万円は父の財産として相続税の課税対象となって結果的に追徴課税されてしまいます。
このケースのように、たとえ父が子の預金口座にお金を移したとしても子にその認識がない場合には、単に名義が変わっただけで実質的な預金の所有者は父です。
贈与は成立していないが、預金名義だけが他の人に変わっている預金のことを「名義預金」といいます。
名義預金であると判断されれば贈与税の時効という考え方そのものが存在しなくなり、それは父の財産として相続財産の計上漏れという結果となります。
そもそも贈与が行なわれていなかったわけですから。
逆に「もらいます」だけの意思により贈与が成立しないケースもあります。
よくあるのは認知症などで意思決定能力が低下している親の預金を子が使ったケースなどです。
この場合、「もらいます」の一方通行で「あげます」の意思がないため、贈与は成立していません。
その親が亡くなって相続税の税務調査においてその資金がどのように使われたかを問われた場合、贈与が成立していないため、親から子への貸付金として相続財産に計上すべきだとの指摘が想定されます。
贈与税を申告していないのが発覚するのはいつ?

ではまた贈与税のお話に戻りましょう。
「あげます」「もらいます」の意思が一致して贈与が成立したが、贈与税の申告をせずに時効期間が過ぎると贈与税の支払義務は時効によりなくなります。
さらに贈与税単独での税務調査は実はほとんどありません。
かといって贈与税の申告をしなくてもばれることはないのかというとそうでもありません。
ではどのようにして贈与税の申告漏れを税務署に指摘されるのでしょうか。
不動産の贈与
不動産の贈与があって申告していなければほぼ100%、申告漏れを指摘されると思っておいたほうが良いです。
理由ですが、不動産を贈与により名義変更するためには法務局に登記する必要があります。
不動産に名義変更がある場合は、①売買があった場合、②相続があった場合、③贈与があった場合、④建物の場合は新築された場合、に限られます。
しかも名義変更があった理由についても登記原因として登記簿謄本に記載されますから贈与があったことはすぐに分かります。
税務署はこの不動産登記の情報をいつもチェックしているため、不動産の名義変更があった時点で税務署はその事実を把握することとなります。
翌年3月15日までに申告がされていなければ早々に申告漏れを指摘されるでしょう。
現金や預金の贈与
一方で現金や預金の場合はどうでしょうか。
不動産と違い、現金を渡したり預金の名義を変えたりしても登記されるわけではないので、贈与の時点では税務署がその事実を把握することは難しそうです。
現金や預金の贈与が問題となるのは、先ほどの「名義預金」でもお話したように、現金や預金をあげた人が亡くなったときです。
さらにいえば相続税の税務調査のときです。
亡くなった人の預金口座やその家族の預金口座の入出金の履歴を調査できる権限が税務調査官には与えられています。
亡くなった人の口座を調査して、名義預金の可能性のある出金がないか詳細に調べられます。
その上で相続税の税務調査において相続人にその内容を確かめることとなります。
このように、現金や預金の場合には相続税の税務調査を通じて過去の贈与税の申告が必要であったかどうかが問われることとなります。
最終的には税金を支払うことになる
贈与が成立しているにもかかわらず、その申告がもれている場合には贈与税が課税されます。
一方、名義預金のように贈与が成立していない財産については相続財産としてカウントされ相続税が課税されることとなります。
相続税、贈与税いずれかの形で申告漏れに対するペナルティーは課されるというわけです。
贈与税の時効後も相続税として徴収される?

確かに法律的には贈与税には時効があり、それを過ぎると贈与税を支払う必要はなくなります。
しかしながら、贈与税というのは相続税を補完するための税金という性質があります。
贈与税は逃れたとしても後から相続税としてきっちり徴収されるケースも多くあります。
贈与税の有無自体は判明しづらい
不動産のように名義に変更があったことを届出する場合には、税務署も贈与の事実があったことを容易に把握できます。
しかし現金や預金については贈与があった時点でその事実を把握するのはきわめて困難です。
全国民の預金の出入りをタイムリーに調査するのは、いくら税務署とはいえ不可能だからです。
したがって贈与があった時点では、納税者自身が適正に申告することに委ねられている実情ではないでしょうか。
とはいえ、親から現金の贈与を受けてマイホームを建てた場合などは要注意です。
贈与を受けた人の収入状況を調査し、マイホーム資金はどのように調達しましたか?という内容のお尋ね文書が税務署から送付されてきますので念のため申し添えます。
そこで贈与の事実があれば贈与税が課されます。住宅資金については贈与税の非課税制度もありますので必ず申告しましょう。
贈与は証拠がないと成立しづらい
名義預金でのお話でも述べましたが、贈与とは契約であり、「あげます」と「もらいます」、双方の意思が一致して初めて成立します。
あげたほうは贈与したつもりでも、もらった方の「もらいます」という意思があったことを証明できない限りは贈与が成立したとは言い切れません。
相続税の調査の現場では頻繁に贈与が成立したかどうかが争点となり、納税者が贈与の成立を証明できずに、贈与したつもりの財産が相続財産に加算され、相続税の追徴を余儀なくされることが多くあります。
このような場合に贈与の成立を立証したいのであれば、たとえ親子間の贈与であっても意思の一致を図った上で、贈与契約書を作成や適正に贈与税の申告を行なうなど、贈与があったことについての証拠作りが大切となります。
贈与税の納付が遅れると追徴課税がかかる
その年の1月1日から12月31日までの間に110万円を超える贈与があった場合には、翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、申告した税額を納付しなければなりません。
申告書を提出するだけでなく納税も3月15日までに済ませる必要がありますので注意が必要です。
納付期限までに正しく納税した人との公平性を図るために、申告が遅れた場合や正しく申告しなかった場合には罰金として加算税などが追徴課税されます。
- 過少申告加算税: 申告はしているが、本来申告すべき金額より少ない金額で申告をした場合には過少申告加算税が課されます。原則として税率は10%となります。
- 無申告加算税: 申告期限までに申告しなかった場合には無申告加算税が課されます。原則として税率は15%となります。
- 重加算税: 申告期限までに申告をせず、かつ意図的に贈与があった事実を隠すなど、その行為が悪質である場合には重加算税が課されます。税率は35%となります。
- 延滞税: 上記の加算税に加え、納税が本来の納税期限より送れた場合には延滞税が課されます。延滞税は本来の納付期限から実際の納付日までの期間に応じた利子のようなものです。加算税が課されるということは、追加的な贈与税を後から納付することを意味しますから、この遅れた期間に応じこの延滞税もセットで課されることとなります。
まとめ
贈与税の無申告がなぜバレるのか不思議に思う人もいるかもしれませんが、この記事を読んで理解していただけたのではないでしょうか。贈与の際には、「贈与の成立」と期限内の申告を意識して行いましょう。
 安井貴生
安井貴生税理士。税理士法人に所属して活動しており、法人税決算から税務申告・税務調査立会、経営相談まで幅広く業務を行っている。最近は、相続や事業承継案件、M&Aなどの取扱いが増加中。土地や非上場株式などの財産評価を得意とするが、節税ありきではなく相続人全員が納得する相続業務を何よりも重視している。