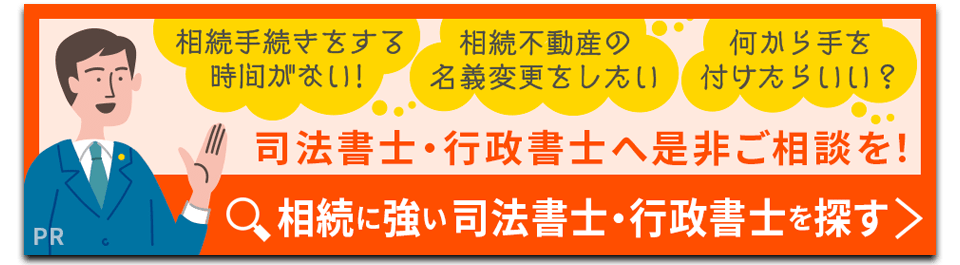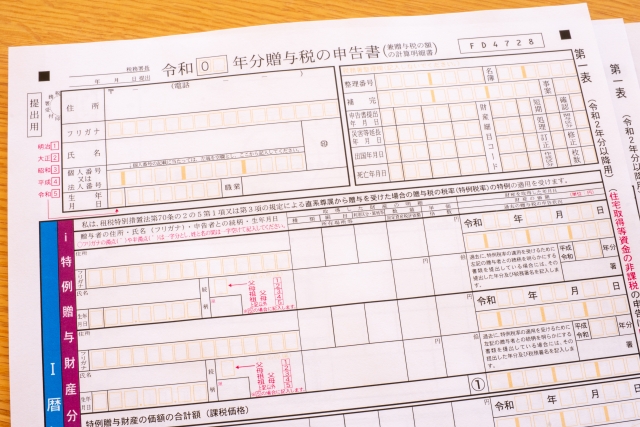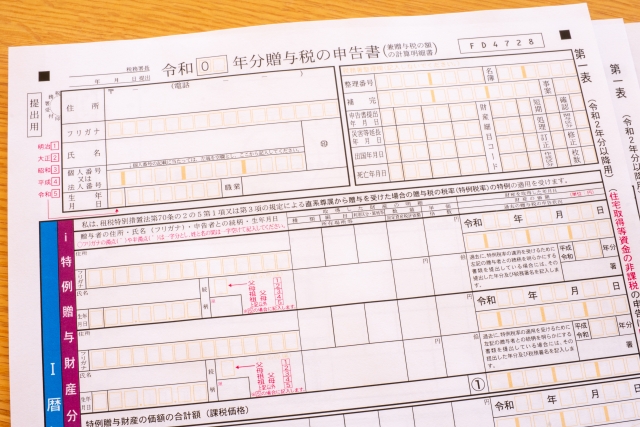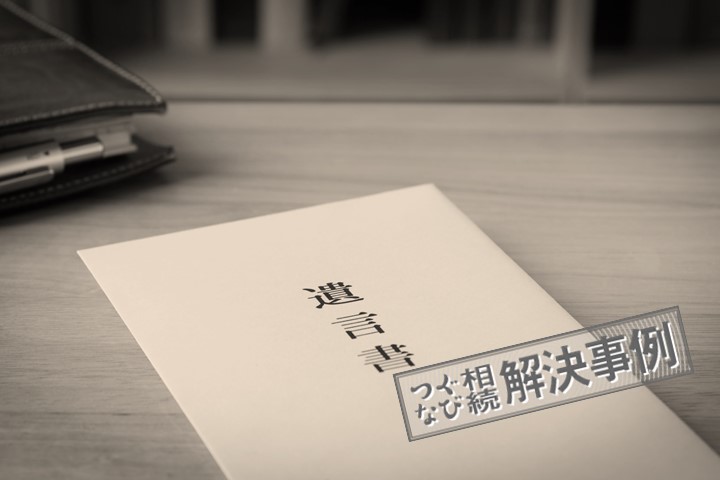遺言書を作成しても、その内容に沿って実際に手続きを行うのは相続人自身です。生前にあらかじめ「遺言信託」の契約を締結しておけば、信頼できる資産管理のプロに相続手続きを任せることができ、遺された家族の負担を大幅に減らせます。
本記事では、遺言信託のサービス内容(サービスの特徴・利用の流れ・費用)を一望できるよう解説し、どんな人に向いているのか紹介します。
1. 遺言信託とは
1-1 遺言信託の概要
遺言信託とは、相続手続きの全体(遺言からその内容実現まで)を一括支援する有料サービスです。サービス提供は法令に沿って信託商品を扱う銀行が行っており、契約プランには下記3つの支援がパッケージされています。
- 遺言のコンサルティング: 担当者と契約者との間で打ち合わせを行い、ヒアリングした内容や財産目録等をもとに、作成する遺言書の内容の提案が行われます。
- 遺言書の保管: 遺言書の紛失・滅失・改ざんや偽造等がないよう、信託業者(銀行)が安全に保管します。
- 死後の遺言執行: 契約者の死後は速やかに相続人に通知され、遺産の名義変更やこれに伴う売却手続きが開始されます。遺言書で指定があれば、子の認知あるいは相続人の廃除(相続権の剥奪)に関する届出もしくは申立てが行われます。
1-2 商品名の「遺言信託」と法律上の「遺言信託」の違い

「遺言信託」という名称には2通りあり、①信託業者の商品名と②遺言で生じる効力で混同しないように注意しましょう(下記参照)
- 商品名としての「遺言信託」: 遺言の効力が現実に生じるよう、信託業者が手助けするサービスを指します。どんな効力が発生するかは遺言する人次第であり、商品を利用するかどうかも遺言者が資料を比較しながら決められます。
- 遺言で生じる効果としての「遺言信託」: 遺言の効力のうち、特定の財産について管理処分の委託(=信託)するものを指します。受託者・受益者・信託資産を指示し「受託者ができる管理処分の範囲」や「受益者が信託財産から得られる利益」(定期定額給付や運用益の配当など)を遺言書に明記する事で、法律上の遺言信託の効力が生じます。
なお、本記事で解説するのは①商品名としての「遺言信託」です。
2. 取扱い銀行例
遺言信託の取り扱いはメガバンクから地方銀行まで業界全体に広がっており、下記で紹介するのはそのごく一例です。
2-1 りそな銀行の「遺言信託」
りそな銀行の「遺言信託」は、特定の相続人が単独で全財産を承継するケースなら格安利用できる「パッケージ型遺言信託」が特徴です。最低執行報酬は55万円。
2-2 三菱UFJ銀行の「遺心伝心」
三菱UFJ銀行の「遺心伝心」は、MUFJグループの他の企業とも取引があれば、対象の預託財産について遺言執行報酬が優遇されるのが特徴です。最低執行報酬は77万円。
2-3 三井住友銀行の「遺言信託」
三井住友銀行の「遺言信託」は同じく、SMBCグループの他の企業とも取引があれば、対象の預託財産について遺言執行報酬が優遇されます。最低執行報酬は55万円。
2-4 三井住友信託銀行の「遺言信託」
三井住友信託銀行の「遺言信託」は公益性の高い団体や法人と提携をとっており、相続財産の寄付を希望するケースできめ細かい対応を行っているのが特徴です。最低執行報酬33万円。
2-5 千葉銀行の「遺言信託」
千葉銀行の「遺言信託」は大手銀行のように際立った特徴はないものの、相続人からの相談を遺産整理業務について積極的に情報公開しており、地域や顧客により密着した対応が期待できます。最低執行報酬55万円。
2-6 遺言信託のメリット

遺言信託の何よりのメリットは、資産管理全般に熟練したプロへ相続開始後の遺産承継手続きを任せられる点です。
本来、遺言執行は誰に任せてもかまいません。多くのケースは弁護士や司法書士、遺言者が望めば特定の相続人や親族が選ばれます。
しかし、いずれも「金融機関側での内部処理」や「取引市場での資産の扱い方」が詳しいわけではありません。
顧客資産の運用管理経験に優れた金融機関であれば、どんな資産でもスムーズに承継手続きができます。
特に、時価変動が頻繁で管理を継続する必要性の高い資産(有価証券や収益用不動産)では、相続と前後してきめ細かい運用相談が行われ、適切な管理を途切れさせないといったメリットも期待できます。
2-7 遺言信託のデメリット
他方で、契約当初に行われる遺言内容のコンサルティングは、弁護士(または司法書士)ほど充実していません。信託業者はあくまでも金融業界の専門家であって、相続法やトラブル防止策の知識が十分であるとは言えないからです。
加えて、営利性が強いのも問題です。第一に指摘できるのは、士業(弁護士や司法書士)が受任する同様の依頼に比べ、報酬が高額である点です。
弁護士会の旧報酬基準(弁護士の登録数が増加した現在より高水準)をベースにし、さらに最低報酬額を設けて一定の利益を上げていることが背景にあります。
第二に指摘できるのは、資産状況の開示により、商品利用の勧誘が増加しやすい点です。信託業者は、顧客になるべく多くの商品やサービスを利用してもらって利益を得ているため、勧誘にあう可能性が高いといえます。
遺言信託を利用しようとする際は、以上の点を考えて「コスト対効果は十分か」をよく検討する必要があります。
3. 遺言信託の手続きの流れ

遺言信託の利用は下記Step1~Step5の流れで進み、事前に認識しておきたいポイントとしては以下の2つです。
第1のポイントは、遺言執行報酬(※遺産評価額に応じて決定)に最低額が定められているため、一定以上の目的価額が必要になる点。
2つ目は、信託業者が希望通りの遺言執行を確実に実施できるよう、事前の打ち合わせと公正証書の作成が前提になる点です。
STEP1. 事前相談
担当者と面談や電話相談を行い、死後どのように財産処分をしたいのか伝えます。担当者が「より高度な提案が必要」と判断した時は、信託業者が提携する弁護士や税理士との協力が行われます。
STEP2. 遺言書作成のコンサルティング
契約手続き後にさらに打ち合わせを重ね、遺言内容の詳細を取り決めます。
遺言したい内容が決まり次第、担当者と共に「公正証書遺言※」を作成し、さらに担当者を遺言執行者(相続手続きに関する一切の権利義務を持つ法律上の役職)に指名します。
作成時には証人確保が必要となり、多くの場合は担当者が引き受けます。
※参考:公正証書遺言とは: 公正役場(公文書の作成業務を行う官公庁の一種)に遺言内容を伝え、文面作成と遺言書原本の保管を任せる遺言方法です。遺言内容の真正が保証される上、紛失や滅失のリスクがほとんどないのが特徴です。
STEP3. 遺言書(正本)の保管
公正証書遺言の作成時、遺言書原本と同じ効力を持つ「正本」が交付されます。遺言執行で必要となるため、正本は信託業者が保管します。
なお、以降相続開始まで継続的に遺言書保管料(後述)が発生します。
STEP4. 相続状況の定期照会
遺言書の保管中は、相続状況の変化について担当者から定期的な確認が実施されます。
相続人構成あるいは相続財産に変化があれば、遺言内容を当初のままにしておいても良いのか検討し、必要に応じて遺言書の変更(有料)を実施します。
STEP5. 遺言執行
信託した人が亡くなると、担当者の手で遅滞なく以下の処理が行われます。
【遺言執行の手続き】
- 相続開始の通知
- 財産目録の交付
- 遺産の名義変更手続き(預金払戻しや相続登記など)
- (必要に応じて)遺産の名義変更に伴う資産売却
- (遺言されている場合のみ)子の認知届の提出
- (遺言されている場合のみ)相続人の廃除の申立て
4. 遺言信託の費用目安
遺言信託には以下の費用が発生します。いずれも信託業者(=銀行)によって異なるため、契約前に条件を確認しましょう。
【遺言信託の費用内訳】
- 手数料: 契約時に発生
- 遺言書の保管料: 生前(遺言書の保管中)に継続的に発生
- 遺言執行報酬: 死後(遺言執行時)に発生
- その他の費用: 各種書類の交付手数料・遺言書の変更手数料・税理士報酬など
利用の検討材料として遺言信託の負担額が大まかに分かるよう、各費用の目安を順に紹介します。
4-1 手数料
信託業者の多くは手数料の異なる2つのプランを用意しています。手数料の安いプランは20万円~30万円、高いプランは70万円~110万円がそれぞれ目安です。
手数料が高いプランは、契約後に発生する保管料や遺言執行報酬が安くなり、信託の総費用を抑えられる点をアピールポイントにしています。
4-2 遺言書の保管料
保管料は年払いとする業者が多く、目安は相続開始まで1年につき6,000円前後です。地方銀行の金額にはバラつきがあるものの、メガバンクや大手信託銀行は年間保管料6,600円で足並みをそろえています。
4-3 遺言執行報酬
遺言執行報酬は定額ではなく、遺産評価額に対する一定の割合(=遺言執行報酬率)でかかります。報酬率は遺産評価額に応じて段階的に引き下げられ、ほとんどの業者で0.3%から2%までを目安に設定されています。
先で触れた通り「最低執行報酬」が定められており、遺産の評価がそれほど高くないケースでは負担が大きくなる点に注意しましょう。
【三菱UFJ銀行の場合】
| MUFGグループ預かり財産の部分 | 0.3% |
| 1億円以下の部分 | 1.8% |
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.9% |
| 3億円超10億円以下の部分 | 0.5% |
| 10億円超の部分 | 0.3% |
| 最低執行報酬 | 165万円 |
【三井住友銀行の場合】
| SMBCグループ預かり財産の部分 | 0.22% |
| 5,000万円以下の部分 | 2.20% |
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% |
| 1億円超2億円以下の部分 | 1.10% |
| 2億円超3億円以下の部分 | 0.88% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.66% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.55% |
| 10億円超の部分 | 0.33% |
| 最低執行報酬 | 55万円または165万円※契約プランによる |
4-4 その他の費用
遺言信託のために必要な公的書類の取得費等については、プラン料金にパッケージされていません。また、遺言執行後は相続人が税申告手続きと納付を負担します。
| 負担時期 | 遺言信託の契約者が負担する費用(一例) |
| 契約時 | 戸籍謄本や住民票などの交付手数料 |
| 遺言書の作成or変更時 | (作成時・変更時)公正証書の作成費用 / (作成時・変更時)戸籍謄本や住民票などの交付手数料 / (変更時のみ)信託業者に支払う変更手数料 |
| 遺言執行の完了時 | 戸籍謄本や住民票などの交付手数料 / 不動産登記時の費用(登録免許税など) / 預貯金等残高証明書の交付手数料 / 相続税申告等にかかる税理士報酬 |
5. 遺言信託利用に向いているケース

遺言信託の費用感やサービスの範囲から考えると、利用を検討できるのは少なくとも次の3条件が揃うケースです。
【遺言信託の利用を検討できる最低条件】
- ある程度まとまった財産がある
- 相続トラブル発生の可能性が低い
- 信頼できる人物に手続きを主導してほしい
利用の最低条件が揃うケースの中で、下記3つのいずれかに該当する場合、とりわけ利用に向いています。
5-1 子どもがいない(配偶者等に単独相続させたい)
子どもがいない夫婦では、存命の父母・祖父母・兄弟姉妹などが法定相続人に含まれます。
長年連れ添ったパートナーに全財産を相続させるのは遺言で十分ですが、「高齢の配偶者が一人で相続手続きできるかどうか」という問題もあります。
こうした場合、遺言書作成に加えて信託を利用しておくと、信頼できる人物の支援でスムーズな遺産承継が叶います。
5-2 未成年者・障がい者が相続人に含まれる
未成年者や障がい者が相続人に含まれるケースでも、同様に「独力で相続手続きできるかどうか」の問題が生じます。
遺言する人自身が扶養や介護を行っているケースでは、なおのこと死後の対応がスムーズに進まない恐れがあるでしょう。
信託を利用して業者に遺言執行を主導してもらえるなら、上記の不安は解消できます。遺言内容そのものについても、業者のコンサルティングで「経済的基盤が揺るぎやすい」という特徴に配慮できます。
5-3 相続人以外の人に遺産を承継させたい
内縁のパートナーやお世話になった施設に相続させたいと考える人は、決して少数ではありません。
こうした相続の希望は遺言で実現できますが、実際の個別事例においては、遺言のやり方や相続手続きで戸惑うことも多くなります。
このような場合では、金融業界での顧客資産の扱いに詳しい信託業者に任せる事で、資産状況を事前分析した上で適切な対処を取ってもらえます。
6. まとめ
全国の銀行で提供されている「遺言信託」サービスのメリットは、遺言書作成から相続開始後の手続きまで、一括で資産管理のプロに任せられる点です。
相続人の手続き負担が重いケース、あるいは経済的基盤に特別の配慮を要する相続人がいるケースでは、不安解消の一手段として活用できます。
一方で「相続トラブルの可能性を予期する」「特殊事情を考慮してトラブル対策を行う」等のサポートに関しては、信託業者では対応しきれません。
契約前に弁護士または司法書士に相談し、相続法の側面から遺言したい内容についてアドバイスをもらうと良いでしょう。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。