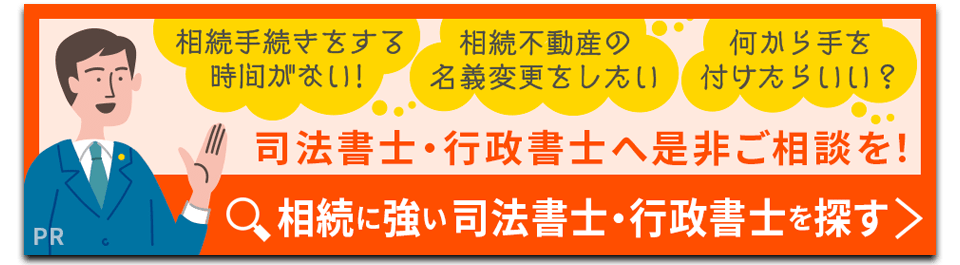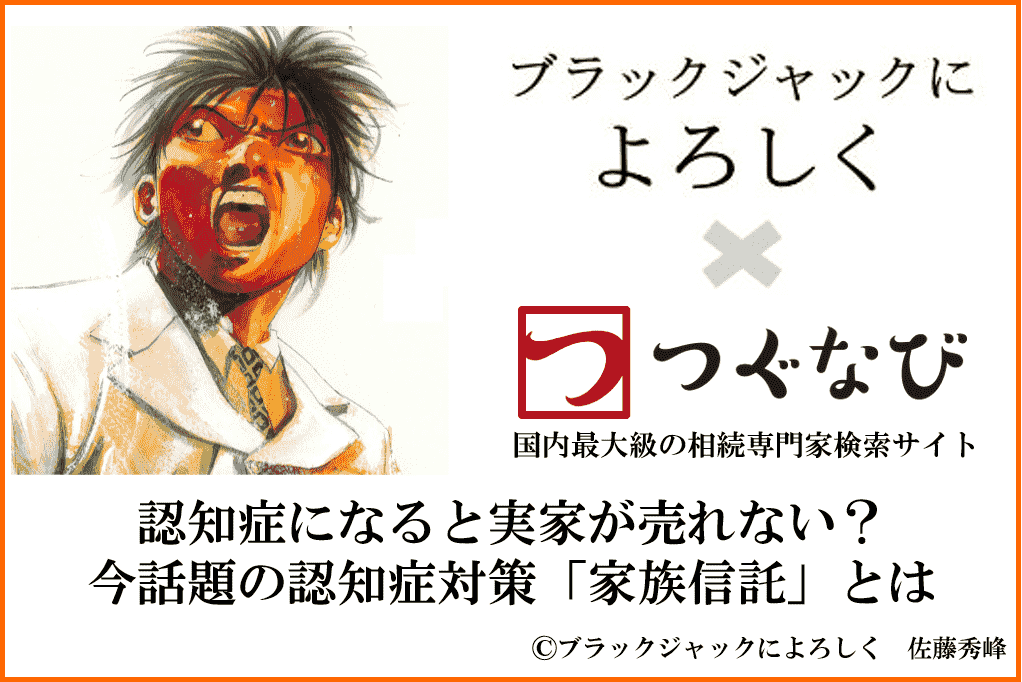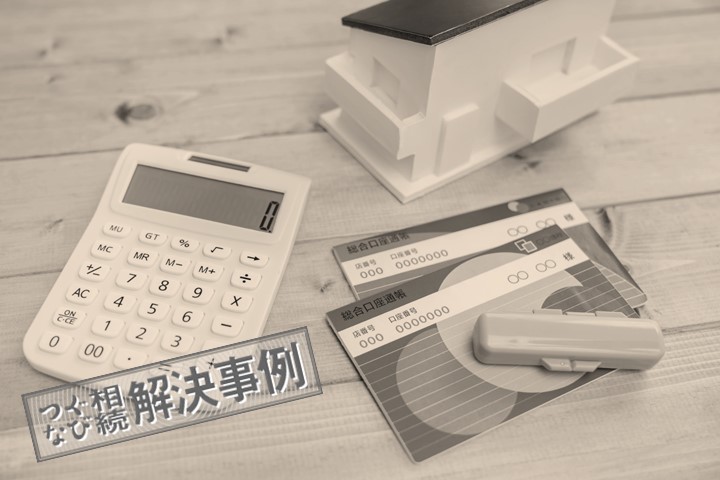相続トラブル防止の最大の秘訣は、家族と話し合って意見をすり合わせておくことです。また、相続準備には「認知症による資産凍結リスク対策」が含まれる点にも留意する必要があります。
被相続人の健康状態悪化に備えてスムーズな財産承継を実現するとともに、遺言書では不可能な“遺産の流れのカスタマイズ”を可能とするのが今回取り上げる「家族信託」です。
仕組み・既存制度との違いを軸に、利用イメージが容易になるよう家族信託の特徴を解説します。
目次
「家族信託」とは
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せ(=信託)、同時に信託した財産のなかから老後の生活費等の給付等を受ける契約を指します。
家族間の契約であるため、信託は必ずしも報酬を必要としません。契約内では死後の財産の扱いについても定められ、生前からの緩やかな資産承継のプランとして利用できます。
「家族信託」の概要
家族信託では、まず財産管理を任せたい人が自身の資産から「信託財産」を切り出し、その所有権だけを自身に残しておきます。
次に、信託財産の管理処分権・信託財産から利益を得る権利(=受益権)それぞれの扱い方について、委託者・受託者・受益者の3者間で契約を結びます。
契約発効後に関係者が死亡した場合は、特定の人に信託財産の所有権を承継させて信託を終えるか、受益権を死亡者から別の人へと移転させて信託を継続します。

【家族信託の関係者】
- 委託者: 財産の管理を任せる人(将来被相続人になる人)
- 受託者: 信託財産の管理を行う人
- 受益者: 信託財産から給付や分配を受ける人
家族信託の内容をどのように設計するかは、話し合いで自由に取り決めて構いません。相続法に制限を受けず、家庭ごとにオリジナルの信託プランを設計できます。
家族信託のメリット
家族信託の最大のメリットは、財産管理権の移行をスムーズかつ柔軟に行える点・高性能な遺言機能がある点の2つです。
その他にも、破産による財産処分のリスクを防ぎつつ、次世代に必要な費用を捻出することで節税効果が得られる長所があります。

本人の判断能力に左右されない財産管理
家族信託が特にいきるのは、加齢により認知症リスクが迫っているケースです。
まだ判断能力が十分あるうちに信頼できる家族へ財産を任せることで、本人の健康状態に左右されない適切な財産管理が可能になります。
財産管理が柔軟&簡単に
受託者から見た家族信託のメリットは、第三者の介入なく財産管理を行える点です。
収益不動産など適切な管理処分が行われるべき資産だけを信託財産として切り出すことで、受託者の管理行動に一定の制限を設けることも可能です。
遺言書の代替にも
家族信託では、「受益者死亡時の権利移転先」「信託終了時の資産承継先」を細かく取り決められます。
受益権については、委託者(第一受益者)→配偶者(第二受益者)→将来生まれる孫(第三受益者)→…とのように、連続して移転させることも可能です。
最終的に相続させたい人へ信託財産が渡るよう契約を設計することで、遺言書の代替として利用できます。
倒産隔離機能も
家族信託では、信託財産を受託者の名義に属するものとして扱います。したがって、委託者が破産手続きを開始しても、信託財産に債権者分配の手続きが及ぶことはありません。これを「倒産隔離機能」と呼びます。
相続トラブル回避が期待
信託契約の準備段階で家族としっかり話し合うことで、相続開始後の意見対立を防げます。いったん合意が成立すると“遺産の流れ”が確約され、家族のその相続分に関する不安を解消できます。
教育資金の一括贈与が1,500万円まで非課税
委託者の直系卑属にあたる家族(子・孫など)を受益者に指定し、受益者の教育資金を信託財産とした場合、1,500万円までは贈与税が賦課されません。
受益者の親権者や保護者にあたる人物を受託者としておくことで、本人の判断で教育資金を別の目的のために使いこんでしまうリスクも防げます。
家族信託のデメリット
家族信託の最大のデメリットは税制面です。
節税効果はほぼ得られず、収益不動産等を信託する場合はかえってコスト(課税額と申告の手間)が増える懸念があります。
信託の仕組みづくりそのものも困難を極め、専門性の高いアドバイザーによる緻密なフォローが欠かせません。
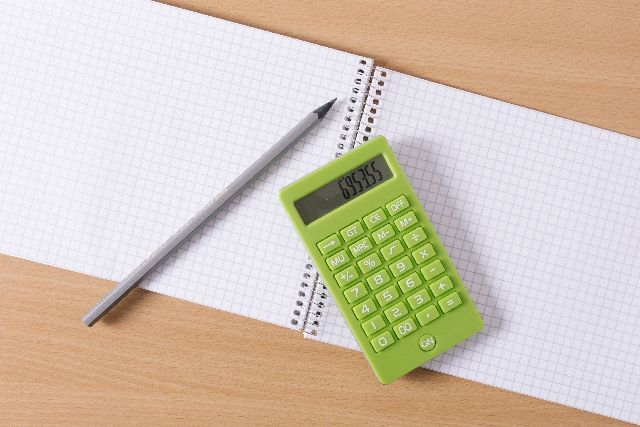
所得税に注意
家族信託の受益者は、信託財産から収益が上がっている場合に「所得税」が課せられます。
さらに、信託財産に含まれる収益不動産(賃貸アパート等)から年間3万円以上の収益が出た場合、受託者側でも翌年1月31日までに不動産所得の明細書の提出する義務を負います。
損益通算ができなくなる可能性
収益不動産を信託する場合のデメリットとして「損益通算」ができない点も挙げられます。不動産所得の赤字は、その黒字部分から控除して税申告できるのが本来です。
ところが収益不動産が信託されてしまうと、以降生じた赤字は”なかったもの”とみなされ、利益との相殺ができなくなってしまうのです。
節税効果は期待できず
家族信託の契約自体には、税額控除などの節税効果はありません。
生前贈与の際に活用できる「相続時精算課税制度」(贈与税の賦課方式を控除額2,500万円・一律20%の税率とする制度)などを利用したい場合には、信託設計を含めて別途検討する必要があります。
成年後見人制度・遺言より劣る点がある
家族信託の契約には、委託者の日常を支えるための「身上監護権」を含められません。
また、遺言機能にも限界が存在します。一例として、信託財産に対する「遺留分侵害額請求」(法定相続人が得るべき最低限の取り分を請求する手続き)は妨げられません。
生前準備として考えるなら、信託契約を過信しすぎず、足りない機能は成年後見人制度や遺言書作成で補う必要があります。
税務申告が煩雑に
課税関係の説明で触れた通り、信託設定時から終了までの税申告は複雑です。
「誰が・いつ・何を申告しなければならないのか」といった点に混乱が生じ、たとえ申告義務の理解が完全でも、申告書類の準備などの負担は無視できません。
受託者決定時にもめる可能性

家族信託の受託者は、当然”委託者から最も期待されている相続人”になるはずです。財産管理をする見返りとして、遺産相続で優遇されることも期待するでしょう。
以上の点を背景に、受託者を誰にするのかを巡ってもめる可能性があります。
家族信託を扱う専門家が少ない
家族信託は相続法・税制・不動産管理運用の3分野にまたがった複合スキルが求められます。
一方で、ごく新しい信託形態であることもあいまって、個別で信託コンサルティングできるスキルを持つ専門家はまだ少ないのが現状です。
他制度と比べて費用が高額
家族信託にかかる費用は信託財産の評価額に左右され、一般に30万円~50万円(信託開始までにかかる初期費用)と高額です。
これに対し、認知症発症時に財産管理権を委譲できる2種類の成年後見人制度(法定後見・任意後見契約)は、書類作成等を自力で行うなら高くても2万円程度とごく低予算で済みます。
| 比較項目 | 家族信託 | 法定後見 | 任意後見契約 |
| 裁判所に納める費用 | ― | 800円+登記費用2,600円+切手代+必要に応じて5万円~10万円の鑑定費 | 800円+登記費用1,400円+切手代 |
| 公正証書の作成費用 | 5,000円~4万3,000円+諸手数料 | ― | 1万1,000円+登記費用4,000円+諸手数料 |
| 不動産登記の費用 | 固定資産税評価額の0.3%または0.4% | ― | ― |
| 専門家報酬 | 信託評価額の1%程度(目安) | 5~20万円(目安) | 5~20万円(目安) |
| 監督人報酬 | 契約内容による | 月額1万円~3万円(目安) | 月額1万円~3万円(目安) |
家族信託が注目される理由
家族信託は「認知症への備えになる」「遺産承継の理想形を実現できる」と注目されています。
注目の背景をさらに詳しく説明します。
認知症への備え
認知症はごく身近な人すら兆候に気づかない病であり、発症すると以下のようなリスクにさらされます。
【認知症発症後のリスク】
- 高齢者を狙った詐欺などの犯罪被害に遭う
- 入出金等が一切できない”資産の凍結状態”が生じる
- 認知症患者が遺産分割協議に参加できず、相続手続きが進まない
家族信託が注目されたのは、社会全体の高齢化に伴い、上記のリスクが多くの家庭にとって他人事でなくなったためです。
既存の成年後見人制度の欠点(後見人選任までのタイムラグ・本人の意志の反映しづらさ)との対比で、信託の利便性が専門家を中心に広く知られるようになりました。
「家族のかたち」の多様化
注目のもう1つの理由は、社会全体の離婚率の上昇・人間関係の希薄化を受けて、家族のかたちが多様化しつつある現状です。
相続法では「一定範囲の近親者に対して平等に相続権を与える」ことを趣旨としていますが、実際には血縁関係と”家族の絆”が一致しているとは限りません。
また、相続法に従って遺産承継を繰り返すことで、配偶者を通じて血縁関係のない家族に財産が渡るケースもあります。
上記のように、相続法は現代の家庭の在り方にそぐわなくなりつつあります。遺言機能を持つ家族信託は、法律に依らず被相続人の意志を遺産承継に反映させる“新しい手段”として注目されました。
既存の制度との違い
家族信託以外にも、認知症や遺産分割に備える方法は複数存在します。下記では信託の仕組みを各方法と比較し、家族信託との優劣のポイントを解説します。
生前贈与との違い
生前贈与と家族信託の違いは、移転対象となる”権利”にあります。生前贈与は資産の所有権をまるごと移転させるため、贈与後は財産の使い道に干渉できません。
一方で家族信託の場合は、所有権はあくまでも委託者に留めておき「管理処分の権限」と「利益を受ける権利」を分離して譲渡できます。
金銭管理が不得手な承継人に対しては、委託者・受託者という2つの立場からフォローできるのです。
生命保険との違い
生命保険と家族信託の違いは”生前の財産管理の自由度”と”非課税枠”の2点です。預貯金を生命保険の掛け金としてしまうと、払込済み保険料の利用には著しい制限があります。
信託財産とした場合は、実質的にほとんど制限を受けず、生活費等の利用目的で受託者を通して出勤できます。
ただし、財産管理の自由度だけを評価して家族信託のほうが優れているとは言い切れません。
生命保険の給付金には、信託財産にはない非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられているからです。
遺言書との違い
遺言書は家族信託とは異なり、あくまでも「作成者本人が亡くなったときの遺産承継先」を定めるものです。配偶者や子が死亡したときの財産の承継先は指定できません。
他方、遺言書は「身分行為」「遺留分侵害額請求の順序指定」という2つの家族信託にない機能を備えています。
死亡に際して子の認知や相続権のはく奪(相続廃除)したい場合は、遺言書を作成するほかありません。
家族信託で遺留分侵害額請求を回避する上でも、遺留分相当額を手元に残した上での遺言書作成は不可欠です。
成年後見人制度との違い
成年後見人制度と家族信託との決定的な違いは、財産の管理処分を任せられる時期です。
家族信託では設定後すぐ信頼できる人による財産管理が始まりますが、成年後見人制度はあくまでも“相当に健康状態が悪化している”と家裁が認めたときが後見開始のタイミングです
2つ目の相違点は、財産を任せる人・任される人に対する制約です。
成年後見人制度のうち「法定後見」は、後見人の決定権すら本人にありません。
健康状態が悪化する前に後見人を決められる「任意後見契約」も存在しますが、いずれにしても後見人から家裁への収支状況に関する定期報告義務は免れられません。
以上の成年後見人制度の弱点に対し、家族信託は「本人の希望する人へ即時的かつ自由に財産管理を任せられる」という利点を持ちます。
ただし、財産を任された人が本人の日常生活を支えるための「身上監護権」「身上配慮義務」の2点については、家族信託にはなく成年後見制度にはあるものです。
信託財産の受託者による介護を想定するなら、別途任意後見契約を結んで権利義務を補うプランも検討すべきでしょう。
民事信託・商事信託との違い
そもそも”信託”と呼ばれるシステムには「商事信託」と「民事信託」の2種類があります。
家族信託とは、民事信託のなかでも受託者を家族とするものを指しています。信託法が2007年に改正されるまで、信託業者(銀行や証券会社など)が受託する投資益を目的とした「商事信託」のみ認められていました。
法改正後に認められるようになった「民事信託」は、投資益を目的としない代わりに、受託者が信託業者であることを要しません。
民事信託の誕生によって、その仕組みを有効活用する手段として発案されたのが「家族信託」です。
家族信託手続きの流れ
契約を発効させる手続き(公正証書の作成・信託登記)の適切な処理を含め、専門家による指針作りや書類作成のサポートは必須です。

【家族信託の手続きの流れ】
- 契約内容に関する協議: 家族のイメージする遺産承継や財産管理の方法について、まずはじっくりと話し合います。
- 信託契約書の原案作成: 合意した内容に基づき、信託のシステムを設計して契約書原案に落とし込みます。
- 信託契約書の公正証書化: 契約内容が誠実かつ正しく実施されるよう、原案を管轄の「公証役場」に持ち込んで証書化します。
- 信託財産の名義変更: 信託財産に含まれる不動産は法務局で信託登記を行い、現金や有価証券等の資産は受託者名義の口座を解説して移管します。
- 財産管理の開始: 以上の流れを終えて家族信託の契約は発効します。以降、委託者や受益者が亡くなったときは、速やかに契約内容に沿った給付あるいは権利移転が行われます。
家族信託にかかる費用
家族信託の利用に最低限かかる費用は下記の5項目です。
【家族信託の費用】
- 公正証書の作成費用: 5,000円~4万3,000円(信託評価額により異なる / 後述)+各種事務手数料
- 専門家によるコンサルティング費用: 目安として信託評価額の1%
- 信託登記時の登録免許税(不動産を信託財産に含める場合): 土地は固定資産税評価額の0.3%・建物は固定資産税評価額の0.4%
- 信託登記にかかる専門家報酬(不動産登記も専門家に任せる場合): 目安として8万円~15万円
- 信託中に賦課される税金(固定資産税・所得税など): 不動産の固定資産税評価額・信託中の収益により異なる※詳細は後述
上記費用に加え、受益者代理人や信託監督人を置く場合は報酬が発生する可能性があります。個別のケースでの初期費用の目安は、専門家に相談することで確認できます。
公正証書の作成費用
家族信託の諸費用のなかで最も大きく変動するのは、公正証書の作成費用です。
日本公証人連合会では、目的の価額(=信託財産の評価額)に応じて全国統一で下記費用としています。
| 信託財産の評価額 | 作成費用 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 1万7,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 2万3,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 2万9,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円+超過額5000万円ごとに1万3000円 |
| 3億円を超え10億円以下 | 4万5000円+超過額5000万円ごとに1万1000円 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円+超過額5000万円ごとに8000円 |
上記以外にも、契約発効の証明に欠かせない確定日付(=公正証書の作成日)の付与をはじめとし、下記事務手数料が定められています。
【公正役場で生じる諸事務手数料】
- 確定日付の付与: 1通につき700円
- 正本・謄本の送達: 1400円
- 送達証明: 1通につき250円
- 正本・謄本の交付: 1枚につき250円
- 証書等の閲覧手数料: 1回につき200円
家族信託に係る税金
信託財産に対する課税はすべて受益者に対するもので、①信託設定時・②信託中・③信託終了時・④受益権移転時の4つのタイミングで生じます。
- 信託設定時: 委託者≠受益者で契約を結んだ場合(=他益信託)は贈与税がかかります。反対に、委託者=受益者である場合(=自益信託)は課税されません。
- 信託中: 先述で触れた通り、信託財産から発生する収益に対しては所得税が課せられます。信託財産に含まれる不動産に対しては、収益を生んでいない場合でも固定資産税が賦課され、これは不動産管理の通常費用として受託者が負担するのが一般的です。
- 信託終了時: 信託が終了して特定の人に財産が属するときは、信託財産を受け取る人が受益者かどうかにより課税有無が異なります。
- 受益者がそのまま財産を受け取る場合は課税されませんが、受益者以外の人が財産を受け取る場合は権利の無償移転があったとして「贈与税」が課せられます。
- 受益権移転時: 受益権の移転は、受益者の死亡・権利売却・無償譲渡のいずれかによって起こります。死亡による移転は「相続税」、権利売却による移転は「譲渡所得税」、無償譲渡による移転は「贈与税」が新しい受益者に課せられます。なお、賃貸物件の売買等で得たときにかかる不動産取得税は、原則として課税されません。ただし、非課税となるのは「(a)自益信託で委託者以外に受益権が移っていない」「(b)信託終了時に委託者かその相続人が不動産を取得する」の2要件が満たされているあいだのみです。
家族信託を検討すべき人
被相続人となる予定かつ下記のような事情を抱える人は、家族信託を前向きに検討してはいかがでしょうか。
具体的には次のような人が家族信託を検討するとよいでしょう。
本人や家族に判断能力に不安、もしくはそうなる可能性が
家族構成員に高齢者や障がい者が一人でも存在する場合、将来に備えた財産管理の仕組み作りが急がれます。
被相続人が世帯主としてパートナーや障がいのある子を扶養する世帯では、被相続人の状態変化とともに家族全体が“共倒れ”しかねません。
委託者の健康状態にかかわらず財産管理できる「家族信託」は、被相続人の認知症発症から死亡後まで、判断能力に不安のある要支援を一括で長期的に支えられます。
本人が会社経営や個人事業主
事業承継を予定しているケースでは「先代オーナーを委託者・後継者を受益者」とする家族信託が理想的です。
自社株(あるいは他の事業用資産)を信託財産とすることで、贈与税の賦課を回避しながら経営権移転を実施できます。
また、事業に対する支配権は先代オーナーに留保できるため、後継者の育成が終わるまでは先代の経営判断を事業に反映させられます。
二次相続対策をしたい
子のいない家庭や再婚家庭で懸念されるのは「配偶者の兄弟姉妹」や「先妻・先夫の子」などの繋がりの希薄な親族に相続権が生じるリスクです。
懸念していたことが起こるのは、被相続人のあとに相続人が亡くなったとき(=二次相続)以降であり、遺言書でリスクを排除できないのは前述の通りです。
家族信託であれば、受益権移転先あるいは信託終了時の資産承継先を「委託者自身の兄弟姉妹」や「現配偶者の子」などと指定しておくことで、遺言書では不可能な”二次相続以降の部外者排除”が実現します。
財産に占める不動産比率が高い
不動産は管理行為を必要とするタイミングが多く、収益目的のものであれば売却や改築などの判断もスピーディさが求められます。所有者の高齢化が進めば、正しい管理運用判断が徐々に行えなくなり、後見が開始されるまでに荒廃や多額の赤字を招きかねません。
そこで、財産に占める不動産比率の高い家庭では、所有者の健康状態が良好なうちに次世代に委託するなど、管理運用に空白を生じさせない工夫が必要です。
また、不動産の”争続”の原因になりやすい性質を考慮すると、信託契約で先々の承継プランを組んでおくのは生前準備として有効です。
家族信託の活用例
ここでは、家族信託の検討理由に多い「認知症リスク」「障がいのある子の将来に対する不安」にどう対処できるのか、信託の活用例を紹介します。
認知症に備える
最初の例は、被相続人夫婦がそろって認知症リスクを抱えており、なるべく生前のうちから子に財産管理を委譲しておきたいと考えるケースです。
父を委託者兼第一受益者・母を第二受益者・息子を受託者とし、母の死亡時点で資産を息子に承継させて信託終了とする家族信託を設計します。
夫婦のうちどちらが先に認知症を患っても、息子による財産管理や給付が途切れることはありません。
障がいを持つ子に財産を残す
次の例は、被相続人が障がいを持つ子の財産管理を行っているケースです。
父を委託者兼第一受益者・母を第二受益者・息子を第三受益者とし、受託者は適当な信頼できる人物に任せた上で、息子の死亡時点で養護施設に資産承継させて信託終了とする家族信託を設計します。
家族それぞれの健康状態にかかわらず適切に財産管理を行える上、息子が遺言書を残せないために国庫に帰属するはずだった財産も、いずれしかるべき機関で役立ててもらえます。
家族信託の依頼
家族信託のコンサルティングは司法書士・税理士・弁護士のいずれかに委ねられます。依頼先を検討する際は、専門職により得られるサポートが違う点に注意しましょう。

家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託のイメージが固まっている場合は、書類作成や申請業務に長けた「司法書士」への依頼がおすすめです。信託内容の契約書への落とし込みから信託登記まで、必要な手続きを一括で任せられます。
【司法書士のサポート範囲】
- 信託契約書原案の作成
- 信託登記の手続き全般
- 成年後見人制度に関するアドバイス
- 遺言書作成のフォロー
家族信託を税理士に依頼するメリット
税理士は家族信託の設計そのものではありません。しかし、相続開始までにかかる課税額をシミュレートした上で節税テクニックを提案することで、間接的に生前準備の全体像を示せます。
さらに、信託で煩雑になりやすい税申告の手続きも任せられます。
【税理士のサポート範囲】
- 課税額のシミュレート
- 適用できる税制の提案
- 財産全体に対する信託割合の提案
- 課税毎の申告手続き代行
家族信託を弁護士に依頼するメリット
弁護士は相続法や判例に照らし合わせて“遺産の流れ”を組めるエキスパートです。
家族がイメージする信託のかたちを診断し、将来のトラブルに発展する可能性を排除できるよう設計や既存制度での補強等のコンサルティングが受けられます。
書類作成も得意としており、信託契約書原案・遺言書・任意後見契約などの作成も任せられます。
【弁護士のサポート範囲】
- 相続トラブル(遺留分侵害額請求など)への対策
- 要望に合わせた家族信託の設計
- 遺言書作成・成年後見人制度の利用サポート
- 信託設定時の契約書作成
まとめ
家族信託は、信託設定と同時に信頼できる人による受託行為が始まる“即効性”、家裁の介入なしで意のままに財産管理手法がとれる“自由度”の2点を兼ね備えることから、認知症への備えとして最適です。
二次相続以降も対象とする「遺言機能」も既存の制度にはみられません。
信託財産として切り出された資産の安全性についても、被相続人本人に対する破産処理(債権者分配や強制執行)から免れられる利点があります。
一方で、信託中の所得税や贈与税の仕組みが分かりづらく煩雑な点や、既存の制度で補うべき弱点があることに注意しなければなりません。
また、信託内容を取り決める話し合いでもめ事に発展してしまう懸念もあります。家族信託を取り決める際は、なるべく専門家のコンサルティングを得ましょう。
話し合いの方向性から信託設計、さらに節税アドバイスや登記等の諸手続きまでのトータルサポートがあることで、信託は長期安定的に機能します。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。