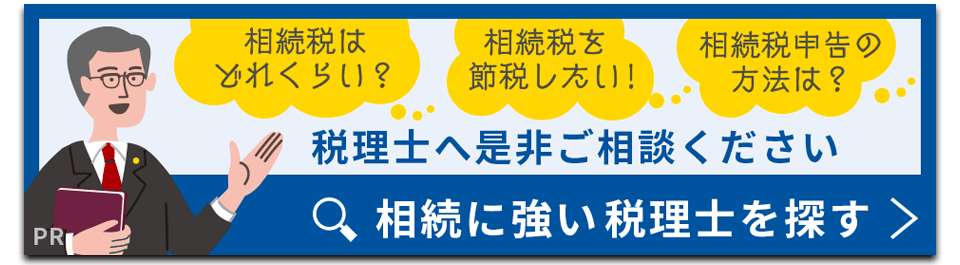「住んでいる家の相続税ってどうなるの?」「亡くなった人が住んでいた家の相続税がかからないって本当?」など、住んでいる家の相続税について疑問がある方も多いです。
実際には相続税がかからない場合もありますが、そのためには一定の要件を満たす必要があります。
それではどのような場合に相続税がかかり、またかからないのでしょうか?
この記事では住んでいる家の相続税について詳しくご説明いたします。
目次
1. 住んでいる家の相続税には「小規模宅地等の特例」が適用できるので相続税がかかりにくい
相続人が現在住んでいる家には「小規模宅地等の特例」が適用できるため、相続税が減額できる場合が多いといえます。
ただし一定の要件があり、その要件を満たせない場合は適用できませんので、その時は税額の減額を受けることができません。
また減額の割合についてもその人の相続の状況によって変わってくる場合があります。
それでは小規模宅地等の特例について詳しくご説明します。
1-1 小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続が始まる直前に被相続人などが事業または居住に用いていた宅地等について一定の条件を満たした場合、その宅地等のうち一定の面積までの部分は相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、規定されている区分に対応してそれぞれ減額することができる相続税の特例です。
この宅地等とは、土地や土地の上に存在する借地権や地上権などの権利のことも指します。
ただし別の特例を適用していることにより、小規模宅地等の特例が受けられない場合があります。
受けられないのは、「相続時精算課税に係る贈与」によって取得した宅地等及び「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の特例を受けた特例事業受贈者係る贈与者、または前記の「納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける特例事業相続などに係る被相続人から相続などで取得した特定事業用宅地などです。
1-2 小規模宅地等の特例ができた背景
相続財産の金額の構成比は、発表されている平成28年を例にすると、土地が38.0%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%となっています。
このように、土地は相続財産の中で最も比率が高いものとなっています。
その中で、被相続人が亡くなり相続が発生した際に住んでいた土地や事業を引き継ごうとしても、その土地にかかる相続税が高額の場合、相続税を支払うために土地を現金に替える必要が出てくるかもしれません。
同居していた人が相続したのに相続税のために家を失ってしまう、また事業を引き継ごうとしたけど会社建物・建物のある土地を相続するためにはその土地などを引き払わないといけなくなる、そんな本末転倒な状況を避けるために小規模宅地等の特例は存在しています。
小規模宅地等の特例は相続人の生活基盤を失わせないための制度です。
1-3 つまり親の家に住む・同居すると節税対策となる
つまり小規模宅地等の特例は、簡単にいうと、相続する親の家に相続の開始後に住むか相続の開始前から同居している場合、適用条件を満たしますので適用が可能です。
この特例を適用・利用することで最大80%の相続税の減額なので、大きく相続税額を減らすことができ節税効果が期待できます。
小規模宅地等の特例の適用条件について、詳しくは相続する土地などの区分ごとに次のトピックで詳しく説明します。
1-4 ただし住んでいる家とその他の財産を別々に計算するのではないことに注意
ただし小規模宅地等の特例を適用する時も、相続財産から相続税を計算するにあたって相続財産の総額を考えるという方法は変わりません。
特例適用後も基礎控除の対象となりますし、基礎控除よりも計算した相続税額が上回った場合は相続税が発生します。
基本的には、以下のように相続税課税評価額を算出します。
相続税課税評価額総額=相続した土地(小規模宅地等の特例適用後の金額)+他の相続財産の相続税課税評価額
この相続税課税評価額の総額を遺産分割がある際は協議によって決定した割合、または法定相続分で分割し、相続人それぞれの相続税額を算出します。
2. 住んでいる家の相続税に小規模宅地等の特例を適用できる条件
それでは小規模宅地等の特例について、詳しい適用条件をみていきます。
一口に住んでいる家といっても、居住の目的のみに用いている、自宅兼店舗として使っているなどバリエーションがあります。
小規模宅地等の特例は宅地の利用ごとに区分され、評価額の減額条件が変わってきます。
また前提として小規模宅地等の特例の対象となる宅地などは、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかであることが必要です。
2-1 特定居住用宅地の場合
特定居住用宅地とは相続が始まる直前に被相続人等の居住に用いられていた宅地のことをいいます。配偶者が取得する場合は条件なく適用することが可能です。
同居していた親族が取得する場合も、その親族が相続した宅地等を相続税の申告期限までに有していることのみを条件に、特例を適用することができます。
同居していない親族が取得する場合は以下のような条件があります。
①居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
②被相続人に配偶者がいないこと。
③相続が開始する直前において、被相続人が居住していた家屋に居住していた相続人がいないこと。
④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
2-2 特定事業者宅地の場合
相続が開始する直前において被相続人などの事業の用に供されていた宅地などで、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
ただし不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業など一定の事業を除きます。
一定の要件は以下の通りです。
・被相続人が事業に用していた宅地等
事業継承要件:その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること
保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業に用していた宅地等
事業継承要件:相続の開始する直前からその申告期限まで、その宅地等の上でその事業を営んでいること
保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
2-3 特定同族会社事業用宅地の場合
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業に用いられていた宅地等で、一定の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
ただし一定の法人の事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業など一定の事業を除きます。
また、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超を有している法人をいいます。
つまり、これは家族経営の小さな会社を想定しています。
・一定の法人の事業に用いられていた宅地等
法人役員要件:相続税の申告期限においてその法人の役員であること。
保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
2-4 不動産貸付用宅地の場合
相続開始の直前において被相続人等の不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などの事業に用いられていた宅地等で、それぞれの要件の全てに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
その相続の開始前3年以内に新しく貸付事業に用いられた宅地である3年以内貸付宅地等は除きます。
・被相続人の貸付事業に用いられていた宅地等
事業継承要件:その宅地等にかかる被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業をおこなっていること
保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に用いられていた宅地等
事業継続要件:相続の開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等にかかる貸付事業を行っていること
保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
3. 住んでいる家の相続税に対して小規模宅地等の特例で軽減できる税金はどのくらい?
住んでいる家に対して小規模宅地等の特例が適用できる場合について説明してきました。
小規模宅地等の特例を利用すると相続税が減額されますが、それではどのくらい相続税が軽減されるのでしょうか?
特例適用時の相続税の減額割合については、宅地等の種類、またその相続する宅地等の面積によって適用が変わってきます。
なお2つ以上を選択する場合は、限度面積を足した面積が限度面積となりますので注意が必要です。それでは宅地等の種類ごとに詳細を見ていきましょう。
3-1 特定居住用住宅の場合
特定居住用宅地とは相続が始まる直前に被相続人等の居住に用いられていた宅地のことをいいます。
|
限度面積 |
330㎡まで |
|
減額率 |
80% |
3-2 特定事業用宅地の場合
相続が開始する直前において被相続人などの事業の用に供されていた宅地などで、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
|
限度面積 |
400㎡まで |
|
減額率 |
80% |
この場合の事業は店舗、工場などを指し、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などの貸付事業は含みません。
3-3 特定同族会社事業用宅地の場合
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業に用いられていた宅地等で、一定の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
ただし一定の法人の事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業など一定の事業を除きます。
|
限度面積 |
400㎡まで |
|
減額率 |
80% |
3-4 不動産貸付用宅地の場合
貸付事業用の宅地等の場合、3つの場合に分かれます。
①一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業に用いられる宅地等
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業など一定の事業を除きます。
|
限度面積 |
200㎡まで |
|
減額率 |
50% |
②一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業に用いられる宅地等
|
限度面積 |
200㎡まで |
|
減額率 |
50% |
③被相続人等の貸付事業用の宅地等
|
限度面積 |
200㎡まで |
|
減額率 |
50% |
4. 配偶者が住んでいる家の相続税には「配偶者の居住権」が適用できる
「配偶者居住権」は令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
簡単にいうと住んでいる家を夫婦で住んでいる場合、配偶者が亡くなった際に残された配偶者がそのまま住んでいた家に無償で居住することができる権利です。
この配偶者居住権は小規模宅地等の特例を適用した際にも使うことができるのでしょうか?また、併用を希望する際、何か条件はあるのでしょうか?
4-1 配偶者の居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、残された相続人である配偶者が、亡くなった配偶者が所有していた建物に、自身が亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができるという権利です。
結論からいうと、小規模宅地等の特例と配偶者居住権は同時に適用することが可能です。
小規模宅地等の特例は土地のみに適用することができ、建物には適用することができません。
また、配偶者の居住権は建物の居住権に対して適用することになりますので、競合しません。
つまり、配偶者居住権が設定された家屋の敷地となっている土地の相続税課税評価額について小規模宅地等の特例を適用することは可能であるということです。
4-2 配偶者の居住権ができた背景
建物の価値を所有権と居住権に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件のもとで居住権を取得することで、亡くなった被相続人と共に住んでいた家に引き続き済み続けることができます。
これは相続開始時に相続人が配偶者以外もいる場合、残された配偶者が家屋を取得してしまうと、家屋と家屋のある敷地の相続税評価額がそのまま相続財産の分割した後の資産として計算されてしまいます。
その結果、居住するために家屋の所有権を取得したために生活費とすべき現金などが手元に残らないことになります。
これでは生活が立ち行かなくなるため、所有権自体は残った配偶者以外の他の相続人に取得させ、残った配偶者は居住権と現金などを相続することになります。
所有権ではなく居住権ですので、処分に制限がかかる分、相続課税評価額が抑えられます。
そのため、民法改正前よりもより多くの現金を相続することが可能になり、生活費に十分充てられる分の現金を手に入れることができます。
5. 住んでいる家の相続税評価額の計算方法
小規模宅地等の特例を適用するのは住んでいる家が上に建っている土地に対してです。
ではその土地の相続税評価額はどのように計算するのでしょうか?
住んでいる家は土地と建物により構成されています。
相続税評価額を算出する際、つまり住んでいる家の価値を金額として出す場合、その2つは別々に分けて計算します。
5-1 一戸建て・一軒家の場合も土地と建物は別々で計算する
住んでいる家は土地と建物でできており、相続税評価額は別々に計算します。
そして、別々に計算したものを合算して、住んでいる家そのものの相続税評価額を算出します。
これは住んでいる家が一戸建て・一軒家の場合も当てはまります。
小規模宅地等の特例を適用する際は、算出した相続税評価額の総額で減額割合を乗じて算出するのではなく、土地のみの相続税評価額に乗じる必要があることに注意してください。
5-2 土地の相続税評価額の計算方法
それでは土地の相続税評価額はどのように計算するのでしょうか?土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つです。
路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域で使うことができる評価方法です。
主に市街地は路線価が定められており、郊外では定められていないところも存在します。
路線価とは、路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額の事をいいます。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正してから、その土地の面積を乗じることで算出することができます。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
この一定の倍率は地域により変動します。
路線価及び評価倍率は国税庁のサイトにて確認することができます。
5-3 住んでいる家の相続税評価額の計算方法
土地の評価方法は上記の路線価方式・倍率方式の2種類を土地の所在地によって使い分けます。
建物、つまり家屋の評価は固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
なお賃貸されている土地や家屋については権利関係に応じて評価額が調整され、減額されます。
・土地の相続税評価額を路線価方式で算出した場合
住んでいる家の相続税評価額=土地の相続税評価額+建物の相続税評価額=路線価×土地面積(㎡)×補正率+建物の固定資産税評価額
・土地の相続税評価額を倍率方式で算出した場合
住んでいる家の相続税評価額=土地の相続税評価額+建物の相続税評価額=土地の固定資産税評価額×評価倍率+建物の固定資産税評価額
6. 住んでいる家の相続税の計算にも使える「基礎控除」
相続税を計算する際に、必ず控除されるものがあります。それは「基礎控除」です。
小規模宅地等の特例を適用する際にも、まずはこの基礎控除を相続財産の総額から控除してから、特例を適用して実際の相続税額を計算します。
それでは基礎控除とはどういったものなのでしょうか?また基礎控除の額はどのように算出するのでしょうか?
6-1 基礎控除とは
そもそも相続税とは、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合にのみ発生する税金です。
相続税は全ての亡くなった方についてかかってくるわけではありません。
法改正により平成27年に基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象の人口が増えましたが、それでも相続が発生した方のうち相続税が発生しているのは毎年約8%の人たちです。
基礎控除は、まず相続財産の総額について金額を出し、その金額に対してその相続に対応した基礎控除額を控除し、またその相続に対応した税率を乗じることにより相続税の総額を算出します。
最終的に、算出された相続税の総額について、相続人で実際に財産を取得した割合に応じて分割します。
6-2 基礎控除の計算方法
基礎控除額は以下のように算出します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式を見ると、法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額が大きくなることがわかります。
相続税評価額の総額が基礎控除額の範囲内の場合、相続税を支払う必要がなくなるので、節税の効果が見込まれます。
それでは法定相続人はどのように規定されているのでしょうか?
6-3 法定相続人に含まれる人
法定相続人になれるのは、配偶者と血族のみになります。
相続人には順位があり、血族の場合、先順位の相続人が1名でもいる際は後順位の人は相続人になることができません。
配偶者:必ず相続人になります。
血族:順位が高い人が相続人になります。先順位に1人でもいた場合、後順位の人は相続人になることができません。
血族の順位については、以下のようになります。
第1順位:子及び代襲相続人(孫など)
子が既に被相続人の相続開始より以前に亡くなっている場合、代襲相続が発生します。
つまり子が相続する代わりに孫が相続することになります。
第2順位:両親などの直系尊属
被相続人よりも先の世代に属する場合は尊属といい、下の世代に属する場合は卑属といいます。
第3順位:兄弟姉妹及び代襲相続人
7. 住んでいる家の相続税の計算方法
それでは実際に住んでいる家の相続税の計算方法について検討します。
順序に従って計算をすれば、相続税は計算することができます。
STEP1.同居している家(持ち家)の相続税評価額を計算する
まず第一に、住んでいる家の相続税評価額を計算します。前述の通り、住んでいる家は土地と建物により構成されており、それぞれの相続税評価額を計算してから合算して総額を出して、住んでいる家の相続税評価額とします。
例として、市街地に所在している一軒家で、土地200㎡、路線価10万円、補正率1、家屋の固定資産税評価額1,000万円とします。
住んでいる家の相続税評価額=面積×路線価×補正率+家屋の固定資産税評価額
=200(㎡)×300,000(円)×1(補正率)+1,000(万円)=60,000,000+10,000,000(円)=7,000(万円)
STEP2.家以外の財産も合計した課税遺産総額を計算する
相続税を計算するには相続財産の相続税課税評価額の総額を計算する必要があります。
相続財産は検討している住んでいる家のように土地や家屋はもちろん、事業用財産である機械や器具、製品や有価証券、現金や預貯金も含まれます。
基本的には相続や遺贈によってもらうすべてのものが含まれます。
その中で、課税財産と非課税財産に分かれています。
今回の例の場合、住んでいる家以外に財産はありませんでした。
よって例の場合の相続財産の総額は、7,000万円となります。
STEP3.債務や葬式費用などを遺産総額から引き、課税遺産総額を計算する
借金などの債務や相続開始後直近でまとまったお金が必要となる葬式費用はまず相続遺産から差し引かれます。
今回の例の場合、被相続人に借金などの債務はなく、お葬式は100万円がかかりました。
相続財産の総額は7,000万円でしたので、お葬式代の100万円を差し引いて、6,900万円が残ります。
STEP4.基礎控除額を差し引く
算出した相続税課税評価額から、被相続人の相続に対応した基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
今回の例の場合、相続人は配偶者と子供が1人の合計2人でした。
よって基礎控除額は上の式にあてはめると、以下のようになります。
3,000万円+600万円×2=4,200万円
今回の例の場合の基礎控除額は4,200万円と計算できました。
この基礎控除額をSTEP3.の相続財産の額から差し引きます。
6,900万円-4,200万円=2,700万円
STEP5.相続人ごとに相続できる遺産総額を計算する
その相続ごとの相続人の分割に従って遺産を分割します。
法定相続分、遺書での指定相続分、もしくは分割協議によって、遺産分割の割合を決定します。
今回の例の場合、法定相続分により遺産分割することになりました。
遺産分割の割合は以下のようになります。
配偶者1:子1
2,700万円÷2=1,350万円
結果、1人1,350万円ずつ課税対象となる相続税課税評価額が算出されました。
STEP6.特例や控除などを差し引き、最終的な納税額を計算する
特例や控除を利用する場合、相続人ごとに適用できるものかどうか検討します。
今回の場合、配偶者には配偶者控除が適用できます。
配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち、課税対象の額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されない制度です。
この制度を適用した結果、配偶者は相続税を支払う必要がなくなりました。
今回の例の場合、子が土地を相続しました。
子は小規模宅地等の特例を適用したので、以下のように減額ができます。
土地の価格=6,000万円
土地の面積は小規模宅地等の特例の適用範囲内です。
6,000万円×80%=4,800万円
特例の適用により減額される額は4,800万円と算出できました。
結果、子も相続税を支払う必要がなくなりました。
このように特例の適用するか否かによって、相続税は大きく変わってきます。
8. 住んでいる家を相続するときの注意点
現在住んでいる家を相続することがわかっている場合、相続が開始する前に準備しておいた方がよいこともあります。
相続時のトラブルを避けるためにも、相続の可能性がある場合は備えておくことが大事です。
ではどのようなことを準備しておけば安心して相続財産を引き継ぐことができるのでしょうか?
注意点1.認知症になる前に遺産分割の内容を決め遺言書を書いておく
遺言書の作成には遺言者の意思能力が必要となります。遺言書は原則15歳以上であれば誰でも作成できます。
しかし有効な遺言書とするためには、遺言の形式を守って作成する必要があります。
遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と大きく3つあります。
その中でも自筆証書遺言はその名の通り自筆で用意することが可能ですが、パソコンで文書を作成したりすると無効になります。
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと民法に規定されているためです。
また、遺言について争いのある場合、認知症を患っていたかどうかは大きな判断基準となります。
書かれた当時に認知症であり、遺言を自身の意思で作成することが不可能であったと認められた場合にも遺言が無効になってしまいます。
余計なトラブルを避けるためにも、早めに遺産分割について明確に記された有効な遺言書を作成することをおすすめします。
注意点2.住んでいる家を相続したときの費用や維持にかかる金額を把握する
土地や家屋といった資産は突然大きく価値を変えません。
またかかってくる費用も、急なトラブルによる出費も可能性自体は否定できませんが、経年劣化が理由のリフォームなど予測の立てられるものが多いです。
相続時に慌てて計算したり見積もりを立てたりすると思わぬ勘違いで判断を誤る可能性があります。
予測の立つものですので早めからどれくらいの費用や維持費がかかるのか把握しておくことをおすすめします。
注意点3.共有名義はトラブルになりやすい
共有名義での相続はトラブルの元になりやすいです。
なぜなら、共有名義にしてしまうと、1人の独断で処分したり増築などの改変をしたりといったことができなくなってしまうからです。
必ず相続人同士の同意が必要になります。
同意がないと処分などの行為ができませんので、建物の利用、維持にとっても、また相続人間にとってもどんどん厄介なパターンになることもありえます。
共有名義はできるだけ避けて住んでいる家は単独で遺産分割できるように協議しましょう。
注意点4.相続した後は相続登記を行う
住んでいる家を相続した場合、相続登記が必ず必要になってきます。また、登記を行う際には相続税とは別に登録免許税がかかってきます。
なお相続の登録免許税は不動産の売買などによる権利移転の登記より少額で済むので、必ず登記をして名義を変えておきましょう。
9. 住んでいる家の相続税に小規模宅地等の特例を適用するには申告が必要
しかしこの小規模宅地等の特例ですが、適用して相続税課税評価額を減額させるには相続税申告時に手続きが必要になります。
この手続きを怠った場合、適用することができませんので注意が必要です。
手続きとしましては、相続税の申告書にこの特例を受けようとする旨を記載して、その上で小規模宅地等にかかる計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどの一定の書類を申告書と一緒に税務署へ提出します。
この添付書類につきましては、相続する宅地の区分などによって変わる場合がありますので注意してください。
共通して必要になるものとしては相続税申告書・戸籍謄本・遺言書のある場合は遺言書の写し・遺産分割協議書のある場合は遺産分割協議書の写し・遺産分割協議書のある場合は相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
10. 住んでいる家の相続税に悩んだら税理士に相談
相続税の手続きは申告書の作成について計算や書類を揃えることなど、いろいろな作業が必要となります。
慣れない方が行うには大変な作業です。また適切な申告を行わなければ、後々の税務調査で払わなくてもよかったはずの税金を払うことになってしまうかもしれません。
住んでいる家を相続しても、小規模宅地等の特例を申告時に適用しなければ相続税はかかってきてしまいます。
申告書作成について不安がある場合は税理士へご相談をおすすめします。
故人が残してくれた遺産をよりよい形で相続して受け継いでいくために、そしてご自身にとって一番良い形で税金を間違いなく納めるためにも、専門家である税理士にぜひ一度ご相談ください。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。