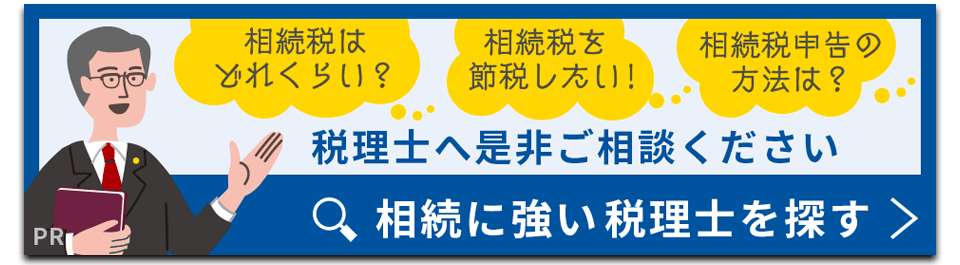相続財産の中に美術品・骨董品が含まれていた場合、相続税の申告はどのように変わってくるのでしょうか?また、申告が不要な場合もあるのでしょうか?
価値の鑑定や相続税評価額について、また相続時の注意点、美術品・骨董品を相続をする際のメリット・デメリットをこちらの記事にてご紹介いたします。
目次
1. 美術品・骨董品の相続税評価額の計算方法
相続財産の中に含まれていた美術品・骨董品について、専門的知識がなくては価値を判断するのは難しいです。
相続税の申告は根拠のあるきちんとした金額で示さなくてはいけません。
必ず専門家に相談や鑑定依頼をして価値判断をしてもらい、相続税評価額を決定しましょう。
1-1 物理的な価値+付加価値の「時価」で計算をする
相続財産の評価は、法律で相続財産の取得の時、つまり被相続人が亡くなって相続開始時における時価により決まると定められています。(「評価の原則」相続税法第22条)
美術品・骨董品等の時価とは、物理的な価値と付加価値の合計です。
貴金属でできた骨董品の価値を評価する場合、地金としての価値にそのもの自体の美術品としての付加価値がプラスされたものが時価となります。
付加価値は需要の高さや希少性から判断されますが、基本的には鑑定人に依頼し、真偽等を確かめてもらった上で証明書を発行してもらいます。その上で、種別・作者別・年代別等による市場価格や類似品価格を参考とし、相続税評価額を判断します。
比較的低額の美術品・骨董品についても、目利きの意見を参考にする等、簡易でも構わないものの合理的な方法で評価しなければなりません。
1-2 価値が低い場合は家庭用財産として計上する
相続財産には家の中にあるタンスや椅子などの家財道具やアクセサリーなどといった装飾品も含まれます。
国税庁の出している財産評価基本通達において、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下の場合はまとめて家財道具として評価することができる旨が示されています(財産評価基本通達128)。
つまり、相続する家庭用動産の相続税評価額が5万円以下であった場合は、家庭用財産としてまとめて計上することができます。
美術品・骨董品については全てまとめて5万円以下ではなく、動産ひとつにつき5万円以下という点に注意です。
2. 美術品・骨董品の相続税評価額の計算をするときの注意点
美術品・骨董品の相続税評価額の概要についてご説明しましたが、美術品・骨董品を相続する際には気をつけなくてはならない注意点があります。
誤った認識のまま相続税申告を行ってしまうと結果的に税務調査が入り、資産隠しとみなされてしまった場合には追徴課税が課される可能性もあるので特に注意が必要です。
注意点① 資産を隠すためには使えない
美術品・骨董品の相続はいわゆる資産隠しには使えません。
絵画や壺、器などの美術品・骨董品は資産として取り扱われ相続財産となります。
付加価値によって高額な資産となり得ますので、相続税申告時には鑑定を行う必要があります。
節税対策も度を超えると脱税行為となり、税務調査や相続税の加算税(追徴課税)の対象になってしまいます。悪質なケースでは、申告漏れとなっている美術品等の課税額に最大50%にも達する重加算税が上乗せされます。
そのような事態を避けるためにも、適切な節税方法で相続税申告をする必要があります。
注意点② 購入時の領収書や売却時の見積書・明細などは残しておく
相続税評価額の評価は専門家が行います。専門家が決めるその価格は精通者意見価格と呼ばれ、以下の価格などを参考にして専門家が判断します。
- 購入価格
- 流通している類似品の価格
- リサイクルショップなどの買取価格
- 美術商・骨董商などの査定価格
相続税評価額を評価する際に、購入価格や売却時の価格は参考の一つとなります。必ず残しておきましょう。
注意点③ 書画・骨董などの評価は有名品であっても価格差が出るケースがある
財産評価基本通達135条には以下のように定められています。
”(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。”
(1)に掲げる書画骨とう品とは販売業者の所有するもののことを指しているので、一般の方の相続の際にはこちらの項目は関係ありません。
「売買実例価格」は似たようなもの・同じようなものの市場価格のことをいいます。
「精通者意見価格」とは、わかりやすく言うと、専門的に詳しい人に教えてもらった価格ということです。
精通者意見価格は鑑定する人によって価格が変動してしまう可能性があります。そのため、鑑定業者を選ぶ際には慎重に検討する必要があります。
3. 特定美術品の寄託契約を締結していた場合は納税猶予及び免除となる
絵画などの美術品・骨董品がある場合、相続開始後すぐに相続税を納付しなくてはいけないのでしょうか?
結論からいうと、被相続人が死亡した日の翌日より10か月以内が相続税申告及び納付の期限です。
また、特定美術品の指定を受けている美術品に限りますが、美術館などと寄託契約を既に締結していた場合、納税猶予及び免除の対象となることがあります。それではどのような条件の時に納税猶予及び免除の対象となるのでしょうか?
3-1 特定の美術品の相続税の納税猶予及び免除が適用される条件
特定美術品とは、国宝や重要文化財の美術工芸品及び登録有形文化財の美術工芸品のうち、世界文化の見地から歴史上、芸術上、又は学術上特に優れた価値を有するものとされています。納税猶予及び免除が適用されるのは、以下の条件を満たす場合です。
①個人であること。
②美術館と特定美術品の長期寄託契約を締結していること。
③文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受け、その美術館にその特定美術品を寄託していること。
④特定美術品を寄託している者が死亡し、その特定美術品を相続または遺贈で取得した者が寄託を継続したこと。
⑤寄託相続人が担保を提供すること。
3-2 特定の美術品の相続税の納税猶予及び免除を適用する流れ
納税猶予及び免除の対象となると、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品にかかる課税価格の80%が納税猶予されます。また、その後寄託相続人の死亡などにより納税猶予されている相続分の納付が免除されます。
この制度を適用する流れは以下の通りです。
(1)相続開始前
①寄託先美術館の設置者と寄託契約の締結
②保存活用計画の認定
(2)相続開始
①認定保存活用計画について、計画の変更の認定申請(重要文化財)もしくは新たな計画の認定申請(登録有形文化財)を文化庁長官に行う。
②特定美術品の価格評価の申請を文化庁長官に行う。
価格評価の申請は相続が開始してから8か月以内に行う必要があります。
(3)相続税の申告期限までの間
①申告書の作成・提出
申告期限までに制度適用を受ける旨を記載した申告書を税務署に提出します。
申告後も引き続き寄託することで納税の猶予も継続されます。
4. 美術品・骨董品を相続するメリット
美術品・骨董品を相続するメリットは以下の2つがあります。
- 故人の大切にしていたものを引き継げる
- 資産として引き継げる
故人の大切にしていたものを受け継ぐことができるということがメリットとしてまず挙げられます。美術品・骨董品をそのままの形で残すことができれば、故人の思い出もそのまま残すことができます。
次に、資産価値を引き継ぐという点もメリットといえます。
有名作家の作品であるなど、値崩れの恐れが少ないものであればますますそのメリットは高まります。需要が高まった場合は時価が上がるので、今現在売却するよりも売却益が大きくなるといったことも考えられます。
また、美術品・骨董品もその他の相続財産と同じく、相続税評価額がほかの相続財産の評価額と合わせて基礎控除内であれば、相続税がかかりません。
基礎控除とは、相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば相続税の申告が不要になる制度です。
基礎控除内であれば相続するメリットはさらに大きくなります。
5. 美術品・骨董品を相続するデメリット
美術品・骨董品を相続するデメリットには以下のようなものがあります。
- 相続税が大きくかかる可能性がある
- 売却処分した場合、費用がかかる
- 売却処分した場合、売却利益には所得税と相続税が二重で課税される
相続する美術品・骨董品の価値が高い場合、相続評価額も高くなるので、相続税も相応に大きい金額になります。しかし、相続する動産は現金ではないため、相続人の資金力によっては相続税が支払えない可能性があります。
また相続時に売却処分した場合でも、業者の鑑定代が必要になること、また売却利益に対して所得税がかかってくるため相続税と二重に課税されることになり、この2点もデメリットといえます。
6. 美術品・骨董品を相続せず、手放すことは可能?
相続する際の相続税評価額を調べたり、他の相続財産と合わせて基礎控除額内かどうかの検討を行ったりと、美術品・骨董品を相続する際に手間がかかることは否定できません。
それでは、美術品・骨董品を相続せずに手放してしまうことは可能なのでしょうか?
結論からいうと、手放すことはもちろん可能です。
それではどのような方法があるのでしょうか?
6-1 国や地方公共団体に寄付をする
相続財産を国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄付した場合は、その相続財産は相続税の対象としないという特例があります。つまり然るべきところへ寄付をした場合、相続税を支払う必要がなくなります。
この寄付は無償で対象の相続財産を譲渡することをいい、この場合所有権は寄贈先へ移ります。
寄付をすることで相続財産自体を減らし、結果的に相続税を減らすことができます。
6-2 美術館へ寄託する
前述の特定美術品の納税猶予制度でも寄託契約について触れましたが、こちらの条件をクリアし認定された場合、対象動産の相続税の80%を納税猶予された上で寄託によって手放すことが可能です。この場合、依然として相続財産ではあり、所有権は寄託した相続人にあります。
専門の機関に美術品・骨董品を管理してもらいつつ、所有権そのものは手元に残ることになるのがメリットといえます。
6-3 売却・廃棄をする
相続により対象の美術品・骨董品の所有権は相続人に移るため、売却や廃棄などの方法で処分することが可能になります。また、売却によって現物から現金に換価することで、相続税の納付に直接充てることができます。
ただし、売却する際に業者に対して鑑定料などといった手数料を支払う必要が出てくるので、資産価値そのままの金額で現金が受け取れるわけではありません。また売却をして売却利益が出た場合は所得税もかかってくるため、所得税・相続税と二重で課税されることになります。
7. 相続財産に美術品・骨董品があった場合は税理士に相談
相続税の手続きは申告書の作成などいろいろな作業が必要となります。手続きは難しい部分も多く専門性が高いため、慣れない方が行うには大変な作業です。
また、美術品・骨董品があった場合、相続税評価額の計算のため専門家に依頼したり、他の相続財産と合わせての検討が必要であったり、手間が掛かってしまうことが多いです。
その上、適切な申告を行わないと、後々の税務調査で払わなくてもよかったはずの税金を払うことになってしまいます。
せっかくの遺産をよりよい形で相続して受け継いでいくために、そしてご自身にとって一番良い形で税金を正しく納めるためにも、相続税申告に迷われた際には専門家である税理士にぜひご相談ください。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。