-
トップ
-
選ばれる理由
-
料金
-
解決事例73
-
お客様の声口コミ32
選ばれる理由
-


「相続手続き全般」の依頼数年間約100件/実績のある司法書士が在籍
司法書士法人東京横浜事務所の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、このようなことでお悩みの方が多いのではないで…
続きを見る> -


他事務所で断られた複雑な案件もまずはご相談を
・遺産の数が多く、調べるだけでも大変な時間がかかりそう。 ・故人には子供がいなかったため、相続人を確定させるために膨大な量の戸籍集めが必要になりそう。 ・相続人…
続きを見る> -


東京・横浜の駅近立地20か所以上で相談可
お申込みご希望の方は、面談でのご相談会を実施いたします。お仕事でお忙しい方、あまり遠くまで出かけるのは難しいという方のために、東京横浜の20か所以上の駅近くに相…
続きを見る> -
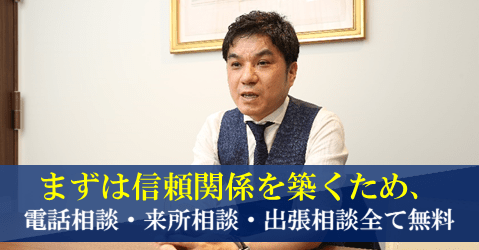

電話相談・来所相談・出張相談全て無料で実施!
司法書士法人東京横浜事務所では、電話相談、事務所相談、出張相談いずれも相談料は無料で実施しております。私たちの仕事は信頼関係がとても大切です。お客様との信頼関係…
続きを見る> -
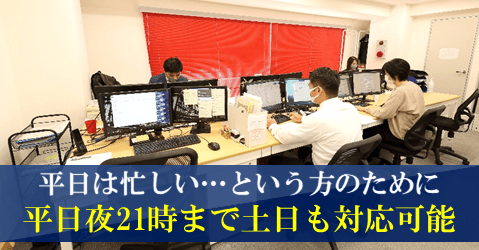

夜21時まで土日祝日も対応
お忙しい皆様のために、夜21時まで(最終面談開始時刻は20時)、土日祝日もご相談を受け付けております。仕事帰りに仕事場近くでのナイター相談や、休日に最寄り駅やタ…
続きを見る> -
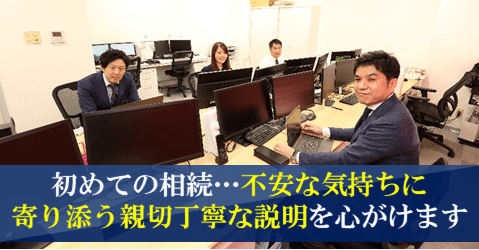

不安な気持ちに寄り添う丁寧な対応
初めての相続で不安なお気持ちに寄り添った対応をいたします。ゆとりのある面談時間を設け、親切丁寧な説明を心がけています。もちろん相談したからといって、契約を迫るよ…
続きを見る>

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
解決事例
-
成年後見
相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様と子供たち。
お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能…続きを見る -
相続手続き
遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様と子供と孫。
相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代…続きを見る -
相続手続き
母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)
遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮…続きを見る
司法書士法人東京横浜事務所の事務所案内
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、そのほかの約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
基本情報・地図
| 事務所名 | 司法書士法人東京横浜事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷 |
| アクセス | JRほか各線 渋谷駅より徒歩6分・東京メトロ 表参道駅より徒歩7分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00〜19:00 土曜10:00〜17:00 ※事前の予約で土日の面談も可能です |
代表紹介

田中暢夫
司法書士
- 代表からの一言
- 相続に関しては、難しい法律問題や手続きがたくさんございます。そのため、言葉にできない漠然とした不安を感じることがあるかもしれません。ですが、そういった不安やお悩みを解決するために我々のような専門家がいます。相談するだけで問題が解決することもございますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 資格
- 東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号 - 所属団体
- 東京司法書士会
- 経歴
- 長崎県で生まれる。
18歳の時にミュージシャンになることを夢見て上京。
それまで法律と全く無縁の世界にいたが、一念発起して司法書士を志す。
3度目の受験で司法書士試験に合格。
都内の大手司法書士事務所で勤務開始。
簡裁訴訟代理権取得および司法書士登録。
その後、所属事務所で主にお客様との面談業務を担当。2千人を超えるお客様との面談を経験するも、もっとお客様一人一人と向き合いたいとの思いから独立を目指し退職。
東京横浜司法書士事務所を設立、開業。
開業から3年目に業務拡大のため法人化。司法書士法人東京横浜事務所設立。 - 出身地
- 長崎県

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
選ばれる理由
「相続手続き全般」の依頼数年間約100件/実績のある司法書士が在籍

司法書士法人東京横浜事務所の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、このようなことでお悩みの方が多いのではないでしょうか?
☑相続手続きで何から手を付けて良いか分からない
☑相続手続きをお任せして円滑に終わらせたい
☑遺産分けが進まないのでアドバイスが欲しい
相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、最近ではインターネットや書籍で相続手続きに関する情報は一般の方が取得することもた易いですが、このような偏った知識だけで全ての手続きを円滑に進めることは困難と言えます。
このような場合においては、司法書士に「相続手続き全般(遺産整理)」を依頼するという選択肢を一度ご検討いただくと良いかと思います。平日に役所に行く手間、また場合によっては様々な窓口をたらい回しになってしまう手間、親族間での納得度を考えた際には、最良の選択肢でしょう。
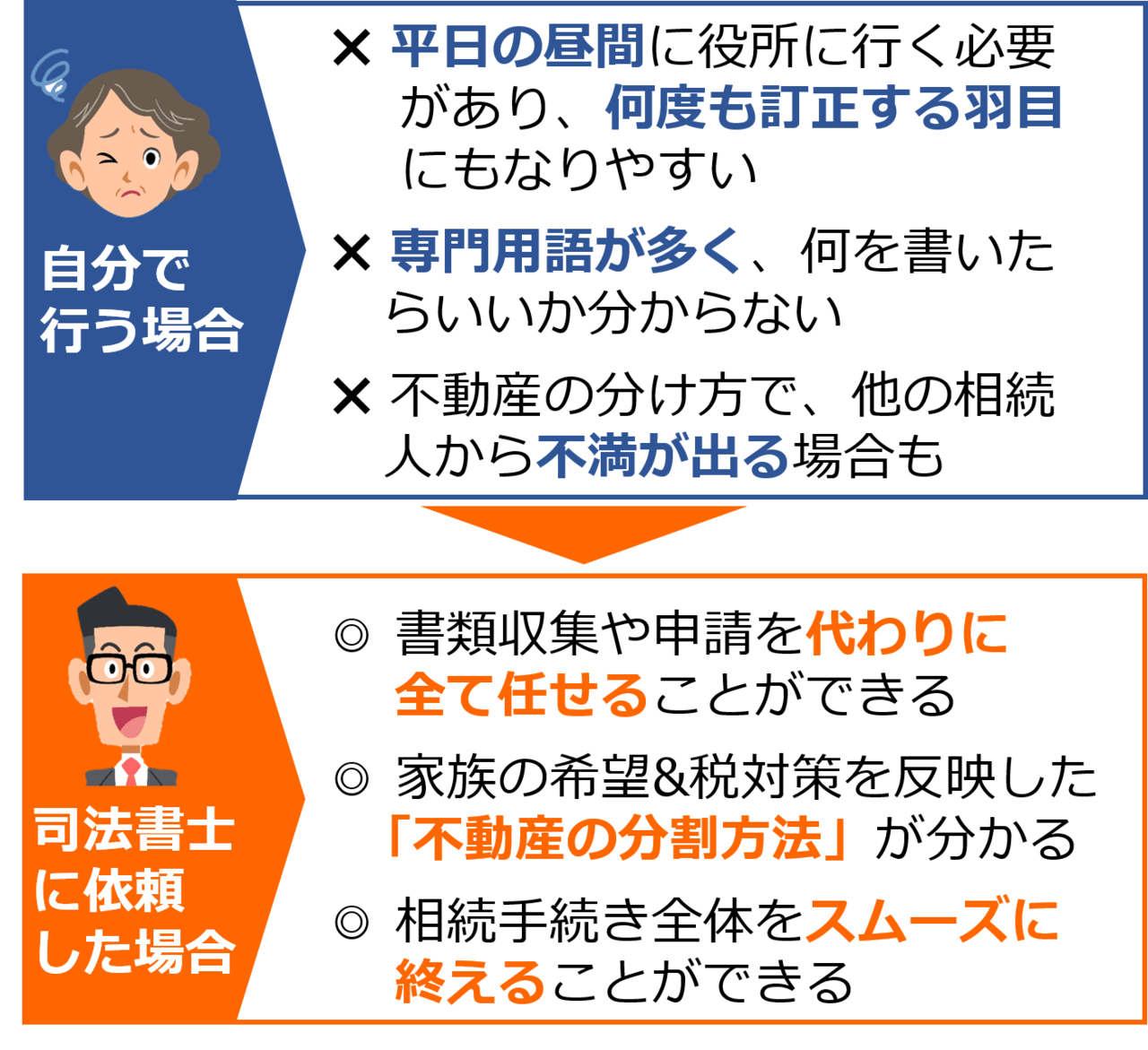
司法書士法人東京横浜事務所には「相続手続き全般」をまとめてサポートする相続手続き丸ごと代行サポート(遺産整理)は、2019年1年間で約100件の依頼実績がある司法書士が在籍しております。これは相続登記のみ等の簡易な依頼は除いた数字で、相続に注力している事務所でも通常年間10件ほどと言われております。
この依頼実績は司法書士一人当たりとしては日本トップクラスです。相続手続き全般といった包括的な内容だからこそ、豊富な知識と経験が物を言う分野でもあります。何事も、経験に勝るものはございません。どうぞ安心してご相談ください。
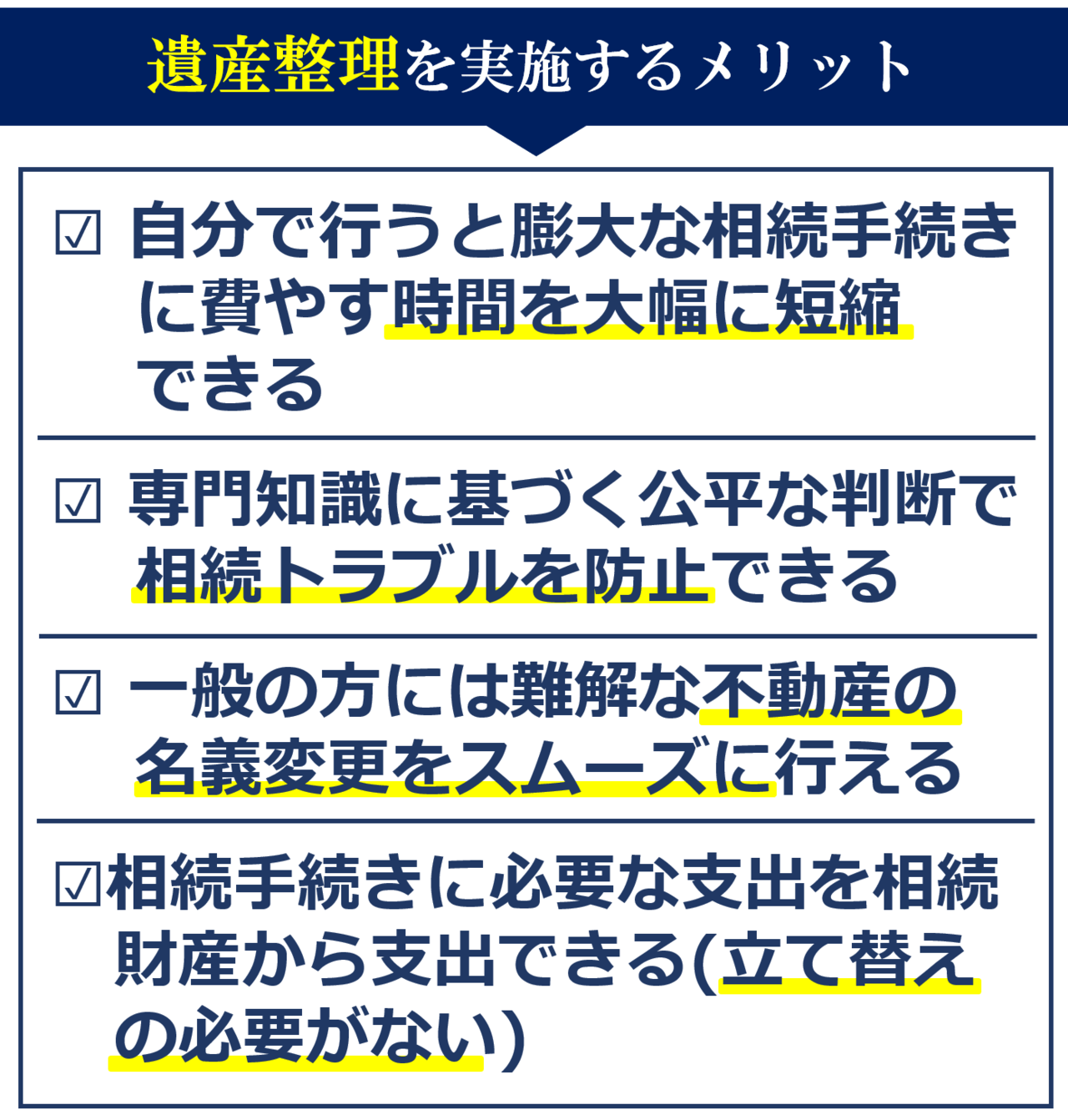
相続手続きでお悩みの方はまず当事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。私たちの仕事はお客様との信頼関係がとても大切と考え、お客様との信頼関係を築き、納得の上でご依頼いただくために、当事務所ではご依頼を検討中の方については、電話相談・来所相談・出張相談の全ての相談を無料としています。
他事務所で断られた複雑な案件もまずはご相談を

・遺産の数が多く、調べるだけでも大変な時間がかかりそう。
・故人には子供がいなかったため、相続人を確定させるために膨大な量の戸籍集めが必要になりそう。
・相続人の人数が多く、遠方に住んでいる人もいるので、遺産分割協議の調整が大変。
・相続人の中にほとんど面識のない人がいて、遺産分割についてどう切り出せばいいか不安がある。
このような複雑な事情はありませんでしょうか?
司法書士法人東京横浜事務所は、他事務所では断られるような難しい案件であっても積極的にお受けしています。そのため相続についてのありとあらゆるノウハウが蓄積されており、各専門家とのネットワークも豊富です。安心して、私たちに「まるごとおまかせ」ください。
東京・横浜の駅近立地20か所以上で相談可
お申込みご希望の方は、面談でのご相談会を実施いたします。お仕事でお忙しい方、あまり遠くまで出かけるのは難しいという方のために、東京横浜の20か所以上の駅近くに相談会場を設けております。渋谷、池袋、東京、横浜、自由が丘、二子玉川、たまプラーザなど、ほとんどの会場が駅から5分以内の大変便利な立地です。土日や夜間のご相談も承っております。もちろん完全個室ですので安心してお越しください。サービスについてご不明点・ご質問などございましたら、些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽に司法書士法人東京横浜事務所までお問合せください。

電話相談・来所相談・出張相談全て無料で実施!
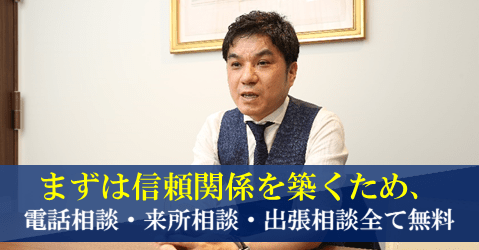
司法書士法人東京横浜事務所では、電話相談、事務所相談、出張相談いずれも相談料は無料で実施しております。私たちの仕事は信頼関係がとても大切です。お客様との信頼関係を築き、納得の上でご依頼いただくために、当事務所ではご依頼を検討中の方については、面談を含む全ての相談を無料としています。
もちろん相談した結果、依頼しない場合も費用は一切いただきません。また、駅前相談会や通常の業務対応地域への訪問相談で出張料金をいただくこともありません。どうぞ、安心してご相談ください。

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!
夜21時まで土日祝日も対応
お忙しい皆様のために、夜21時まで(最終面談開始時刻は20時)、土日祝日もご相談を受け付けております。仕事帰りに仕事場近くでのナイター相談や、休日に最寄り駅やターミナル駅近くでの相談も可能です。平日昼間はお仕事のためなかなか時間が取れない方、家事や育児で忙しい方など、ぜひお気軽にご連絡・ご利用ください。
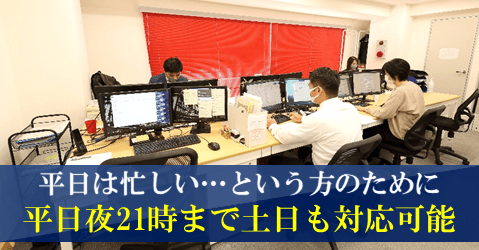
不安な気持ちに寄り添う丁寧な対応
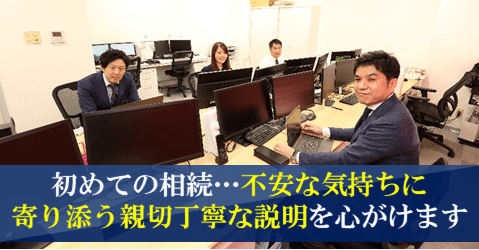
初めての相続で不安なお気持ちに寄り添った対応をいたします。ゆとりのある面談時間を設け、親切丁寧な説明を心がけています。もちろん相談したからといって、契約を迫るようなことはありません。相談だけで解決することもあるので、お気軽にお問い合わせください。
料金は、なんと銀行の1/5以下
当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」は、大手銀行の遺産整理業務と同等以上のサービスを1/5以下の料金でご提供いたします。遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他の約100種類の手続きについてもサポートしています。

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
対応業務・料金表
相続登記ライトプラン
サービスの概要
相続登記シンプルプラン:
・戸籍等の収集
・相続関係説明図の作成
・登記申請に必要な評価証明書等の取得
・登記申請書の作成及び登記申請
・登記識別情報の代理受領
・添付した書類の原本還付請求
※法定相続情報証明書の取得はプラス5,500円で承ります。
※遺産分割協議書の作成が必要な場合はプラス16,500円で承ります。
料金
87,780円
適用条件
・対象不動産の固定資産評価額が3,000万円以内(3,000万円を超える場合は500万円ごとに5,500円ずつ加算)
・対象不動産の数が3つ以内で同一管内(4つ目からは1つにつき5,500円加算、管轄外は1管轄につき2万2,000円加算)
・相続人等の数が4人以内、必要な戸籍等の数が10通以内(5人以上は1人につき5,500円加算、11通以上は1通につき2,200円加算)
・代襲相続、数次相続等の特別な事情がない(特別な事情がある場合は別途見積もり)
遺言書作成サポート
サービスの概要
自筆証書遺言作成:77,000円
・専門家による遺言相談
・専門家による遺言内容に関するアドバイス
・作成された遺言書のリーガルチェック(2回まで)
公正証書遺言作成:87,780円〜
・専門家による遺言相談
・遺言書案の作成
・公証人との事前打ち合わせ など
料金
77,000円~
・財産の数が多く、財産目録の作成が必要な場合は別途見積もりいたします。
・対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
・当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。
相続手続き丸ごとサポート
料金
217,800円~
※財産総額が1億円以下の場合、次の条件をいずれも満たすときは基本報酬額以外に追加の料金はございません(実費、遠方への出張費、税理士等への報酬等は別途かかります)。
・相続の対象となる不動産が同一管轄にあり2筆・2個以内。
・相続の対象となる預貯金口座、有価証券等が2手続先以内
・被相続人が被保険者となっている生命保険契約が1契約以内
・法定相続人および相続人以外の受遺者の数が3人以内。
・相続人間で遺産分割をめぐって大きな争いがない。
・裁判所に書類を提出する必要がない。
・その他通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情がない(相続人の中に行方不明者がいる、相続人や相続財産が一部海外に存在する等)。
贈与サポート
サービスの概要
不動産の生前贈与による相続対策をご希望の方のために、必要に応じて税理士による税務相談等も交えたうえでの相続対策コンサルティングを行い、贈与契約の締結から所有権移転登記までをトータルにサポートさせてていただくプランです。遺言書作成プランとの同時利用がおすすめです。
料金
109,780円~
相続不動産売却代理おまかせプラン
サービスの概要
当事務所がお客様の代理人となって、相続登記、不動産会社の選定、媒介契約の締結、売買価格の交渉・決定、売買契約の締結、代金決済まで売却に関するすべてを行わせていただくプランです。
入院中で自分では売却のために動くことはできない方、売却のための手続きが面倒なのでおまかせしたい方、売却物件が遠方にある方、公平性の面から相続人の代表者ではなく第三者に売却手続きや売却代金の分割までを任せたい方などにおすすめです。
必要に応じて不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士などをご案内することも可能です。
・相続登記に必要な一切の手続き
・不動産会社の選定、媒介契約の締結
・現地調査
・不動産会社との連絡・調整
・売買価格の交渉・決定
・売買契約の締結
・代金決済
・物件の引き渡し
・必要に応じて各相続人への売却代金の分配
・相続税申告が必要な方には税理士のご案内
料金
売却代金の0.5%〜要相談円
※本プランの不動産売却の代理行為は、司法書士法施行規則第31条の定める財産管理・処分業務にあたり、民法上の委任契約に基づいて行うものです。当事務所が主体となって不特定多数の売却先を募集する等の行為は宅建業法等で禁止されているため行うことができません。
※相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合はお受けできない可能性があります。
※遺産分割について相続人間で争いがある場合は本プランはご利用いただけません。
※費用、報酬については原則として売却代金からの清算となりますが、ご事情によっては登記費用等の一部を前もって預からせていただく場合もございます。
※相続不動産以外の不動産も代理人として売却をサポートさせていただくことが可能です。ぜひご相談ください。
相続対策まるごとおまかせプラン
サービスの概要
・相続総合コンサルティング
・相続税シミュレーション
・税理士による税務相談
・専門家による資産運用相談
・保険のご提案
・オーダーメイドの相続プラン作成
・財産目録の作成
・贈与契約書の作成
・贈与登記
・遺言書案の作成
・戸籍等の収集
・公証人との事前打ち合わせ
・公正証書作成当日の証人の手配
・家族信託など当事務所の他サービスが特別料金
料金
162,800円~
※税理士に税申告等を依頼される場合は別途税理士報酬がかかります。
相続対策コンサルティングプラン
サービスの概要
・相続対策コンサルティング
・個別ご提案書の作成
・必要に応じて遺言書作成、生前贈与、不動産運用・売買サポートなど
料金
33,000円~
※税務相談を伴う場合は55,000円〜、2回目以降の相談は1回につき22,000円

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
お客様の声
-
相続手続き
私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、紹介させていただきます
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 相続に関する手続きの多さ、準備する書類の多さ、手続きするための時間など本やネットから調べましたが、一人では到底で…続きを見る
-
相続手続き
私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、紹介させていただきます
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
相続に関する手続きの多さ、準備する書類の多さ、手続きするための時間など本やネットから調べましたが、一人では到底できないと悩んでおりました。
司法書士の先生に相談するにしても伝手もなく、ホームページにも手続きをする事業者がたくさんあり、信頼できる事業者を探すのが大変でした。
多くのホームページを読みましたが、貴事務所のものがわかりやすく平易な言葉で説明されていました。
先生との初回の相談では丁寧で素人相手にゆっくりとした説明をしていただき、心配が解消いたしました。
もし、私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、貴事務所を紹介させていただきます。この度は本当にお世話になりましてありがとうございました。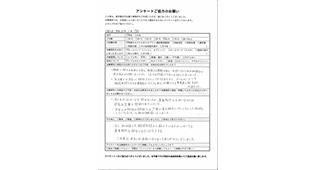

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
仕事終わりの時間に、地元で手続き等ができた事が最大のポイントでした
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 父親の死亡で預金等の整理、不動産の名義変更など、どのようにしたら良いのかまったくわからなかった。 財産の整理の…続きを見る
-
相続手続き
仕事終わりの時間に、地元で手続き等ができた事が最大のポイントでした
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
父親の死亡で預金等の整理、不動産の名義変更など、どのようにしたら良いのかまったくわからなかった。
財産の整理の他に、後見人の手続きまでわかりやすく指示いただき、少し時間はかかりましたが、無事に終わらせられてほっとしました。
平日、仕事をしていると時間を作って公共機関に出向くことがむずかしいのですが、仕事終わりの時間に、地元で手続き等ができた事が最大のポイントでした。その都度有給休暇を使うのは避けたかったのでとても助かりました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
「とにかく面倒」が解決しましたし、すべてに満足する結果でした
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 一つは、妻が書き残した鉛筆書き遺言書の有効性でした。具合の悪いなか何度も書き直ししながら作っていたもので、妻の気…続きを見る
-
相続手続き
「とにかく面倒」が解決しましたし、すべてに満足する結果でした
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
一つは、妻が書き残した鉛筆書き遺言書の有効性でした。具合の悪いなか何度も書き直ししながら作っていたもので、妻の気持ちを思うと役立つ内容になっていればと気がかりでした。
※幸い遺言書の出番はなく助かりました。妻の気持ちが通じていたのでしょうか。
二つは、相続は何をどうすれば、どう進めるのか、自分にできるか、とにかく面倒と言ったことでした。
※相続財産を整理する金融機関や法律事務所のあることを知り、この度、東京横浜司法書士事務所を選択・依頼しました。60日で完了し、「とにかく面倒」が解決しましたし、すべてに満足する結果でした。
三つは、依頼する事務所が満足する仕事をしてくれるかでした。料金、依頼内容、期日、報告書類などです。
※結果、期日に整理の報告を受けました。整った送付書類を見て依頼は正解だったと痛感しました。特に不動産関係は到底自分では叶わないことでした。改めてお礼申し上げます。
その他に
近く私が被相続人になります。相続人が面倒なく受け取り易い形で整理しておきたいと思っています。相続整理のほか、公共、企業、個人ら生前丸投げの事項とその可否などでしょうか。受け皿が欲しいものです。後見人制度は意に添いません。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
今後のことについての提案もしていただき大変助かりました
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 兄の急死により何から手を付けていいやら、特に遺産、相続税等不安でした。 担当者の方の説明で不安解消しました。親…続きを見る
-
相続手続き
今後のことについての提案もしていただき大変助かりました
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
兄の急死により何から手を付けていいやら、特に遺産、相続税等不安でした。
担当者の方の説明で不安解消しました。親切、丁寧でとても良かったです。又実家の遺品整理業者の紹介や銀行、証券会社の調査や今後事などの提案して頂き大変助かりました。
6ヶ月以上にわたり、大変お世話になり有難うございました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 初回の税理士法人との打ち合わせのときに司法書士の田中さんを紹介して頂き、次回の打合せで相続手続きの説明を受け、…続きを見る
-
相続手続き
相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
初回の税理士法人との打ち合わせのときに司法書士の田中さんを紹介して頂き、次回の打合せで相続手続きの説明を受け、特に信託銀行との比較をしながらの判りやすいものでした。また、適時、ご報告も頂き、質問等にも即座に解答して頂きありがとうございました。
相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。また信託銀行よりもかなり費用が安くなっていました。
田中様、色々ありがとうございました。二次相続時もよろしくお願い致します。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応して頂けました
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 まわりに相続にくわしい人もいなく、だれに相談すれば良いのかわからなく、初めは銀行の方にお願いしようと思いましたが…続きを見る
-
相続手続き
いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応して頂けました
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
まわりに相続にくわしい人もいなく、だれに相談すれば良いのかわからなく、初めは銀行の方にお願いしようと思いましたが、複雑ではない内容でも金額が高く、安心出来る事務所さんを探していました。
どのくらい金額がかかるのかわからなかったのでとても不安でした。
ホームページを拝見してお願いしましたが、相続を専門でされているという事で初めから親切に説明して下さり、金額もとても良心的でしたが、いろいろなご相談や質問にもしっかりと答えて頂け安心しました。
初めての事ばかりで、何をすればよいのかとても不安でしたが、相続に関する事はすべておまかせ出来て、きちんと理解ができました。
いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応して頂けました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
料金体系が明確だったので安心して任せられた
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 費用、手間、時間がどのていどかかるかわからなかった。 料金体系が明確だった。安心してまかせられた。 また機会…続きを見る
-
相続手続き
料金体系が明確だったので安心して任せられた
相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様
費用、手間、時間がどのていどかかるかわからなかった。
料金体系が明確だった。安心してまかせられた。
また機会があったらおねがいしたい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
誠実な対応にリラックスできました。
・専門家に相談するのははじめてなので少し緊張しました。 ・誠実な対応にリラックスできました。こちらの質問にも親切に答えてくれました。 ・母と離れて暮らしてる…続きを見る
-
相続手続き
誠実な対応にリラックスできました。
・専門家に相談するのははじめてなので少し緊張しました。
・誠実な対応にリラックスできました。こちらの質問にも親切に答えてくれました。
・母と離れて暮らしてることもあり自分では難しかったが、迅速に対応してくださって助かりました。やはり専門家に相談することは大事だと思いました。この度はお世話になりました。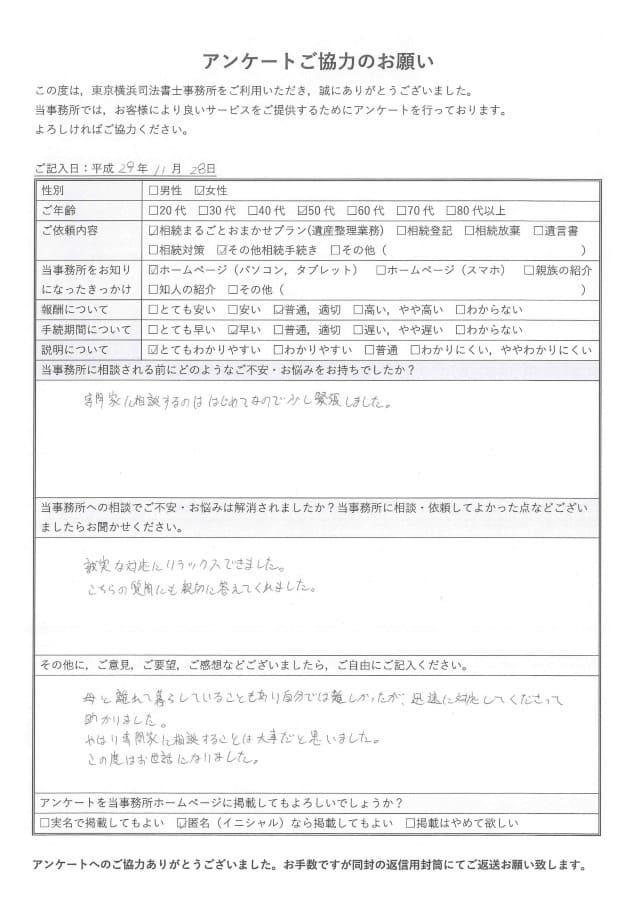

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
面倒なことは本当に全部おまかせできたのでよかったです。
・相談する前はどんな手続きが必要かわからず、うまく伝えられる自信もなかったので不安でした。 ・わかりやすいように丁寧に説明してくださったのでとても安心できまし…続きを見る
-
相続手続き
面倒なことは本当に全部おまかせできたのでよかったです。
・相談する前はどんな手続きが必要かわからず、うまく伝えられる自信もなかったので不安でした。
・わかりやすいように丁寧に説明してくださったのでとても安心できました。
・面倒なことは本当に全部おまかせできたのでよかったです。それと、手続きに関係ないことまで親身になって話を聞いてくださってありがとうございました。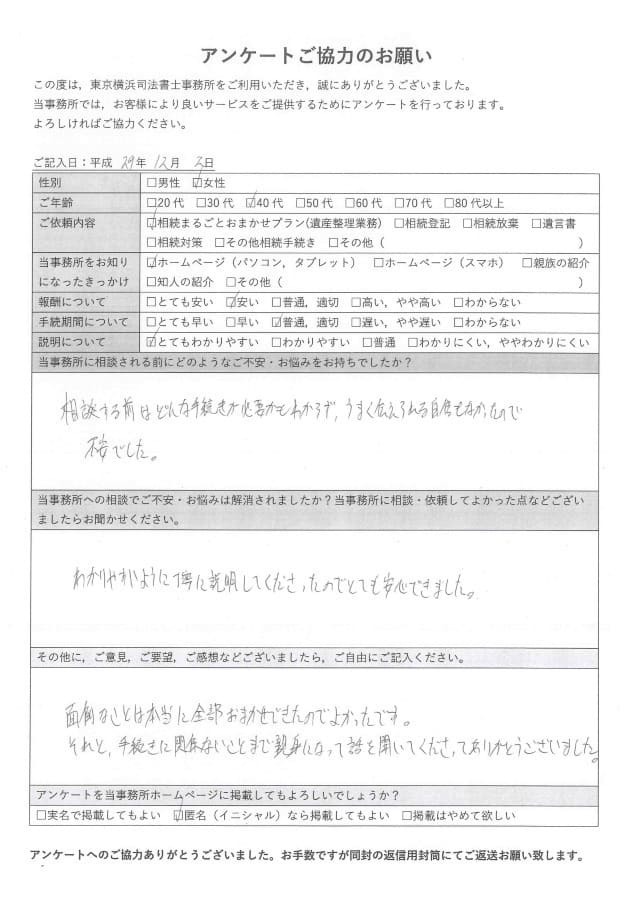

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
はじめから親切に対応していただき頼んで正解でした。
・父が亡くなりどこから手を付けていいかわからず、途方に暮れていたところこちらを知り思い切って頼むことに決めました。 ・初めての相談だったが、説明がとても分かり…続きを見る
-
相続手続き
はじめから親切に対応していただき頼んで正解でした。
・父が亡くなりどこから手を付けていいかわからず、途方に暮れていたところこちらを知り思い切って頼むことに決めました。
・初めての相談だったが、説明がとても分かりやすかった。いろいろ相談にのっていただいたので不安な気持ちが解消した。
・はじめから親切に対応していただき頼んで正解でした。専門家に任せてよかったと思います。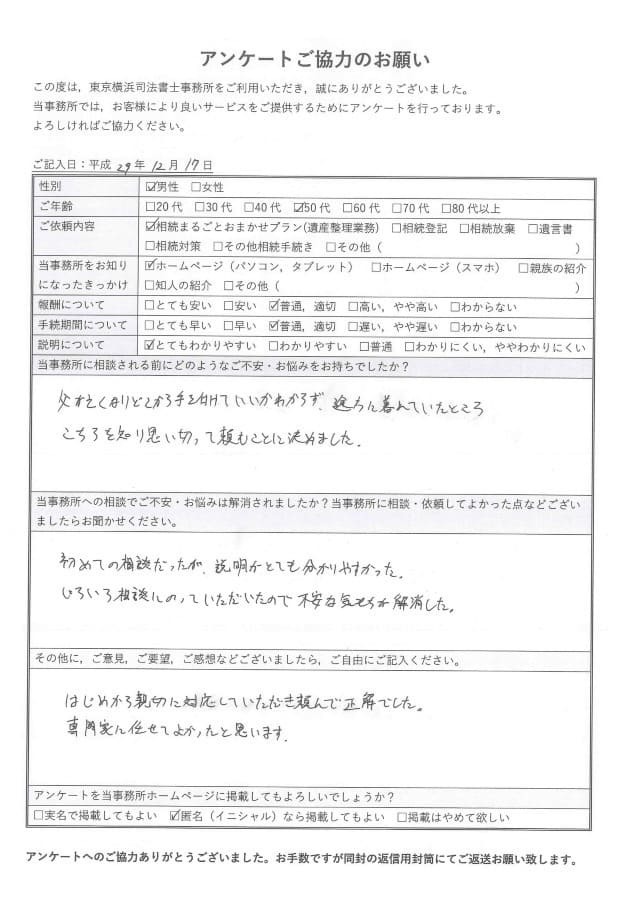

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
わかりやすく説明していただきよかったです。
・相続発生時何をしたら良いか、誰に何を頼んだら良いかわからず困った。(貴社のHPは理解しやすくとてもよかったです。) ・不安・悩みが解消されました。わかりやす…続きを見る
-
相続登記
わかりやすく説明していただきよかったです。
・相続発生時何をしたら良いか、誰に何を頼んだら良いかわからず困った。(貴社のHPは理解しやすくとてもよかったです。)
・不安・悩みが解消されました。わかりやすく説明していただきよかったです。
・ご説明を受け、理解したと思っても、時間がたつと疑問がわいてきて、何度も丁寧に説明いただきありがとうございました。処理が終了してやっと理解しました。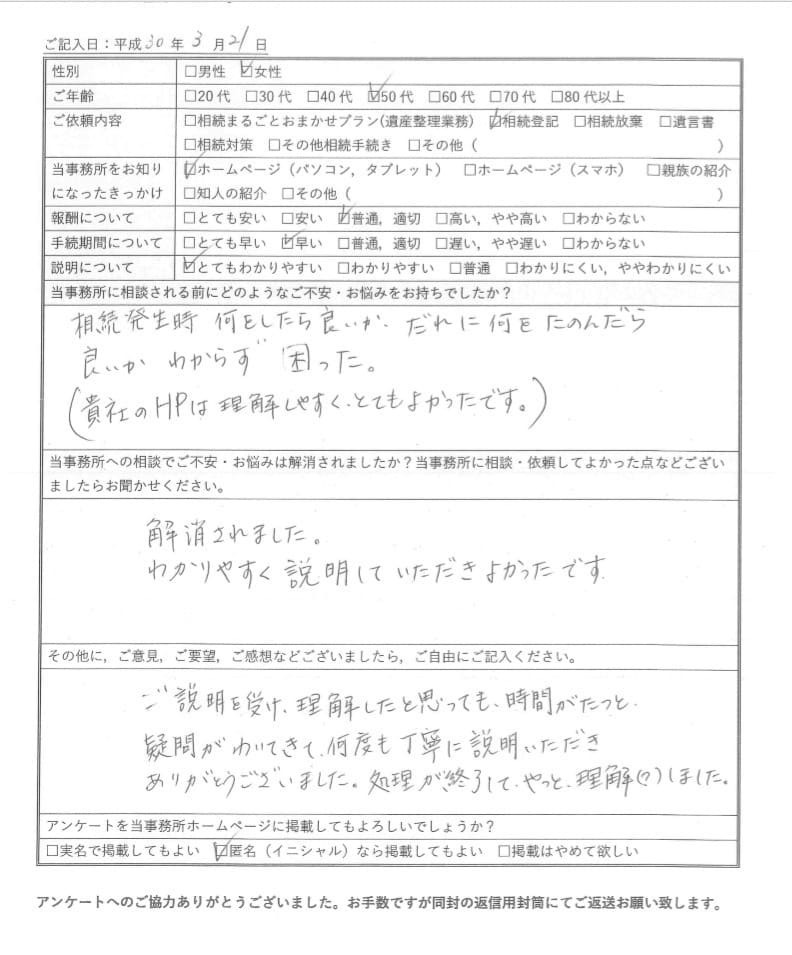

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。
・急に父が亡くなり、全く何をしていいのかわからなくて不安でした。 ・とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。 ・本当にいろいろと…続きを見る
-
相続手続き
とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。
・急に父が亡くなり、全く何をしていいのかわからなくて不安でした。
・とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。
・本当にいろいろとありがとうございました。又、何かあったとき、お願いしたいと思いますので、よろしくお願い致します。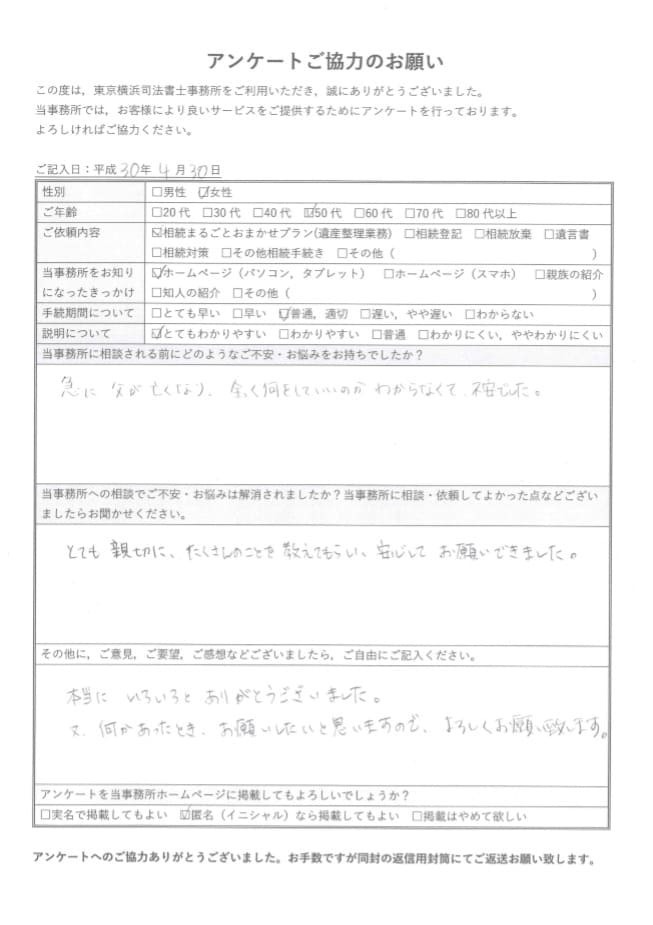

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
費用も良心的でした。
・相続手続きを自分一人で行うのは大変だと思い、手続きの代行を依頼したいと考えたが、費用の相場等がわからなかった。 ・最初の面会時に様々な疑問に答えていただき、…続きを見る
-
相続手続き
費用も良心的でした。
・相続手続きを自分一人で行うのは大変だと思い、手続きの代行を依頼したいと考えたが、費用の相場等がわからなかった。
・最初の面会時に様々な疑問に答えていただき、不安が解消された。また、費用も良心的であった。
・このたびは大変お世話になりました。有難うございました。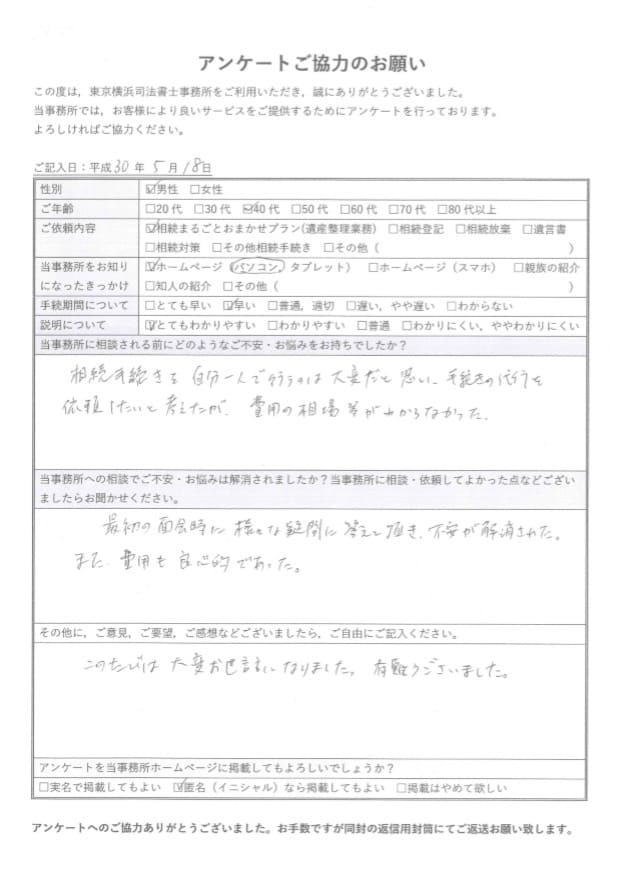

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。
・(相談前に不安だったことについて)手続きの煩雑さ、費用負担額について ・ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。…続きを見る
-
相続登記
ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。
・(相談前に不安だったことについて)手続きの煩雑さ、費用負担額について
・ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。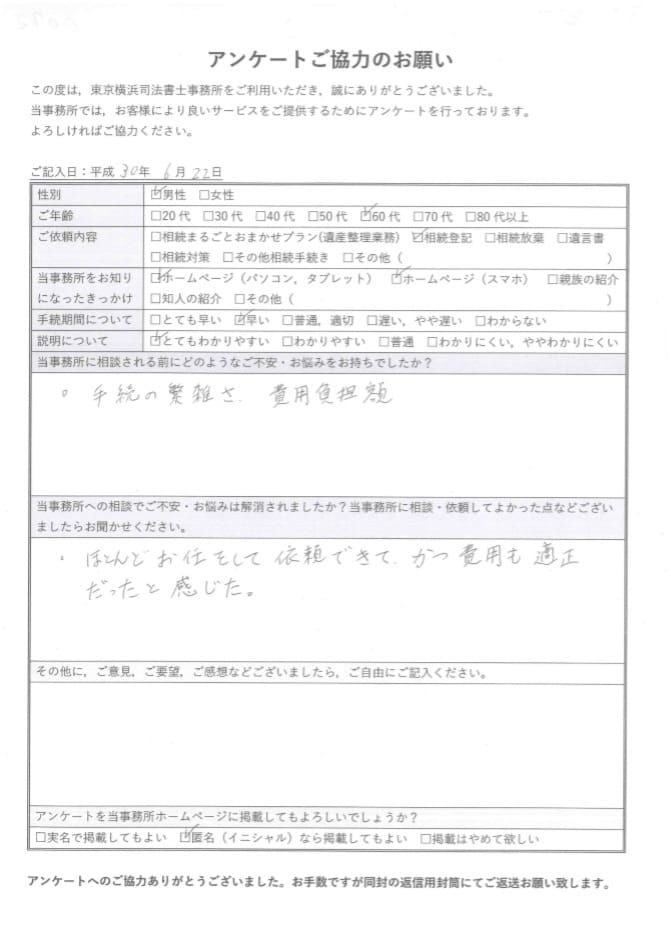

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
1人で時間とお金をかけてやるより専門の方にお願いしてとても良かったです。
・まず何をしていいのか、どこに行って手続きをするのか、どこまでが土地で山で田なのかはっきりわからず、何回実家(岩手)まで行って手続するのか不安で全く分かりません…続きを見る
-
相続手続き
1人で時間とお金をかけてやるより専門の方にお願いしてとても良かったです。
・まず何をしていいのか、どこに行って手続きをするのか、どこまでが土地で山で田なのかはっきりわからず、何回実家(岩手)まで行って手続するのか不安で全く分かりませんでした。
・自宅から近いところで1回の相談ですべての相続手続きが2か月ほどで完了しました。私のした事は印鑑証明書を取っただけで、しかも相続放棄の期限が近付いていたのですが、手早く進めていただいて大変感謝しております。
・1人で時間とお金をかけてやるより専門の方にお願いしてとても良かったです。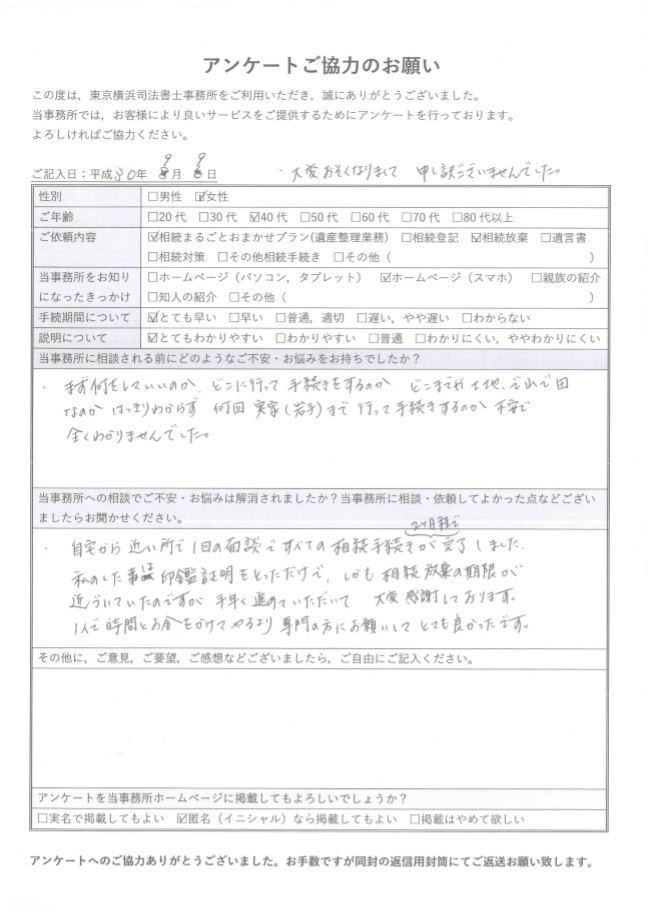

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
進捗状況をメールでご連絡いただき、安心しました。
・(相談前に不安だったことについて)司法書士と税理士の関係、報酬について。 ・わかりやすくご説明いただきました。大田先生からの紹介も安心しました。 ・進捗状…続きを見る
-
相続登記
進捗状況をメールでご連絡いただき、安心しました。
・(相談前に不安だったことについて)司法書士と税理士の関係、報酬について。
・わかりやすくご説明いただきました。大田先生からの紹介も安心しました。
・進捗状況をメールでご連絡いただき、安心しました。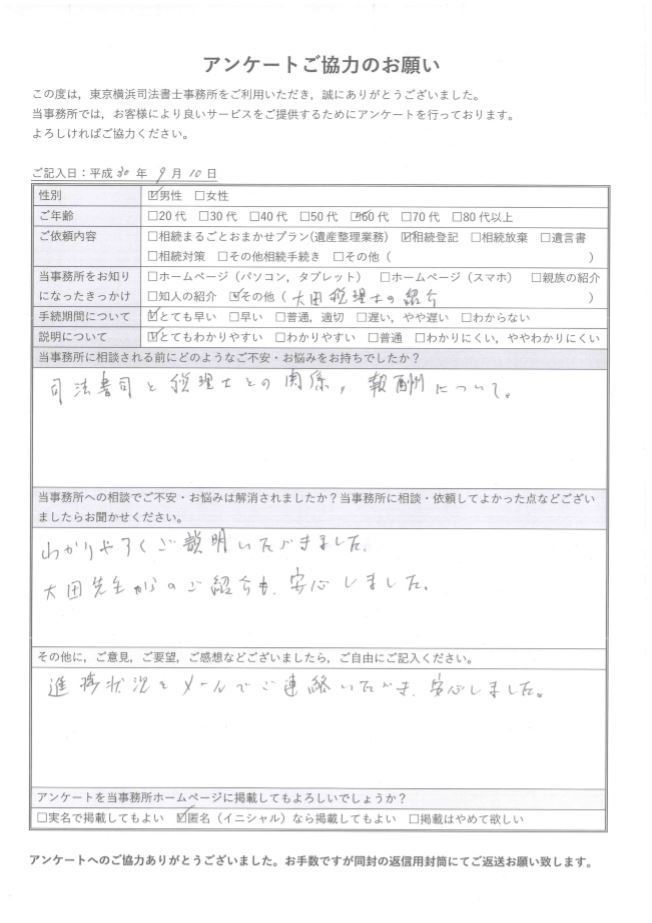

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
ユーザーフレンドリーであり、感謝しております。
・(相談前に不安だったことについて)(紹介してもらった)税理士さんを信頼していたことから特に不安はありませんでした。 ・丁寧にご説明いただき、手続きが良く理解…続きを見る
-
相続登記
ユーザーフレンドリーであり、感謝しております。
・(相談前に不安だったことについて)(紹介してもらった)税理士さんを信頼していたことから特に不安はありませんでした。
・丁寧にご説明いただき、手続きが良く理解できました。
・ユーザーフレンドリーであり、感謝しております。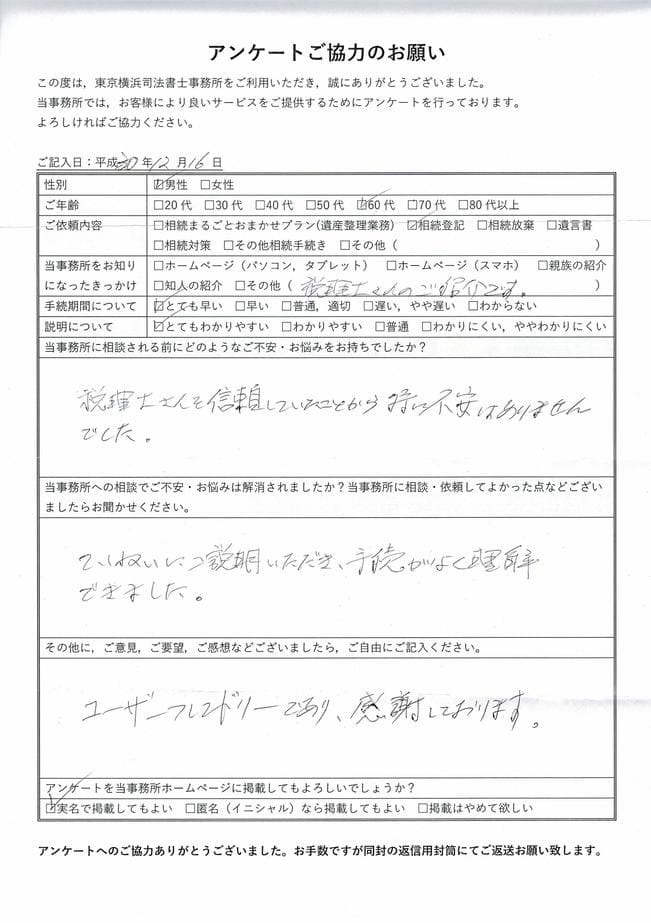

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
すべてお任せして無事完了でき感謝しております。
・たいへんお世話になりありがとうございました。すべてお任せして無事完了でき感謝しております。…続きを見る
-
相続登記
すべてお任せして無事完了でき感謝しております。
・たいへんお世話になりありがとうございました。すべてお任せして無事完了でき感謝しております。
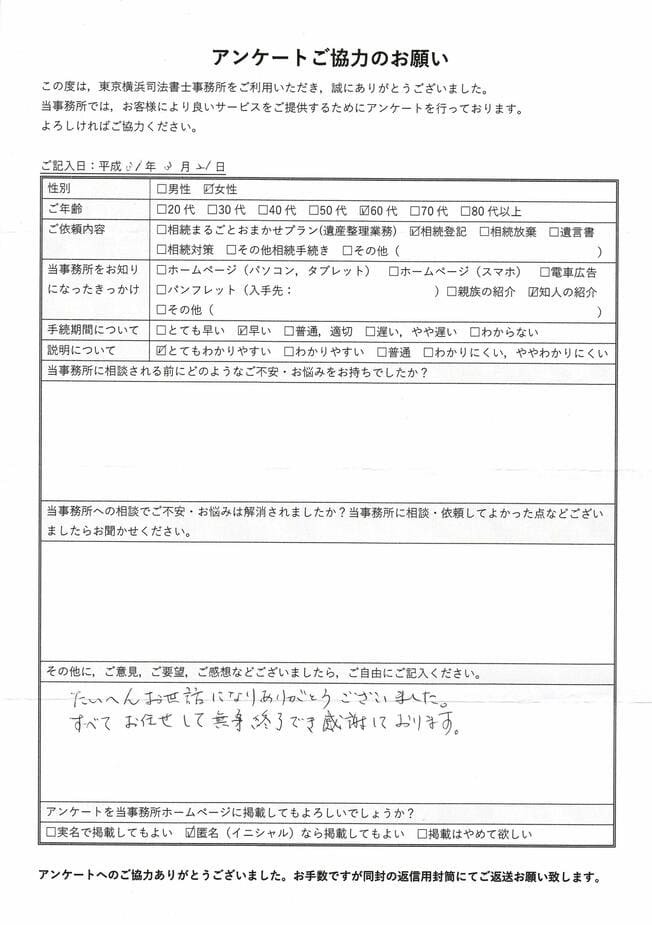

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
丁寧な対応で、こちらの希望する面談予約時間を取って下さり助かりました。
・相続のことなどまるきりわからず、仕事を持っているので時間に余裕もなく悩んでいました。 ・大変わかりやすく、こちらの相談に丁寧な対応で、こちらの希望する時間を…続きを見る
-
相続手続き
丁寧な対応で、こちらの希望する面談予約時間を取って下さり助かりました。
・相続のことなどまるきりわからず、仕事を持っているので時間に余裕もなく悩んでいました。
・大変わかりやすく、こちらの相談に丁寧な対応で、こちらの希望する時間を取って下さり助かりました。
・いろいろとありがとうございました。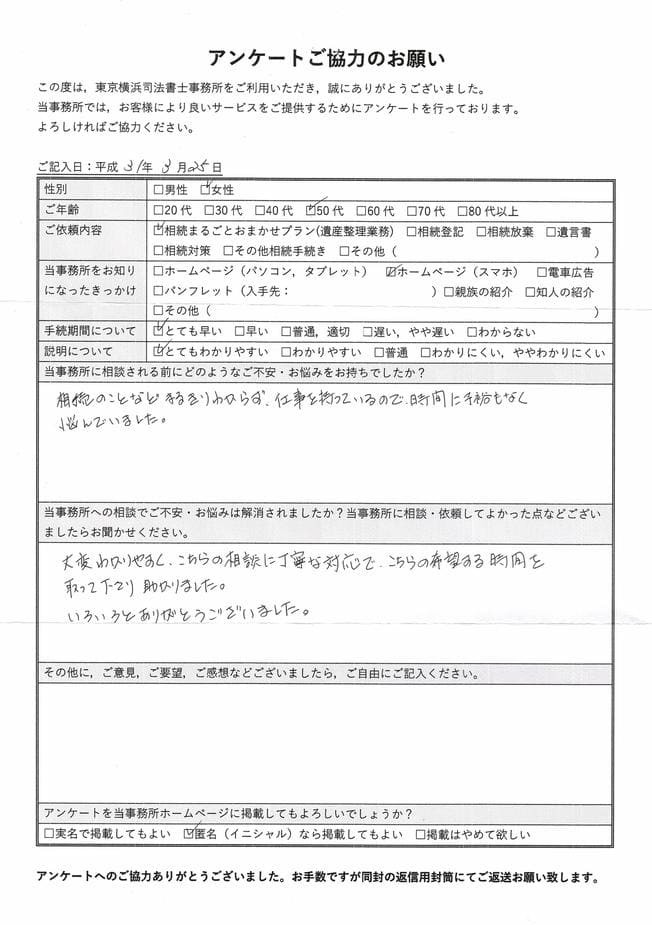

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。
・手続き方法等わからず不安であった。 ・TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。 ・この度はありがとうございました。…続きを見る
-
相続登記
TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。
・手続き方法等わからず不安であった。
・TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。
・この度はありがとうございました。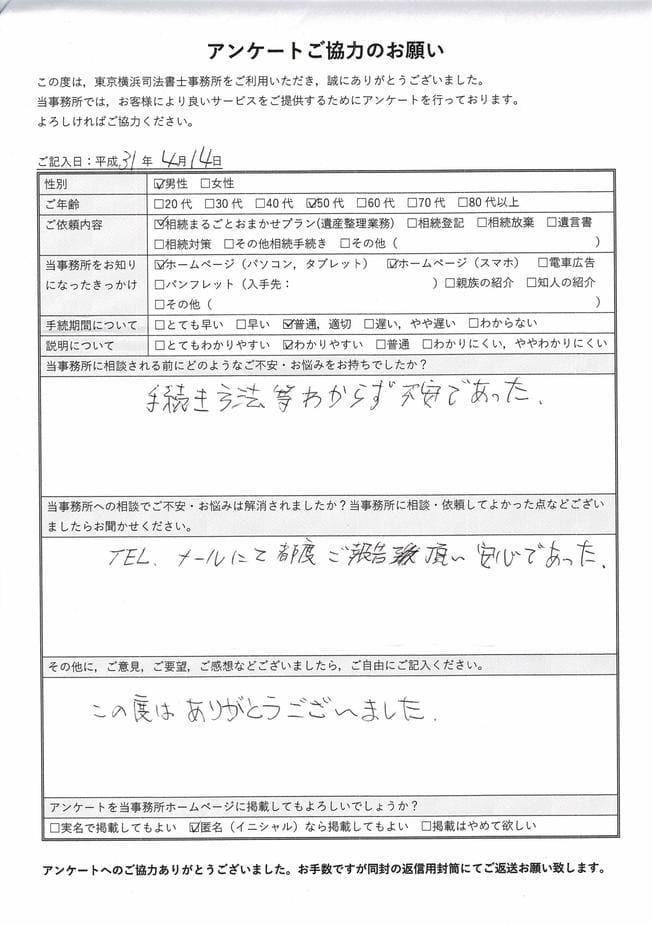

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。
・ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。 ・また機会がございましたら、その時はよろしくお願い申し上げます。…続きを見る
-
相続登記
ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。
・ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。
・また機会がございましたら、その時はよろしくお願い申し上げます。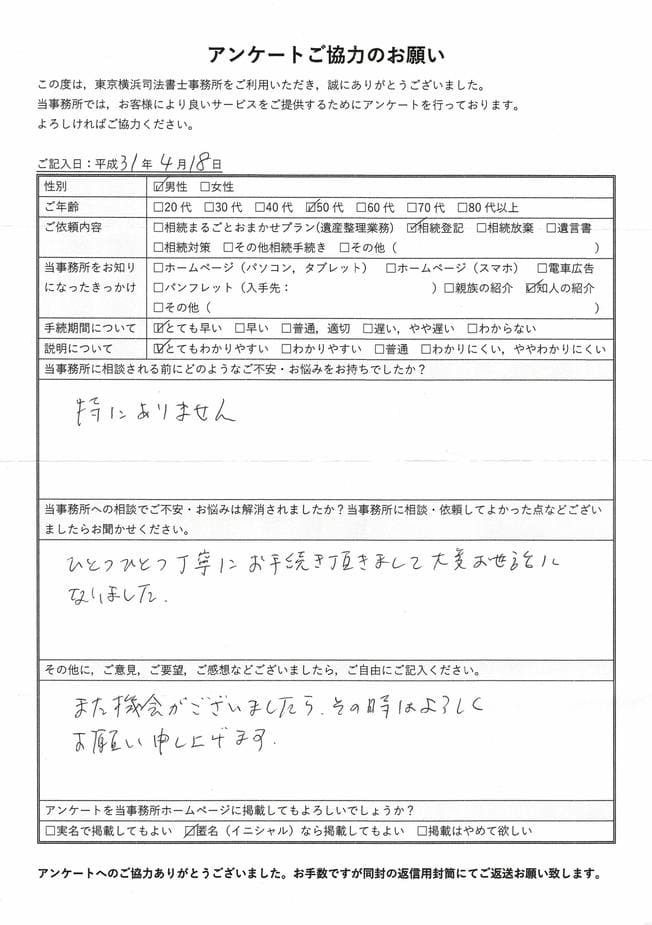

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
兄弟間で意見の違いが明らかになった際にも、適切かつ公平な見解を頂いたことから、無事完了することができました。
・いずれの司法書士に依頼すればいいか、全くわからない状況でした。 ・PCサイトで全国的に信頼度の高い相続関係事務所から貴社(東京横浜司法書士事務所)を紹介され…続きを見る
-
相続手続き
兄弟間で意見の違いが明らかになった際にも、適切かつ公平な見解を頂いたことから、無事完了することができました。
・いずれの司法書士に依頼すればいいか、全くわからない状況でした。
・PCサイトで全国的に信頼度の高い相続関係事務所から貴社(東京横浜司法書士事務所)を紹介された。実際に(代表の)田中さんにお会いしてお任せできると考えた。
・兄弟間で保険金の分配をめぐっで意見の違いが明らかになった際にも、適切なアドバイスを公平なコメントで頂いたことから、相続が無事完了することができ、感謝しています。
・上記意見相違の時点で頂いた意見をお聞きし、適切な判断をできるようになったのは、田中さんの深い経験があっての事と思います。大変ありがとうございました。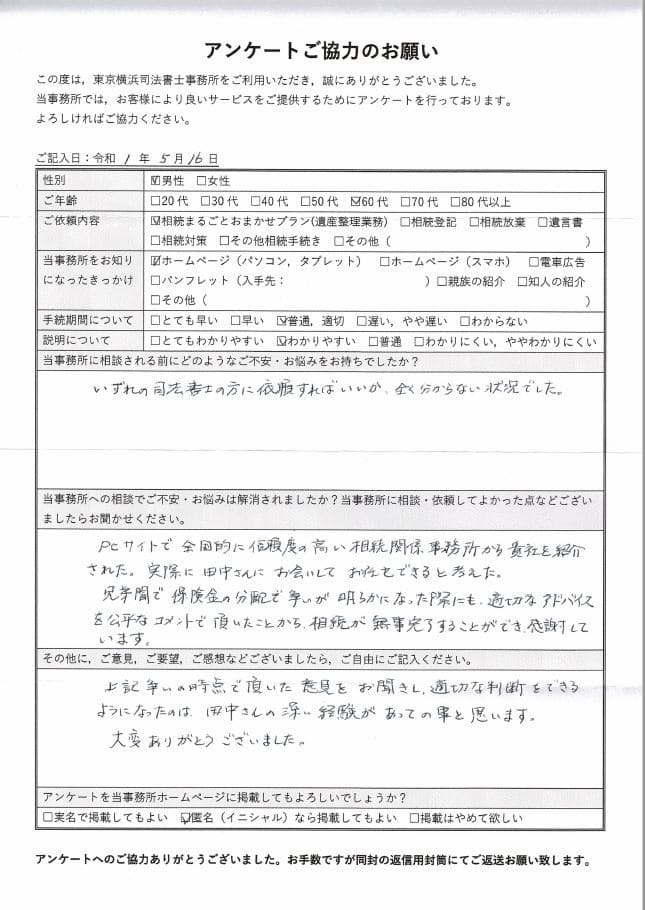

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
メールなどの返事もすぐにくださり大変助かりました。
・相続について、どのくらい費用がかかるのか、司法書士がどこまでやってくれるのかが不安でした。 ・費用などは良く説明してくださいましたし、こちらがわからないこと…続きを見る
-
相続手続き
メールなどの返事もすぐにくださり大変助かりました。
・相続について、どのくらい費用がかかるのか、司法書士がどこまでやってくれるのかが不安でした。
・費用などは良く説明してくださいましたし、こちらがわからないことも調べてくださって大変助かりました。
・土日にメールなどしてもすぐ返事をくださり大変助かりました。
・役所の手続きや人との話し合いが苦手な人は、司法書士さんのほうではかんたんなことでも、本人にとってはすごく苦痛なときがある。そんなとき司法書士さんの方でできることは私の方でやりましょうかとか言ってもらえるとすごく助かります。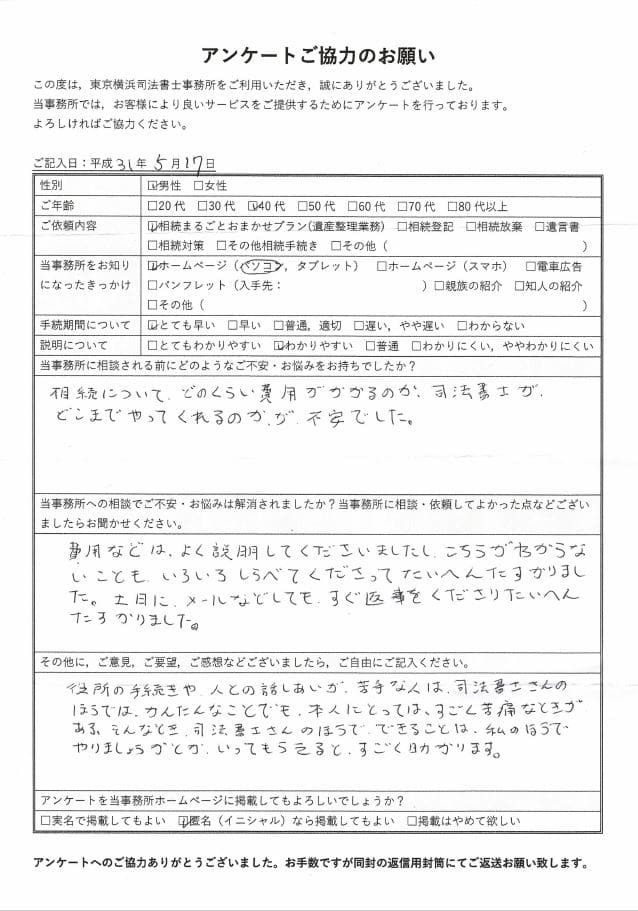

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
専門外の所も色々手を尽くして下さってありがとうございました。
・昨年に、妻が亡くなり銀行の預貯金や共有名義の建物登記の名義変更等色々あり、頭を悩ませておりました。また、相続税はどうなのか。 ・先生にお会いして、お話をさせ…続きを見る
-
相続手続き
専門外の所も色々手を尽くして下さってありがとうございました。
・昨年に、妻が亡くなり銀行の預貯金や共有名義の建物登記の名義変更等色々あり、頭を悩ませておりました。また、相続税はどうなのか。
・先生にお会いして、お話をさせていただいたところ、親身になって話を聞いて下さり、分からないところの部分も、親切丁寧に教えていただきました。
・専門外のところもいろいろ手をつくしてくださって、ありがとうございました。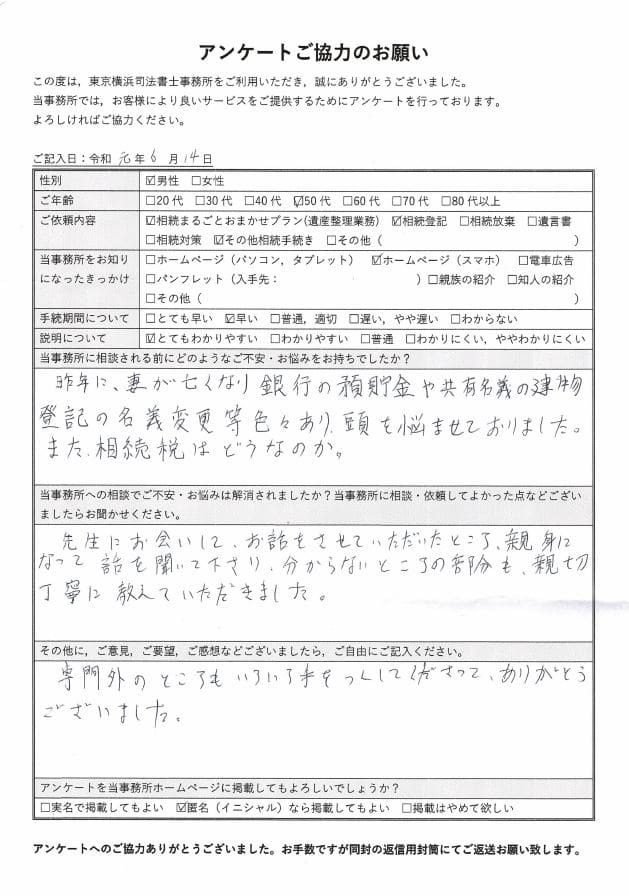

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
対応の早さと丁寧さは信頼につながるなと改めて実感しました。
・家の登記はおわっていたが、お金の相続がおわっていなかった状態。家のローン引きつげるかわからなかった状態で 何をどうしていいかわからなかった。 ・田中さんはと…続きを見る
-
相続手続き
対応の早さと丁寧さは信頼につながるなと改めて実感しました。
・家の登記はおわっていたが、お金の相続がおわっていなかった状態。家のローン引きつげるかわからなかった状態で 何をどうしていいかわからなかった。
・田中さんはとてもていねいに話をきいて下さり、メールなどの対応も早くてとても信頼できました!
・安心しておまかせずることができました。急な問合せにもすぐ対応して下さり、田中さんにお願いしてよかったです!困っている方がいたらおススメしたいです。
・状況が複雑だったにも関わらず、終始ていねいに対応して下さったこと、心から感謝しています!
・対応の早さとていねいさは信頼につながるなーと改めて実感しました。またお世話になる機会がありましたら、せひお願いしたいです。ありがとうございました!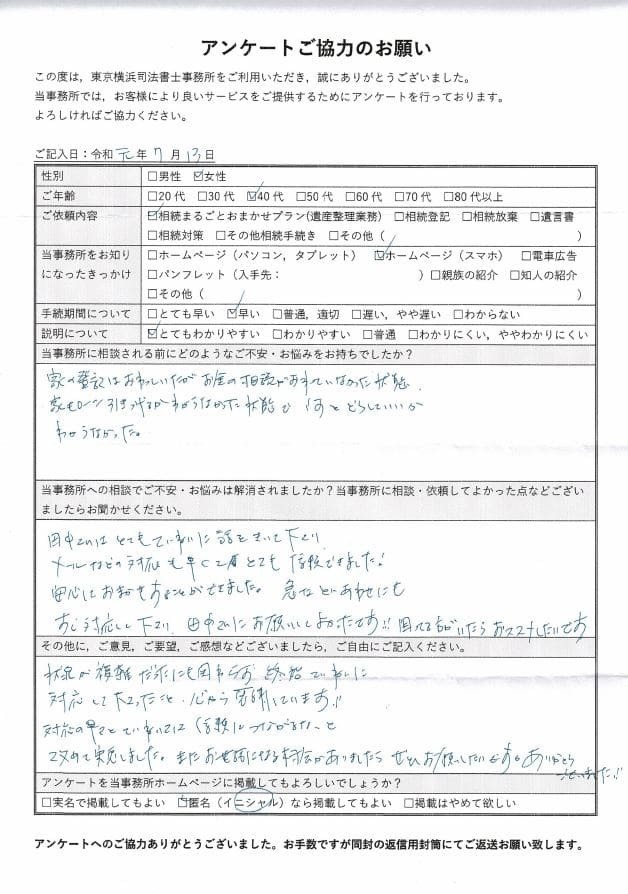

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
一度お会いしただけで、全ての手続きが済みましたので、大変助かりました。
・父の葬儀後、自分で遺産整理を始めようと、それほど多くない相続物件でしたが、仕事をしながら一気に処理しようとするとそれなりに手間暇も掛かることがわかっていて、つ…続きを見る
-
相続手続き
一度お会いしただけで、全ての手続きが済みましたので、大変助かりました。
・父の葬儀後、自分で遺産整理を始めようと、それほど多くない相続物件でしたが、仕事をしながら一気に処理しようとするとそれなりに手間暇も掛かることがわかっていて、ついには3回忌が過ぎてしまいました。
・相続人も妹と2人だけでモメる要素もなかったのですが、あまり遅くなっても片付くものでもないし、専門家に頼むことにしました。
・色々とネットで検索して料金を調べると、どこもそれなりに費用が掛かることがわかり、それでまた二の足を踏んでいましたが、ようやく貴所のホームページに行きつき、料金も明瞭なこともあり、ようやく遺産整理を依頼することができました。
・司法書士の先生に自宅近くまで足を運んでいただけることや、相談も無料であったので、気楽に話をすることができました。
・事前に伺っていた準備する書類や印など用意していたので、一度、先生とお会いして、その後郵送等で数回やり取りしただけで、全ての手続きが済みましたので、大変助かりました。
・手続き依頼に当たっては、特に期限を設けていたわけでもありませんでしたが、複雑な相続でもなかったので、2か月程度で完了するものと勝手に思っていたため、少し時間がかかったといった思いはありますが、それでも4か月程度でしたし、費用が他者よりも圧倒的にリーズナブルだったことを考えれば、とても満足な結果です。
なお、手続きの進捗状況をもう少しこまめに連絡していただければ、依頼者の不安は更になくかるかもしれません。ありがとうございました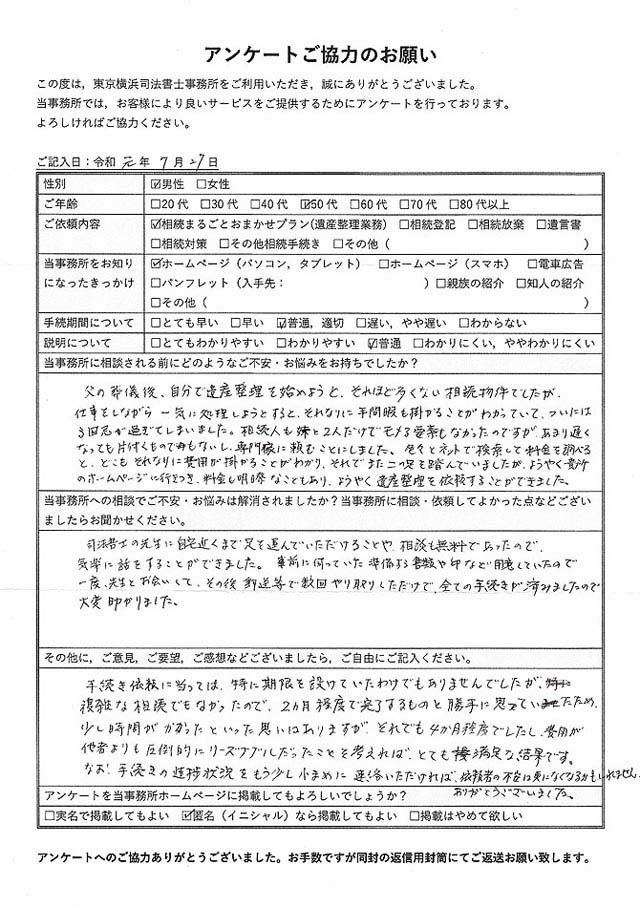

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
東京からわざわざ出張して対応していただいてありがとうございました。
・死亡した姉が宮城県で、私が埼玉県、田中様が東京であり、遠隔地の対応をして頂けるかどうか不安でした。実際に他の事務所へ電話で相談した際に遠隔地という事で断られた…続きを見る
-
相続手続き
東京からわざわざ出張して対応していただいてありがとうございました。
・死亡した姉が宮城県で、私が埼玉県、田中様が東京であり、遠隔地の対応をして頂けるかどうか不安でした。実際に他の事務所へ電話で相談した際に遠隔地という事で断られた事がありました。
・また、相続の対象となるものが不明だったし、情報も殆ど無かった為に、どうなるか不安でした。そして処分したり、アパートや車の処理についても不安でした。
・アパートや車の手続きに関しては、東京から宮城県までわざわざ出張して現地で対応して頂いてありがとうございました。
・また、相続対象がわからないなか、色々と調べてもらい対応して頂きありがとうございました。
・最初に大まかな費用の説明があり、大体の感じがわかったのがありがたかったです。
・地元(宮城県)と私と(埼玉県)と田中様(東京)が離れているので、一つ一つの対応に時間がかかってしまい、申し訳ありませんでした。
それにより、長期の対応となってしまい、申し訳ありません。また、最後まで対応して頂き、ありがとうございました。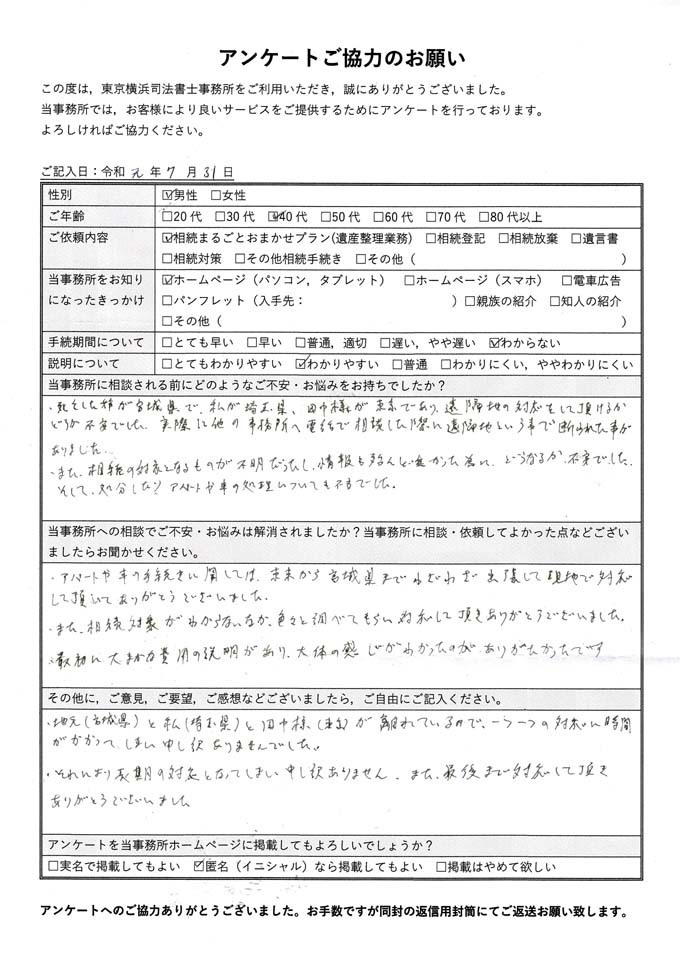

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。
(当事務所に相談される前にどのようなご不安・お悩みをお持ちでしたか?) ・相続関連業務の範囲がどこまで依頼できるのか ・料金体系及び追加料金はどの位か ・…続きを見る
-
相続手続き
相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。
(当事務所に相談される前にどのようなご不安・お悩みをお持ちでしたか?)
・相続関連業務の範囲がどこまで依頼できるのか
・料金体系及び追加料金はどの位か
・税理士との連携がどこまでできるのか
・信託銀行とのサービス、料金等々がどの程違うのか
・初回の税理士法人との打ち合わせのときに司法書士の田中さんを紹介して頂き、次回の打合せで相続手続きの説明を受け、特に信託銀行との比較をしながらの判りやすいものでした。また、適時、ご報告も頂き、質問等にも即座に解答して頂きありがとうございました。
・相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。また信託銀行よりもかなり費用が安くなっていました。
・田中様、色々ありがとうございました。二次相続時もよろしくお願い致します。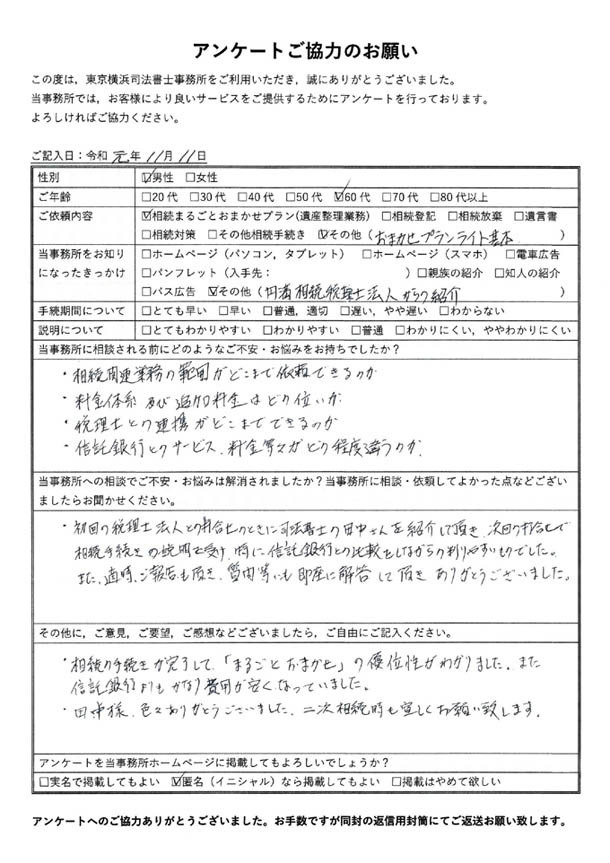

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
途方に暮れていたところ、えきまえ相談会を発見。無事相続手続きを終えることが出来ました。
・相続の手続きが必要だとわかり、本やネットなどで調べましたが、私ども家族の場合、当てはまるような事例がほとんど無く、何をして、どう進めたらよいのか、どなたにお願…続きを見る
-
相続手続き
途方に暮れていたところ、えきまえ相談会を発見。無事相続手続きを終えることが出来ました。
・相続の手続きが必要だとわかり、本やネットなどで調べましたが、私ども家族の場合、当てはまるような事例がほとんど無く、何をして、どう進めたらよいのか、どなたにお願いするのがベストなのか悩んでいました。
・えきまえ無料相談会を開催されていたので、自宅の近くでご相談が出来た事も本当に助かりました。
その後も、度々こちらまでご足労頂けたこともありがたかったです。
相続の手続きに関しては、私ども家族にとってベストなご提案をして頂き、無事に終えることが出来た事を大変感謝しております。
相続税に関しても、相続に強い税理士さんををご紹介いただき、情報を共有していただけたので、私どもの負担も軽減され、こちらもスムーズに終えることが出来ました。
・貴所の田中様にお願いして、本当に良かったです。誠実なお人柄で、温厚でやさしい話し方も好感が持てました。今後も信頼してご相談出来る司法書士の田中様とのご縁が持てた事もうれしく存じます。また何かの折には、宜しくお願い致します。
この度は、大変お世話になり、本当にありがとうございました。
最後となりましたが、貴所のご発展と田中様の益々のご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。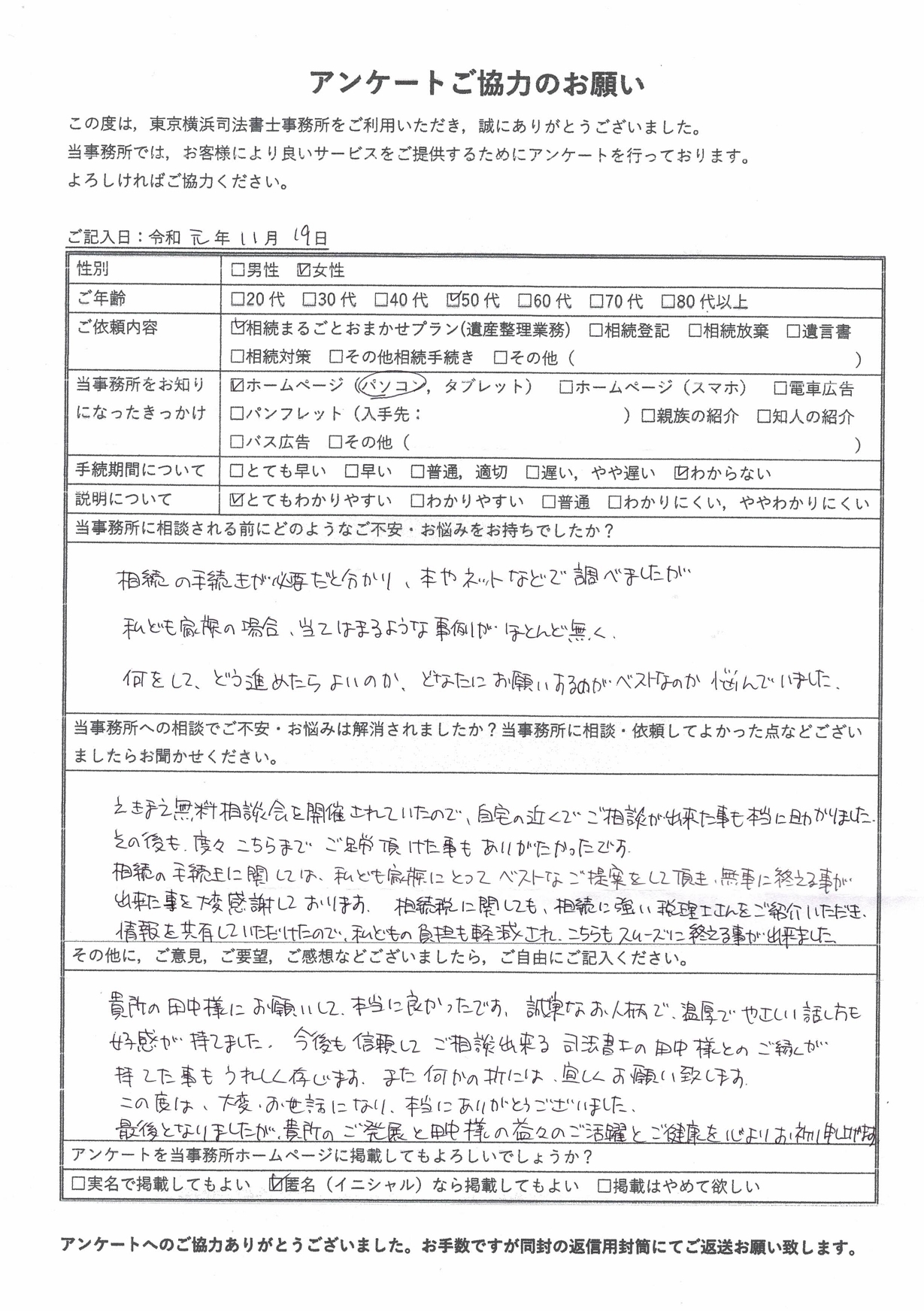

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
初めから御社に依頼しておけば無駄なお金がかからなかった…
・自分で全てやってしまおうと思っていたが行き詰ってしまったので依頼。全額がいくらかかるのか不安だった。 ・別の税理士に分割協議書の作成を依頼したのが大失敗…続きを見る
-
相続手続き
初めから御社に依頼しておけば無駄なお金がかからなかった…
・自分で全てやってしまおうと思っていたが行き詰ってしまったので依頼。全額がいくらかかるのか不安だった。
・別の税理士に分割協議書の作成を依頼したのが大失敗。初めから御社に依頼しておけばムダなお金がかからなかった。的確なアドバイスがとてもよかった。
・税理士先生、司法書士先生、色々なタイプな先生がいて、それぞれ違うのを今回実感した。選ぶ消費者にとって正直どの方を選ぶか非常に悩まされる。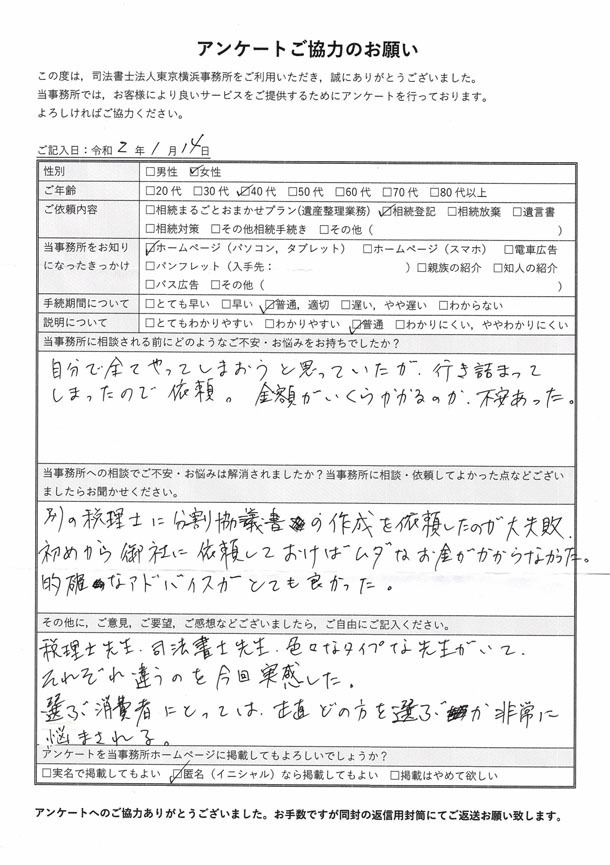

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
直接電話でお話し、不安な点を全て答えていただきました。
・初めての経験でしたので、何から始めるのかも不明でした。信頼して良いか不安でした。 ・直接電話させていただいて会話した結果、信頼できる事務所だと解りました…続きを見る
-
相続手続き
直接電話でお話し、不安な点を全て答えていただきました。
・初めての経験でしたので、何から始めるのかも不明でした。信頼して良いか不安でした。
・直接電話させていただいて会話した結果、信頼できる事務所だと解りました。当方(当初?)の不安な点を全て答えてもらいました。
・全体的にとても良いご対応をしていただき感謝しています。
・途中、手続きが長引いた際は一報いただけると、更に安心感が増すと思いました。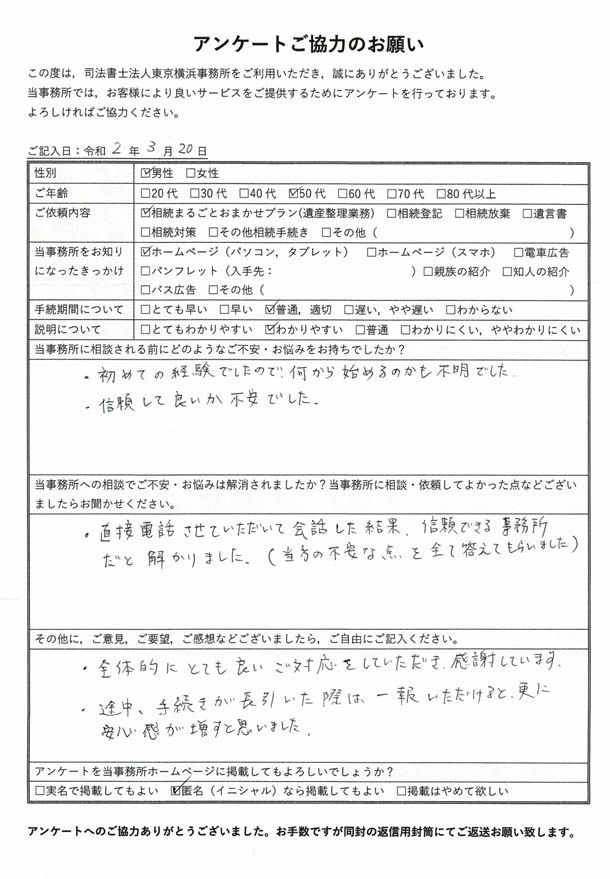

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
各機関への問合せ等、迅速に対応いただけて助かりました。
・被相続人である父との接点があまり無かった為、不明瞭な借金等がある可能性等。 ・各関係機関への問合せ等、迅速に対応頂けて助かりました。…続きを見る
-
相続手続き
各機関への問合せ等、迅速に対応いただけて助かりました。
・被相続人である父との接点があまり無かった為、不明瞭な借金等がある可能性等。
・各関係機関への問合せ等、迅速に対応頂けて助かりました。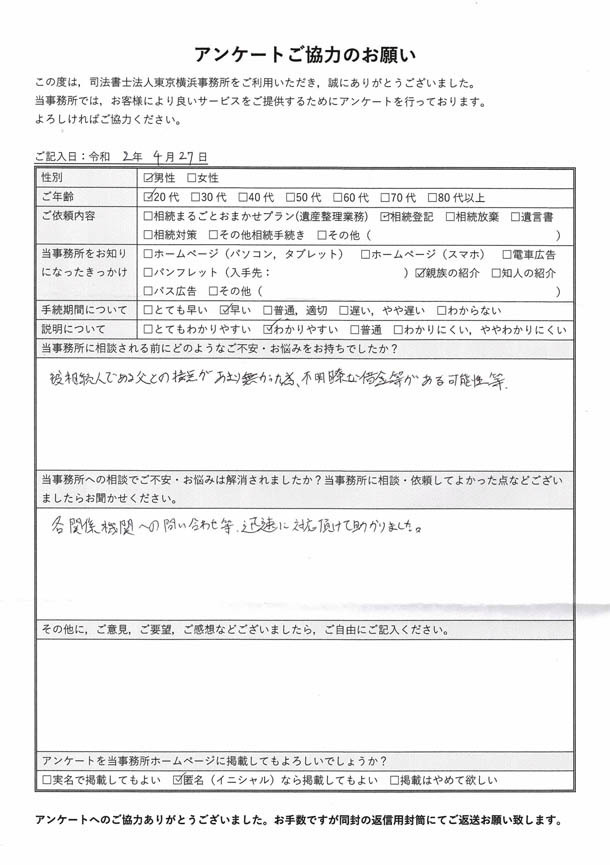

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
解決事例
-
成年後見
相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様と子供たち。
お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能…続きを見る-
成年後見
相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様と子供たち。
お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能力(判断能力)が無い状態。
意思能力が無い方がいると、そのままでは手続きを進めることができないと知り、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。相談後
遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。
認知症だからと言って必ずしも意思能力が無いというわけではありませんが、このケースではお母様は施設に入所されており、すでに日常会話も難しい状況でした。
そこで今後のことも考えて、お母様の一番近くに住んでいる長男様を成年後見人として申し立てを行うことになりました。
ただし、今回はお母様と長男様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長男様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできなません。
そこで成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
また、お母様ご自身の財産と今回相続する財産を合わせるとかなりの金額になるため、家庭裁判所が、司法書士や弁護士などの専門家を成年後見人に選任してくる可能性が高いと思われました(当時の運用では、親族後見人による横領を防ぐという名目で、財産が一定額を超えると機械的に専門家が選任されていました。)。
成年後見は一度開始されると、原則として本人が亡くなるまで続くため、月3~4万円の後見人報酬がかかり続けることが懸念されました。
そこで後見制度支援信託という仕組みを利用し、かかるコストを最小限に抑える方法を提案しました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様と子供と孫。
相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代…続きを見る-
相続手続き
遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様と子供と孫。
相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代襲相続人になる。
姪には母親(亡兄の妻)を通して一度は相続手続に協力してもらえるとの口約束は取り付けているが、その後はなかなか連絡が取れない。
揉めているわけではないものの、亡兄家族とはほとんど面識がないため、今後の手続きをどう進めていいか困っているという事で相談にいらっしゃいました。相談後
相続人であるお子様がすでに亡くなっている場合、その方に子供がいれば代襲相続人として相続人となります。
代襲相続人がいるケースでは、他の相続人との面識がほとんどないという事はよくあり、今回もそうでした。
そこで、当事務所で戸籍収集、財産調査、疎遠な相続人とのやり取り、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント
このケースでは、相続人の中に疎遠な方がいるため自分たちで連絡を取ることについて心理的負担があること、相続人が離れて暮らしているため、書面が必要な場合にやり取りの方法が難しいこと、が主にネックとなりました。
このような負担や手間を回避するためには、生前に相続・死後手続きに精通した司法書士などの専門家に相談の上、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
また、すでに相続が発生した方で同様のケースでお困りの方は、放っておくと余計に解決が難しくなる可能性が高くなるので、お早めに相続手続きに強い専門家に相談することをおすすめします。
遺言書作成についてのご相談や、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)
遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮…続きを見る-
相続手続き
母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)
遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮らしているので、相続手続が進まない、という事で相談にいらっしゃいました。相談後
この方のように遠く離れた実家の方に財産がまとまっているが、財産調査や相続手続きのために頻繁に足を運ぶことが難しいとお悩みの方は多いです。
さらに、相続人がばらばらに離れて暮らしているので、手続きを分担するのも難しく、遺産分割の話し合いをするのも一苦労という事もよくある話です。
そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。
また、調査の結果、不動産については10年前に亡くなったお父様名義のままであることが判明したため、お母様の相続手続と併せて、お父様名義の不動産についての名義変更も行うことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、亡くなった方の財産を調査していく中で、実は以前に亡くなった方(妻や夫、祖父や祖母など)の名義のままであることが判明することは少なくないです。
このケースでは、お父様とお母様で相続関係が同一であり、全員がご健在だったため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。
しかし、手続きを放置している間に次の相続が発生した場合は、関係性の微妙な方と連絡を取らなければならいなどのやっかいな問題が生じてしまう可能性が高くなります。
不動産については今の所(2020年現在)、相続登記をしなくても罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、放置した結果、後で余計な手間や費用がかかることはあっても、得をすることはありませんので、相続が発生したら、相続手続きに強い専門家に相談のうえ、すみやかに手続きを済ませておくことをおすすめします。
放置してしまっている相続登記やその他の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】
相談前
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くな…続きを見る-
相続手続き
被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】
相談前
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くなられたお父様に名義のままである可能性が高いとのこと。
相続人が1名のみで他に相談できる方もいないため、どこから手を付けていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました相談後
相続登記をしないまま、相続人の方(一次相続人)が亡くなってしまった場合、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)と一次相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
この方の場合、亡くなったお父様とお母様の相続人はお子様二人のみで全く同じ、次に亡くなったお兄様の相続人もご相談者様のみだったので、それほど複雑な話にはならずに済みました。
このように、最終の相続人が一人のケースで相続登記を行う場合、生前に遺産分割についての合意があったかどうかによって、必要な書類や申請する登記が異なります。
聞き取りの結果、1件の登記でご相談者様に名義変更ができそうだという事がわかったので、生前に合意があったことの証明書などを作成し、最小限の手間と費用で行う方法を提案しました。
また、お仕事がお忙しく手続きのための時間が取れないという事で、当事務所で戸籍収集、金融機関への連絡、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、相続手続きを放置している間に次の相続が発生してしまった、というのは良くある話です。特に相続登記については今の所(2020年現在)罰則がないため、「そのうちやればいいか」でそのままになっている方も多いようです。
しかし、このケースのように最終的な相続人が一人になるケースばかりではなく、むしろ相続が発生するたびに関係者が増えていくのが普通です。関係者が増えるとその度に手続きに要する手間と費用も増えていくことになります。
手続きを後回しにしても得することはないので、相続が発生したら、お早めに相続手続きに精通した専門家への相談をおすすめします。
また、この方のように相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議等の必要がないため、一見楽に思われますが、他に相談できる人や手続きを分担してもらえる人がいないため、すべて自分でやらなくてはならず、お困りの方が実はとても多いです。
一人で悩んでいた時はとても解決できないと思えた事でも、専門家に相談することで意外にあっさりと解決することはありますので、悩んでいるうちに時間が過ぎて、後で大変なことになってしまう前に、やはり相続に強い専門家に相談することをおすすめします。
放置してしまっている相続登記やその他の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
コストが高過ぎる!銀行の遺言信託をキャンセルしたい・・・【信託銀行の遺言信託をキャンセルしてご依頼をいただいたケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお父様とお子様3人。
生前にご夫婦で信託銀行に遺言信託を依頼し、遺言を作成されていましたが、銀行が行う…続きを見る-
遺言作成
コストが高過ぎる!銀行の遺言信託をキャンセルしたい・・・【信託銀行の遺言信託をキャンセルしてご依頼をいただいたケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお父様とお子様3人。
生前にご夫婦で信託銀行に遺言信託を依頼し、遺言を作成されていましたが、銀行が行う遺言執行のサポート内容とかかるコストが見合ってないのではないか、また銀行から紹介された税理士の対応にも疑問があるということで、相談にいらっしゃいました。相談後
信託銀行等の金融機関が取扱う商品に“遺言信託”というものがあります。これは生前に銀行等が遺言書の作成をサポートして、相続が発生したら銀行等が遺言執行者として金融機関の解約等の相続手続を執り行うというものです。
銀行等の行う遺言執行は金融機関の解約、名義変更等に限定したものがほとんどで、業務内容に比べて報酬が高いと感じる方が多いのか、当事務所でも、相続発生後に相続人の方からキャンセルできないかという相談を受けることがあります。
このケースでは、金融機関の解約や不動産の名義変更といった基本的な手続きの他に、賃貸物件のオーナー変更手続き、住宅ローンの債務者変更手続き、貸金庫の開扉と内容物の確認等の銀行では対応できない手続きが必要という事と、銀行から紹介された相続税申告を担当する税理士の対応に疑問がある(あまり相続に詳しくなさそうだった)という事で、銀行の遺言執行をキャンセルしてすべての手続きを当事務所で代行・サポートさせていただくことを提案しました。
また、遺言書の内容のとおり財産を分けると、将来お父様の相続の際に高額の相続税を負担しなければならないことを懸念されていたため、相続人全員の同意の元、相続に強い税理士と相談の上で、遺言と異なる内容の遺産分割を検討することを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、銀行等の行う相続手続きサポートについて、コスト面やサポート内容の面での懸念からキャンセルを希望される方は少なからずいらっしゃいます。
銀行がサポートする場合、手続きは銀行の担当者や紹介された司法書士や税理士等の専門家が行うのですが、担当者が相続に精通しているわけではないのは仕方ないとしても、紹介された専門家まであまり相続に強くなさそうだったので不安になったというお話を聞くこともあります。また、銀行と専門家との連携が上手くいっていないのか、同じことを何度も聞かれ、やり取りにストレスを感じたという方もいらっしゃいました。
相続手続き、死後に必要な手続きは100種類以上にも及ぶと言われ、どの手続きが必要になるかは一人一人異なります。しかし銀行等のサポートで対応できるのは相続手続きのほんの一部であり、それ以外の細かい手続きについて相談しても、“それは別の所に相談してください”とか“それは簡単なので自分で行ってください”と対応されてしまうことがほとんどのようです。また、相続税申告等に必要な資料についても基本的には自分で集めなければなりません。
相続発生後の気分が落ち込んでいる時期に、わずらわしい手続きで悩まされたくないという方、忙しくて手が回らないという方、銀行の対応に不満があるという方は、お早めに相続手続き全般に精通した司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
※銀行との契約を解約する際にはキャンセル料が発生する可能性があります。また、すべてのケースで確実に解約できるというわけではないのでご注意ください。
また、相続税については頻繁に法律や制度の運用が変わるため、遺言のとおりに財産を分けてしまうと将来の相続税の負担が大きくなりすぎてしまうという事もよくあります。
もちろん遺言は故人の想いを反映した大切なメッセージですので、基本的には尊重すべきですが、このケースのように相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要)の上、仲良く分けるという事であれば、遺言と違う遺産分割を行っても、故人の想いを無視することなく、むしろ“残された家族が仲良く幸せに暮らしてほしい”という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。また、このような方法は実務上も認められていています。
ただし、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、後に揉め事になることを防止するために、通常の遺産分割以上に慎重な配慮が必要です。また、将来の相続税の負担を検討しなくてはならない場合もあります。
必要な手順を誤ると、相続人同士の仲がこじれたり、後で遺産分割の無効を主張されたりする可能性もあるので、遺言と異なる遺産分割をしたいとお考えの方は、必ず相続全般に詳しい専門家に相談することを強くおすすめします。
遺言執行以外の手続きも代行して欲しいとお考えの方や、遺言と異なる遺産分割をお考えの方のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家…続きを見る-
遺産分割
実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家の今後について意見の違いがあったため、公平な第三者に間に入ってもらおうという事で相談にいらっしゃいました。相談後
相続をきっかけに空き家となった不動産について、処分や活用方法をめぐって相続人間で意見が食い違うケースは少なくありません。特に実家不動産については、思い入れなども絡むため、いずれ売却するにしても、すぐに処分はしたくないという方もいらっしゃいます。
このケースでも、お兄様の方がすぐに売却はしたくないとのご意向をお持ちでした。
そこで、不動産についてはお兄様が単独で取得し、それ以外の金融資産を妹様が多く取得することでバランスを取り、公平に遺産を分ける方法を提案しました。
また、どちらか一方が相続手続きを行う事で負担が偏ることの無いよう、当事務所で戸籍収集、金融機関の調査、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように基本的には揉めないように平等にしたいものの、不動産について意見の食い違いがあるため、分け方で悩まれる方は多くいらっしゃいます。不動産については固定資産評価、相続税評価、時価評価と様々な評価基準があるため、分けるにあたってどのように金額を決めるかが難しいというのも悩ましいところです。
このような場合、公平な第三者の意見を聞くことですんなりと話がまとまることも多いので、相続人同士の話し合いが長期化して関係性がこじれてしまう前に、お早めに相続実務に精通した専門家に相談することをおすすめします。
また、このケースでは該当しなかったものの、誰が実家不動産を相続するかで相続税の金額が大きく違ってくることもあります。相続税の負担が大きくなると手元に残る金額は減り、実質的な不公平感も大きくなるため、相続人間の関係にしこりを残すこともあります。
平等に分けたつもりなのに関係性が悪化してしまった・・・というのは誰も望まない結果だと思いますので、そうならないように相続に強い専門家に相談した上で、分け方を決めることを強くおすすめします。
揉めないように公平に遺産分割を行いたい方のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】
相談前
お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。
お父様が亡くなられたのは18年前。
当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をし…続きを見る-
相続登記
相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】
相談前
お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。
お父様が亡くなられたのは18年前。
当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまい、その子供や配偶者が相続人になってしまった。
他の相続人から合意を取り付けてはいるが、離れて暮らしており、不動産も遠方にあるため、とても自分で手続きをすることはできないという事で相談にいらっしゃいました。相談後
この方のように、相続登記をしない間に次の相続が発生してしまい、相続関係が複雑化してしまったために、手続きを行うことがさらに億劫になってしまう方は少なくないです。
この方の場合は、自分の次の世代に迷惑をかけたくないという事で一念発起して相続人全員に連絡を取ったとのことでした。
幸いにも全員から手続きに協力する旨の合意をもらえたとのことでしたので、当事務所で手続きに必要な遺産分割協議書を作成し、署名捺印の手配等は郵送で行うことを提案しました。
また、戸籍の収集や固定資産評価証明書等の不動産に関する資料などの登記に必要な書類一式の資料の収集も含めて、一括して当事務所で代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント
相続登記は今のところ(2020年現在)、しないことによる罰則がないため、なんとなくすぐに登記しないまま放置されてしまう方もいらっしゃいます。
しかしこのケースのように放置している間に次の相続が発生してしまうと、その度に手続きを行うことがより困難になってしまいます。
その結果さらに放置が進むと、次の世代に問題を引き継ぐことになってしまいます。
幸いにもこのケースでは相談者様の尽力の結果、関係者全員から手続きにご協力いただくことができました。しかし最初の相続人同士は仲が良くても、次の相続が発生した結果、ほとんど面識のない相続人と連絡を取ることになり、手続きに協力してもらえずに頓挫してしまう事は珍しくありません。
相続登記を放置してもいいことは何もありませんので、子どもたちや孫の代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したらすみやかに相続に強い司法書士に相談するなどして、登記を完了させましょう。
放置してしまっている相続登記や遠方にある不動産の相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
公正証書で作った遺言なのに問題あり⁉【公正証書遺言に従って相続手続きを行うケース】
相談前
奥様を亡くされた方からのご相談。
相続人はご主人様とご両親の3名。
生前、財産はすべて夫に、という内容の公正証書遺言を遺されていましたが、手続きにな…続きを見る-
遺言作成
公正証書で作った遺言なのに問題あり⁉【公正証書遺言に従って相続手続きを行うケース】
相談前
奥様を亡くされた方からのご相談。
相続人はご主人様とご両親の3名。
生前、財産はすべて夫に、という内容の公正証書遺言を遺されていましたが、手続きになかなか手が付けられない、また、本当に遺言のとおりに進めていいのか不安があるという事でご相談にいらっしゃいました。相談後
亡くなった方が遺言書を遺されていた場合、基本的には遺言に従って手続きを進めることになります。
特に公正証書遺言の場合、手続きに必要な戸籍が少なく済み、検認手続き等も不要なため、手続きにかかる手間は大きく減ります。
しかし、そうは言っても、この方のように大切な家族を失ったばかりで気分が落ち込んでいる時に、慣れない手続きに煩わされたくない、という方は多くいらっしゃいます。
そこで、当事務所で戸籍収集、義両親への連絡、生命保険金の請求、預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。
また、すべての財産を夫に相続させる内容の遺言はあるものの、自分たちには子供がおらず、若くして亡くなってしまったので、田舎の義両親にも財産を少しはもらってほしいということでしたので、遺言と異なる遺産分割が可能かについてもアドバイスさせていただきました。事務所からのコメント
公正証書で作成された遺言がある場合、手続きに必要な戸籍が通常より少なく済むため、相続人の方の負担は軽くなります。
また、遺言書で遺言執行者が指定されていれば、他の相続人の関与なく手続きを進めることができるので、手続きが滞る可能性をかなり減らすことができます。
しかし、このケースのように法律上必須ではないが、手続きを行う(遺言を執行する)際に重要な文言が抜けていたため、結局残された方が大変な思いをするというケースは、残念ながら珍しくありません。
また、遺言執行者は基本的に誰でもなることができるので、財産を受け取る方が指定されていることも多いのですが、昨今の民法改正によって遺言執行者の義務がより具体的に明文化されたため、ご家族を指定したことによって、意図せず過大な負担を負わせることになるケースもあります。
今回のようなケースを防ぐためには、遺言の作成段階で、相続開始後の手続きにまで精通した専門家に相談の上、抜け漏れのない遺言を作ることが大切です。また、遺されたご家族が手続きの事で悩まされることの無いよう、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう。
相続発生後の手続き面にまで配慮した遺言作成や、遺言執行についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とご長男様の二人。
実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての…続きを見る-
遺産分割
遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とご長男様の二人。
実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての財産を遺贈する旨の公正証書遺言を作成させていたことが発覚したとのこと。
幸いにも相続発生前に発覚し、ご両親の本意ではなかったので遺言は撤回することができたが、こうした経緯から現状把握している財産以外にも財産があるのではないかと思い、相談にいらっしゃいました。相談後
高齢者の面倒を看ていた方が、自分に都合のいい遺言を書かせるというケースはたまにあります。
もちろん、自分の面倒を看てくれた方に、お礼を込めて財産を貰ってほしいという本心で書いた遺言の方が圧倒的に多いですが、心身が弱くなってくると、面倒を看てくれる方の言いなりになって、本意ではない遺言を作成してしまうという事もあるようです。
この方の場合、遺言は撤回できたものの、生前父は株式を保有していたはずなのにそれが見当たらないということで、自分が把握できていない財産があるのではという疑念を持っていらっしゃいました。
お母様に聞いても、高齢のためかよくわからない様子であり、また、あまりご負担をかけたくないという事でしたので、当事務所で財産調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、以前はもっと財産を持っていたはずなのに、相続開始後に家を探しても資料が見当たらないということはよくあります。
多くはすでに生前にご自身で処分されているのですが、実は資料を失くしているだけで、やはり存在していたというケースもあります。
詳細不明の財産については調査によって判明することもありますが、預貯金、上場株式、不動産等の財産の種類によってそれぞれ調査方法は異なるため、一般の方がすべてご自身で調査・確認されるには大変な労力が必要になります。
お仕事等が忙しく、そんな時間は取れない!という方は、相続手続き全般に詳しい司法書士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。
詳細不明の相続財産の調査についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続人は海外在住!印鑑証明書はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいるケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様3名。
お母様が亡くなったのは3年前で、金融機関の手続きは終わっているが、不動産の名義変更をする…続きを見る-
相続手続き
相続人は海外在住!印鑑証明書はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいるケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様3名。
お母様が亡くなったのは3年前で、金融機関の手続きは終わっているが、不動産の名義変更をするにあたり、相続人の中に海外在住の方がいるため手続きが進まないという事で相談にいらっしゃいました。
相談後
相続手続では、ほとんどの場合、相続人全員の印鑑証明書が、実印を押した遺産分割協議書とセットで必要になります。
ところがこの方のように、日本に住民登録が無い方については、印鑑証明書を取得することができません。
もちろんだからと言って手続きができないわけではなく、いくつか代わりの方法があるのですが、どの方法が適しているかは、事情に応じて、手間や確実性を考えて決める必要があります。
今回のケースでは、海外在住の方が比較的大都市にお住まいで、当面日本に戻る予定はないとのことだったため、お近くの日本大使館でサイン証明書を取得していただく方法を提案しました。事務所からのコメント
相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合、通常の手続きで必要になる、戸籍や住民票、印鑑証明書等が取得できないため、代わりの方法で手続きを行う必要があります。
今回のように、比較的大きな国、大都市にお住まいであればサイン証明書をご取得いただくのがポピュラーな方法ではありますが、事情によっては証明書を取得することが困難な場合もあります。
また、サイン証明書は形式が2種類あり、手続きによっては形式が限定されている場合もあります。
無事書類を取得できたとしても、日本と違って郵便事情が良くない国も多いので、どのような方法で書類のやり取りをするかにも気を配らなくてはなりません。
自分の場合にどのような書類が必要か、書類取得のためにどのような手続きが必要かを正確に把握するのはとても難しいと思いますので、外国籍の方や海外在住の方がいる場合は、相続発生後、すみやかに相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。
相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】
相談前
奥様を亡くされた方からのご相談。
相続人はご主人様とご両親の3名。
お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある…続きを見る-
遺産分割
妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】
相談前
奥様を亡くされた方からのご相談。
相続人はご主人様とご両親の3名。
お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある。
義両親との関係は悪くはないものの、デリケートな話なので、どう切り出せばいいかについて不安があるという事で相談にいらっしゃいました。相談後
亡くなった方にお子様(又はお孫様)がいない場合、配偶者と共に父母が相続人になります。
ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、お子様の方が先に亡くなってしまい悲しみに暮れている義父母方と話をしなければならないということで、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。
幸いにもこのケースでは、義父母様の方から早々に相続については辞退したい旨の申出があったため、後は遺産分割協議書等の書面のやり取りをどうするかが問題となりました。
ご相談者様は近いうちに遠方への転勤が決まっており、手続きのための時間を取ることは難しく、また、辞退していただいた義両親にも負担をかけたくないということだったので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのようにお子様がいないご夫婦で、配偶者が亡くなってしまった場合、直系尊属(父母や祖父母)の方がご存命であれば、財産の分け方について話し合いをしなくてはなりません。
ただでさえ財産の分け方というデリケートな話題であることに加え、お子様を亡くされた御父母様方と話をしなければならないというのは大変な心労が伴います。
また、今後の生活のことを考えて、できれば法定相続分(配偶者および直系相続人が相続人の場合は配偶者が3分の2)より多くの財産を相続させてもらいたいとの希望を持つ配偶者の方も多いのですが、現実は厳しいとお考え下さい。
幸いにもこのケースでは義父母様から辞退の申し出があり、すべての財産をご主人様が相続することになったのですが、私の数多くの経験上、このようなケースはむしろ稀で、きっちり法定相続分どおりの請求をされることが大半です。
残された配偶者の方が、自分がいなくなった後の生活に困らないように、また、わずらわしい手続きや親とのやり取りで疲弊してしまうことのないように、とお考えであれば、お子様がいないご夫婦は、必ず遺言書を書いておきましょう。
まだ自分たちは若いから・・・とお考えの方々もいるかもしれませんが、人生何が起こるかはわかりません。少なくとも35歳以上のご夫婦については、万が一の場合に備えて、夫が妻に、妻が夫にそれぞれ相続させる旨の「夫婦相互遺言」をすぐにでも作成することを、強く、強くおすすめします。
お子様がいないご夫婦の相続手続きや相続対策・遺言作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続税申告
銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだ…続きを見る-
相続税申告
銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだったとのこと。
ところが税理士から、相続税の申告のために金融機関から残高証明書や取引履歴を取り寄せるよう言われ、当初は全て自分でやることも考えたが、仕事が忙しく、銀行口座や証券口座の数も多いため、相続税の申告期限に間に合わないかもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。相談後
亡くなった方の相続開始時点での預金残高を証明する書面を「残高証明書」と言い、各金融機関ごとに必要な書類を提出して請求することで取得することができます。
残高証明書は遺産分割協議の対象となる相続財産の確認のために必要なほか、相続税の申告が必要な場合は申告の際の添付資料として必要になります。
また、過去の預金通帳を紛失している場合は、金融機関で過去の取引履歴を取得する必要が出てくる場合もあります。
これらの書類については相続税の申告を依頼した税理士から取得するよう言われることが多いのですが、ご自身で取得してみようとしてみたものの、金融機関の数が多いのに加え、対応がそれぞれ微妙に異なるため、思ったより手間がかかるという事がわかり挫折した、という方からご相談をいただくことも多いです。
このケースでも、金融機関の解約手続きについては時間ができてからゆっくりとやればいいとお考えでしたが、金融機関が10以上もあったため、相続財産の調査については費用はかかっても専門家に代行をお願いしたいとのご意向をお持ちでした。
そこで、金融機関の解約手続きについてはご自身で行っていただくことで費用を節約していただくとともに、相続財産の調査及びそのために必要な戸籍の収集については当事務所におまかせいただくことで、ご相続人様の負担を減らしながらも、確実に相続税の申告に間に合わせることを提案いたしました。
また、不動産の名義変更(相続登記)については専門性が高く、ご自身で行うことが難しいので、当事務所におまかせいただくことを提案いたしました。事務所からのコメント
このケースのように、金融機関の手続きについては頑張れば自分でもできそうだけど、手続きのための時間を取れないので代行を依頼したいという方は、実はとても多いです。
特に、相続税の申告が必要な場合は、迅速に財産調査を完了させないと、遺産分割のために話し合いの時間をゆっくり取れなくなったり、最悪の場合申告期限に間に合わないことさえあります。
ただ、期限内に申告さえ済ませてしまえば、解約は後からゆっくりでいいという事であれば、このケースのように自分でできる部分は自分でやって、面倒な部分、専門的な部分だけを専門家に依頼して費用を節約するというのも選択肢の一つかもしれません。
ただし、代行を依頼する場合、調査と解約で別々に依頼できる(=その分費用を調整してもらえる)所は実はそれほど多くありません。(金融機関1社につきいくら、というところが多いです。)また、別々に依頼するとかえって高くなることもあります。
相続手続きの面倒なところは代行して欲しいけど、簡単なところは自分でやって費用を節約したい、とお考えの方は、相続手続きの実績が豊富で、お客様の細かなニーズにも柔軟に対応してくれる所に相談することをおすすめします。
当事務所では、面倒な相続手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」のほか、財産調査と相続登記のみ代行して欲しい、等のお客様の様々なニーズに対応可能なプランをご準備しております。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?【期限までに財産調査を完了させ、分割協議をまとめなければならないケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は妻と、前妻との子供4人。
不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、そ…続きを見る-
遺産分割
タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?【期限までに財産調査を完了させ、分割協議をまとめなければならないケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は妻と、前妻との子供4人。
不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、その周辺処理も必要、と財産調査だけでもかなりの工数が必要にもかかわらず、後妻と前妻の子という微妙な関係性のため手続きが全く進んでいない状態。
相続税の申告期限まで3か月と少ししか残されておらず、銀行預金の解約手続きを済ませなければ納税資金を準備できないというかなり切羽詰まった状況でご相談にいらっしゃいました。相談後
こちらのケースは、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であり、さらに相続税申告期限が迫っており、時間的制約もあるという大変難易度の高いご依頼となりました。
このようなケースでは、事実関係を正確に把握し、必要な手続きをリストアップした上で優先順位を決め、期限に間に合うようにスケジュールを組み、実行する必要があります。
そこでまずは、相続税申告を間に合わせることを最優先事項とし、金融機関及び不動産等の資料収集を完了させ、すみやかに遺産分割協議のための準備を整えることを提案しました。
また、相続税が高額になるため、お子様方の納税資金を準備しなければならないという問題に対しては、遺産分割協議成立後に、預金残高が一番多い金融機関の解約を当事務所で行い、各相続人様に分配するという方法を提案しました。
また、相続人同士の関係性を考慮し、万が一にも後で揉めないように、事前に公証役場で公正証書遺言の検索を行うことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であるというのはさすがに多くはありませんが、自分たちで手続きをやろうとしたが、思ったより時間がかかり、相続税の申告期限に間に合わなくなりそうになったので、慌てて相談に来られる方は多くいらっしゃいます。
相続税の申告の際には、資料として様々な書類を準備する必要があるのですが、その中でも金融資産に関する資料としては、亡くなった方と取引のあった金融機関から残高証明書や取引履歴等の資料を取り寄せなくてはならないことがほとんどです。
残高証明書等の請求については各金融機関によって微妙に対応が異なるため(最寄りの支店で手続きできるケース、相続センター等での一括対応となるケース、郵送対応のみのケースなど)、一つづつ確認しながら進めていくしかないのですが、金融機関の数が多い場合、書類に不備があった場合のやり取りや郵送手続きに時間がかかってしまうと、申告期限に間に合わない可能性があります。
また、書類の準備がぎりぎり間に合ったとしても、その後時間がない中で慌てて遺産分割協議を成立させてしまうと、後で相続人間の関係が微妙になってしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、相続税の申告が必要な場合は、書類の準備だけでなく、遺産分割についてじっくりと話し合う時間を確保することも頭に入れてスケジュールを組まなければなりません。
相続の経験のない一般の方が、各手続きや書類の準備にどれぐらい時間がかかるかを想定してスケジュールを組むのは難しいと思いますので、少しでも不安がある方はお早めに相続全般に精通した専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、申告期限まで2か月を切った状態から、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告まで完了させた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】
相談前
お父様を亡くされた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くなく、また、今後…続きを見る-
遺産分割
母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】
相談前
お父様を亡くされた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くなく、また、今後の介護費用等を考えて、お母様に多く相続させるべきか、それとも財産管理をきちんとできるようにお子様が相続するべきかについて悩んでいる、という事で相談にいらっしゃいました。相談後
相続財産のメインは実家不動産で、それ以外の財産はそれほど多くない、というのはよくある話です。特に東京都心などでは不動産が高額になるため、公平に分けることが難しく、分け方をめぐってトラブルになってしまうケースも少なくありません。
幸いにも今回は、財産の分け方や今後の使い道について相続人の意見が大筋では一致していたため、全員が納得・安心できる内容で遺産分割協議書を作成することを提案しました。
お話を伺う中で、ご家族の間にはしっかりとした信頼関係がある事がわかったので、お子様方に今後の方針について確認していただくとともに、お母様に安心していただけるように、不動産以外の財産については、お母様の今後の医療費や介護費用に充てることを条件として、妹様お一人が相続するという内容の遺産分割案を提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、介護等の負担を条件として特定の相続人に多く相続してもらうことを望まれるご家族は少なくありません。
もちろん、信頼関係があれば遺産分割協議書にあえて記載しなくても問題はないのですが、今後のことについて明確にし、後のトラブルを防ぐという意味では、条件や負担があれば、しっかりと明記しておくべきでしょう。
ただし、条件とされた義務や負担が履行されなかった場合でも、そのことによって直ちに協議が無効になったり、一方的に解除できるわけではないという事は頭に入れておく必要があります。
相続人全員による遺産分割協議の合意解除は可能ですが、裁判手続きによって強制的に履行させることなどもできないため、条件を付ける場合は、強い信頼関係がある事を大前提として、確認のために協議書に明記する、という事を理解した上で協議を行いましょう。
記載の仕方等について不安がある場合は、必ず相続に精通した専門家に相談の上で、協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書作成を含む、相続手続全般についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※ご自身で作成中の協議書について、書き方を教えて欲しい等のご質問は、責任を負えないため一切お答えすることができません。ご依頼を検討中の方は無料面談をご予約下さい。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
成年後見
判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなった方からのご相談。
相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。
相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お…続きを見る-
成年後見
判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】
相談前
お父様が亡くなった方からのご相談。
相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。
相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お孫様に障がいがあり、遺産分割協議についての判断能力が無いため、どのように協議をすればいいかわからないという事でご相談にいらっしゃいました。相談後
相続人の中に認知症や障がい等で意思能力(判断能力)が無い方がいる場合、本人の利益を守るために、本人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
このケースでは、すでに相続人であるお孫様のお母様が成年後見人として代理人になっていたため、お母様に遺産分割協議に参加してもらい、協議書への署名捺印をいただくことになりました。事務所からのコメント
遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に意思能力がある事が前提となるため、自分の意思で判断できない方がいる場合は、その方の代わりに成年後見人等の代理人が協議に参加することになります。
このケースではすでに成年後見人が選任されていましたが、未選任の場合は、まず家庭裁判所に申立てを行って後見人等を選任してもらう必要があります。
また、本人と成年後見人等の代理人が共に相続人になる場合(配偶者と子供など)は、後見人等の選任後に、更に申立てを行い、特別代理人等を選任してもらう必要があります。
また、遺産分割協議を行うために後見人等を選任する際は、後々問題が生じないように、本人の財産状況や今後の介護方針等を考慮し、誰を後見人等候補者にして申立てを行うかを慎重に判断する必要があります。
軽い気持ちで後見人になったものの後で問題が生じてしまい、後悔している…ということの無いよう、申立ての際には、相続と成年後見制度に精通した司法書士などの専門家に相談の上で、行うことを強くおすすめします。
成年後見開始の申立てや後見人等がいる場合の相続手続についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
遺言書と異なる内容で相続登記はできる?【遺言書と異なる内容で相続登記を行うケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様2人。
亡くなったのは数年前で、自筆の遺言があったため金融機関の解約手続き等は遺言に従っ…続きを見る-
相続登記
遺言書と異なる内容で相続登記はできる?【遺言書と異なる内容で相続登記を行うケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様2人。
亡くなったのは数年前で、自筆の遺言があったため金融機関の解約手続き等は遺言に従って済ませたが、不動産については今後のことを考えて遺言とは違う分け方で登記をしたいという事で相談にいらっしゃいました。相談後
亡くなった方が遺言を遺していたものの、様々な事情により遺言とは異なる財産の分け方をしたい、という方は多いです。
遺言は故人の想いを反映した大切なメッセージですので、基本的には尊重すべきですが、相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要)がある場合は、遺言と異なる内容で遺産分割を行う事は実務上認められています。
このケースでも、相続人全員が同意の上で、遺言とは異なる分け方で不動産の名義を変更したいという事でしたので、相続人全員の同意の元、新たに遺産分割協議書を作成し、それをもとに相続登記を行うことを提案しました。
また、相続人の皆様がばらばらに暮らしているので、手続きのために集まるのは負担になるとのことでしたので、当事務所で戸籍の収集、不動産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書への署名捺印の手配、相続登記申請までを一括して代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的にはその内容通りに相続手続を行う事とになります。
ただ、遺言を作成した時とは状況が変わっていることは当然あります。不動産を貰っても居住・活用できない、相続税その他の税金の負担が過大になる、等理由は様々ですが、遺言とは異なる内容で不動産やその他の財産を分けたい、というのは良くある話です。
もちろん遺言は尊重すべきですが、このケースのように相続人全員の同意の元、仲良く分けるという事であれば、遺言と違う遺産分割を行っても、故人の想いを無視することなく、むしろ“残された家族が仲良く幸せに暮らしてほしい”という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。また、このような方法は実務上も認められています。
ただし、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、後に揉め事になることを防止するために、通常の遺産分割以上に慎重な配慮が必要です。また、将来の相続税の負担を検討しなくてはならない場合もあります。
よくわからないまま強引に手続きを進めた結果、家族間の関係が悪化してしまった…というのは遺言者の方が最も望まない結末だと思いますので、遺言書と異なる内容で遺産分割を行い、その後の手続きを行おうと考えている方は、相続全般に精通した専門家に相談の上で進めることを強くおすすめします。
遺言書と異なる内容での相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
相続不動産売却のために便宜上単独名義にしたい・・・【換価分割のために便宜上代表相続人の単独名義にする相続登記を行いたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
不動産については今後の利用予定もないため、売却して代金を二人で半分に分けようということで…続きを見る-
相続登記
相続不動産売却のために便宜上単独名義にしたい・・・【換価分割のために便宜上代表相続人の単独名義にする相続登記を行いたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
不動産については今後の利用予定もないため、売却して代金を二人で半分に分けようということで話はまとまっているが、相続人の一人が連絡を取りづらいので、売却の際に支障が出ないように登記の名義については、できれば代表者の単独名義にしたいという事でご相談にいらっしゃいました。相談後
相続した不動産等の財産を売却して、その代金を分けることを「換価分割」といいます。
亡くなった方名義の不動産を換価分割する場合、故人名義のままでは売却することはできないので、一旦相続人の名義へ名義変更(相続登記)をする必要があります。
この相続登記の際、通常は売却後の代金を受け取る割合に応じて共有名義にするのですが、様々な事情から、あえて相続人のうちの一人の単独名義にしてから売却したい、というご要望をいただくことも多いです。
今回は、相続人のうちの一人がなかなか連絡が取れないという事情があり、共有名義にしてしまうと売却活動や売却の際の手続き等に時間がかかってしまい、売り時を逃してしまうかもしれないという事を懸念されていました。
ただ、単純に単独名義にしてしまうと、売却時の税金が一人だけに課税されてしまったり、売却代金の分配の際に贈与税が課税されてしまうリスクがあるため、「換価分割の前提として便宜上単独名義にする」ことを遺産分割協議書等に明示しておくことが必要になります。
しかし、「便宜上」という文言が入った協議書では登記申請が通らない可能性があります。
そこで、当事務所で関係各所に確認の上、登記実務及び税務の両面から問題ないような遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことを提案しました。事務所からのコメント
このケースのように、相続した不動産を売却するために便宜上代表者の単独名義にしたいという方は少なくないです。
しかし、単独名義にしてしまうことには様々なリスクが伴います。
譲渡所得税や贈与税課税等のリスクはもちろん、単独名義人となった代表相続人が、他の方の意向に反して勝手な処分を行ってしまえば、取り消すことは難しいです。
このケースでは、あらかじめ問題が生じないことを確認して行いましたが、似たようなケースであっても、官公署の管轄や相続人同士の関係性などの事情が異なれば、異なる見解、異なる結果になるかもしれません。
手間を省くために行ったつもりが、後でトラブルになってしまいかえって手間がかかってしまった…という事にならにように、不動産売却の前提として相続登記をお考えの方は、相続に精通した司法書士に相談することをおすすめします。
また、売却のための手間を省きたいという事であれば、売却のための面倒な手続きを、専門家にまるごとおまかせするという方法もあります。
ただ、相続登記だけでなく、相続不動産の売却手続きや売却時の税務関係にまで精通した専門家はそれほど多くないので、売却をお考えの方は、相続不動産の売却をはじめとした相続全般に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、売却の前提としての相続登記から、売却後の代金分配、譲渡所得税申告のための税理士の手配まで、相続不動産の売却に必要なすべての手続きを一括しておまかせいただける「相続不動産売却まるごとおまかせプラン」をはじめとして、相続した不動産の売却・有効活用をお手伝いさせていただくためのプランをご用意しております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
ご相談者様は後妻との子供。
相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複…続きを見る-
相続手続き
養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
ご相談者様は後妻との子供。
相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複雑な関係。
それぞれ連絡はとれるものの、被相続人との関係や相続人同士の関係が微妙なため、相続手続きを進めるにあたり不安があるという事で相談にいらっしゃいました。
疎遠な相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
相続を希望されない方について、3か月以内に相続放棄の申立てをしなければならない。
離れて暮らしている相続人と連絡を取り、相続登記や金融機関の解約手続き、相続預金の分配を行わなくてはならない。
相続人がお子様しかいない場合、通常は相続関係はシンプルであり、相続手続きも比較的スムーズに進むことが多いです。
しかしこのケースのように、複雑な事情がある場合は手続きにかかる負担や困難の度合が全く異なってきます。
相続人同士の関係性が微妙な場合は、単に事務的に物事を進めるのではなく、相手の状況、心情にも配慮した上で、慎重に進めなければ、思わぬ理由で手続きが頓挫してしまうことがあります。
幸いこのケースでは相続人同士で連絡を取ることができ、手続きにご協力いただけるという事になりました。
そこで当事務所で、戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。
また、相続人のうちの一人は、財産はいらないので相続放棄をしたいというご意向だったため、他の方の費用負担により、当事務所で相続放棄手続きをサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・戸籍の収集、残高証明書の取得等の必要な調査を行った上で、財産目録の作成を行い、遺産分割協議の前提となる資料を整えました。
・郵送等によるやり取りで、各相続人の意向確認をさせていただいた結果、無事遺産分割協議がまとまり、署名捺印をいただくことができました。
・分割協議成立後に、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約を行い、各相続人への分配までを行いました。
・公平な第三者が間に入ることで、相続人の皆様の負担や不満なく手続きを終えることができました。
・相続放棄を希望された方について、家庭裁判所での相続放棄手続きのサポートを行い、無事相続放棄が認められました。事務所からのコメント
このケースのように相続人同士の関係性が微妙な場合は、例え財産の額がそれほど多くない場合でも、慎重に事を運ぶ必要があります。
なぜなら、相続をきっかけにそれまで表に出さなかった感情が爆発して、それぞれの言い分がぶつかり合い、結果、相続手続が頓挫したり、泥沼の争いに発展してしまうことがよくあるためです。
そうは言っても親族同士なんだから話せばわかる…と思われるかもしれませんが、実際にはそれぞれを取り巻く環境が異なれば、赤の他人より遠い関係性であり、考え方も自分とは全く異なると肝に銘じておくべきです。
また、相続手続きには事務的な面の負担がかなりありますが、ひたすら事務的に手続きを進めようとすると、他の方の気分を害する可能性が高いです。
他人の心情に配慮しながら事務手続きを進めることはかなりの心労を伴いますので、相続人同士の関係性が複雑な方は、相続が発生したら、相続に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談様と妹様のお二人。
ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続…続きを見る-
相続手続き
田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談様と妹様のお二人。
ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続きのための時間が取れないということで相談にいらっしゃいました。
また、相続財産の中に、遠く離れた田舎の田畑や山がたくさんあるということで、何か特別な手続きが必要なのかという事も気になっているとのことでした。
・遺産の分け方については大筋で同意しているものの、仕事が忙しく、戸籍などの必要書類を手配したり、金融機関に手続きに行く時間が取れない。
・相続財産の中に田畑や山林が多数含まれるが、通常の名義変更手続き(相続登記)以外に何か手続きが必要かわからない。
相続財産の中に不動産が含まれる場合、通常は相続登記を行えば、名義変更の手続きとしては十分です。
税務署にも何か届出が必要かと聞かれることが多いのですが、登記の名義変更の情報は税務署も把握しているため、名義変更された翌年以降は固定資産税の納税通知書(納付書)も登記名義人の住所に送られてきます。
ですので、相続登記を行う場合は特別な届出等は不要です。(未登記家屋の場合は役所への届出が原則必要です)
ただし、不動産の地目が田畑や山林の場合は、登記以外にも関係各所への届出が必要になることがあります。
まず、地目が田や畑の場合は、管轄の農業委員会へ、権利を取得したことを知った日から10か月以内に、相続によって農地を取得したことを届け出る必要があります。
ただし、登記簿上の地目が田や畑であっても現況は宅地や雑種地である(=農地ではない)というケースも多いため(その場合は届出が不要なこともあります)、まずは当事務所で管轄の農業委員会に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。
また、地目が山林の場合は、その土地が「森林の土地」に該当するときは、土地の所有者となった日から3か月以内に、市町村等に所有者変更の届出が必要になります。
こちらも山林全てが「森林の土地」に該当するというわけではないので、当事務所で役所の担当部署に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。
また、お仕事等でお忙しく、手続きのための時間が取れないという事でしたので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して代行させていただくことを提案しました。相談後
・農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
・役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
・お忙しい相続人の皆様に代わって、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更までを一括して代行し、ご相続人様の負担なく手続きを完了させることができました。事務所からのコメント
このケースのように田舎の不動産を相続したものの、そもそもその不動産がどこにあるのかもわからないし、どんな手続きが必要かもわからないと悩まれる方は多いです。
農地や森林の土地を相続した場合は登記とは別に届出が必要なことを知らず、放置される方も多いのですが、どちらも届出の期限が決まっており、放置することによって今後の農地や森林の管理に支障を及ぼす可能性があります。
相続登記についてはほとんどの司法書士で問題なく対応可能ですが、こういった細かい手続きにまで精通している司法書士は(特に都市部では)少ないので、田舎の不動産を相続された方はお早めに相続手続きに精通した司法書士等に相談されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
不動産の共有者の相続人が不明・・・調べることはできる?【血縁関係のない不動産共有者の相続人調査が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人の合計3名。
お父様の単独名義だと思っていた不動産について、亡くなった後に登記簿を確…続きを見る-
相続手続き
不動産の共有者の相続人が不明・・・調べることはできる?【血縁関係のない不動産共有者の相続人調査が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人の合計3名。
お父様の単独名義だと思っていた不動産について、亡くなった後に登記簿を確認したところ、実はかなり前に亡くなったご祖父様(亡父の父)の後妻との共有名義であることが発覚したとのこと。
現在の相続人が誰であるかまったく見当もつかないという事で、お父様の相続手続きの件も含めてご相談にいらっしゃいました。
・すでに亡くなっている不動産の共有者について、現在の相続人を確認して名義変更の交渉等を行いたいが、相続人にまったく心当たりがなく、調査する方法もわからない。
・自分たちや後の世代が困らないように、父名義の不動産持分と預貯金等についてはしっかりと相続手続を行っておきたい。
亡くなった方名義の不動産を調査したところ、実はその親やその前の世代から名義変更しないままになっていたというケースは珍しくはありません。
このような場合、まず戸籍を取得して名義人の方の相続関係を調査しなくてはなりません。
その後戸籍で確認した現在の相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議書へ署名捺印をもらい、印鑑証明書を提出してもらう事で名義変更が可能になります。
こう書くとそれほど難しくなさそうに聞こえるかもしれませんが、亡くなったのが数十年前だったりすると、その間に次々と相続が発生していることがあります。
相続人が数十人(時には100人を超えることも!)になったり、さらにその中で連絡が取れない方や行方不明の方がいたりすることも多く、実際にはかなり大変な作業です。
手続きのための膨大な手間と費用がネックとなり途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。
とは言え、相続人を確定させるために必要な戸籍については、亡くなった方の相続人であれば時間さえかければ収集することが可能です。
相続登記のためという正当な理由があれば、関係者の戸籍を請求することができるからです。
ところがこのケースでは、ご相談者様一家は亡くなった共有者の方の相続人ではありませんでした。
ご祖父様の後妻と亡くなったお父様は同居して親子同然に暮らしていたものの、養子縁組はしていなかったので、戸籍上はあくまで赤の他人となります。
そうなると相続登記のために必要という理由では戸籍を取得することはできません。
当初、相続関係の調査は難しいかと思われたのですが、ヒアリングの結果、実はお父様はこの事実を把握しており、「後妻の相続人が全員亡くなった後は、共有持分は自分たち家族のものになるから大丈夫。」と言っていたのを生前奥様が聞いたことがある、という事実が判明しました。
確かに、相続人が一人もいない場合、所定の手続きを踏めば、共有物については他の共有者が取得できる可能性があります。(民法第255条)
そこで、相続人が本当に誰もいなかった(全員死亡していた)場合には、相続財産管理人選任の手続きを経て共有持分をお父様の相続人に帰属させることを視野に入れ、当事務所で共有者である後妻の戸籍を取得し、相続関係の調査を代行することを提案しました。相談後
・10を超える役所に請求を行い、50通以上の戸籍を取得し、相続関係を調査しました。
・踏査の結果、共有者である後妻には現在も生存している相続人が複数名いることが判明しました。
・相続人がいるため、共有者への財産帰属による名義変更はできないことがわかりましたが、自分ではとてもできなかったという事で、調査結果には満足していただけました。
・共有状態の解消については、どのような解決方法があり、今後どうしていくのがベターかをアドバイスさせていただきました。
・お父様の相続手続きについては、戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、相続登記や金融機関の解約までを一括して代行させていただき、滞りなく完了させることができました。事務所からのコメント
不動産の名義が、大昔に亡くなった方のまま放置されているというケースは珍しくありません。
このケースのように相続人調査すら難しいというのはさすがに稀ですが、名義人が自分の直系尊属(祖父母や曽祖父母など)であっても、亡くなってから時間が経っていれば膨大な量の戸籍の収取が必要となります。
調査の結果判明した相続人に一人ずつ連絡を取るのにも大変な労力を要することになります。
後の世代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したら、すみやかに登記の専門家である司法書士に相談の上、相続登記を済ませておくべきです。
また、このケースでは実の親子同然に暮らしていたにもかかわらず、戸籍上は赤の他人だったため相続することができないという大変残念な結果を招くことになってしまいました。
このような結果を防ぐためには、後妻とお父様が養子縁組をしておくか、お父様に不動産を遺贈する旨の遺言を遺しておけばよかったのです。
ただし、養子縁組や遺言のような生前対策は、方法を誤ると効果がないばかりか、かえってトラブルの原因になってしまう事さえあります。
どの方法が適切かはそれぞれの家族事情等によって異なりますので、生前の相続対策をお考えの方は、法律面だけでなく、相続実務にまで精通した司法書士などの専門家に相談の上で実行することを強くおすすめします。
遺言書や養子縁組など、生前の相続対策についてのご相談や、複雑な事情のある相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
不動産が全国各地に⁉相続登記を迅速に行うためにはどうすればいい?【管轄の異なる複数の地域に不動産が存在するケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
生前に信託銀行の遺言信託業務で遺言を作成されていて、遺言執行はお父様の意思を汲ん…続きを見る-
相続登記
不動産が全国各地に⁉相続登記を迅速に行うためにはどうすればいい?【管轄の異なる複数の地域に不動産が存在するケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
生前に信託銀行の遺言信託業務で遺言を作成されていて、遺言執行はお父様の意思を汲んで組んでそのまま銀行に任せることにしたとのこと。
しかし銀行から紹介された税理士と司法書士に不満があるという事で、相続税申告と相続登記については別の所に頼みたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
・不動産が管轄の異なる4つの地域に存在しているため、登記申請のための資料集めに手間がかかる。
・遺言執行者から必要書類を一時的に預かって登記申請を行うため、4か所の法務局への登記申請を手際よく行い、迅速に手続きを完了させなければならない。
不動産の名義変更は、その不動産が存在する地域を管轄する法務局に登記を申請して行います。
管轄が同じ不動産であればまとめて申請することも可能ですが、管轄が異なる不動産については、たとえすべて同じ人が取得するとしても、別々に登記を申請しなければなりません。
相続登記については、相続税申告のような短期間(相続開始から10か月以内)の期間制限はないため、通常であれば一つずつ順番にゆっくりと申請していっても大丈夫です。
しかしこのケースでは、登記のために必要な書類のほとんどを遺言執行者である信託銀行が預っていました。
年内に登記を済ませたいというご要望だったため、先に登記申請を行うという事で銀行から必要書類を借りることはできたのですが、書類は各1部ずつしかありません。
遺言書等は金融資産等の遺言執行時にも必要になるので、できるだけ早く返却して欲しいという要望を銀行から受けました。
そこで、当事務所で登記申請のための不動産資料請求を4か所同時に行い、書類が届いた所から順に登記申請を行う事で、できるだけ迅速に登記を完了させることを提案しました。相談後
・登記申請のための不動産資料請求を4か所同時に行い、登記申請のための準備を最短で整えました。
・4か所の法務局に順番に登記申請を行い、迅速に登記を完了させ、遺言執行が滞ることのないよう速やかに書類を返却することができました。事務所からのコメント
亡くなった方がたくさんの不動産をお持ちの場合、特に異なる地域にいくつもの不動産を持っていた場合は調査をするだけでも大変な手間がかかります。
たくさんの不動産がある場合には、登記漏れが無いよう名寄帳等を取得して、課税明細に載っていない物件がないかを特に慎重に調査すべきです。
ところが、遺言書がある場合は遺言書に記載されたものがすべてという思い込みがあるため、調査を怠ってしまいがちです。
売却が決まった等の理由で迅速に登記を済ませたい場合でも、登記漏れの物件があったために後でトラブルになってしまっては元も子もないので、調査は必ず行うべきです。
たくさんの不動産がある場合や、迅速に登記を済ませたい事情がある場合は、相続登記に精通した司法書士に、戸籍収集や不動産調査含めて依頼されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】
相談前
叔父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。
主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみ…続きを見る-
相続手続き
相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】
相談前
叔父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。
主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみであり、相続人間で公平に分けることで一応の合意はできているものの、戸籍の収集や相続人間でのやり取りや書類の手配が大変という事で相談にいらっしゃいました。
・相続人である兄弟姉妹や甥姪合計10人に連絡を取り、それぞれから遺産分割協議及び相続手続きについての協力を取り付ける必要がある。
・相談者も含めて、相続人はほとんどが地方在住のため、郵送等でのやり取りにかなり手間がかかる。
・相続関係を証明するために膨大な量の戸籍を取得しなくてはならない。
・建物の名義人のうちの一人については、かなり前に亡くなっており、相続登記をしない間に二次相続が発生してしまっているため、戸籍を調査して現在の相続人を確認する必要がある。
・不動産については売却して代金を公平に分配することを考えているが、関係者が多く、代表者の方も地方に住んでいるため、売却活動や売却のための諸手続き等を行うのが難しい。
・関係者が多く、調整が大変なため、代表者の方が手続きを行うと過大な負担となる。また、相続預金分配の方法等で後になって揉めることは避けたい。
・さらに、お話を伺う中で、実は土地については叔父様名義だが、その上に建っている建物2つについてはそれぞれ別の親族の名義になっていることが判明しました。
亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人である場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。
また、兄弟姉妹の方が亡くなっていればその子供(甥姪)が相続人になるのですが、この場合はそもそも亡くなった方との関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことも多いです。
このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で頻繁に上京することが難しいという事情もありました。
そこで、特定の方に負担がかからないように、当事務所で、戸籍収集、各相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び各相続人への分配、さらには相続した不動産の売却及び売却代金の分配まで、必要な手続きを全て代行させていただくことを提案しました。
また、30年以上前に亡くなった建物の名義人のうちの一人について戸籍を調査した結果、やはり複数の相続が発生しており、現在の相続人は全く知らない方であることが判明しました。
そこで判明した相続人に当事務所で連絡を取り、事情を説明して手続きに協力してもらえるようサポートさせていただくことを提案しました。
ご依頼をいただいてからは、膨大な量の戸籍を収集して相続人の確定作業を行い、各相続人に電話や手紙で連絡を取って協力を取り付ける等の地道な作業を少しずつ進めていきました。
その結果、時間はかかりましたが、何とか全員から同意を貰うことができました。
戸籍もそろったので、遺産分割協議書を作成して関係者全員に郵送して後は印鑑証明書と一緒に返送してもらえれば、相続登記や預貯金の解約手続きができる…と思っていた矢先に新たな問題が発生しました。
実は、相続人のうちのお一人(当初の被相続人のきょうだいの方)が突然亡くなられてしまったのです。
この場合は亡くなった相続人の相続人(二次相続人)に遺産分割協議に参加してもらい、手続きに協力してもらうことになります。
幸いお子様二人が相続人という事で、連絡先はわかったのですが、他の相続人の方とはほとんど面識がないとのことでした。このような関係性の場合は慎重に事を運ぶ必要があります。
そこで、失礼のないように四十九日が明けてから、当事務所の方でまずはお手紙を出させていただき、ご連絡が欲しい事をお伝えし、今後の手続きへの協力をお願いすることになりました。相談後
・膨大な量の戸籍を収集し、それぞれ相続関係の異なる3人の被相続人について、相続人を確定することができました。
・全国各地にいる10人(後に増えたため合計12人)の相続人に一人ずつ連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。
・面識のない相続人の方については特に慎重な対応が必要だったため、書面等で丁寧に事情を説明させていただきました。結果、無事同意を貰い、手続きに協力してもらうことができました。
・特定の方に負担がかからないように、遺産分割協議の調整及び協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び分配まで、必要な手続きを全て代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。
・不動産の売却についても当事務所で手配を行い、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートいたしました。事務所からのコメント
相続手続きを放置している間に、今度は相続人に相続が発生してしまい、遺産分割協議書に印鑑を貰う相手が増えてしまった…というのはよくある話です。
特に兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人自身も高齢であることが多いので、亡くなってから数か月の間に次の相続が発生してしまうという事もあり得ます。
今回のケースはそもそもの相続関係が複雑な上に、さらに相続が発生してしまったという事で手続きは困難を極めました。
一度は相続人全員から同意を貰ったものの、正式に遺産分割協議書に署名捺印をいただく前に亡くなってしまった以上、再度協議が必要になります。
最悪の場合、協議がまとまらず、遺産分割調停や審判が必要になるというケースまで想定されました。
幸いにも面識のない相続人の方からご協力いただけるとの返事をすぐにもらえたため、さらに長期化して次の相続が発生して…という泥沼の事態は避けられました。
しかし、面識のない相続人がいる場合、まず連絡を取ることが困難な上、連絡を取れたとしても、手続きへの協力を貰うことが難しいという事態も想定しなくてはなりません。
不動産の相続登記については、現時点(2020年現在)では、登記をしないことによる罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、今はシンプルな相続関係であっても、年月を経れば経るほど相続関係は複雑になっていきます。
そうなると関係者全員から同意を得るのはどんどん難しくなってしまいます。また、解決のための手間と費用が重くのしかかってきます。
さらに2024年以降は罰則(10万円以下の過料)付きで義務化されることが決まっているので手続きを放置するメリットは何もないと言えます。
不動産を処分したくても、関係者から同意を貰えないので処分できない…という最悪の事態を避けるためにも、相続が発生したらすみやかに相続に精通した司法書士などの専門家に相談の上、相続手続きを完了させることを強くおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
不動産だけでも50筆以上!財産がたくさんあって調査が大変・・・【相続財産の種類が多く、手続きが大変なケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様(養子)一人。
もともとお子様がいない方だったのですが、ご相談者様に財産を託したいという事で亡く…続きを見る-
相続手続き
不動産だけでも50筆以上!財産がたくさんあって調査が大変・・・【相続財産の種類が多く、手続きが大変なケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様(養子)一人。
もともとお子様がいない方だったのですが、ご相談者様に財産を託したいという事で亡くなる少し前に養子縁組をされたため、ご相談者様のみが相続人になったという経緯がありました。
相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議も不要なので、当初は手続きは難しくないかと思われました。
しかし、故人はたくさんの財産をお持ちで、特に不動産については50以上もあり、その多くが地方の田畑や山で、どこにあるかもよくわからず、相続税申告のための資料集めも一人では手に負えないという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・不動産が50筆以上あり、すべてを把握できていないため、詳細に調査をして漏れのないようにリストアップする必要がある。
・地目が田畑や山の不動産については、相続登記とは別に関係各所への届出が必要な可能性がある。
・10近くの金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整える必要がある。
・株式等の証券も持っていたようだが、詳細がほとんど不明なため、調査をして確かめる必要がある。
・保険契約やその他の財産についても詳細を確認し、資料を収集して、10か月以内に相続税の申告を完了させなくてはならない。
相続人が一人のみの場合、相続人間のやり取りは不要なため、手続きとしてはやりやすい部分もあります。
しかしこのケースでは、財産の数や種類がとにかく多く、しかも亡くなる少し前に養子縁組をするまでそれほど交流はなかったという状況でした。
結果として、財産の詳細についてはほとんどわからないにも関わらず、10か月以内に資料を集めて相続税の申告をしなくてはならないという大変難易度の高いご依頼となりました。
このような場合、まず必要な手続きをリストアップしてスケジュールを組み、期限内に完了するよう手際よく迅速に財産調査を完了させる必要があります。
特に不動産については、多くの不動産が先に亡くなられたご主人様名義のままであるという事が判明したため、ご主人様名義の財産も含め徹底的に調査を行う必要がありました。
しかし、ご相談者様は都内在住で、亡くなられた方は遠く離れた地方在住だったため、調査や手続きのために頻繁に出向くのは物理的に難しいとのことでした。
そこで、当事務所で、不動産、預貯金、株式、投資信託、保険契約その他あらゆる財産についての調査を行い、迅速に相続税申告の準備を整え、その後の名義変更や解約手続きについても全面的にサポート・代行させていただくことを提案しました。相談後
・不動産については、配偶者名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように徹底的に調査を行いました。
・10近くの金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整えました。
・株式等の証券についてはほふりに開示請求を行い、判明した証券会社等についても調査を行い、相続税の申告準備を整えました。
・保険契約やその他の財産についても詳細を確認し、資料を収集して、10か月以内に相続税申告を完了させることができました。
・その他にも、不動産の名義変更、預貯金や証券の解約・移管手続き、農地や森林の土地についての届出等のあらゆる手続きをサポートさせていただき、ご相続人様の負担なく完了することができました。事務所からのコメント
このケースのように相続人が一人の場合、他の相続人との調整等が必要ないため、自分ですべての手続きを行うのも簡単なように思われるかもしれません。
しかし、実は当事務所に相談にいらっしゃるお客様の中で、相続人がお一人のみのケースはかなりの割合を占めます。
というのも、他に相続人がいないので、すべての手続きを自分で行わなければならず、困ったことがあっても相談する相手もいないため、想像以上に手続きが負担になることが多いのです。
ましてやこのケースのように財産が多く、種類も多岐にわたり、詳細もよくわからないという状況から、一人ですべての手続きを完了させることはほとんど不可能と言っていいでしょう。
しかし、一人ではとても不可能と思われた手続きでも、相続の専門家にまかせればあっという間に解決するという事はよくあります。
手続きをあきらめて放置するわけにもいかないが、自分一人ではとても手に負えそうにない…という方は、相続全般に精通した専門家にすぐに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
父の借金⁉とっくに返済終わったはずだけど・・・【完済済みの借入に関する根抵当権の抹消登記をしていなかったケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
当初はお父様名義の実家不動産を相続人の名義に変更したいという事でいらっしゃいまし…続きを見る-
相続手続き
父の借金⁉とっくに返済終わったはずだけど・・・【完済済みの借入に関する根抵当権の抹消登記をしていなかったケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
当初はお父様名義の実家不動産を相続人の名義に変更したいという事でいらっしゃいました。
しかし登記簿を確認したところ、根抵当権が設定されており、債務の状況についての確認が必要という事が判明しました。
▼問題点
・30年以上前に設定された根抵当権について、債務が残っているかを確認しなくてはならない。
・もしすでに完済済みの場合、根抵当権抹消のための書類を抵当権者から発行してもらい、抹消登記を申請する必要がある。
亡くなられた方が、以前住宅ローン等で金融機関からお借入れされた際に設定した抵当権が、抹消されずにそのままになっているというのは良くある話です。
とっくに返済は終わっており、抹消の登記をしていないだけ、という方が多いのですが、もし債務が残っていれば、債務の返済や承継手続き、債務者の変更登記など、金融機関と話し合って行う必要があります。
また、このケースのように抵当権ではなく“根”抵当権の場合はより注意が必要です。
根抵当権(ねていとうけん)とは、債権者(金融機関等)と債務者の間で、あらかじめ貸し出しできる上限(極度額)を決めておき、その範囲内でなら何度もお金を借りたり返したりすることができるよう不動産で担保するというものです。
通常の抵当権は一つの契約に紐づくため、借金を完済すると抵当権も消滅するのですが、根抵当権の場合は、完済してもまた別の契約を結んでお金を借りる可能性があるので、原則として当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません。
普通の方は担保が必要なほどの大金を何度も借りたりはしないので、根抵当権が設定されている場合は、不動産の所有者が個人事業主や法人の経営者であることがほとんどです。
亡くなった方が個人事業主や法人の経営者の場合、事業上の借入があったり、付き合いで誰かの連帯保証人になっていたりすることがあるので、財産や債務についてより詳細に調べる必要があります。
幸いにもこのケースでは、お父様は昔商売をされていたものの、とっくの昔にやめられており、借り入れはなく、保証人になっていることも無いとのことでした。
そこで当事務所で金融機関に連絡を取り、債務を完済していることを確認の上、抹消登記に必要な書類を出してもらい、相続登記と一緒に根抵当権抹消登記申請を代行させていただくことを提案しました。相談後
・金融機関に連絡を取り、債務を完済していることを確認の上、根抵当権抹消登記に必要な書類を出してもらいました。
・相続登記と一緒に根抵当権抹消登記を申請し、無事登記を完了させました。
・相続登記に必要な戸籍の収集、評価証明書・名寄帳の取得、遺産分割協議書の作成及び署名・捺印の手配等も当事務所で代行し、相続人の皆様の負担なく手続きを完了させることができました。事務所からのコメント
このケースのように、とっくに完済した借入金についての抵当権や根抵当権が抹消されずにそのままになっているというケースは多いです。
抵当権が残ったままでも、普通に生活している分には全く支障がないため放置されてしまう方も多いのですが、抵当権が残ったままでは第三者への売却等はできないのが基本です。
売却が決まってから慌てて抹消登記のご相談にいらっしゃる方も多いのですが、抵当権がかなり昔に設定されている場合は注意が必要です。
抵当権者である金融機関が合併や事業譲渡を何度も行っているため、現在の抵当権者を探すのに手間取ったり、抹消の前提として抵当権移転の登記が必要だったりすると、抹消登記に予想以上に時間がかかることもあります。
抵当権の抹消登記に時間がかかったせいで、せっかく決まった契約が流れてしまった…ということの無いように、相続した不動産に抵当権が付いていることが分かった場合は、相続に強い司法書士にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
母と父が相次いで亡くなってしまった・・・遺産分割協議はどうすればいい?【父母が相次いで亡くなってしまったケース】
相談前
ご両親が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
お母様が亡くなられてから1か月も経たないうちにお父様も亡くなられてしまい、お母様の遺産分…続きを見る-
遺産分割
母と父が相次いで亡くなってしまった・・・遺産分割協議はどうすればいい?【父母が相次いで亡くなってしまったケース】
相談前
ご両親が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
お母様が亡くなられてから1か月も経たないうちにお父様も亡くなられてしまい、お母様の遺産分割協議も終わっていないので、どのように進めていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・お母様の遺産分割協議を行う前にお父様が亡くなってしまったため、誰が協議を行えばいいか確認する必要がある。
・財産の中に株式があったため、念のため把握している以外に証券口座がないか確認する必要がある。
・お父様の方は相続税の申告が必要なため、期限内に遺産分割協議を成立させ、申告を完了する必要がある。
亡くなった方の遺産分割協議は、相続開始時点の相続人全員で行わなければなりません。
しかし、このケースのように残念ながら協議成立前に相続人の方が亡くなられてしまうこともあります。
このような場合、亡くなられた相続人の相続人(二次相続人)が遺産分割協議に参加することになります。
このケースではお母様とお父様の相続人はお子様二人で全く同じだったため、お母様とお父様についての遺産分割協議を二人で行えばいいことになります。
ただし、ご相談時点でお父様については相続税の申告期限まで3か月を切っていたため、早急に財産調査を完了させ、ご両親それぞれの遺産の範囲を確定させる必要がありました。
そこで、当事務所で戸籍の収集や財産調査等を迅速に行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続きもサポートさせていただくとともに、相続に強い税理士と連携の上、相続税の申告についてもサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・調査のために必要な戸籍の収集を迅速に行い、金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴の請求を行いました。
・証券についてはほふり(証券保管振替機構)の開示請求を行い、把握している以外に口座がないかの確認を行いました。
・不動産その他についても調査を行い、迅速に必要な資料を揃え、遺産の範囲を確定させることができました。
・遺産分割協議についても、税理士とともにサポートさせていただき、迅速かつ円満に協議を整えることができました。
・遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配を迅速に行い、期限内に申告を終えることができました。
・不動産の名義変更、預貯金の解約および分配、株式の移管手続きについても当事務所で代行し、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。事務所からのコメント
このケースのように、高齢のご両親が相次いで亡くなられてしまうケースは少なくありません。
そのような場合、先に亡くなった方の遺産分割協議が終わっていなければ、二次相続人が遺産分割協議に参加することになります。
大抵はお子様たちが相続人で、相続関係は全く同じという事が多いので、大きな問題にならない事が多いのですが、ご両親の相続関係が異なる場合(例えば前妻との間に子供がいるなど)はやっかいなことになるかもしれません。
先の相続と後の相続でそれぞれ相続人が異なる場合は、基本的に先に発生した相続について遺産分割協議を行い、遺産の範囲を確定させなければ後の相続について遺産分割協議を行う事はできません。
遺産分割協議ができなければ、相続税の申告にも大きな影響を及ぼします。
遺産分割協議の前提としての資料集めや、協議成立後の解約・名義変更手続きについても、二人分の相続となるとかなりの負担になりますので、いずれにしても相続が発生した場合は、相続に精通した専門家に早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様3人。
お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無い…続きを見る-
遺産分割
障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様3人。
お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無いため、どのように相続手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、遺産分割協議を行うにあたり、成年後見人の選任が必要。
・さらに相続人の方が成年後見人になる場合は、特別代理人の選任も必要。
・成年後見人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(被後見人)の法定相続分の確保が必要。
相続人の中に障がい等で判断能力(意思能力)が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。
知的障害をお持ちであっても、必ずしも意思能力が無いというわけではありません。
しかしこのケースでは、本人の財産管理は同居しているお母様と亡くなったお父様が行っており、日常生活にもサポートが不可欠という状況だったため、ご本人には分割内容の是非について判断する能力は明らかにないと思われました。
そこで今後のことも考えて、ご本人(三女)様と同居している長女様を成年後見人候補者として申し立てを行うことになりました。(お母様はご高齢のため後見人になるのは難しいと判断しました。)
ただし、今回は三女様と長女様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長女様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。
そのため成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
そこで、長女様が無事成年後見人に選任された場合は、当事務所の司法書士を特別代理人として選任してもらうための申立てを行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続き等まで一括してサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・三女様について申立てに必要な資料の収集を行い、成年後見開始の申立てを行いました。
・成年後見人選任後に、当事務所の司法書士を候補者として特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。
・遺産分割協議には、特別代理人として当事務所の司法書士が参加し、ご本人の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。
・当事務所で戸籍等の収集、財産調査、財産目録及び遺産分割協議書の作成、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して行い、ご相続人様ご自身でほとんど動くことなく手続きを完了することができました。事務所からのコメント
このケースでは、ご家族の方が以前から成年後見人の必要性を感じており、今後のことを考えて後見制度の利用に前向きだったため、迅速かつ円満に解決することができました。
しかし、後見制度は、本人の利益を守るために仕方がないとは言え、やや硬直的な運用がなされるため、使い勝手が悪いと感じられ、利用を望まれない方もいらっしゃいます。
また、利用することに異存は無いとしても、誰を後見人(候補者)にするかは慎重に検討する必要があります。
後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまでやめることはできないので、軽い気持ちで引き受けたものの、思った以上に大変で後悔しているという親族後見人の方の話を聞くことも少なくありません。
制度の運用は時間と共に変わっていきますので、後見制度の利用を検討されている方は、制度の実情に精通した司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
また、成年後見開始の申立ての際には事前に様々な資料を集める必要がありますが、慣れていないと思った以上に準備に時間がかかります。
特に遺産分割協議のために成年後見等開始の申立てを行う場合は、特別代理人が必要になることが多く、特別代理人選任申立ての際は遺産分割協議案の提出が原則必要なため(家庭裁判所によって異なります)、より入念に準備を整えておく必要がああります。
相続手続きと並行してこのような準備を整えるのは、大変負担となりますので、相続をきっかけに後見制度の利用を検討されている方は、成年後見制度だけではなく相続にも精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】
相談前
妹様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄と妹の二人。
きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思…続きを見る-
相続手続き
遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】
相談前
妹様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄と妹の二人。
きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思うように進んでいないとのこと。
二人とも高齢のため、今後の手続きを自分たちだけで行うのは難しいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・きょうだい間相続のため、手続きに必要な戸籍の数が多く、集めるのが大変。
・相続人が離れて暮らしているため(栃木と横浜)、遺産分割の話し合いをまとめるのが大変。
・話し合いがまとまっても、遺産分割協議書署名押印をもらうためのやり取りが大変。
・預金口座は栃木県にあるが、近くに住んでいる方は高齢のため自身で動くことが難しい。
亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人確定のために、本人の生まれてから亡くなるまでの戸籍に加えて、ご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるため、戸籍の収集作業は通常に比べてかなり大変な作業になります。
また、請求先の役所の担当者が不慣れな方だと、直系尊属(父母、祖父母など)以外の方の戸籍を請求するには本人からの委任状(つまり亡くなったきょうだいからの委任状!)が必要と言われて、発行してもらえない事がたまにあるようです。
もちろん、戸籍は正当な理由があれば委任状が無くても請求可能なので、相続手続きのために必要という理由であれば交付してもらえます。
ですが、よくわかっていない窓口の方に対してこちらが正しいことを説明してするのは、普通の方には大変骨が折れる作業でしょう。
この方も、そのような対応を受けてしまい、戸籍集めの段階でつまずいているとのことでした。
また、きょうだい間相続の場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。
この方も自分が一番近くに住んでいるので、本来であれば動きたいところだけど、身体もきついので、手続きのために何度も金融機関や役所へ足を運ぶことは難しいとのことでした。
そこで、当事務所で、戸籍収集、相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。相談後
・複数の役所から多数の戸籍を取集し、相続人を確定することができました。
・遠方の相続人に連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。
・相続人様に負担がかからないように、当事務所で、残高証明書等の取得、遺産分割協議の取りまとめ、不動産の相続登記、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。事務所からのコメント
このケースのように、兄弟姉妹が相続人となる場合はすでに相続人自身が高齢であり、離れて暮らしていることも多いため、手続きにかかる負担は想像以上に重くなります。
とは言え、手続きを放置している間に次の相続が発生してしまうと、相続関係が余計複雑になり、手続きを完了させることはより困難になります。
兄弟姉妹が亡くなり自分が相続人になってしまった…という方は、次の世代に迷惑をかけることのないように、相続に精通した司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
きょうだい間相続の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
よくわからない田畑や山がたくさん・・・地主の相続は登記漏れにも注意!【多数の不動産について相続登記が必要なケース】
相談前
ご主人様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は奥様とお子様4人。
かなりの数の不動産をお持ちで、その中にはどこにあるのかもよくわからない田畑や山も…続きを見る-
相続登記
よくわからない田畑や山がたくさん・・・地主の相続は登記漏れにも注意!【多数の不動産について相続登記が必要なケース】
相談前
ご主人様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は奥様とお子様4人。
かなりの数の不動産をお持ちで、その中にはどこにあるのかもよくわからない田畑や山も含まれているため、自分たちの手に負えそうにないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・不動産が40筆以上あり、すべてを把握できていないため、詳細に調査をして漏れのないように名義変更を行う必要がある。
・地目が田畑や山の不動産については、相続登記とは別に関係各所への届出が必要な可能性がある。
・未登記の家屋があれば別途自治体への届出が必要になる。
亡くなった方が多数の不動産をお持ちの場合、名義変更(相続登記)を行うにあたっては慎重に物件調査を行う必要があります。
というのも、このような場合、すべての物件について相続人の方が存在を把握している事は稀で、権利証などの資料も全部は残っていないため、登記漏れが生じる可能性が高いのです。
通常、不動産については毎年送られてくる固定資産税納税通知書や、登記の際に発行された登記済権利書などで存在を確認します。
ところが、墓地などの非課税不動産や、私道などの共有名義の不動産については課税明細(固定資産税納税通知書)に載っていないこともあります。
こうなると一般の方には確認することが難しく、不動産が多数ある場合は特に漏れが生じてしまいやすいのです。
そこでこのような漏れを防ぐためには、「名寄帳」を取得するという方法があります。
名寄帳はその自治体が管轄する不動産について所有者単位で編集されたもので、「固定資産課税台帳」や「土地家屋台帳」と呼ばれることもあります。
今回も、登記を申請する前にまず当事務所で名寄帳を取得して、漏れが無いよう調査を行うことを提案しました。
また、不動産の地目が田畑や山林になっている場合は、登記以外にも農業委員会や市町村等への届出が必要になることがあります。
さらに、建物が未登記の場合、管轄する自治体へ「未登記家屋所有者変更届」が必要になります。
そこで、当事務所で、登記だけではなく、各種届出が必要かについても確認を行い、届出が必要な場合には手続きについてアドバイス・サポートさせていただくことを提案しました。相談後
・共有名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように徹底的に不動産調査を行いました。
・農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
・役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
・未登記家屋については、未登記家屋所有者変更届のためのサポートをさせていただきました。
・お忙しい相続人の皆様に代わって、当事務所で遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、相続登記申請を代行し、無事相続人様への名義変更を完了させることができました。事務所からのコメント
このケースのようにたくさんの不動産をお持ちの方が亡くなられたケースでは、自分たちが把握している不動産がすべてかどうかもわからなければ、どんな手続きが必要かもわからないという方は多いです。
名寄帳を取得すれば少なくともその管轄内の不動産については調査することが可能なのですが、それだけでは完璧ではないかもしれません。
信じられない話かもしれませんが、司法書士が関与した相続登記でも、後になって登記の漏れが発覚したという話を聞くことはあります。
仕方のない事情で漏れたケースもあるのですが、事前に調査をしていれば防げたというケースもたまにあります。
相続登記に強い司法書士であれば、名寄帳の取得はもちろん、登記簿の情報から別の不動産の存在に気づくこともあります。
相続登記をご依頼の際は必ずその司法書士が相続に詳しいか確認しておきましょう。(少なくとも名寄帳の取得すらしない所はやめておきましょう)
また、農地や森林の土地を相続した場合の届出や、未登記家屋の所有者変更届については、相続手続き全般に精通した司法書士でなければ、そもそもそのような手続きが必要なことも知らず、依頼者へのアドバイスもできないでしょう。
“相続登記だけ”であればほとんどの司法書士で問題なく対応可能ですが、こういった細かい手続きにまで精通している司法書士は(特に都市部では)実はとても少ないです。
亡くなった方が多数の不動産をお持ちだった場合は、お早めに相続手続き全般に詳しい司法書士に相談されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
借地の相続、登記以外に何が必要?【借地権を相続したケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様2人。
遺産の中に借地とその上に建っている建物があるため、名義変…続きを見る-
相続手続き
借地の相続、登記以外に何が必要?【借地権を相続したケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様2人。
遺産の中に借地とその上に建っている建物があるため、名義変更登記が必要だとは思うものの、登記以外の手続きが必要かについて不安があるという事で相談にいらっしゃいました。
また、お孫様二人は離れて暮らしているため、必要書類の手配などでどれだけ手間がかかるのかも心配しているとのことでした。
▼問題点
・借地権については相続登記とは別に、地主に連絡を取り、名義変更手続きを行う必要がある。
・離れて暮らしている相続人がいるが、必要書類の手配などで必要以上の手間をかけるのは避けたい。
他人が所有している土地の上に自分名義の建物が建っている場合、地主(土地所有者)に対して地代を支払っていれば、建物所有者には「借地権」という権利が発生します。
借地権については借りているだけという認識のため、遺産にはカウントしなくていいと思われている方も多いのですが、れっきとした権利であり、遺産として相続税評価の対象にもなれば、売買することも可能です。
都心部にも借地権は数多く存在しており、数千万円で取引されることもざらです。
相続財産なので、借地権にも相続手続きが必要なのですが、一般的に借地権(建物所有目的の土地賃貸借契約)は登記されません。
そこでどのような手続きが必要かというと、通常は、以下の2つを行うことになります。
①地主に連絡を取り、建物所有者に相続が発生した旨を通知し、今後の地代の支払方法等を確認する。必要であれば地主が指定する書面を提出する。
②建物について相続人名義への所有権移転登記(相続登記)を行う。
このうち②についてはどのようなケースでも手続きの内容にほとんど違いはありません。
しかし①については、地主によって細かく手続き方法や提出書類を指定されることもあり、手順に従わなければ今後の関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、まずは地主に連絡を取っていただき、手続きの手順と名義変更のために必要な書類を確認していただいた上で、適切なタイミングで建物の相続登記と借地権の名義変更手続きを行うことを提案しました。
また、離れて暮らすお孫様二人については、当事務所で遺産分割協議書等の書類の郵送及び署名捺印の手配を代行し、ご相続人様の負担を軽減することを提案しました。相談後
・当事務所で登記に必要な戸籍や不動産に関する資料等を収集し、建物について相続登記申請を完了させました。
・離れて暮らす相続人については、当事務所で連絡を取り、遺産分割協議書等の書類の郵送及び署名捺印の手配を代行し、ご相続人様の負担を軽減することができました。
・事前に地主に確認した手順に沿って借地権の名義変更手続きを行い、スムーズに手続きを完了させることができました。事務所からのコメント
借地権の相続に伴う名義変更手続きは、基本的に建物の相続登記以外は地主の指示に従えばよく、必要書類も相続登記に必要な書類とほぼ同じため、それほど難しくはありません。
しかし、地主の中には名義変更についてかなり細かく手順を指定してくる方もいます。(例えば、先に遺産分割協議書を提出して、確認後に登記申請して欲しいなど)
手順を誤ったからと言って直ちに契約が解除になるわけではありませんが、今後の関係を考えると、要求がよっぽど不当なものでない限りは素直に従った方が得策ですので、相続が発生したら、まず地主に連絡を取っておくことをおすすめします。
また、地主の中には相続の際の名義変更の際にも承諾料や更新料が発生すると言って、請求してくる方もいます。(単に勘違いしている方もいれば、知っていてあえて請求してくる悪質な方もいます)
相続による名義変更の際には承諾料等はかからないのですが(遺言で相続人以外に遺贈した場合はかかります)、地主からそう言われたら言い返すのは難しいという方もいることでしょう。
借地権の名義変更の際にはいずれにしても建物の相続登記が必要になりますので、余計なトラブルになることは避けたいという方は、相続が発生したら、早めに相続に精通した司法書士に相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
亡くなった姉の財産が不明・・・株式、投資信託はどうやって調べればいい?【相続財産の中に詳細不明の株式があるケース】
相談前
お姉さまが亡くなられた方からのご相談。
相続人は弟3名。
相続人が全員故人とは離れて暮らしており、頻繁に交流もなかったため、財産について詳細不明な部…続きを見る-
相続手続き
亡くなった姉の財産が不明・・・株式、投資信託はどうやって調べればいい?【相続財産の中に詳細不明の株式があるケース】
相談前
お姉さまが亡くなられた方からのご相談。
相続人は弟3名。
相続人が全員故人とは離れて暮らしており、頻繁に交流もなかったため、財産について詳細不明な部分が多い状態。
特に株式、投資信託等の証券についてはかなり昔の書類が出てきたものの、他に手がかりもなく調べ方もわからないとのこと。
相続人が皆高齢という事もあり、手続きをどう進めていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・亡くなった方の生活状況を把握している相続人がいないため、相続財産について漏れのないよう入念に調査を行う必要がある。
・株式、投資信託について、昔証券会社から届いた書類はあるものの、現在も取引があるかどうかわからないため、確認する必要がある。
・相続人がそれぞれ離れて暮らしており、皆高齢のため、自分たちだけで手続きを行うことが難しい。
・手続きについて代表者の方に過大な負担がかかることは避けたい。
亡くなった方との交流が生前にあまり無かった場合に、財産の詳細がわからないというのは良くある話です。
資料を手掛かりに探すにしても古い通帳や株券などしかない場合は、現在も取引があるかどうか確認するのも大変な作業です。
多くの金融機関が1990年代から2000年代にかけて合併や社名変更を行っていることも確認が難しい要因の一つです。
特に兄弟が相続人になる場合は、故人とは離れて暮らしていることも多く、相続人自身も高齢である事がほとんどなので、より一層手続きの負担が重くのしかかります。
今回もまさにそのようなケースであり、特に株式、投資信託については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外に故人名義の口座がないかを確認する必要がありました。
そこで、当事務所でほふりの調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。相談後
・古い通帳や取引報告書等の資料がある金融機関について、現在の問い合わせ先を一つずつ調べ、取引状況について確認を行い、残高証明書等の請求を行いました。
・株式、投資信託については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外の故人名義の口座が存在しないか調査を行いました。
・不動産や保険契約等その他の財産についても調査を行い、遺産分割の対象となる財産について漏れのないようリストアップした財産目録を作成しました。
・当事務所で戸籍収集、遺産分割協議書の手配、株式や投資信託の相続移管手続き、預貯金の解約および分配等の必要な手続きを代行し、高齢のご相続人様のご負担なく相続手続を完了させることができました。
・ご相続人様に行っていただいたのは遺産分割協議書へのご署名ご捺印作業と株式・投資信託受取のための口座開設のみでした。事務所からのコメント
亡くなった方が株式や投資信託をお持ちだった場合、特に慎重に調査を行う必要があります。
というのも、上場株式については本人も認識されていない口座をお持ちのケースがよくあるからです。
上場株式については2009年の株券電子化に伴い、原則すべての株式を証券会社(野村証券や大和証券など)の口座で管理することになりました。
ところが、株券電子化前にほふり(証券保管振替機構)に株券を預託されなかった株式については、信託銀行等に開設された「特別口座」で管理されている場合があります。
この特別口座で管理されている株式は単元未満株(端株とも言います)であることが多く、株主総会の招集通知等の郵送物が一切届かないこともあるため、その存在に気付きにくいのです。
しかし、単元未満株についても相続手続きは必要ですし、相続税申告が必要な場合は課税対象財産になるため、漏れのないよう調査を行う必要があります。
ほふりに情報開示請求を行うことで、漏れのないよう調査することが可能なのですが、普通の方には慣れない手続きとなるため、負担となるかもしれません。
特にこのケースのように、他にも詳細不明の財産があり、自分たちだけでは手に負えそうにないという場合は、相続手続き全般に精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。
当事務所では、ほふりの調査をはじめとした株式・投資信託等の調査や相続手続きについて多数のご相談・ご依頼をいただいております。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
離れた地方に住む母が亡くなった・・・地方銀行の相続手続きはどうすればいい?【遠方にある地方銀行の相続手続きが必要なケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
お母様は投資や資産運用がお好きで、かなりの数の銀行や信用金庫、証券会社等に口座をお持ちだ…続きを見る-
相続手続き
離れた地方に住む母が亡くなった・・・地方銀行の相続手続きはどうすればいい?【遠方にある地方銀行の相続手続きが必要なケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
お母様は投資や資産運用がお好きで、かなりの数の銀行や信用金庫、証券会社等に口座をお持ちだったため、財産調査にかなり手間がかかりそうとのこと。
しかしお母様は九州の地方都市で暮らしており、お子様は二人とも関東在住のため、財産調査や手続きのために何度も足を運ぶのは難しい状況。
相続税申告も必要なため、確実に期限内に調査を終わらせ、二人のどちらかに負担が偏ることなく手続きを終わらせたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・地方銀行・信用金庫を含む多数の金融機関に一つずつ連絡を取り、残高証明書や取引履歴等を取得し、相続手続の手順を確認しなければならない。
・株式、投資信託については把握している以外の口座がないかを含めて調査しなくてはならない。
・相続税申告が必要なため、不動産、保険契約その他の財産についても漏れのないよう調査を完了させ、迅速に申告の準備を整える必要がある。
・財産の中に自動車、農地、賃貸物件などがあり、それらについても名義変更手続きや届出、通知を行う必要がある。
・飛行機で行かなければならない距離のため、手続きのために何度も現地に足を運ぶことは難しい。
・利用していない不動産については今後売却をしたいが、遠方のため不動産業者等のつてもなく、売却活動を行うことが難しい。
地方に暮らす親が亡くなり、離れて暮らす子供が相続手続きを行わなければならないという場合、手続きのための時間と費用がネックになります。
新幹線や飛行機で行かなければならない距離であれば休日を丸々つぶして往復することになりますし、交通費だけでかなりの金額になってしまいます。
このケースのように、金融資産をたくさんお持ちの場合、各金融機関に連絡を取って残高証明書や取引履歴の請求を行い、その後の相続手続きを行うことになります。
当然ながら一つずつ現地に行って手続きを行おうとすると、大変な労力と費用を要することになります。
もちろん相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送等のやり取りで対応してくれるところが多いです。
しかし地方銀行や信用金庫は、郵送でのやり取りについて、独自のルールが決められていることも多く、調査の段階でつまずくことがよくあります。
※例えば、残高証明書の発行手数料をどうやって支払うかなど。
また、相続人が複数いる場合、分担がうまくいかず、どちらかに負担が偏ってしまい、不満がたまってしまうという事もよくあります。
うまく分担できれば負担を軽減することも可能ですが、大体の場合、代表者の方が見返りもなく、ほとんどの手続きを行うことになりがちです。
不満がたまってしまうと手続き後の関係も微妙になってしまうかもしれません。
そこでご相続人様にそのような負担をかけることの無いように、当事務所で戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更、相続税申告を担当する税理士の手配まで一括して代行することを提案しました。
また、相続した不動産の一つについては、今後の利用予定もなく売却を検討しているが、現地の不動産業者のつてもなく、遠方のため売却活動を行うことが難しいとお困りでした。
そこで当事務所の方で、現地の業者にもネットワークを持つ不動産会社をご紹介させていただくことになりました。
ご依頼をいただいてからは、各金融機関に連絡を取って、手続き方法の確認や必要書類の取り寄せ等の地道な作業を少しずつ進めていきました。
その結果、時間はかかりましたが、何とか調査を終え、財産目録等を整えることができました。
調査の結果相続税申告が確実に必要となったため、相続に強い税理士もご紹介して、これから遺産の分け方を決めよう…とした矢先に新たな問題が発生しました。
実はお母様名義の口座の他に、口座名義はお子様であるものの、実質的にはお母様が管理している預金口座が存在することが判明したのです。
このような預金口座のことを「名義預金」といい、実情によっては税務署に相続財産と判断されてしまう可能性があるため、慎重な判断が必要になります。
幸い今回は申告前に判明したため、名義預金については、税理士に精査してもらい、税務署から指摘されないような内容で処理し申告を行うことになりました。相談後
・地方銀行・信用金庫を含む多数の金融機関に連絡を取り、残高証明書等を取得し、手続の手順を確認し、滞りなく手続きを行うことができました。
・ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外の故人名義の口座が存在しないか調査を行いました。
・ほふり調査の結果、新たな口座が判明したため口座を管理している金融機関に連絡を取り、調査及び移管手続きを行いました。
・不動産や保険契約等その他の財産についても漏れのないよう調査を行い、相続税申告のための準備を整えました。
・自動車、農地、賃貸物件などについては、それぞれ名義変更手続きや届出、通知等のサポートをさせていただきました。
・当事務所で戸籍の収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して担当させていただき、特定のご相続人様にご負担をかけることなく相続手続を完了させることができました。
・利用していない不動産については、現地の業者にもネットワークを持つ不動産会社をご紹介し、売却のサポートをさせていただきました。事務所からのコメント
このケースのように、財産の種類が多く、相続人が何度も現地に足を運ぶことが難しい場合、まず初めに必要な手続きをリストアップして、優先順位を決める必要があります。
きちんとスケジュールを組んだ上で実行しなければ、手続きの途中でよくわからない状態になり、無駄に手間や費用がかかってしまう可能性があります。最悪の場合、手続きが途中で頓挫してしまうことさえあります。
また、相続税申告が必要であれば期限を意識して、より迅速に進める必要があります。
ほとんどの方にとって相続手続きを自分で行うのは初めてだと思いますが、はじめての相続で、滞りも漏れもなく、正確かつ迅速に手続きを進めることはほぼ不可能と言っていいでしょう。
ここまで複雑でない場合であっても、手続きを難しく感じるかは人それぞれですので、自分には難しいかも知れないと少しでも感じられた方は、相続全般に詳しい専門家にお早めに相談することをおすすめします
地方銀行の相続手続きを含む遠方の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
故人が役員を務めていた非上場会社の株式、相続手続きはどうすればいい?【相続財産の中に非上場会社の株式が含まれるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
仕事が忙しく自分で手続きを行うことが難しいが、なるべく早くかつ公平に手続きを終わ…続きを見る-
相続手続き
故人が役員を務めていた非上場会社の株式、相続手続きはどうすればいい?【相続財産の中に非上場会社の株式が含まれるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
仕事が忙しく自分で手続きを行うことが難しいが、なるべく早くかつ公平に手続きを終わらせたいので他の相続人に任せるのも不安があるとのこと。
また、財産の中に、ゴルフ場会員権や生前お父様が役員を務めていた会社の株式などがあり、難航することも予想されるので、手続き全般を専門家に任せたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・財産の中に非上場会社の株式があるため、相続税評価のための資料開示や相続手続きについて確認する必要がある。
・財産の中には借地やゴルフ場会員権があるため、それぞれ相続手続きについて確認する必要がある。
・財産額が高額になることが予想されるため、相続税申告のために迅速かつ漏れのないように財産調査を完了させる必要がある。
・相続人は忙しく、手続きのための時間を取ることが難しい。
・財産額が高額になるため、公平な第三者に遺産承継手続きだけでなく分配手続きまで行って欲しい。
遺産の中に非上場会社の株式(非公開株式)がある場合、自身で相続手続きを進めるのであればそれなりの覚悟が必要です。
上場株式であれば、証券会社や株主名簿管理人に連絡をして手続きを行えばよく、どこも専門部署で対応してくれるので、困難というほどではありません。
しかし、非上場会社の場合、移管手続きや必要書類、相続人への買い取り請求の規定の有無などについて、会社によって対応が全く異なる上、専門部署が無いため対応に非常に時間がかかることも珍しくありません。
故人が100%株主であるオーナー会社やそれに近い状態であれば、大抵は身内で処理すれば済むのでそれほど負担にはならないかもしれません。
しかし、以前役員を務めており、今でも(名前だけの)少数株主である場合などは、会社の方も相続による株主変更の対応経験がほとんどないため、なかなか話がかみ合わず埒が明かないという事もよくあります。
また、相続税申告が必要な場合は、評価額計算のために会社の経理や財務に関する資料を出してもらう必要があります。
大抵は顧問税理士から出してもらうのですが、外部(株主なので外部ではないのですが…)に資料を出すことを戸惑われる方も多く、提出までのやり取りが負担になることも多いです。
このケースもまさにそのような事態が予想された上、財産の中には借地やゴルフ場会員権等の特殊な手続きが必要なものもありました。
そこで、お忙しいご相続人様に代わって、非上場会社の株式の手続きを含むすべての相続手続きを当事務所で代行し、各相続人様への公平な分配まで一貫してサポートさせていただくことを提案しました。
ご依頼をいただいてからは、非上場会社をはじめとした関係各所に連絡を取って、手続き方法の確認や必要書類の取り寄せ等の地道な作業を少しずつ進めていきました。
その結果、時間はかかりましたが、無事調査を終え、相続税申告の準備を整えることができました。
その後相続税申告及び相続財産の名義変更や移管、分配手続きを終え、すべての手続きが完了…と思っていたところに新たな問題が発生しました。
実は、当初把握していた非上場株式の他に、別の非上場会社の株式をお持ちだったことが発覚したのです。
当然、新たに判明した財産についても評価額の計算や承継手続きが必要になり、場合によっては新たに遺産分割協議を行う必要があります。
この時点で相続税の申告期限は過ぎていたものの、幸いすぐに修正申告を行えば、追徴課税は免れそうな財産額でした。
そこで、当事務所で新たに発覚した非上場会社に速やかに連絡を取り、相続税評価のための資料開示や相続手続きについて確認を行い、相続税申告及び株式の承継のための手配をさせていただくことになりました。相談後
・非上場会社の株式に関しては、相続税評価のための資料請求や相続手続きについての確認を行い、その後の承継・買取手続きまで代行しました。
・借地やゴルフ場会員権については、関係各所に確認を行い、それぞれ必要な手続きについて代行・サポートさせていただきました。
・不動産その他の財産についても財産調査を行い、相続税申告のための準備を整えました。
・当事務所で戸籍の収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更まで一括して代行し、お忙しいご相続人様のご負担なく完了させることができました。
・預貯金等については、解約だけでなく各相続人への公平な分配まで行わせていただきました。
・追加で判明した株式についても手続きを行い、修正申告及び承継・買取まで無事完了させることができました。事務所からのコメント
非上場株式が遺産に含まれる場合、移管手続きや必要書類、買取等について会社ごとに対応が全く異なるので、手続きが難航することが多いです。
また、株主総会の招集通知が届いていない・気づかないまま放置しているなど、そもそも非上場株式の存在を認識しづらい場合も多く、後になってその存在に気付くこともあります。
このケースではすぐに発覚したため、大事には至りませんでしたが、発覚が遅れた場合、税務調査や追徴課税のリスクが高まるほか、新たな財産をめぐって相続人間でトラブルに発展してしまう事もあります。
せっかくまとまった遺産分割協議をやり直すことは心理的にもかなり負担となるので、できれば避けたいところです。
亡くなった方が非上場会社の株式をお持ちだった場合は、調査方法や承継手続きについても相談できる、相続に強い司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
亡くなった息子の相続手続き、高齢の自分では手に負えない・・・【唯一の相続人である母親が高齢のため手続きが難しいケース】
相談前
お子様を亡くされた方の甥の方からのご相談。
すでにご主人様も他界されており、今回一人息子であるお子様を亡くされたとのこと。
お子様には配偶者や子供が…続きを見る-
相続手続き
亡くなった息子の相続手続き、高齢の自分では手に負えない・・・【唯一の相続人である母親が高齢のため手続きが難しいケース】
相談前
お子様を亡くされた方の甥の方からのご相談。
すでにご主人様も他界されており、今回一人息子であるお子様を亡くされたとのこと。
お子様には配偶者や子供がいなかったため、お母様が唯一の法定相続人となるが、かなり高齢で体の具合も思わしくないため、ご自身では手続きが難しい状況。
以前から何かと面倒を看ていた甥御様が代わりに手続きを行おうとしたものの、自身は相続人ではなく、手続きの最初の段階である戸籍集めすら難航したため、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続人が高齢のため、自分で手続きを行うのが難しい。
・他の親族は相続人ではないため代わりに手続きを行う事も出来ない。
・お子様と同居はしていたものの、財産状況については全く関知していなかったため、どの金融機関と取引があったかもわからない。
・相続人が一人のため、遺産分割協議は必要ないものの、相続税申告が必要な場合に備えて、早急に調査を完了させ準備を整える必要がある。
・お子様が亡くなってしまったことで、自分の今後の生活や相続のことについて改めて考えなくてはならない。
亡くなった方にお子様がいない場合、父母が存命であれば相続人になります。
父母が相続人になる場合、相続手続きが難航することはよくあります。
子供に先立たれた悲しみからなかなか手続きが手につかないという事もあるでしょうし、高齢のため健康上の理由から自分で手続きを行うのが困難という場合もあります。
このケースでも、お母様は高齢のためご自身で手続きを行うことは難しく、甥にあたるご相談者様が手続きを進めようとしていました。
しかし、相続人ではなく、直系血族でも無い方が役所で戸籍を請求したり、金融機関で相続手続きをするためには手続きの都度、委任状が必要になり、手間がかかります。
仕事をしばらく休んでまで、手伝っていたのですが、さすがにずっと休むわけにもいきません。
そこで、当事務所で、戸籍の収集、金融機関への連絡、各種財産の調査、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更、相続税申告を担当する税理士の手配まで必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。
また、今回自分の相続人であった子供が亡くなってしまったということで、ご自身の今後の生活や相続のことについても相談したいとお考えでした。
そこで相続手続き完了後に、遺言等の生前対策を提案させていただくことになりました。相談後
・通帳や郵送物をもとに金融機関に一つずつ確認を取り、残高証明書等の請求を行い、すみやかに遺産額を確定させました。
・調査の結果、相続税の申告が必要なことが明らかになったため、相続に強い税理士をご紹介させていただきました。
・ほふり調査、不動産その他の財産調査を迅速に行い、相続税申告の準備を整えました。
・当事務所で、戸籍の収集、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更まで一括して担当させていただき、ご相続人様の負担なく相続手続きを終えることができました。
・今後のご自身の生活や相続のことについて、遺言書を含む生前対策を提案させていただきました。事務所からのコメント
お子様が先に亡くなってしまった場合、ご父母様の悲しみは計り知れないものがあります。しばらくは何も手につかなくても仕方ありません。
ましてや複雑な相続手続となればなおさらでしょう。
とは言っても、相続手続きには相続税申告など期限が決まっているものもあるので、いつまでも何もしないままというわけにはいきません。
また、精神的に落ち着いても、このケースのように健康上の理由で動くのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。
お子様を亡くされて自分が相続人になってしまった方は、お早めに相続の専門家へご相談ください。わずらわしい手続きは専門家に任せて、どうぞご自愛ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
未成年の子を残して夫が死亡・・・相続はどうすればいい?【相続人の中に未成年の子供が複数いるケース】
相談前
ご主人様を亡くされた方からのご相談。
相続人は奥様と未成年のお子様二人。
お子様とその親が両方とも相続人になる場合は、相続のために特別な手続きが必要…続きを見る-
相続手続き
未成年の子を残して夫が死亡・・・相続はどうすればいい?【相続人の中に未成年の子供が複数いるケース】
相談前
ご主人様を亡くされた方からのご相談。
相続人は奥様と未成年のお子様二人。
お子様とその親が両方とも相続人になる場合は、相続のために特別な手続きが必要という事を聞いたものの、どのように手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・未成年者がその親と共に相続人になる場合、遺産分割協議を行うにあたり、特別代理人の選任が必要。
・さらに未成年者が複数いる場合は、それぞれ別々に特別代理人を選任してもらう必要がある。
・特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要。
遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に未成年の方がいる場合、本人に代わって親(親権者)が遺産分割協議に参加することになります。
代表的なのは、子供が親より先に亡くなっているため、代襲相続人として未成年の孫が相続人になるケースです。
この場合特別な手続きは必要なく、遺産分割協議書には未成年の法定代理人として親が署名捺印すればそれで済みます。
しかし、今回のように親子どちらも相続人という場合は、形式上親子間で利害関係が対立するので、お母様は代理人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。
そこでこのような場合、母の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
特別代理人は家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。今回も当事務所で特別代理人の申立て手続きをサポートさせていただくことを提案しました。
このケースのように未成年者が複数いる場合は、子供たちの間でも形式上利害関係が対立するため、お子様一人ずつにそれぞれ別の特別代理人を選んでもらう必要があります。
特別代理人は誰でもなることができますが、今回のように遺産分割協議のために選任してもらう場合、財産状況というかなりデリケートな状況を開示することになるため候補者は限られます。
通常は祖父母や叔父伯母などの関係性の近い親族や、司法書士等の信頼できる専門家に候補者になってもらうことが多いです。
ご相談の結果、今回はご祖父様(相談者の父)と、相続税申告を担当する税理士を候補者としてお子様二人の特別代理人選任申立て手続きを行うことになりました。
なお、特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要であり、申立て時に遺産分割協議書案を提出する必要があります。
この点について税理士も交えて相談した結果、不動産の持分を相続させることで問題なくクリアできることを確認した上で、手続きを行うことになりました。相談後
・未成年者お二人について、特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。
・遺産分割協議には、特別代理人が参加し、未成年者の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。
・不動産の名義変更(相続登記)に必要な、戸籍の収集や遺産分割協議書の手配も当事務所で代行し、無事相続登記を完了させることができました。事務所からのコメント
遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に遺産分割に関する十分な判断能力がある事が前提となります。
未成年者は自分の意思で判断できないとされているので(実際には十分に能力がある場合もあるでしょうが)、未成年者がいる場合は、その方の代わりに親権者や特別代理人が協議に参加することになります。
特別代理人を選任してもらう手続き自体はそれほど難しくはないかもしれませんが、申立ての際に未成年の法定相続分を確保した遺産分割協議案を提出することが原則であり、この点がネックになることが多いです。
財産の額やお子様の年齢にもよるでしょうが、法定相続分相当額が結構な金額になる場合は、未成年に多額の財産を渡すのはまだ早い…と考えるのも親として当然だと思います。
このような場合、裁判所に上申書や事情説明書を提出すれば、例外的にお子様の取得分が法定相続分を下回る内容での遺産分割協議案が認められることもあります。
ただし、認められる条件はかなり厳しく、裁判官が納得するような事情を書面で説明しなければならないため、一般の方にはかなりハードルが高いでしょう。
また、裁判所が遺産分割案をチェックしていると言っても、特別代理人には遺産分割協議についての責任が生じます。(実際に過失が認められたケースもあります)
どのような内容の遺産分割協議案を提出するべきかは、遺産総額や財産の種類、未成年者の年齢等、それぞれの事情により異なります。
未成年者につき遺産分割のために特別代理人が必要な場合は、相続に詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
相続財産は共有不動産のみ・・・どうやって分ければいい?【共有不動産について遺産分割が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
財産はほぼ自宅不動産のみだが、きょうだいの間では公平に分けることで意見は一致しているとのこと…続きを見る-
遺産分割
相続財産は共有不動産のみ・・・どうやって分ければいい?【共有不動産について遺産分割が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
財産はほぼ自宅不動産のみだが、きょうだいの間では公平に分けることで意見は一致しているとのこと。
ただし、不動産の名義の半分が別れた妻(相続人の母親)名義のため、どのように手続きを行えばいいか知りたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・不動産が元妻との共有名義になっているため、今後の管理、処分方針について確認する必要がある。
・すぐに売却をすることが難しい場合、お子様二人の名義を入れることで将来的に問題が生じないか検討する必要がある。
相続した不動産が夫婦の共有名義になっているということは珍しくありませんが、このケースのように元配偶者との共有になっている場合は、最終的にどのような形で分配できるかについて慎重に検討する必要があります。
というのも、不動産を売却する際は共有者全員が同意の上、所有権すべてを移転することが原則のため、共有者のうち一人でも反対する方がいれば売却は難しいためです。
売却して代金を分配することが可能であれば、それぞれの取得割合に応じて共有の登記をしても問題ないですが、売却が難しい場合に下手に共有の登記をしてしまうと、長期間にわたって解決できない問題が生じてしまいかねません。
幸いこのケースではお母様とお子様は普通に交流があり、売却の方針も一致していました。そこで、売却した代金を分割することを前提として、お父様名義の不動産持分をお二人の共有名義とする内容の遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことを提案しました。相談後
・不動産を売却して代金を分割するという換価分割の内容で遺産分割協議書を作成し、ご相続人様の署名捺印をいただきました。
・相続登記に必要な戸籍の収集、評価証明書や名寄帳の取得も当事務所で代行し、無事登記を完了することができました。事務所からのコメント
共有不動産は、共有者全員の意見が一致しないと処分が難しいため、トラブルがつきものです。昔は相続が発生した際にとりあえず相続人全員の共有名義にしてしまうというケースが多く、今になって管理・処分方針をめぐって問題になっているという話をよく聞きます。
このようなトラブルを避けるためには単独名義にしてしまえばいいのですが、コストがかかる、不動産以外に財産が無い等の理由でそれが難しい場合もあります。
とは言え、このケースのように共有者全員の意見が一致していて、すぐに売却をするつもりでなければ、できるだけ共有名義にすることは避けるべきです。
共有名義の登記をする以外にどのような解決方法があるかは事情によって異なりますので、共有不動産の持ち主に相続が発生した場合は、相続や共有不動産の売却に精通した司法書士等の専門家に、お早めに相談することをおすすめします。
共有名義の不動産の相続や売却に関するご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
海外在住の相続人、財産の分配はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいて、財産の分配が必要なケース】
相談前
伯母様を亡くされた方からのご相談。
配偶者も子供もおらず、唯一の相続人であったごきょうだいもすでに亡くなっていたため、その子供である甥二人が相続人。
相…続きを見る-
相続手続き
海外在住の相続人、財産の分配はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいて、財産の分配が必要なケース】
相談前
伯母様を亡くされた方からのご相談。
配偶者も子供もおらず、唯一の相続人であったごきょうだいもすでに亡くなっていたため、その子供である甥二人が相続人。
相続人の間では公平に分けることで合意はできているものの、お一人が海外在住であり、仕事の都合上ほとんど日本に帰って来られないという状況。
相続手続きも大変そうだが、日本の銀行の口座も持っていないため、相続した金融資産の分配についても悩んでいるという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続人の一人が海外在住であり、基本的にメールでのやり取りになるため、遺産の内容や、必要な手続きについて説明し、理解してもらうのに手間がかかる。
・海外在住者については、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができない。
・海外在住者から遺産分割協議書等の必要な書類を貰うのに手間がかかる。
・海外在住のため、日本の銀行に口座を持っておらず、相続した金融資産の分配方法について検討する必要がある。
海外在住の相続人の方がいる場合は、相続した預貯金の受取方法が問題になることがあります。
というのも、相続した預貯金の受取口座については、国内にある金融機関の口座への振り込みにしか対応していない金融機関がほとんどであるためです。
そのため、相続手続きを進めるにあたっては、海外在住者の方が日本国内に銀行口座をお持ちで、かつ海外からも利用することができるか、について確認する必要があります。
このケースでも、当初、海外在住の方は日本の銀行口座を持っていないという事でした。
幸い、少し先になるが日本への帰国の予定があるとのことでしたので、その際に日本の銀行に口座を開設していただくことで、この点はクリアできそうでした。
また、相続手続きでは、ほとんどの場合、相続人全員の印鑑証明書が、実印を押した遺産分割協議書とセットで必要になります。しかし、印鑑登録は日本国内に住民登録がないとできないため、このケースのように、日本に住所が無い方は、印鑑証明書を取得することができません。
印鑑証明書がない場合、現地にある日本大使館や総領事館等の在外公館でサイン証明書を取得してもらうことになります。
しかし、このケースではそれほどメジャーではない国にお住まいだったため、現地に在外公館が存在しないという事態も懸念されました。
幸いにも、ちょうど相続開始の数か月前に現地に日本の総領事館ができたという事だったので、サイン証明書についてもクリアできることになりました。
そこで、海外在住の方とのやり取りにかかる負担をできるだけ少なくするため、当事務所で戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。相談後
・海外在住の方へはメールで進捗状況のご報告や財産目録等の資料のご提供、手続きについてのご説明等を行い、ご確認・ご納得いただいた上で手続きをすすめました。
・海外在住の方へメール添付で遺産分割協議書及び委任状を送付し、プリントアウトしたものを日本総領事館に持ち込みの上、証明を受けていただきました。
・証明を受けた遺産分割協議書を国際郵便で送っていただき、他の方から頂いた遺産分割協議書及び委任状並びに印鑑証明書と併せて、相続手続きを行いました。
・解約後の相続預金については、いったん当事務所の遺産管理専用口座に振込後、海外在住の方の口座開設を待って分配・送金を行いました。
・当事務所で戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、金融機関の解約、相続預金の分配まで、一括して代行させていただき、相続人様のご負担を最小限にとどめつつ、手続きを完了させることができました。事務所からのコメント
相続した預貯金を受け取る方法は、相続人名義の口座への振り込みとなることがほとんどです。そして、その際の受取口座については、国内にある金融機関の口座への振り込みにしか対応していない金融機関がほとんどです。中にはゆうちょ銀行のように、同じ金融機関の間での振り込みにしか対応していないところもあります。
日本国内に住民登録が無い海外在住の方(非居住者)でも、日本の銀行の口座をお持ちで、かつ海外から利用できれば問題ないのですが、このケースのように海外移住時にすべての口座を解約してしまっている場合(ネット銀行のほとんどは非居住者になる場合は口座を解約する必要があります)や、口座のある銀行が海外在住者向けのサービスを提供していない場合は、受け取り方法やその後の管理・利用方法について慎重に検討する必要があります。
日本にいる相続人の方に代表して受け取ってもらい、その後に海外送金してもらうという方法もありますが、個人口座については海外送金について一定の限度額が決められている所がほとんどのため、遺産の額が大きい場合は送金手続きがかなりの負担となります。また、送金手数料も高めに設定されているため何回も送金することになれば、その負担も馬鹿になりません。なにより円から外貨へ替える際の為替レートによっては大きく損をする可能性もあるので、長期間にわたって小分けに送金する方法はかなりの労力とリスクを伴います。
また、海外在住のため印鑑証明書を取得できない場合は、サイン証明書をご取得いただくのがポピュラーな方法ではありますが、居住国に在外公館が存在しない場合は、近隣国の在外公館で手続きを行う、日本への一時帰国時に公証役場で認証を受ける、住民登録を行い印鑑証明書を発行してもらう、等の方法を検討する必要があります。いずれの方法もそれなりに手間がかかりますし、場合によっては手続きの時期がだいぶ先になることもあります。
このように海外在住の相続人がいる場合は、たとえ遺産の分け方をめぐって争いが無くても、特有の事情により手続きが難航することが予想されます。
自分の場合にどのような手続きが必要か、手続きのためにどのような準備が必要でいつまでに行えばいいか等を正確に把握するのはとても難しいと思いますので、相続人の中に海外在住の方がいる場合は、相続発生後、なるべく早く相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。
海外在住の相続人の方がいる場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
不動産の表記が異なる・・・署名捺印済みの遺産分割協議書に記載間違いがあった場合はどうすればいい?【遺産分割協議書に不動産の記載間違いがあったケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
遺産分割協議がまとまったので相続登記をお願いしたいとのご相談でした。
最初のご相談時に署名…続きを見る-
遺産分割
不動産の表記が異なる・・・署名捺印済みの遺産分割協議書に記載間違いがあった場合はどうすればいい?【遺産分割協議書に不動産の記載間違いがあったケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
遺産分割協議がまとまったので相続登記をお願いしたいとのご相談でした。
最初のご相談時に署名捺印済みの遺産分割協議書をご持参いただいたので、確認させていただいたところ、不動産のうち一つの物件の表示が登記簿上の地番と異なるという事が発覚しました。
▼問題点
・遺産分割協議書に記載された不動産の地番等の表示が登記簿と異なる場合に、そのまま登記ができるか。
・そのままでは登記ができない場合、どのような対応が必要か。
相続を理由とする不動産の名義変更(相続登記)は、必要書類を揃えて、不動産を管轄する法務局に申請をして行います。そして多くの場合、相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書を添付書類として提出します。
この遺産分割協議書に記載間違いがある場合は、基本的にそのままでは登記はできません。ごく軽微な記載違いであれば訂正しなくて済むこともありますが、このケースでは不動産の地番の一部が全く異なっていたため、訂正をしなければ登記が通らないことは確実でした。
このような場合、間違った箇所を二重線で消して訂正をすれば大丈夫なのですが、相続人同士の関係が微妙な場合は訂正印をもらうのが難しいこともあります。
このケースも相続人間で揉めた末に弁護士を付けてようやく協議がまとまったというケースだったため、当人同士で話をするのは難しいとのことでした。
ただ、協議書を作成したのは弁護士だったため、弁護士経由で相手方相続人(不動産を取得しない方)に連絡は取ってもらえるかもとのことでした。
そこで、弁護士を通じて相手方に連絡を取り、遺産分割協議書に訂正印をもらうか、別途覚書を作成してもらって、正確な地番が記載された書類を揃えたうえで登記を申請することを提案しました。相談後
・弁護士を通じて相手方に連絡を取り、不動産の記載について別途覚書を作成してもらうことができました。
・作成した覚書を遺産分割協議書その他の必要書類と共に管轄の法務局に提出し、無事登記を完了させることができました。事務所からのコメント
最近では、インターネットや書籍等で相続についての情報を目にすることも多く、遺産分割協議書を自分で作成される方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書に記載間違いや記載漏れがあった場合、相続人全員に実印を押印してもらい、訂正する必要があります。特に不動産については登記申請の際に法務局で厳格にチェックされるので、登記簿上の記載と全く同じように記載しておく必要があります。
そのような手間を省くために、捨印を押しておけば軽微な間違いについては訂正できるのですが、専門家でない方が作成した書面に捨印を押すのは抵抗があるという方も多いでしょう。
とは言っても、今回のように法律の専門家が作成した協議書でさえ、記載間違いがあるのですから、一般の方が間違いのない正確な遺産分割協議書を作成するのは、大変な労力を要する作業です。また、信用していないわけじゃないけど他の相続人の作成した協議書に実印を押すのは抵抗がある、協議書の内容で万が一にも揉めることのないようにしておきたいと考える方も多くいらっしゃいます。
協議書の記載をめぐってトラブルになることを防ぐためには、早めに相続に精通した専門家に相談することをおすすめします。
また、今回のような記載間違いでなくても、協議書の記載内容によっては登記ができないこともあります。私も税理士や弁護士の作成した協議書を見る機会は多いのですが、相続税申告の際の添付書面や、当事者同士の確認書面としては問題のない内容であっても、登記には使えないという事も珍しくありません。
相続手続きの中でも相続登記は司法書士の専門領域であり(弁護士も一応申請はできますが、専門ではないので司法書士に任せている方がほとんどです。)、特有のルールもあるので、相続財産の中に不動産がある場合は、必ず司法書士に相談することをおすすめします。
相続財産の中に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書の作成や、相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
今後のことを考えて、相続を機に母の共有持分を移したい。【不動産の共有持分をコストをかけずに移転したいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
財産の分け方については法定相続分ベースで考えており特に問題はないものの、相続財産であ…続きを見る-
相続手続き
今後のことを考えて、相続を機に母の共有持分を移したい。【不動産の共有持分をコストをかけずに移転したいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様二人。
財産の分け方については法定相続分ベースで考えており特に問題はないものの、相続財産である不動産にお母様の持分が一部入っていることが気になっているとのこと。
今後、高齢の母の介護費用等で不動産の売却が必要になった際に、認知症等の理由ですぐに売却ができないという事態にならないように、相続を機に母名義の持分を子供に移す方法はないかという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・将来の売却に備えて、相続を機に母名義の不動産持分を子供に移しておきたいが、移転のコストや税務上のリスクを踏まえて慎重に方法を検討する必要がある。
・場合によっては遺産分割内容に共有持分移転について盛り込む必要がある。
・相続税申告が必要なため、税理士と連携して速やかに遺産分割協議をまとめる必要がある。
共有名義になっている不動産を売却をする場合、共有者全員が当事者となって売却を行います。
この時、共有者の一人でも売却についての判断能力(意思能力)が無い方がいれば、そのままでは売却をすることはできません。
売却するためには、成年後見人等を付ければいのですが、主にコストや手間の面でできるだけ後見人等は付けたくないという方も多いです。
このような事態を防ぐためには、認知症等で意思能力が無くなる前に、事前に共有者の持分を他の方に移転しておくという方法があります。
具体的には贈与や家族信託等で持分を移転するという方法がありますが、贈与の場合は高額の贈与税がかかってしまい、現実的でないことも多いです。また、家族信託は認知症対策として高い効果が見込めますが、まだ世間的な認知度がそれほ高くなく、ご家族の理解が得られにくいこともあります。
今回も、母はあまり難しい話は分からないので、コストがそれほどかからずに済む別の方法があればそれでお願いしたいのとのご要望をお持ちでした。
そこで、遺産分割の際の代償金がわりに、お母様の共有持分を他の相続人の方へ贈与するという方法を提案しました。相談後
・税理士による税務チェックを受けた上で、「お母様が相続財産を受け取る代償として、自分の不動産持分を他の相続人へ贈与する」という内容の遺産分割協議書を作成しました。
・作成した遺産分割協議書を添付書面として、お父様についての相続登記と、お母様についての「遺産分割による贈与」を原因とする所有権移転登記を申請しました。
・無事登記が完了し、コストを最小限に抑えつつ、簡易な手続きで共有持分を移転することができました。
・作成した遺産分割協議書を添付書面として、期限内に相続税申告を完了させることができました。
・その他、当事務所で、戸籍の収集、相続預金の解約および分配、証券の移管手続き等の手続きを代行させていただき、ご相続人様の負担なく完了することができました。事務所からのコメント
遺産分割の際に、特定の相続人が相続財産を受け取る代わりに自分の不動産(持分)を他の相続人に譲渡(贈与)することを、「遺産分割による贈与(代償譲渡)」と言います。
いわゆる代償分割の形式で、代償金(お金)の代わりに不動産で支払うというイメージです。
ただこの方法を用いる場合、譲渡所得税、不動産取得税等の課税には気を付ける必要があります。
特に譲渡所得税については、思いがけず高額になってしまう可能性がある事を十分に理解しておかなければなりません。
事前に税理士と相談して、相続する財産の評価額、譲渡する持分の評価額、不動産の市場価格(時価)等を精査し、十分に検討した上で判断しなければ後で大変なことになってしまうかもしれないので、この方法を検討されている方は、絶対に自己判断をせずに専門家に依頼してください。
また、今回のようなケースでも、必ずしも「遺産分割による贈与(代償譲渡)」が最適解であるとは限りません。(むしろ、他の方法をおすすめする方が多いと思います。)
将来的な売却を検討している不動産について、どのような対策が必要かについては、相続や後見だけでなく、不動産売却にまで精通した専門家でなければ正しい提案はできません。
相談をする際は相続や不動産売却サポートの経験豊富な専門家を選んで相談しましょう。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
親族一同の共有財産である預金口座はどうやって相続すればいい?【相続財産の中に他人と共同管理していた口座があるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様一人。
当初、お父様と離れて暮らしており、不動産含む財産もすべて遠方にあるが、仕事柄休みが取りづらく…続きを見る-
相続手続き
親族一同の共有財産である預金口座はどうやって相続すればいい?【相続財産の中に他人と共同管理していた口座があるケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様一人。
当初、お父様と離れて暮らしており、不動産含む財産もすべて遠方にあるが、仕事柄休みが取りづらく、自分で手続きを行うことが難しいという事で相談にいらっしゃいました。
相談を伺う中で、相続財産の中に、名義は父になっているが、実際には親族数名の共同管理口座として利用されていた預金口座があるという事がわかりました。
▼問題点
・親族数名の共同管理口座として利用されていた預金口座について、承継方法や処理方法を他の親族と話し合う必要がある。
・不動産を含む相続財産がすべて遠方にあるため、手続きのために時間を取って現地に行くのが難しい。
財産の名義と実際の管理・処分権限者が違う財産のことを「名義財産」(名義だけの財産)と言います。名義財産は主に相続税の申告の際に問題になることが多いです。
名義財産は、親が子供の名義で口座を作って管理しているケースが多いのですが、このケースでは、祖父(亡父の父)の相続の際にきょうだいが話し合って、祖父から相続した預金の一部を今後の実家財産維持のための共同管理口座として使っていくことを決め、代表者である父名義の口座に移して、今までその通り利用されていた、という少々珍しいケースでした。
幸い今回は相続税の申告は不要だったため、税務上の問題は生じない見込みでしたが、実態は共有財産である父名義の預金口座についてどのように承継・清算手続きを行えばいいかについては検討しなくてはなりません。
このような場合、実態が名義財産であっても、銀行等の手続き上は、あくまで口座名義人(名義人が亡くなっていればその相続人)による手続きを求められます。
そこで、当事務所で名義財産を含む相続財産の承継に必要な一切の手続きを代行させていただき、共有財産である預金については、他の親族との話し合いで決まった内容に従って清算する方法を提案いたしました。相談後
・遠方にある不動産等の相続財産について、当事務所で関係各所への連絡、必要書類の取り寄せ、提出等を代行し、ご相続人様が直接現地に出向くことなく手続きを完了させました。
・共同管理口座として利用されていた預金口座については、口座名義人の相続人の代理人として相続手続きを行い、相続人様名義の口座にいったん払戻しを行いました。
・その後、親族間での話し合いで決まった内容に従って、一定の金額を他の親族へ分配することで清算することができました。
・その他、戸籍の収集、不動産の名義変更(相続登記)、相続預金の解約等の相続に必要な手続きの一切を代行させていただき、ご相続人様の負担なく相続を終えることができました。事務所からのコメント
このケースのように、相続財産の中に名義財産がある場合は、税務上の処理について検討が必要なほか、承継方法が問題になることがあります。
基本的にはその財産の名義人の方が手続きを行えばいいのですが、銀行の届出印を失くしてしまっている場合などは手続きに手間がかかってしまいます。
また、このケースのように、複数人での共有財産となっていた場合は、その後の処理・清算をめぐって共有者間で争いになってしまう事もあります。
おそらく名義財産を遺された方は良かれと思って遺されたものと思いますが、場合によっては残された方に大きな負担がかかってしまいます。
ご家族にそのような負担をかけないためにも、相続対策を行う場合は、必ず相続手続きにまで精通した専門家に相談の上で行う事をおすすめします。
また、相続財産の中に名義財産らしきものがあるとわかった場合は、自分自身で判断せずに、やはり相続手続きの実績豊富な専門家に相談することをおすすめします。
名義預金等の名義財産を含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、不動産売却を含む遺産分割をしなければならない…【疎遠な相続人との間で不動産売却を含む遺産分割が必要なケース】
相談前
叔父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はごきょうだいが一人と代襲相続人である甥姪が4人。
比較的故人と関係の近い自分が代表して相続手続きを取り…続きを見る-
遺産分割
ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、不動産売却を含む遺産分割をしなければならない…【疎遠な相続人との間で不動産売却を含む遺産分割が必要なケース】
相談前
叔父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はごきょうだいが一人と代襲相続人である甥姪が4人。
比較的故人と関係の近い自分が代表して相続手続きを取りまとめることになったが、他の相続人とは、いとことは言えほとんど交流が無く、遺産分割等についてどう切り出せばいいかわからないとのことでした。
また、自宅不動産については売却して代金を分けることを考えているものの、自分の住む場所から離れており、売却活動を継続的に行うのが負担になりそうとのこと。
不動産の売却やその後の代金分配も含めてすべて専門家に任せて、早く相続を終わらせたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印を貰わなくてはならない。
・遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して詳細を明らかにしなければならない。
・遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しなければならない。
・不動産について売却して代金を分配する場合、売却活動のための負担が特定の相続人にかかり不公平感が生じやすい。
亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合、相続人同士の関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことが多いです。
また、居住地等の関係で相続人のうち特定の方が手続きの大部分を行わざるを得ず、過大な負担を負うことになってしまう事もよくあります。
このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で、手続きのために頻繁に東京に来ることが難しいという事情もありました。
そこで、まずは財産の調査を行い、他の相続人に対して詳細な財産目録を開示した上で、法定相続をベースとした遺産分割を提案する、という方法を提案しました。
また、特定の方に負担がかからないように、当事務所で、各相続人への連絡、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更や金融機関の解約・分配、さらには相続した不動産の売却および売却代金の分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。相談後
・ほとんど面識のない相続人の方については、書面等で丁寧に事情をご説明しました。結果、無事手続きに協力してもらうことができました。
・遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
・法定相続分をベースとした遺産分割案を提案した結果、無事話し合いがまとまり、署名捺印をいただくことができました。
・遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しました。
・特定の方に負担がかからないように、戸籍収集、不動産の名義変更(相続登記)等の手続きについても一括して代行させていただき、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。
・不動産の売却についても手配を行い、売却代金の公平な分配までサポートさせていただきました。事務所からのコメント
このケースのように、相続人同士に面識がほとんどない場合は、特に最初の対応の際に十分に気を付ける必要があります。
仲のいい親族間であれば、お互いに言わなくても通じる部分があっても、疎遠な方の場合はそうはいきません。
手続きを早く進めようとするあまり、他の方の気分を害してしまい、結果として手続きが滞ってしまったというのは、当事務所のお客様からもよく聞く話です。
そのような事態を避けるためには、財産の調査を十分に行ったうえで、詳細な財産目録を開示し、公平な遺産分割方法を提案する必要がありますが、自分たちだけで上手くやってのけるのはとても難しいでしょう。
下手に自分たちだけで手続きを行おうとして辞退が泥沼化する前に、相続人の中に疎遠な方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な司法書士等の専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。
疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
戸籍を調べてびっくり!相続人が一人増えてしまった・・・【戸籍調査によって当初把握していなかった相続人の存在が判明したケース】
相談前
奥様を亡くされた方からのご相談。
お子様はおらず、ご両親はすでに他界されていたため、ご主人様とともにお姉様が相続人になるとのこと。
すでにお姉様と話をし…続きを見る-
相続手続き
戸籍を調べてびっくり!相続人が一人増えてしまった・・・【戸籍調査によって当初把握していなかった相続人の存在が判明したケース】
相談前
奥様を亡くされた方からのご相談。
お子様はおらず、ご両親はすでに他界されていたため、ご主人様とともにお姉様が相続人になるとのこと。
すでにお姉様と話をして、遺産については全てご主人様が相続されるという事でまとまっているとの事でした。
高齢の自分には負担が大きいため、手続きをおまかせしたいという事で相談にいらっしゃいましたが、財産の数もそれほど多くなく、当初は問題なく手続きは進むものと思われました。
▼問題点
・すでに分け方についての話はできているものの、妻のきょうだいと連絡を取り、遺産分割協議書や印鑑証明書を手配してもらう必要がある。
・相続人が高齢のため、自分で相続手続きを行うのは難しい。
亡くなった方にお子様(又はお孫様)がおらず、さらに父母や祖父母もすでに他界している場合、配偶者と共に兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人になります。
ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、兄弟姉妹とはそれほど面識がないということも多く、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。
幸いにもこのケースでは、すでにご相談者様自身で相続人である義姉様と話はできており、すべての財産を夫であるご相談者様が引き継ぐことになっているとのことでした。
ただ、ご相談者様は高齢のため、自分自身で関係各所に出向いて手続きを行うことは難しく、また、辞退していただいた義姉様にも負担をかけたくないということでした。
そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。
ご依頼をいただいてからは、まずは戸籍を収集して相続人の確定作業を行う事から始めました。しかし戸籍収集の途中で新たな問題が発生してしまいました。
実は、相続人である義姉様の夫が、義姉様のご両親(つまり亡くなった方のご両親)と養子縁組をされていることが判明したのです。
養子も実子も子供に変わりはないので、この場合、義姉様だけでなく、ご主人様も兄弟として相続人になります。
ご相談者様に確認したところ、養子縁組の事実は何となく認識はしていたものの、相続人になるとは思わなかったので、伝えていなかったとのことでした。おそらく義姉様も同様だったのでしょう。しかし、本人たちにその認識がなかったにせよ、戸籍上の相続人である以上、遺産分割協議に参加してもらい署名捺印を貰う必要があります。
そこで、改めて義姉様を通じてご主人様に連絡を取っていただき、相続についてのご意向を確認していただいたところ、快く辞退していただけることになったため、引き続き手続きを進めることになりました。相談後
・義姉様及び義兄様に連絡を取り、遺産分割協議書を送付させていただき、署名捺印をいただくとともに印鑑証明書をご提供いただくことができました。
・ご高齢のご相続人様に代わり、当事務所で、戸籍収集、相続財産の調査、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きの一切を行い、ご相続人様の負担なく手続きを完了させました。事務所からのコメント
このケースのように戸籍を調査したところ、新たな相続人が判明したというケースは、稀にあります。
今回のように新たに判明した相続人が、他の相続人と関係が近い方であれば、それほど問題にはなりませんが、まったく面識の無い方(例えば全く聞いていなかった隠し子など)だった場合は、慎重に対応する必要があります。
手続きもかなり長期化することが見込まれるため、戸籍調査の結果、新たに相続人が判明した場合や、相続関係が複雑でそもそも誰が相続人になるかよくわからない場合は、相続に精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。
面識のない相続人がいるなど、相続関係が複雑な場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
相続税の支払督促が来たことで、財産がある事が発覚!財産調査はどうやればいい?【遺産分割協議の前提として詳細不明の財産調査が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
相続が発生したのは3年前だが、実家に住む姉が財産管理を取り仕切っていて、遺産分割も行わないま…続きを見る-
遺産分割
相続税の支払督促が来たことで、財産がある事が発覚!財産調査はどうやればいい?【遺産分割協議の前提として詳細不明の財産調査が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
相続が発生したのは3年前だが、実家に住む姉が財産管理を取り仕切っていて、遺産分割も行わないままになっていたとのこと。
最近になって税務署から相続税支払いの督促状が届き驚いているが、姉とはなかなか連絡が取れず、どうしていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・他の相続人と遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、対象となる財産を確定させる必要があるが、調べ方がわからない。
・連絡がなかなかとれない姉と連絡を取り、遺産分割協議を行わなくてはならない。
亡くなった方の財産を、同居の子供など特定の相続人が管理していた場合、他の相続人は財産の詳細についてまったくわからないというケースはよくあります。
もちろん、そのような場合、財産を管理している方が他の方に財産の詳細をきちんと開示すべきなのですが、残念ながら財産開示が行われず、遺産分割協議や相続手続きが滞ってしまっているというケースもあります。
このケースもまさにそういった事例であり、さらに悪いことに相続税の基礎控除額を超えていたため、税務署の調査が入り、延滞税等が加算された内容で相続税の督促状が届いていました。
幸い、その後すぐに税務署に確認を取ったところ、すでに相続税については全額支払いがあった(相続人である姉が支払った)とのことだったため、大急ぎで高額の納税資金を捻出しなくてはならないという事態は避けられました。
しかし、ご相談者様によれば、遺産分割協議も相続手続きも全く進んでおらず、自分は何も財産を受け取っていないとのことでした。また、姉と連絡を取ろうにも、体の調子が思わしくないため遠く離れた姉の住所まで直接出向くことは難しく、ここ最近は電話に出てくれないので、途方に暮れているとのことでした。
そこで、当事務所でまずは税務署から届いた書類をもとに相続財産の詳細についての調査を行い、遺産分割の対象となる財産を確定した上で、お姉さまに手紙を出し、連絡を取ってみることを提案しました。相談後
・税務署から届いた書類の記載をもとに、金融機関に一つずつ連絡を取り、残高証明書や取引履歴の取得を行い、相続開始時点及び現時点の財産についての調査を行いました。
・不動産については管轄の自治体に名寄帳の請求を行い、漏れのないように調査を行いました。
・調査の結果、確定した遺産分割の対象となる財産について、他の相続人との話し合いの際の資料とするために財産目録を作成しました。
・財産目録をはじめとした調査結果をまとめた資料に、遺産分割協議を行いたいので連絡が欲しい旨のご本人からの手紙を添えて他の相続人に送付しました。
・連絡の結果、相続人間での話し合いは難しいという事になったため、相続に強い弁護士をご紹介させていただきました。事務所からのコメント
遺産分割協議を行うためには、まず対象となる財産を正確に把握する必要があります。ところがそのための資料を他の相続人が開示してくれないため、話し合いが一向に進まないという事があります。
そのような場合、早々に弁護士に依頼するというのも一つの手ではありますが、一人が弁護士を立てると、他の方も弁護士を立てて徹底的に争うという事態に発展してしまうことが多いのも事実です。必要以上に揉めるつもりはなく、できれば穏便に済ませたいと考えているという方にとって、まだはっきりと揉めていない段階で弁護士へ依頼するかどうかは、費用を含め悩ましいところかもしれません。
とは言え、手がかりが少ない状態で正確な財産の調査を行う事は普通の方にはとても難しいと思います。話し合いは自分でやってみるつもり、という方も、話し合いの前提としての財産調査については相続手続き・財産調査に精通した専門家に依頼することをおすすめします。
※完全に揉めていることが明らかな場合は、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。
手がかりが少ない状態での相続財産調査についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
揉めないように公平に分けたいが、二次相続の時の税金も気になる・・・【二次相続のことを考慮しつつ公平な遺産分割を行いたいケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご主人様とお子様二人。
相続人同士で揉めるつもりはなく、公平に分けるつもりだが、お父様もご高齢で健康状態も…続きを見る-
遺産分割
揉めないように公平に分けたいが、二次相続の時の税金も気になる・・・【二次相続のことを考慮しつつ公平な遺産分割を行いたいケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご主人様とお子様二人。
相続人同士で揉めるつもりはなく、公平に分けるつもりだが、お父様もご高齢で健康状態も思わしくないので、二次相続の際の税金等の事も考えて分け方を決めたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・節税のためには、今回の相続だけでなく二次相続のことも考えた上で、できるだけ相続税の負担を抑えられるような遺産分割を検討する必要がある。
・税金面だけでなく、一次相続・二次相続あわせて公平になるような、財産の承継方法を検討する必要がある。
このケースのように、夫婦のどちらかが亡くなられた際に、相続税申告が必要であれば、遺産の分け方は慎重に決める必要があります。
というのも、夫婦の片方がご存命であれば、配偶者控除や小規模宅地等の特例等の適用によって、相続税の負担はそれほどでもないという事が多いため、あまり良く考えずに配偶者に多く相続させてしまうという方も多いのですが、その後、さらに夫婦のもう一方が亡くなられた際には、特例等の適用もなく、相続人が減ったことにより相続税の基礎控除額も減るため、多額の税金がかかってしまうという事が多いのです。
このような事態を避けるためには、最初の相続(一次相続)の際に次の相続(二次相続)の際にかかる税金のことまで考えた上で、遺産の分け方や承継方法を決めておく必要があります。このケースではお父様ご自身も財産をかなりお持ちだったたため、分け方によって相続税の額がかなり変わる可能性がありました。
とは言え、節税のことを考えるあまり、不平等な遺産分割になってしまい、家族の仲がこじれてしまっては意味がありません。
そこで、当事務所で、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、税理士による一次・二次合計の相続税シミュレーションを行い、その結果を参考に遺産の分け方を検討していただくとともに、お父様については遺言書を作成していただき、一次・二次あわせてご両親からお子様への公平かつ確実な財産承継が行われるようサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・相続に強い税理士による相続税シミュレーションの結果を参考に、遺産の分け方を検討していただき、一次・二次合計の納税額の負担を抑えた内容で分割協議を成立させることができました。
・手続きの負担で相続人間に不公平感が出ないように、当事務所で、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、相続預金の解約及び分配手続き等の相続に必要な手続きをまるごと代行させていただき、特定の方に負担が偏ることなく、お母様の相続を終えることができました。
・お父様の相続の際に分け方で揉めることがないように、お父様に遺言を作成していただき、公平に分配されるように当事務所を遺言執行者に指定していただきました。事務所からのコメント
このケースのように、ご両親の相続をまとめて考えることで、相続税の負担を抑えたいと考える方は多いです。
将来かかる相続税については、相続に強い税理士がシミュレーションを行えば、ある程度は予測可能です。しかし、節税を気にするあまり、不平等な分け方になってしまったり、二次相続についての遺言書の作成等のケアを怠ったことにより、子供たちが不仲になってしまっては全く意味がありません。ご両親もそのようなことは望まれていないでしょう。
生前対策を実行するにあたっては、節税面だけではなく、将来の紛争の防止やスムーズかつ公平に財産を引き継ぐための対策も検討する必要があります。
特に手続き面で想定されるトラブルについては、一般の方が正確に認識していることはほとんどないでしょう。
家族全員から不満の出ない円満相続を実現するためには、相続についての法律や税務の知識だけでなく、手続きにまで精通した専門家に相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
相続開始から半年以上経過、亡き息子に高額の借金があったことが判明!【相続発生後3か月が過ぎてから債務があることが判明したケース】
相談前
息子さんを亡くされた方からのご相談。
息子さんには子供がいなかったため、相続人は妻と父の二人。
亡くなった息子さんについて、死亡後半年以上経って、債権者…続きを見る-
相続放棄
相続開始から半年以上経過、亡き息子に高額の借金があったことが判明!【相続発生後3か月が過ぎてから債務があることが判明したケース】
相談前
息子さんを亡くされた方からのご相談。
息子さんには子供がいなかったため、相続人は妻と父の二人。
亡くなった息子さんについて、死亡後半年以上経って、債権者から督促状が届いたとのこと。
慌てて息子の妻に連絡を試みたが、全く連絡が付かないという事で、当方に暮れた状況で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続放棄は、基本的に相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月が経過していた。
・相続人は高齢のため、自分自身で相続放棄手続きを行うことが難しい。
亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。
相続放棄は、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるため、今回のように相続発生から半年以上経過しているような場合は、相続放棄できないと考える方もいらっしゃいます。
しかし、期限内に相続放棄をしなかった(若しくはできなかった)ことについて相当な理由がある場合は、相続発生から3か月以上が経過していても放棄が認められることもあります。
今回のケースでは、亡くなった事実については死亡当日から知っていましたが、債権者から通知が届くまでは高額の借金があるという事実を知らなかったこと、また、健康上の理由により長期間入院をしていたため、財産・債務等の状況を知りようがなく、調査することも難しい状況であったこと、プラスの財産についてはすべてもう一人の相続人である被相続人の妻が相続すると思っており、実際にそのような処理がなされたこと、等の状況から、期限内に相続放棄をしなかったことに相当な理由があるものと思われました。
そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。
また、高齢でご自身で手続きを行うことが難しいとのことでしたので、当事務所で戸籍収集、申述書等の提出代行、裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。
さらに、ご相談者様の相続放棄が認められた場合に繰り上がりで相続人になるもう一人のお子様についても、相続放棄手続きをサポートさせていただくことになりました。相談後
・期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
・相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。
・お父様の相続放棄が認められた後、次順位相続人であるお子様についても相続放棄手続きを一貫してサポートさせていただき、無事放棄が認められました。事務所からのコメント
相続放棄の期限は、原則として亡くなった事を知ってから3か月以内です。
しかしこのケースのように、亡くなった事を知ってから長期間が経過した後に、債権者からの連絡によってはじめて高額の債務の存在を知った場合は、その事実をきちんと裁判所に伝えることによって相続放棄が認められることがあります。
しかし、単に「債務がある事を知ったのが最近だった」という事を伝えるだけでは、少し調べれば債務の存在を知ることができたのではないか、といった疑問が残るため、相続放棄が認められない可能性もあります。
相続放棄は、一度却下されると再度の申立てはできない手続きになりますので、3か月を過ぎているけど相続放棄をしたいと考えている方は、相続放棄にも詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。
3か月を過ぎてしまった後の相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
子供の頃、母と離婚した父に多額の借金があった・・・【幼い頃に離婚して以来音信不通の父親の相続放棄をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
父とは母は幼い頃離婚しており、以来音信不通の状態で、亡くなったことは弁護士(債権者の代理人)から借金の督促状が届いた…続きを見る-
相続放棄
子供の頃、母と離婚した父に多額の借金があった・・・【幼い頃に離婚して以来音信不通の父親の相続放棄をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
父とは母は幼い頃離婚しており、以来音信不通の状態で、亡くなったことは弁護士(債権者の代理人)から借金の督促状が届いたことではじめて知ったとのこと。
すでにお母様も他界されていて、親族含めてまったく交流のない状況のため、父についての情報がほとんどなく、何をどうすれば良いかわからず、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・父について名前以外の情報がまったくないため、相続放棄に必要な死亡時の住所情報や戸籍の集め方など、どうやって調べれば良いかわからない。
・相続放棄は、基本的に相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月が経過していた。
亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。
相続放棄はいつでもできるわけではなく、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があります。
今回のケースでは、お父様が亡くなったのは半年以上前であり、ご相談時点で相続発生から3か月が過ぎていたため、一見すると相続放棄できないようにも思えます。
しかし、今回は債権者(代理人弁護士)からの連絡により死亡を知ったため、「死亡の事実を知ってから」から3か月が過ぎていなければ、相続放棄は可能です。
ただ、亡くなった方との交流が全くなかったため、相続放棄の申立ての際に必要な情報や資料を集めることが自分ではできそうもないとのことでした。
そこで、当事務所で、相続放棄の申立てに必要な住所情報や戸籍の調査を行い、必要書類を揃えるとともに、亡くなったことを知ってから3か月が過ぎていないという事を裁判所に説明するための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。相談後
・当事務所で戸籍等の調査を行い、正確な死亡日や死亡時の住所等、相続放棄の申述に必要な情報を把握しました。
・亡くなったことを知ってから3か月が過ぎていないという事を裁判所に説明するための上申書を作成しました。
・戸籍謄本等の必要書類を揃え、相続放棄申述書、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。事務所からのコメント
相続発生日と「亡くなったことを知った日」が異なる場合、「亡くなったことを知った日」からは3か月が過ぎていないという事を裁判所に説明することができれば、相続放棄は認められます。
また、このケースのように子供の頃両親が離婚していて、何一つ手がかりがない状態であっても、戸籍等を調査することで必要な情報や書類を入手することはできます。
ただ、多額の借金を背負うかもしれないというプレッシャーを受けながら、3か月という短い期間内に戸籍等の調査を完了させ、裁判所を納得させるような書面を作成することは、普通の方にはとても難しいと思います。仕事や家事育児などで忙しい場合はなおさらでしょう。
債権者からの通知で疎遠な親族が亡くなり、借金の返済義務があることを知った場合は、慌てず、相続放棄をはじめとした相続手続き全般に強い司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。
音信不通の親族の相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
亡くなった父名義の不動産について固定資産税の納税義務者を変更する旨の通知が届いた…【亡くなってから長期間経過後に父の相続放棄をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様とお兄様のお子様二人。
父は2年前に亡くなっており、父の財産は全て兄が取得することで処理されてい…続きを見る-
相続放棄
亡くなった父名義の不動産について固定資産税の納税義務者を変更する旨の通知が届いた…【亡くなってから長期間経過後に父の相続放棄をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様とお兄様のお子様二人。
父は2年前に亡くなっており、父の財産は全て兄が取得することで処理されていると思っていたが、最近になって、亡父名義の実家不動産について、固定資産税の未納分の支払いと、納税義務者の変更を求める内容の通知が役所から届いたとのこと。
兄とはここ何年間はほとんど連絡が取れない状態のため、状況の確認もできず、登記名義を変更するようお願いすることも難しいという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続放棄は、基本的に相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月が経過していた。
・不動産取得者である兄と連絡がつかず、登記名義を変更してもらうことが期待できないため、相続放棄をしなければ今後も役所から請求書が送られてくる可能性がある。
不動産に課税される固定資産税は、原則として登記簿上の名義人(所有者)に対して、納税通知書が送られてきます。
亡くなった方の不動産について、名義変更(相続登記)を行わず、納税管理人(登記簿上の名義人の代わりに納税等の処理を行う人)の届出も行わなければ、いつまでも亡くなった方の名前で納税通知書が送られてきます。また、役所が名義人の死亡を把握している状態で未納が続くと、納税管理人や納税義務者の届出をするよう求められたり、納税義務者として一方的に指定されたりすることもあります。
このケースも、まさにそういったケースであり、このままお兄様が名義変更を行わなければ、ご相談者様が納税義務者として指定され、未納分だけでなく、今後発生する固定資産税についても、ずっと支払い続けることになる可能性がありました。
そのような事態を避けるためには、相続放棄手続きを行い、相続放棄の事実を役所に伝えるという方法があります。正式に相続放棄をしたことが確認できた方に対しては、以後役所からの請求等は行われないのが通常です、
ただ、相続放棄は、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるため、今回のように相続発生から2年以上経過しているような場合は、一見すると相続放棄できないように思えます。
しかし、期限内に相続放棄をしなかった(若しくはできなかった)ことについて相当な理由がある場合は、相続発生から3か月以上が経過していても放棄が認められることもあります。
今回のケースでは、亡くなった事実については死亡当日から知っていましたが、お話を伺ったところ、以下のような状況でした。
・役所から通知が届くまでは未納の税金があるという事実を知らなかった。
・ご相談者様は実家から遠く離れて暮らしており、調査することも難しい状況であった。
・財産や債務の状況について知っているはずの兄と連絡が取れない。
・プラスの財産についてはすべてもう一人の相続人である兄が相続すると思っており、実際に生前から今まで兄によって管理されていて、ご相談者様はまったく受け取っていない。
上記のような状況だったため、期限内に相続放棄をしなかったことに相当な理由があるものと思われました。
そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。
また、実家から遠く離れて暮らしており、戸籍等の必要書類を集めるのも難しいとのことだったため、当事務所で戸籍収集、申述書等の提出代行、裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の役所や他の相続人への通知等、相続放棄に関する手続きをまるごとサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
・相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び役所への通知もサポートさせていただきました。
・お兄様には、相続放棄をしたことを伝え、相続登記を行うよう促す内容の手紙を送付させていただきました。事務所からのコメント
このケースのように、亡くなったことは知っていたものの、未納税金等の債務があったことは知らず、長期間経過後に、債権者からの連絡によってはじめて債務があったことを知るというケースはよくあります。そのような場合でも、自分が財産をまったく受け取っておらず、処分もしていなければ相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄の期限は、原則として亡くなった事を知ってから3か月以内ですが、このケースのように、債務がある事を知らなかったことについて相当の理由がある場合は、例外的に相続放棄を認めるという判例があるためです。
しかし、相続放棄を認めてもらうためには、「相当の理由」について裁判所にきちんと説明し、納得してもらう必要があります。
一般の方が、裁判所に説明するための書面を作成することはとても難しいと思います。相続放棄は、一度却下されると再チャレンジできない手続きになりますので、3か月を過ぎた後に相続放棄をしたいと考えている方は、相続放棄にも詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。
3か月を過ぎてしまった後の相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
なぜ私が相続人になるの?兄には子供がいたはずなのに・・・【先順位の相続人全員が相続放棄をしたために相続人になってしまったケース】
相談前
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
亡くなった事を知ったのは1年前だが、兄には子供がいたので相続については何も考えていなかったとのこと。
ところが最近…続きを見る-
相続放棄
なぜ私が相続人になるの?兄には子供がいたはずなのに・・・【先順位の相続人全員が相続放棄をしたために相続人になってしまったケース】
相談前
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
亡くなった事を知ったのは1年前だが、兄には子供がいたので相続については何も考えていなかったとのこと。
ところが最近になって、役所から兄が滞納していた税金について、支払いを求める通知が届いたとのことで、何をどうすればいいかわからず、相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・先順位の相続人全員が相続放棄をしたために、繰り上がりで相続人になってしまった。
・相続放棄は、基本的に死亡の事実を知ってから3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月が経過していた。
・被相続人やその家族とは疎遠だったため、状況を確認することが難しい。
亡くなった方に子供がいる場合、(配偶者がいれば配偶者と共に)子供が相続人になります。そのため、故人に借金があっても兄弟姉妹に請求が来ることはないのですが、子供達全員が相続放棄をしてしまった場合は話が変わります。
この場合、直系尊属(父母や祖父母)が繰り上がりで相続人になるのですが、父母等が全員亡くなっている場合(または全員相続放棄した場合)は、さらに繰り上がりで兄弟姉妹が相続人になります。そうなると当然相続人として債務の支払い義務が生じるため、債権者から督促状等が届くことになります。
このケースも、ご相談者様が役所に確認したところ、相続人である子供たちが全員相続放棄をしたために相続人になっているとのことでした。
ところで、相続放棄の期限は相続開始(つまり死亡の事実)を知ってから3か月以内となっているので、このケースのように死亡の事実自体はだいぶ前に知っていた場合は、一見すると相続放棄できないようにも思えます。
しかし、相続放棄の期限は正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」(民法第915条)となっています。
このケースでは、債権者からの通知によってはじめて自分が相続人になったことを知ったわけですから、「自己のために相続の開始があったこと」を知った日(=役所からの郵便物の中身を確認した日)から3か月以内に申し立てをすれば相続放棄は認められます。
そこで、当事務所で上記のような事情を説明するための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。
また、お兄様とは疎遠だったため、死亡時点の本籍地等もわからず、手続きに必要な戸籍等を集めることが難しいとのことでしたので、当事務所で戸籍収集を行い、さらには申述書等の提出代行、裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・先順位相続人の相続放棄の事実を最近になって知ったという事を裁判所に説明するための上申書を作成しました。
・戸籍謄本等の必要書類を揃え、相続放棄申述書、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。事務所からのコメント
相続放棄は家庭裁判所に申し立て(申述)をして行いますが、相続放棄が認められても、裁判所はそのことを次に相続人になる方へ知らせてくれたりはしません。また、先に相続放棄した人が次の方に伝える義務もありません。
そうなると、亡くなった方の家族と疎遠であれば、相続放棄をしたという連絡も来ないでしょうから、このケースのようにある日債権者からの通知によってはじめて自分が相続人になったことを知る、という事が起こりえます。
そのような場合は慌てずに、先順位相続人が相続放棄したことを知った日から3か月以内に相続放棄の申述をすればいいのですが、まさか自分が相続人になるとは思っていなかったケースがほとんどでしょうから、気が動転して冷静な対応ができないかもしれません。
焦って債権者に連絡を取って、債務を支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
そのような事態にならないように、ある日突然債権者から、あなたが相続人で債務の支払い義務があるとの連絡を受けた場合は、相続放棄をはじめとした相続手続きに強い司法書士に、すぐに相談することをおすすめします。
先順位の相続人が相続放棄をした後の相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
数年前に亡くなった父に実は借金があった!今から相続放棄できる?【亡くなってから数年後に債権者からの連絡によりはじめて債務の存在を知ったケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様三人。
父が亡くなったのは3年ほど前だが、最近になって弁護士(債権者の代理人)からの連絡により未払い…続きを見る-
相続放棄
数年前に亡くなった父に実は借金があった!今から相続放棄できる?【亡くなってから数年後に債権者からの連絡によりはじめて債務の存在を知ったケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様三人。
父が亡くなったのは3年ほど前だが、最近になって弁護士(債権者の代理人)からの連絡により未払いとなっている借金がある事を知ったとのこと。
父の死亡から時間が経っているため、相続放棄ができるかわからず、ご不安な状態で相談にいらっしゃいました。
・相続放棄は、基本的に相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3年以上が経過していた。
・故人とは亡くなる前数年間は疎遠だったため、名前と大まかな死亡日くらいしかわからず、最後の住所等については不明。
・他の相続人と連絡を取ることが難しく、状況の確認ができない。
亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。
相続放棄は、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるため、今回のように相続発生から数年も経過しているような場合は、相続放棄できないと考える方もいらっしゃいます。
しかし、期限内に相続放棄をしなかった(若しくはできなかった)ことについて相当な理由がある場合は、相続発生から3か月以上が経過していても放棄が認められることもあります。
今回のケースでは、父とは疎遠だったとはいえ絶縁状態というわけではなく、亡くなった事実についても死亡日の翌日には知っていたので、債務がある事を知らなかったとしても仕方がない事情があるか、がポイントになります。
そこで詳しくお話を伺ったところ、以下のような状況でした。
・債権者から通知が届くまでは借金があるという事実を知らなかった。
・父との関係は悪いわけではなかったが、亡くなる前数年は仕事が忙しいこともあり疎遠だった。
・自分が知っている限り、父は真面目で浪費するような性格ではなく、質素な暮らしぶりだったはずなので、まさか借金があるとは思わなかった。
・財産や債務の状況について知っているはずの兄弟と連絡が取れない。
・父は賃貸アパート暮らしで財産と呼べるようなものは何もなかったとの認識だった。当然、自分はまったく財産を受け取っていない。
上記のような状況だったため、期限内に相続放棄をしなかったことに相当な理由があるものと思われました。
そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。
また、お仕事が忙しく、戸籍等の必要書類を集める時間がないとのことだったため、当事務所で戸籍収集、申述書等の提出代行、裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の役所や他の相続人への通知等、相続放棄に関する手続きをまるごとサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・当事務所で戸籍等の調査を行い、正確な死亡日や死亡時の住所等、相続放棄の申述に必要な情報を把握しました。
・期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
・相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。事務所からのコメント
亡くなってから長期間が経過した後で、債権者からの連絡により債務の存在を知った場合、その事実をきちんと裁判所に伝えることによって相続放棄が認められることがあります。
しかし、「債務の存在を知らなかった」だけでは、少し調べれば知ることができたのではないか、という疑問が残るため、簡単に相続放棄を認めてくれない可能性があります。
このケースのように、「疎遠ではあったが絶縁状態とは言えない親の債務を知らなかった」という場合は、なおさら「債務がある事を知らなかったとしても仕方がない事情」についてきちんと説明しなければなりません。
ただ、一般の方がこうした事情を正確に伝えるための書面を作成することは難しく、自分でやろうとすると大変な労力を要します。また、書類に不備があって申立てが却下されると再度の申立てはできません。
亡くなって大分経った後に債務が判明したので相続放棄を検討している、という方は、自分一人でやろうとせずに、相続放棄にも詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
新型コロナウイルスの影響で相続放棄がしたくてもできなかった・・・【相続放棄を検討したが、3か月以内にできなかったケース】
相談前
伯母様が亡くなられた方からのご相談。
伯母様に子供はいないと聞いており、親もすでに亡くなっているため、兄弟姉妹や甥姪数人が相続人になるはずとのこと(ご相談…続きを見る-
相続放棄
新型コロナウイルスの影響で相続放棄がしたくてもできなかった・・・【相続放棄を検討したが、3か月以内にできなかったケース】
相談前
伯母様が亡くなられた方からのご相談。
伯母様に子供はいないと聞いており、親もすでに亡くなっているため、兄弟姉妹や甥姪数人が相続人になるはずとのこと(ご相談者様方は甥姪)。
伯母とはそれほど親しい関係ではなかったため、財産は他の相続人が受け取るものと思っており、また、家族の介護や仕事でそれぞれ忙しく、相続手続きに煩わされたくないという思いもあり、相続放棄を検討していたとのことでした。
ところが検討している間に新型コロナウイルスが蔓延してしまったため、それどころではなくなり、情勢が落ち着いたころにはすでに3か月が過ぎてしまっていたとのこと。
その後、故人の家の整理をしていた際に督促状が見つかったため、不安になり、今からでも相続放棄できないかという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続放棄は、基本的に相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月以上が経過していた。
・故人とはそれほど親しかったわけではないため、財産や債務の状況について不明。
・新型コロナウイルスの感染拡大もあり財産・債務状況を調査するだけの余裕もない。
・仕事や介護で忙しく、自分たちで相続放棄手続きを行うことが難しい。
相続放棄は通常、借金を引き継がないために行われることが多いですが、プラスの財産が多い場合にも、故人と疎遠だったので関わりたくない、他の相続人が貰うべき、相続手続きに煩わされたくない、等の理由で行われることがあります。放棄の理由がどのようなものであっても、期限内に裁判所に申し立てを行えば、基本的に相続放棄は認められます。
しかし、相続放棄の期限である相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされるため、原則として放棄は認められません。
今回のケースも、亡くなったこと自体は相続発生から数日後に知っていたため、当初は相続放棄は難しいように思われました。
しかし、お話をよく伺ってみると、以下のような状況であったことがわかりました。
・伯母の相続関係についてはっきりと確認したことはなく、戸籍を調査したこともないため、もしかして先順位の相続人(子供など)がいるかもしれない。
・戸籍を調査しようとしたところ、新型コロナウイルスの感染拡大により非常事態宣言が発令されたため、中断せざるを得なかった。
・伯母とは多少交流はあったものの、そこまで親しいわけではなかったので、財産・債務の状況については知らなかった。
・督促状を発見するまでは債務があることを知らなかった。
・プラスの財産についてはすべて他の親しい相続人が相続すると思っており、ご相談者様方はまったく受け取っていない。
上記のような状況だったため、期限内に相続放棄ができなかったとしても仕方がないものと思われました。相続放棄の期限は原則として相続発生を知った日から3か月以内となっていますが、実は期限内に相続放棄をしなかった(若しくはできなかった)ことについて相当な理由がある場合は、3か月以上が経過していても放棄が認められることがあります。
そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。
また、仕事や介護で忙しく、自分たちで手続きを行うことが難しいとのことでしたので、当事務所で戸籍収集、申述書等の提出代行、裁判所から届く照会書の回答支援等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・まず、ご相談者様方が相続人であることを確かめるために戸籍調査を行いました。
・戸籍調査の結果、先順位の相続人がいないことが確認できたため、ご相談者様方が確かに法定相続人であることがわかりました。
・期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
・相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。事務所からのコメント
このケースのように、3か月以内に相続放棄を行うことを検討していたものの、諸事情によって期限内に申し立てできなかったという方はたまにいらっしゃいます。
期限内に財産・債務の調査が終わらない場合は、相続放棄の熟慮期間伸長の申立てを行って、3か月の期間を延ばしてもらうという方法もありますが、このケースのように、そもそも戸籍調査自体ができない状況ではそれも難しいでしょう(熟慮期間伸長の申立ての際には戸籍謄本や住民票除票等が必要になります)。
3か月の期限内に相続放棄ができなかったことにつき、相当な理由がある場合には例外的に3か月経過後の放棄が認められることもありますが、単に仕事が忙しかったといった理由だけでは、相当な理由があったとは認められないため、相続放棄をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
また、弁護士や司法書士などの専門家であっても、それほど相続放棄に詳しくない方に相談すると、今回のようなケースでは放棄できないと言われることもあるかもしれません。実際には裁判所に丁寧に事情を説明することで、相続放棄が認められる可能性があるにも関わらず、です。
もちろん事情を説明しても必ず相続放棄が認められるとは限りませんが、少なくともプラスの財産を一切受け取っていないという事であればチャレンジしてみる価値はあります。
ただ、一般の方はもちろん、専門家であっても相続放棄の実務経験が乏しければ、裁判所を納得させるだけの書面を作成することは難しいでしょう。
相続放棄手続きは、一度却下されてしまうと再度のチャレンジはできないので、3か月を過ぎてしまっているけれど相続放棄をしたい、という方は、相続放棄の実務経験豊富な司法書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
当事務所ではこれまでに3か月経過後の相続放棄について、数多くのサポート実績があり、そのほとんどが受理されております。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
相続を機に不動産の共有関係を解消したい【家族の共有名義になっている不動産を単独名義に変更したいケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様とお兄様のお子様二人。
主な財産は預貯金と自宅不動産で、不動産は現在居住している兄が取得するつも…続きを見る-
相続登記
相続を機に不動産の共有関係を解消したい【家族の共有名義になっている不動産を単独名義に変更したいケース】
相談前
お母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様とお兄様のお子様二人。
主な財産は預貯金と自宅不動産で、不動産は現在居住している兄が取得するつもりだが、不動産の名義が、母と兄弟の共有名義になっているとのこと。
母の遺産は公平に分配することで話はできているが、今後のことも考えて、この機会に共有関係を解消してお兄様の単独名義にしたいということで相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・不動産持分を共有者の一人が取得するとして、遺産全体について公平に分ける方法を検討する必要がある。
・弟様がもともと持っている共有持分について、お兄様に移転する方法を検討する必要がある。
不動産が家族全員の共有名義になっているということはたまにあります。
共有名義になっていても、家族が同居している間は問題は生じることはあまりありません。しかし時間が経過して離れて暮らすようになると、管理方針や処分について意見を一致させるのが難しくなります。そこで相続をきっかけに、今後のことを考えて共有関係を解消したいと考える方も多くいらっしゃいます。
このケースもまさにそのようなケースであり、お母様の共有持分に加えて、ご相談者様が持っている共有持分についても、この機会にすべてお兄様に移転したいというご希望をお持ちでした。
幸い、兄弟関係は良好だったため、手続き面と税金面等のコストの問題をクリアできれば、単独名義にすることは可能と思われました。
そこで、当事務所で、お母様の財産を公平に分けるための遺産分割案の提案を含む相続手続き全般のサポートをさせていただくとともに、ご相談者様の共有持分をお兄様へ贈与する手続きをサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・実家不動産についてはお兄様が取得し、その分弟様が金融資産を多めに取得するという分割案をご提案し、合意していただきました。
・多めに取得する金額は、お母様の持分と、贈与する予定の弟様の持分に相当する額とし、評価基準については、今後もお兄様が住み続け、売却するつもりはない事を考慮し、客観的な金額である固定資産評価額をベースとすることをご提案しました。
・合意内容に従って遺産分割協議書を作成し、お二人のご署名ご捺印をいただくことができました。
・お忙しいご相続人様に代わって、当事務所で、戸籍の収集、評価証明書や名寄帳の取得、金融資産の調査・解約及び分配までを行い、どちらか一方に負担が偏ることなく相続手続きを完了することができました。
・弟様の共有持分の贈与にあたっては、贈与税等の移転コストについて税理士に計算を依頼し、想定以上の負担にならないことを事前に確認しました。
・弟様の共有持分に関する贈与契約書を作成し、それをもとに贈与登記を申請しました。その結果、不動産はお兄様の単独名義になりました。
・贈与税の申告についても、担当する税理士をご紹介させていただき、必要書類の連携を行いました。事務所からのコメント
相続による所有権移転は他の方法と比べてコストが低く済むため、相続を機に他の共有者に持分を移転して、共有関係を解消するというのは悪くない考えです。
しかし、すでに登記されている持分を、贈与によって他の方に移転する場合、登録免許税の他に不動産取得税や贈与税等のコストがかかります。
これらの移転にかかるコストの問題を考えずに安易に贈与してしまうと、贈与を受けた側に思わぬ多額の課税がされてしまい、結果として不公平感が生まれ、家族の関係にひびが入ってしまう事もあります。
共有関係の解消について、どのような解決方法があるかは事情によって異なりますので、不動産の共有関係を解消したいと考えている方は、相続や贈与等に精通した司法書士等の専門家に、お早めに相談することをおすすめします。
共有名義の不動産の相続や贈与に関するご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
父の相続手続きを放置している間に兄が亡くなってしまった!しかも借金がありそう・・・【相続手続きを放置している間に二次相続が発生し、相続人が一人になってしまったケース】
相談前
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
配偶者やお子様はおらず、相続人は弟であるご相談者様一人のみ。
数年前に父が亡くなっていたが、相続手続きをしないまま…続きを見る-
相続手続き
父の相続手続きを放置している間に兄が亡くなってしまった!しかも借金がありそう・・・【相続手続きを放置している間に二次相続が発生し、相続人が一人になってしまったケース】
相談前
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
配偶者やお子様はおらず、相続人は弟であるご相談者様一人のみ。
数年前に父が亡くなっていたが、相続手続きをしないまま、兄まで亡くなってしまったとのこと。
ご相談者様が唯一の相続人となったため、父と兄の相続手続きを行わなければならないが、兄宛の請求書等が大量に届いており、借金が沢山あるのではないかと悩んだ末に相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・数年前に亡くなった父の相続手続きが終わっていない上に、財産状況も不明な点がある。
・兄には債務があり、財産もあるが、詳細については不明な点が多い。
・兄は在職中に亡くなったため、退職金や保険金の請求など、やるべきことが多く大変。
亡くなった方の財産について詳細が不明という事は珍しくありません。特に亡くなっってから時間が経ってしまっている場合や、兄弟姉妹などで生活環境が違う場合はなおさらです。
そのような場合、金融機関の通帳やキャッシュカード、取引報告書などの郵送物から目星をつけ、一つずつ連絡を取り、地道に調査を行うことになります。
このケースでは、金融機関の通帳や郵便物等で、ある程度の財産がある事は予想できましたが、債権者からの請求書や督促状なども大量に見つかったため、信用情報機関に情報開示請求を行うなどのより詳細な調査が必要と思われました。
そこで、当事務所で信用情報の調査を行い、お兄様の債務の状況を把握するとともに、各金融機関に連絡を取り、プラスの財産についても調査を行い、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることを確認してから、各債権者への返済や相続手続きを進めることを提案しました。
また、お兄様は在職中に亡くなられたため、死亡退職金や保険金の請求などの相続手続き以外の死後手続きについても対応が必要だが、数が多すぎて一人で行うのは大変とのことでしたので、そちらについても当事務所でサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・財産調査に必要な戸籍等を収集を行い、信用情報機関に提出して個人情報の開示請求を行いました。
・通帳等の資料を基に各金融機関に連絡を取り、取引状況の確認を行い、口座があれば残高証明書や取引履歴を取得するなどして財産調査を行いました。
・株式等の財産についてはほふり(証券保管振替機構)に開示請求を行い、判明した証券会社等に対して残高証明書等の請求を行いました。
・調査の結果、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることがわかりました。
・調査結果判明後、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関の解約・名義変更手続、債務の精算、保険金の請求などをまるごとサポートさせていただき、無事全ての手続きを完了することができました。事務所からのコメント
亡くなった方の財産の詳細が不明な場合、まずは財産調査を行い、相続の対象となる財産を確定させる必要があります。また、亡くなった方宛ての請求書がたくさん見つかったなど、多額の債務の存在が疑われる場合は、より慎重に調査を行う必要があります。
しかし、このケースのように、亡くなってから時間が経ってしまっている場合や、兄弟姉妹などで生活環境が違う場合は、手がかりも少なく、調査に大変な手間がかかることも少なくありません。
亡くなってから時間が経てば経つほど調査は難しくなるので、相続が発生したら、相続に強い司法書士などの専門家に相談の上、早めに手続きを終わらせることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
自分で手続きをやってみたけど大変なのでやっぱり専門家におまかせしたい・・・【一部完了済みの相続手続きの代行を専門家に依頼したいケース】
相談前
ご主人さまが亡くなられた方からのご相談。
お子様がいらっしゃらないご夫婦のため、相続人は妻と姉の二人。
すでに義姉様とは、すべての財産をご相談者様が…続きを見る-
相続手続き
自分で手続きをやってみたけど大変なのでやっぱり専門家におまかせしたい・・・【一部完了済みの相続手続きの代行を専門家に依頼したいケース】
相談前
ご主人さまが亡くなられた方からのご相談。
お子様がいらっしゃらないご夫婦のため、相続人は妻と姉の二人。
すでに義姉様とは、すべての財産をご相談者様が取得することで合意はできており、(当事務所とは別の)司法書士にご依頼のうえ、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更(相続登記)も完了していました。
難しい登記は終わったので、金融機関の手続きは自分でできると考え、やってみたものの、平日はお仕事の関係で時間を取ることが難しいうえ、金融機関ごとに必要書類や手続きの手順等の対応がばらばらで、想像以上に大変だという事がわかったため、自分には手に負えそうもないという事でご相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・金融機関の数が多いため、各金融機関ごとに必要書類や手続きの手順を確認して、効率よく手続きを進める必要がある。
・登記申請用に作成された遺産分割協議書のため、金融機関等の特定が不十分。
・住宅ローンの承継に関して、抵当権の債務者変更手続きが必要になる。
一般の方がご自身で相続手続きを行われる場合、ハードルが高いのは相続税申告と相続登記でしょう。この2つは専門性が高く、自分でやることによるリスクもあるため、費用をかけても税理士や司法書士等の専門家に依頼される方がほとんどです。
他方、金融機関の相続手続き(解約、名義変更)については、税申告や登記申請と比べると難易度は高くはなく、また、最寄りの支店で手続きができる場合が多いため、時間的余裕があり、事務作業が苦手でなければ、ご自身で手続きをされる方もいらっしゃいます。
今回も、金融機関の数は多いものの、何とかなるだろうと考え、当初は難しい登記だけを司法書士に依頼して、後はご自身で手続きを行われる予定でした。
しかし、金融機関の手続きは、各銀行・証券会社ごとに必要書類や手続きの手順が微妙に異なるため、金融機関の数が多いと確認するだけでも大変な手間がかかります。また、金融機関の担当者は相続の専門家ではないため、基本的にはマニュアル通りの対応となります。そのため、少しでもイレギュラーなことがあると確認や対応に非常に時間がかかることも珍しくありません。さらに、本当はこちらの対応があっているにもかかわらず、間違った案内をされてしまう事もあります(当事務所でも何度も経験しています)。
今回も、そのような金融機関とのやり取りに疲れたため、残りの手続きをすべておまかせしたいとのことでした。
そこで、当事務所で、各金融機関に連絡を取り、把握していない口座がないかの調査や、解約・名義変更手続きの一切を代行させていただくことを提案しました。
また、遺産分割協議書を確認したところ、登記申請が主な目的だったため、金融機関や口座の特定が不十分であることがわかりました。このままでは金融機関の手続きの際に、他の相続人の協力をお願いして、いちいち署名押印を貰わなくてはならない可能性があります。
そこで、そのような手間をかけないために、当事務所で改めて遺産分割協議書を作成し、義姉様にご署名ご捺印をいただくという方法を提案しました。この方法であれば、義姉様にご協力をお願いするのは一度だけで済みます。
さらに、住宅ローンについても、承継手続きが必要であり、それに伴う抵当権の債務者変更登記が必要であることも判明したため、そちらについても当事務所で代行させていただくことになりました。相談後
・各金融機関に対して迅速に必要書類や手続きの手順の確認を行い、把握している以外の口座がないかの確認のため、全店照会を行いました。
・当事務所で改めて遺産分割協議書を作成し、手続きについてのご説明(なぜ協議書の再作成が必要か)と共に、義姉様に送付いたしました。結果、快くご署名ご捺印をいただくことができました。
・いただいた協議書等を金融機関に提出し、ご相続人様の負担なく解約・名義変更手続きを完了させることができました。
・抵当権の債務者変更手続きについても、金融機関と連絡を取り、抵当権変更登記を申請し、完了させることができました。事務所からのコメント
このケースのように、自分で頑張って手続きをやってみたものの、思った以上に大変だったため、やっぱり専門家に任せたいということでご相談にいらっしゃる方は非常に多くいらっしゃいます。その際、皆様が口を揃えて仰るのは、「こんなに大変だとわかっていたら、初めから専門家にお任せしていた。」ということです。
このケースのように財産を取得する方が一人の場合は、その方がすべての手続きを行わなければならいことがほとんどでしょうから、なおさら大変です。
また、複数の相続人がいて、分担すればそれほど負担はないと思える場合でも、実際には特定の方に負担が偏ることが多く、そのことで不満がたまり、家族関係が微妙になってしまうというのもよくある話です。
確かに自分たちで手続きを行うことによって専門家への報酬を節約することはできますが、費用を節約しようとするあまり、ご相続人様が疲弊してしまったり、ご家族の関係がこじれてしまっては意味がありません。そのようなことは亡くなられた方も望まれていないでしょう。
わずらわしい手続きのための時間は、故人を偲ぶためや、ご自身のために使うべきです。相続が発生したら、まずは相続手続きに精通した専門家に相談して、肩の荷を下ろされることをおすすめします。
当事務所では、面倒な相続手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」のほか、金融機関の解約手続きのみ代行して欲しい、等のお客様の様々なニーズに対応可能なプランをご準備しております。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
父と母両方の相続手続きが必要・・・だけど財産の詳細がわからない【両親の相続財産の詳細が不明なため調査が必要なケース】
相談前
ご両親が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
お母様は数年前に亡くなっているが、相続手続きについては何も手を付けないでいるうち、この度お父…続きを見る-
相続手続き
父と母両方の相続手続きが必要・・・だけど財産の詳細がわからない【両親の相続財産の詳細が不明なため調査が必要なケース】
相談前
ご両親が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
お母様は数年前に亡くなっているが、相続手続きについては何も手を付けないでいるうち、この度お父様が亡くなられたとのこと。
ご両親の財産については、同居していた弟が把握していると思っていたが、確認したところ特に銀行や証券会社の口座について不明な部分が多いとのこと。
ご相談者様は仕事で忙しく、弟様は体調を崩しているため、自分たちでは手に負えないと思い相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・預貯金口座や証券口座について、現在も存在しているか不明なものが多いため、各金融機関に連絡を取り、調査する必要がある。
・株式については、銘柄はわかっているものの、どこの証券会社等で取り扱っているか不明なものがある。
・相続人のお一人が体調を崩されているため、なるべく負担をかけずに手続きを完了させたい。
亡くなった方の財産について詳細が不明という事はよくあります。
金融機関であれば通帳やキャッシュカード、取引報告書などの郵送物から目星はつくと思いますが、それらの資料が古いものである場合、現在も取引があるかを確認するために結構な手間がかかります。
まず、金融機関名が現在と異なる場合は、現在の問い合わせ先がどこであるかを調べることから始まります(多くの金融機関は合併や商号変更等により名前が変わっています)。
また、問い合わせ先がわかっても、長年取引がない場合は休眠口座扱いとなっており、確認に時間がかかることがあります。
何より、金融機関の数が多い場合には、片っ端から連絡を取り確認をするだけでも大変な労力を要します。
このケースでも、お父様はともかく、お母様については亡くなってから時間が経っていることもあり、現在の取引状況がわからないため、手元の資料をもとに総当たりで調査をしてみるしかない状況でした。
そこで、当事務所で各金融機関に連絡を取り、取り引き状況の確認を行ったうえで、残高証明書等の請求を行い、相続の対象となる財産を確定させることを提案しました。
また、株式については、配当に関する通知書以外に資料が無く、どこの証券会社に口座があるかもわからない状況だったので、当事務所でほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、他に保有している株式が無いかの確認も含めて調査を行うことを提案しました。
さらに、ご相続人様に負担のないよう、当事務所で戸籍の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関の解約・名義変更手続き及び財産の分配まで一括してサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・不動産については、配偶者名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように調査を行いました。
・10近くの金融機関に連絡を取り、取引状況の確認を行い、口座があれば残高証明書や取引履歴を取得して、相続の対象となる財産を確定させました。
・株式等の証券についてはほふりに開示請求を行い、判明した証券会社等に対して残高証明書等の請求を行いました。
・その他にも、当事務所で、戸籍の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関の解約・名義変更手続き及び財産の分配まで一括してサポート・代行させていただき、お父様お母様お二人分の相続について、ご相続人様の負担なく完了することができました。事務所からのコメント
亡くなった方の財産の詳細が不明な場合、まずは財産調査を行い、相続の対象となる財産を確定させる必要があります。
しかし、このケースのようにご両親ともに亡くなっている場合、手がかりも少なく、調査に大変な手間がかかること多いです。
亡くなってから時間が経てば経つほど調査は難しくなるので、相続が発生したら、相続に強い司法書士などの専門家に相談の上、早めに手続きを終わらせることをおすすめします。
詳細不明の財産の調査を含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
遠く離れた地方に住む姉の死後手続きをまるごとおまかせしたい【賃貸借関係の清算などを含む死後に必要な手続きすべての代行を依頼したいケース】
相談前
お姉様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様のみ。
お母様がご高齢のため自分で手続きするのが難しいため、息子の自分が動いているが、故人は遠く離れ…続きを見る-
相続手続き
遠く離れた地方に住む姉の死後手続きをまるごとおまかせしたい【賃貸借関係の清算などを含む死後に必要な手続きすべての代行を依頼したいケース】
相談前
お姉様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様のみ。
お母様がご高齢のため自分で手続きするのが難しいため、息子の自分が動いているが、故人は遠く離れた地方にお住まいだったため、手続きのために何度も足を運ぶのは難しいとのこと。
借りていたアパートの賃貸借関係の清算も済んでおらず、できれば相続手続きだけでなく死後に必要な手続きの一切を代行してもらいたいとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・亡くなった方は地方在住だったため、賃貸借関係の清算(遺品整理、未払賃料や清掃費用の支払)が必要だが、遠方のため手続きのために足を運ぶのが難しい。
・故人が所有していた自動車についても、名義変更の上、処分が必要。
・金融機関の解約や、保険金の請求、その他の細かい手続きを含めて一切手を付けていないが、すべての手続きを代行してくれる専門家や専門業者は少ない。
身近な人が亡くなった後には、想像以上にたくさんの手続きが必要になります。
不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約などのいわゆる相続手続きだけでなく、役所等への届出、年金や保険に関する手続き、公共料金の解約・清算などの細かいものも含めると、その数は100種類以上にも上ります。
※すべての人が100種類の手続きが必要なわけではないですが、少なくとも数十の手続きは必要なことがほとんどです。
これらの手続きを自分たちですべて行うというのは、大変な労力を伴うものです。
亡くなった方と離れて暮らしていたり、疎遠だったため財産の詳細や暮らしぶりがわからない場合はなおさら大変です。
このケースでも、亡くなったお姉様とは最近はほとんど連絡を取っていなかったため、どのような手続きが必要かもわからず、また、遠方のため手続きのための時間も取れないとのことでした。
詳しく状況を伺ってみると、借りていたアパートの管理会社からは、未払賃料の清算と、遺品を整理して引き払うことを求められており、また、敷地内駐車場の自動車についても撤去を求められていたので、早急な対応が必要な状況でした。
そこで、当事務所で、現地まで行って、遺品整理や、未払賃料・清掃費用等の清算、自動車の処分を行い、金融機関の解約、保険金等の請求、公共料金の解約その他の細かい手続きまで、まるごと代行させていただくことを提案しました。相談後
・遺品整理業者を手配し、遠方にある故人宅まで行って、遺品の中から必要な資料等の仕分けを行いました。
・賃貸アパートの解約、未払賃料、清掃費用等の支払も代行し、賃貸借関係を清算しました。
・敷地内にあった自動車については、地元の業者に連絡を取り、必要な手続きを行ったうえで引き取ってもらいました。
・その他、戸籍の収集、金融機関への連絡・解約、保険金等の請求、公共料金等の解約・清算など、亡くなった後に必要な手続きの一切を代行させていただき、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。
・手続きについてご相続人様にご対応いただいたのは、印鑑証明書の取得と、郵送で送られてきた書類への記入のみでした。事務所からのコメント
身近な人が亡くなった場合、役所等への届出や各種契約の解約・清算などの比較的簡単な手続きについてはご自身で対応される方が多いでしょう。
しかし、様々な事情から、そのような細かい手続きまで含めてすべて代行をお願いしたいという方もいらっしゃいます。
ただ、相続手続き代行を謳う専門家や専門業者でも、相続登記や金融機関の解約などのいわゆる相続手続き以外の細かい手続きまで幅広く対応してくれるところは多くありません。
全部おまかせしたつもりだったのに、後になって「その手続きは対応できない」と言われて困った…、という事にならないように、ご相談の際には、本当にあらゆる手続きに対応してくれるかを確認の上、信頼できる専門家に依頼されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
遺言を作成しようとしたら不動産が亡夫名義のままだった・・・【遺言を作成するにあたって相続登記が必要なケース】
相談前
お母様の遺言作成についてのご相談。
遺言に記載するために不動産の登記簿を確認したところ、すでに亡くなっているお父様様名義のままであることが判明。
遺言作…続きを見る-
遺言作成
遺言を作成しようとしたら不動産が亡夫名義のままだった・・・【遺言を作成するにあたって相続登記が必要なケース】
相談前
お母様の遺言作成についてのご相談。
遺言に記載するために不動産の登記簿を確認したところ、すでに亡くなっているお父様様名義のままであることが判明。
遺言作成にあたって母への名義変更が必要かもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・遺言作成にあたっては財産の特定が必要になるが、自分の名義でない不動産について特定可能か検討する必要がある。
・特定が不十分な場合は遺言での手続きに支障が出る可能性があるため、名義変更を行う必要がある。
遺言書に財産を記載するにあたっては、どの財産をだれに相続させるかを十分に特定する必要があります。特定が不十分だと相続人間で争いになったり、相続手続きの際に支障が出たりすることがあるためです。
今回は遺言作成にあたっての財産調査でご主人様名義のままであることが発覚したため、相続登記を行うべきか、このまま(亡夫名義のまま)遺言に記載するかというお話になりました。
お話を伺ったところ、すでにご主人様(お父様)についての遺産分割協議は済んでおり、不動産は奥様が取得するという事で話はついているとのことでしたので、遺言書に「亡夫名義であるが、実際には遺産分割協議によって依存者に帰属している」旨を付記すれば、一応特定できると思われました。
しかし、お母様が亡くなられた後、不動産を取得する相続人名義にするためには、登記申請の際にお父様についての遺産分割協議書を添付する必要があります。その時に万が一相続人の方が認知症になっていたり、行方不明になっていたりすると、大変な手間と費用がかかることになります。一方、遺産分割協議書を今作成して、すぐに登記を申請すればそのような手間はありません。
また、公正証書遺言作成の際は公証人に登記簿謄本等の不動産特定のための資料を提出する必要がありますが、名義が遺言者の方でない場合、確実に指摘を受けるので、説明に余計な手間がかかります(そしてほぼ確実に登記をしておくことをおすすめされると思います)。
そこで、そのような手間がかからないよう、当事務所でお父様名義の不動産について遺産分割協議書を作成し、相続登記を行って、お母様の名義に変更した後で遺言を作成することを提案しました。相談後
・お父様名義の不動産について、遺産分割協議書を作成し、ご相続人様の署名捺印をいただきました。
・登記申請に必要な戸籍等の収集も代行させていただき、遺産分割協議書と共に提出し、無事、お母様への名義変更が完了しました。事務所からのコメント
ご家族が亡くなったので、不動産の名義変更(相続登記)の相談にいらっしゃったところ、すでに亡くなっている配偶者や親の名義のままであることが判明した、という事はよくあります。
そのような場合、基本的には不動産の名義人の方の遺産分割協議と、不動産を取得された方の遺産分割協議を行って相続登記を申請することになります。
今回のように配偶者の名義のまま、ということであれば相続関係は同じ(お子様が相続人)という事が多く、比較的スムーズに行くこともありますが、親の名義のままの場合や、配偶者名義でも子供がいないケースでは、遺産分割協議書に署名や印鑑を貰うのが大変ということも多いです。
今後は、相続登記は義務化の方向で法整備が進んでいくと思われます。相続登記を放置してしまうと、後で手間や費用が余計にかかることはあっても何もメリットはありません。
相続が発生したら、相続登記の専門家である司法書士に相談の上、お早めに相続登記を完了させておくことをおすすめします。
放置したままの相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
自筆の遺言の記載に不備があるため手続きができない・・・【自筆証書遺言の記載に不備があり、疎遠な相続人との協議が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様2名。お子様のうちの一人は前妻との間の子のため、ほとんど面識がないという関係。
幸いお父様は…続きを見る-
遺言作成
自筆の遺言の記載に不備があるため手続きができない・・・【自筆証書遺言の記載に不備があり、疎遠な相続人との協議が必要なケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様2名。お子様のうちの一人は前妻との間の子のため、ほとんど面識がないという関係。
幸いお父様は遺言書を残されていたので、これに従って手続を進められれば、と思い相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・自筆の遺言の場合、相続手続きを行う前提として検認手続きが必要になる。
・検認を経ても、遺言に法的不備があれば無効になるため、確認する必要がある。
・法的不備が無くても、記載内容に問題があれば、遺言書だけでは手続きはできず、相続人全員の協力が必要になる。
・遺言書による手続きが可能でも、疎遠な相続人に連絡を取って説明する必要がある。
相続手続きをおこなう場合、遺言書が無ければ原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印を貰う必要があります。相続人の中に関係の良く無い方や、連絡を取りづらい方がいれば、協議のために大変な労力を要することも珍しくありません。
遺言書があればそのような負担は無いか、かなり軽減されるのですが、遺言書の内容によっては、まったく負担が減らないどころか、余計に手間がかかることさえあります。
今回は遺言書が自筆で書かれており、幸い、署名捺印や日付などの法的要件に不備はなかったのですが、相続手続きを行うにあたって、まず家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありました。
また、検認は遺言書の存在を公に確認して、偽造・変造を防ぐための手続きなので、遺言書の内容のチェックはしてくれません。そのため、検認を経たとしても、記載内容に不備があれば、結局相続人全員の協力の元、手続きを行うことになってしまいます。
今回も、遺言書を確認したところ、既に存在しない財産が記載されていたり、財産の分け方の特定が不十分だったため、やはり他の相続人に連絡を取り、手続きに協力してもらう必要がありそうでした。
しかし、もう一人の相続人とはほとんど面識がなく、前妻の子という微妙な関係のため、連絡を取ることに相当なストレスがある。また、法的なことや手続きのことについて、上手く説明できるか不安があるとのことでした。
そこで、当事務所で疎遠な相続人の方に連絡を取り、遺言書や相続手続きについてご説明させていただき、遺言書の内容に沿って遺産分割協議書を作成して、相続手続きを行うようご協力をお願いすることを提案しました。相談後
・相続手続きの前提として検認が必要なため、戸籍等の必要書類を収集の上、家庭裁判所に検認の申立てを行いました。
・疎遠な相続人の方に、遺言書の内容と、記載に不備があるため遺産分割協議書を作成して手続きを行うことに協力して欲しいという内容のお手紙を出しました。
・遺産分割協議の前提として、不動産や金融機関の調査を行い、相続財産を確定させた上で財産目録を作成し、相続人の皆様に開示いたしました。
・その後、何度かのやり取りの末、手続きにご協力いただけることになりました。
・遺言書の内容に沿った遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に署名捺印をいただくことができました。
・その後の不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約、分配まで当事務所で代行させていただきました。
・公平な立場の第三者が手続きを行うことにより、公明正大かつ迅速に手続きを終えることができました。事務所からのコメント
このケースのように、相続人の中に微妙な関係の方がいると、相続手続きを行うにあたり、ご家族の方が大変な苦労をされることになります。
遺言書があればそのような負担は無いか、かなり軽減されるのですが、遺言書の内容によっては、まったく負担が減らないどころか、余計に手間がかかることさえあります。
このケースのように自筆で書かれた遺言の場合、残念ながら手続きに使えなかったり、揉め事の原因になってしまうという事もよくあります。
ご家族のことを思って作成したはずの遺言書が、かえってご家族に負担をかけてしまうという事は望まれないと思います。
遺言書作成の際は、相続手続きに精通した司法書士等の専門家に相談の上、法的要件だけでなく内容についても不備のない遺言書を作成されることを強くおすすめします。
疎遠な相続人がいる場合の相続手続きや、遺言書作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
きょうだい間相続、長い間疎遠な親族との遺産分割協議が必要・・・【長い間疎遠にしていた方との遺産分割協議が必要なケース】
相談前
伯母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はきょうだい二人と甥であるご相談者様の3人。
きょうだいのうちの一人とご相談者様は親しい間柄だが、もう一人の…続きを見る-
遺産分割
きょうだい間相続、長い間疎遠な親族との遺産分割協議が必要・・・【長い間疎遠にしていた方との遺産分割協議が必要なケース】
相談前
伯母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はきょうだい二人と甥であるご相談者様の3人。
きょうだいのうちの一人とご相談者様は親しい間柄だが、もう一人のきょうだいについては20年以上連絡を取っていないとのこと。
親族から連絡先を聞き連絡を取ってみたが不通で、遠方に住んでいるらしいが正確な住所もわからないという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続手続きのためには相続人全員の協力が必要なため、疎遠な相続人に連絡を取る必要がある。
・遺産分割協議の前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して開示する必要がある。
・協議がまとまった後の不動産の名義変更や、金融資産の解約・名義変更及び分配についても、公平に行う必要がある。
・不動産については、利用予定もないため、売却して代金を分けるつもりだが、遠方に住んでいるため、売却活動を行うのが難しい。
亡くなった方にお子様がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹や甥姪の方が相続人になります。
ごきょうだいや甥姪全員が仲のいい方ばかりであればいいのですが、現実的にはそのようなケースばかりではなく、ごきょうだいでも長い間連絡を取っていなかったり、甥姪であればそもそも会ったこともないという事も多いです。
このケースも、全く面識がないわけではないものの、長い間連絡を取っておらず、亡くなったことを伝えるために親族から聞いた電話番号にかけてみたが、出てもらえないという状況でした。
また、連絡が取れた場合、法律的な話についてきちんと説明した上で、遺産分割について話し合う必要があると思っているが、うまく説明できるか自信が無いとのことでした。
そこで、当事務所で疎遠な相続人の方に連絡を取り、手続きについてご説明した上で、ご協力をお願いすることを提案しました。
また、遺産分割協議を行うにあたっては、後から問題にならないように、前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して開示する必要があります。
さらに、無事協議がまとまった際には、金融資産の解約・名義変更及び分配、不動産については売却して代金の分配まで行う必要がありますが、これらのことを公平性を保ちつつ迅速に行うのは非常に大変です。
加えて、相続税の申告も必要なため迅速に手続きを進める必要がある一方、ご相続人様が皆離れて暮らしているということもあり、自分たちだけで行うのは難しいとのことでした。
そこで、公平かつ迅速に手続きを終えるために、当事務所で、戸籍収集、相続財産の調査、財産目録の作成および開示、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関の解約及び各相続人への分配、さらには相続した不動産の売却および売却代金の分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。相談後
・疎遠な相続人の方に、相続関係や相続手続きについての説明と、手続きを行うことに協力して欲しいという内容を記載したお手紙を出しました。結果、無事協力していただけることになりました。
・遺産分割協議の前提として、不動産や金融機関の調査を行い、相続財産を確定させた上で財産目録を作成し、相続人の皆様に開示いたしました。
・分け方については、法定相続分をベースとすることでまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただく手配を行いました。
・その後の相続登記や、預貯金の解約・分配まで当事務所で代行させていただきました。
・相続税の申告についても税理士をご案内させていただき、必要な資料の収集等についてもサポートさせていただきました。結果、無事期限内に申告を終えることができました。
・不動産の売却についても当事務所で手配を行い、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートいたしました。
・当事務所にすべておまかせいただいたことで、特定の方に負担が偏ることなく、公平かつ迅速に手続きを終えることができたということで、相続人様の皆様に大変ご満足いただくことができました。事務所からのコメント
このケースのように、疎遠な相続人の方がいる場合は、連絡を取る際の伝え方や、手続きの進め方について、十分に気を付ける必要があります。
仲のいい親族間であれば、お互いに言わなくても通じる部分があっても、疎遠な方の場合はそうはいかないからです。
相続税の申告が必要な場合は10か月という期限があるため、気が逸るのもわかりますが、手続きを早く進めようとするあまり、失礼な対応をしてしまうと、他の方の気分を害してしまいます。
その結果、手続きが滞ってしまっては元も子もありません。
そのような事態を避けるためには、財産の調査をしっかりと行い、詳細を明らかにした財産目録を開示したうえで、法定相続分や相続手続きについての説明を十分に行い、不公平にならないような内容での遺産分割方法を提案する必要があります、
しかし相続の専門家ではない一般の方が、これらのことを自分たちだけで上手くやってのけるのはとても難しいでしょう。
また、このような場合、大抵代表者の方が主導して手続きを進めることになるのですが、苦労して手続きを行ったにもかかわらず、見返りはなく、それどころか他の方から手続きの公平性や透明性についてあらぬ疑いの目を向けられてしまうことさえあります。これでは亡くなった方含め誰も幸せになりません。
下手に自分たちだけで手続きを行おうとして泥沼化し、疲弊してしまう前に、相続人の中に疎遠な方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な専門家に相談の上、公平な立場で手続きを代行・サポートしてもらうことを強くおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続人は外国籍!戸籍謄本はどうする?【相続人の中に外国籍の方がいるケース】
相談前
伯母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄弟姉妹や甥姪など全部で6人。
亡くなった方は東京にお住まいでしたが、相続人の方はほとんどが地方在住で、高…続きを見る-
相続手続き
相続人は外国籍!戸籍謄本はどうする?【相続人の中に外国籍の方がいるケース】
相談前
伯母様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は兄弟姉妹や甥姪など全部で6人。
亡くなった方は東京にお住まいでしたが、相続人の方はほとんどが地方在住で、高齢のため自分たちで動くのは難しく、手続きすべてをおまかせしたいという事で相談にいらっしゃいました。
お話を伺う中で、相続人の中に、日本在住だが外国籍(アメリカ合衆国)の方がいるという事が判明しました。
▼問題点
・相続手続きの際には相続人全員の戸籍が必要になるが、外国籍の方は基本的に戸籍が無い。
・戸籍が無い場合、在日アメリカ大使館等で宣誓供述書を取得する必要があるが、遠方にあるため高齢の相続人が自ら出向くことは難しい。
・相続人のほとんどが地方在住で離れて暮らしているため、遺産分割協議の取りまとめや、遺産分割協議書等の必要書類の手配が難しい。
・相続人に高齢の方が多く、自分たちで書類を集めたり、金融機関に出向いて手続きを行うことが難しい。
相続手続きの際には、原則として相続人全員の現在の戸籍(謄本、抄本)を、金融機関や法務局などの各手続き先に提出する必要があります。
遺産分割協議や相続手続きは、基本的に相続人全員の同意の元行いますが、相続する権利を持つ方が誰なのかは金融機関等にはわからないため、公的書類である戸籍謄本等を提出して、客観的に相続関係を証明することになります。
ただし、戸籍制度は日本独自のもので、外国には基本的に戸籍はありません(台湾、韓国には日本のような戸籍制度があります。ただし韓国では2007年限りで廃止されました。)。
戸籍が無いからと言って、金融機関等は「では仕方ないですね、その方の分は証明無しでいいです。」とはなりません。相続人であることを証明するために代わりの書面の提出を求められることが通常です。
今回は、もともと日本国籍の方がアメリカに帰化され、米国籍ではあるものの、今は日本に住んでいるという状況でした。
このような場合、日本国籍離脱前の戸籍謄本に加え、日本にある駐日外国公館(米国籍であればアメリカ大使館や領事館など)に行って、宣誓供述書(自分が間違いなく相続人であるという宣誓をしたという事実を、本国大使等が認証したもの)を取得して提出するのが最も一般的な方法です。
ただ、今回は当該相続人の方は高齢で体調も思わしくなく入院されていたため、大使館等に出向くのは難しいとのことでした。
そこで、当事務所で大使館等に連絡を取り、宣誓供述書やそれに代わる書類の取得方法について確認の上、取得のための手続きをサポートさせていただくことを提案しました。
また、自分たちで動くことが難しい相続人の皆様に代わって、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融資産の名義変更や解約・分配、相続税の申告を行う税理士の手配まで、相続に必要な一切の手続きを代行・サポートさせていただくことを提案しました。
ご依頼をいただいてから早速、当該相続人の居住地の最寄りのアメリカ領事館に連絡を取り、宣誓供述書が必要な事情を説明の上、そちらに伺うのが難しいので出張をお願いできないか問い合わせました。
しかし領事館の回答は「(絶対に対応できないとは言えないが)原則対応できない」というものでした。領事館と居住地が遠方であり、対応のために半日以上かかるのでスケジュール調整が困難なこと、車椅子利用者の方などのかなり身体が不自由な方でも来所していただいていること、等が主な理由であり、登記申請のために必要という事も伝えたのですが、「今までにそのような前例がないので、法務局の方と調整して欲しい」と言われてしまいました。
この時点でアメリカ領事館とのこれ以上の交渉は難しいと思われたため、いったん要望に従って法務局と相談することにしました。
法務局に今回の事情を説明した上で、宣誓供述書なしでの手続きを認めてもらえないか打診したところ、いくつかの条件付ですが(外国人登録原票を取得して提出する、相続人全員の実印付きの保証書(上申書)を提出する、など)、何とか登記を認めてもらえることになりました。
また、念のため金融機関にも確認したところ、法務局に提出したものと同内容の書類等の提出があれば、手続きできるという回答を得られました。
なんとか解決の道筋が見えたので、当事務所で、外国人登録原票や相続人全員の保証書等の書類の手配もサポートさせていただき、手続きを進めることになりました。相談後
・法務局に事情を説明し、書面で照会を行った結果、外国籍の方については現在戸籍に代わる書面の提出で登記を認めてもらえることになりました。
・金融機関にも、現在戸籍に代わる書面の提出で手続きを進めることが可能か確認を行いました。
・現在戸籍に代わる書面(外国人登録原票や相続人全員の保証書)の取得についてもサポートさせていただき、無事手配することができました。
・離れて暮らしている相続人に一人ずつ連絡を取り、手続きについてのご説明や遺産分割協議の取りまとめを行い、遺産分割協議書へ署名捺印をいただくことができました。
・遺産分割協議書や現在戸籍に代わる書面を法務局や金融機関に提出しました。その結果、無事、相続登記や金融資産の相続手続きを完了させることができました。
・相続税の申告についても税理士をご案内して、期限内に納税まで終えることができました。
・その他、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、財産目録の作成などの相続に必要な一切の手続きまで代行・サポートさせていただき、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。事務所からのコメント
相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合、通常の手続きで必要になる、戸籍や住民票、印鑑証明書等が取得できないため、代わりの書面を取得するなどして手続きを行う必要があります。
ただ、今回のケースのように、宣誓供述書などの代わりの書面を取得することが困難な場合もあります。
そのような場合は、関係各所と調整の上、手続きを進めていくことになりますが、様々な手続き先に一つ一つ事情を説明したり、どのような手続きが必要かを正確に把握したりといった作業が必要なため、一般の方には大変な負担になります。
無理に自分たちだけで進めようとしても、慣れない作業で疲弊してしまう上、かかった時間のわりにはまったく手続きが進んでいない、という状態になりかねません。
そのような状態になる前に、外国籍の方や海外在住の方がいる場合は、相続発生後、すみやかに相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。
相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
第三者に関与してもらい、公平に遺産の分配を行いたい【公平のため専門家に相続手続きを任せたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
財産の分け方については揉めることなく分けることで合意はできているものの、手続きの分担や金…続きを見る-
相続手続き
第三者に関与してもらい、公平に遺産の分配を行いたい【公平のため専門家に相続手続きを任せたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様二人。
財産の分け方については揉めることなく分けることで合意はできているものの、手続きの分担や金融資産の分配方法をめぐって万が一にも争いになることの無いよう、公平な立場の第三者に手続きを任せたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・複数の相続人がいる場合、相続手続きを完全に分担して行うことは難しいため、不公平感が生じる可能性がある。
・代表者がまとめて手続きを行う場合、公平性や透明性の点で揉める可能性がある。
・第三者に手続き代行を依頼する場合、相続に精通した専門家以外に任せると、手続きが滞ったり、相続人への情報開示や説明が不十分だったりして、かえって揉める原因になる。
身近な方が亡くなった後に必要な手続きは、100種類以上にものぼり、すべてを自分たちで行おうとすると大変な負担になります。
相続人が複数人いれば、分担して負担を減らすこともできますが、うまく分担できる事例は少なく、大抵の場合は特定の方に負担が偏ることになります。また、預貯金等を代表者の口座にいったん入金して、その後に各相続人に分配する場合、分配手続きの透明性をめぐってトラブルになることもあります。
このケースでは、財産は公平に分けるという事で合意できたので、手続きの分担や公平性をめぐって揉めるよりは、費用をかけてでも公平な立場の第三者に手続きを任せたいというご意向をお持ちでした。
そこで、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融資産の名義変更や解約・分配などの相続に必要な一切の手続きを、第三者である当事務所が代行・サポートさせていただくことによって、公平に相続を完了させることを提案しました。相談後
・戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融資産の名義変更や解約・分配などの相続に必要な一切の手続きを代行・サポートさせていただき、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。
・相続に関するこれまでの豊富な経験をもとに、適切なアドバイスを行い、迅速に手続きを進めました。
・ご相続人様へのご説明やご報告を適宜行い、安心しておまかせしていただけるよう努めました。
・公平な立場の第三者が手続きを行うことによって、特定の方に負担が偏ることなく、公明正大に相続を終えることができました。事務所からのコメント
相続人が複数人いる場合の相続手続きの分担は、意外と見落とされがちな落とし穴です。
多く負担した方がその分財産を多く貰うのであれば問題ないのですが、実際は手続きの負担の多い少ないにかかわらず、財産は法定相続分で分けましょうというケースが多く、不満がたまる原因となっています。
また、代表者の方がほとんど一人で取り仕切っているケースでは、他の方から手続きの公平性や透明性をめぐってあらぬ疑いの目を向けられてしまうこともあります。
せっかく遺産は仲良く分けることで合意ができても、手続きの負担や公平性をめぐってわだかまりができたり、争いになってしまっては元も子もありません。
そのような事態は亡くなった方を含め誰も望んでいないと思いますので、相続が発生したら、まずは相続手続きに精通した司法書士などの専門家に相談の上、公平に手続きを進めることをおすすめします。
当事務所では、亡くなった後の面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめ、お客様のニーズに応じた様々な相続サービスをご提供しております。相続の実績豊富な国家資格者が公平な立場で手続きを行うので、安心しておまかせいただくことができます。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
両親が相次いで亡くなってしまい、一人でたくさんの手続きをしなければならない・・・【父母の相続手続きを相続人一人で行わなくてはならないケース
相談前
ご両親が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様一人のみ。
お母様が亡くなられた3か月後にお父様が亡くなられたため、相続手続きについてはまだ全く進ん…続きを見る-
相続手続き
両親が相次いで亡くなってしまい、一人でたくさんの手続きをしなければならない・・・【父母の相続手続きを相続人一人で行わなくてはならないケース
相談前
ご両親が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお子様一人のみ。
お母様が亡くなられた3か月後にお父様が亡くなられたため、相続手続きについてはまだ全く進んでいない状況で、どこから手を付けていいかもわからず相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続人が一人しかいないため、父母二人分の相続手続きについて、すべて自分で対応しなくてはならない。
・相続手続き以外にも、保険金や共済金の請求、年金の届出など、やることがたくさんあり大変。
・両親とは離れて暮らしていたため、財産の詳細について不明な部分があるが、仕事が忙しく、何度も現地に足を運ぶのは難しい。
ご両親が相次いで亡くなられた場合、悲しむ暇もなく二人分の手続きを行わなくてはならず、ご家族にはかなりの負担がのしかかります。相続人が一人しかいなければ、すべての手続きを一人で行わなくてはならないため、仕事や家事育児等をこなしながらとなれば、手に負えないという方がほとんどではないでしょうか。
このケースでも、ご相談者様は仕事が忙しく、相続についてはまだ何も手を付けられていないとのことでした。
そこで、当事務所で、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、不動産の名義変更(相続登記)、金融資産の名義変更や解約まで、相続に必要な一切の手続きを代行・サポートさせていただくことを提案しました。
また、保険金・共済金の請求や、年金その他の届出などの、相続手続き以外の死後に必要な手続きについてもほとんど手付かずの状態だったので、こちらについても当事務所で代行・サポートさせていただくことを提案しました。相談後
・お忙しいご相続人様に代わり、当事務所で、戸籍の収集、金融機関や不動産の調査、相続登記、金融資産の名義変更や解約まで、相続に必要な一切の手続きを代行・サポートさせていただきました。
・保険金や共済金の請求、各種届出などの死後手続きについても代行・サポートさせていただき、ご相続人様のご負担なく終えることができました。
・後相続人様にご対応いただいたのは、印鑑証明書の取得と、当事務所から郵送された書面へのご記入ご捺印のみでした。事務所からのコメント
当事務所へのご相談の中でも、相続人が一人しかいないというケースはかなりの割合を占めます。
相続人が一人であれば遺産分割協議が不要なため、一見すると楽に思えるのですが、実際にやってみると、全ての手続きを自分で行わなくてはならず、相談できる人もいないため、とても大変という事を、ご相談いただいた皆様が口を揃えておっしゃいます。
費用を節約しようと自分で頑張った結果、疲弊してしまい、体調を崩してしまっては元も子もありません。相続が発生したら、相続全般に詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談されることをおすすめします。
当事務所では、亡くなった後の様々な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめ、お客様のニーズに応じた様々な相続サービスをご提供しております。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
きょうだいの保険金請求に亡夫の子の協力が必要で困った・・・【保険金請求のためにまったく面識のない方の協力が必要なケース】
相談前
お姉様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はきょうだいである弟様のみ。
わずかな預金以外にめぼしい財産は無かったため、相続は完了したと思っていたが…続きを見る-
相続手続き
きょうだいの保険金請求に亡夫の子の協力が必要で困った・・・【保険金請求のためにまったく面識のない方の協力が必要なケース】
相談前
お姉様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はきょうだいである弟様のみ。
わずかな預金以外にめぼしい財産は無かったため、相続は完了したと思っていたが、故人が被保険者になっている保険契約に関する書類が見つかったとのこと。
ただ、死亡受取人がすでに亡くなっている姉の夫となっているため、請求できるかどうかもよくわからないという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・すでに受取人が死亡している生命保険契約について、請求が可能か確認する必要がある。
・請求が可能な場合、誰に権利があるのか確認する必要がある。
・請求できるのが法定相続人の場合、戸籍等を調査した上で、面識の無い方に連絡を取り、協力してもらわなければならない可能性がある。
亡くなった方の財産を相続するにあたっては、原則として法定相続人全員で遺産分割協議を行い、全員で協力して手続きを進める必要があります。
しかし、死亡保険金等についてはこの限りではありません。死亡保険金等は受取人が指定されていればその方の固有財産となるため、原則として遺産分割の対象外であり(ただし、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなります)、受取人が単独で請求することになります。
ただし、既に指定受取人が死亡していて、かつ、受取人の変更をしていない場合は話がややこしくなります。この場合は保険会社の規定によって誰にどのような割合で請求権があるか決められているので、保険会社に確認の上、手続きを進める必要があります。
もし規定で受取人の法定相続人となっていた場合は、まず戸籍等を調査して相続人を把握しなくてはなりません。さらに相続人全員に連絡を取り、手続きに協力してもらう必要がありますが、このケースでは亡夫の相続人は、配偶者であるお姉様以外まったく面識がなかったので、事情を説明して協力をお願いするのは大変な負担になると思われました。
そこで、まずは当事務所で保険会社に連絡を取り、保険金が請求可能か、可能であれば誰に権利があるのかを確認することを提案しました。
さらにご相談者様以外に請求権を持つ方がいれば、その方に当事務所より連絡を取り、事情を説明した上で、手続きへの協力をお願いすることを提案しました。相談後
・当事務所で保険会社に連絡を取り、保険金が請求可能か、可能であれば誰に権利があるのかを確認しました。
・確認の結果、亡夫の死後も受取人は変更されておらず、亡夫の死亡時点での法定相続人全員(相続人が亡くなっていればその相続人)が受取人になるとの回答を得ました。
・亡夫の戸籍を調査した結果、相続人は配偶者であるお姉様の他に、前妻との子が二人いることがわかりました。
・当事務所で、前妻との子二人に手続きへの協力をお願いするお手紙を出しました。結果、手続きに協力してもらえることになりました。
・手続きに必要な書類の手配も当事務所で行い、保険金の請求を行いました。
・保険金は代表者の口座にまとめての振り込みだったため、他のお二人への分配手続きについてもサポートさせていただき、無事手続きを完了させることができました。事務所からのコメント
死亡保険金や共済金については、通常は受取人単独での請求が可能なため、このケースのように複雑な手続きになる事は稀です。
しかし、保険や共済の内容によっては指定の受取人ではなく受取人の順位が決められていることもあり(大抵、生計同一親族が最優先で、関係性の近い親族ほど優先順位が高くなっています。)、その場合、ほとんど面識の無い方の協力が必要になることも珍しくありません。
面識が無ければ、そもそもコンタクトを取ることも困難でしょうし、仮に連絡が取れたとしても、知識のない一般の方が、事情を説明して協力をお願いするのは大変な負担になります。
不確かな説明をしてしまうとかえって事態は混乱し、協力を貰うのがいっそう難しくなってしまうかもしれません。そのような事態を避けるため、死亡保険金等の請求に他の方の協力が必要な場合は、相続手続き全般に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。
複雑な事情のある相続や死後手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
父が亡くなり、債権者から相続人全員宛の請求書が届いた!【相続人全員が同時に相続放棄をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は妻と子供3人。
お父様は生前会社を経営していて、すでに事業は清算しているものの、個人としての連帯保証債…続きを見る-
相続放棄
父が亡くなり、債権者から相続人全員宛の請求書が届いた!【相続人全員が同時に相続放棄をしたいケース】
相談前
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は妻と子供3人。
お父様は生前会社を経営していて、すでに事業は清算しているものの、個人としての連帯保証債務が残っているとのこと。
特にプラスの財産もないため、相続放棄をするつもりだが、一人一人別に放棄をするのではなく、全員が一緒に相続放棄をして、早く楽になりたいということで、相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・相続放棄は、相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、ご相談時点で約1か月しか残っておらず、迅速に手続きを進める必要がある。
・相続人全員まとめての放棄を希望しているが、それぞれが忙しく、手続きのための時間やその後の債権者への対応について時間を取ることが難しい。
亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。
相続放棄はいつでもできるわけではなく、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があります。
今回のケースでは、ご相談時点で3か月は過ぎていませんでしたが、期限まで約1か月という状況でした。
そこで、当事務所で至急手続きに必要な戸籍等を収集するとともに、相続人全員から相続放棄申述書をいただき、期限に間に合うよう家庭裁判所に提出させていただくことを提案しました。
また、相続人の皆様がそれぞれ忙しく、相続放棄手続きや債権者への対応であまり煩わされたくないとのことでしたので、申述書提出後の、裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。相談後
・戸籍謄本等の必要書類を迅速に揃え、期限内に裁判所に提出しました。
・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。事務所からのコメント
相続放棄は、相続発生日から3か月以内であれば、すでに故人の財産を受け取っている・処分している等の事情が無い限り、基本的に認められます。
そのため、ご自身で戸籍等の収集を行い、相続放棄申述書を作成して提出されるという方もいらっしゃいます。
しかし、身近な人が亡くなった後は葬儀などの様々な事柄の処理に追われるため、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。多額の借金を背負うかもしれないという重圧の中、3か月という短い期間内に必要書類の収集を終え、不備のない書面を作成することは、普通の方には簡単ではないと思います。仕事や家事育児などで忙しい場合はなおさらでしょう。
相続放棄の申述は失敗してしまうと再度のチャレンジはできない手続きですので、確実に相続放棄をしたいという方は、相続放棄をはじめとした相続手続き全般に強い司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。
相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
お世話になっている妹とその子供にすべての財産を相続させたい【特定の方にすべての財産を相続させる遺言を遺したいケース】
相談前
遺言書作成含む生前対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹5人。
夫が亡くなって以来、何かと世話をしてくれている妹とその…続きを見る-
遺言作成
お世話になっている妹とその子供にすべての財産を相続させたい【特定の方にすべての財産を相続させる遺言を遺したいケース】
相談前
遺言書作成含む生前対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹5人。
夫が亡くなって以来、何かと世話をしてくれている妹とその子供にすべての財産を相続させたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・お世話になっている妹と甥にすべての財産を遺したいが、何もしないと相続発生後に他の兄弟姉妹から権利を主張されてしまう。
・遺言を遺すとしても、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
・相続税の負担が過大にならないように、納税資金確保や節税についても対策の必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。
各相続人にはそれぞれ法定相続分が決められていて、分け方を決める際にも法定相続分をベースにすることが多いです。
そうなると、生前や死後に特定の方が親身になってお世話や手続きを行ったにもかかわらず、何もしていない他の方と取り分がほとんど同じという事態が起こりえます(遺産分割調停や審判になっても、介護等の負担は労力に比べるとごくわずかしか考慮されない場合が多いです。)。
これでは、一生懸命にお世話した方が報われません。また、財産を遺す方も、お世話になった方に多くの財産を遺したいと思うのが普通ではないでしょうか。
このような事態を避けるためには、遺言を作成することが最もシンプルで効果的です。
今回ご相談者様は、同居している甥とその母親(ご相談者様から見て妹)にとてもよくしてもらっているという事で、二人にすべての財産を遺したいとのご希望をお持ちでした。
そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。
また、後で遺言を巡って揉め事にならないように、遺言を作成するにあたり、万が一亡くなる順番が逆になったときの対策や、財産を貰わない相続人への配慮(今回は兄弟姉妹が相続人のため遺留分は発生しませんが、やはり心情面への配慮は必要です。)についても検討して提案させていただくことになりました。
さらに、このまま相続が発生した場合、相続税の納税や、相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても税理士とも協力の上、対策をご提案させていただくことになりました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・また、財産を貰わない相続人への配慮として、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士及び職員が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
・税理士の相続税試算をもとに、生命保険への加入や効果的な生前贈与などの納税・節税対策についても提案及び実行のサポートをさせていただきました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、将来、相続が発生した後の様々な手続きについての相続人様・受遺者様の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。事務所からのコメント
遺言は故人の最後の想いを、大切な人へ伝える重要なツールです。
しかし、日本で発生する相続の中で、遺言書があるケースは割合としてはごくわずかです。法的不備が無く、トラブルになる要素が無い内容のものとなるとさらにその数は限られます。
しかし、このケースのように特定の方にすべての財産を遺したい場合、遺言書の作成は必須です。また、せっかく作った遺言書が争いの種にならないよう、法的要件だけでなく、遺留分対策や予備的遺言など、内容についても不備が無いないものを作成すべきです。
しかし、ご自身だけで相続発生後のあらゆるトラブル想定し、それらを回避するための完ぺきな遺言を作成するのは普通の方には難しいでしょう。
財産を遺す方、貰う方、さらには財産を貰わない方まで、全員が満足する遺言を作成したいとお考えであれば、遺言を含む生前対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の作成含む生前の相続対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続放棄
亡き妻の借金を相続放棄したい・・・と思ったら過払金が発生していた!【亡くなった方の債務について帳消しの上、さらに過払金を取り戻せたケース】
相談前
奥様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご主人様とお子様一人。
預貯金等の財産はほとんどなかったものの、ご主人様が受取人の生命保険契約があったと…続きを見る-
相続放棄
亡き妻の借金を相続放棄したい・・・と思ったら過払金が発生していた!【亡くなった方の債務について帳消しの上、さらに過払金を取り戻せたケース】
相談前
奥様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご主人様とお子様一人。
預貯金等の財産はほとんどなかったものの、ご主人様が受取人の生命保険契約があったとのこと。
実は奥様には借金があり、亡くなる前数カ月は支払いが滞っており、消費者金融からの督促状が届いたとのこと。
このため当初は、債権者へ支払すべきか、場合によっては相続放棄も検討すべきか、という事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・亡くなった方には消費者金融からの借入があるが、債務の全容が不明なため、他の債権者からの借り入れを含め調査をする必要がある。
・債務の額が大きい場合は、相続放棄も視野に入れて対応について検討する必要がある。
・生命保険金は原則として相続財産にならないため、受け取っても問題ないが、その他の財産の処分や債務の支払いについては慎重に対応する必要がある。
亡くなった方に借金等の債務がある場合、金額によっては相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄を検討している場合、相続を承認したとみなされる行為(法定単純承認)を行わないよう気を付ける必要があります。
相続を承認したとみなされる行為の代表的なものは、預貯金などの引き出し、故人の財産からの債務の支払いなどです。ただし、生命保険金は受取人の固有財産とされているので、受け取っても原則として単純承認事由にはあたりません。
このケースでは、保険金以外にめぼしい財産はないとのことでしたが、もしもの時に相続放棄ができなくならないよう、調査が終わるまでは奥様名義の預金口座や現金には手を付けず、債権者に連絡を取らないで欲しいことをご説明しました。。
その上で、まずは財産の全容を把握するために信用情報の調査を行い、その結果によって相続放棄をするか、相続をして債権者に返済をするかを決めることを提案しました。
また、ご相談時にお持ちいただいた債権者から届いた書類に、現在の法律では違法となる利息が記載されていたため、返済状況によっては借金が帳消しになる可能性があると思われました。
そこで、消費者金融2社についても当事務所が代理人として連絡を取り、まずは取引履歴の開示請求を行い、本当の残債額について確認することを提案しました。
ご依頼を受けてからは、まず戸籍謄本等の調査のために必要な書類の収集から始め、その後、信用情報機関3社及び消費者金融2社に対して、被相続人の情報や取引履歴について開示請求を行いました。
消費者金融2社から届いた取引履歴について確認したところ、予想通り、亡くなった奥様は契約当初から最近まで違法利息で返済を続けていたことが判明しました。
さらに取引履歴をもとに返済額を法定利息に引き直して計算したところ、2社ともにすでに借金は完済済みであり、それどころか本来の返済額を超えて大きく払い過ぎている状況でした。
このようなケースでは金融業者に対して請求を行えば、既存の借金は帳消しになり、さらに過払い金を取り戻すことができます。
過払い金については、以前は大手法律事務所等によって盛んにCMがされていたため、ご存知の方も多いかもしれません。
当時のCMで“過払い金は10年で時効”という言葉が喧伝されていたため、大昔に契約したものについては取り返せないと思い込んでいる方も多いのですが、過払い金(正確には不当利得返還請求権)は“最後の取引(返済)から10年で時効によって消滅する”というのが正しいです。
大昔の契約であっても連続した一つの取引として返済を続けていれば、最後の取引から10年経っていない限り、今からでもすべての過払い金を取り戻すことが可能です。
また、契約者本人が亡くなった場合、過払い金は故人に帰属する権利として相続財産になるので、相続人からの請求によって取り戻すことが可能です。
ただし、消費者金融等の金融業者は、一般の方からの過払い金請求に対しては、経営状態が苦しいと言って、返還額の減額や返還日の先送りを交渉してきたり、法律的な論点があると主張して(大抵の場合専門家から見ると容易に反論可能な論点なのですが、一般の方には反論が難しいでしょう)、交渉の引き延ばしを行ってきたりして、相手があきらめたり、自分たちに有利な条件の和解が成立することを狙ってきます。
今回は、奥様は亡くなる数か月前まで、ほとんど滞納することもなく返済を続けており、業者の交渉に応じざるを得ないような不利な点はこちらにはない状況でした。
そこで、頑張って返済された奥様のためにも、当事務所が代理人として業者と交渉し、場合によっては訴訟を提起して、満額かそれに近い条件で過払い金を取り戻すことを提案しました。相談後
・戸籍等の必要書類を取集の上、信用情報機関3社に被相続人の個人情報の開示請求を行いました。調査の結果、把握している債権者以外に大きな借り入れはありませんでした。
・消費者金融2社から取引履歴を調査したところ、すでに債務は完済済みであり、過払い金が発生していることが判明しました。
・当事務所が代理人として、消費者金融2社に対して、任意交渉及び不当利得返還請求訴訟の提訴を行いました。
・交渉及び訴訟の結果、借金は帳消しになった上、2社合わせて200万円以上の過払い金を取り戻すことに成功しました。事務所からのコメント
このケースのように、亡くなった方に借金があったので、相続放棄をしようと思い相談にきたところ、実は借金は帳消しどころか高額の過払い金が発生していたというケースはたまにあります。
過払い金が発生する方は真面目な方が多く、家族には迷惑をかけたくないとの思いからか、誰にも言わずに亡くなってしまい、借金があると知ってびっくりしたというケースが多いです。
過払い金は消費者金融からの借入だけでなく、カード会社のキャッシングでも生じる可能性があるので、昔契約をして亡くなるまで返済を続けていたという方や、完済したのがここ10年以内かもしれないという方は、相続と過払い金に強い司法書士等に相談の上、まずは取引履歴を調査してみることをおすすめします。
当事務所では亡くなった方の過払い金請求に関するご相談を承ります。司法書士は代理人として金融業者との交渉や訴訟を行うことが可能です(司法書士の業務範囲を超える場合は弁護士をお繋ぎしますのでご安心ください)。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
夫の相続が終わっていないが、今すぐ遺言を作りたい【家族の相続手続きが終わる前に自分の相続についても対策をしたいケース】
相談前
遺言書の作成を検討されている方からのご相談。
現時点での推定法定相続人はお子様3人。
現在、夫の相続手続き中だが、相続人であるお子様の一人と少し揉め…続きを見る-
遺言作成
夫の相続が終わっていないが、今すぐ遺言を作りたい【家族の相続手続きが終わる前に自分の相続についても対策をしたいケース】
相談前
遺言書の作成を検討されている方からのご相談。
現時点での推定法定相続人はお子様3人。
現在、夫の相続手続き中だが、相続人であるお子様の一人と少し揉めており、自分の財産は絶対に渡したくないので、今すぐに遺言を作りたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・夫の相続についての遺産分割が終わっていないので、夫から相続する財産について、遺言中の記載方法を検討する必要がある。
・特定の方に財産を一切渡さないのであれば、遺留分請求のリスクについても検討する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、法定相続分をベースとして、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。
しかし、様々な事情から、相続人の中でも仲の悪い方には絶対に財産を遺したくないという方もいらっしゃいます。
もちろん自分の財産をどのように遺すかは自由なので、遺言書で財産の分け方を指定すれば、基本的には自分の意思を実現できます。
ただし、法定相続人には法律上最低限保証されている取り分として「遺留分」というものが定められており、遺言によってもらえる財産がこの遺留分を下回る場合は、他の相続人等に不足する分に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求といいます)。
死後に遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってかなり負担になるので、遺言書の作成や生前贈与等の相続対策を検討するにあたっては、遺留分については常に考慮しておく必要があります。
今回はお子様の一人には財産を一切渡したくないとのことでしたので、遺留分について説明したのですが、他の子供たちの負担になることは理解はしたがそれでも心情的には渡したくないとのことでした。
また、今回は先に亡くなられたご主人様の相続手続きが終わっておらず、遺産分割についても最終的な確定はまだこれからという状況でした。
本来であれば、財産の帰属が最終的に決まってから遺言を作成した方が、遺留分についてもより正確な金額が想定できるため、確実な対策ができるのですが、どうしても今すぐに作成したいという事でしたので、遺留分対策とは別に未確定の財産を遺言書に同記載するかについても検討する必要がありました。
そこで、とりあえず、すべての財産を仲のいいお子様のみに相続させる内容の遺言書を作成し、ご主人様の相続が完了してから、改めて遺留分についても配慮した内容の遺言書を作成することを提案しました。
また、万が一相続が発生した場合に、財産を貰えないお子様とのやり取りで他のお子様に負担をかけたくないとのことでしたので、そちらについても遺言で対策することを提案しました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、基本的にご希望通りの内容で遺言書の原案を作成しました。
・ご主人様から相続する予定の財産についても、可能な限り特定して遺言書案に記載しました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・また、遺留分侵害額請求のリスクを少しでも減らすために、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
・後ほど公正証書で改めて遺言を遺すことが前提だったため、公正証書ではなく、作成した原案をもとにご自身で自筆の遺言書を作成していただきました。
・将来、相続が発生した後のやり取りについての相続人様の負担を軽減するために、遺言の中で当事務所を遺言執行者に指定していただきました。
・当事務所で、作成した遺言書のチェックを行い、法的に有効な遺言であることを確認しました。事務所からのコメント
このケースのように、特定の相続人の方には財産を絶対に残したくないという方は一定数いらっしゃいます。
しかし、単純に財産を一切渡さない内容の遺言を作成するだけでは、遺留分を請求されるリスクを廃除・軽減することはできません。
特に遺留分についての対策をしなかった場合、遺留分の請求を受けて困るのは財産を貰う相続人の方です。大切な家族にそのような負担を負わせることは望んでいないという方も多いのではないでしょうか。
もちろん、このケースのように、様々な事情から遺留分を侵害する内容であえて遺言を作成するケースもありますが、その場合でも少しでもリスクを減らすための対策は必須です。
特定の方には絶対に財産を遺したくないが、できれば他の家族には迷惑をかけたくないとお考えの方は、遺留分対策を含む相続対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。
遺留分対策を含む相続対策や遺言書の作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
障がいを持つ子供のために遺言を遺したい・・・【障がいを持つ実子の面倒を看ることを条件に養子にすべての財産を相続させたいケース】
相談前
長年連れ添った奥様と障がいを持つお子様のために遺言の作成を検討されている方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は奥様と実子及び養子の計3名。
特…続きを見る-
相続手続き
障がいを持つ子供のために遺言を遺したい・・・【障がいを持つ実子の面倒を看ることを条件に養子にすべての財産を相続させたいケース】
相談前
長年連れ添った奥様と障がいを持つお子様のために遺言の作成を検討されている方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は奥様と実子及び養子の計3名。
特に自分がいなくなった後の障がいを持つ実子の生活が心配なので、奥様と実子の面倒を看ることを条件に、養子にすべての財産を相続させる内容の遺言を作りたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・負担付相続(遺贈)の遺言書を作成するにあたっては、貰える財産と負担のバランスがとれているかなど、内容を十分に検討する必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
遺言書で、相続人の方に財産を相続させる代わりに、親の介護など、一定の義務を負担させることを負担付相続(相続人以外の方に財産を継がせる場合は負担付遺贈)と言います。
負担付相続(遺贈)を内容とする場合、通常の遺言と比べて検討すべき事項がいくつかあります。
例えば、以下のような事項です。
①貰える財産と負担のバランスがとれているか
②財産を貰う方が確実に負担を履行してくれるか
③万が一負担が履行されない場合の対策
①については、負担ばかりが大きいと、逆に負担義務履行の確実性が低くなるためです(民法では、相続人(受遺者)が責任を負うのはもらった財産の価額の範囲までとされています)。
②については、財産を貰う方が信頼できるのか、負担義務を履行するための能力があるのか、相続発生時に高齢のため負担が履行できないという事は無いか、について検討する必要があります。
③については、負担が履行されない場合には、民法で「負担付遺贈に係る遺言の取消し」(民法第1027条)という制度が設けられていますが、家庭裁判所での手続きが必要で、手間も時間もかかるため、できれば使いたくない所です。
今回は、①については、十分な財産を貰うという事で問題はなく、②③についても、強い信頼関係があるということで問題はなさそうでした。
そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。
また、相続が発生した後の手続きについて、相続人に負担をかけたくないとのことでしたので、そちらについても遺言で対策することを提案しました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただき、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・将来、相続が発生した後の様々な手続きについて、当事務所が執行者として執り行わせていただくための遺言執行引受予諾契約を締結させていただきました。
・今回負担付遺贈を内容とする遺言書を作成したことで、遺言者様亡き後のお子様の生活についても、安心していただくことができました。事務所からのコメント
両親亡き後の障がいを持つお子様の生活支援や財産管理の関する様々な問題は、「親亡き後問題」として、社会的な問題となっています。
「親亡き後問題」の解決のためには、任意後見、障がい者のための特定贈与信託、障がい者福祉型の家族信託や生命保険信託など、様々な制度の活用が考えられますが、このケースのように信頼できる親族の方がいるなら、負担付相続(遺贈)を内容とする遺言を遺すというのも選択肢の一つです。
ただし、負担付相続(遺贈)は万が一負担が履行されなかった場合のリスクが大きいため、実行するにあたっては財産を貰う相続人の人間性、年齢、事務処理能力、経済状況等が重要になります。場合によっては他の対策との併用も検討すべきです。
どの方法が適しているかは、実情によって異なりますので、障がいを持つお子様やきょうだいがいらっしゃる方は、相続だけでなく、後見制度や家族信託にも精通して司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。
障がいを持つお子様の「親亡き後問題」についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続人は兄弟姉妹のみ、亡くなった後に負担をかけないよう対策をしたい【兄弟姉妹や甥姪に死後手続きの負担をかけないように対策をしたいケース】
相談前
遺言書の作成を含む相続対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹や甥姪あわせて9人。
夫が亡くなって、相続人は兄弟姉妹及び…続きを見る-
相続手続き
相続人は兄弟姉妹のみ、亡くなった後に負担をかけないよう対策をしたい【兄弟姉妹や甥姪に死後手続きの負担をかけないように対策をしたいケース】
相談前
遺言書の作成を含む相続対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹や甥姪あわせて9人。
夫が亡くなって、相続人は兄弟姉妹及び甥姪のみとなってしまったので、自分が亡くなった後のことについて今のうちから対策をしておきたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・兄弟姉妹や甥姪は全員離れて暮らしており、自分が亡くなった後の手続きの事や、財産をめぐって争いになることが心配。
・近くに住んでいてお世話になっている亡夫の子供にも財産を遺したいが、養子縁組については本人の意向もあるので慎重に考えたい。
・遺言を遺す場合、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
・相続税の納税が負担にならないように、現時点での相続税の金額についても確認しておく必要がある。
・残された方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
亡くなった後の財産は、民法によって相続できる方の順位や取り分が決まっています。
亡くなった時点でお子様も配偶者もおらず、父母や祖父母もすでにいない場合は兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)が相続人として遺産分割協議や相続手続きを行うのが原則です。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、大抵、特定の相続人と仲が良く、何かと世話をしていたという事が多いのですが、遺言を遺さず無くなってしまったため、仲の良かった方とその他の相続人とで取り分が全く変わらないという残念なケースもよくあります。
このような事態を避け、自分の思い通りに財産を遺すには、遺言を作成することが最もシンプルで効果的です。
今回ご相談者様は兄弟姉妹や甥姪とは離れて暮らしており、その中には仲の良い方もいれば、ほとんど連絡を取っていない方もいるとのことでした。
また、自分が亡くなった後の諸手続きについては、近くに住んでいて何かと気にかけてくれている亡夫の子供(ご相談者様との血縁関係は無し)にお願いしたいと思っており、その分遺言で財産を相続させたいとの希望をお持ちでした。
※相続人以外の方に財産を遺すためには、遺言の他に養子縁組という選択肢もありますが、養子縁組については本人の意向もあるので慎重に考えたいとのことでした。
そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。
また、後で遺言を巡って揉め事にならないように、遺言を作成するにあたり、万が一亡くなる順番が逆になったときの対策や、財産を貰わない相続人への配慮についても検討して提案させていただくことになりました。
さらに、相続税の納税額や、利用予定のない不動産の生前処分、自分が亡くなった後の相続手続きの負担についても気になるとのことでしたので、そちらについても税理士や不動産会社と協力の上、対策等を提案させていただくことになりました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・また、財産を貰わない相続人への配慮として、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士及び職員が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
・税理士による相続税の試算を行い、相続によって取得する財産によって十分に納税可能な金額であることを確認していただきました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、将来、相続が発生した後の様々な手続きについての相続人様・受遺者様の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。
・今後も利用予定のない不動産については、不動産会社をご紹介させていただき、無事早期に売却することができました。
・亡夫の子供との養子縁組など、今後も引き続きご相談いただき、場合によってはサポートさせていただくことになりました。事務所からのコメント
このケースのように、相続人が多数いる場合、亡くなった後の手続きの負担や、財産の分け方をめぐってトラブルになる可能性は高くなります。
トラブル防止のため、また、お世話になった方へ想いを遺すためにも以後の作成は必須ですが、せっかく作るのであれば、法的要件だけでなく、遺留分対策や予備的遺言など、内容についても不備が無いないものを作成すべきです。
しかし、ご自身だけで相続発生後のあらゆるトラブル想定し、それらを回避するための完ぺきな遺言を作成するのは普通の方には難しいでしょう。
財産を貰う方の負担にならないような遺言を作成したいとお考えであれば、遺言を含む生前対策全般にくわしい司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続人が多数いる場合の遺言書の作成など相続対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
甥姪が相続人、財産が少なくても遺言は必要?【死後手続きの負担軽減のために遺言を作成するケース
相談前
伯母様に遺言を作成して欲しいという方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹や甥姪複数人。
相続手続き含む死後の手続きについて不安があると…続きを見る-
遺言作成
甥姪が相続人、財産が少なくても遺言は必要?【死後手続きの負担軽減のために遺言を作成するケース
相談前
伯母様に遺言を作成して欲しいという方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹や甥姪複数人。
相続手続き含む死後の手続きについて不安があるとのこと。
伯母には子供がおらず、夫もすでに亡くなっているので、死後の手続きは何かと面倒を看ている自分が行うことになると思うが、他の相続人の同意を得るなどの面倒なことはできるだけ避けたいので遺言を作ってもらいたい。
ただ、伯母にはわずかな預貯金以外に財産と呼べるものは無いので、そのような場合でもあえて遺言を作る必要はあるか疑問に思ったため、相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・このまま相続が発生すると、相続人全員の同意の元、遺産分割協議や相続手続きを行わなければならないが、相続人が多数いるため、難航することが予想される。
・残された方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについて対策しておく必要がある。
亡くなった後の財産の分け方は、遺言書が無ければ、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることになります。
亡くなった時点でお子様も配偶者もおらず、父母や祖父母もすでにいない場合は兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)が相続人になるので、その全員の同意・協力の元、遺産分割協議や相続手続きを行うことになります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、大抵、故人と生前親しかった相続人が代表して手続きを進めることが多いのですが、手続きを進めるためには、各相続人に連絡を取ったり、手続きの内容について説明したり、遺産分割協議を取りまとめたり、遺産分割協議書やその他の必要書類に署名捺印を貰ったりといった作業が必要になるため、相続人が多かったり、離れて暮らしていたりすると、代表者の方にかなりの負担がかかります。
このケースでも、伯母様の面倒を看ているのはご相談者様であり、このまま相続が発生すると、相続手続きをはじめとする死後手続きを行うにあたり、大変な苦労が予想されました。
遺言書の作成などの相続対策を行うにあたり、紛争防止や節税のための対策を考える方は多いですが、死後の手続きの負担については意外と見落とされがちなポイントです。
しかし、死後の手続きは財産の多寡に関わらず相続人の負担となるので、遺言書でしっかりとケアしておかなければならない重要な問題です。
そこで、当事務所で伯母様から相続関係や財産状況等を詳しく伺い、残された方の負担にならないように遺言を作成することを提案しました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況等を詳しく伺い、残された方の負担にならないようにするための遺言書の原案を作成しました。
・財産額が少なく揉めるリスクも無かったので、手間と費用の節約のため、公正証書ではなく、作成した原案をもとにご自身で自筆の遺言書を作成していただきました。
・将来、相続が発生した後の手続きについての負担を軽減するために、遺言の中で財産を貰う方(ご相談者様)を遺言執行者に指定していただきました。
・当事務所で、作成した遺言書のチェックを行い、法的に有効な遺言であることを確認しました。事務所からのコメント
亡くなった後に必要な手続きは大小合わせて100種類以上あり、その中でも相続手続きでは原則として相続人全員の同意・協力が必要になるため、手間がかかります。
相続手続きの負担は、見落とされがちですが、財産の多い少ないに関わらず発生するため、とても重要な問題です。
ただ、相続の専門家と言われる方の中でも死後の手続きや相続手続きについてどのような点が問題になり、どのような対策をすべきかを正確に答えられる方はごく僅かでしょう。
それは、死後に必要な手続きが多岐にわたり、そのすべてについて把握して、実際にどのような手続きかを経験するのが難しいためです。
残される方の負担にならないよう、死後の手続きについてもしっかりと対策をしておきたいとお考えの方は、死後手続き・相続手続きの実績豊富な専門家へのご相談をおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
子供たちが揉めないように、亡妻の分と合わせて平等に相続させたい【子供たちが相続で争わないように遺言等で対策をしたケース】
相談前
遺言書作成含む生前対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人はお子様2人。
子供のうち一人には、亡妻の相続の際に多めに相続させている…続きを見る-
遺言作成
子供たちが揉めないように、亡妻の分と合わせて平等に相続させたい【子供たちが相続で争わないように遺言等で対策をしたケース】
相談前
遺言書作成含む生前対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人はお子様2人。
子供のうち一人には、亡妻の相続の際に多めに相続させているので、自分の分と合わせて平等になるように財産の配分を調整した上で、相続させたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・亡妻の相続と合わせて平等になるよう財産の配分を調整したいが、賃貸している不動産があるため調整が難しい。
・一見すると不公平な配分となるため、相続人から不満が出ないように、亡妻の相続を考慮したことなど、遺言書を作成した理由や遺言者の想いなども遺言書に明記する必要がある。
・意思能力の問題で後で揉め事にならないように、きちんとした形で作成する必要がある。
・遺留分請求など相続人同士の揉め事が起きないよう遺留分についても考慮する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
・相続税の負担が過大にならないように、納税資金確保や節税についても対策の必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、法定相続分をベースとして、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。
もちろん、遺言を遺すことによって法定相続分とは異なる分け方で相続させることも可能ですが、特に親から子へ相続させる場合、多くの方が子どもたちには平等に相続させたいと希望されます。
今回も、ご相談者様は平等に相続させることを望まれていましたが、数年前に亡くなられた奥様の相続の際に、お子様のお一人に賃貸不動産を相続させたため、両親から子への相続という点では、現状は不平等な状態となっていました。
そこで、当事務所で、税理士の協力の元、現在までの賃料収入や今後の賃料収入も加味した上で、できるだけ実質的に平等になるような分け方を検討し、アドバイスさせていただいた上で、公正証書遺言を作成することを提案しました。
また、今回の遺言で貰える財産の額が遺留分(法律上最低限保証されている各相続人の取り分)を下回ってしまうと、死後に遺留分の請求をされてしまう可能性があります。
遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってかなり負担になるので、財産の分け方を決めるにあたっては遺留分についても考慮することになりました。
さらに、このまま相続が発生した場合、相続税の納税や、相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても税理士とも協力の上、対策をご提案させていただくことになりました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・原案を作成するにあたっては亡き奥様の相続の際の遺産分割や、現在の賃料収入の状況についても詳しく伺い、今回の相続と合わせて平等になるような財産の分け方を提案させていただきました。
・死後に遺留分請求の問題が生じないよう、今回の相続における遺留分についても確保されていることを確認しました。
・一見すると不公平な配分となるため、感情面にも配慮して、亡妻の相続を考慮したことなど、遺言書を作成した理由や遺言者の想いなどを付言事項に盛り込みました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士及び職員が証人として立ち会いのもと、意思能力についても証拠が残る形で公正証書遺言を作成しました。
・税理士の相続税試算をもとに、生命保険への加入や効果的な生前贈与などの納税・節税対策についても提案及び実行のサポートをさせていただきました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、将来、相続が発生した後の様々な手続きについての相続人様の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。事務所からのコメント
今回のケースのように、子供達には父と母の分を合わせて平等に相続させたいと考える方は多いです。
しかし、財産の内容によってはきれいに分けるのが難しい場合もあります。
特に不動産がある場合は、利用状況、市場価格、税金等を考慮して慎重に判断しなければ、実質的な不公平が生まれてしまい、後で子供達の間にわだかまりができる原因となってしまいます。
遺言の内容が問題になるのは自分が亡くなった後の話なので、生前に万全な対策をしておく必要があります。
自分たちだけで考えるのが難しい、と感じられた方は遺言をはじめとする相続対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。
平等に相続させるための遺言書含む生前の相続対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺言作成
苦労をかけた子供のために遺言で財産を遺したい【特定の相続人に多くの財産を相続させたいケース】
相談前
遺言書の作成をご検討中の方からのご相談。
すでにご主人様は亡くなられており、現時点での推定法定相続人はお子様4人。
お子様のうちご長女様については、…続きを見る-
遺言作成
苦労をかけた子供のために遺言で財産を遺したい【特定の相続人に多くの財産を相続させたいケース】
相談前
遺言書の作成をご検討中の方からのご相談。
すでにご主人様は亡くなられており、現時点での推定法定相続人はお子様4人。
お子様のうちご長女様については、当時の経済状況から希望どおり進学させてあげられなかったことを悔やんでおり、せめてご長女様のお子様の学費については全面的に支援したいという思いがあり、自分が亡くなった後も確実に希望を実現したいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・苦労をかけた長女の子供の学費の支援のために十分な財産を遺したいが、多額の財産があるというわけではないので調整が難しい。
・他の相続人に遺す財産が少なくなるようであれば、遺留分請求のリスクについても検討する必要がある。
・一見すると不公平な配分となるため、相続人から不満が出ないように、遺言書を作成した理由や遺言者の想いなども遺言書に明記する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、法定相続分をベースとして、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。
遺言を遺すことによって法定相続分とは異なる分け方で相続させることが可能ですが、特定の方に多くの財産を相続させる場合、慎重な配慮が必要です。
もし、遺言で貰える財産の額が遺留分(法律上最低限保証されている各相続人の取り分)を下回ってしまうと、多く貰った方に対して、死後に遺留分の請求がされる可能性があります。
遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってかなり負担になるので、できるだけ遺留分を下回らないような分け方が望ましいですが、やむを得ず下回る場合でも、遺留分の請求を控えてもらうような配慮や、請求された場合の対策を検討しておくべきです。
今回は、お孫様が複数いることもあり、財産の総額に対してこれからかかる学費が大きな割合を占めるため、相続発生の時期によっては他の方への相続分が遺留分を下回ることが予想されました。
このような場合、他の相続人との関係性や、各自の経済状況(仕事は安定しているか、経済的に不自由していないかなど)が重要になりますが、状況を伺ったところ、他の相続人との関係は良好で、経済的にも皆自立しているとのことでした。
そこで、当事務所で遺言者様の半生、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、遺留分を下回った場合でも請求はしないで欲しいという強い想いを遺言作成の経緯と共に記した遺言を公正証書で作成することを提案しました。
また、相続が発生した際に、ご長女様がすみやかに財産を受け取れるように、スムーズな財産承継のための対策もご提案させていただくことになりました。相談後
・当事務所で、遺言者様の半生、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・死後に遺留分請求の問題が生じないよう、今回の相続における遺留分についても確保されていることを確認しました。
・遺留分を下回った場合でも請求を控えてもらえるように、ご長女様に苦労をかけた事など、遺言書を作成した経緯や遺言者の想いなどを付言事項に盛り込みました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書には予備的遺言も盛り込みました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士が証人として立ち会いのもと、公正証書遺言を作成しました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、将来、相続が発生した際のスムーズな財産承継が可能となり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。事務所からのコメント
このケースのように、特定の相続人の方に多くの財産を遺したいという方は一定数いらっしゃいます。
しかし、法定相続人には遺留分があるので(兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合を除く)、単純に特定の方に財産を多く遺すという内容の遺言を作成するだけでは、死後に遺留分を請求されるリスクがあります。
特に遺留分についての対策をしなかった場合、困るのは財産を貰う相続人の方です。大切な方にそのような負担を負わせることは望んでいないという方も多いのではないでしょうか。
もちろんこのケースのように、やむを得ず遺留分を侵害する内容で遺言を作成するケースもありますが、その場合でも付言事項で遺言作成の経緯や遺留分請求を控えて欲しい旨を記すなどして、請求のリスクを少しでも減らすための対策は必須です。
付言事項は法的効力・拘束力はないので、軽視する専門家もいるのですが、私の経験上、相続人同士の仲が元々険悪でない限り、感情面への働きかけはとても有効です。
遺留分請求は放っておいても誰かが勝手にやってくれるわけではなく、自ら行動を起こし、他の方への請求が必要なことを考えると当然のことです。
特定の方に多くの財産を遺したいが、できれば他の方は遺留分を請求せずに円満に解決してほしいとお考えの方は、遺留分対策を含む相続対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。
特定の方へ多くの財産を遺す内容の遺言書の作成など、相続対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
子供たちが揉めないように平等に財産をのこしたい【建築中の不動産等含め、公平に財産を相続させたいケース】
相談前
遺言書の作成をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は奥様とお子様3人の計4人。
奥様には自分の死後も不自由なく生活できるだけの財産を…続きを見る-
遺産分割
子供たちが揉めないように平等に財産をのこしたい【建築中の不動産等含め、公平に財産を相続させたいケース】
相談前
遺言書の作成をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人は奥様とお子様3人の計4人。
奥様には自分の死後も不自由なく生活できるだけの財産を相続させ、残りの財産は不動産を含め子供たち3人に平等に相続させたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・子供たちが揉めないよう平等な配分にしたいが、複数の不動産があるため調整が難しい。
・遺留分請求などで死後にトラブルにならないよう遺留分についても考慮する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
・相続税の負担が過大にならないように、納税資金確保や節税についても対策の必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、法定相続分をベースとして、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。
もちろん、遺言を遺すことによって法定相続分とは異なる分け方で相続させることも可能ですが、特に親から子へ相続させる場合、多くの方が子どもたちには平等に相続させたいと希望されます。
今回もご相談者様は、まずは奥様に相続税の納税資金と不自由なく暮らせるだけの財産を相続させ、残りの財産については子供たちに平等に相続させることを望まれていました。
ただ、ご相談様は資産家で、自宅以外に複数の不動産をお持ちだったため、不動産をどう相続させ、残りの金融資産等の分け方にどのように反映させるかが問題になりそうでした。
不動産は、利用状況(自宅か収益物件か)、市場価格(今後値上がりの見込みがあるか)、取得・維持・処分に係る税金(相続税、固定資産税、譲渡所得税など)等を考慮して、価値を総合的に判断した上で配分を決めなければ、実質的な不公平が生まれてしまい、後で子供達の間にわだかまりができる原因となってしまいます。
お話を伺ったところ、お子様たちは皆独立されており、経済的にも安定していて、関係性も悪くないとのことでした。
また、お子様のうち二人にはすでに将来自宅を建築する用の土地を購入しており、もう一人にもこれから建設されるマンションの購入を申し込んでいるとのことでした。
お子様方の関係性が悪くなく、それぞれの自宅のために生前から不動産を購入しているという事であれば、多少不動産の評価額が違っても、その他の財産の配分や付言事項での配慮によって十分に対策は可能です。
そこで、当事務所と税理士で連携して、現在建築中またはこれから建築中の不動産含め、できるだけ平等になるような分け方を検討し、アドバイスさせていただいた上で、公正証書遺言を作成することを提案しました。
さらに、このまま相続が発生した場合、相続税の納税や、相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても税理士とも協力の上、対策をご提案させていただくことになりました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・原案を作成するにあたっては、不動産の評価を行い、できるだけ平等になるような財産の分け方を提案させていただきました。
・死後に遺留分請求の問題が生じないよう、お子様たちそれぞれについて遺留分が確保されていることを確認しました。
・感情面にも配慮して、この分け方にした理由や遺言者の想いなどを付言事項に盛り込みました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士が証人として立ち会いのもと、公正証書遺言を作成しました。
・税理士の相続税試算をもとに、不動産の購入や保険・金融商品の活用などの納税・節税対策についても提案及び実行のサポートをさせていただきました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、将来、相続が発生した後の様々な手続きについての相続人様の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。事務所からのコメント
親密さの違いなどが多少あっても、子供達には平等に相続させたいと考えるのは、親として自然なことです。
しかし、財産が預貯金のみであれば平等に分けることは難しくないですが、多くの場合、不動産をどう相続させるかがネックになります。
不動産については、利用状況、市場価格、税金等を考慮して分け方を決めなければ、実質的な不公平が生まれてしまい、後で子供達の間にわだかまりができる原因となってしまいます。
平等な配分にしたつもりでも、それぞれに別の不動産を相続させる場合などは、結果として不公平な分け方になってしまいやすいので注意が必要です。
ただ、複数の不動産があるような場合に、すべての不動産について実質的な評価額を決めるのは普通の方には難しいでしょう。
遺言のせいで子供たちの関係が微妙になってしまっては元も子もありません。そのような事態は絶対に避けたい、とお考えの方は、不動産にも詳しい相続の専門家に相談の上、しっかりと対策を行うことをおすすめします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
知人にすべての財産を遺す代わりに死後の手続きを任せたい【相続人ではない方に財産を相続させる代わりに死後の手続きを任せたいケース】
相談前
遺言の作成をはじめ、死後手続きや今後の財産管理についてお悩みの方からのご相談。
配偶者やお子様はおらず、現時点での推定法定相続人はきょうだい2人だが、疎遠…続きを見る-
相続手続き
知人にすべての財産を遺す代わりに死後の手続きを任せたい【相続人ではない方に財産を相続させる代わりに死後の手続きを任せたいケース】
相談前
遺言の作成をはじめ、死後手続きや今後の財産管理についてお悩みの方からのご相談。
配偶者やお子様はおらず、現時点での推定法定相続人はきょうだい2人だが、疎遠なため、今後の財産管理や死後の手続きを任せるのは難しいとのこと。
日ごろから何かと気にかけてくれる信頼できる知人がいるので、その方にすべての財産を遺す代わりに、認知症になった場合の財産管理や、死後の手続きを任せたいという事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・信頼できる知人にすべての財産を遺したいが、何もしないと法定相続人であるきょうだいがすべての財産を相続することになる。
・遺言を遺すとしても、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
・死後の手続きについて、きょうだいには任せたくないので、知人に任せたいが、方法を検討する必要がある。
・今後、自分が認知症になった場合の財産管理等についても、知人に任せたいが、方法を検討する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の財産承継手続きについても対策しておく必要がある。
亡くなった方の財産は、その時点の法定相続人全員によって相続されることが原則です。
しかし、様々な事情から、相続人の方には財産を遺さず、信頼できる知人等に財産を遺したいという方もいらっしゃいます。
もちろん自分の財産をどのように遺すかは自由なので、遺言書で財産の分け方を指定すれば、相続人ではない方に財産を遺す事が可能です。
今回のように兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺留分の問題も生じないので(兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません)、遺言書を作成すれば確実に自分の意思を実現できます。
ただし、財産を貰えなかった相続人から、死後に遺言無効の訴えをされてしまうと受遺者(財産を貰う方)にとってかなり負担になるので、遺言書作成時の意思能力が問題にならないように、きちんとした形で作成しておくことが必要です。
そこで、お世話になっている知人の方にすべての財産を遺す内容の遺言を、公正証書で作成することを提案しました。
また、今回は相続の事だけではなく、自分が認知症になった場合の財産管理や、死後に必要な(相続手続き以外の)諸手続きについても、きょうだいではなく知人に任せたいとの希望をお持ちでした。
そこで、当事務所で現在の財産状況や生活状況、今後の生活についての希望等を詳しく伺い、生前の財産管理については「財産管理等委任契約」及び「任意後見契約」を、死後の諸手続きについては「死後事務委任契約」を、知人との間で結ぶサポートをさせていただくことを提案しました。
また、相続が発生した際、他の相続人とのやり取りで受遺者の方に負担をかけたくないとのことでしたので、そちらについても遺言で対策することを提案しました。相談後
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士及び職員が証人として立ち会いのもと、意思能力の問題が生じないよう公正証書遺言を作成しました。
・将来、相続が発生した後のやり取りについての受遺者様の負担を軽減するために、遺言の中で当事務所を遺言執行者に指定していただきました。
・知人の方にもお話を伺った上で、財産管理等委任契約及び任意後見契約並びに死後事務委任契約の原案を作成しました。
・作成した原案をもとに、遺言書の作成と一緒に、公正証書で各契約を締結していただきました。
・死後事務委任契約については、万が一に備えて当事務所を予備的受任者とする契約を締結しました。
・将来、認知症になった場合の財産管理や、亡くなった後のことについての不安が無くなり、安心していただくことができました。事務所からのコメント
近年のライフスタイルの変化によって、生涯未婚の方は年々増えてきており、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケース、あるいはきょうだいもいないため相続人が誰もいないケースも多くなってきています。
兄弟姉妹であっても大人になってからは他人以上に疎遠な関係であることは珍しくないので、今回のケースのように、信頼できる友人・知人に全財産を相続させる代わりに、老後の財産管理や死後の手続きをまかせたいというニーズは高まる一方でしょう。
とは言え、現段階では、財産管理等委任契約や任意後見契約、死後事務委任契約の一般的な認知度は低く、対応可能な専門家も限られています。
これらは将来のことを考えて結ぶ契約なので、今後予期せぬトラブルがあっても耐えうるような内容で契約書を作成する必要があり、習熟度が問われます。また、相続と密接に関係する問題のため、相続に精通していることも必須です。
専門家へ相談される際は、これらを踏まえて、認知症対策や死後手続き・相続手続きについての経験豊富な専門家を選びましょう。
当事務所には任意後見契約や家族信託等の認知症対策はもちろん、死後手続き・相続手続きについての多数の実績がある専門家が在籍しています。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺留分
同居の娘に全財産を相続させたいが遺留分も気になる【死後の遺留分請求のリスクを減らせるよう生前対策をしたいケース】
相談前
遺言書作成をはじめとする相続対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人はお子様2人。
現在同居している娘と、成人してからはほとんど連…続きを見る-
遺留分
同居の娘に全財産を相続させたいが遺留分も気になる【死後の遺留分請求のリスクを減らせるよう生前対策をしたいケース】
相談前
遺言書作成をはじめとする相続対策をご検討中の方からのご相談。
現時点での推定法定相続人はお子様2人。
現在同居している娘と、成人してからはほとんど連絡のない息子がいて、色々と助けてくれる娘の方にできるだけ多くの財産を遺したいが、一方で遺産を巡るトラブルで娘にあまり負担をかけたくない気持ちもある、という事で相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・特定の方に多く財産を遺すのであれば、遺留分請求のリスクについても検討する必要がある。
・明らかに不公平な配分となっても、相続人から不満が出にくいように、遺言書を作成した理由や遺言者の想いなどを遺言書に明記する必要がある。
・意思能力の問題で後で揉め事にならないように、きちんとした形で作成する必要がある。
・万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
・相続税の負担が過大にならないように、納税資金確保や節税についても対策の必要がある。
・財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
亡くなった後の財産の分け方をめぐって、遺された子供達がトラブルになることは避けたいと考えるのは親として当然の気持ちでしょう。
一方で、相続人の中でも特にお世話になった方にできるだけ多くの財産を遺したいと考えるのも、ごく自然なことです。
遺産をめぐるトラブルを避けるために、公平に財産を相続させる旨の遺言を作成するというのも一つの方法ではありますが、近くにいて何かと助けてくれる子とほとんど連絡もよこさない子に、公平に相続させるのはどうも納得がいかないと考える方も多いかもしれません。
もちろん自分の財産をどのように遺すかは自由なので、遺言書で財産の分け方を指定すれば、基本的には自分の意思を実現できます。
ただし、法定相続人には法律上最低限保証されている取り分として「遺留分」というものが定められており、遺言によってもらえる財産がこの遺留分を下回る場合は、他の相続人等に不足する分に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求といいます)。
死後に遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってかなり負担になるので、遺言書の作成や生前贈与等の相続対策を検討するにあたっては、遺留分については常に考慮しておく必要があります。
今回は同居している娘様にできるだけ多くの財産を遺したいとのことでしたので、まずは税理士の協力の元、現状の財産の評価を行い、遺留分の金額を算出することを提案しました。
さらにその上で、ご相談者様のお気持ちと、死後に遺留分請求等のトラブルになるリスク、その際に娘様にかかる負担などを考慮し、最もバランスの取れた内容で遺言を作成することを提案しました。
さらに、このまま相続が発生した場合、相続税の納税や、相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても税理士とも協力の上、対策をご提案させていただくことになりました。相談後
・税理士の協力の元、現状の財産評価を行い、遺留分の金額を算出しました。
・遺留分請求のリスクと、遺言者様のお気持ちのバランスを考慮し、遺留分には足りないものの、一定の財産を息子様に相続させる内容で遺言を作成することになりました。
・また、遺留分侵害額請求のリスクを少しでも減らすために、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士及び職員が証人として立ち会いのもと、意思能力についても証拠が残る形で公正証書遺言を作成しました。
・相続税の納税資金や、遺留分請求された場合の資金確保のために、娘様が受取人となる生命保険への加入をご提案し、加入していただきました。
・相続税の節税対策として、自宅の住み替えをご提案し、信頼できる不動産会社をご紹介させていただきました。
・遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
・将来、相続が発生した後の様々な手続きや、相続人間でのやり取りについての相続人様の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。事務所からのコメント
このケースのように、特定のお子様に多くの財産を遺す内容の遺言を作成する場合は、遺留分や相続人間の関係性等を慎重に検討した上で、様々な対策を行っておく必要があります。
家事や介護で貢献してくれたお子様に多くの財産を遺してあげたいと思うのは自然な感情ですが、せっかく多くの財産を遺してあげても、そのせいでトラブルに巻き込まれ、疲弊してしまっては、お子様もあまり喜ばれないのではないでしょうか。
正式に遺留分放棄の手続きを行わない限り、遺留分請求のリスクをゼロにすることはできませんが、生前にできるだけの対策をしておくことでトラブルのリスクを最小限にとどめることはできます。
大切なお子様が、自分が亡くなった後も困らないように遺言を作成したいとお考えであれば、死後のトラブル予防にも詳しい専門家に相談した上で対策しておくことをおすすめします。
遺留分請求の生前対策含む相続対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!





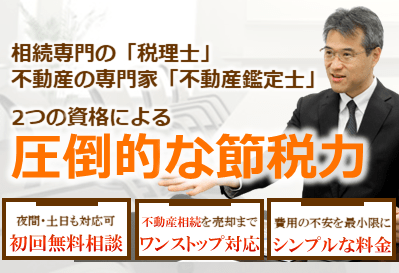

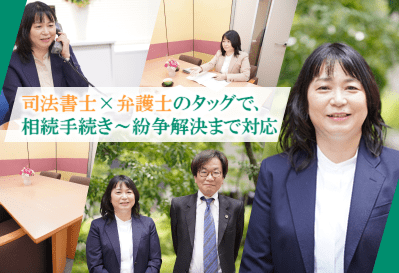
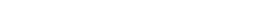
事務所からのコメント
このケースでは、お子様方の仲が良く、以前から長男様がお母様の面倒を看られていたため、コストを抑えることを重視して後見制度支援信託をおすすめしましたが、お子様の間で監護方針をめぐって対立があるなど、事情によっては信託の利用が適さないケースもあります。
どのような方法が適切かは事情によって異なりますので、成年後見制度を利用するにあたっては、制度に精通した司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、遺産分割のために成年後見制度を利用すると、後見人報酬等のコストがかかる、法定相続分の確保が必要なため税務上有利な遺産分割ができない、等のデメリットが生じることがあります。
このようなデメリットを回避するためには、生前に相続に精通した司法書士などの専門家に相談の上、遺言書の作成、特にご夫婦の場合は夫婦相互遺言を作成しておくことを強くおすすめします。
遺言書作成、夫婦相互遺言作成についてのご相談や、遺産分割のための成年後見制度の利用についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。