-
トップ
-
選ばれる理由
-
料金
-
解決事例7
-
お客様の声口コミ3
選ばれる理由
-


困難な案件でも安心。経験豊富な頼れるパートナー
神戸ライズ法律事務所は、神戸の中心地である「三ノ宮駅」から徒歩8分、アクセスの良い弁護士事務所です。平成24年の開所以来、相続・遺産に関する相談だけでなく、労働…
続きを見る> -


揉めない為の事前対策も、弁護士にお任せください
神戸ライズ法律事務所では、争族にならない為のアドバイスも積極的に行っています。ポイントは、財産整理と遺書作成だといいます。 「亡くなられた後に散らばった財産を探…
続きを見る> -


料金面からも依頼者に寄り添います
神戸ライズ法律事務所の料金は、「着手金低め」「調停審判期日の日当無料」が特徴です。 「着手金は、全国に10支店以上展開している複数の大規模事務所の相場の価格帯よ…
続きを見る> -


神戸の中心地「三ノ宮駅」から徒歩8分 利便性抜群の好立地
神戸ライズ法律事務所は、神戸の中心地である「三ノ宮駅」から徒歩8分。「三ノ宮駅」は、JRのほか私鉄、地下鉄、新交通の各線の「三宮駅」「神戸三宮駅」と接続している…
続きを見る> -


依頼者にとってのベストを追求します
坪井代表が弁護士を志したのは、肉親の遺産相続問題を目の当たりにした経験からだといいます。「中学生の頃、祖父の遺産相続で親兄弟が争う姿を見ました。少しでも心配事が…
続きを見る>

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
解決事例
-
遺産分割
生前に引き出した使途不明金の返還を求められた事例(不当利得返還)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。相手方)
<概要>
依頼者であるAさんが母の死亡直前に預金の引き出したために、兄弟…続きを見る -
遺産分割
遺産分割協議を話し合いで終了できた事例(遺産分割協議)
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。異母兄弟)
<概要>
依頼者であるAさんが寄与分の主張をして早期に話し合いで遺産分…続きを見る -
遺留分
もっと財産が有るはずだという相手方からの遺留分侵害額請求を退けた事例(請求された側)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。相手方)
<概要>
母は生前に公正証書遺言を作っており、母の死後、全財産を依頼者で…続きを見る
神戸ライズ法律事務所の事務所案内
神戸の中心地、「三ノ宮駅」から徒歩8分の神戸ライズ法律事務所。「どんな状況からでも必ず上昇する、決して諦めずに立ち直る、そしてご依頼者様のために最高の解決を目指す」という信念のもと、平成24年に開所しました。相続・遺産に関する相談だけでなく、労働災害・交通事故・自己破産など、幅広い案件に対応する、地域密着型の弁護士事務所です。問い合わせ件数は年間200件を超え、その豊富な経験と知識から、どんなに困難な内容でも粘り強く解決へと導きます。初回相談から代表が一貫して対応。親身なサポートが魅力です。
基本情報・地図
| 事務所名 | 神戸ライズ法律事務所 |
|---|---|
| 住所 |
650-0031 兵庫県神戸市中央区東町122-2 |
| アクセス | 「三ノ宮駅」から徒歩8分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~18:00(メールは24時間) |
| 対応地域 | 神戸を中心に、幅広いエリアに対応致します。 |
代表紹介

坪井 俊郎
弁護士
- 代表からの一言
- ご依頼者様が徹底的に戦うことを望まれるのであれば、当事務所は一切の妥協をせず、徹底的に立ち向かいます。
また、ご依頼者様が早期解決を望まれるのであれば、できるだけご依頼者様に有利な条件で和解するように交渉いたします。
当事務所では、困難と思われる事案であっても、簡単に諦めたりしません。
なんとかご依頼者様の言い分を認めてもらうように、さまざまな角度から検証をし、証拠を探すなどして最後まで諦めずに立ち向かいます。
- 資格
- 弁護士
- 所属団体
- 大阪弁護士会
- 経歴
- 平成15年3月 関西学院大学 法学部法律学科 卒業
平成18年11月 司法試験合格
平成20年9月 大阪弁護士会弁護士登録 - 出身地
- 昭和55年11月 福岡県京都郡に生まれる
昭和58年 大阪府に転居 - 趣味・好きなこと
- ダイビング(サイパン、宮古島、石垣島、白浜など)
読書(綾辻行人や石持浅海などのミステリー小説や経営関係の本)

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
選ばれる理由
困難な案件でも安心。経験豊富な頼れるパートナー

神戸ライズ法律事務所は、神戸の中心地である「三ノ宮駅」から徒歩8分、アクセスの良い弁護士事務所です。平成24年の開所以来、相続・遺産に関する相談だけでなく、労働災害・交通事故・自己破産など、多様な案件に対応してきました。その豊富な実績と知識から、個別の状況に合わせたアドバイスを得意としています。
代表の坪井俊郎弁護士は、「困難な問題や、こちらの言い分を通すのが難しいと思われる事件であっても、全力を尽くしています」と粘り強さを強調します。
当初の依頼を解決する中で、意図的に隠された遺産を発見したケースもあったそうです。親が死亡する8年前に親名義の預金3,000万円を自身の口座に送金。その後すぐに口座を解約し、証拠と遺産を隠していたというものです。坪井代表は、「単に通帳や取引履歴を見ただけでは他銀行への送金情報は出て来ません。口座の解約から年月が経過している場合は、裁判所を通して法的手続きをしないと記録を開示しない銀行が多いのです。こういった、通常では入手できない様々な情報を見落とさずに拾っていくことが重要です」といいます。弁護士だからこそ可能な資料の収集を行い、問題を丁寧に整理し、和解へと導きました。
揉めない為の事前対策も、弁護士にお任せください

神戸ライズ法律事務所では、争族にならない為のアドバイスも積極的に行っています。ポイントは、財産整理と遺書作成だといいます。
「亡くなられた後に散らばった財産を探すのは大変です。近頃はPCやスマホで資産管理をされている方も増えており、暗号資産ともなると追いかけるのがとても難しくなります。日常的に財産の整理整頓やパスワード管理は心がけていただきたいですね。また、争族と呼ばれる相続人間の揉め事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。ご自身で些細な事だと決めつけず、少しでも心配事があればご相談ください」と坪井代表は言います。
神戸ライズ法律事務所では、法的に効力のある遺言書の作成、個人では調査が難しい複雑な相続人調査や財産調査を行います。また法定相続人の関係をまとめた、法定相続情報一覧図も作成しています。
料金面からも依頼者に寄り添います
神戸ライズ法律事務所の料金は、「着手金低め」「調停審判期日の日当無料」が特徴です。
「着手金は、全国に10支店以上展開している複数の大規模事務所の相場の価格帯より低くなっているので(2024年時点での弊所調べ)、初期費用を抑えることができます」。(坪井代表)
調停審判期日の日当は、弁護士が裁判所へ赴く際の経費です。1回毎に2~3万円請求されることが一般的ですが、神戸ライズ法律事務所では無料です。(※交通費等の経費は別途請求あり)少しでも諸費用を抑えたい方にとって嬉しい料金設定です。
坪井代表は「時間と費用を惜しまずに徹底的に立ち向かうことがベストな解決であるときもあれば、ある程度の譲歩をして早期に和解をすることがベストな解決であるときもあります。当事務所では、ご依頼者様にとってのベストな解決案をご提案いたします」と話します。神戸ライズ法律事務所は、依頼者に寄り添う姿勢が強みの、相談しやすい事務所だといえるでしょう。

神戸の中心地「三ノ宮駅」から徒歩8分 利便性抜群の好立地

神戸ライズ法律事務所は、神戸の中心地である「三ノ宮駅」から徒歩8分。「三ノ宮駅」は、JRのほか私鉄、地下鉄、新交通の各線の「三宮駅」「神戸三宮駅」と接続している交通の要衝です。兵庫県内だけでなく、大阪など近郊からもアクセスがよい立地です。
初回無料相談は1時間30分と長めの設定なので、初回からしっかり相談することができます。2回目以降の相談は30分5,500円。安心の明朗会計です。

初回の無料相談から解決に至るまで、坪井代表がワンストップで対応しているのも大きな魅力です。初回の無料相談や打合せは、対面、電話、オンラインにて対応しています。契約後も、メール、LINEでの連絡がメインとなるので、日中は仕事で連絡が取りにくいという方でも時間を気にせず連絡を取り合あうことができます。
「生まれて初めてトラブルに巻き込まれたりすると、何から話していいのか、どこまで話していいのか、を正確に考えることは難しいです。当事務所では、ご依頼者様のトラブルを正確に把握し、適切な解決策を探していくため、じっくりと時間をかけて丁寧にお話をお伺いしています。また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することも心がけています」。(坪井代表)
依頼者にとってのベストを追求します
坪井代表が弁護士を志したのは、肉親の遺産相続問題を目の当たりにした経験からだといいます。「中学生の頃、祖父の遺産相続で親兄弟が争う姿を見ました。少しでも心配事がある方や、これから相続するという方には、できる限り揉めない為の事前対策をしていただきたいです」と話します。自身の苦い経験と、揉めた後に起こる問題の数々を熟知した、坪井代表ならではの細やかなアドバイスを受けることができます。
「当事務所では、事案の性質とご依頼者様のご事情を熟慮し、ご依頼者様にとってベストな解決案をご提案いたします。そして、最終的にどのような方針で事件処理を進めるかは、ご依頼者様にご判断いただいております。何かお悩みや不安等がございましたらご遠慮なくご相談下さい」。(坪井代表)


-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
対応業務・料金表
遺産分割事件
サービスの概要
弁護士がご依頼者様の代理人となり、他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議の成立を目指します。
料金
220,000円~
料金詳細
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉 | 220,000円 | 得られた額の16.5%(最低報酬440,000円) |
| 調停 | 330,000円(交渉段階から調停に移行の方は追加110,000円) | 得られた額の16.5%(最低報酬440,000円) |
| 審判 | 330,000円(調停段階から審判に移行の方は追加110,000円) | 得られた額の16.5%(最低報酬440,000円) |
※当事務所では、遺産分割・遺留分・使途不明金について、ご親族からご自身に請求された場合についてのご対応も承っております。
着手金/550,000円~(詳細をお伺いしてからの別途協議)
報酬金/減額した額の16.5%(最低報酬550,000円)

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
遺留分侵害額請求事件
サービスの概要
遺留分侵害が疑われる場合に弁護士がご依頼者様の代理人となり、遺留分侵害額に相当する金銭を支払いを目指します。
また逆の立場として、遺留分侵害額請求を受けた側の代理人として正しい評価を行い、支払額を軽減することに努めます。
料金
220,000円~
料金詳細
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉 | 220,000円 | 得られた額の16.5%(最低報酬330,000円) |
| 調停 | 330,000円(交渉段階から調停に移行の方は追加110,000円) | 得られた額の16.5%(最低報酬330,000円) |
| 裁判 | 440,000円(交渉段階から裁判に移行の方は追加220,000円。調停段階から裁判に移行の方は追加110,000円) | 得られた額の16.5%(最低報酬330,000円) |
※当事務所では、遺産分割・遺留分・使途不明金について、ご親族からご自身に請求された場合についてのご対応も承っております。
着手金/550,000円~(詳細をお伺いしてからの別途協議)
報酬金/減額した額の16.5%(最低報酬550,000円)

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
生前の使途不明金返還請求事件
サービスの概要
故人の使途不明金が疑われる場合に、弁護士がご依頼者様の代理人となり、使途不明額に相当する金銭の請求を行います。
料金
220,000円~
※遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件をご依頼いただいた場合はこちらの生前の使途不明金返還請求事件をご依頼いただく必要はございません。
料金詳細
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉 | 220,000円 | 得られた額の16.5%(最低報酬330,000円) |
| 裁判 | 440,000円(交渉段階から裁判への移行の場合は追加220,000円) | 得られた額の16.5%(最低報酬330,000円) |
※当事務所では、遺産分割・遺留分・使途不明金について、ご親族からご自身に請求された場合についてのご対応も承っております。
着手金/550,000円~(詳細をお伺いしてからの別途協議)
報酬金/減額した額の16.5%(最低報酬550,000円)

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
遺言無効確認訴訟
サービスの概要
遺言が無効であることを確認するため、弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所にて訴訟を行います。
料金
550,000円~
料金詳細
| 着手金 | 報酬金 |
| 550,000円~(詳細をお伺いしてからのお見積り) | 無効になって得られる予定額の16.5% |

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
遺産確認訴訟
サービスの概要
被相続人の財産のうち、相続財産に含まれるものを判断し、遺産の範囲を確定させるために提起します。
遺産確認訴訟にて遺産の範囲を確定させておくと、後々、遺産の範囲で争う心配がなくなります。
料金
330,000円~
料金詳細
| 着手金 | 報酬金 |
| 330,000円~(詳細をお伺いしてからのお見積り) | 遺産に含まれることになって得られる予定額の16.5% |

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
相続放棄
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
料金
44,000円~
料金詳細
| 相続放棄 | 1人 44,000円(2人目以降は1人 33,000円) |
| 相続放棄申述期間の伸長申立て | 1人 55,000円 |
【加算料金】
| 債権者に対する弁護士対応 |
債権者1人あたり 22,000円 |
※債権者に対する弁護士対応(連絡のやり取りや相続放棄完了の通知等)をご希望される方のみの追加オプションです。相続放棄だけをご依頼いただくことも可能です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
遺言書作成
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
料金
55,000円~
料金詳細
| 自筆証書遺言作成サポート | 55,000円 | |
| 公正証書遺言 | 定型の場合 | 110,000円 |
| 非定型の場合 | 220,000円~330,000円 | |
※別途:公証人費用などが生じます

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
遺言検認
サービスの概要
遺言者が死亡したら、その遺言者の自筆証書遺言を保管している人、発見した人は、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければならないことが、法律(民法)に定められています。
弁護士が代理人となって、法定相続人の調査(戸籍の取り寄せ)、申立書の作成などを行います。また、代理人弁護士が申立人ご本人と一緒に家庭裁判所に出席し、裁判官による遺言書検認の手続に同席します。
司法書士や行政書士と異なり、弁護士は代理人として手続に同席できるので、裁判官への説明や手続き等を全て任せることができます。
料金
110,000円
相続人調査
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になるのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。
料金
55,000円~
料金詳細
| 基本手数料 | 55,000円 |
| 事務手数料 | 33,000円 |
※相続関係図の作成も含みます。
※相続財産調査に引き続いて交渉・調停・訴訟をご依頼いただけた場合、着手金を55,000円お値引きいたします(お値引きの回数は1回だけです)。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする
相続財産調査・使途不明金調査
サービスの概要
相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査します。
料金
165,000円
料金詳細
| 基本手数料 | 165,000円 |
【追加費用】
| 追加調査対象1件について | 22,000円 |
※遺産目録作成を含みます。
※基本手数料に含まれるもの:①名寄帳に基づく不動産の登記簿謄本の取得、②兵庫県内の金融機関(証券会社含む)3社までの取引履歴の取得
※財産の調査が困難な場合(暗号資産や海外に財産がある場合等)は別途手数料が必要です。
※相続財産調査に引き続いて交渉・調停・訴訟をご依頼いただけた場合、着手金を110,000円お値引きいたします(お値引きの回数は1回だけです)。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 050-1868-5933
- Webで相談予約をする

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
お客様の声
-
相続手続き
調停で解決しました
長期に渡りお世話になり、心から感謝いたしております。 重ね重ねお礼申し上げます。…続きを見る
-
相続手続き
調停で解決しました
長期に渡りお世話になり、心から感謝いたしております。
重ね重ねお礼申し上げます。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
長い間お世話になりました
いろいろあった大変な問題も、これで全て決着となりました。 ありがとうございました。…続きを見る
-
相続手続き
長い間お世話になりました
いろいろあった大変な問題も、これで全て決着となりました。
ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺留分
遺留分を請求されました
丁寧に説明していただいて、とても分かりやすかったです。相手の理不尽な言い分にきちんと反論していただいて、解決内容も納得のいくもので満足しております。依頼してよか…続きを見る
-
遺留分
遺留分を請求されました
丁寧に説明していただいて、とても分かりやすかったです。相手の理不尽な言い分にきちんと反論していただいて、解決内容も納得のいくもので満足しております。依頼してよかったです。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
解決事例
-
遺産分割
生前に引き出した使途不明金の返還を求められた事例(不当利得返還)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。相手方)
<概要>
依頼者であるAさんが母の死亡直前に預金の引き出したために、兄弟…続きを見る-
遺産分割
生前に引き出した使途不明金の返還を求められた事例(不当利得返還)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。相手方)
<概要>
依頼者であるAさんが母の死亡直前に預金の引き出したために、兄弟であるBさんから引き出し分の不当利得返還請求を受けたものの、Bさんも生前に母名義の預金の引き出しを行っており、さらに母には遺言書があったのでわずかな解決金を渡すだけで終了した事件。
<詳細>
もともと母はBさんと一緒に過ごしていました。Bさんは、ことあるごとに母名義の通帳から10万円~50万円を頻繁に引き出していました(当時、そのことをAさんは知りませんでした)。
Bさんは、あまり母の面倒を良く見なかったので見かねたAさんが母を引き取って地元で同居して過ごしていました。
数年後、母の状態が悪くなったので、母が、「全財産をAに相続させる」との自筆証書遺言を作りました。その数カ月後に母が死亡しましたが、その直前にAさんが母名義の通帳からほぼ全財産である数千万円を引き出してA名義の口座に移動させていました。
母の死後、銀行の取引履歴を取得したBさんが、数千万円の引き出しについてその相続分の不当利得返還請求を弁護士に依頼をして内容証明をAさんに送りました。相談後
内容証明を受けたことで当事務所に相談がありました。
当事務所では、まずは財産の把握と事案の整理を行いました。
その結果、銀行の取引履歴から、①Bさんが母と同居時代に2,3年にわたり合計2,000万円くらいの引き出しがあり、母の生活費として考えると金額が多くて不自然であること、②母は、「全財産をAに相続させる」との遺言を作っており、それをBさんが知らない状態であることが判明しました。
そのため、最初に遺言書の検認手続きを行いました。
そして、確かにAさんは母の死亡直前に数千万円の預金をA名義の口座に移動させましたが、そもそも遺言書によって遺産相続は全てAが相続すること、Bさんも母名義の口座から多額の使途不明金を出金している可能性が濃厚であると反論をしました。
遺言があってもBさんには遺留分があります。ただし、Bさん自身も多額の出金があったので既に遺留分の多くを実質的に受け取っているという状態でした。
そのため、Bさんの本来受け取れる遺留分の額よりも低い100万円の解決金をAさんがBさんに支払うことで和解が成立しました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺産分割
遺産分割協議を話し合いで終了できた事例(遺産分割協議)
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。異母兄弟)
<概要>
依頼者であるAさんが寄与分の主張をして早期に話し合いで遺産分…続きを見る-
遺産分割
遺産分割協議を話し合いで終了できた事例(遺産分割協議)
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。異母兄弟)
<概要>
依頼者であるAさんが寄与分の主張をして早期に話し合いで遺産分割を終了させることが出来ました。
<詳細>
Aさんは、異母兄弟の存在は知っていましたが、Bさんの名前も知らず、会ったこともない状態でした。
Aさんは、父が亡くなる前に父の介護を行い、また死亡時には葬儀等も取り仕切って行いました。
父の死亡時の財産は約1,500万円でした。
父が死亡しそのことを知ったBさんが、弁護士を立てて法定相続分に従った金銭の主張をしてきたので当事務所に依頼がありました。相談後
Bさんにも相続する権利はありますが、Aさんは葬儀代、生前の治療費を負担し、仕事を休んで介護も行っていました。
そうした事情をもとに交渉した結果、Bさんは法定相続分の金額よりも2割低い額での遺産分割に応じてくれました。事務所からのコメント
相手方が弁護士を立ててきたので、Aさんが自分で対応するのは難しいと思い、以降の交渉を当事務所にお任せいただいたことで、安心して遺産分割協議書を作って終えることが出来ました。
寄与分を資料に基づいて主張して認めさせました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺留分
もっと財産が有るはずだという相手方からの遺留分侵害額請求を退けた事例(請求された側)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。相手方)
<概要>
母は生前に公正証書遺言を作っており、母の死後、全財産を依頼者で…続きを見る-
遺留分
もっと財産が有るはずだという相手方からの遺留分侵害額請求を退けた事例(請求された側)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(相続人。依頼者)
子B(相続人。相手方)
<概要>
母は生前に公正証書遺言を作っており、母の死後、全財産を依頼者であるAさんが相続しました。Bさんが弁護士を立てて遺留分侵害額請求の調停を起こしました。相談後
調停では、Bさんは「もっと母には遺産があったはず」として根拠なしに多額の遺留分を請求してきました。
しかし、当事務所は、Aさんは出せる資料はすべて開示しているので、もしもっと遺産があるというのであればBさんの方で証明してくださいと強く主張しました。
さらに、母の銀行口座の取引履歴を取り寄せて確認すると、Bさんは母から生前に1,000万円の贈与を受けていました。
Bさんには遺留分侵害額請求権がありますが、その生前贈与を考慮すればBさんが請求できる額は200万円ほどでした。
そうしたこともあり、200万円の解決金をAさんがBさんに支払うという内容で調停が成立して終了しました。事務所からのコメント
Aさんは社会的立場があったので、実は裁判をされたら少し困っていたのですが、それでも調停で強気で押し切って低い金額での和解が成立しました。
Bさんに生前贈与があったことを発見したことが大きなポイントです。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺産分割
遺産分割調停で相手方の寄与分の主張を排斥した事例(遺産分割調停)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(法定相続人。依頼者)
子B(法定相続人。相手方)
<概要>
相手方Bさんが、母の生前に母の事業を無償で手伝ったと主…続きを見る-
遺産分割
遺産分割調停で相手方の寄与分の主張を排斥した事例(遺産分割調停)
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(法定相続人。依頼者)
子B(法定相続人。相手方)
<概要>
相手方Bさんが、母の生前に母の事業を無償で手伝ったと主張して寄与分5,000万円を主張して調停を申し立ててきた事例。
<詳細>
母は代々の地主であり遺産総額は数億円でした。
Bさんは、母の死後、母の財産の資料を依頼者であるAさんに全く見せずに、「母の遺産総額は3億円である。Bさんが、母の事業(不動産管理業)を無償で長期間手伝ってきたので5,000万円の寄与分が認められる。その内容の遺産分割協議書を作ったので署名するように」とAさんに迫ってきました。Aさんは、資料もまともに見せないBさんのことを信用できずに署名を断っていたら、Bさんが弁護士に依頼してすぐに遺産分割調停をしてきたので、当事務所にご依頼がありました。相談後
Bさんから遺産分割調停を起こしたにもかかわらず、Bさんは財産の資料をほとんど提出してきませんでした。
そのため、当事務所で銀行や証券会社の取引履歴を取得し、土地の価格調査を行い、母の事業会社の戦前からの登記簿を取得したり、土地の現地に行って調査をしたりするなどして、全容の把握を行いました。
その後、Bさんが主張する「母の事業を手伝った」との主張について具体的にどのようなものであるのかの説明を求めましたが、資料に基づく具体的な回答はないため、Bさんの主張を丁寧に反論していきました。
最終的に、裁判所和解案ではBさんの主張する事業を手伝った分の寄与分は全て認められない和解案が出されましたので、その内容で調停が成立しました。事務所からのコメント
財産を適切に把握して、相手方の主張する寄与分には根拠資料を求めて丁寧に反論をしていくことが重要です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺産分割
会社の株式の生前贈与を否定する判決を取得した事例(遺産の範囲確認訴訟)
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(法定相続人。依頼者)
子B(法定相続人。相手方)
<概要>
会社を経営する父が生前に株式の2分の1を相手方Bさんに…続きを見る-
遺産分割
会社の株式の生前贈与を否定する判決を取得した事例(遺産の範囲確認訴訟)
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(法定相続人。依頼者)
子B(法定相続人。相手方)
<概要>
会社を経営する父が生前に株式の2分の1を相手方Bさんに譲渡したものの、そのときは既に父の認知症が進んでいたので譲渡無効を争った事例。
<詳細>
父は、会社を経営していました。
父に認知症が出始めたころに、父が、会社の株式の2分の1(時価総額5,000万円)をBに譲渡するという譲渡契約書を作成しました。
しかし、その譲渡契約書を作成したころには認知症が進んでいて適正な意思能力はなかったはずです。そのため、譲渡契約は無効であり株式は全部、父の遺産に含まれるはずです。
ところが、Bは、譲渡契約書を理由に、株式の2分の1については父から生前に譲り受けており、遺産の範囲に含まれないと主張して譲りませんでした。相談後
とある財産が遺産に含まれるか否かを争うためには家庭裁判所ではなく地方裁判所での遺産確認訴訟をする必要があります。
そのため、地方裁判所に遺産確認訴訟を提起しました。
その裁判の中で、父の病院のカルテ、介護施設の記録等を取り寄せて、譲渡契約書作成当時に父に意思能力がないと主張した結果、判決で、意思能力に疑問があるので譲渡契約が締結されたとは認められないと判断されました。
その後、遺産分割調停を申し立てて、株式の全部が父の遺産であるという前提で法定相続分に従って相続をする調停が成立しました。事務所からのコメント
意思能力について医療記録を元に丁寧に立証できたのがポイントです。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺留分
遺留分で隠し財産を発見した事例
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(法定相続人。依頼者)
子B(法定相続人。相手方)
<概要>
訴訟の中で、相手方Bが母死亡8年前に母名義の預金3,0…続きを見る-
遺留分
遺留分で隠し財産を発見した事例
相談前
<登場人物>
母(被相続人)
子A(法定相続人。依頼者)
子B(法定相続人。相手方)
<概要>
訴訟の中で、相手方Bが母死亡8年前に母名義の預金3,000万円を解約してB名義の口座に送金していたことを発見しました。
<詳細>
母の死亡後、母が公正証書遺言を作っていることが判明しました。
その公正証書遺言の内容は、母の遺産はすべて相手方Bに相続させるというものでした。
その公正証書遺言が作られたときは依頼者Aさんも母と会ったり話をしていたりしたので、さすがに意思能力がないとまではいえないと判断し、遺言無効ではなく遺留分侵害額請求をBに対して行う方針にしました。相談後
母の銀行と証券の口座の取引履歴は一通り取得して民事裁判を提起しました。
事前に判明していた母の口座はX銀行とY銀行の2行だけでした(支店名は省略します)。
そのX銀行の取引履歴を見ると、母が死亡する約8年前に約1,000万円の出金がありました。
Bさんと母とは家が近所で、母のことで何かあったら基本的にはBさんが対応していましたし、母名義のX銀行の口座から母の生活費のためにBさんが出金もしていました。
とはいえ、1,000万円の出金は多額ですので、この出金はなんなのかとBさんに尋ねたら、Bさんは、「自分が出金したものではあるが、母が施設で暮らすために必要な費用なのでその費用として母のために使った」などと言っていました。
さすがに金額が多くて信用できなかったので、当事務所が裁判所を通じてX銀行に対し、取引履歴だけではなく、約1,000万円の出金時の資料の開示を求めたところ、その資料の中に1,000万円をZ銀行に送金したとの記載がありました。母の口座はX銀行とY銀行だけだと思っていたので驚きました。
当事務所は、裁判をする前に、おそらく母はZ銀行にも口座があるであろうとあたりを付けていたので、裁判前にZ銀行の口座の取引履歴を入手しようとしたところ、Z銀行からは母名義の口座が存在しないと回答があったのです。そのため、当事務所では、Z銀行に母名義の口座はないと思っていたのですが、実は口座があったのです。
なぜ当初の調査で発覚できなかったのかをご説明いたします。
一般的な銀行の処理として、Xの窓口で出金してその場でZ銀行に送金した場合、X銀行の通帳や取引履歴には単に出金があったことしか記載されずにZ銀行に送金したことは記載されません。
そのため、単にX銀行の通帳や取引履歴を見ただけではZ銀行の情報は出て来ません。
しかし、出金の際の請求書や送金伝票の開示を求めると、送金伝票や送金時の情報が開示されることがあります。
そして、出金伝票や出金の情報に関する内部データは、裁判所等において法的手続きで取得を試みないと開示しない銀行が多いのです。
もともと「Z銀行」の口座はないと思っていたのですが、存在することが判明しましたので、「Z銀行」の取引履歴を通常の方法ではなく裁判所を通じた文書送付嘱託で取り寄せると、取引履歴が開示されました。
取引履歴を見ると、Z銀行の口座には1,000万円以外に合計で約3,000万円の預金があり、1,000万円の送金直後に全額出金して口座が解約されていました。
解約して年月が経った口座については、通常の取引履歴の取り寄せにはZ銀行が対応していなかったようで、当初は存在しないとの回答だったようです。
そして、その3,000万円は最終的には母の生前にB名義の口座に移されており、しかも、公正証書遺言によって母の遺産を全て相続したはずのBが行った相続税申告には、その3,000万円は遺産目録に入っていませんでした。
Bさんは、母名義の預金口座から3,000万円を引き出して横領していたのです。
このようにして母の遺産額を適正に把握できたので、遺留分の割合に従った金額を取得する裁判上の和解が成立しました。相手方は、相続税について修正申告をする羽目になりました。事務所からのコメント
裁判所を通じて得る資料には通常では入手できない様々な情報があるので、そうした情報を見落とさずに拾っていくことが重要です。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続放棄
長く交流がなかった父親の死亡に伴う相続放棄
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(相続人)
<概要>
父とAさんは、長らく交流がありませんでしたが、ある日、警察からAさんに連絡があり父が変死したとの…続きを見る-
相続放棄
長く交流がなかった父親の死亡に伴う相続放棄
相談前
<登場人物>
父(被相続人)
子A(相続人)
<概要>
父とAさんは、長らく交流がありませんでしたが、ある日、警察からAさんに連絡があり父が変死したとのことでした(事故死でした)。
Aさんは父と交流がなかったので父の生活状況は知りませんでしたが、遺品を整理しているとどうやら消費者金融からの多額の借金がありそうでした。
そこで、相続放棄をするためにご依頼がありました。相談後
相続相続放棄は、相続があることを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。戸籍謄本等の必要書類を揃えて、期限内に申立て無事に相続放棄が認められました。
事務所からのコメント
相続放棄はご自身でも申立てが可能ですが戸籍謄本などの書類をそろえるのが大変ですし、場合によっては債権者からの問い合わせに対応する必要がある場合もございます。手続きがご面倒だと感じられたら弁護士へのご依頼をお勧めいたします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ


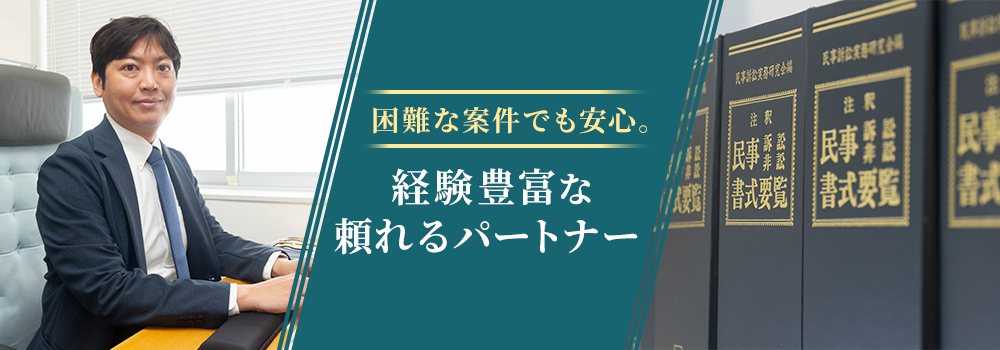











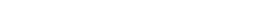
事務所からのコメント
母の口座の取引履歴から的確にBさんが出金したと思われる使途不明金を探し出し、遺言書との合わせ技で当方の負担を少なく抑えることが出来ました。