-
トップ
-
選ばれる理由
-
料金
-
解決事例12
-
お客様の声口コミ12
選ばれる理由
-


相談・支援実績500件以上、丁寧かつ迅速に相続のお悩みを解決いたします
司法書士法人 あい総合事務所では、「丁寧かつ迅速にお客様のお悩みを解決する」をモットーに、これまで500件以上の相続のご相談・ご支援を行ってきました。 広島事務…
続きを見る> -


「公正証書遺言」の作成など、生前対策のサポート実績も豊富です
当事務所では、遺言書の作成や成年後見・死後事務委任契約などの生前対策にも力を入れております。なるべく費用負担が大きくならないよう最適なご提案ができるのも、当事務…
続きを見る> -


地域の専門家と連携し、相続税や土地・家屋の調査などにも対応
相続問題の解決には、司法書士以外にも、税理士や土地家屋調査士などの専門職の力が必要になるケースがあります。例えば、相続税なら税理士、相続した不動産の調査・測量な…
続きを見る> -


「法律家っぽくない」話しやすい雰囲気の司法書士事務所です
「司法書士」と聞くと堅いイメージを持たれている方が多いですが、司法書士法人 あい総合事務所では、ご相談者様やご依頼者様が話しやすい雰囲気づくりを心がけております…
続きを見る> -


家庭裁判所前駅から徒歩1分。出張・土日祝・時間外のご相談も承っております
司法書士法人 あい総合事務所は、広島市中区に「広島事務所」、三次市に「三次事務所」を構えております。広島事務所は、家庭裁判所前駅(広電白島線)から徒歩1分の場所…
続きを見る>

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
解決事例
-
相続手続き
不動産の相続方法をどうしたら良いかわからない
相談前
相続人が複数人おり、価値の高い不動産の相続方法をどのようにしたら良いかわからず、相続手続きが滞っておりました。
…続きを見る -
遺産分割
相続人に未成年がいるケース
相談前
相続人が配偶者(ご依頼人)と未成年のお子供様2名の計3名の手続きでした。相続財産はご依頼人が全て相続することを希望しており、未成年者がいる場合どうしたらよいかお…続きを見る
-
相続手続き
戸籍記載内容が複雑でわからない
相談前
被相続人の配偶者(ご依頼人)より、ご自分で相続手続きを行うため戸籍を取得したが、被相続人が養子縁組を繰り返しており誰が相続人になるのかがわからないとご相談をいた…続きを見る
司法書士法人 あい総合事務所の事務所案内
司法書士法人 あい総合事務所は、広島市中区に「広島事務所」、三次市に「三次事務所」を構える司法書士事務所です。 話しやすいアットホームな雰囲気づくりを心がけ、相続問題に幅広く対応しております。 “気軽に相談できる身近な法律家”として、ご相談者様やご依頼者様がしっかりご納得した上で手続きが進められるよう努めてまいります。
基本情報・地図
| 事務所名 | 司法書士法人 あい総合事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒730-0004 広島県広島市中区東白島町20-8 川端ビル3F-C |
| アクセス | 広電白島線「家庭裁判所前駅」より徒歩約1分 同線「白島駅」より徒歩約3分 同線「縮景園前駅」より徒歩約4分 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~18:00 ※土日祝日も面談・相談対応いたします(要予約) |
| 対応地域 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県 |
| ホームページ | https://ai-sougou.com/ |
代表紹介

原田 明宏
司法書士
- 代表からの一言
- これまで「丁寧かつ迅速にお客様のお悩みを解決する」をモットーに、さまざまなご相談をお受けしてまいりました。
専門家としての経験と知識を活かした丁寧なヒアリングと、お一人おひとりへの最適なご提案を心がけております。
広島市中区の“皆様のそばにいる身近な法律家”としてスタッフ一同精進しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
- 経歴
- 2014年 司法書士試験 合格
2015年 広島司法書士会 所属
2015年4月 あい司法書士事務所 開設
2017年4月 法人化し、司法書士法人あい総合事務所へ名称変更
2017年4月 三次事務所 開設
スタッフ紹介

木川 恭隆
司法書士

前田 憲一郎

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
選ばれる理由
相談・支援実績500件以上、丁寧かつ迅速に相続のお悩みを解決いたします

司法書士法人 あい総合事務所では、「丁寧かつ迅速にお客様のお悩みを解決する」をモットーに、これまで500件以上の相続のご相談・ご支援を行ってきました。
広島事務所は司法書士3名体制、三次事務所は司法書士1名体制で運営しています。広島市内や三次市内を中心に、毎月15件前後の新規ご依頼を承っております。土地や建物などの不動産を相続した場合は、その不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」が必要です。令和6年4月より相続登記の申請が義務化されますが、当事務所でも相続登記に関するご相談が最も多いです。
司法書士は“相続登記の専門家”とも言われており、複雑な登記申請を代理し、着実に手続きを進めてまいります。相続登記のほかにも、相続した銀行口座の解約や生命保険金のご請求・相続放棄の書類申請など、相続全般に関するサポートが可能です。
「相続したものの、どのような手続きを踏めばいいかわからない」など、相続問題でお悩みならまずは一度ご相談ください。
「公正証書遺言」の作成など、生前対策のサポート実績も豊富です

当事務所では、遺言書の作成や成年後見・死後事務委任契約などの生前対策にも力を入れております。なるべく費用負担が大きくならないよう最適なご提案ができるのも、当事務所の特長です。
生前対策には遺言書の作成のご相談がもっとも多いですが、当事務所では公証人が作成する「公正証書遺言」のほか、ご自身で遺言書を作成される方へのアドバイスも行っております。ご本人様のご希望を実現できるよう最適なご提案をさせていただきます。
地域の専門家と連携し、相続税や土地・家屋の調査などにも対応
相続問題の解決には、司法書士以外にも、税理士や土地家屋調査士などの専門職の力が必要になるケースがあります。例えば、相続税なら税理士、相続した不動産の調査・測量なら土地家屋調査士に任せる方法が一般的です。
このように、相続問題の解決では、専門職にはそれぞれ得意な分野があるのです。司法書士法人 あい総合事務所の代表司法書士は、2015年4月の開業以来、税理士・土地家屋調査士・弁護士などの地域の専門職と信頼関係を構築してまいりました。司法書士事務所として、どのような問題にも対応できる連携体制をつくっておりますので、相続問題はお任せください。

「法律家っぽくない」話しやすい雰囲気の司法書士事務所です

「司法書士」と聞くと堅いイメージを持たれている方が多いですが、司法書士法人 あい総合事務所では、ご相談者様やご依頼者様が話しやすい雰囲気づくりを心がけております。
遺産や相続の手続きは複雑で、戸惑う方がほとんどです。気持ちに余裕がないと、手続きがより大変に感じられるものです。
そのため当事務所は“皆様のそばにいる身近な法律家”を目指しており、ご相談者様やご依頼者様がご理解・ご納得いくまで話し合えるよう努めております。

初回のご相談は、無料で対応いたしております。相談時間に制限はございませんので、ご理解・ご納得いくまでしっかり話し合うことが可能です。
正確なお見積りをご提示いたします。ご予算を十分確認していただいた上でサービスのご利用を検討できますので、どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士で対応が難しい問題につきましては、弁護士や税理士などご相談内容に適した専門職をご紹介しております。そのため基本的にどのような案件でも承りますので、ぜひご相談ください。
家庭裁判所前駅から徒歩1分。出張・土日祝・時間外のご相談も承っております
司法書士法人 あい総合事務所は、広島市中区に「広島事務所」、三次市に「三次事務所」を構えております。広島事務所は、家庭裁判所前駅(広電白島線)から徒歩1分の場所にあります。また付近にはコインパーキングが点在しており、電車やお車でお越しいただけます。
三次事務所は、三次駅(JR芸備線)から徒歩10分の場所にあり、事務所前には専用駐車場を設けております。また広島事務所では、事務所にお越しいただくことが難しい方のために出張相談も行っております。ご自宅や喫茶店などにお伺いし、事務所と同じようにご相談・ご支援に対応させていただきます。
さらにご予約いただければ土日祝や時間外のご相談も承っておりますので、お仕事やご家庭の事情でお忙しい方も、まずは一度ご相談ください。


-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
対応業務・料金表
相続人調査サポート
サービスの概要
◆サポート内容
・戸籍収集
・相続関係説明図
料金
22,000円~
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴致します。
相続登記ライトプラン
サービスの概要
◆サポート内容
・収集した戸籍のチェック業務
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得
料金
55,000円~
相続登記お任せプラン
サービスの概要
ライトプランの内容+被相続人の出生から死亡までの戸籍収集+相続人全員分の戸籍収集+相続関係説明図(家系図)作成+評価証明書取得+遺産分割協議書作成(1通)
料金
100,000円~
※1.戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2.相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3.不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4.不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5.当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
◆サポート内容
・戸籍収集
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
料金
44,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
遺言書作成サポート
料金
66,000円~
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
お客様の声
-
相続手続き
真摯に向き合ってくださいました。
困難な問題に対しても真摯に向き合ってくださり、親身になって相談にのっていただきました。そのおかげで問題を解決できました。本当に感謝しています。 …続きを見る
-
相続手続き
真摯に向き合ってくださいました。
困難な問題に対しても真摯に向き合ってくださり、親身になって相談にのっていただきました。そのおかげで問題を解決できました。本当に感謝しています。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
迅速な対応に感謝しています。
質問や疑問に対する迅速な対応と丁寧な説明があり、手続きの過程がわかりやすかったです。コミュニケーションがとても円滑でした。…続きを見る
-
相続手続き
迅速な対応に感謝しています。
質問や疑問に対する迅速な対応と丁寧な説明があり、手続きの過程がわかりやすかったです。コミュニケーションがとても円滑でした。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺言作成
的確なアドバイスが頼りになりました!
遺言書作成の件でお力添えいただき、本当にありがとうございました。初めての手続きで戸惑うことも多かったですが、丁寧なご説明と親身なサポートのおかげで安心して手続き…続きを見る
-
遺言作成
的確なアドバイスが頼りになりました!
遺言書作成の件でお力添えいただき、本当にありがとうございました。初めての手続きで戸惑うことも多かったですが、丁寧なご説明と親身なサポートのおかげで安心して手続きを進めることができました。的確なアドバイスと専門知識には本当に頼りになりました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
不動産の相続手続きが方法がわからず依頼しました。
不動産相続で抵当権が設定されており、法的な問題について理解がなくどうしたら良いか分からず困っている中、不明点を分かりやすい説明をいただき、無事に手続きを完了する…続きを見る
-
相続手続き
不動産の相続手続きが方法がわからず依頼しました。
不動産相続で抵当権が設定されており、法的な問題について理解がなくどうしたら良いか分からず困っている中、不明点を分かりやすい説明をいただき、無事に手続きを完了することが出来ました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
手続きを急いでいたので、迅速に対応いただき助かりました。
忙しく相続人と財産の振り分けをどうするかの話し合いをなかなか取れず、決まった日程迄に手続きを頂かない状況で素早い対応と丁寧な説明のおかげで手続きがスムーズに進み…続きを見る
-
相続手続き
手続きを急いでいたので、迅速に対応いただき助かりました。
忙しく相続人と財産の振り分けをどうするかの話し合いをなかなか取れず、決まった日程迄に手続きを頂かない状況で素早い対応と丁寧な説明のおかげで手続きがスムーズに進み、助かりました。
事務所からのコメント
ご相談いただきありがとうございます。お客様の個別の状況やニーズを理解し、それに基づいた最善の解決策を提供することを心がけています。信頼を築きながら、共に問題を解決できることがうれしく思っております。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
不動産、銀行、保険等手続きする量が多くとても手が回りませんでした。
相続手続きが複雑でストレスが溜まっていましたが、司法書士の的確なアドバイスと丁寧なサポートで、負担が軽減されました。感謝しています。 …続きを見る
-
相続手続き
不動産、銀行、保険等手続きする量が多くとても手が回りませんでした。
相続手続きが複雑でストレスが溜まっていましたが、司法書士の的確なアドバイスと丁寧なサポートで、負担が軽減されました。感謝しています。
事務所からのコメント
お選びいただきありがとうございます。弊社は、皆様の法的な問題や手続きをスムーズに進めるお手伝いができることを嬉しく思っています。何かお困りの点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続登記
複雑な状況で頭を抱えておりましたが、親切に対応いただき助かりました。
父親の相続手続きを進めておりましたが、不動産の手続きが3世代前から手続きされていないことが発覚しどうしたら良いかわからず相談しました。相続権がある人を整理してい…続きを見る
-
相続登記
複雑な状況で頭を抱えておりましたが、親切に対応いただき助かりました。
父親の相続手続きを進めておりましたが、不動産の手続きが3世代前から手続きされていないことが発覚しどうしたら良いかわからず相談しました。相続権がある人を整理していただき、全員と連絡することができました。協議内容が決まったので、必要な書類や手続きも全部対応してくださり相続を終えることが出来ました。一時はどうなるか冷や冷やしましたが相談して本当に良かったです。
事務所からのコメント
ご相談をいただきありがとうございます。無事に手続きが完了でき幸いです。不動産の相続は長年放置されているケースがございます。この場合手続きが煩雑になることがございます。お悩みの際は是非ご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
専門知識の豊富さに助けていただきました。
亡くなった母親がいろいろな資産運用をしていたため、相続手続きを何からしたらよいかわからず困っておりました。あい総合事務所に相談したところ、非常に専門的で、様々な…続きを見る
-
相続手続き
専門知識の豊富さに助けていただきました。
亡くなった母親がいろいろな資産運用をしていたため、相続手続きを何からしたらよいかわからず困っておりました。あい総合事務所に相談したところ、非常に専門的で、様々な法的手続きについての深い知識をお持ちで的確なアドバイスをいただき、安心して進めることができました。
事務所からのコメント
無事に手続きが完了して良かったです。最近は様々な方法で資産運用されている方が増えてきております。運用内容によっては他の専門家と連携して手続きを進める必要がございます。お困りの際は是非ともご相談ください。手続きが円滑にできるよう全力でサポートいたします。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
親切な対応に本当に助けられました
母が亡くなってから役所や保険会社等からたくさんの書類が届き、普段見慣れていないものがどんどん増えていき何から手を付けたらよいかわからなく困っておりました。ほぼ丸…続きを見る
-
相続手続き
親切な対応に本当に助けられました
母が亡くなってから役所や保険会社等からたくさんの書類が届き、普段見慣れていないものがどんどん増えていき何から手を付けたらよいかわからなく困っておりました。ほぼ丸投げ状態でも快く引き受けてくださり、司法書士で対応できない分は他の専門家をご紹介くださり、スムーズに手続きが進みました。ありがとうございます。
事務所からのコメント
役所や保険関係の書類等、相続手続きは普段見慣れない書類や手続きが多くございます。お困りの際は気軽に専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
相談しやすい方で良かったです
相続手続で不動産があったので司法書士を探してました。勝手なイメージで士業は敷居が高く、堅苦しい方が多いと思っておりましたので、なかなか依頼する事務所を決められず…続きを見る
-
相続手続き
相談しやすい方で良かったです
相続手続で不動産があったので司法書士を探してました。勝手なイメージで士業は敷居が高く、堅苦しい方が多いと思っておりましたので、なかなか依頼する事務所を決められずにいました。ホームページを見て恐る恐る電話したところ、物腰柔らかく話しやすかったので相談しました。面談時も司法書士の先生方もイメージとは違い、緊張することなく話をすることが出来ました。手続きもスムーズに対応いただき感謝でいっぱいです。
事務所からのコメント
数ある事務所の中から弊社にお引き合い頂き誠にありがとうございます。法律家も個性豊かな方がたくさんいらっしゃいますので、怖がらず気軽にご相談いただければと思います。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続放棄
相続放棄を決意することが出来ました。
夫が亡くなり財産を確認したところ、資産を上回る負債があることが分かりました。当初は借りたものは返さないといけないと思い相続することを考えましたが、負債額が大きか…続きを見る
-
相続放棄
相続放棄を決意することが出来ました。
夫が亡くなり財産を確認したところ、資産を上回る負債があることが分かりました。当初は借りたものは返さないといけないと思い相続することを考えましたが、負債額が大きかったので相談しました。
相続した場合と放棄した場合の流れを確認し、相続放棄をすることは悪いことではないと分かったので手続きをお願いし、放棄することが出来ました。放棄出来たおかげで気持ちが軽くなりました。事務所からのコメント
この度はお引き合いをいただき誠にありがとうございます。相続放棄することを「悪いこと」とお考えの方がいらっしゃいますが、そんなことはございません。相続放棄も選択肢の一つです。今後の生活のことも考え、ご家族・専門家と話し合い選択いただければと思います。
相続放棄には申告する期限がございますので、迷わず専門家にご相談下さい。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
成年後見
母の資産を整理いただき、生活を安定させることが出来ました。
母の世話をしておりましたが、銀行などのお金に関する諸手続きが出来ず施設利用料の滞納させてしまったり、役所の諸手続きも内容がわからず滞っており相談をしました。先生…続きを見る
-
成年後見
母の資産を整理いただき、生活を安定させることが出来ました。
母の世話をしておりましたが、銀行などのお金に関する諸手続きが出来ず施設利用料の滞納させてしまったり、役所の諸手続きも内容がわからず滞っており相談をしました。先生より成年後見人制度を紹介いただき、あい総合事務所に後見人として就任頂きました。就任後資産の整理、社会保険・税務手続きを対応いただき、施設の滞納金精算も出来一安心しました。
事務所からのコメント
ご相談いただきありがとうございます。昨今個人の権利保護の重視からご本人以外は手続きができないことが多々ございます。ご本人が意思表示できれば問題ございませんが、意思能力が低下していると後見人等の申立てが必要です。後見人等はご親族が就任することもできます。どうすることがご本人のためになるか専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ
解決事例
-
相続手続き
不動産の相続方法をどうしたら良いかわからない
相談前
相続人が複数人おり、価値の高い不動産の相続方法をどのようにしたら良いかわからず、相続手続きが滞っておりました。
…続きを見る-
相続手続き
不動産の相続方法をどうしたら良いかわからない
相談前
相続人が複数人おり、価値の高い不動産の相続方法をどのようにしたら良いかわからず、相続手続きが滞っておりました。
相談後
不動産の相続方法として、複数の相続人の共有名義にして相続する「共有分割」、相続人の1人が相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う「代償分割」、売却現金化してから分割する「換価分割」の3パターンを提案し、相続人の方のライフスタイルに合った物を選択し相続手続きが無事に完了しました。
事務所からのコメント
所在地により大きく変動しますが、不動産は相続財産全体の半分以上を占めることもございます。不動産相続の方法として「共有分割」「代償分割」「換価分割」がございます。それぞれメリット・デメリットございますので、相続人の今後のライフプランを視野に入れてどれが良い方法なのか専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺産分割
相続人に未成年がいるケース
相談前
相続人が配偶者(ご依頼人)と未成年のお子供様2名の計3名の手続きでした。相続財産はご依頼人が全て相続することを希望しており、未成年者がいる場合どうしたらよいかお…続きを見る
-
遺産分割
相続人に未成年がいるケース
相談前
相続人が配偶者(ご依頼人)と未成年のお子供様2名の計3名の手続きでした。相続財産はご依頼人が全て相続することを希望しており、未成年者がいる場合どうしたらよいかお困りで弊社にご相談をいただきました。
相談後
未成年者に対し「特別代理人」選任申立を家庭裁判所に行いました。選任後、ご依頼人と特別代理人で協議いただき、ご依頼人のご希望通りで協議書内容が決まり手続きを完了することが出来ました。
事務所からのコメント
遺産分割の協議を行うときに未成年者がいる場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立が必要な場合があります。相続手続は法定相続に拘らず相続人皆様で決められた内容で行うのが一番だと思いますが、未成年等の意思能力が未成熟、又は、低下している方々の権利保護をしっかりと検討する必要もございます。
今回のケースでは、弊社が作成した上申書で協議内容の妥当性を主張し、家庭裁判所に許可を求め無事に許可を得ることが出来ました。
許可は必ず下りるとは限りませんので、お悩みの方は専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
戸籍記載内容が複雑でわからない
相談前
被相続人の配偶者(ご依頼人)より、ご自分で相続手続きを行うため戸籍を取得したが、被相続人が養子縁組を繰り返しており誰が相続人になるのかがわからないとご相談をいた…続きを見る
-
相続手続き
戸籍記載内容が複雑でわからない
相談前
被相続人の配偶者(ご依頼人)より、ご自分で相続手続きを行うため戸籍を取得したが、被相続人が養子縁組を繰り返しており誰が相続人になるのかがわからないとご相談をいただきました。
相談後
戸籍を拝見したところ被相続人が養子・養父の手続きを複数回行っておりました。不足している戸籍を集め、養子縁組を解除していない縁組を確認し、相続人を整理しました。無事相続人と連絡を取ることが出来遺産分割協議を進めることが出来ました。
事務所からのコメント
稀なケースですが、養子縁組を多数回行っている方がいらっしゃいます。相続人を一人でも見落としてしまうと、折角まとまった遺産分割の協議が一からやり直しになることもございます。戸籍枚数が多くなるようでしたら専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
相続人の行方が分からない事例
相談前
相続人のA様より、お父様が亡くなられ相続手続きを行いたいが、弟様と連絡が取れずどうしたらよいかわからずご相談に来られました。
…続きを見る-
相続手続き
相続人の行方が分からない事例
相談前
相続人のA様より、お父様が亡くなられ相続手続きを行いたいが、弟様と連絡が取れずどうしたらよいかわからずご相談に来られました。
相談後
まずは相続人がA様と弟様のお二人なのか確認しました。その後、弟様の住民票上の住所に手紙を送付しましたが、「宛名不明」で戻ってきました。
A様に連絡が取れてた時期と取れなくなった経緯を伺い、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立てを行いました。弊社が管理人に就任でき、家庭裁判所に協議書案の許可をいただき相続手続きを完了することが出来ました。
事務所からのコメント
相続人と連絡が取れない、または取りにくいというケースがございます。今回の場合は不在者財産管理人に就任しましたが、裁判所の調査で住所が確認できるケースもございます。相続人と連絡のお困りでしたら専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
証券の口座を特別口座でお持ちだった方の事例
相談前
被相続人が持っている株の郵便が届くが、どこの証券会社で持っているのかわからないとご相談をいただきました。
…続きを見る-
相続手続き
証券の口座を特別口座でお持ちだった方の事例
相談前
被相続人が持っている株の郵便が届くが、どこの証券会社で持っているのかわからないとご相談をいただきました。
相談後
郵便物を拝見すると株主名簿管理人から送付されておりました。確認すると特別口座で株式を保有していることが確認できました。ご依頼人に証券会社を通しての保有ではなく株主名簿管理人が管理しているため、相続手続きに通常よりもかなりお時間をいただくことをご了解いただき、相続手続きを完了しました。
事務所からのコメント
株券電子化以前に株式のお取引をされていた方で証券会社を通さずに保有を継続されている方がおられます。その場合、保有している株式数によって手続きが異なり、さらに1か月以上のお時間がかかります。株式の保有方法は様々なパターンがございますので、お困りの方は専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続放棄
被相続人が死亡してから3ケ月を経過した時の相続放棄
相談前
役所から亡くなった夫には生活保護過払い分の返還金があったため、その支払いをしてほしいと説明されました。役所から説明された時には既に死亡から3か月を超えていたが、…続きを見る
-
相続放棄
被相続人が死亡してから3ケ月を経過した時の相続放棄
相談前
役所から亡くなった夫には生活保護過払い分の返還金があったため、その支払いをしてほしいと説明されました。役所から説明された時には既に死亡から3か月を超えていたが、相続放棄ができるかという相談でした。
相談後
当時の事情を細かく確認しました。ご依頼人とご主人は長期間音信不通状態で亡くなったことも親戚伝いであったため、ご主人の当時の状況や財産状況を把握できる状態ではありませんでした。
弊社でご主人とご依頼人の生前の関係性、亡くなった後の役所からの連絡の時系列を整理し、役所から説明を受けた日付が自己のために相続の開始があったことを知った時とすることが妥当であるとし、家庭裁判所に相続放棄を申立し無事認められました。事務所からのコメント
民法で相続放棄は原則「自己のために相続開始があったことを知った日」から3ケ月以内にしなければならない旨規定されておりますので、この期間内に手続きを行う必要がございます。
ただ、同時に利害関係人請求によって、家庭裁判所において伸長できる旨も記載されているので、今回のように必要と認められる場合は期限を変更することも可能です。
必ず認められるとは限りませんので、相続開始があったことを知った日から3ケ月を超えてしまったら専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
相続財産に非上場会社の株式が含まれていたときのご相談
相談前
亡くなった方宛にある会社から配当金に関する案内が届いたが、財産整理した時に証券口座は持ってなかったので発送会社を調べると非上場会社であることがわかりました。証券…続きを見る
-
相続手続き
相続財産に非上場会社の株式が含まれていたときのご相談
相談前
亡くなった方宛にある会社から配当金に関する案内が届いたが、財産整理した時に証券口座は持ってなかったので発送会社を調べると非上場会社であることがわかりました。証券会社に相談しても対応ができないと言われたという相談でした。
相談後
会社に連絡し、株式の「公開会社」か「非公開会社」か確認しました。公開会社であったため、株式買い取りいただけるか確認しました。買取可能と回答をいただいたので、必要な書類と手続きを確認し無事売却することが出来ました。
事務所からのコメント
非上場会社の株式売却は会社運用携帯「公開」「非公開」、保有している株式の種類、財源の有無等様々な確認が必要です。
今回はスムーズに売却することが出来ましたが、パターンによっては売却が出来ないケースもございます。さらに、売却後納税が必要になるケースもございますので専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
成年後見
相続人の中に成年後見申立手続きが必要な方がいる
相談前
父親が亡くなり相続手続きをしたいのだが、母親の判断能力が低下しており、このまま相続手続きを進めても良いのかという相談でした。…続きを見る
-
成年後見
相続人の中に成年後見申立手続きが必要な方がいる
相談前
父親が亡くなり相続手続きをしたいのだが、母親の判断能力が低下しており、このまま相続手続きを進めても良いのかという相談でした。
相談後
お母様の判断能力がどのくらいか確認するため、医師に診断書を書いていただきました。「自ら理解し、判断ができない」との診断であったため、ご依頼人とご親族の方に成年後見制度の説明をしました。今回は長男の配偶者が後見人に就任することを希望されましたので、必要な書類を揃え申立てを行いました。無事に成年後見人に就任することができましたので、お父様の相続手続きも完了することが出来ました。
事務所からのコメント
相続人に判断能力が低下されている方がいらっしゃる場合、「保佐」「成年後見」の申立てが必要になります。ご本人の状況によりどの申立になるかが決まります。保佐人や後見人の就任はご親族の方も可能です。ただ、ご本人様が資産運用などをされている場合などもございますので、申立ての前に専門家にご相談いただいたほうが良いと思います。
相続手続もご本人の権利保護の観点から裁判所に上申申立てが必要なケースもございます。相続人に保佐・後見の手続きをされている方がいらっしゃる時も専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続登記
被相続人がお住いの市町村以外にも土地を所有されていたときのご相談。
相談前
ご依頼人より、被相続人(お父様)が住んでいる家以外にも土地を保有しており、いくつか他県もあり確認方法が分からずご相談に来られました。
…続きを見る-
相続登記
被相続人がお住いの市町村以外にも土地を所有されていたときのご相談。
相談前
ご依頼人より、被相続人(お父様)が住んでいる家以外にも土地を保有しており、いくつか他県もあり確認方法が分からずご相談に来られました。
相談後
ご自宅に「権利証」や「登記識別情報」、「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届いていないか確認をいただき、3つの市より「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届いておりましたので、各市に「名寄帳」を請求しました。被相続人名義の不動産を確認しご依頼人にお伝えしました。無事に相続人の皆様で協議を行い手続きが出来ました。
事務所からのコメント
被相続人が相続によりお住いの市町村以外で不動産を所有していることがございます。被相続人の保有不動産を確認する場合、「権利証」や「登記識別情報」を探してください。もし見つからなければ、毎年4~6月頃に市町村役場より送付される。「固定資産税・都市計画税納税通知書」があれば「名寄帳」被相続人名義の不動産を確認することが可能です。
※名寄帳がない市町村もございます。
不動産が複数個所の市町村にある場合、不動産を管轄している法務局が異なる可能性もございます。お困りの際は専門家にご相談ください。"

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続手続き
被相続人の不動産登記住所と最後の住所が繋がらない事例
相談前
相続不動産の登記情報に記載されいている住所と、死亡時の住民票が異なる場合のご相談。
…続きを見る-
相続手続き
被相続人の不動産登記住所と最後の住所が繋がらない事例
相談前
相続不動産の登記情報に記載されいている住所と、死亡時の住民票が異なる場合のご相談。
相談後
住民票除票を取得しましたが、従前住所と登記簿に記載されている住所が一致しなかったため、戸籍の附票を請求しましたが廃棄済みのため取得することが出来ませんでした。弊社で同一性が確認できる資料を準備し証明し、無事に登記手続きを完了しました。
事務所からのコメント
不動産の住所変更登記をしていない場合、取得時と最後の住所が異なることがあり、取得時~最後の住所の変遷を追う必要がございます。
住所確認できる書類は「住民票」か「戸籍附票」がありますが、令和元年6月20日前は保存期間が5年間と短く遡れない場合がございます。
※現在は保存期間が150年になっております。
そうなった場合、被相続人と登記名義人が同じであることを証明できれば手続きができます。お困りの際は専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
遺言作成
相続財産を孫に引き継いでほしいので公正証書遺言書を作成した事例
相談前
ご依頼人より、財産はご子息で話し合って分けてほしいが、ある不動産だけは一人のお孫様に相続させたい、どうやったら財産と人を指定することはできるか教えてほしいとご相…続きを見る
-
遺言作成
相続財産を孫に引き継いでほしいので公正証書遺言書を作成した事例
相談前
ご依頼人より、財産はご子息で話し合って分けてほしいが、ある不動産だけは一人のお孫様に相続させたい、どうやったら財産と人を指定することはできるか教えてほしいとご相談いただきました。
相談後
ご相談をいただき遺言書があることを説明し、公正証書遺言を作成することになりました。件の不動産情報と遺したいお孫様とご依頼人の関係性を確認し、遺言内容を伺い、公正証書遺言が完成しました。
事務所からのコメント
財産に対する思いを伝える方法として「遺言書」がございます。遺言書は自筆・公正証書等様々な種類を作成することが出来ます。今回のケースでは、お孫様は相続人に当たらないため「遺贈」となります。このように相続人以外にも財産を遺すことが可能です。作成にはルールもございますので、作成ご希望の際は専門家にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-
-
相続登記
相続したい不動産に明治時代の抵当権が残っていた事例
相談前
弊社に相続相談をいただき、相続動産の登記情報を確認したところ、名義人がご依頼人のご祖父様で、さらに、明治時代に登記された抵当権が残っていることが確認できました。…続きを見る
-
相続登記
相続したい不動産に明治時代の抵当権が残っていた事例
相談前
弊社に相続相談をいただき、相続動産の登記情報を確認したところ、名義人がご依頼人のご祖父様で、さらに、明治時代に登記された抵当権が残っていることが確認できました。
相談後
お金は個人から借りられてたため、お金を貸された方の相続権をお持ちの方を探しました。3名様見つかり、皆様に手紙で事情を説明し、債権を放棄いただくことが出来、抵当権抹消と相続登記を完了できました。
事務所からのコメント
不動産相続登記がされてなかった際、稀に古い抵当権がそのまま残っていることがございます。今回はスムーズに手続きが出来ましたが、お金を貸した方が「法人」か「個人」、連絡の可否等によって手続きが大きく変わってまいります。2024年4月より相続登記が義務化されますので、本ケースが増えることが予想されます。手続きにはお時間がかかりますので、お早めに司法書士にご相談ください。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- Webで相談予約をする
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
-
Webで相談予約をするココを
タッチ






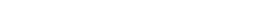
事務所からのコメント
ご相談いただきありがとうございます。弊社は皆様のお困りごとに対し責任を持って丁寧なサポートを提供し、問題解決に全力を尽くしております。お困り、ご不明点などございましたらお気軽にご連絡ください。