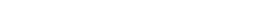-
トップ
-
選ばれる理由
-
料金
-
解決事例5
-
お客様の声口コミ3
選ばれる理由
-


1,000件を超える相続の相談実績
相続に関する業務に専門的に携わるようになって実感するのは、相続は「机上の学問だけでできることではない」ということです。1つひとつのケースに異なる家族関係があり、…
続きを見る> -


高品質なサポートを行うための「適正価格」を設定
税理士報酬については、「安いほうが良い税理士事務所である」とは考えておりません。私どもがめざす高品質なサポートを行うための「適正価格」を設定させていただいており…
続きを見る>

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
解決事例
-
相続税申告
親の借金があったケース
相談前
相談者の父親は財産が8億円、借金が11億円の状態で平成24年3月亡くなられましたが、純財産がマイナスということで相続税の申告は不要で、申告はなされていませんでし…続きを見る
-
遺産分割
居住用の自宅実家の相続
相談前
平成23年9月父が95歳で死亡致しました。もともとは山林だったところを高速道路建設のため山の一部を収用で国に売却した約2億円の金額で長男夫婦との二世帯住宅を約1…続きを見る
-
遺産分割
将来を見据えた家族の遺産分け(二次相続)
相談前
父が平成28年12月97歳で亡くなりました。相続人は高齢の95歳の母と私と姉の3人です。母は父と福岡の自宅で一緒に過ごしておりましたが、一人になり耳も遠くなり、…続きを見る
廣瀬税理士事務所の事務所案内
廣瀬税理士事務所は、平成27年の相続税大改正にいち早く対応。みなさまのニーズにお応えすべく、他事務所にさきがけて「相続専門」税理士事務所としての活動をスタートいたしました。 相続分野は高い専門性が求められ、九州・福岡エリアでは相続専門税理士はまだまだ少ないのが現状です。相続人となる多くの方とほぼ同じ世代であり、豊富な人生経験を積んだ所長・税理士の廣瀬政光をはじめ、相続業務にあかるい精鋭スタッフ陣が親身に的確にサポートいたします。
基本情報・地図
| 事務所名 | 廣瀬税理士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
819-1117 福岡県糸島市前原西1-8-27 第2広瀬ビル3F |
| アクセス | 筑前前原駅から徒歩3分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~18:00(平日夕方・土日は事前にお問い合わせください) |
代表紹介

廣瀬政光
税理士
- 代表からの一言
- 相続専門の税理士事務所として、節税だけではなく「円満」な相続となるようお手伝いしたい。
それが所長をはじめ、私たちスタッフの切実な思いです。
「相続」とは、ご親族の皆様の想いをはらんだたいへんデリケートな問題であり、お悩みの形もそれぞれです。たとえば普段は仲の良いご兄弟であっても相続となると行き違いが生じるケースは数多くございます。
当事務所では、相続に関わるみなさま全員のお気持ちを理解できるよう努め、どなたにも納得いただける解決策を一緒に見つけてまいります。相続のことで何かお悩みのことがありましたら、是非お気軽にご相談ください。
- 所属団体
- 九州北部税理士会 福岡支部
TKC全国会 福岡支部
TaxHouse 福岡天神店
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 副支部長
福岡北ロータリークラブ
企業再建・承継コンサルタント協同組合(CRC) - 経歴
- 昭和52年3月 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
昭和52年4月 株式会社福岡銀行入社
昭和57年1月 株式会社福岡銀行退社
昭和58年11月 等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入社
昭和63年12月 税理士試験合格
平成元年6月 税理士登録(No.66998)
平成8年1月 監査法人トーマツ退職(マネージメント・コンサルティング部)
平成8年7月 デロイトトゥシュ・トーマツグループ提携税理士事務所(現税理士法人トーマツ) 初代所長就任
平成11年10月 日本FP協会 AFP登録
平成13年9月 税理士法人トーマツ福岡事務所の協力事務所として事務所独立
平成16年8月 事務所を中央区天神に移転 - メディア登場実績
- ・福岡市介護保険事業協議会主催セミナー
・日本生命「エンディングノートを活用した相続対策活用法」
・住友生命主催「住友生命保険相互会社主催相続対策セミナー」
・船井総合研究所主催「相続セミナー」
・岩田屋新館の福岡総合行政相談所にて、税金全般の無料相談会
・日本FP協会福岡支部主催「第1部平成28年度税制改正の要点、第2部贈与の最新情報」
・福岡銀行主催「相続・事業承継対策勉強会講師」
・日本FP協会佐賀支部主催「継続教育研修会の講師」

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
選ばれる理由
1,000件を超える相続の相談実績

相続に関する業務に専門的に携わるようになって実感するのは、相続は「机上の学問だけでできることではない」ということです。1つひとつのケースに異なる家族関係があり、個別のお悩みがあり、解決すべき問題が存在するのです。つまり経験こそが学びであり、むしろ経験からしか学べないことがほとんどです。
廣瀬税理士事務所では、これまでに1,000件を超える相続の相談実績を積み重ねてまいりました。これら膨大な経験から得たのは、それぞれのケースに応じた「問題解決力」と「提案力」です。お客様のご負担を最小限にし、どなたにも納得いただけるきめ細かなご提案をいたします。
高品質なサポートを行うための「適正価格」を設定

税理士報酬については、「安いほうが良い税理士事務所である」とは考えておりません。私どもがめざす高品質なサポートを行うための「適正価格」を設定させていただいております。
また、税理士報酬について比較検討される場合は、税理士報酬額に加え、税務署に支払う「相続税の納税額」と合わせてお考えください。相続税申告の経験が少ない税理士に依頼した場合、申告の仕方によっては相続税の納税額が大幅に高くなってしまう可能性があります。
二次相続も含めた提案
たとえばお父様が先に亡くなった場合、配偶者であるお母様への相続を「一次相続」、そのお母様が亡くなった時に起こる2回目の相続を「二次相続」と言います。
通常は一次相続の時はその対応でいっぱいいっぱいになってしまい、二次相続のことまで考える余裕がないものです。しかし相続税対策においては、二次相続のことまで考えることが大切です。たとえ一次相続では節税ができても、二次相続で多額の相続税が課税される場合もあり、トータルでみると失敗してしまった…というケースもあるのです。廣瀬税理士事務所では、このようなことにならないよう、二次相続まで含めた節税対策をご提案いたします。

無料相談のこだわり

相続に対するお客様の不安や疑問を少しでも取り除いて差し上げたい。そんな思いから、当事務所では相続専門税理士による「初回無料相談」を承っております。当事務所の税理士は、ファイナンシャルプランナーの有資格者でもあります。お客様の相続が納得のいく内容で終わるようサポートいたします。
なお、無料相談では無理な勧誘は一切行っておりませんのでどうぞご安心ください。お客様に安心してご依頼いただけるように当事務所では御見積もりとサポート内容を無料相談のその場でご提示し、両者納得の上でご契約させていただきます。ご不明な点があれば、その場で何なりとご質問ください。

無料相談は基本的には60分間でのご予約となります。事情が複雑などの理由で相談が長引きそうな場合は、事前に言っていただければ延長も無料で可能です(※ただし、生前対策に関するご相談で60分を超える場合は料金を頂戴しております。ご了承ください)。
無料相談は、日中はお仕事等でお忙しい方のために平日は20時まで、さらに土日祝のご相談もお受けしています。また、遠方やお体が不自由な方のために出張相談も承っております。お気軽にご相談ください。
税務調査を回避
税務調査は相続税申告の4件に1件が対象になるといわれており、この調査が入り、申告が適正でないと判断されれば追徴課税を支払うことになってしまいます。
そのようなリスクをできる限り回避するため、当事務所では税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」を標準で採用しております。これは申告書の内容が正しいことを税務署に証明するもので、税務調査からお客様を守る「盾」のようなものとお考えください。
書面作成のためには入念な財産チェックが必要です。特に不動産の調査では、役所の航空写真などでは詳細が分からないため、実際に足を運んで私どもの目で確認することが不可欠です。時には山林に入るため、手足に傷をつくってしまったということもありますが、正確な申告のために徹底して実施しております。
ちなみに同制度で適正でない書面を提出した場合、税理士も懲戒処分が課せられるおそれがあります。そのため同制度を活用している税理士事務所は少なく、わずか18.2%(平成29年事務年度国税庁実績評価書より)となっています。


-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
対応業務・料金表
相続税申告サポ―ト
サービスの概要
◆サポート内容:
①相続人の確定
②財産内容の確認と評価
③遺産分割協議用の財産一覧表の作成
④遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
⑤遺産分割協議に応じた相続税額の試算
⑥相続税申告書の作成・提出
料金
500,000円~
・遺産総額は、債務控除前・各種優遇規定前の金額です。
・不動産の現地調査費用 1日/5万円 ※交通費実費
・遺産分割協議書作成料 5万円 ※遺産分割協議書作成は法律行為であるため、外部委託
・遺産の中に非上場株式がある場合は、15万円以上加算となります。
・土地(路線価方式)が複数ある場合は、1利用区分に応じ5万円加算となります。
・名義預金や生前贈与があり、預金調査が複雑になる場合は、10万円~20万円加算となります。
・申告期限まで、2ヶ月を切る方は基本報酬に3割加算、1ヶ月を切る場合は基本報酬に5割加算となります。
・遠隔地の調査を必要とする場合、複雑な土地の評価を必要とする場合、その他特殊事情により作業が膨大となる場合は別途お見積りとなります
料金詳細
| 遺産総額 | 料金 |
|---|---|
| ~500万以下 | 500,000円 |
| 500万円超~3,000万円以下 | 500,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 500,000円 |
| 5,000万円超~7,000万円以下 | 500,000円~700,000円 |
| 7,000万円超~8,000万円以下 | 700,000円 |
| 8,000万円超~9,000万円以下 | 900,000円 |
| 9,000万円超~1億円以下 | 900,000円 |
| 1億円超~1.5億円以下 | 1,000,000円 |
| 1.5億円超~2億円以下 | 1,500,000円 |
| 2億円超~3億円以下 | 2,000,000円 |
| 3億円超 | 2,500,000円~ |

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 0120-028-920
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
お客様の声
-
相続税申告
大変良き出会いであったと嬉しく思っております
懇切丁寧にご指導で職務代行されるに至り大変恐縮に、有難く存じます。スタッフの方の対応も良くスムーズに処理して頂き、助かりました。 大変感謝申し上げます。今後共…続きを見る
-
相続税申告
大変良き出会いであったと嬉しく思っております
懇切丁寧にご指導で職務代行されるに至り大変恐縮に、有難く存じます。スタッフの方の対応も良くスムーズに処理して頂き、助かりました。
大変感謝申し上げます。今後共、何かにつれて又、お願い致し度く存じます。ネットで探した廣瀬先生でしたが、大変良き出会いであったと嬉しく思っております。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続税申告
こちらの話を丁寧に聞いてくださり、スムーズに進めていただいた
税理士の先生に仕事をお願いすることになるとは思ってもいませんでしたがこの度、相続税の納付に関し、手続きをお願いしました。 こちらの話を丁寧に聞いてくださり、ス…続きを見る
-
相続税申告
こちらの話を丁寧に聞いてくださり、スムーズに進めていただいた
税理士の先生に仕事をお願いすることになるとは思ってもいませんでしたがこの度、相続税の納付に関し、手続きをお願いしました。
こちらの話を丁寧に聞いてくださり、スムーズに進めていただいたと思います。
自分ではとても書類をまとめることが出来なかったと思いますので、大変助かりました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続税申告
安心しておまかせする事ができました
母の相続申告の手続きを無事完了していただき、ありがとうございました。相続の申告が必要らしいと分りました時には、妹と二人で本当に心細かったのですが、先生に御相談し…続きを見る
-
相続税申告
安心しておまかせする事ができました
母の相続申告の手続きを無事完了していただき、ありがとうございました。相続の申告が必要らしいと分りました時には、妹と二人で本当に心細かったのですが、先生に御相談してからは、すっかり肩の荷がおりたような(?)、安心しておまかせする事ができました。当初は、相続関係の本を読んだり、公的な無料相談を尋ねたりしたのですが、全く先が見えずに困っておりましたので、本当にありがたかったです。これを前回、父の時にもお世話になり、廣瀬先生のざっくばらんなお人柄と、分り易い説明で円満に終わらせていただき、今回のお願いにつながったような気が致します。どうぞこれからも健康に気をつけられてますますのご活躍を・・・。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
解決事例
-
相続税申告
親の借金があったケース
相談前
相談者の父親は財産が8億円、借金が11億円の状態で平成24年3月亡くなられましたが、純財産がマイナスということで相続税の申告は不要で、申告はなされていませんでし…続きを見る
-
相続税申告
親の借金があったケース
相談前
相談者の父親は財産が8億円、借金が11億円の状態で平成24年3月亡くなられましたが、純財産がマイナスということで相続税の申告は不要で、申告はなされていませんでした。その1年半後の平成25年11月に植物状態だった母親も後を追うように亡くなられました。
相談者は父親が多額の借金があることから、相続すべきか、放棄すべきか、自己破産すべきかなど色々なケースを考えながらもどうしていいか分からない中で、父親の遺志を継いで長男である相談者が3棟のビルを借金ともども相続し、何とか返済しながらもビル経営をやっていかなければならないと考えられておられました。
私どもの事務所には相談者とその妹さんの間で意見がまとまらず、遺産争いに発展しそうな状況下で、いてもたってもいられなくなった銀行が仲介役を買って出て、遺産分割案の作成とお母様の相続税の申告の依頼を受けた訳であります。相談後
財産及び借金の大半は賃貸ビルが3棟あったので、ビルごとの損益状況、財産状況、資金繰り状況などの分析資料を作成し
・全くビルを売却しないで3棟のビルをすべて相続するケース
・1棟のビルを売却し、2棟のビルを相続するケース
・2棟のビルを売却し、1棟のビルを相続するケース
など想定されるケースごとにシミュレーション資料を作成し、数回遺産分割に係る協議を開催。
その結果、もともとの材業の発生した製材所の跡地に建設されたHビルに妹のデザイン事務所と自宅があることから、借金付きのHビルとその他の不動産を妹が相続し、残りの2棟のビルは売却してその売却代金から2棟のビルの借金を返済した残額を2人で均等相続することで決着がつきました。
今回の遺産分割協議のポイントは、ビルごとの損益状況、財産状況、資金繰り状況を分析した資料を作成したことにありました。
この内容が明白なったことで、売却するという選択肢が見えてきて、実際の市場に売却見積もりを出した結果、借金を返済してもなお余剰金が生じるケースが見いだせたことで兄弟間の意見がまとまったということです。
この分析資料を作成していなかったら、恐らく今現在は争族事案に発展しており、我々はその時点で弁護士マターということで手を引かざるを得ない状況となっていたことであります。
母の相続税の申告については、1次相続である父の遺産分割協議が固まっていなかったため、法定相続分で計算した未分割で申告をしていたので、父の遺産分割協議が確定後に修正申告及び更生の請求を行いました。毎年の所得税の確定申告についても長男である相談者が確定申告されていたので、こちらも修正申告及び更正の請求をしたところ、所得税の税務調査がすぐにありましたので長かった業務がこれですべてが終了しました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
居住用の自宅実家の相続
相談前
平成23年9月父が95歳で死亡致しました。もともとは山林だったところを高速道路建設のため山の一部を収用で国に売却した約2億円の金額で長男夫婦との二世帯住宅を約1…続きを見る
-
遺産分割
居住用の自宅実家の相続
相談前
平成23年9月父が95歳で死亡致しました。もともとは山林だったところを高速道路建設のため山の一部を収用で国に売却した約2億円の金額で長男夫婦との二世帯住宅を約1億円使って建てたものの、生前贈与等の対策は何もしておりませんでした。
父が死亡して始めて、長男夫婦と同居している二世帯住宅の敷地及び畑、長男の事務所の敷地、長女夫婦の住宅の敷地が分筆されないままで父名義であったため、土地全体の評価額が1億2,500万円にもなっていました。この敷地をどのように分割したらいいのか、相続税がいくらくらいかかるのか、相続税を節税する方法はあるのか、実家の自宅の相続について今後の二次相続対策も踏まえてご相談に乗ってほしいということでした。
他に二世帯住宅の建物が1,500万円、金融資産が2,000万円、国債が3,000万円、財産合計約2億円の相続財産です。相談後
まず、遺産分割するためには広大な一区画の敷地を利用形態ごとに分筆するところからスタートしました。
そし二世帯住宅の敷地については配偶者が取得して、小規模宅地の評価減を受け、長男事務所敷地は長男が相続し、長女夫婦の自宅敷地は長女が相続すると同時に、現預金について三女とのバランスを図ること及び納税資金もいることから、3人に500万円ずつの現預金を相続することとし、それ以外の財産はすべて配偶者が相続することでできるだけ配偶者の軽減の適用を受けて、1次相続税の負担を少なくするように考えました。
分割案として将来の2次相続やもし自宅敷地を売却した場合に共有にしておくと3,000万円×2人=6,000万円の特別控除が適用できるので、配偶者100%単独所有の場合と長男との共有の場合の分割案を提案しました。
最終の分割案は、二世帯住宅敷地は配偶者が100%の単独所有にする分割案で合意しました。その結果、1次相続税を最小にする分割案が採用されました。
しかし、平成29年に配偶者が相続した現預金が底をつく状況になったことを知らされたため、お母様及び長男家の今後のキャッシュ・フロー表を作成し、今後の生活費を捻出するため、二世帯住宅敷地を8,000万円で売却、その売却代金で畑に3,000万円で二世帯住宅を建て直し、残額の5,000万円で老後資金とすることで生活設計の再構築を行いました。
譲渡所得税の申告を当事務所で行いましたが、当初の取得費の書類がまるまる一式残っていたため、概算経費5%使わないで実額計算と3,000万円特別控除を適用し、大幅に譲渡所得税を減少させることに成功しました。
また、本来ならば自宅を売却する場合、建物を取り壊して更地にして売却するため、新しい自宅が建築されるまでどこかアパートに引っ越す必要があるのですが、自宅を購入した業者が半年間、新築家屋ができるまで居住させてくれたため、引越しをすることなくスムーズに住替えできました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
遺産分割
将来を見据えた家族の遺産分け(二次相続)
相談前
父が平成28年12月97歳で亡くなりました。相続人は高齢の95歳の母と私と姉の3人です。母は父と福岡の自宅で一緒に過ごしておりましたが、一人になり耳も遠くなり、…続きを見る
-
遺産分割
将来を見据えた家族の遺産分け(二次相続)
相談前
父が平成28年12月97歳で亡くなりました。相続人は高齢の95歳の母と私と姉の3人です。母は父と福岡の自宅で一緒に過ごしておりましたが、一人になり耳も遠くなり、認知の具合も進んできたので、相談者である長男が2年くらい前から単身で両親の面倒を見てきました。長女は嫁に行って現在は名古屋市に居住しております。母名義の不動産も加えると5つの不動産があり、母の相続もそう遠くないことから、将来の2次相続も含めて今回の1次相続をどのように分割したらよいかご相談に乗っていただきたい。
相談後
まずは、ポイントとなる5つの不動産についての現状確認からスタート致しました。被相続人の所有する不動産はすべて配偶者との共有不動産であり、配偶者の所有する不動産も含めて全体の不動産の状況を調査する必要がありました。一つ一つの不動産の現状を確認するとほとんどの不動産が相当古く建て替えの時期に来ているものばかりでした。
建て替えして有効利用を図るか、建物を取り壊して更地にして売却するかの判断はやはり専門家の力をお借りする必要がありました。さらに不動産の一つは借地の上に建物を建てて借家として賃貸している借地権付き建物でありとても立退料等の問題もあり、とても売却できる物件とは思えませんでした。
そこで、借地権付き建物の整理を業としているSR社に借地権付き建物の整理の方法と合わせて他の不動産の診断もして頂き、将来の売却可能性や売買予想価額などを見積もってもらい、不動産ごとに整理を致しました。
今回のポイントは今回の相続が1次相続であり、まだ2次相続を発生していない中でお母様が自宅に居住されていることから、所有不動産が相当古くなっていても将来有効利用するのか、更地にして売却するのかの判断について専門家の目からアドバイスを頂いたことで今後の方針が立て易くなったことです。
具体的には、まず将来一番売却できそうなKアパートの土地建物をお姉さんに被相続人の持分を相続してもらい、二次相続時も残りの母の持ち分を相続することでいつでも売却することが出来る状況を確保することでお姉さんの相続分がまず確定させました。
その次は自宅の敷地について、昔からこの自宅敷地で商売をされてきたことから貸店舗がある店舗併用の自宅でした。
そこで、お母さんが亡くなったら、賃貸マンションを建て替えすることが出来る敷地なので、長男である相談者とお母さんが二次相続発生時まではここで生活をして、二次相続が発生したら売却するか、建て替えするかは長男が決めるということで、この自宅の建物及び敷地を長男が相続することになりました。
当然小規模宅地の評価減も二次相続時には適用できるのは言うまでもありません。二次相続が発生していない状況下で、将来を見据えた分割を提案することは非常に困難ではありましたが、
一つ一つ専門家と連携して解決することができ、相続人の方々に納得して頂いた分割案が提示できたことは非常に満足しています。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続税申告
兄弟間で意見が異なるケース
相談前
母が平成25年に亡くなり、その3年後の平成28年に父が死亡したが、今回の2次相続の申告期限が3か月先に迫っているなかで、カナダ在住の次女から四女が申告を依頼して…続きを見る
-
相続税申告
兄弟間で意見が異なるケース
相談前
母が平成25年に亡くなり、その3年後の平成28年に父が死亡したが、今回の2次相続の申告期限が3か月先に迫っているなかで、カナダ在住の次女から四女が申告を依頼している税理士事務所が作成した遺産分割案の精査と一番高いと考えられる遺産分割のポイントになる甲土地の評価をセカンドオピニオンとして依頼された訳であります。
相続人は5人姉妹であり、四女が提案してきた遺産分割案では次女及び三女が支障ありということで難色を示しており、このままだと未分割事案に発展することが予想される案件でありました。相談後
当事務所としては事務所の無料相談日まで1か月近くあったので、海外在住の相談者でありましたが、メールや郵便で資料をできるだけ収集しました。
遺産分割のポイントである不動産については登記簿謄本、公図、ストリートビューによる実物の確認、路線価又は倍率方式での土地の評価、及びポイントになる甲土地の評価の簡易時価算定を行い、1次相続と2次相続の合算の分割案を相続税評価額での分割案と時価評価額での分割案を作成し、特別受益額を考慮した1人当たりの相続分との差額を計算して、レポートとして提案致しました。
1個1個の不動産の評価資料も添付資料として遺産分割案のレポートに添付して、依頼者に送付致しました。やはり、遺産分割は相続税の申告時における相続税評価額で計算すると6,000万円であった甲土地が、将来の売買価額をも考慮した時価で評価したら2倍の1.2億円になったことから大幅に乖離が出たことから、遺産分割は時価で検討するべきであるということが最確認させられた事案であったと思います。
そして、根拠資料をきちんと付けた分析資料と相続税評価額及び特別受益まで考慮した比較資料を作成したことから、その差額が1,000万円近くにもなることが判明致しました。
その結果、一番時価が高い甲土地を相続する四女が提案してきた分割案と異なるその他の自宅や事務所・倉庫、貸家などの田舎の不動産も後の始末(補修や売却などの維持管理)まできちんと行うことを条件として四女がすべて相続し、相続税も支払うことで相続人全員が反対意見もなく、円満に合意に至ったとのことでありました。後日丁重なお礼状が送られてきて、一時はどうなるのか心配していたのですが、スムーズに行き、本当にやって良かったなあとやりがいを感じた仕事となりました。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続手続き
相続分の譲渡が発生したケース
相談前
先月、後妻である甲が90歳で亡くなりました。
小学校の時から一緒に同居していた乙兄弟は相続の手続きに司法書士さんに依頼したところ、乙兄弟は後妻である夫婦の間で…続きを見る-
相続手続き
相続分の譲渡が発生したケース
相談前
先月、後妻である甲が90歳で亡くなりました。
小学校の時から一緒に同居していた乙兄弟は相続の手続きに司法書士さんに依頼したところ、乙兄弟は後妻である夫婦の間で養子縁組していなかったことから法定相続人でないことが判明し、何とかならないかということで弁護士事務所を訪ね、相続分の譲渡ができるということでその課税関係を調査致しました。相談後
民法905条の規定により、相続人は相続放棄をせずに相続する権利(相続分)を他人(他の相続人又は相続人以外の第三者)に譲渡することが出来ることになっております。ここで言う相続分とは個々の財産の共有持分ではなく、積極財産と消極財産の全体に対する分数的割合(法定相続分)であり、相続人としての地位を譲渡するものではありません。資産税での営業譲渡における包括的な持分の譲渡と同じと考えられることから、相続人以外の第三者への譲渡の場合は第三者への包括遺贈が行われた場合と同じ効果があると思われます。
相続分の譲渡については、決まった手続きがあるわけではないので口頭でも構いませんが、より確実に契約したい場合は「相続分譲渡契約書(相続分譲渡証書)」を作成することがベターとなります。
今回の乙兄弟は相続分を無償で譲渡してくれた方が6人、有償譲渡になった方が4人いました。乙兄弟は無償譲渡を受けた相続財産6,000万円×8/20=2,400万円に対しては各々贈与税が課税されることが判明。父親が亡くなった小学生の頃に父の遺産を継母がすべて相続したとのことですが、継母であることは成人した時には戸籍謄本を見れば確認できたはずであり、なぜ養子縁組をしていなかったのかが悔やまれて仕方なかった案件でした。

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!