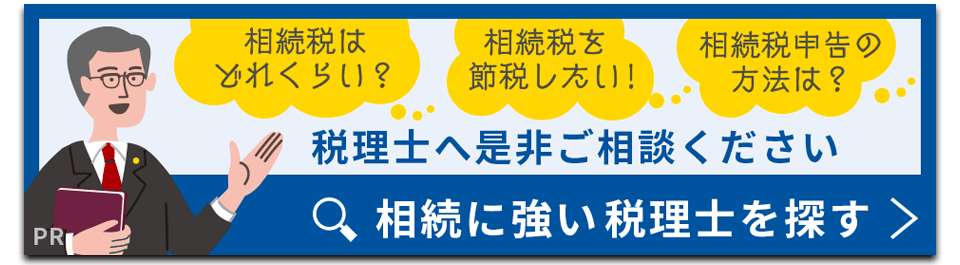相続が発生した場合、相続財産等の金額によっては、相続税が課税されることがあります。
相続税額を計算する際に使用する「税率」は、消費税のように一律ではなく、相続財産等の金額に応じて変化します。
初めて相続に直面するとき、相続税率や計算方法がわからず、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税率をご紹介したうえで、相続税額の計算方法についてシミュレーションを交えながら解説します。
相続税率の確認、および相続税額の計算にお役立てください。
目次
相続税の税率とは
相続税は、文字通り相続が発生したときにかかる税金です。
相続税を算出するには、法定相続分に応じた取得金額に「相続税率」を適用する必要がありますが、相続税率は法定相続分に応じた取得金額によって変化します。
相続税率は10%から55%まであり、法定相続分に応じた取得金額が高くなればなるほど、相続税率も高額になります。これを「超過累進税率」といいます。
相続税率一覧表
相続税率の一覧は下記のとおりです。
なお、平成27年の税制改正により、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以後で税率が異なるので注意しましょう。
平成27年1月1日以後
相続が開始した日(被相続人が死亡した日)が平成27年1月1日以降の場合、下表の相続税率が適用されます。
| 法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁
平成26年12月31日以前
相続が開始した日(被相続人が死亡した日)が平成26年12月31日だった場合、下表の相続税率が適用されます。
| 法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁
【計算例あり】相続税率一覧表の使い方とは
相続税率一覧表を用いた相続税額の計算方法を、シミュレーションを用いてご紹介します。
手順1:課税遺産総額を計算する
まずは、相続税が課税される遺産の総額を計算します。
はじめに相続税の課税対象となる財産の価値を合計します。主な課税対象財産は、以下のとおりです。
・被相続人が死亡時に所有していた財産
・被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産
・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
・生命保険金
・被相続人の死亡によって支給される退職手当金
など
ただし、以下の財産は非課税とされています。
・墓地・墓石、仏壇などの祭祀財産
・生命保険金のうち「500万円×法定相続人」までの部分
・退職手当金のうち「500万円×法定相続人」までの部分
など
被相続人が死亡時に負担していた債務と葬儀費用は、課税対象財産の総額から差し引きます。
上記で計算した課税対象財産の合計額から、「基礎控除」を差し引いて、課税遺産総額を求めます。
基礎控除額は、以下の計算式で算出できます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※法定相続人の数には、相続放棄をした者も含みます。
※法定相続人の数に含める養子の人数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人が上限です。
相続税は、基礎控除額を差し引いた後の課税遺産総額に対してかかります。課税遺産総額が0円以下であれば、相続税はかかりません。
例えば、父、母、子2人の家庭で父が死亡した場合の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円です。
課税対象財産の合計額が1億円の場合、課税遺産総額は1億円-4,800万円=5,200万円となり、この5,200万円に対して相続税が課されます。
これに対して、課税対象財産の合計額が基礎控除額の4,800万円以下である場合には、相続税がかかりません。
手順2:法定相続分に応ずる取得金額を計算する
法定相続分に応じた取得金額とは、課税遺産総額を法定相続分に応じて各相続人に割り当てた金額を意味します。
上記の例では、父が死亡した場合の相続人は母、子2人で、法定相続分は母が1/2、子はそれぞれ1/4ずつとなります。
課税対象財産の合計額を1億円とした場合、課税遺産総額は5,200万円です。これを母と子2人が法定相続分どおりに相続したと仮定して取得金額を計算すると、
母 5,200万円×1/2=2,600万円
子 5,200万円×1/4=1,300万円ずつ
よって、法定相続分に応じた取得金額は、母は2,600万円、子はそれぞれ1,300万円となります。
手順3:相続税の総額を計算する
法定相続分に応じた取得金額に対して、税率表を適用して相続税額を計算します。
母 2,600万円×15%-50万円=340万円
子 1,300万円×15%-50万円=145万円ずつ
相続税額は母340万円、子はそれぞれ145万円となります。
上記で算出した相続税額をすべて合算して、相続税の総額を計算します。
340万円+145万円+145万円=630万円
すなわち、このシミュレーションでの相続税の総額は630万円です。
手順4:各相続人の相続税額を計算する
上記で求めた相続税の総額を、実際の課税対象財産の取得割合に応じて、各相続人に割り当てます。
例えば、実際の遺産分割割合が母3/5、子が1/5ずつだった場合、母と子2人の相続税額は以下のとおり計算されます。
母 630万円×3/5=378万円
子 630万円×1/5=126万円
手順5:各種加算・控除を適用して、最終的な相続税額を計算する
上記で求めた各相続人の相続税額に、各種加算・控除を適用して、実際に納付すべき相続税額を計算します。
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人が遺産等を取得した場合、その人が負担する相続税額は2割加算されます。
また、以下に控除の適用を受けることで、相続税額を軽減できる場合があります。
・配偶者控除
・未成年者控除
・障害者控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
など
相続税率を用いる場合の注意点とは
税率表を用いて相続税を計算する際に、知っておきたいポイントをご紹介します。
課税対象財産の総額が基礎控除以下なら相続税は発生しない
相続税の課税対象財産の総額が基礎控除額以下である場合、相続税額は0円になります。
この場合原則として、相続税を申告する必要もありません。
上記の例では課税対象財産の総額が1億円で、基礎控除額が4,800万円を上回っていたので相続税が発生しました。
しかし、仮に課税対象財産の総額が4,000万円だった場合は、基礎控除額以下なので、相続税は発生しません。
ただし、後述する税額軽減や特例を利用する場合は、相続税が0円であるとしても相続税の申告義務が発生します。
税負担を軽減する効果の高い控除・特例等を活用しましょう
相続税は、控除・特例等を活用することで、その負担を軽減できる場合があります。
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、相続税の節税に大きく役立ちます。
他にも未成年者控除や障害者控除など、相続人の属性に応じて、さまざまな控除を利用することが可能です。
ここでは、特に節税効果の高い配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例について、各概要をご紹介します。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が財産を相続する場合、1億6,000万円までなら相続税がかからない制度です。
1億6,000万円を超えた場合でも、法定相続分以下なら相続税は発生しません。
仮に課税対象財産の総額が5億円の場合、配偶者の法定相続分である2億5,000万円までは相続税がかかりません。
これに対して、課税対象財産の総額が2億円の場合、配偶者が取得した財産のうち相続税が非課税となるのは、1億6,000万円が上限となります。非課税上限を超えた部分については、相続税が課税されます。
配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税が0円でも相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、土地の利用区分に応じて一定の面積まで、課税対象財産である土地の相続税評価額が最大80%減額される制度です。
例えば、被相続人が住んでいた自宅の土地であれば、330平方メートルまで、相続税評価額が80%減額されます。
小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税の課税対象財産額を圧縮できるため、相続税額を大きく軽減できる可能性があります。
なお、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、相続税が0円でも相続税の申告が必要です。
【関連記事】配偶者(夫婦間)の特例についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:夫婦間の相続税は【1.6億円まで0円!?】|配偶者控除の条件を解説
【関連記事】小規模宅地の特例についてもっと知りたい方におすすめ
>コラム:小規模宅地の特例とは?相続税が減額される要件や必要書類を解説
相続税は超過累進税率、相続税は基礎控除以下なら発生しない
相続税は、亡くなった人から財産を取得した人などに対してかかる税金です。
相続税率は一律ではなく、取得財産の金額が高額であればあるほど税率が高くなる超過累進税率が採用されています。
相続税率を把握するには、税率表を確認するのが便利です。相続税の課税対象財産の総額が基礎控除以下なら、相続税はかかりません。
この場合、原則として相続税の申告も不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける場合には、相続税がかからなくても相続税の申告が必要になるので注意しましょう。
この記事の監修者:阿部 由羅
 ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。
ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。