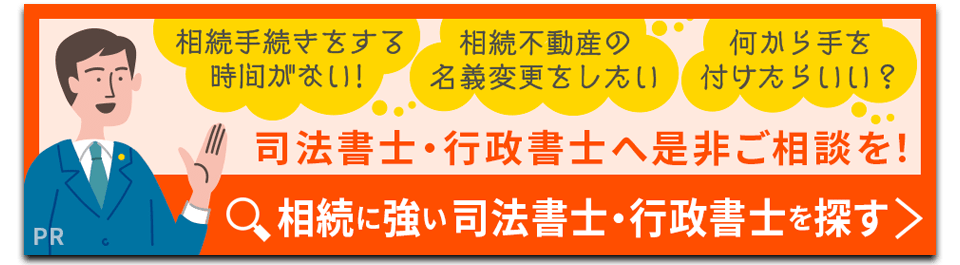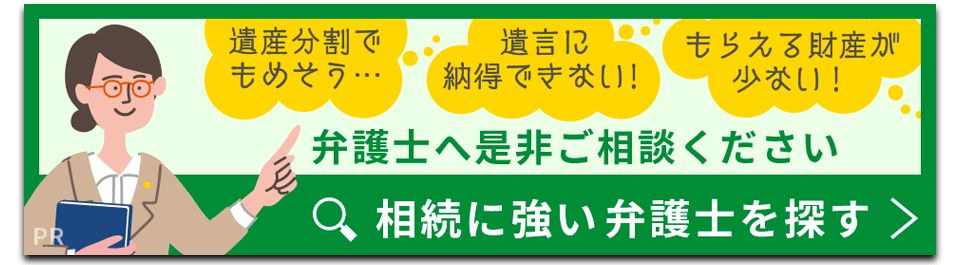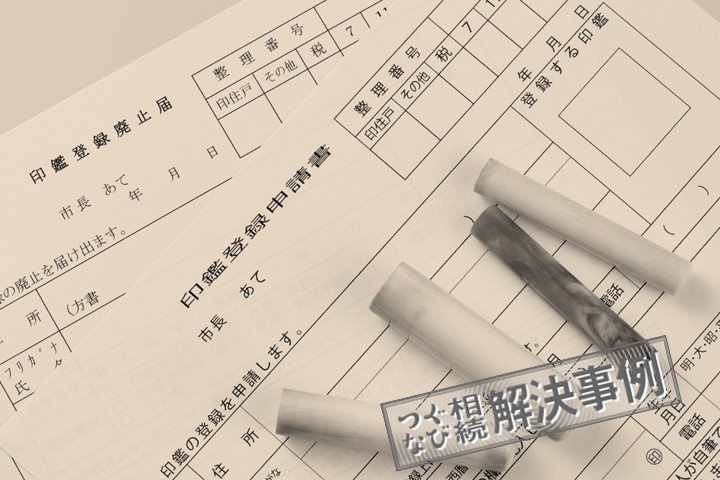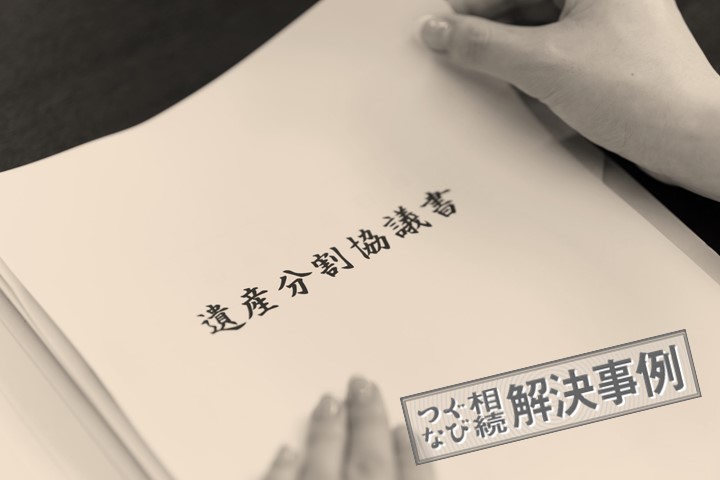借地権とは、地主から土地を借りて使用する権利のことで、建物所有を目的とするものを意味します。
ここでは、借地権を相続した際の注意点や借地権の評価方法について解説します。
目次
借地権とは?
借地権とは、建物を所有することを目的として、地主から土地を借りて使用する権利のことをいいます。
借地権には「普通借地権」と「定期借地権」とがあります。
普通借地権の場合、借主は地主(貸主)に対し契約期間の延長や更新を請求することができ、地主は正当な事由がない限り、その請求を拒むことができません。
また、普通借地権が終了した場合、借主は地主に対して、借地上の建物を時価で買い取ることを請求することができます。
この場合、地主はその買取りを拒否することはできません。
一方、定期借地権の場合は、契約期間の延長や更新が認められません。
定期借地権には、①定期借地権、②事業用定期借地権、③建物譲渡特約付借地権の三つがありますが、
①定期借地権と
②事業用定期借地権については、借主の地主に対する建物買取請求権を認めないとする定めができます。
③建物譲渡特約付借地権は、借主が地主に対して建物を相当の対価で譲渡する旨の定めをすることができます。
このように、普通借地権は借主の権利がより保護されており、逆に「定期借地権」は借主の権利が制限されるため、地主の権利が強くなっているといえます。
借地権も相続財産に含まれる?

借地権も土地家屋の所有権と同様に、相続財産に含まれます。
被相続人が地主から土地を借りて建物を所有していた場合には、建物の所有権のみならず、その土地に関する借地権についても、相続人が相続により取得できます。
借地権を相続するときに覚えておきたいポイントは?
借地権を相続するときに、是非覚えておいてほしいポイントが3つあります。
- 借地権を相続するのに地主の許可は不要
- 借地権の相続に更新料は発生しない
- 相続した借地権は譲渡・売却が可能
以下、その詳細をご説明します。
①借地権を相続するのに地主の許可は不要
相続が発生した場合、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、とされています。
借地権もこの中に含まれるため、相続人は相続開始の時から、当然に、被相続人の借地権を承継することができます。
そのため、借地権を相続することについて地主の承諾は不要、となっております。
地主は、相続人が被相続人から借地権を承継することを、拒否することはできません。
ただし、地主に承諾をもらうことは不要ですが、借主が変更したことは伝える必要がありますので、地主に対して、従前の借主が死亡し自分が借地権を相続により取得したことを連絡するようにして下さい。
その際、従前の借地権に関する契約書に関し、借地権を取得した相続人名義に変更しておくとより良いでしょう。
②借地権の相続に更新料は発生しない
借地権を購入したり、贈与により取得したりする場合は、その前提として地主の承諾が必要です。
借地権が売買や贈与などにより移転するときは、地主の承諾が要件となるのです。
この場合、地主は承諾を与える代わりに承諾料を要求することがあります。
しかし、相続により借地権を取得した場合は、地主の承諾は不要であるため、地主に対して承諾料を支払う必要はありません。
被相続人から相続人へと借主が変わったことによる名義書換料や更新料、といったものも発生しません。
③相続した借地権は譲渡・売却も可能
相続により取得した借地権であっても、通常の借地権と同様に、これを第三者に売却したり、贈与したりすることは可能です。
ただしこの場合には、地主の承諾が必要になります。
相続により取得した借地権を譲渡したい場合には、事前に地主に対してそのことを連絡しておくのがおすすめです。
借地権の評価方法は?
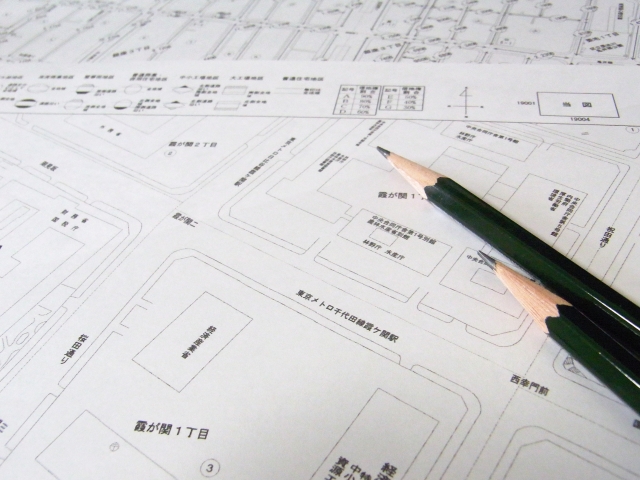
借地権を相続する場合、その評価方法を知っておくと良いでしょう。
普通借地権と定期借地権とでその評価方法が異なりますので、それぞれご説明いたします。
普通借地権の評価方法
普通借地権の場合は、次の計算式でその借地権の評価額を算出できます。
「路線価」は国税庁のホームページで確認できます。
「土地面積」は借地権の契約書や、法務局でその土地の登記事項証明書を取得すれば確認できます。「借地権割合」も国税庁のホームページで確認可能です。
しかし、土地によっては「路線価」が定められていない場合もあります。この場合は、次の計算式で借地権の評価額を算出することになります。
「固定資産税評価額」は、市役所や都税事務所で固定資産評価証明書を取得することで確認できます。
そして「倍率」は、国税庁のホームページに「評価倍率表」というものがありますので、そこで確認します。
「借地権割合」は、前述の通り国税庁のホームページで確認可能です。
以上の2つの方法のどちらかで、普通借地権の評価額が算出できます。
定期借地権の場合
定期借地権の評価方法はかなり複雑です。
国税庁の指針によれば、「定期借地権の価額は、原則として課税時期(相続の場合は被相続人の死亡日)において、借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額により評価する。
ただし、定期借地権の設定時と課税時とで、借地権者に帰属する経済的利益に変化がないような場合等、課税上弊害が無い場合に限り、定期借地権の目的となっている土地価額(自用地価額)に、一定の算式により計算した数値を乗じて計算する」としています。
上記前段の「原則的な評価方法」を求めるには、不動産鑑定士による鑑定評価を依頼しなければなりません。
よって、通常は上記後段の「ただし書きによる評価方法」で算出することになります。これによる場合は、以下の計算式を用います。
定期借地権の評価額 = 土地の価格(※)×(ア÷イ)×(ウ÷エ)
※土地の価格は、「路線価×土地面積」または「固定資産税評価額×倍率」で求めます。
ア:定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額
イ:定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価額
ウ:課税時期におけるその定期借地権等の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
エ:定期借地権等の設定年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
なお、この計算式を用いることができるのは、あくまでも「課税上弊害が無い場合に限り」とされております。
上記計算式による算出も難しいものですが、そもそも「課税上の弊害」があるかどうかの判断は、専門家でないと困難でしょう。
定期借地権の評価を算出する場合には、税理士等の専門家に相談するのがよいでしょう。
借地権を相続したら管理面をチェック!

借地権を相続した場合、その借地上の建物が古家や空き家であるときには特に注意を要します。
倒壊などで周囲に被害を及ぼした場合、その責任が相続人に及ぶ可能性があるからです。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行されたことにより、空き家をそのままにしていると、行政庁から罰金や取り壊しなどの執行処分を受けてしまうこともあり得ます。
古家や空き家を放置することなくしっかりと管理し、老朽化が進んでいる場合にはメンテナンスを施すなどの対策が必要です。定期的な見回りや業者に委託する等の対策を検討しましょう。
借地権の相続人が複数いる場合は?
借地権付きの建物を複数の相続人で取得することは可能です。
例えば、相続人が3人いる場合、持分3分の1ずつを取得する、といったケースです。
ただし、複数で取得した場合は、その借地権付き建物を売却しようとしたとき、全員で合意しないと売却は難しくなります。
最近は「持分」を買い取るという業者も散見されますが、そもそも借地権付き建物は売却価格が低廉になることが多く、「持分」ではさらに安く買いたたかれてしまう可能性があります。
将来的に売却の可能性がある場合には、相続人の1人が単独で借地権付き建物を取得し、他の相続人はそれと等価の相続財産を取得する、という方法の方が無難かもしれません。
なお、相続財産に借地権付き建物がある場合は、借地権とその借地上の建物は、同一の相続人が取得すべきです。
借地権と借地上の建物が別々の相続人のものになってしまうと、借地権につき「転借」とみなされ、地主の承諾が必要になる可能性が出てくるからです。
借地権付き建物は、その借地権と建物を同じ相続人が取得すべきでしょう。
まとめ
以上、借地権と相続の関係について解説しました。
借地権相続の際にはその評価方法を知っておくのがおすすめとしていますが、定期借地権の評価方法は非常に難しいことから専門家への依頼がベストです。
また、借地権を複数の相続人で相続する際も注意が必要ということに頭に入れておきましょう。
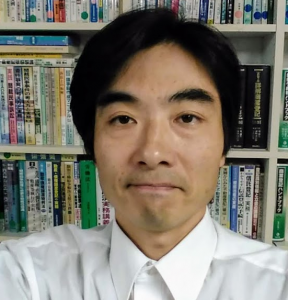 山下晋広
山下晋広司法書士。2000年、司法書士試験合格。2004年、司法書士事務所を開業。所属する東京司法書士会では、調停センター運営委員、広報委員を担当。大学では文学部にて東洋哲学を学び、博物館学芸員を志しつつも、諸事情にて転身。現在、司法書士として研鑽を積む。主な業務は相続手続・不動産登記手続・企業法務・成年後見業務。