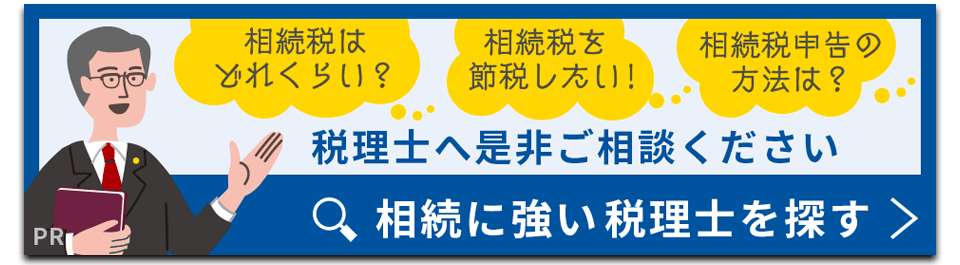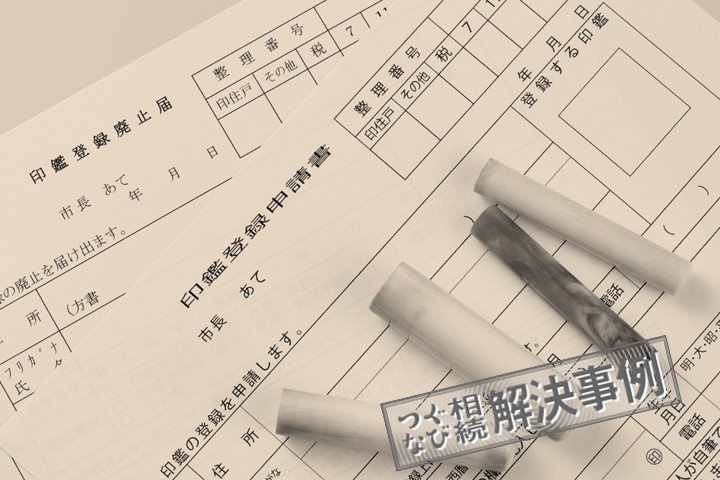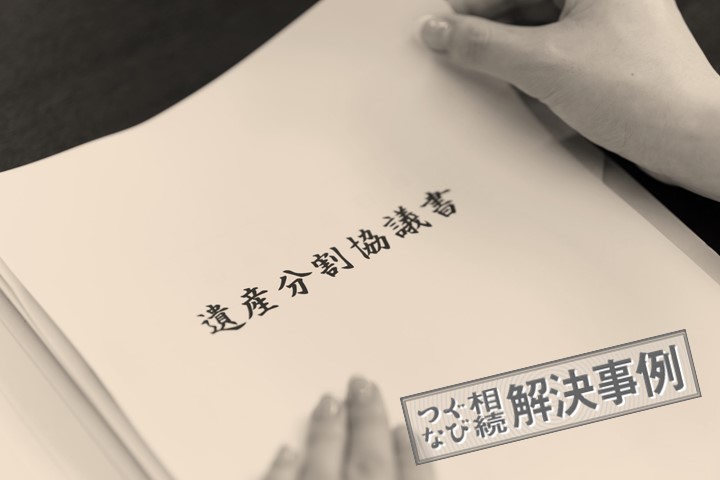相続や贈与の世界では、普段私たちの生活ではなかなか聞きなれない専門用語や法律用語が頻発します。
「受贈者」や「受遺者」はそれらの一部であり、いずれも財産を譲り受ける側の立場であることは共通していますが、対象となる税金が異なるなど、両者は似て非なるものと言えるでしょう。
受贈者とは、財産をもらう人のことをいいます。この記事では、受贈者と受遺者の更に詳しい定義を踏まえ、どのような違いがあるのかについて解説していきます。
目次
1. 受贈者とは?

「受贈者(じゅぞうしゃ)」とは、文字通り贈与を受ける側の人(=財産をもらう人)を指します。
「贈与者(ぞうよしゃ)」とは財産を渡す人のことを言い、贈与者と受贈者は対の関係となります。
なお贈与とは、当事者の一方(=贈与者)が自分の財産を無償で他者(=受贈者)へ与える行為を言いますが、財産を渡す「贈与者」の意思だけでなく、もらう側の「受贈者」についても受け取る意思がなければ成立しません。
したがって受贈者の知らないところで贈与者が一方的に財産を移したとしても、贈与として認められない可能性がありますのでご注意ください。
2. 受遺者とは?
「受遺者(じゅいしゃ)」とは遺贈によって財産をもらう人のことをいいます。
「遺贈者(いぞうしゃ)」とは、反対に遺贈によって財産を渡す人のことを言います。
なお遺贈とは、遺言により、死後に遺言者の財産を無償で他者(=受遺者)へ与えることを言います。
つまり遺贈の場合には、”遺言者=遺贈者“という関係性になるのです。
3. 受贈者と受遺者の違いは?
受贈者も受遺者も、”無償で財産をもらう”という点では同じですが、それが贈与と遺贈のどちらに基因するものなのかによって区別されます。贈与と遺贈の違いについては、下表のようにまとめることができます。
| 贈与 | 遺贈 | |
| 形式 | 口頭でも可 | 正式な遺言が必要 |
| 合意の有無 | 必要 | 不要 |
| 撤回の可否 | 書面による贈与は不可 / 書面によらない贈与の場合には、履行前の部分のみ可 | 生前ならいつでも可 |
| 年齢 | 未成年の場合でも親権者が代理可 | 15歳未満は不可 |
| 税金 | 贈与税(死因贈与の場合には相続税) | 相続税 |
| 不動産の登記義務者 | 贈与者(死因贈与の場合には相続人全員) | 遺言執行者(選任されていない場合は相続人全員) |
それでは上表に記載した相違点について、順番に解説していきます。
3-1 形式や合意の有無について

贈与においては契約の存在を証明するために贈与契約書を作成するケースが一般的ですが、その形式は遺言のように厳格なものではなく、いわゆる口約束であっても成立します。
また贈与は「契約」であることから、財産を”渡す側”と”もらう側”の双方の合意によってはじめて贈与契約が成立します。
一方で遺贈については遺言書に基づくものであり、遺言書は法律に則った形式によるものでなければ効力を発揮しません。
また遺贈は双方の合意ではなく、財産を渡す側である遺贈者のみの一方的な意思によって実行できることから、贈与のような「契約」ではなく、「単独行為」に該当することとなります。
なお遺贈と似たものに「死因贈与」がありますが、死因贈与はあくまで贈与契約の1つであり、亡くなった際に財産を贈与することについて生前に双方で合意している点が遺贈とは異なります。
3-2 撤回の可否について
お伝えした通り、贈与には”贈与契約書”のような書面によるものとそうでないもの(口約束など)が存在します。
お互いの意思を明らかにするという面では契約書を交わすことは有効ですが、一方で書面による贈与の場合には撤回ができないというリスクが存在します。
これに対して書面によらない贈与の場合には撤回することは可能ですが、すでに履行が終わった部分、つまり渡してしまったものに関しては撤回することができませんのでご注意ください。
一方、遺贈の場合には「契約」ではなく「単独行為」であることから、遺贈者が生前のうちであれば自由に撤回や内容の変更が可能となります。
また遺言書も複数作成することができ、内容に矛盾点が生ずる場合には日付が新しいものが採用されます。
3-3 年齢について
贈与の場合には「契約」であることから、贈与者や受贈者が未成年の場合には単独で行うことはできず、親権者が代理で行うこととなります。
それに対して遺贈の場合、民法上、遺言を作成できるのが「満15歳以上」と定められているため、15歳に満たないうちは遺贈を行うことはできません。
3-4 税金について
生前贈与の場合には贈与税が課せられますが、死因贈与では被相続人が亡くなったことによって効力が発揮されるため、相続税の対象となります。
遺贈についても、死因贈与と同様に被相続人の死後に遺言によって実行されるものであるため、相続税の対象です。
また不動産を死因贈与で取得する場合には、遺贈に比べて登録免許税の税率が高くなったり、不動産取得税が掛かってしまう(遺贈のうち、包括遺贈については不動産取得税はかかりません)などの違いもありますので、併せて抑えておきましょう。
3-5 不動産の所有権移転登記について
贈与の場合、贈与者と受贈者の双方が協力して登記手続きを行う必要がありますが、死因贈与の場合には贈与者がすでに死亡しているため、贈与者の地位を相続した相続人全員と受贈者の協力が必要となります。
対して遺贈の場合には、遺言によって遺言執行者が指定されている場合であれば遺言執行者と受遺者の双方の協力で登記手続きが可能となります。
遺言執行者が指定されていない場合には相続人全員の協力が必要となりますが、相続開始後であれば家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てを行うことも可能となります。
4. 生前贈与の場合は贈与税の対象となる!

上述の通り、財産を生前に贈与した場合には贈与税が課せられることとなります。贈与税の課税方法には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つに分類されます。
暦年贈与の場合には毎年110万円ずつの基礎控除額があり、相続時精算課税にも2,500万円までの特別控除額が設定されていますが、これらの金額は財産を渡す側ともらう側のどちらでカウントをすべきなのでしょうか。
まずは暦年贈与の場合ですが、こちらは「受贈者(=財産をもらう人)ごと」に判断します。したがって1年のうちに複数人から贈与を受けた場合でも、贈与者(=財産を渡す人)が何人であろうと、受贈者が1人であれば基礎控除額は110万円であることに変わりはありません。
それに対して相続時精算課税では、贈与者と受贈者をセットで考えることとなります。
したがって「父と子」や「母と子」の組み合わせでそれぞれ2,500万円ずつの特別控除を適用することも可能であり、1人の受贈者が父母2名や祖父母4名の計6名から計1億5,000万円の贈与を受けることも可能となります。
また反対に贈与者である1人の親から、子や孫にそれぞれ2,500万円ずつ贈与を行い、それぞれの受贈者が2,500万円の特別控除を適用することもできるのです。
その一方で、父からの贈与は相続時精算課税を適用し、母からの贈与については暦年贈与を適用することも可能です(同じ贈与者と受贈者の組み合わせで「暦年贈与」と「相続時精算課税」を併用することはできません)。
複数人の間で贈与を行う場合には、このような制度の違いを理解した上で実行するようにしましょう。
5. まとめ
今回は受贈者と受遺者、贈与と遺贈の違いについて解説しました。似たような制度であっても、細かなポイントを見ていくといくつもの違いが隠されています。それらをきちんと踏まえた上で、適切な判断を心掛けましょう。
 服部大税理士事務所 税理士・中小企業診断士 服部 大
服部大税理士事務所 税理士・中小企業診断士 服部 大2020年2月、30歳のときに愛知県名古屋市内にて税理士事務所を開業。平均年齢が60歳を超える税理士業界内で数少ない若手税理士として、同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘中。単発の税務相談や執筆活動も承っており、「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。