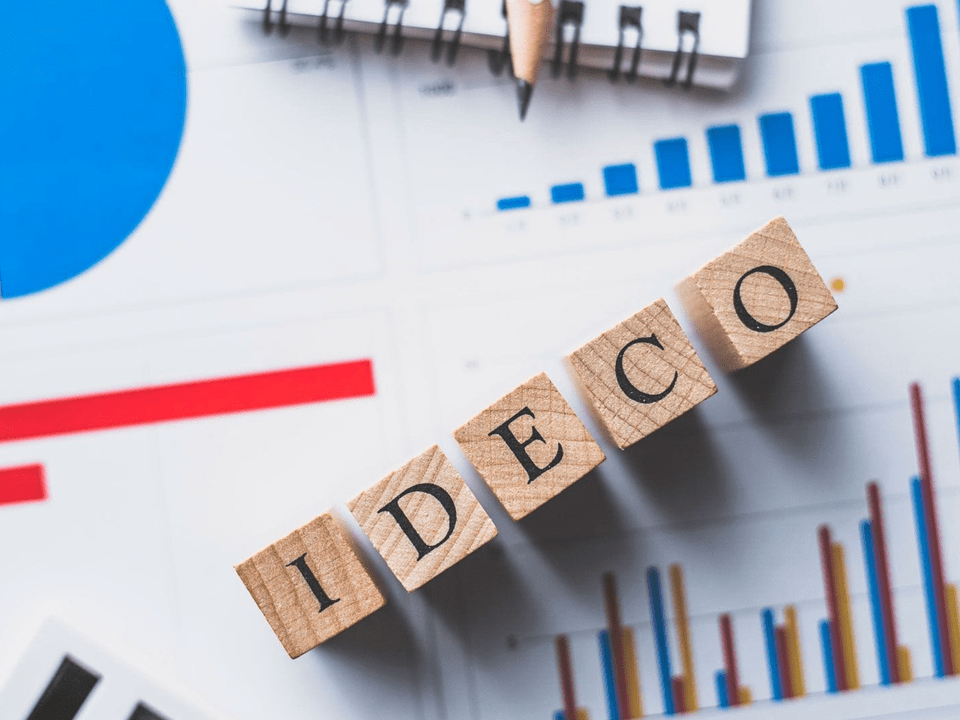末期がん患者等に対する蘇生の努力は通常行われるべきものですが、処置される本人生活の質や尊厳をかえって損ねることもあるでしょう。こうした考え方に基づき、患者や家族の同意で「蘇生措置の見合わせ」(DNAR)が行える医療ルールが設けられています。
DNARに関しては、患者のみならず医師の間でも「同意した場合は延命措置も行われない」「患者の一存で決められる」との間違った認識が広まっています。
本記事では、終活で検討する際に誤解がないよう主に医療機関向けの資料に基づいてDNARのルールを紹介します。
目次
1. DNARとはなにか

DNAR(“Do Not Attempt Resuscitation”)とは、医療現場において患者が心停止や呼吸停止に至った際、本人の利益を尊重して蘇生処置をしない判断を指します。
かつてはDNR(“Do Not Resuscitation”)と短く表現されていましたが、この名称は「成功する可能性が高い状況でも」蘇生処置を施さないとの誤解を招き、命を救うための努力が放棄されかねないと考えられています。
そこで、正しくは「成功する可能性が乏しい状況下での」蘇生を試す事(“Attempt”)を拒む行為だと分かるように改称されました。
現在、医療機関向けのDNARの方針に関しては、厚生労働省の「人生の最終段階の決定プロセスに関するガイドライン」でまとめられています。
1-1 DNARのルール
DNARは患者本人との事前合意によって行われます。すでに病気が進んでおり、本人自ら意思を伝えられない場合には、家族もしくは成年後見人などの代理人からDNARの要望を出す方法も認められます。患者と家族の考えが違うときは、もちろん患者の意思が優先されます。
なお、医療機関の判断だけで蘇生措置を見合わせるのは、患者本人が意思を伝えられない状態に陥っており、かつ家族・代理人の誰とも連絡がとれないようなイレギュラーケースのみです。
また、DNARについて患者側が判断する際には、携わる医療・ケア関係者から必要十分な情報(全身の状態や蘇生処置をした場合の不利益)を伝えるべきとされています。
このとき、与えられた情報に基づいて「やはり蘇生を試してほしい」と考えが変わった際には、患者本人の意思を優先しつつDNARを取り消す事もできます。
1-2 DNARとリビングウィル

医療業界でのDNARは、人生の最終段階(=終末期)について本人の意思を示す行為である「リビングウィル」の1つと認識されています。
広い意味では「臓器提供の意思表示」のように比較的健康な世代でも行われるものも指しますが、特にリビングウィルと呼ばれるのは、延命治療の見合わせやDNARのような差し迫った状況での医療行為です。
1-3 リビングウィルの歴史
リビングウィル(“Living Will”)という考え方が急速に普及したのは、1976年に米国内で下された「持続的植物状態の患者からの生命維持装置取り外し」を認める判決がきっかけです。
同年制定のカリフォルニア州自然死法では、「終末期に生命維持装置が付けられていた場合、その装置を外して自発呼吸できるようにしてもらい、寿命が来た時は医療に介入させずに自然死を迎える」という指示を書面で医師に伝えられるようになりました。
1980年代に入ると、日本国内にもリビングウィルの考え方が持ち込まれました。そして1998年、輸血拒否事件における東京高等裁判所の判決で「医療に関する自己決定権」が認められ、患者が医療行為を拒否する際の法的根拠になりました。
その後、医療機関向けに「終末期医療の決定プロセス関するガイドライン」が厚生労働省から公表され、延命治療や蘇生措置の見合わせ指示に関する基本ルールが定められています。
そして近年、上記のガイドラインが現在の名称に変更され、DNARの基本的な方針がまとまったのです。
1-4 DNARの意向は直ちに受け入れられるわけではない
ただし、患者側からDNARの要望があっても、そのまま受け入れられるわけではありません。前述の厚労省のガイドラインでは「医療・ケアチームと十分な話し合いを行った上で」人生の最終段階における事前合意を行うべきとされています。
患者が自分で意思を示せない状態に陥り、代わりに家族がDNARを決断する場合も同様です。同ガイドラインでは、家族が汲み取った患者本人の希望を「推定意思」と呼び、尊重するように指導されています。
しかし、あまりにも早く症状が進んだために「ごく近しい関係の家族ですら本人の要望を汲めない」という事態もあり得るでしょう。
このような場合には、本人にとって何が最善であるのか医療関係者と家族との間で話し合いを行い、時間経過・心身の状態変化・医学的評価の変更等に応じて、最善の方針をとるよう指導されています。
2. DNARは治療不要ではない

誤解を避けたいのは、DNARはあくまでも「心停止時ないし呼吸停止したした際に蘇生を行わない」行為であり、延命治療や心停止を避けるための努力まで差し控えるという意味ではない点です。
日本集中治療医学会の医師向けの勧告では、第一に「DNAR指示と終末期医療は同義ではない」としています。終末期の定義は全日本病院協会の資料で公表されていますが、医師向けにDNARの要件を定めた資料との記載事項の違いは明らかです。
【終末期の定義と判断】
終末期とは「集中治療室等で治療されている急性重症患者に対し適切な治療を尽くしても救命の見込みがないと判断される時期」と定義づけられています。
具体的には、脳死診断・脳血流停止・生命維持に必要な複数の臓器が不可逆的機能不全となった状態が挙げられています。
参考:全日本病院協会『救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言』
【DNARの定義と判断】
「DNAR指示は心停止時に心肺蘇生をしないであり(後略)」と強調されており、指示終末期の定義にあった「脳死診断」や「脳血流停止」などの状態は記載されていません。
参考:日本集中治療医学会倫理会「DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)の考え方」
先で紹介した日本集中治療医学会の勧告では、さらに「DNAR指示に関する合意と終末期医療に関する合意は別々に行うべきだ」との趣旨で続けられています。ここで言う終末期医療とは、胃ろう(胃から直接栄養を摂取するための医療措置)や人工呼吸器の装着を意味し、通常は心停止前の延命の努力として当然行われるものです。
つまり「蘇生拒否の合意を済ませているかどうかに関わらず、延命治療は基本的に必要」かつ「延命治療をしてほしくない場合には、それについても合意が必要」とされているのです。
3. DNARを希望するときは

DNARを希望する際は、口頭ではなく病院備え付けの同意書に記入します。多くの場合、終末期に入った時点からのリビングウィルをセットで行えるよう、延命治療に関する同意の項目もDNARと並んで記載されています。
DNARの要否について「医療・ケア関係者とよく話し合った上で患者の意思が優先される」点はすでに説明した通りですが、家族とも十分話し合いましょう。
また、脳の病気や救命救急を要する病気に陥った場合に備えて「患者の代弁者」を決めておくのも、患者とその家族の理解のために策定された「終末期医療に関するガイドライン」(全日本病院協会)で推奨されています。
自身のみならず周囲の人のダメージを緩和するためにも、医療・ケア関係者の意見も聞きながら、いざという時の措置について考えを共有しておくことが大切です。
4. まとめ
解説を元にDNARの定義とルールを整理すると、終活で検討する際に知っておきたいポイントとして以下3点が挙げられます。
- 患者側の事前同意で「心停止後の蘇生措置」を拒否できる
- 心停止前の延命治療を拒否したい時は、別途同意する必要がある
- 医療・ケア関係者からの情報を元に、家族で話し合って決める
「蘇生を諦める」決断は、本人のみならず遺される家族にとっても重大なものです。また、延命治療にも様々な考え方や感じ方がある点から、DNARへの同意との混同しないよう注意を要します。
納得できるまで情報を提供してもらい、最善の選択をしましょう。
また相続が発生した後の手続き全般のことは、司法司法書士や行政書士など相続手続きの専門家に相談することも1つの方法です。ぜひご検討を。
 遠藤秋乃
遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。