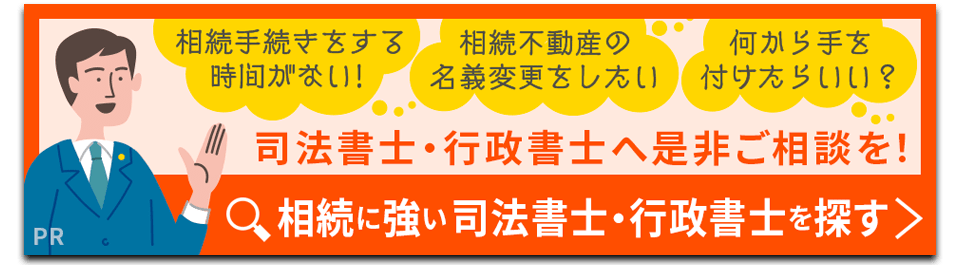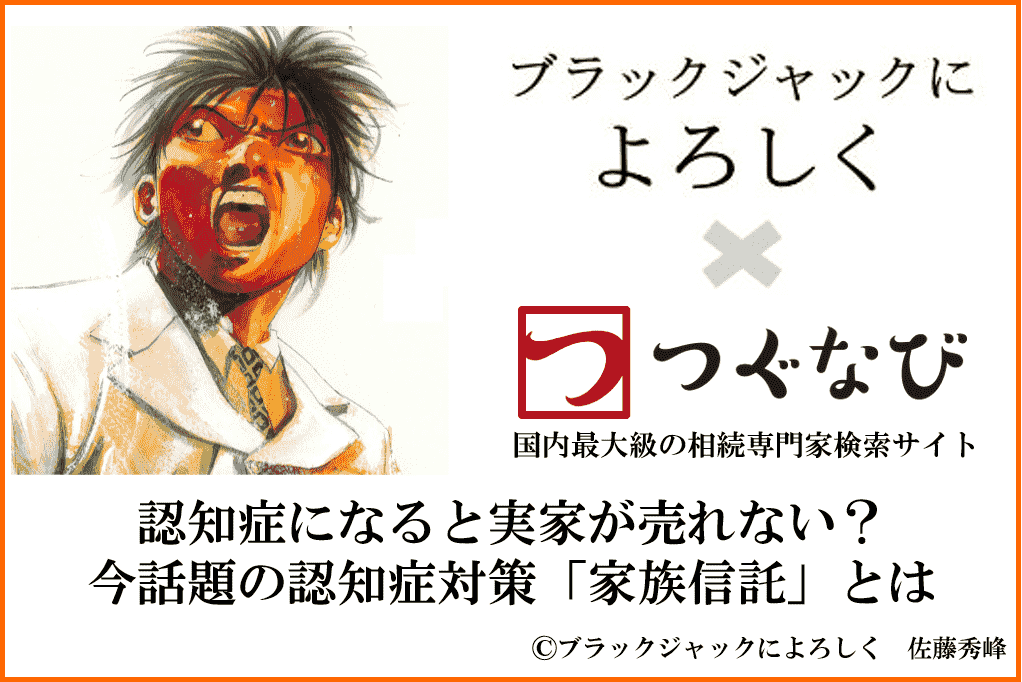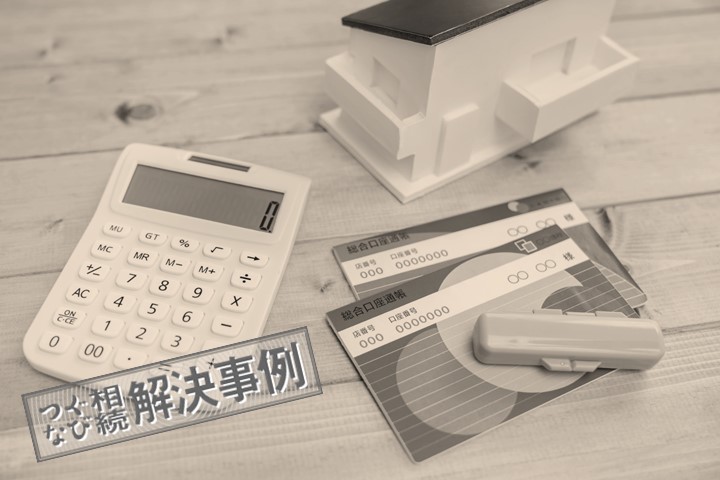家族信託をしようと考えたものの、どうしてよいかわからない。
いろいろ考えてみて、「信託銀行」があるくらいだから「銀行」に相談すればいいのではないか。そう考える人は少なくないでしょう。
しかし、家族信託のことを銀行に相談するときには注意が必要です。
銀行員でも「家族信託」のことをよく知っている人はまだまだ少ないのが現状です。
今回は、家族信託の手続き方法や、銀行にやってもらうとどうなるのかをご紹介していきます。
1. 家族信託とは?
まずは家族信託がどういったものなのかを理解しておく必要があります。
一般によく言われる家族信託とは、「受託者を委託者の家族とする民事信託」です。
ただし、「家族信託=受託者を委託者の家族とする民事信託」とは言い切れない点にも注意が必要です。
一方、銀行が主に取り扱っている信託は「商事信託」と呼ばれるもので、家族信託ではありません。
商事信託は金融機関が受託者となるものであり、家族信託とは全く異なるものなのです。
「家族信託の実行を支援するサービス」を始めている銀行は徐々に増えているようですが、まだまだ一般的にはなっていません。
信託銀行のホームページなどを見てみても、商事信託のページしかありません。このような状態ですから、銀行員自体も家族信託のことをよく知らない状態といえるでしょう。
「家族信託について相談したいのですが」と窓口を訪問しても、「ご家族様名義の口座開設には、ご本人様がいらっしゃるか成年後見制度での対応となります」と家族名義の口座開設の話と思われるか、「信託でしたらこういったサービス内容となっております」と商事信託の説明を始められてしまう可能性が高いでしょう。
ちなみに、2017年4月現在、みずほ信託銀行では「家族信託(安心の贈りもの)」という名前の「商事信託」が提供されています。
まさに、「民事信託としての家族信託」がまだまだ浸透していない証拠ではないでしょうか。
2. 家族信託での財産管理をどうすればよいのか
それでは、実際に家族信託をする場合に、受託者はどうやって財産管理をすればよいのでしょうか。
受託した現金をそのまま保管するわけにはいかないので、やはり、銀行に信託口座を開設するのが最も良い選択肢です。
運よく、訪問した銀行に家族信託に詳しい担当者がいたり、すでに家族信託での口座開設をしたことがある店舗だったりすると、スムーズにいくでしょう。
しかし、そのような銀行は少ないため、担当者としっかり話をしなければなりません。専門用語なども含めて、民事信託の仕組みについてかなり勉強しなければならないでしょう。
そこで、民事信託に詳しい弁護士や司法書士といった士業のサポートを受けるという方法があります。
銀行との交渉をスムーズに進めてくれるほか、この銀行なら家族信託の口座開設ができるといった情報を持っているかもしれません。
3. 受託者個人名義の口座で管理するのは危険
家族信託での口座開設(「委託者・受託者信託口口座」という扱いの口座となる)ができない場合の代替手段として、受託者が自分名義で銀行に口座を開設する、といった方法があります。
しかし、この方法には深刻なデメリットがあります。
この場合、委託者と受託者の間で信託契約を結んでいるため、受託者は委託者のために財産を管理します。
ところが、「受託者固有の財産を銀行に預けている」という形式になってしまうため、受託者個人の債務の返済ができなくなってしまった場合、債権者が受託者個人名義の口座を差し押さえることができてしまうのです。
家族信託の契約を締結し、銀行とちゃんと話をして「家族信託用の口座」を開設できていれば、受託者が破産したとしても、その財産が差し押さえられる心配はありません。
4. 家族信託に自信がなければ、商事信託にするのも1つの手段
こういったデメリットを考えると、代替手段を考えるより家族信託ができるようにするべきです。
しかし、どうしても家族信託で銀行に口座開設するのが難しそうであれば、銀行に支払う費用が発生しますが、銀行との商事信託を選ぶのもひとつの手です。
銀行などで取り扱っている商事信託とは、金融機関が受託者となり、委託者の財産の運用を行うものです。
信託銀行の場合では、金銭だけしか受託できない場合が多いようです。
家族信託の代わりに商事信託を利用する場合、相続のことを視野に入れているのであれば、「遺言代用信託」が有効です。
遺言代用信託では、契約時に法定相続人の中から受取人を指定し、委託者が生存している間の配当は委託者に支払われます。
そして、委託者が死亡した場合には、その財産を受取人に引き渡されます。財産の引き渡し方は、一時金として引き渡すほか、年金形式で一定額ずつ引き渡す方法も選ぶことができます。
遺言代用信託を利用する場合、遺言書を作成するなどの手間がかかります。その他にも、戸籍謄本や印鑑証明書など、たくさんの書類を用意しなければなりません。
しかし、この信託方法はかなり以前からあるもので、金融機関側も対応に慣れているため、どのような手順で何をするべきなのかを教えてくれます。
手続き自体は複雑かもしれませんが、何をすればいいかわからなくなってしまうことはないでしょう。
また、個人ではハードルが高い遺言書の作成も、専門家を一緒にアドバイスをしてくれるため、遺言書が無効になるというリスクは避けられます。
ただし、家族信託の場合と異なり、信託銀行は委託者からの財産を受託・運用することをビジネスとして行っています。
財産を信託する際の信託報酬のほか、遺言書の保管サービスや遺言執行などのサポートを受ける際に費用がかかります。
また、最低でも数百万円以上のまとまった資産でないと、信託を引き受けてもらえないのもデメリットです。
銀行によっては1,000万円を超える金額でないと申し込めない場合もあります。
家族信託が難しく、委託したい財産の差し押さえリスクなどを避けたいのであれば、手数料等のコストを考慮した上で銀行への信託も視野に入れてみるのもよいでしょう。
この記事の監修者